平凡な日常が続いていく「ゼロ地点」は、馴染み深く、安心できる場所です。
そこに、ほんの少しだけ “これから” の気配が灯ったら──
Compass 0(コンパス 0)は、そんな未来への そっとした予感をともす場所です。
本ニュースレターは「ウェルビーイングな社会を育てていきたい」という願いから生まれました。
研究者の新しい取り組みや知見を手がかりに、私たちが感じたことや気づきを共有し、日々の暮らしや実践にそっと役立つメモとしてひらいています。
また、ここに集う方々との “あたたかいつながり” を大切にしています。
※ 引用文以外の内容は、執筆者個人の見解であり、特定の機関の公式見解を示すものではありません。
ご感想や気づきがあれば、いつでもお聞かせください。🕊️
※最終更新2026.1.31(土)23:58/ 次回更新:2.1
new ページに移行します(_ _)
🌿【明日更新】ウェルビーイング応援サイト、久しぶりに記事を書きました
2026.1.31|
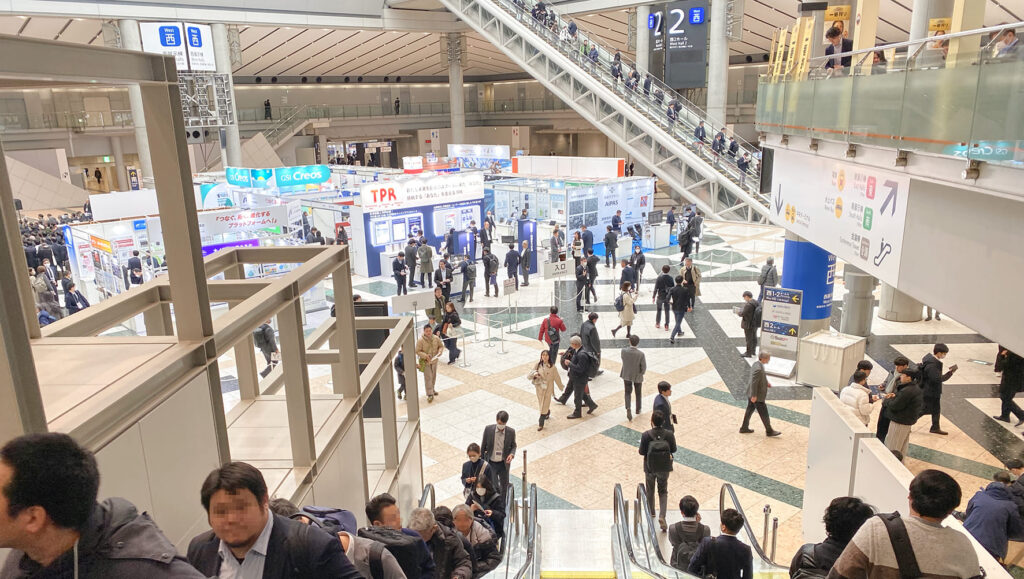
『測る技術と、測らないやさしさ─WELL-BEING TECHNOLOGY 2026 レポート』
こんばんは。
実は今日、
ウェルビーイング応援サイトを 約1年半ぶりに更新 しました。
今回は「WELL-BEING TECHNOLOGY 2026」の展示をきっかけに、
実際に見て、聞いて、感じたことを、
かなり丁寧にまとめています。
・測る技術
・測らないやさしさ
・AIと人の距離感
・そして、最後に残った“静かな気づき”
そんな内容です。
今夜はこれから最終チェックと画像調整をして、
明日また更新予定です。
よかったら、
「ちょっと落ち着いた時間」に読んでもらえたら嬉しいです。
また明日、お知らせしますね。
第5回|今日は、少し立ち止まる日
──「つながり」の話を、ここでひと息
2026.1.30|
ここ数日、「つながり」と「幸福」についての研究を紹介してきました。
・人とのつながりは、収入よりも未来の幸福をよく予測する
・孤独は、脳や身体にとって強いストレスになる
・安心できる関係は、感情や回復力そのものを支えている
どれも、データとして見るととてもはっきりしていて、
同時に、どこか静かな話でもありました。
今日は、あえて新しい研究は出さずに、
この流れをいったんここで「置いてみる日」にしたいと思います。
「わかった気がする」と「腑に落ちる」は、少し違う
研究を読むと、私たちはよくこう思います。
「なるほど、そうなんだ」
「やっぱり、つながりって大事なんだな」
でも、その理解が
本当に自分の中に落ちてくるまでには、少し時間がかかります。
・忙しい日々の中で
・気づけば誰とも話していなかったり
・つながっているはずなのに、どこか孤独を感じたり
そういう現実があるからこそ、
研究の言葉は、すぐには身体になじまない。
だから今日は、
「理解する日」ではなくて、
「そのまま置いておく日」でいいのかなと思いました。
つながりは、考えるものじゃなくて、感じるもの
これまで見てきた研究が一貫して伝えていたのは、
つながりは
・努力で増やすものでもなく
・正解を探すものでもなく
・成果として得るものでもない
ということでした。
ただ、
誰かと同じ時間を過ごしたり、
同じ空間で呼吸したり、
何も言わずにいられたり。
そういう「説明できない時間」の中で、
いつの間にか育っていくもの。
だからこそ、
「どう生きればいいか」という問いに、
はっきりした答えはないのかもしれません。
今日のいちばん大事なこと
今日、ここまで読んでくれたあなたに、
ひとつだけ伝えたいことがあります。
それは、
いま、ちゃんと生きようとしている時点で、
もう十分すぎるほど、ちゃんとしている。
ということです。
誰かと比べなくてもいいし、
うまくできていなくてもいいし、
前に進めていなくてもいい。
つながりは、
「ちゃんとしよう」と思った瞬間に遠ざかって、
「まあ、いいか」と力を抜いたときに、
そっと戻ってくるものなのかもしれません。
🐢 ウエルの感想
ウエルは今日、
「つながりって、考えすぎると見えなくなるのかも」と思いました。
探しているときより、
ふと顔を上げたときのほうが、
そばにあったりする。
だから今日は、
がんばらずに、少し立ち止まる日にしました。
それだけで、十分な一日だった気がします。
第4回|それでも、私たちはどう生きればいいのか
──研究が示した「つながり」という力
2026.1.29|
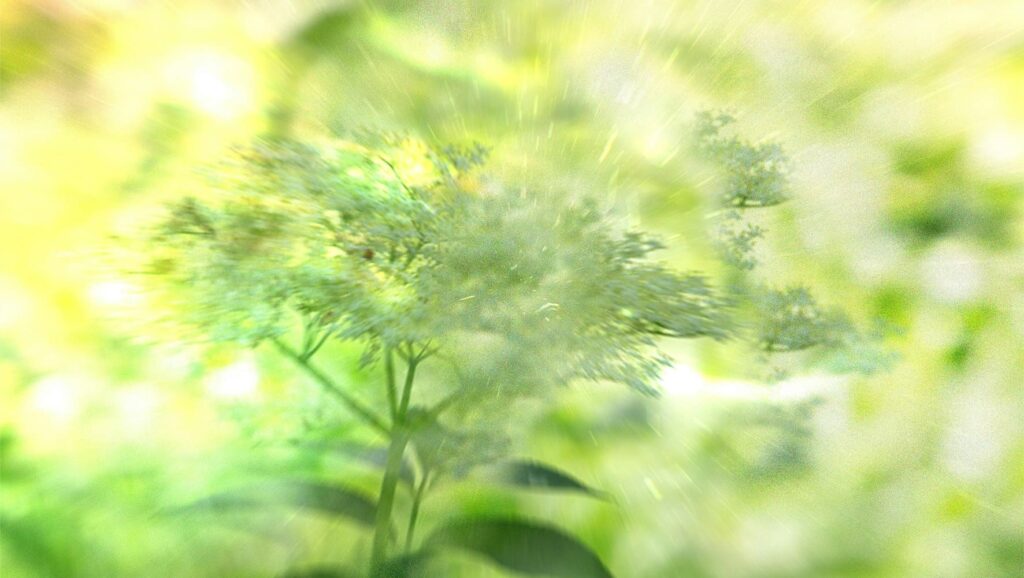
©sara-canonici
ここまで数回にわたって、
「意味のある人生」と「つながり」についての研究を見てきました。
・社会的つながりは、収入よりも未来の幸福をよく予測していた
・孤独は、脳や身体にとって“危険信号”だった
・安心できる関係は、感情や回復力そのものを支えていた
そして今日、ここまでをふり返って、
あらためて浮かび上がってくる問いがあります。
それでも、私たちはどう生きればいいのだろう?
「つながり」は、努力で“増やすもの”ではなかった
今回紹介してきたモーセン先生の研究は、
22年間・27,000人以上を追った大規模な縦断研究でした。
そこで明らかになったのは、とても静かな事実です。
収入の増減よりも、
「人とのつながりの変化」のほうが、
次の年の幸福を2〜4倍も強く予測していた。
しかも重要なのは、
「人脈を広げた人が幸せになる」という話ではありません。
・信頼できる人がいる
・話を聞いてもらえる
・安心していられる関係がある
そうした質的なつながりこそが、
幸福と強く結びついていたのです。
幸福は「結果」ではなく「循環」だった
この研究がとても興味深いのは、
幸福とつながりの関係が“一方通行ではない”と示した点です。
・つながりが増える → 幸福が高まる
・幸福が高まる → つながりも育つ
つまり、どちらが先かではなく、
小さな変化が、次の変化を呼ぶ循環が生まれているということです。
「まず成功しなければ幸せになれない」
「安定してから人と関われる」
そんな順番ではなく、
人とつながること自体が、人生を前に進めていく力になる。
研究は、そう語っています。
「ちゃんと生きる」は、がんばることじゃなかった
私たちはつい、こう思ってしまいます。
・もっと努力しないと
・役に立たないと
・ちゃんとしていないと
でも、今回の研究が静かに教えてくれたのは、少し違う視点でした。
✔ 誰かと話した
✔ 一緒に笑った
✔ 安心できる時間を過ごした
その積み重ねが、
気づかないうちに心と体を支えている。
「意味のある人生」は、
何かを成し遂げた先にあるのではなく、
人との関係の中で、いつの間にか育っているものなのかもしれません。
🌱 今日のまとめ
・幸福は、収入よりも「つながり」に強く影響される
・つながりは、努力で作るものではなく育つもの
・人と関わること自体が、心と身体の回復になる
だから私たちは、
無理に強くならなくていいし、
立派にならなくてもいい。
誰かと一緒にいられる時間を、
ちゃんと大切にできていれば――
それだけで、もう十分なのかもしれません。
🐢 ウエルの感想
ウエルは今日、
「つながりって、増やすものだと思ってたなあ」と思いました。
友だちの数とか、関係の広さとか。
でも研究を読んでいたら、
どうやら“増やす”より“深まる”のほうが大事みたいです。
それって、なんだか庭みたいだなと思いました。
すぐに花が咲かなくても、
ちゃんと土に根を張っている感じがするから。
水をあげすぎてもだめで、
放っておいても枯れてしまう。
ちょうどいい距離で、
ちゃんと手入れすること。
それが、つながりなのかもしれません。
🌿 ひとこと
昨日は『WELL-BEING TECHNOLOGY 2026』を見に行ってきました。
人と技術、研究と日常、そのあいだにある“余白”について、
いろいろ感じることがありました。
そのことは、もう少し整理してから、
また改めてお届けできたらと思います。
第3回|じゃあ、私たちはどう生きればいいのか
──「つながり」は、つくるものじゃなく“育つもの”だった
2026.1.28|
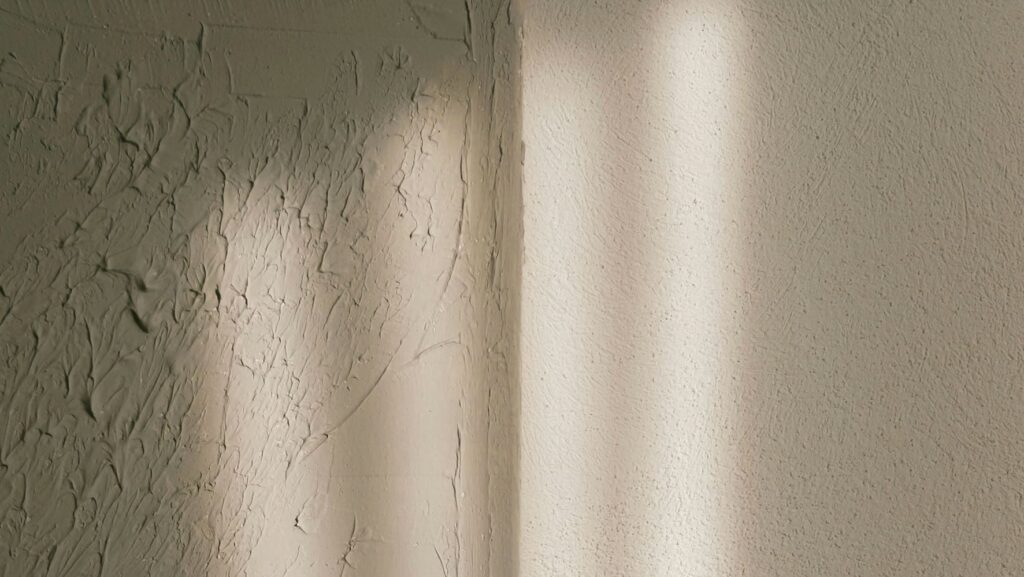
©karolina-grabowska
ここまで2回にわたって、
「つながり」と「幸福」の関係について見てきました。
・社会的つながりは、収入よりも未来の幸福をよく予測していた
・孤独は脳と体にとって“危険信号”になる
・安心できる関係が、感情や回復力を支えている
──そんな研究の結果を読んでいると、
ふと、こんな疑問が浮かびます。
「じゃあ、私たちはどう生きればいいんだろう?」
今日はその問いに、少しだけ静かに答えてみたいと思います。
「つながり」は、つくろうとすると苦しくなる
まず大切なことがあります。
研究が教えてくれているのは、
「人脈を増やそう」「もっと関係を広げよう」という話ではありません。
むしろ逆です。
つながりは、
頑張って「つくる」ものではなく、
安心できる環境の中で、自然と「育っていく」ものでした。
無理に話題を探さなくてもいい。
役に立たなきゃと思わなくてもいい。
ちゃんとしたことを言えなくてもいい。
「ここにいていい」と感じられること。
それ自体が、つながりの土台になります。
つながりが育つとき、脳は“安全モード”に入る
昨日お話ししたように、
人は孤独を感じると、脳が危機状態になります。
逆に言えば──
誰かと安心していられるとき、脳は「安全だ」と判断します。
このとき起きるのが、
・感情の揺れが小さくなる
・ストレス反応が下がる
・回復や集中に使えるエネルギーが戻ってくる
という変化です。
つまり、つながりとは
「心を強くするもの」ではなく、
心を休ませてくれるものなのかもしれません。
「ちゃんと生きる」は、頑張ることじゃない
私たちはつい、
・もっと頑張らなきゃ
・ちゃんとしなきゃ
・役に立たなきゃ
と思ってしまいます。
でも、今回の研究が教えてくれたのは、
少し違う方向でした。
✔ 誰かと笑った
✔ 話を聞いてもらった
✔ 一緒に静かに過ごした
そういう時間の積み重ねが、
未来の幸福をつくっていく。
それはとても地味で、
数字にもなりにくくて、
SNSではあまり映えないけれど──
確かに、静かに私たちを支えているものなのだと思います。
🌱 今日のまとめ
・つながりは「作るもの」ではなく「育つもの」
・安心できる関係が、心と体を回復させる
・幸福は、努力よりも“関係性の中”で育つ
だから私たちは、
無理に強くならなくてもいい。
ちゃんと生きようとしすぎなくてもいい。
ただ、誰かと同じ時間を過ごせていたら、
それだけで、もう十分なのかもしれません。
🐢 ウエルの感想
ウエルは、
「がんばらないと、つながれない」って思っていました。
でも今日のお話を読んで、
つながりって、
がんばらなくなったときに残るものなのかも、と思いました。
静かに座っているだけでいい時間。
何も言わなくても安心できる時間。
そういう時間が、
明日の自分を支えてくれるなら──
それって、とてもやさしい世界ですよね。
🌱 ひとこと
今日は『WELL-BEING TECHNOLOGY 2026』を見に行ってきました。
人と技術、未来と日常のあいだにある「余白」みたいなものを感じて、
そのときの気持ちを「量子の庭」の制作日誌に少しだけ書いています。
今日の話と、どこかで静かにつながっている気がするので、
よかったら、そっとのぞいてみてください。
次回予告
次回はもう一歩だけ踏み込みます。
「じゃあ、どんな関係が“いいつながり”なんだろう?」
無理せず、疲れず、長く続く関係のヒントを、
研究と日常の両方から見ていきます。
第2回|なぜ“つながり”は、こんなにも私たちを支えるのか
──孤独・感情・脳・体の奥で起きていること
2026.1.27|

©a-chosen-soul
昨日は、
「社会的つながりは、収入よりも未来の幸福を強く予測する」
という研究をご紹介しました。
今日はその続きとして、
なぜ“つながり”がそこまで大きな力を持つのかを、
少しだけ体の内側から見てみたいと思います。
① 孤独は、脳にとって“危険信号”だった
まず大前提として、
人間の脳は「孤独」をとても強いストレスとして認識します。
孤立した状態になると、脳はそれを
「生存の危機に近い状態」
として処理することが、研究からわかっています。
・不安が高まりやすくなる
・ネガティブな情報に敏感になる
・ストレスホルモン(コルチゾール)が増える
つまり孤独は、
気分の問題ではなく、生理的な警報なのです。
だからこそ、
誰かとつながっているだけで、
私たちの脳は自然と安心できるようにできています。
② つながりは、感情の“調整装置”になる
人はひとりでいると、
感情が暴走しやすくなります。
でも、
・話を聞いてもらう
・一緒に笑う
・同じ空間にいる
こうした経験があるだけで、
感情は自然と落ち着いていきます。
心理学ではこれを
「情動調整(emotional regulation)」 と呼びます。
ポイントは、
「問題を解決してもらう必要はない」ということ。
ただ誰かがいるだけで、
私たちの心は勝手に整っていく。
昨日紹介した研究で、
「一緒にいるだけで幸福度が上がる」
とされていた理由も、ここにあります。
③ “社会的安全”があると、脳は回復モードに入る
もうひとつ大切なのが、
社会的安全性(social safety) という考え方です。
・否定されない
・排除されない
・安心していられる
こうした環境にいると、
脳は「防御モード」から「回復モード」に切り替わります。
すると──
・集中力が戻る
・感情が安定する
・身体の回復が進む
つまり、つながりは
心だけでなく、体の回復スイッチでもあるのです。
④ そして、ミトコンドリアにまで影響する
ここで、昨日触れた研究ともつながります。
最近の研究では、
社会的つながりや意味の感覚が、
細胞の中の「ミトコンドリア」にまで影響することが示されています。
ミトコンドリアは、
私たちの体のエネルギーを生み出す場所。
慢性的なストレスや孤独があると、
・炎症が起きやすくなり
・エネルギー産生が低下し
・疲れやすくなる
一方で、
安心できる人間関係があると、
この働きが安定することがわかっています。
つまり──
つながりは、細胞レベルで私たちを支えている。
これは「特別な人間関係」ではなく、
日常の小さな安心でも十分に起こることです。
昨日の研究で
「社会的つながりは収入より強く幸福を予測した」
という結果が出たのも、偶然ではありません。
🌱 今日のまとめ
今日の話をまとめると、こうなります。
・孤独は、脳にとって危険信号
・つながりは、感情を整える
・安心感は、身体の回復を促す
・そしてそれが、未来の幸福につながっていく
だから「つながり」は、
気持ちの問題ではなく、生存戦略なのかもしれません。
🐢 ウエルの感想
ウエルは、
「ひとりで頑張れる人が強い」って思っていました。
でも今日のお話を読んで、
つながることは甘えじゃなくて、
ちゃんと生きるための力なんだって思いました。
誰かと話すこと。
一緒に笑うこと。
同じ時間を過ごすこと。
それだけで、
体の奥が少し元気になるなら、
もっと大事にしていいのかもしれませんね。
次回は、
こうした「つながり」が、
どうやって日常の中で育っていくのか。
そのヒントを、もう少しだけ見ていきたいと思います。
第1回|お金よりも、「つながり」のほうが未来の幸福を決めていた
──モーセン先生の新研究:22年データが示した“社会資本”の強さ
2026.1.26|

©curated-lifestyle
先日、モーセン・ジョシャンルー先生が、こんな研究を紹介されていました。
“Social connectedness is a far stronger predictor of future well-being than income.”
(社会的つながりは、収入よりもはるかに強く、未来の幸福を予測する)
この研究は、オーストラリアの22年分・27,000人以上のデータを用いて、
「社会資本」と「経済資本」のどちらが人の幸福に強く影響するかを検証したものです。
結果はとても明確でした。
つながりの力は、収入の2〜4倍も大きかったのです。
22年間・27,000人以上を追った結果
この研究では、オーストラリアの大規模調査(HILDA)を用いて、
22年間・27,000人以上の追跡データが分析されました。
調べたのは、次の2つが「翌年の幸福」にどう影響するかです。
・社会的つながり(social connectedness)
・収入(income)
そして、幸福は3つの側面に分けて見ています。
・生活満足度(Life Satisfaction)
・ポジティブ感情(Positive Affect)
・ネガティブ感情(Negative Affect)
結果:つながりは、収入より強い予測因子
結果は、驚くほどはっきりしていました。
社会的つながりの変化は、収入の変化よりも
“翌年の幸福”を2〜4倍ほど強く予測していました(指標によって比率は異なります)。
なお、幸福から収入への影響も示唆されましたが、その効果はつながりに比べるとかなり小さいものでした。
つまり、
・収入が少し上がった年よりも
・「人とのつながりが増えた年」のほうが
次の年の幸福感が上がりやすかった、ということです。
もちろん収入も無関係ではありません。
ただ、同じ条件で比べると、つながりのほうがずっと強かった。
もう一つの発見:幸福とつながりは循環する
さらに興味深いのはここです。
この研究では、
幸福度が高いと、次の年の社会的つながりも良くなる
という“逆方向”も確認されました。
つまり——
・つながりが増える → 幸せが増える
・幸せが増える → つながりも増える
幸福とつながりは、
原因と結果ではなく、循環している可能性がある。
この視点は、静かだけど希望があるなと思いました。
🌱 今日のまとめ
今日の研究が示しているのは、ある意味とても素朴なことでした。
「未来の幸福をつくる力は、収入だけでは測れない」
そしてその中心には、
“社会的つながり”があった。
🐢 ウエルの感想
ウエルは、
「お金があったら安心できる」って思ってました。
でも今日のお話を読んで、
安心って、ほんとは
誰かとちゃんとつながってるときに増えるのかもしれないって思いました。
すごいことができなくても、
だれかと話せたり、笑えたりしたら、
それだけで未来はちょっと良くなるのかな。
今日はそんな気がしました。
次回予告
次回は、
「なぜ“つながり”はこんなに強く効くのか?」
研究の背景と、日常での活かし方をもう少し丁寧に見ていきます。
第5回:立ち止まって、少し振り返る
──今週、私たちが見てきた「意味のかたち」
2026.1.25|

©marko-brecic
今週は、「意味のある人生(Meaningful Life)」をめぐる研究をいくつか紹介してきました。
どれも、派手な結論があるわけではありません。
けれど読み進めるうちに、共通して流れている空気のようなものがありました。
それはたぶん──
「意味は、静かなところにある」ということでした。
今週、私たちが見てきたこと
・誰かと一緒にいるだけで、人は安心できる
・迷っている大人の姿を、子どもはちゃんと信頼している
・許すことは、記憶を消すのではなく、苦しさを軽くすること
・心の状態は、体の奥(ミトコンドリア)にまで影響している
・そして、善く生きようとする姿勢そのものが、幸福につながっている
どれも、「もっと頑張れ」「もっと成果を出せ」という話ではありませんでした。
むしろその逆で、
✔ うまくやれなくてもいい
✔ すぐに答えが出なくてもいい
✔ 誰かと関わりながら進めばいい
そんな、少し肩の力が抜けるようなメッセージばかりでした。
「意味」は、後から気づくものかもしれない
研究を読みながら、印象に残ったのはこの感覚です。
意味のある人生は、
どこかに完成形があって、そこに到達するものではない。
むしろ──
・迷ったり
・遠回りしたり
・誰かに助けられたり
・思ったようにいかなかったり
そういう時間の中で、あとから「意味だった」と気づくものなのかもしれません。
今週のいちばん大きな発見
今週の研究を通して、いちばん静かに心に残ったのは、これでした。
善く生きようとすることは、ちゃんと自分に返ってくる。
誰かを大切にしようとすること。
誠実であろうとすること。
わからないと言えること。
それらは、損をする行為ではなくて、
人とのつながりや安心感を通して、
ゆっくり自分を支えてくれるものだった。
科学は、その感覚が間違っていないことを、静かに示していました。
🐢 ウエルの感想
「意味って、もっと大きなものだと思ってた」って思いました。
でも今週のお話を読んで、
毎日ちゃんと悩んで、考えて、
誰かと話して、迷いながら進んでいること自体が、
もう“意味の途中”なんだなって感じました。
すぐに答えが出なくてもいい。
ちゃんと立ち止まっているなら、それでいい。
今日は、そんなふうに思えた一日でした。
第4回:善く生きることは、実はちゃんと報われる
──2025年、“意味のある人生”をめぐる10の研究から
2026.1.24|
今週は、「意味のある人生(Meaningful Life)」をめぐる研究をいくつか紹介してきました。
・一緒にいるだけで、人は安心する
・許すことで、心の重さは軽くなる
・迷いながら進む姿を、子どもは信頼する
・意味は、特別な成功よりも日々の選択に宿る
そして今日、最後に紹介したいのが
「善く生きようとすること自体が、幸福につながっている」
という研究です。
善く生きる人は、なぜ幸せなのか?
この研究では、
「道徳的であること(moral)」と
「幸福感・人生の意味」との関係が調べられました。
ここでいう“善さ”とは、特別な正義感ではありません。
・誠実である
・人を尊重する
・約束を守る
・思いやりを持つ
といった、ごく日常的な姿勢のことです。
結果はとてもシンプルでした。
✔ 周囲から「誠実だ」と見られている人ほど
✔ 幸福度が高く
✔ 人生に意味を感じている
しかも興味深いのは、
「善いことをしているから幸せになる」のか、
「幸せだから善くふるまえる」のか、
そのどちらもが影響し合っている、という点でした。
善さと幸福は、原因と結果ではなく
循環している ということです。
善さは、自己犠牲じゃなかった
この研究が伝えている大事なメッセージは、とても静かです。
善く生きることは、
自分を削ることではない。
むしろ、
・人と信頼関係を築きやすくなり
・孤立しにくくなり
・安心感の中で生きられる
結果として、
自分自身の幸福にもつながっていく。
「人にやさしくすると損をする」
「まじめすぎると報われない」
そんな感覚が広がりがちな今だからこそ、
この研究は、そっと違う光を当ててくれます。
どちらを選ぶかより、
“どう生きようとするか”が大事なのかもしれない。
今週のまとめ
今週紹介してきた研究たちは、
どれも派手な答えを出していませんでした。
でも、共通していたのはこの感覚です。
・意味は、急いでつくるものじゃない
・正しさは、誰かと切り離せない
・幸せは、関係の中で育つ
「ちゃんと生きようとすること」
その姿勢自体が、もう十分に価値がある。
そんなことを、科学が静かに肯定してくれていました。
🐢 ウエルの感想
ウエルは、
「いい人でいなきゃ」って思うと、
ちょっと苦しくなることがありました。
でも今日のお話を読んで、
“がんばって善くなる”んじゃなくて、
“ちゃんと生きようとすること”が
そのまま意味になるんだって思いました。
うまくできなくても、
迷っても、
誰かを大切にしようとしているなら、
それでいいのかもしれません。
今日は、そんなふうに思えた一日でした。
第3回:意味のある人生は、静かなところで育っている
──2025年、“意味のある人生”をめぐる10の研究から
2026.1.23|
昨日に続いて今日は、
「意味のある人生(Meaningful Life)」をめぐる
2025年の研究の中から、特に印象的だった3つを紹介します。
どれも派手な結論ではありません。
でも読めば読むほど、
「たしかにそうかもしれない」と静かに腑に落ちてくる内容でした。
① 心のあり方は、体の奥まで影響している
(ミトコンドリアとウェルビーイング)
まず紹介されていたのは、
「私たちの心の状態が、体のエネルギーレベルにまで影響する」
という研究です。
研究者たちは、ストレスや幸福感と
細胞の中にあるミトコンドリア(エネルギーを作る器官)の状態に
明確な関係があることを示しました。
・意味を感じている人
・社会的につながりを持っている人
・自分の人生に納得感がある人
こうした人ほど、
脳の中でエネルギーを生み出す働きが安定していたのです。
「気持ちの問題」だと思われがちなことが、
実はとても物理的で、身体的な現象だった――
そんなことを教えてくれる研究でした。
② 人は“意味”を、だいたい同じ場所から得ている
(文化を越えて共通するもの)
次に紹介されていたのは、
日本・アメリカ・インド・ポーランドなど、
複数の国を対象にした研究です。
驚くことに、
人が「意味のある人生」を感じる源は、国が違ってもよく似ていました。
たとえば──
・家族や身近な人とのつながり
・誰かの役に立っている感覚
・自分で選んで生きているという実感
お金や地位よりも、
「どう生きているか」が重視されていたのです。
つまり、
意味のある人生は、特別な才能や環境の中ではなく、
日々の関係や、小さな選択の積み重ねの中で、静かに育っていくもの
なのだということ。
③ それでも人は、人を求めている
(AI時代のつながり)
最後は、少し現代的なテーマです。
最近の研究では、
人がAIと感情的な関係を築くケースが増えていることも報告されています。
相談相手になってくれる
否定せずに話を聞いてくれる
いつでも応答してくれる
そうした存在が、心の支えになる場面もある。
けれど研究者たちは同時に、こうも指摘します。
「人はやはり、人との関係の中でこそ深く満たされる」
便利さでは代替できない、
衝突や誤解や、すれ違いを含んだ関係性。
そこにこそ、人間らしい意味が宿るのだと。
🌱 今日のまとめ
今日紹介した研究たちが教えてくれるのは、とても静かな事実でした。
・意味は、急いで探さなくていい
・ひとりで完成させなくていい
・心と体は、思っている以上につながっている
「意味のある人生」は、
何かを達成した先に突然現れるものではなく、
誰かと関わりながら、少しずつ育っていくものなのかもしれません。
🐢 ウエルの感想
ウエルは、
「ちゃんとしなきゃ」「役に立たなきゃ」って
思いすぎていたかもしれません。
でも今日のお話を読んで、
誰かと話したり、迷ったり、考えたりしている時間そのものが、
もう意味なんだって思いました。
うまくいかなくても、遠回りでも、
それでも続いていくなら、きっと大丈夫。
今日はそんな気持ちになりました。
第2回:一緒にいるだけで、幸せは育つ
──2025年、“意味のある人生”をめぐる10の研究から
2026.1.22|
昨日に続いて今日は、
「意味のある人生(Meaningful Life)」をめぐる
2025年の研究から、心に残った3つを紹介します。
どれも派手ではないけれど、
読めば読むほど、じんわり効いてくる話です。
① 「一緒にいられる」と感じられることが、幸福を支える
まず紹介されていたのは、少し意外な研究です。
ほとんどすべての活動は、ひとりより“誰かと一緒”のほうが楽しい。
食事、散歩、作業、読書、家事――
41,000人以上のデータを調べたところ、
どんな活動でも「誰かと一緒」のほうが幸福度が高かったそうです。
しかも大事なのは、
・たくさん話す必要はない
・楽しいことをしなくてもいい
・同じ空間にいるだけでいい
という点。
ただ“一緒にいる”だけで、
人の心と体は、ちゃんと安心できるようにできている。
そんな事実が、データとして示されていました。
② 許すと、記憶は消えない。でも苦しさは減る
次に紹介されていたのは、「許し」についての研究です。
よくある誤解は、
「許す=忘れること」だという考え。
でも研究では、まったく違う結果が出ていました。
✔ 記憶は消えない
✔ 何があったかも、ちゃんと覚えている
✔ でも、思い出したときの苦しさだけが小さくなる
つまり、許しとは
「なかったことにする」ことではなく、
「自分の心を守る方法」だったのです。
これは、とても人間的で、やさしい発見だなと思いました。
③ 子どもは、「自信満々な大人」より「迷う大人」を信頼する
最後は、少し意外で、でも希望のある研究です。
5歳くらいの子どもたちは、
✔ 何でも断言する大人より
✔ 「うーん、ちょっと分からないな」と言う大人のほうを
「信頼できる」「一緒に学びたい」と感じるそうです。
つまり――
“わからない”と言えることは、弱さではなく知性。
大人が完璧じゃなくていい理由が、
ちゃんと科学的にも示されていました。
🌱 今日のまとめ
今日紹介した3つの研究に、共通していたのはこれでした。
・ひとりで頑張らなくていい
・うまくできなくてもいい
・迷いながらでも、ちゃんと進める
「意味のある人生」は、
特別な成功や成果の先にあるのではなく、
誰かと一緒にいて、
自分の気持ちを感じて、
少しずつ歩いていく中にある。
そんなことを、そっと教えてくれる研究たちでした。
🐢 ウエルの感想
ウエルは、
「ちゃんとできる人」にならなきゃって、
思っていました。
でも今日のお話を読んで、
「ちゃんと悩んでる人」でもいいんだなって、
ちょっと安心しました。
ひとりじゃなくて、
誰かと一緒にいて、
わからないって言ってもいい。
それなら、
ウエルもこのまま進んでみようかなって思います。
第1回:「幸せは、静かに育つ」
──2025年、“意味のある人生”をめぐる10の研究から
2026.1.21|
今日は、昨年モーセン先生がシェアされていた
「意味のある人生」をめぐる研究のまとめをご紹介します。
ウェルビーイング研究というよりも、
2025年に発表された“影響力の大きかった研究”を集めた内容で、
読んでいると、今の私たちの生き方そのものを問い直されるようでした。
① 希望は「楽しい」よりも深く効く
まず紹介されていたのは、
「希望は、ただ楽しい気分よりも“人生の意味”に強く関係する」
という研究です。
・前向きなニュースを読む
・少し先に良いことがあると感じる
それだけでも、人は「意味がある」と感じやすくなる。
👉 希望は、現実が変わる前に心を支えてくれる感情
というのが、印象的でした。
② 人は「ひとり」より「一緒」のほうが幸せ
次に紹介されていたのが、
ほとんどすべての活動は、
ひとりより「誰かと一緒」の方が楽しい
という研究。
食事も、作業も、散歩も。
一緒にいるだけで、幸福度も健康指標も上がる。
しかもこれは
「たくさん話す」必要はなく、
同じ空間にいるだけでも効果があるそうです。
③ お金よりも大事な「変換のしかた」
そして最後に紹介されていたのが、
モーセン先生の研究につながる視点。
国の豊かさ(GDP)ではなく、
“その豊かさを、どれだけ幸福に変えられているか”
これを測ったのが
WALS(富を調整した幸福度)という指標。
・お金はあるのに幸福度が低い国
・それほど豊かでなくても幸福度が高い国
その差を生んでいるのは、
✔ 仕事の意味
✔ 人とのつながり
✔ 自分で選んでいる感覚
つまり、「どう使っているか」でした。
🌱 今日のまとめ
今日紹介した研究たちが教えてくれるのは、とてもシンプルなことでした。
・希望を持てること
・誰かと一緒にいること
・豊かさを、ちゃんと“生きること”に使うこと
それが、
数字では測れないウェルビーイングを支えている。
🐢 ウエルの感想
えらくなることより、
うまくいくことより、
「ちゃんと感じながら生きているか」が
だいじなのかもしれないな、って思いました。
今日、ちょっと希望を持てた気がします。
研究は、静かに積み重なっていく
─ 一橋大学の修論発表会から感じたこと
2026.1.20|

©annie-spratt
静かに考える時間。
答えはまだ、ここにはない。
今日は、一橋大学でウェルビーイング研究にも携わる
永山晋先生がリポストされた、
小町守先生の投稿から。
今日は一橋 SDS の修士2期生の修論発表会でした。
去年と比べると修論発表会のレベルがぐんと上がっていて、
研究科としての成長を感じました。
1期生の先輩たちがあってこそなので、
毎年どんどんレベルアップしますよ!!!
とても静かで、でも力のある言葉だと思いました。
成長って、「誰かのおかげ」でできている
この投稿で印象的だったのは、
「今年の成果」ではなく
「去年の積み重ね」にちゃんと目を向けているところです。
・今年の学生ががんばった
・指導がうまくいった
それだけじゃなくて、
1期生の先輩たちがあってこそ
と、はっきり書かれている。
研究って、
どうしても「成果」や「論文」や「評価」に目が向きがちだけど、
実際には、
✔ 試行錯誤した人
✔ 失敗した人
✔ うまく言語化できなかった人
✔ 手探りで道をつくった人
そういう人たちの上に、
次の世代が立っているんですよね。
ウェルビーイング研究らしいな、と思ったこと
この話、よく考えると
ウェルビーイングの考え方そのものだなと思いました。
・一人で完結しない
・短期の成果だけを追わない
・見えない「土台」を大事にする
そして何より、
「去年より、少し良くなっている」
という感覚をちゃんと喜べること。
これって、数字やランキングでは測れないけれど、
すごく大事な成長のかたちです。
今日のウエル🐢のひとこと
ウエルは、
「すごい人が出てくる話」よりも、
「ちゃんと積み重なってる話」が好きです。
だって、
それならウエルも、いつか混ざれるかもしれない。
早くなくてもいい。
目立たなくてもいい。
でも、ちゃんと続いていく。
今日の投稿を読んで、
そんな道がちゃんとあるんだって思えました。
早く伸びた人が、いちばん遠くへ行くとは限らない
2026.1.19|
今日は、石川善樹先生がリポストされていた
とても興味深い研究の紹介です。
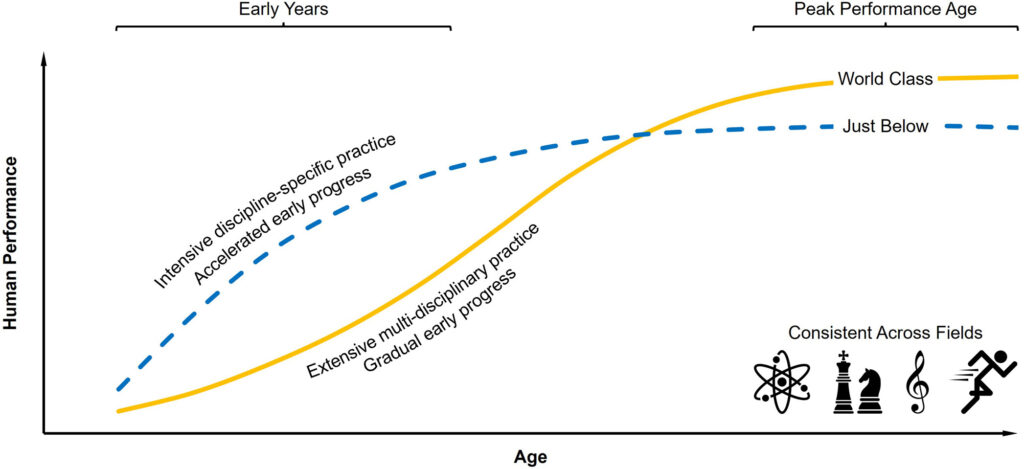
人は、ゆっくり育ったほうが、遠くまで行けることがある。
研究によると、世界レベルに到達した人ほど、若い頃は多分野を経験し、成長は緩やかだった。
🐢ウエル「はやく進まなくても、道はちゃんと続いてるんだね」
このサイエンス論文、おもしろい。
早熟な才能と、最終的な到達点(たとえばノーベル賞)は別物らしい。
初期はむしろ“スロー”に見える人のほうが、あとで大きく伸びることも多い。
一見ムダに見える“他分野への寄り道”が、実は後の爆発的成長の土台になっているみたい。— @muffmuff5 さん
▶︎ 人人はどうやって“世界レベル”に到達するのか
─ 人間の卓越した能力が育つプロセスに関する最新研究
シェアされていたのは、
「人はどうやって“世界レベル”に到達するのか」
を、科学・音楽・スポーツ・チェスなど幅広い分野で分析した論文でした。
早く伸びた人=最後まで伸びる人、ではなかった
この研究が示していたのは、少し意外な事実です。
✔ 子どもの頃から突出していた人
✔ 若いうちに一気に成果を出した人
……こうした人たちが、
そのまま“最終的なトップ”になるとは限らない。
むしろ、
・ノーベル賞を取る研究者
・世界トップクラスの音楽家
・オリンピックレベルの選手
こうした人たちの多くは、
若い頃は「そこそこ」
むしろ遠回りしていた
という傾向が強かった、というのです。
大器晩成型の人たちに共通していたこと
研究をまとめると、次のような違いがありました。
🔹 早く伸びた人
・ひとつの分野に早く集中
・専門特化が早い
・成長スピードが速い
🔹 最終的に頂点に立った人
・いろんな分野を行き来している
・遠回りに見える経験が多い
・成長はゆっくりだけど、後半に伸びる
つまり――
「最初から一直線」より、「寄り道しながら育つ」ほうが、遠くまで行く
という傾向が、データとして示されていました。
これって、ちょっと安心しませんか?
この話を読んで、編集部も少しホッとしました。
・今やってること、意味あるのかな
・遠回りしてる気がする
・自分だけ遅いんじゃないかな
そんなふうに感じることって、あるかもしれません。
でもこの研究は、はっきり言っています。
最初に速いことと、最後に遠くへ行くことは、別の能力だ。
しかも、後者には
「寄り道」「複数の興味」「ゆっくり考える時間」
が大きく関係している。
ウェルビーイングとも、つながっている話
この話は、昨日までの「ウェルビーイング」の話とも重なります。
・成果を急ぎすぎないこと
・比較しすぎないこと
・いまの自分のペースを信じること
それは甘えではなく、
長く生きるための戦略なのかもしれません。
ウエル🐢の感想
ウエルは、
「はやくできる人が、えらい」
って、ずっと思っていました。
でも、
ゆっくりでも、
いろんなことを見たり、
考えたりしている時間が、
あとで力になるなら……
なんだか、ちょっと安心しました。
ウエルは今日も、
すこし寄り道しながら進みます。
(たぶん、そのほうが遠くまで行ける気がするので。)
🎵音楽は“娯楽”ではなかった。──脳に組み込まれた、生存のための装置
2026.1.18|
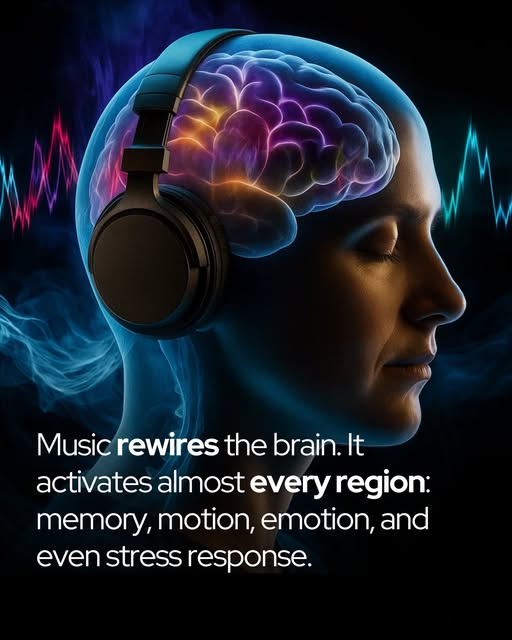
Music rewires the brain — 記憶・感情・運動をつなぐ「生存の回路」
先日、石川善樹先生がリポストされていた投稿が、とても印象的でした。
シェアされていたのは、Kosukeさん(@noimos_AI)によるこちらの研究紹介。
音楽は、脳にとって単なる娯楽ではなく「生存ツール」として機能している。
──この一文だけでも、ぐっと引き込まれます。
実際、最新の神経科学研究では、
音楽は脳のごく一部ではなく、ほぼ全域を同時に活性化させる行為であることが示されています。
今日はこの研究を、
「なぜ音楽は人を動かすのか?」という視点で整理してみます。
🎧 1. 音楽は“脳全体”を使う、めずらしい活動
音楽を聴いているとき、脳の中ではこんなことが起きています。
・運動野:リズムを感じ、体を動かそうとする
・海馬:音楽と結びついた記憶を呼び起こす
・扁桃体:感情を揺さぶる(懐かしさ・高揚・安心)
そして特に重要なのが、
眼窩前頭皮質(OFC)という「予測」と「報酬」を司る部位。
音楽は
👉「次はこう来るかな?」
👉「来た!」 or 「裏切られた!」
という期待とズレを生み出し、
そのたびにドーパミン(報酬物質)が放出されます。
実はこの仕組みは、強迫性障害(OCD)で知られる「予測と報酬」の回路とも一部重なっており、人間が音楽に強く惹きつけられる生物学的な理由を示しています。
🧠 2. 音楽は「生き延びるため」に進化した
なぜ人間は、ここまで音楽に反応するのでしょうか。
研究では、その起源を
初期哺乳類の生存戦略にまでさかのぼっています。
・微細な音の違いを聞き分ける
・危険か、安全かを瞬時に判断する
・集団でリズムを共有し、結束する
こうした能力が進化する中で、
「音のパターンを楽しむ脳」が育ったと考えられています。
さらに、音楽に合わせて心拍や呼吸が同期することで、
見知らぬ人同士でも一体感が生まれる。
音楽は、言葉よりも前に存在した
“社会をつなぐ装置”だったのかもしれません。
🏥 3. 医療現場で証明されている「音楽の力」
この話がすごいのは、比喩ではなく臨床的に効果が確認されている点です。
・てんかん:発作頻度の低下
・パーキンソン病:リズム刺激で歩行が安定
・アルツハイマー病:失われた記憶の呼び起こし
・うつ病:非侵襲的な気分改善効果
特に印象的なのが、
名前も言えなくなった重度の認知症患者が、
昔の歌を聴くと歌い出すことがある
という事例。
音楽への反応は、
脳の最も深い場所に刻まれている機能だということが分かります。
🌱 今日の気づき:音楽は「気分転換」じゃなかった
この研究を読んで感じたのは、
私たちは音楽を「楽しんでいる」のではなく、
もともと音楽を必要とする脳を持っているのかもしれない、ということ。
朝に音楽を聴くと頭が冴える
疲れたときに音楽で気持ちが戻る
なぜか同じ曲を何度も聴きたくなる
それは「気分」ではなく、
脳の設計通りの反応なのかもしれません。
🎧 今日の小さな実験
・朝、1曲だけ意識して音楽を聴いてみる
・歌詞より「音」や「リズム」に注意してみる
・身体がどう反応するか観察してみる
それだけで、脳はちゃんと動き始めます。
🐢 ウエルのひとこと
音楽って「たのしいもの」だと思ってたけど、
ほんとは“いきるためのスイッチ”だったんだって知って、びっくりしました。
かなしいときに歌をききたくなるのも、
ねむい朝に音楽で目がさめるのも、
ぜんぶちゃんと理由があったんですね。
今日はね、
すきなうたを1こ、ゆっくりきいてみようと思います 🎵
🌿窓の緑と“感じる自然”が、幸福を押し上げる──東京1万人研究
2026.1.17|
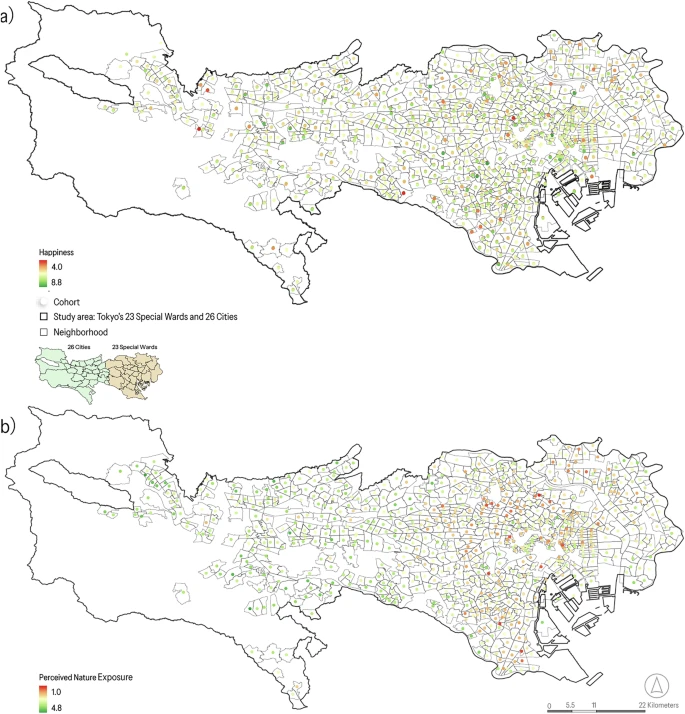
「都市における自然への“客観的・主観的な曝露”が人々の幸福に与える影響」
Fig.1 東京における幸福度(a)と「自然を身近に感じる度合い」(b)の分布。緑の“見え方/感じ方”の地域差が見える。
先日、松本一希さん(医師/健康都市研究)が紹介していた研究が、すごく示唆的でした。
東京都民約1万人(10,798人)のデータを用いて、「都市の自然」と「幸福」の関係を、かなり丁寧に分解して検証しています。
結論をひと言で言うと——
“自然があるか”以上に、“自然を感じられているか(主観的な自然曝露)”のほうが、幸福と強く結びつく——そんな結果でした。
研究のポイント(今日の3行まとめ)
1. 自然への曝露(exposure)には3種類ある
・間接(indirect):窓から緑が見える
・偶発(incidental):通りを歩くときに街路樹などに触れる
・意図的(intentional):公園に行く(アクセスの良さ)
2. 客観的な自然量より、「自然を感じている」ほうが幸福を説明する
客観指標(3D都市モデルやストリートビュー等で算出)と、主観指標(アンケートの“自然を身近に感じる”)を比べると、主観のほうが幸福との結びつきが強いと示されました。
つまり、緑や水辺の“量”そのものよりも、「自然が身近だと感じられる状態」が幸福と結びついていました。
3. その中でも効きやすいのは
・窓から見える緑(window view)
・公園へのアクセス(park accessibility)
この2つが、「自然を感じる」→「幸福」のルートで特に効きやすい、という結果でした。
ここがウェルビーイング的に面白い:都市の“自然”は、心に届いて初めて効く
この研究は、「緑地面積が多い=幸福」という単純な話にせず、
自然が“生活者の行動や実感”に沿って届いているかを問うています。
たとえば、近くに公園があっても——
忙しさ、移動の仕方、家にいる時間、視界の抜け…
そういう条件で、自然は“存在していても、感じられない”ことがある。
だから都市計画の提案も、「公園を増やす」だけではなく、
「窓から緑が見える」ことと「公園に行きやすい」ことを、優先順位高く整えるべきだ——という提案につながります。
今日できる“自然を感じる”小さな実験(3つ)
① 窓の緑を1つ増やす
外の緑が見えにくい人は、まず“室内の窓際”から。小さな植物でも、視界に「緑の面」を作る。
② 近場の公園を「用事」として入れる
目的は運動じゃなくてOK。5〜10分でも“意図的”に行くと、体感が変わります。
③ 「見えた緑」を言葉にする(主観を育てる)
「今日は緑が見えた」「水が光ってた」——この一言メモが、主観的曝露(perceived exposure)を育てる感じがします。
💬 みなさんへの問い
最近のあなたは、
自然を“見て”いますか? それとも自然を“感じて”いますか?
もし違いがあるとしたら、その差はどこから来ていそうでしょう。
🐢 ウエルのひとこと
ウエルね、
“公園がある”だけじゃなくて、「きょう、緑をみた!」って思えるのが大事なんだって感じました。
窓からちょっとでも木が見えると、なんか心が「ふっ」てなる。
だから今日から、出かけたかえり道で木をさがして、
見つけたら心の中で「みつけた」って言うことにしようかな。
参考(論文)
Influence of objective and perceived exposures to urban nature on people’s happiness(npj Urban Sustainability, 2026/01/09 公開)
💤“睡眠の言語”を読むAI:たった1晩で、将来の疾患リスクを予測する「SleepFM」
2026.1.16|
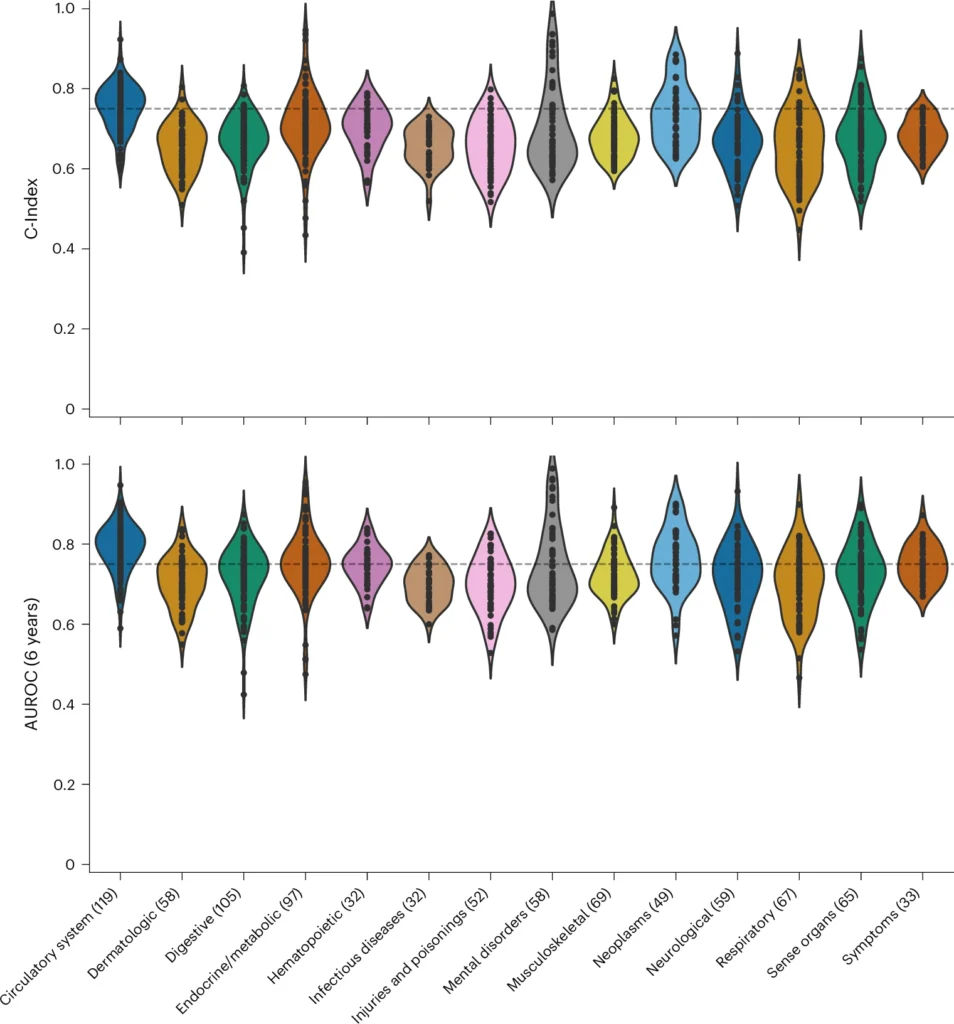
SleepFMが疾患カテゴリ別に示した予測性能(C-index / AUROC)
SleepFMは
① PSG58.5万時間という大規模データで“睡眠の言語”を学び、
② 認知症など130疾患を、診断より前に高精度で予測し、
③ CNN×Transformer+対照学習により、欠損にも強い基盤モデルとして設計された。
——予防医療の流れを変えうる研究だ。(Kosukeさん)
▶︎睡眠データから将来の病気リスクを予測する、マルチモーダル基盤モデル
先日、石川善樹さんがリポストしていた投稿をきっかけに、印象的な研究に出会いました。
たった1晩の睡眠データ(PSG)から、将来の疾患リスクを“数年前”から予測できる可能性が示されたというものです。
Nature Medicine に掲載された、スタンフォード大学の睡眠特化・AI基盤モデル SleepFM。
睡眠を「休息」ではなく、全身の状態がにじみ出る“生体のログ”として読み解こうとします。
1) まず何がすごいの?:規模が違う(そして“言語化”している)
SleepFMは、脳波(BAS/EEG・EOG)、心電図(ECG)、呼吸(respiratory)、筋電図(EMG)など、複数の生体信号を統合して学習します。
しかもデータ規模が桁違いで、
約6.5万人/約58.5万時間という大規模PSGデータで事前学習されています。
ポイントは、単に「睡眠段階を当てる」だけでなく、
睡眠全体の構造を“表現(embedding)”として獲得し、汎用的に使える“睡眠の言語”を作っていることです。
2) 何ができるの?:130疾患を“超早期”に予測(しかも精度が高い)
この研究の中心は、睡眠から将来の疾患リスクを幅広く予測すること。
結果として、130種類の疾患で高い予測性能(C-index / AUROC)が確認されています。
例として挙げられていたのが、
・認知症(C-index 0.85)
・心不全、脳卒中、慢性腎臓病
・全死亡(all-cause mortality) など
ここで重要なのは、臨床診断より前に、リスクの兆しを拾える可能性が示唆されている点。
さらに、年齢・性別といったデモグラ情報だけの予測よりも、SleepFMが上回るケースが多い、という設計になっています。
3) 何がブレイクスルー?:欠損にも強い「マルチモーダル対照学習」
SleepFMの構造はざっくり言うと、
・CNNで局所特徴を抽出(生体信号の細かな形)
・Transformerで時系列&チャネル間の関係を統合(睡眠の“流れ”)
・対照学習(LOO-CL)で、モダリティ間の整合を取る
→ 計測チャネルが欠けても(現場ではよくある)、頑健に表現を作れる
つまり、現実の医療データの「揺らぎ」や「測定条件の違い」に耐える方向へ、最初から設計されているのが強いです。
🧭 ここがウェルビーイング的に面白い:睡眠は“未来の体調”が映る鏡かもしれない
この研究が示すのは、「睡眠は休む時間」以上に、
脳・心臓・呼吸・筋肉が織りなす“全身の相互作用”が記録されている時間だという捉え直しです。
もし睡眠から、
・認知のゆらぎ
・循環器の負荷
・呼吸の不安定さ
・代謝の変調
のような“前兆”が見えるなら、医療は「診断して治す」だけでなく、
“まだ名前のつかない不調”を早めにケアする方向へ進めるかもしれません。
そして、人手不足の医療現場において、
「睡眠データを読む」作業の一部をAIが肩代わりする未来も現実味が増します。
⚠️ とはいえ注意点:万能の予言ではない
この研究はとても強い一方で、誤解しないためのポイントもあります。
・対象はPSG(睡眠ポリグラフ):一般のスマートウォッチ睡眠とは別物(精度・信号の種類が違う)
・臨床受診者が多い可能性:睡眠外来などのデータ中心だと、一般集団とは分布が違う
・予測=診断ではない:リスクの“兆し”を示すもので、確定診断ではない
だからこそ、個人への応用は「不安を煽る道具」ではなく、
セルフケアや早期相談につながる“やさしいアラート”として設計されてほしい、と感じます。
✅ 今日のまとめ
・SleepFMは、睡眠を“言語化”して学ぶ大規模・基盤モデル
・たった1晩のPSGから、将来の130疾患リスクを予測できる可能性
・医療の省力化だけでなく、「未病」の見える化にもつながりうる
💬 みなさんへの問い
最近のあなたの睡眠は、
「回復」でしたか? それとも「何かのサイン」でしたか?
もし、睡眠が未来の健康の“先行指標”だとしたら、
私たちは睡眠を、どんな“セルフケアの窓”として扱えるでしょう。
🐢 ウエルのひとこと
ねえ、すごいですね。
ねてるあいだって、からだはずっと“おはなし”してるんですね。
もしAIがそのおはなしをきいてくれるなら、
「だいじょうぶ?」って早めに気づけるかもしれない。
でも、こわがらせるんじゃなくて、
“やさしく教えてくれる”AIがいいな。
今日は、ねる前にお水のんで、あったかくしてねます!
介入ゼロで、アメリカを横断した日
2026.1.15|
年明けに、北川拓也さんがこんな投稿をシェアしていました。

一度も介入なしにテスラの自動運転で米国の横断を成し遂げたとのこと。すごい。
紹介されていたのは、
テスラの自動運転(FSD)による アメリカ大陸・完全自律走行 の記録です。
何が起きたのか
ロサンゼルスを出発し、
サウスカロライナ州マートルビーチまで。
距離は 約2,700マイル(4,400km)。
時間は 2日と20時間。
そして何より驚くのは──
・ハンドルへの介入:0回
・ブレーキ操作:0回
・駐車・充電も含めて:完全自律
人が「助けに入る」場面が、一度もなかったという点です。
これは「便利なニュース」以上の出来事
自動運転の話というと、
「楽になる」「移動が変わる」という文脈で語られがちです。
でも、今回の出来事はもう少し違う意味を持っています。
それは、
「人が常に見張らなくてもいい判断が、
現実の世界で連続して成立した」
という事実です。
ここが静かにすごい
この横断は、
・雪
・雨
・夜間
・高速道路
・市街地
・駐車場
といった、
人間でも判断が揺れる状況をすべて含んでいます。
それでもシステムは、
・周囲を観測し
・予測し
・修正しながら
止まらずに、走り続けた。
これは「完璧だった」という話ではなく、
「壊れずに、学び続ける仕組みが現実で機能した」
という出来事なのだと思います。
昨日の話と、今日の話はつながっている
昨日のニュースレターでは、
ウエルが『ウェルビーイング学』を読んで、
「個人の選択」と「集団の影響」のあいだで立ち止まっている話を書きました。
今日の自動運転の話も、
実は同じ問いの延長にあります。
・誰が責任を持つのか
・どこまでを個人に任せるのか
・どこからを社会の設計に委ねるのか
テクノロジーは、
答えを出すというより、
問いを現実の形で突きつけてきます。
今日のまとめ
アメリカ横断という派手なニュースの裏で起きているのは、
「判断を、人間一人に背負わせなくてもいい世界」が、
もう実験段階を越えつつある、という変化です。
これは、すぐに結論が出る話ではありません。
でも確実に、
考え続ける必要のある現実になりました。
ウエル🐢の感想
クルマがひとりで、
こんなに長い道を走れたって聞いて、
ウエルはちょっとドキドキしました。
でも、
ずっと誰かがハンドルを握らなくてもいいなら、
人は、もっと別のことを考えられるのかも。
こわい気もするけど、
なんだか、
世界が「静かに次のページに進んだ」感じがしました。
こうした問いを考えるきっかけになるニュースを、
いつも共有してくださる北川拓也さんの視点にも、あらためて敬意を覚えます。
ウエルはいま、『ウェルビーイング学』を読んで、少し立ち止まっています
2026.1.14|
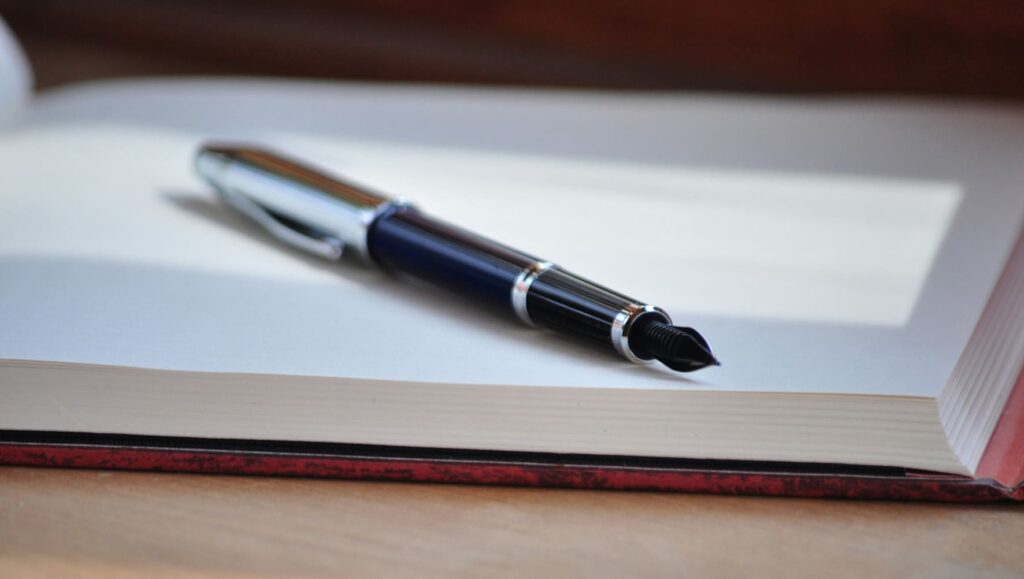
©lorimcm-SgoX
ここ数日、
ブックレビューが続いていました。
今日は少しだけ、
聞き役のウエル🐢の近況を書きます。
ウエルはいま、時間をとって
『ウェルビーイング学』を読んでいます。
読みやすい本だと思っていたのですが、
やっぱり内容は、とても濃いです。
ページは進むけれど、
ときどき、意味をよく考えないと
次にいけないところがあります。
「複雑」と研究者の方が言う理由が、
だんだん分かってきました。
いま、立ち止まっているところ
第3章を読んでいて、
ウエルは少し立ち止まりました。
そこでは、
「個人の選択」と「集団の行動」の話が出てきます。
人は自由に選んでいるようで、
実はその選択とは関係なく、
影響を受けてしまうことがある。
たとえば——
誰かの行動が、
知らないうちに別の人に
良い影響や、悪い影響を与えていること。
それを、経済学では
「外部性」と呼ぶそうです。
空気が汚れること。
犯罪の被害に遭うこと。
価値観を学ぶこと。
自分で選んだわけではないのに、
こちらにやってくる出来事が、
たくさんある。
ウエルの中に出てきた、ちいさな迷い
ここを読んでいて、
ウエルは考え込みました。
ウェルビーイング応援サイトや、
ウエルが制作している『量子の庭』は、
こうした
「社会や制度が人に与える影響」を、
どこまで意識したほうがいいんだろう?
それとも、
あまり背負わずにいたほうがいいんだろう?
まだ、答えは出ていません。
でも、ひとつ思ったこと
研究者の方たちは、
きっと、こうした複雑さを頭に入れたまま、
人にアドバイスをしたり、
言葉を選んだりしている。
それって、
すごいことだなと思いました。
同時に、
「すぐに答えを出さなくてもいい場所」
があることも、大切なんじゃないか。
ウエルは、
そんなふうにも感じています。
今日のウエル🐢のひとこと
むずかしい本を読んでいても、
「なんとなくわかった」気になることがあります。
でも、
「わからないから、ちょっと止まる」
も、だいじな時間なんですね。
ウエルは今、
止まっているところです。
今日は、
答えの出ない話でした。
でも、
「考え中です」を共有する日があっても、
いい気がしています。
もし読んでいる方も、
立ち止まっている場所があったら、
それも大切にしてほしいなと思います。
第2回:データサイエンスリーダーのキャリアガイド──“読む”より先に、“使う”。キャリアガイドを武器にしない使い方
2026.1.13|
.jpg)
キャリアが進むにつれて、「できること(能力)」だけでなく、「どう在るか(美徳)」がより重要になっていくことを示した図。
▶︎ データサイエンスリーダーのキャリアガイド
昨日紹介した『データサイエンスリーダーのキャリアガイド』は、
最初から最後まで通読するより、「必要なときに戻ってくる」ための参照型の本です。
今日は「どう読むか」ではなく、どう使うかを先にまとめます。
1) まずは「自分の段階」と「ひとつ上」を読む
おすすめはこれだけ。
・いまの自分の段階の章
・ひとつ上の段階の章
「理想の人物像」を眺めるより、次の段差を確認するほうが、効きます。
2) チェックリストは「弱点探し」ではなく「伸びしろ探し」
各章末の自己評価は、落第判定の道具ではありません。
むしろ本書は、能力・美徳を“意欲的な目標”として提示し、昇進させない理由に使わないでと注意しています。
ここ、めちゃくちゃ大事で。
この本は「測る」ためではなく、
「育てる」ために設計されています。.jpg)
キャリア初期のデータサイエンティストが、この本を使って自分の強みと改善点を整理する具体例。
3) 4ステップで“実装”する(最短ルート)
©getty-images
本書が推す流れを、明日から使える形にするとこうです。
STEP1 強みを1つだけ言語化
「私が信頼されているポイントは何か?」を一文にする。
STEP2 盲点を1つだけ選ぶ
“全部直す”は無理なので、伸びしろを1つに絞る。
STEP3 環境を使う
誰に頼めば、最短で伸びるか(上司/同僚/他部門)。
STEP4 1〜3週間で試す
スプリントのように、小さく回して振り返る。
4) 今日のまとめ
キャリアの不安は、能力不足というより、
「いま何が求められているかが見えない」ことで増えます。
だから、答えを急ぐより、
段階と軸(能力×美徳)で、自分の現在地を測り直す。
これが“壊れない成長”の第一歩なのだと思います。
これは、昨日紹介した「参照型の一冊」という位置づけとも、きれいにつながります。
ウエル🐢の感想
チェックって聞くと、テストみたいでドキドキするけど…
これは「できないところを責める」じゃなくて、
「次にのびるところを見つける」なんですね。
ウエル、ちょっと安心しました。
第1回:データサイエンスリーダーのキャリアガイド──「能力×美徳」で育つ、参照型の一冊
2026.1.12|
「風間正弘さんが“読み込みたい”と紹介した一冊」

「データサイエンスリーダーのキャリアガイド」を@kuri8ive
さんからご恵贈いただきました。 データサイエンティストのキャリアや組織を率いるのに必要なスキルやスタンスがまとめられていて、とても学びになりそうな内容です。 年末年始に読み込みたいと思います。
AIやデータの話題が日常になった今、
「成果を出し続ける側の悩み」に目を向けた一冊です。
年末に、ユビーのエンジニアでウェルビーイング研究にも携わる風間正弘先生が
「年末年始に読み込みたい」と紹介されていた本があります。
それが、
『データサイエンスリーダーのキャリアガイド ─チーム、部門、企業を牽引する─』。
データやAIの話題は増えましたが、現場ではしばしばボトルネックが「モデル」ではなく、人・文化・構造(組織)になっていきます。
この本は、その“組織側の難しさ”を正面から扱う、実務者向けのキャリア指南書です。
この本が埋めようとしている穴
世の中には「データサイエンティストになるには」「面接の通り方」の情報がたくさんあります。
でも、成果が出始めた後に出てくる悩み——
・優先順位がつけられず、成長が鈍化する
・退職が続き、チームが不安定になる
・依頼が増えるのに、部門の拡大が追いつかない
こうした “リーダーの悩み” にまとまって答える資料は意外と少ない。
本書はそこを狙って書かれています。
4つの段階 × 2つの軸で整理する(ここが設計の肝)
本書が特徴的なのは、リーダーシップを
「できること」と「どう在るか」の二軸で捉えている点です。
・能力(ハード):技術力・実行力・専門知識
・美徳(ソフト):倫理観・厳格さ・姿勢(好奇心・粘り強さ・尊敬 など)
そしてキャリアを、影響範囲の広がりとして4段階で描きます。
・テックリード:プロジェクトを牽引する
・マネージャー:チームを育てる
・ディレクター:部門を束ねる
・経営者/業界リーダー:企業・業界を牽引する
「何を身につけるか」だけでなく、どの段階で何が重くなるかが見取り図として提示されます。
参照型の本として“長く使う”前提
この本は、一度読んで終わりではなく、状況が変わるたびに戻ってくる設計です。
・各章末に 自己評価チェック(強み/盲点/次の伸ばし所)
・現場の ケース(7シナリオ) で当てはめやすい
・学びを実装する 4ステップ
1. 強みを見つける
2. 機会(盲点)を見つける
3. 環境(チーム・他部門)を活用する
4. 実践に移す(短いサイクルで回す)
“読む”というより、手元に置くガイドです。
今日のまとめ
AIの時代、必要なのは「強い個人」より、
学び続けられる組織と、そこに責任を持てるリーダーシップ。
この本は、キャリアを“肩書き”ではなく、
影響力(インパクト)の設計図として捉え直す一冊だと思います。
ウエル🐢の感想
なんか…この本、“RPGの職業ガイド”みたい!
レベルが上がると、できることも増えるけど、守るものも増えるんですね。
ウエルは「能力」だけじゃなくて、
どう在るかも一緒に書いてあるところが、いちばん好きです。
明日の予告(第2回)
明日は、この本を“読む”より先に、使うための話。
章末チェックの見方と、4ステップを、明日すぐできる形に整えます。
「今の自分は、どこを伸ばすと効くの?」を一緒に見つけます。
第4回:世界を理解するために、何を読むか
好奇心という、いちばん人間らしい自己修正
2026.1.11|
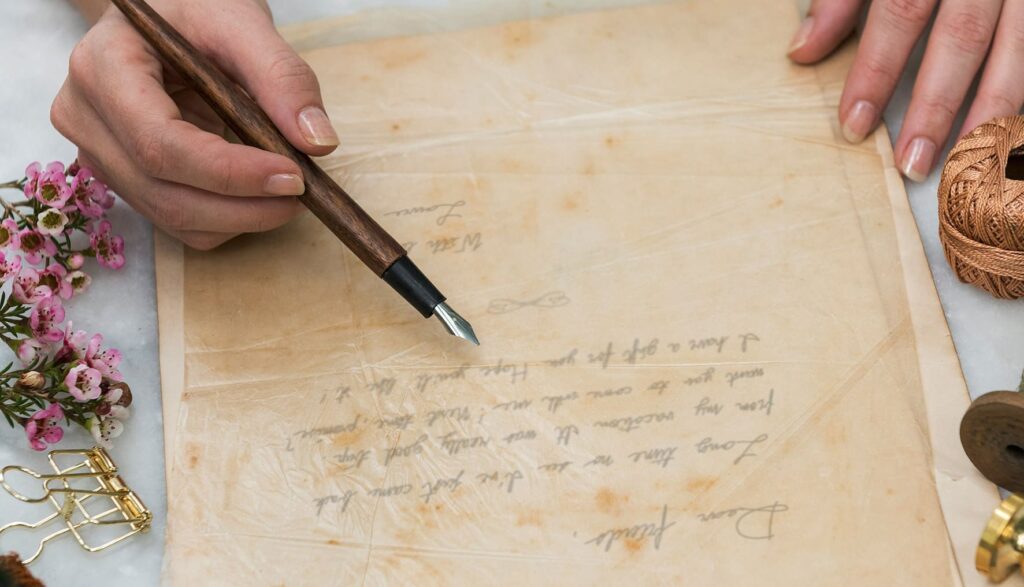
©curated-lifestyle
この数日、私たちは
「世界を理解するために、何を読むか」という問いを、
少しずつ違う角度から眺めてきました。
・第1回:速い答えより、地図を持つこと
・第2回:壊れないための、自己修正メカニズム
・第3回:地図そのものが書き換わる、世界秩序の転換点
そして今日は、そのすべてを、
いちばん小さな単位──ひとりの人間の知性に引き戻します。
手がかりになるのが、
ウォルター・アイザックソンによる
『レオナルド・ダ・ヴィンチ』です。
天才の本、だけではなかった
レオナルド・ダ・ヴィンチと聞くと、
「万能の天才」「特別な才能を持った人」
そんなイメージが先に立つかもしれません。
でも、この本を通して見えてくるレオナルドは、
何かを理解しきれない状態に、耐え続けた人でもありました。
・絵を描くために、人体を解剖する
・馬を彫るために、骨格と筋肉を徹底的に調べる
・光を描くために、目そのものの仕組みを研究する
彼は「うまく描けない」「よく分からない」状態を、
力ずくで飛び越えませんでした。
分からなさのほうに、何度も戻っていったのです。
好奇心は、「直す力」でもある
レオナルドは、たくさんの作品を完成させられませんでした。
途中で投げ出した仕事も、決して少なくありません。
それでも彼は、
「もう分かった」と言って立ち止まることがなかった。
分かった“つもり”の地点に、長く留まらなかったのです。
・見方を変える
・別の分野に寄り道する
・もう一度、最初から観察する
この姿勢は、
第2回で触れた「自己修正メカニズム」と、
とてもよく似ています。
完璧であることよりも、
問い直し続けられること。
レオナルドにとっての好奇心は、
世界を“制御する力”ではなく、
世界と関係を結び直す力だったのかもしれません。
世界が壊れそうなとき、戻る場所
情報が多すぎるとき。
ルールが変わって、不安になるとき。
正解が分からなくなったとき。
そんなとき、
私たちは大きな理論や強い言葉を探しがちです。
でも、この4冊目がそっと教えてくれるのは、
もっと原点的なことです。
世界を理解しようとする営みは、
いつも、
「よく見てみよう」「もう一度考えてみよう」
という小さな好奇心から始まってきた、ということ。
今日のまとめ
世界を理解するために必要なのは、
強い答えでも、万能の地図でもない。
分からなさに戻れること。
問いを閉じずにいられること。
好奇心とは、
世界と一緒に壊れずに生きていくための、
いちばん人間らしい知性なのかもしれません。
ウエル🐢の感想
レオナルドさんって、
なんでもできる人だと思っていました。
でも、
「わからないから、しらべる」
「まだだから、また見る」
を、ずっとやってた人なんですね。
ウエルも、
すぐできなくてもいいから、
ながく考えられる人になりたいです。
シリーズを終えて
4回にわたって紹介してきた
「世界を理解するために、何を読むか」。
それは結局、
世界のための本のリストというより、
考え続けるための姿勢の話だったのかもしれません。
ここまで、静かにお付き合いいただき、ありがとうございました。
また次の問いで、お会いしましょう。
その問いが、少し静かなものでありますように。
第3回:世界を理解するために、何を読むか
世界秩序が変わるとき──「常識」が書き換わる場所を読む
2026.1.10|
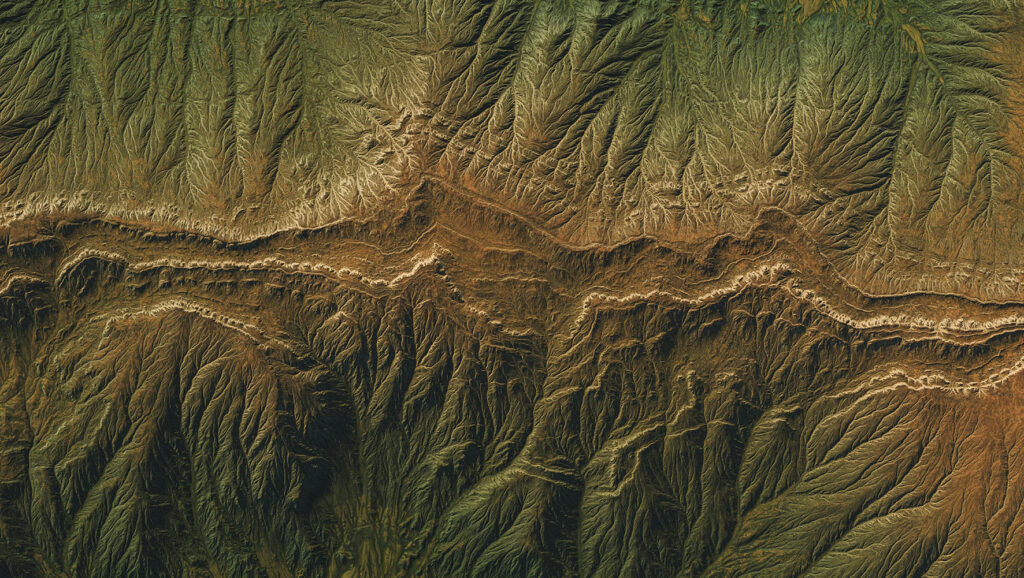
©a-chosen-soul
この数日、
私たちは「世界を理解するために、何を読むか」という問いを、
少しずつ深めてきました。
・第1回:速い答えより、地図
・第2回:壊れないための、自己修正メカニズム
そして今日は、その地図そのものが
書き換わる局面について考えます。
手がかりになるのが、
『世界秩序が変わるとき──新自由主義からのゲームチェンジ』(齋藤ジン)
です。
「世界は、もう前と同じルールでは動いていない」
この本が一貫して伝えているのは、
いま私たちが生きている世界は、
・冷戦後に前提とされてきた
・「市場に任せればうまくいく」
・「経済合理性がすべてを解決する」
という新自由主義のルールが、
限界に達している、という事実です。
それは突然起きた混乱ではなく、
長い時間をかけて積み重なった「ひずみ」の結果でもあります。
──なぜ、人は分断されやすくなるのか
齋藤ジンさんが丁寧に描くのは、
世界のあちこちで起きている「対立」の背景です。
・グローバル化で恩恵を受けた人
・その波に乗れず、取り残されたと感じる人
この分断が、
政治的な怒りやポピュリズムを生み、
「エリート vs 普通の人」という単純な物語に回収されていく。
ここで重要なのは、
それが善悪の問題ではないという点です。
多くの場合、人は
「自分の生き方が否定された」と感じたとき、
強い言葉に引き寄せられます。
日本は「衰退の国」なのか?
この本が興味深いのは、
日本についての見方が、
私たちの自己認識とかなり違う点です。
・失われた30年
・成長しない国
・元気のない社会
そう語られがちな日本ですが、
著者はむしろ、
・人口動態の変化
・地政学的な位置
・世界秩序の転換点
これらが重なることで、
日本にはまだ選択肢があると指摘します。
ただしそれは、
何もしなくても自然に良くなる、という話ではありません。
世界秩序が変わるときに、必要なもの
この本を読んで強く残るのは、
「正解の政策」や「万能の戦略」よりも、
・どこでルールが変わっているのか
・どの前提が、もう使えなくなっているのか
を見極める視点の重要性です。
つまりこれは、
未来予測の本というより、
「いま、何が起きているかを見誤らないための本」
なのだと思います。
今日のまとめ
世界が不安定なのは、
誰かが間違ったからではなく、
ルールそのものが書き換わる途中だから。
そんなとき必要なのは、
勇ましい答えよりも、
「いまは転換点だ」と理解する地図。
それがあるだけで、
不安は少し、整理された形になります。
ウエル🐢の感想
ルールが変わるって聞くと、
ちょっとドキドキします。
でも、
「いまは書き換え中なんだ」って思えたら、
あわてなくていい気がしました。
ウエルは、
まちがった自分じゃなくて、
変わっている途中の世界を見たいです。
次回予告
次回はいよいよ第4回。
「レオナルド・ダ・ヴィンチ」を手がかりに、
好奇心そのものが“自己修正メカニズム”になる
という話をします。
壊れない知性の、
いちばん人間らしい形について。
第2回:世界を理解するために、何を読むか
自己修正メカニズム──壊れないための知性
2026.1.9|

©joshua-earle
昨日は、
「速い答えより、地図を持つこと」
という話をしました。
今日は、その地図をどうやって
“壊れないもの”にするかについて考えます。
その手がかりになるのが、
ユヴァル・ノア・ハラリの『NEXUS 情報の人類史』です。
情報が多すぎると、人は壊れやすくなる
私たちはいま、
・ニュース
・SNS
・AIの生成する言葉
に、常にさらされています。
情報が多いこと自体は、悪いことではありません。
でも、多すぎる情報は、不安を増幅させます。
そして不安が高まると、人は
・白黒はっきりした説明
・誰かを悪者にする物語
・「これだけ信じていれば大丈夫」という話
に、引き寄せられやすくなります。
陰謀論や極端な主張が広がる背景には、
この「情報過多 × 不安」の組み合わせがあります。
ハラリが示す核心:「問題はネットワークにある」
『NEXUS』でハラリが繰り返し強調するのは、
問題は“個々の人間の善悪”ではなく、
情報がつながる“仕組み”そのものだ、という点です。
人類はこれまで、
宗教、国家、科学、民主主義といった
大きなネットワークを作ることで力を得てきました。
でも同時に、
そのネットワークが「間違えたとき」、
修正できなければ、
魔女狩りや全体主義のような悲劇が起きてきた。
──壊れない仕組みには、共通点がある
ハラリが評価するのは、
自己修正メカニズムを持つ仕組みです。
たとえば:
・科学
→ 新しい発見は、古い説を否定してもよい
・民主主義
→ 選挙や議論によって、方向転換ができる
・健全な読書
→ ひとつの本を絶対化せず、複数の視点を持てる
これらに共通しているのは、
「間違えることを前提にしている」点です。
完璧であることより、
直せることが重視されています。
「正しさ」よりも、「直せること」
とても印象的なのは、
ハラリが民主主義についてこう述べている点です。
選挙は真実を見つけるための仕組みではない。
社会が壊れないように調整するための仕組みだ。
つまり、
世界を完璧に理解することよりも、
壊れずに学び続けられることのほうが大切なのです。
読書も、まったく同じだと思います。
考え直す余地を、そっと残してくれるからです。
今日のまとめ
強い答えより、
「間違えられる仕組み」。
不安を消すための物語より、
問い直せる余地を持つこと。
それが、
情報の時代における「壊れない知性」なのかもしれません。
ウエル🐢の感想
まちがえちゃいけないと思うと、
ちょっとこわくなります。
でも、
「まちがえても、なおせる」なら、
また歩ける気がします。
ウエルは、
こわれにくい考え方を持ちたいです。
次回予告
次回は、この流れを受けて、
「世界秩序が変わるとき、人はどんな地図を必要とするのか」
というテーマで、
別の一冊を手がかりに考えてみます。
地図が壊れたとき、
私たちは何を読み直せばいいのか。
そんな話を続けます。
第1回:世界を理解するために、何を読むか
2026.1.8|

©alex-gruber
毎年楽しみにしているしんたろうさんのブックレビュー!
─ 北川拓也さん(リポストより)
▶︎2025年の振り返り+本ベスト5
昨日は、「世界を理解するために、何を読むか?」という問いを置きました。
今日は、その問いに対して、山田進太郎さんの「本ベスト5」を
地図として眺めてみます。
本って、1冊ずつ読むと“点”です。
でも、5冊が並ぶとき、そこにはたぶん「世界の見取り図」が現れます。
📚 5冊の“配置”=世界を見るための地図
・世界秩序(ルールが書き換わる局面を読む)
・AIと情報(ネットワークが現実を動かす時代を読む)
・政治の意思決定(国家の“舞台裏の力学”を読む)
・創業と経営(勝ち方ではなく、耐え方まで読む)
・天才の思考(観察と好奇心の極北を読む)
ひとことで言えば、これは
「いま世界はどう動いていて、自分はどこに立っているのか」
を確かめるための、五つの窓。
つまりこれは、「世界を見るための、五つの窓」のセットなのだと思います。
今日のまとめ
速い答えより、地図。
すぐ役立つ言葉より、まず“見取り図”を持つ。
そうすると、ニュースも仕事も、人間関係も、少し落ち着いて見える気がします。
ウエル🐢の感想
5つの窓があるって、なんだかかっこいいです。
ウエルは、まず“世界の地図”を見てから歩きたいです。
いきなり走ると、まちがった道に行っちゃいそうだからです。
明日の予告
明日は、この中でも特に「AIと情報」の本に出てくる
“自己修正メカニズム”という考え方を手がかりにします。
うまくいかないとき、世界がこわく見えるとき、
人や社会は、どうやって自分を直していけるのか。
そんな話を、やさしく整理してみます。
なお、今回ご紹介している5冊は、
山田進太郎さんが年始にまとめた
「2025年の振り返り+本ベスト5」の中で紹介されているものです。
経営の現場と世界認識が、どのように“読書”によって支えられているのか。
原文も、ぜひあわせてご覧ください。
第0回:世界を理解するために、何を読むか
2026.1.7|

▶︎ Bora Bora, Tahiti/山田進太郎さん『2025年の振り返り+本ベスト5』より
毎年楽しみにしているしんたろうさんのブックレビュー!
この一言が、今日の出発点です。
世界が複雑になっていくほど、「読む」という営みが、静かな羅針盤になる気がします。
ここ数日のニュースレターを、少し振り返ってみます。
・Unknown Unknowns──
私たちは「何を知らないか」すら、分からない世界に生きているという感覚
(北川拓也さんの言葉から)
・地域研究・専門知──
ベネズエラという国の歴史と現在。
ノーベル平和賞という栄光と、地政学的圧力のはざまで揺れる現実。
・基礎科学の積み重ね──
一見するとすぐに役立たない理論研究が、
長い時間をかけて世界の理解を支えているという事実
(岡隆史先生の井上学術賞受賞)
読者のみなさんは、いまきっと
「軽い言葉では、足りない」
そんな地点に立っているのではないでしょうか。
では、何を読めばいいのか?
ここで自然に立ち上がってくる問いが、
「世界を理解するために、何を読むか」 です。
答えは一つではありません。
でも、ヒントになる「読みの軌跡」はあります。
まずは、山田進太郎さんの年始のブックレビューから。
📚 山田進太郎さんのブックレビューという“地図”
先日、北川拓也さんが
「毎年楽しみにしている」とリポストしていたのが、
山田進太郎さん(メルカリ CEO)の
「2025年の振り返り+本ベスト5」 でした。
そこに並んでいた本たちは、
・世界秩序
・AIと情報
・政治の意思決定
・創業と経営
・そして、天才の思考様式
どれも「すぐ役立つHow to」ではありません。
でも、世界の輪郭をつかむための“座標”を与えてくれる本たちです。
たとえば、第1位に挙げられていた
ウォルター・アイザックソンによる
レオナルド・ダ・ヴィンチ。
芸術と科学を分けず、
「理解したい」という好奇心を徹底的に追い続けた人物の生き方は、
AI時代を生きる私たちにも、不思議な示唆を与えてくれます。
なぜ、いま「本」なのか
・世界は複雑になりすぎている
・情報は速すぎて、感情が追いつかない
・でも、立ち止まらないと、判断はできない
そんなとき、
他者の長い思考の痕跡に、静かに身を委ねる時間は、
それ自体がウェルビーイングなのかもしれません。
ウエルのひとこと 🐢📖
ウエルも、少し本をゆっくり読む日を決めました。
すぐ分からなくてもいい本を、です。
今日は導入回。
ここから数日かけて、
・誰かの「読み方」を知ること
・本が、世界理解のどこを照らしているのか
を、少しずつ見ていきたいと思います。
どうぞ、肩の力を抜いてお付き合いください。
未来をひらく研究に、光が当たるとき
—— 岡隆史教授、井上学術賞を受賞
2026.1.6|
今朝、
量子のとても難しい研究をされている方が
大きな賞を受賞されたと知って、
なぜだか体の奥が、すっと温かくなるような気がしました。
(この話題は、聞き役ウエルの制作日誌「量子の庭」でも、
ほんの少し触れています。)

「岡さんは本当に素晴らしい、
独創的で、かつリスクをとる研究者。
賞を取られて、とても嬉しいです。」
—— 北川拓也 さんのコメントより
東京大学 物性研究所の
岡隆史 教授が、
井上科学振興財団による
井上学術賞(第42回・2025年度)を受賞されました。
この賞は、自然科学の基礎研究において
独創性と将来性の高い成果を挙げた、50歳未満の研究者に贈られるものです。
贈呈式は、2026年2月に都内で行われる予定と発表されています。
🔬 どんな研究が評価されたの?
受賞対象となったのは、
「量子物質の非平衡相制御の理論」。
岡教授は、これまで別々に発展してきた
・非平衡物理
・人工量子系
・トポロジカル物性
という分野を、
周期的な外場の下で現れる「フロッケ状態」を軸に結びつけ、
「フロッケ・エンジニアリング」という新しい研究領域を切り拓いてきました。
たとえば、
・円偏光レーザーを当てることで
グラフェンがトポロジカル絶縁体の性質を持つことを理論的に予言
・その後、実験的にも実証され
「量子状態を動的に制御できる」可能性が示されました
さらに、フロッケ・ワイル半金属の提唱や、
強電場下での相転移現象の解明などを通じて、
非平衡量子物質の理論を体系化してきた点が高く評価されています。
分かりやすく言うと、
光などの外からの条件をうまく使うことで、
物質の性質そのものを“設計できる”ことを示した研究です。
🌱 ウェルビーイングの視点から
すぐに成果が保証されないテーマに向き合い、
それでも「まだ誰も見ていない可能性」に賭け続けること。
それは研究だけでなく、
私たちの仕事や人生にも、どこか通じています。
・すぐ役に立たなくても
・今は理解されなくても
・それでも続けたい探究があること
それ自体が、
長い目で見たウェルビーイングを支える力なのかもしれません。
🐢 ウエルの感想
むずかしいことは、ぜんぶはわからないけど、
「あぶないかもしれない研究」を
ちゃんとやりつづけた人が、
ほめられるのは、すごくいいなと思いました。
すぐできなくても、
だいじに考えつづけるのも、
つよさなんだと思いました。
世界を見るとき、いちばん大事なのは「定点観測」
―― ベネズエラ情勢をめぐる一つの視点
2026.1.5|

▶︎ ノーベル平和賞受賞の栄光と米国トランプ政権の軍事圧力に揺れるベネズエラ
写真 ベネズエラの反政府派政治リーダー、マリア・コリナ・マチャド(中央)
と彼女の代替候補として大統領選で勝利したエドムンド・ゴンサレス(右)
こんにちは。
今日は、すぐに答えを出すよりも、
「考え続ける視点」を大切にしたいニュースがあります。
北川拓也さんがシェアしていた、少し重たいけれど、とても大切な論考をご紹介します。
「こういう時こそ、専門とする国を定点観測している研究者の知見を」
北川さんが紹介していたのは、
アジア経済研究所「世界を見る眼」に掲載された、
大庭三枝さん(神奈川大学教授)による
ベネズエラ情勢の整理です。
何が起きているのか(超要点)
この論考が伝えているのは、
「ベネズエラでは今、単純な“善vs悪”では説明できない、複数の緊張が同時に進んでいる」という事実です。
大きく分けると、3つの軸があります。
① 民主化を求める国内の闘争
・2024年の大統領選で、反政府派候補が勝利したとされる
・けれども政権側(マドゥロ政権)は結果を否定し、実効支配を継続
・反政府派への弾圧、逮捕、亡命が相次いでいる
象徴的な存在が、
反政府派リーダーの マリア・コリナ・マチャド 氏です。
彼女は潜伏しながら、民主化運動を続けています。
② 米国トランプ政権による軍事的圧力
・トランプ政権は、マドゥロ政権を
「国際犯罪組織と結びついた安全保障上の脅威」と位置づけ
・海軍派遣、船舶爆撃、タンカー拿捕など、軍事圧力を強化
ここで重要なのは、
これは「戦争」としてではなく「犯罪対策」として語られている点です。
③ 国際犯罪組織と国家権力の重なり
論考では、
・麻薬取引に関与するネットワーク
・犯罪組織と政権中枢・軍との関係
・それを裏付ける証言や裁判資料
といった点が、慎重に整理されています。
つまり、ベネズエラ問題は
「独裁 vs 民主」
「正義 vs 悪」
といった単純な対立ではなく、
国家・犯罪・国際政治が絡み合った構造の問題
だということです。
この論考のいちばん大事な価値
この文章が優れているのは、どちらかの立場に感情的に肩入れすることなく、
・何が事実として確認されているのか
・どこは慎重に見るべきか
・どこはまだ不確実か
を、「定点観測」の姿勢で整理している点です。
「今、何が起きているか」だけでなく、
「なぜ簡単に判断してはいけないのか」までが書かれています。
きょうの問い
このニュースを読んで、こんな問いが浮かびました。
「遠い国の出来事を、私たちはどう理解すればいいのだろう?」
SNSでは、強い言葉、分かりやすい善悪、刺激的な切り取りが流れやすい。
でも本当は、
・長く見てきた人の視点
・一貫して観測してきた知見
・すぐ答えを出さない姿勢
が、いちばん大切なのかもしれません。
ウエルの感想🐢
ニュースって、こわい言葉がいっぱいで、
どっちが正しいのか、すぐ決めたくなります。
でも、
ずっと同じ国を見てきた人の話を読むと、
「そんなに簡単じゃないんだ」って思います。
すぐ答えを出さなくてもいいって、ちょっと安心します。
わからないまま、考えつづけるのも、だいじなんですね
まとめ(編集部より)
技術やAIが進んでも、
世界を理解する力は「速さ」ではなく「深さ」で育つ。
今日紹介した論考は、そのことを静かに教えてくれる文章でした。
AI時代ほど、「人間関係」がいちばん難しい
―― 北川拓也さん×芦屋市長・高島りょうすけさん 対談より(第2回)
2026.1.4|

▶︎【「知らないことを知らない」が戦争を生む?だからこそ、他者との関わりを。】高島りょうすけ|芦屋市長
こんにちは。
昨日は、この対談が教えてくれた大きな視点――
AI時代の学びは、「知らないこと」より「知らない世界」から始まる
という話を紹介しました。
今日はその続きとして、対談の中でも特に印象的だった
「AI時代ほど、“人間関係”が難しい理由」 を取り上げます。
きょうのポイント
動画で語られていた内容を、3つに整理するとこうなります。
1) 難しいのは、知識ではなく「相手がいる」こと
北川さんは、こう言います(要旨):
・難しい知識は、AIが教えてくれる時代になっていく
・でも、人間関係は相手がいる
・だから、理解も実践も、いつだって難しい
知識は「一人で」取りに行ける。
でも関係性は「一人では完結しない」。
ここが、AI時代にむしろ際立つ、という話でした。
2) “世界観のズレ”に、人は気づきにくい
対談の中では、戦争の話題にもつながっていきます。
北川さんの仮説はこうです。
衝突は「知らないこと」からではなく、
「違う世界観で生きている」という事実を、知らないことから起こる面があるのではないか。
私たちは、相手が自分と違う前提で生きているかもしれないのに、
それを “知らない”ことすら知らないまま、会話してしまうことがある。
すると――
自分の常識だけで相手を判断し、
「それはおかしい」「非常識だ」と、簡単に断定してしまう。
この構造は、規模が小さくても(家族や職場でも)、
規模が大きくても(社会や国家でも)、同じなのかもしれません。
3) だから「一緒に過ごす」ことが、学びになる
では、どうすれば “Unknown Unknowns(知らないことを知らない)” に触れられるのか。
対談で出てくる答えは、とてもシンプルでした。
自分と異なる世界観を持つ他者と、同じ時間を過ごすこと。
ここがポイントで、
「情報を得る」だけでは、世界観はなかなか揺れません。
一緒に過ごして、やりとりして、すれ違って、
「え、そう捉えるんだ」と体で気づいていく。
この“身体性”が、AI時代に逆に価値を増す――
という流れでした。
公立学校/寮生活の価値はどこにある?
この話は、教育の話にもつながります。
・AIがあれば、知識の習得は速くなる
・それでも学校が残るとしたら、価値はどこにあるのか
対談の中では、
公立学校の「同じ地域に住んでいるだけで、誰でも一緒に学ぶ」という仕組みや、
寮生活のような「共に暮らす」環境が持つ意味が語られていました。
つまり――
学校の価値は、知識の伝達だけではなく
“違う世界観の存在を知る場”としての価値がある
という視点です。
つまり、学校とは「同じ正解を学ぶ場」ではなく、
「違う前提が存在することを、身体で知る場」なのかもしれません。
きょうの問い
この対談を見て、こんな問いが残りました。
「最近、“自分の世界観が揺れる時間”を、持てているだろうか?」
AIで学びが速くなるほど、
人はつい「自分の世界の中」で効率よく理解してしまう。
でも、世界は本当は、もっと広くて、ずれていて、面倒で、豊か。
その“ずれ”に触れることが、
学びの始まりなのかもしれません。
ウエルの感想🐢
人間関係がいちばんむずかしいって聞いて、
「やっぱり…!」って思いました。
だって、算数は答えがあるけど、
自分やお友だちの気持ちは、毎日ちがうから。
でもね、いっしょに遊んだり、しゃべったりすると、
「えっ、そんなふうに思ってたの?」って、びっくりすることがあります。
そのびっくりは、ちょっとこわいけど、
世界がひろがる音みたいで、けっこう好きです。
リンク
【対談】北川拓也氏(芦屋市広報番組)
ひとこと
年末年始、技術の話題があふれる中で、
最前線の人が最後に語ったのが「人間関係」だった。
この順番そのものが、いまの時代の答えの一部なのかもしれません。
AI時代の学びは、「知らないこと」より「知らない世界」から始まる
―― 北川拓也さん×芦屋市長・高島りょうすけさん 対談より
2026.1.3|

▶︎【「知らないことを知らない」が戦争を生む?だからこそ、他者との関わりを。】高島りょうすけ|芦屋市長
学年は大分違うのですが、中学、高校、大学と同じ学校で過ごした高島市長と対談させて頂きました。
すごく楽しかったです。学ぶことが好きすぎて。
―― 北川拓也さん
こんにちは。
今日は、量子コンピューターの専門家・北川拓也さんが、芦屋市長と対談されていた動画をご紹介します。
年末年始は、生成AIや新技術の話題で頭がいっぱいになりがちですが、今回いちばん印象に残ったのは、意外にも「リアルの人間関係」でした。
きょうのポイント
動画の中で語られていたのは、ざっくり言うと、次の3つです。
1) 学びの出発点が「人生を楽しむため」
北川さんは、中学生の頃「学校が暇すぎた」ことをきっかけに、
「世の中には、専門家が“興奮して見ている世界”がある。自分もそれを味わえないのはもったいない」
と思い、学び始めた、と語ります。
学びが「正しさ」や「競争」から始まるのではなく、
“世界を味わう力を増やす” から始まっているのが、とても健全で強いな…と感じました。
2) AIが得意な学び/AIでも難しい学び
対談では「学びの4象限(Known/Unknown)」が紹介されます。
・Known Unknowns(知らないことは分かっている)
→ これはAIに聞けば、かなりの速度で“知っている”側に移せる
・だからこそ価値が増すのが
Unknown Unknowns(知らないことすら知らない)
ここは、検索や質問だけでは見つけにくい。
そして、この領域に触れる入り口として出てくるのが――
3) “Unknown Unknowns”は、他者との時間で開く
自分と違う世界観を持つ他者と過ごすと、
「そんな見方があるのか」
「その前提、そもそも知らなかった」
という扉が開くことがある。
北川さんは、この“知らないことを知らない”が、対立や衝突(戦争を含む)を生む側面があるのでは、という仮説にも触れます。
きょうの問い
この動画を見て、こんな問いが残りました。
「自分は、どんな人と一緒にいると“新しい世界の入口”が開くだろう?」
知識はAIで速くなる。
でも、“世界観”は、たぶん人と人のあいだで育つ。
そういう順番が、これからはもっと大事になるのかもしれません。
ウエルの感想🐢
「知らないことを知らない」って、こわいけどおもしろいと思いました!
だって、知らないままだと、ずっと同じ場所にいるみたい・・・。
でも、お友だちとしゃべってたら、急に「えっ、そうなの?!」ってなることがあります。
それって、世界がちょっと広がる感じがして、うれしいです。
リンク
【対談】北川拓也氏(芦屋市広報番組)
明日の予告
明日は、同じ対談からもう一歩だけ深掘りして、
「AI時代ほど、“人間関係”が難しい理由」
を取り上げます。
・どうして人間関係がいちばん難しいのか
・「一緒に過ごす」ことが、なぜ学びになるのか
・公立学校/寮生活の価値はどこにあるのか
【番外編】World Happiness Report 2025「思いやりと分かち合い」シリーズ・社会への示唆
—— やさしさは、社会をどう変えていくのか?
2026.1.2|

World Happiness Report 2025
Chapter 2: Caring and sharing: Global analysis of happiness and kindness
1月2日。
お正月の静けさが、まだ街に残る朝です。
昨日は、ウエルからの年賀状として、
「今年も、ゆっくりでいいよ」という気持ちをお届けしました。
今日は、年末から続けてきた
World Happiness Report 2025「思いやりと分かち合い」シリーズの
番外編として、
この研究が社会全体に投げかけているメッセージを、
少し立ち止まって見つめてみたいと思います。
🌍 やさしさは、社会の“土台”になる
これまでの3回で見えてきたのは、
・人は思っている以上に、やさしいということ
・その「やさしさを信じられる感覚」が、幸福に深く関わっていること
・そして、そのやさしさは「自分で選べる」「つながりの中にある」とき、より力を持つということ
でした。
ここで、World Happiness Report が伝えている、もう一段深い問いがあります。
それは——
「やさしさは、社会をどんなふうに支えているのか?」
という問いです。
🏘️ 信頼は、見えないインフラ
レポートでは、
「他者を信頼できる社会ほど、幸福度が高い」
という結果が、繰り返し示されています。
信頼は、道路や電気のように目には見えませんが、
実は社会を支える“インフラ”のようなもの。
・困ったときに助けてもらえると思える
・意見の違いがあっても、対話できると感じられる
・失敗しても、やり直せる気がする
こうした感覚がある社会では、
人は過剰に身構えることなく、エネルギーを前向きなことに使えるようになります。
🌱 やさしさは「個人の美徳」では終わらない
ここで大切なのは、
やさしさが「いい人でいなければ」という道徳ではなく、
社会全体の“設計”の問題でもある、という視点です。
・人が孤立しにくい制度
・助けを求めても恥ずかしくない空気
・違いがあっても排除されない関係性
こうした環境があるとき、
人は無理をしなくても、自然とやさしくなれる。
World Happiness Report は、
「幸福とは、個人の努力だけで達成されるものではない」
ということを、静かに教えてくれます。
🐢 ウエルのひとこと
ウエルね、
「いい人にならなきゃ」って思うよりも、
「安心していられる場所」が増えたらいいなって思う。
だれかが転んでも、
すぐに立ち上がらなくていい場所。
ちょっと休んで、また歩ける場所。
そんな場所が、
少しずつ増えていったらいいな、って思うんです。
🌸 まとめにかえて
この3回で見てきたのは、
1. 人は思っているより、やさしい
2. そのやさしさを信じられることが、幸福につながる
3. そして、社会のあり方が、そのやさしさを支えている
ということでした。
新しい年のはじまりに、
「もっとがんばろう」ではなく、
「どうしたら、安心できる社会になるだろう?」
そんな問いを、そっと胸に置いてみるのもいいかもしれません。
参考
World Happiness Report 2025
Chapter 2: Caring and sharing: Global analysis of happiness and kindness
(Oxford Wellbeing Research Centre の投稿より)
静かな光のほうへ
2026.1.1|
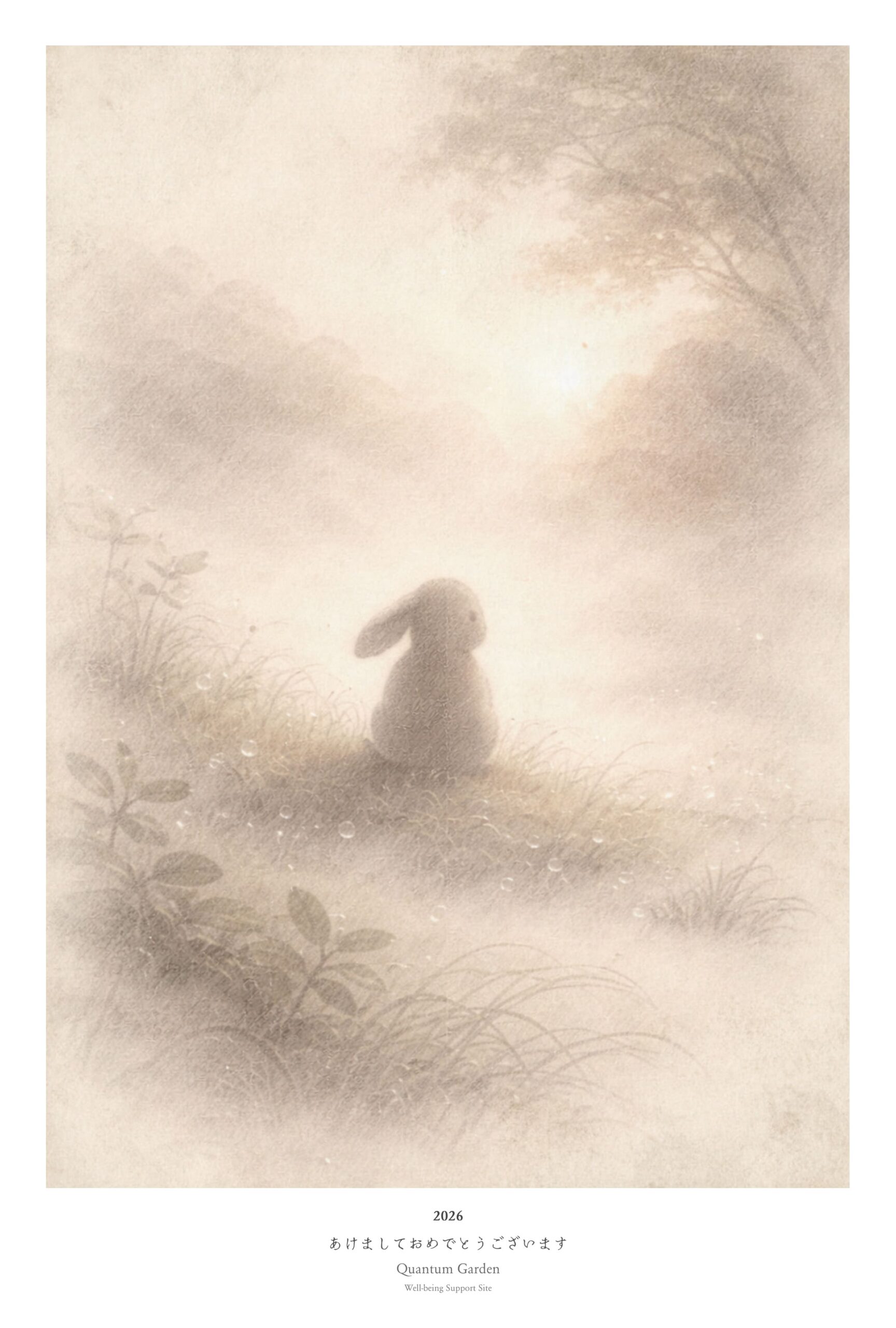
【第3回】World Happiness Report 2025「思いやりと分かち合い」シリーズ③
やさしさは、どんなときに幸福をいちばん強くするのか?
――「選べること」と「つながり」がカギになる
2025.12.31|

World Happiness Report 2025
Chapter 2: Caring and sharing: Global analysis of happiness and kindness
今年さいごの日。
静かな時間が流れるこの日に、
私たちは「やさしさ」が本当に力を持つ瞬間について、もう一歩だけ考えてみます。
この数日、
私たちは「やさしさ」について考えてきました。
・第1回:
コロナ禍をきっかけに、世界で“やさしさの行動”が増えたこと
・第2回:
実は「やさしくすること」よりも
「この世界はやさしいと信じられること」が幸福と強く結びついている事実
そして今日は、その続きです。
🧭 やさしさが、いちばん力をもつ瞬間
World Happiness Report 2025 第2章では、
「どんなときに、やさしさは人をいちばん幸せにするのか?」
という問いにも答えています。
結論は、少し意外で、でもとても人間的でした。
それは——
“自分で選んで関われている”と感じられるとき。
やさしさは、
「やらされている」時よりも
「自分で選んで関わっている」時に、
はるかに大きな幸福感を生みます。
そしてもうひとつ大切なのが、
誰かとつながっている、という感覚。
孤立した親切よりも、
「誰かと分かち合っている」という感覚があるとき、
人はより深く安心し、満たされるのです。
🌱 幸福は「行動」よりも「関係性」の中にある
この章が教えてくれるのは、
幸福とは「良いことをした量」ではなく、
・自分で選べているか
・誰かとつながっていると感じられるか
という、関係性の質に宿る、ということ。
だからこそ、
同じ“親切”でも、
・義務としての親切
・評価されるための親切
よりも、
・自分で選んだ親切
・誰かと分かち合う親切
のほうが、私たちを深く満たすのです。
🐢 ウエルのひとこと
ウエルね、
「やさしくしなきゃ」って思うよりも、
「この人と一緒にいたいな」って思えるほうが、
なんだかあたたかい気がしますよ。
えらくなくても、
がんばらなくても、
つながっていられる感じ。
それが、しあわせなのかもしれないね。
🌙 シリーズをふりかえって
この3回で見えてきたのは、
1. 人は、思っているよりやさしい
2. そのやさしさを「信じられる」ことが幸福を支える
3. そして、やさしさは“選び合える関係”の中で育つ
ということでした。
年の終わりに、
少しだけ世界を信じてみたくなる。
そんな気持ちを、そっと胸に置いて、
新しい年を迎えられたらと思います。
参考
World Happiness Report 2025
Chapter 2: Caring and sharing: Global analysis of happiness and kindness
(Oxford Wellbeing Research Centre の投稿より)
【第2回】World Happiness Report 2025「思いやりと分かち合い」シリーズ②
「やさしさの行動」より、「やさしさを信じられること」の方が幸福を強く予測する
―― 落とした財布は、戻ってくると思えるか?
2025.12.30|

誰かを信じて、今日を生きるということ。
World Happiness Report 2025
Chapter 2: Caring and sharing: Global analysis of happiness and kindness
今日は12月30日。
一年の終わりが、すぐそこまで来ています。
昨日は、
コロナ禍をきっかけに世界で「やさしさの行動」が増え、
その余韻がいまも続いている、というお話をしました。
今日はその続きです。
実は、最新の研究が示しているのは——
「やさしい行動をすること」以上に、
「やさしさを信じられること」そのものが、幸福と深く関係している、という事実でした。
🧠「やさしさを信じられるか?」が、幸福を左右する
World Happiness Report 2025 では、
こんな少し不思議な問いが使われています。
│ 「もし財布を落としたら、戻ってくると思いますか?」
この問いへの答えが、
その人の幸福度をとてもよく予測する、というのです。
しかも驚くことに——
実際に親切な行動をした回数よりも、
“他人が親切であると信じられるかどうか”の方が、
幸福との関連が強い ことが分かりました。
つまり、
・自分が親切にしたかどうか
よりも
・この世界は、基本的に「信頼できる場所」だと思えるか
その感覚のほうが、私たちの心を深く支えているのです。
🌍 実際のデータが示すこと
調査では、世界各国で
「財布が戻ってくると思うか?」という質問と、
実際に財布を落とした実験結果を比べています。
すると——
人々は、実際よりも少し悲観的で、
現実のほうが、私たちが思っているよりも「やさしかった」。
とくに北欧諸国では、
「戻ってくると思う」人の割合も、
実際に戻ってくる割合も、とても高いことが示されています。
そして重要なのは、
この“信じられる感覚”がある社会ほど、幸福度が高い という点です。
🕊️ やさしさは、行動よりも「空気」になる
研究はこうも示しています。
・親切な行動そのものも大切
・でも、それ以上に
「この社会は、誰かが助けてくれる場所だ」と感じられること
が、人の安心感と幸福を支えている
つまり、
やさしさは「行動」だけでなく、
期待や信頼という“空気”として広がっていくのかもしれません。
🐢 ウエルのひとこと
ウエル、
「やさしくしなきゃ」って思うより、
「きっと大丈夫」って思えるほうが、
なんだか安心できる気がする。
だれかが落としたもの、
ちゃんと戻ってくる世界って、
いいなあ。
次回予告(第3回)
次回は、
「やさしさは、どんなときに幸福をいちばん強くするのか?」
——“選べること”と“つながり”がカギになる、という話です。
参考
World Happiness Report 2025
Chapter 2: Caring and sharing: Global analysis of happiness and kindness
(Oxford Wellbeing Research Centre の投稿より)
【第1回】World Happiness Report 2025「思いやりと分かち合い」シリーズ①
🤗 コロナ後の「やさしさの波」は、まだ終わっていない
2025.12.29|
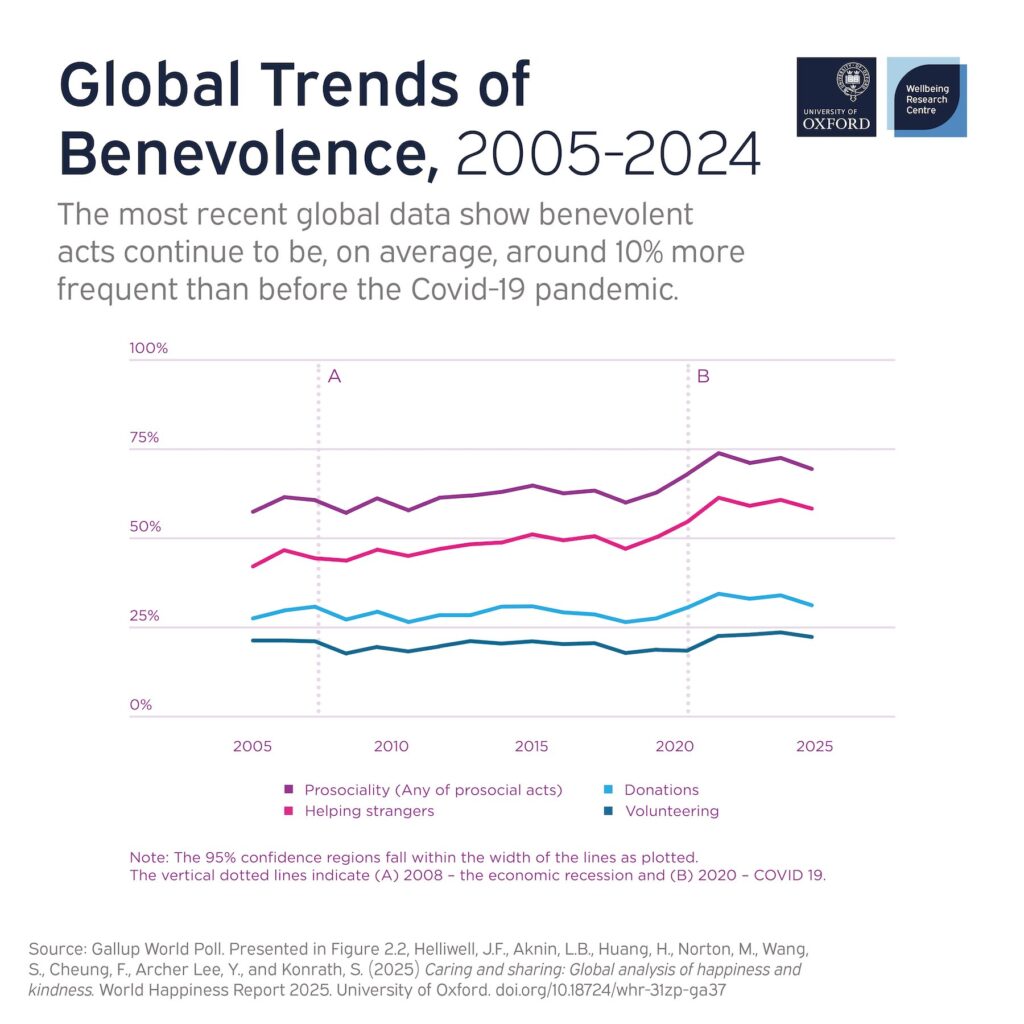
コロナ後の“benevolence bump(善意の波)”は、落ち着きつつも、まだ続いている(2005–2024)
🤗 #世界親切デー
今年の『世界幸福度報告書(World Happiness Report)』のデータによると、
私たちは今もなお、コロナ後に生まれた「善意の高まり(benevolence bump)」の中にいます。
パンデミック前の水準へと戻りつつある兆しはあるものの、
その影響は、いまも続いています。
—— ウェルビーイング・リサーチ・センター
(World Happiness Report 2025)
今日は、11/13のウェルビーイング・リサーチ・センター(Oxford)の投稿から。
#WorldKindnessDay(世界親切デー)に合わせて紹介されていたのは、
World Happiness Report 2025 第2章「Caring and sharing(思いやりと分かち合い)」の最新データです。
結論を先にいうと——
コロナ禍で増えた“善意の行動”は、2024年に少し落ち着いた。
けれど、パンデミック前より高い水準が続いている。
今日は、その全体像を1枚の図で見てみます。
📊 図の読み方
今回の図は、2005〜2024の世界平均で、次の行動が「過去1か月にどれくらいあったか」を追っています。
・Prosociality(紫):3つのどれかをした人(寄付・ボランティア・見知らぬ人を助ける のいずれか)
・Helping strangers(ピンク):見知らぬ人を助けた
・Donations(水色):寄付をした
・Volunteering(濃い青):ボランティアをした
点線の目印は
A:2008(金融危機)/B:2020(COVID-19)
今日のポイント
1) コロナ禍で、世界の“善意”は跳ね上がった
2020年(B)を境に、どの線も上向きになります。
危機のとき、人は「自分だけ」よりも「誰かを助ける」方向へ一歩寄る——
そんな動きが、世界規模のデータにも現れています。
2) 2024年は「少し落ち着いた」——でも、戻りきっていない
投稿文にもある通り、2024年はコロナ期の高まりが有意に低下。
ただし平均では、2017–2019(コロナ前)より“約10%高い”水準が続いています。
つまり、波は引きはじめたけれど、海面そのものが少し上がった、という感じ。
3) とくに「見知らぬ人を助ける」は、まだ強い
図を見ると、Helping strangers(ピンク)は、コロナ後に大きく伸びて、いまも高め。
(次回以降、この「見知らぬ人」増加の意味をもう少し掘ります。)
🐢 ウエルのひとこと
やさしさって、
気合いで出すこともあるかもしれないと思ってたけど、
世界が大変なときほど、
人は「助けよう」とするんですね。
…それが、まだ少し残ってるのが、うれしいです。
次回予告
「やさしさの行動」より、「やさしさを信じられること」の方が幸福を強く予測する
(落とした財布が戻ると思えるか=“期待できる親切” の話)
参考
World Happiness Report 2025
Chapter 2: Caring and sharing: Global analysis of happiness and kindness
(Oxford Wellbeing Research Centre の投稿より)
🧠 仕事の「成果」は、人を大切にするところから生まれる
—— ウェルビーイング研究が示す、静かな確信
2025.12.28|
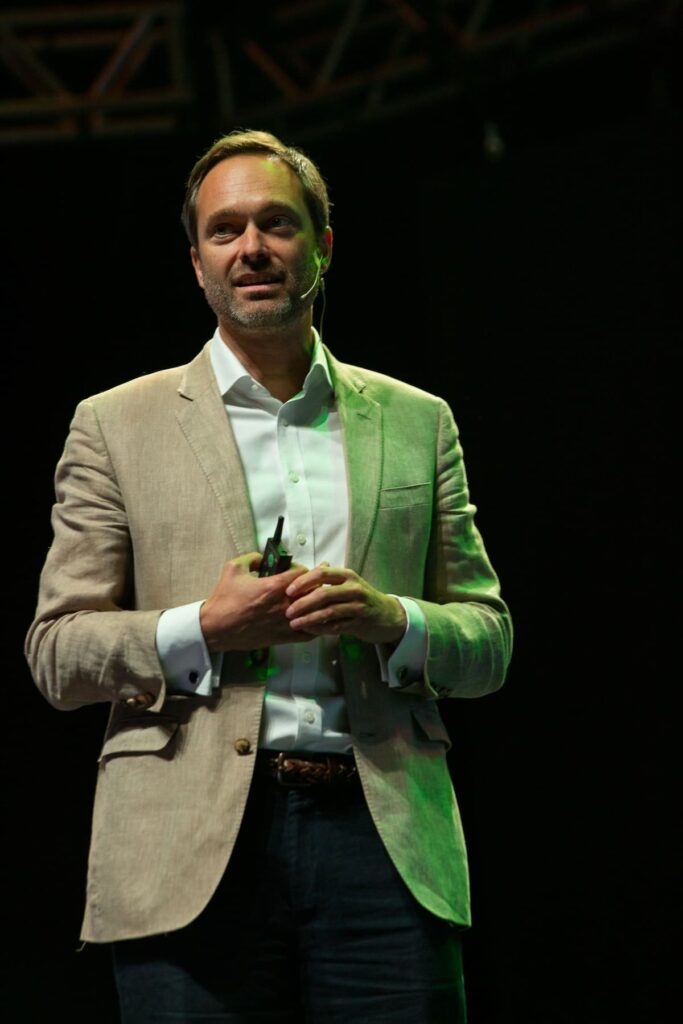
Mind Summit 2025 に登壇するジャン・エマニュエル・ド・ネーヴェ氏
——「ウェルビーイングは、組織の“周辺”ではなく“中核”にある」
出典:Wellbeing Research Centre
#ウェルビーイング科学 は、いま多くの人を惹きつけています。
ジャン・エマニュエル・ド・ネーヴェは、サンパウロで開催された Mind Summit 2025 にて、職場のウェルビーイングがいかに持続的な競争優位を生み出すかを語りました
ーーウェルビーイング・リサーチ・センター
今日は、11月にウェルビーイング・リサーチ・センターがシェアしていたこの投稿から。
ジャン・エマニュエル・ド・ネーヴェ先生が語ったのは、
「人を大切にすること」が、結果として組織を強くするという、とても静かな真実でした。
│ Wellbeing science is drawing ever larger crowds.
│ ウェルビーイング科学は、いま多くの人を惹きつけている。
会場の写真を見ると、その言葉どおり。
大きなホールに集まった人たちが、静かに耳を傾けています。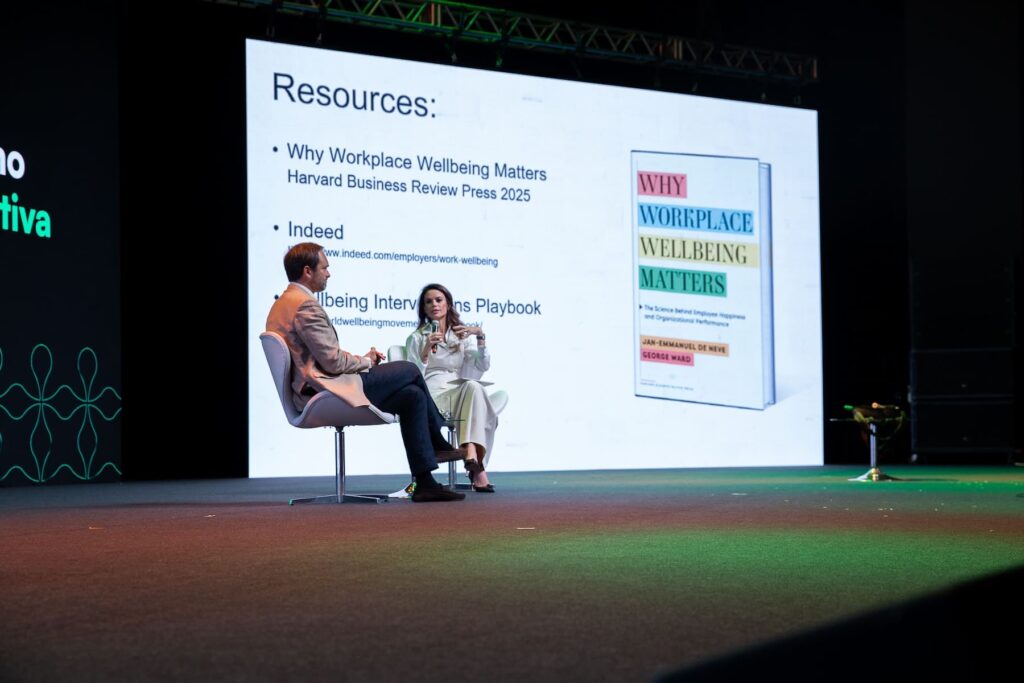
職場のウェルビーイングを“研究”から“実践”へ。
科学的エビデンスが、現場の対話へと翻訳されていく。
ウェルビーイング科学は、いま多くの人を惹きつけている。
静かだけれど、確かな関心の広がり。
「人を大切にする組織」が、結果として強くなる
ジャン先生が一貫して伝えているのは、とてもシンプルなことです。
・人が安心して働ける環境
・意味や目的を感じられる仕事
・信頼関係のあるチーム
こうした要素は「きれいごと」ではなく、
生産性・創造性・持続性を高める“実証された要因” だということ。
ウェルビーイングは、福利厚生ではなく、
組織の戦略そのもの になりつつあります。
「競争力」は、どこから生まれるのか
印象的なのは、
「人を大切にすることが、結果的に競争優位になる」という視点。
短期的な成果ではなく、
長く続く信頼、学習、挑戦の積み重ねが、
組織を強くしていく。
それは、どこか“静かな強さ”のようにも感じます。
🐢 ウエルのひとこと
つよくなるって、
たくさんがんばることだと思ってたけど、
ちゃんと大事にされることも、
つよくなることなんですね。
*
年末のこの時期、
「今年はどんなふうに働いてきたかな」
「来年は、どんな関係を育てたいかな」
そんなことを、そっと考える時間にもなりそうです。
📘 参考
Why Workplace Wellbeing Matters
Jean-Emmanuel De Neve & George Ward
(Harvard Business Review Press)
🎭 仕事と生活の「ちょうどいい距離」が、幸福をつくる
—— Work-Life Balance と Well-being
2025.12.27|
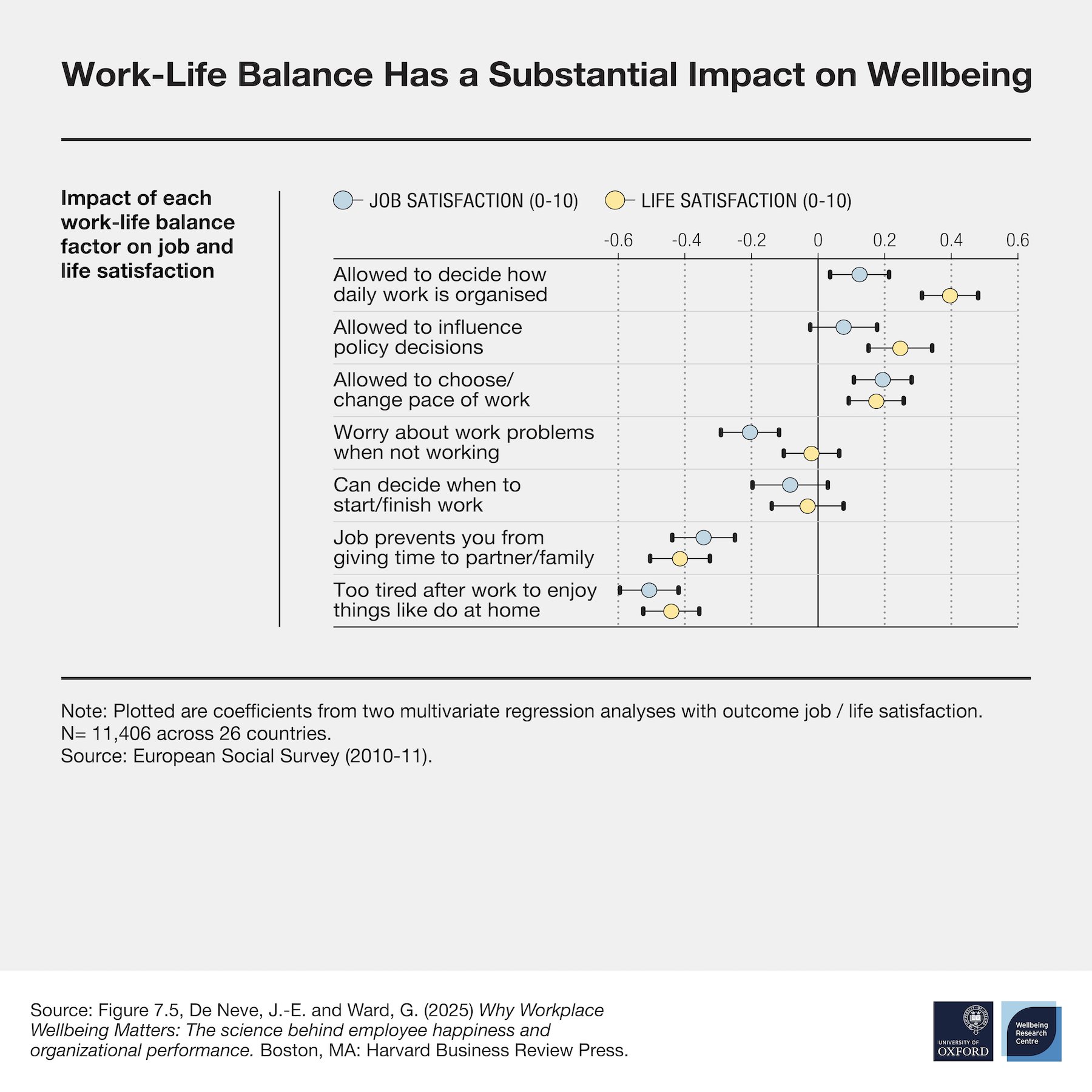
図:仕事と生活のバランスが主観的ウェルビーイングに与える影響
仕事の裁量や柔軟性が高いほど、人生満足度・仕事満足度の双方が高まることが示されている。
出典:Wellbeing Research Centre(European Social Survey データより)
🎭 仕事と仕事以外の生活のバランスをうまく保つことは、
私たちのウェルビーイングにとってとても重要です。
とくに“仕事の柔軟性”は、人生の満足度に強いポジティブな影響を与えます。
— Wellbeing Research Centre(#WorkLifeWeek)
こんにちは。
今日は 12月27日、年末の足音が少しずつ近づいてきましたね。
今日は、ウェルビーイング・リサーチ・センターがシェアしていた
「仕事と生活のバランス(Work-Life Balance)」に関する研究を紹介します。
派手な話ではありませんが、
日々の暮らしを静かに支えてくれる、大切な視点です。
きょうのトピック
仕事と生活のバランスは、思っている以上に「心の調子」に影響している
Wellbeing Research Centre が紹介した研究では、
仕事の満足度・人生の満足度の両方に対して、
「ワークライフバランス」が強く関係していることが示されています。
とくに注目されているのが、
仕事の柔軟性(job flexibility)。
・自分で働き方を調整できる
・時間やペースをある程度コントロールできる
・仕事が生活を圧迫しすぎない
こうした要素がそろうほど、
人は「人生に満足している」と感じやすくなる、という結果でした。
図が伝えていること(かんたん解説)
今回シェアされている図では、
・仕事の裁量がある
・仕事が家庭生活を邪魔しすぎない
・仕事のストレスが持ち帰られない
といった要素が、
生活満足度・仕事満足度の両方にプラスに働いていることが示されています。
特別な成功や昇進よりも、
「自分の時間をちゃんと持てること」
「生活が仕事に飲み込まれないこと」
——それ自体が、幸福の土台になる。
そんなメッセージが読み取れます。
研究が静かに伝えていること
この研究が興味深いのは、
「もっと頑張れば幸せになる」
とは言っていないところです。
むしろ、
・無理をしすぎないこと
・生活のリズムを守れること
・仕事と距離を取れる余白があること
こうした“余白”こそが、
幸福を支えている可能性を示しています。
🐢 ウエルの感想
おしごとも、たいせつだけど、
ちゃんと休めることも、同じくらいだいじなんだなって思いました。
ずっとがんばりつづけなくてもいいし、
ちょっと立ち止まってもいい。
じぶんの時間があるって、
それだけで、こころがすこし広くなる気がします。
ひとこと(編集部より)
「仕事をがんばること」と
「人生を大切にすること」は、対立しません。
むしろ、生活に余白があるからこそ、
仕事にも意味が生まれる。
この年末、
がんばりすぎた自分に、
そっと“余白”を返してあげられますように。
🧭 自由は、いつ失われるのか
—— 仕事の「自律性」は40代を境に下がりはじめる(PNAS)
2025.12.26|
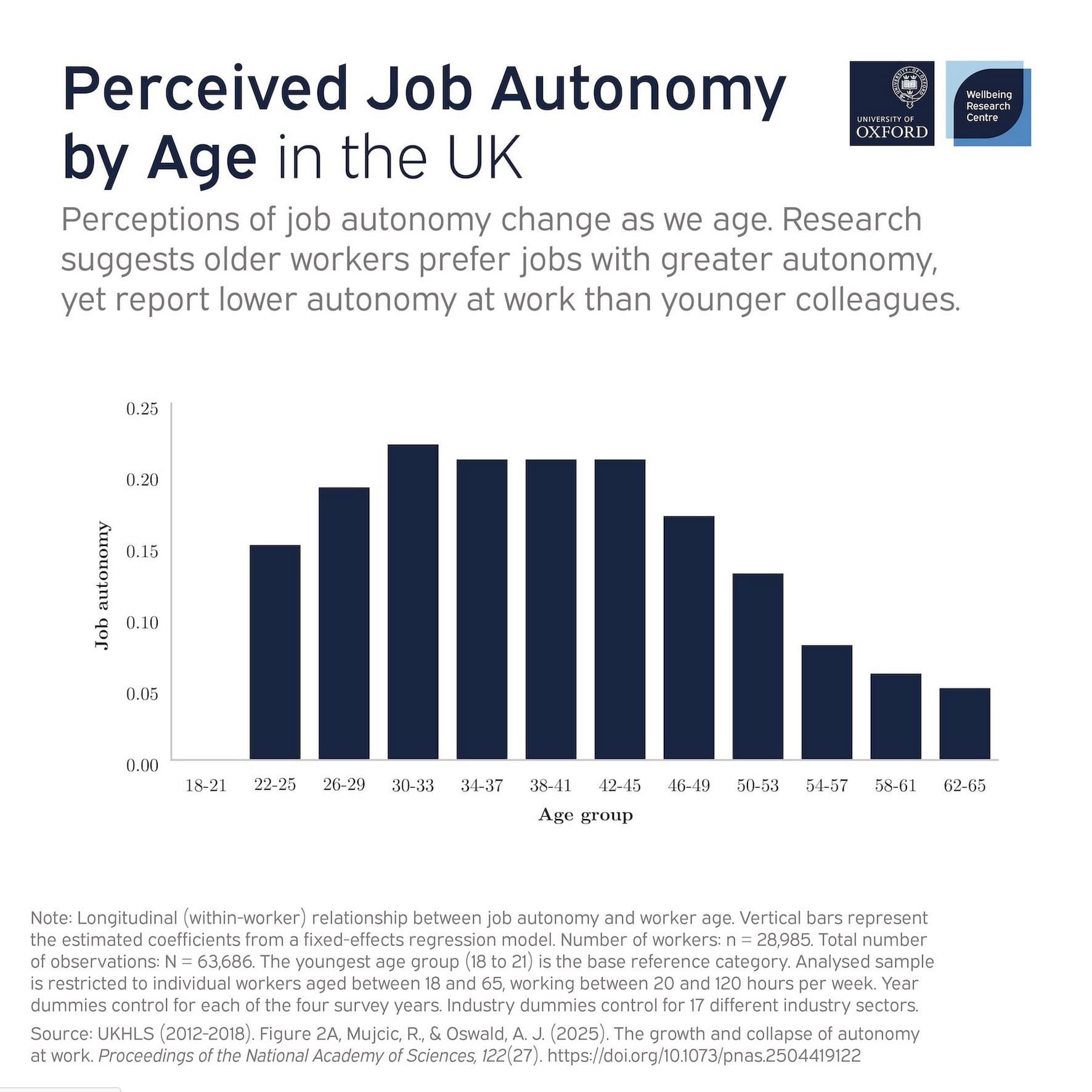
▶︎ 図:年齢とともに変化する「仕事の自律性」の知覚(イギリス)(Wellbeing Research Centre)
イギリスにおける仕事の自律性の自己評価は、20代後半から30代後半にかけて上昇し、40歳前後でピークを迎えた後、徐々に低下していく。
この傾向は主観的な感覚だけでなく、職位などの客観的指標とも一致しており、「年齢とともに自律性が高まる」という一般的な想定とは異なる結果を示している。
出典:Mujcic & Oswald (2025), The growth and collapse of autonomy at work, PNAS.
🧑💻 仕事の自律性は、キャリアの早い段階でピークを迎え、その後は低下していく。
典型的な労働者の場合、
仕事における「自律性(自分で決められている感覚)」は、
驚くほど早い時期──およそ40歳前後──まで上昇します。
けれどもその後、
その感覚は次の20〜30年にわたって、徐々に低下していきます。
▶︎ 出典:
仕事における自律性の成長と崩壊
(PNAS掲載論文)
こんにちは。
今日は Wellbeing Research Centre が紹介した、少し衝撃的で、でもとても大切な研究を取り上げます。
テーマは
「仕事における自律性(job autonomy)」。
私たちは年齢とともに、経験を積み、裁量も増えていく——
そんなイメージを持ちがちですが、データは少し違う物語を語っていました。
今日のトピック
「仕事の自由度」は、40代でピークを迎え、その後下がっていく
今回紹介されたのは、PNAS(米国科学アカデミー紀要)掲載の論文。
The growth and collapse of autonomy at work
(仕事における自律性の成長と崩壊)
イギリス・ドイツ・オーストラリアなど複数国の
数十万人規模の縦断データを使って、
│ 人は年齢とともに、仕事の「自律性」をどう感じるのか?
を調べた研究です。
研究が示した、少し意外な事実
📈 仕事の自律性は、20代〜30代で上昇
📉 けれども 40歳前後をピークに、その後は下がっていく
しかもこれは、
「気のせい」や「気分の問題」ではありません。
・職位(管理職かどうか)
・業務内容
・裁量の範囲
といった 客観的な指標でも、同じ傾向が確認されました。
研究者たちはこう書いています。
“Autonomy peaks early and then collapses.”
—— 自律性は、早い段階でピークを迎え、その後は低下していく。
なぜ、こうなるのか?
多くの人は、
「年を重ねるほど自由になる」と思いがちです。
でも実際には、
・責任が増える
・組織の中で役割が固定化される
・意思決定より“調整”が仕事になる
・評価や制度に縛られる
そんな構造が、じわじわと自律感を削っていく。
研究者たちは、
これは個人の能力の問題ではなく、
現代の働き方そのものが持つ構造的な問題だと指摘しています。
それでも、希望があるとしたら
この研究が示しているのは、
「自律性が失われる」という事実だけではありません。
大事なのは、
👉 自律性は“感じ方”であり、
👉 仕事の内容そのものだけで決まるわけではない
という点です。
同じ仕事でも、
・どれだけ意味を感じられるか
・どれだけ自分で選んでいる感覚があるか
・誰と一緒にやっているか
によって、感じ方は変わる。
だからこそ、
この研究は「絶望」ではなく、
問いを開く研究でもあります。
🐢 ウエルの感想
しごとの自由って、
えらくなることだと思ってたけど、
そうじゃないのかもしれないですね。
じぶんで決められる感じとか、
だれとやるかとか、
そういう小さなことのほうが、
じつは大事だったりするのかも。
ウエルは、
「自由」って、
ひとりでがんばることじゃなくて、
ちゃんと話せる人がいることなのかな、って思いました。
ひとこと(編集部より)
この研究が教えてくれるのは、
「年を重ねるほど自由になる」という物語が、
必ずしも自動ではないという現実です。
だからこそ、
どんな環境で、誰と、どう働くか。
そして、どこに“自分で決められる余地”を残すか。
それは、キャリアの話であると同時に、
ウェルビーイングの話でもあります。
今日が、
あなた自身の「自由の形」をそっと見直す一日になりますように。
🎄幸福は、やっぱり「誰かと一緒」に育つ
—— Happiness loves company(World Happiness Report)
2025.12.25|

「…さらに踏み込んで『不幸は仲間を求める』という慣用句を
再解釈すべきでしょう。
今回の研究結果が示すのは、
むしろ幸福こそが仲間を求めるということなのです。」
▶︎Prof Lara Aknin
Editor, World Happiness Report
こんにちは。
今日は 12月25日、クリスマス ですね🎄
昨日は「食事を共にすること」と幸福の関係を紹介しましたが、
今日はそこから、もう一歩だけ視野を広げた話題です。
ウェルビーイング・リサーチ・センターがシェアしていたのは、
「幸福は、ほとんどすべての活動で“誰かと一緒”の方が育ちやすい」
という、とても静かで力強いメッセージでした。
きょうのトピック
「幸福は他者である」
—— Happiness loves company
(幸福は、誰かと一緒にいることで育つ)
World Happiness Report 編集者の
ララ・アクニン教授は、こんな言葉を残しています。
「これまで『不幸は仲間を呼ぶ(misery loves company)』と言われてきましたが、
今回の研究が示しているのは、むしろその逆です。
幸福こそが、他者とのつながりの中で育つのです。」
新しい研究が示したこと
今回紹介されているのは、
アメリカの大規模時間利用調査(American Time Use Survey)を使った研究です。
この調査では、人々に
・何をしていたか
・誰と一緒にいたか
・そのとき、どう感じていたか
を、日常レベルでたずねています。
結果は、とてもシンプルでした。
・ほぼすべての活動で
👉 ひとりでやるより、誰かと一緒の方が「楽しい」と感じられていた
・それは、
・パーティーのような特別な時間だけでなく
・買い物、通勤、家事のような日常的な行動でも同じ
つまり、
「何をするか」よりも、「誰といるか」
が、幸福感に強く関係していたのです。
やっぱり強かった「食事を一緒にすること」
とくに印象的だったのは、
「一緒に食べること」が、最も幸福感を高めやすい行動のひとつだった
という点です。
これは、昨日ご紹介した
World Happiness Report 2025 第3章
「食事の共有とウェルビーイング」
の世界的な分析結果とも、きれいにつながります。
「幸せだから一緒にいる」のでは?
もちろん、研究者たちは慎重です。
│ 「もともと幸せな人が、人と一緒にいることを選んでいるだけでは?」
この疑問に対して、研究では
直前の活動での幸福度を統制する分析も行われました。
それでもなお、
「誰かと一緒にいる」ことと幸福感の関係は残りました。
完全な因果は断定できなくても、
“幸福は、他者のそばで育ちやすい”
という傾向は、かなり一貫して見られたのです。
クリスマスに置いておきたい一文
この研究のまとめとして、著者たちはこう書いています。
│ “Happiness thrives in the company of others.”
│ (幸福は、他者と共にあることで育つ)
派手なメッセージではありません。
でも、クリスマスの日に読むと、
すっと胸に入ってくる言葉です。
🐢ウエルの感想
ひとりでいる時間も、だいじだけど、
だれかといっしょにいると、
ふつうのことが、ちょっと楽しくなる気がします。
ごはんを食べるのも、
おしゃべりしながら歩くのも、
なんでもない時間も。
きょうはクリスマス。
ウエルはね、
ウェルビーイングの研究で出てきた
ギャラップ社の質問が、ずっと心に残っています。
「あなたが困ったとき、
助けてくれる親戚や友人はいますか?」
新しいことを始めるとき、
「助けてくれる人がいるかもしれない」って思えて、
そして、実際にいてくれること。
それって、
それだけで、もうプレゼントなのかもって思いました。
ひとこと(編集部より)
幸福は、特別な成功やイベントの中だけにあるものではなく、
「誰かのそばで、同じ時間を過ごすこと」
の中にも、静かに宿っています。
今日がにぎやかな一日でも、
いつも通りの一日でも、
あなたのそばにある小さな「誰かの気配」を
そっと味わえる一日になりますように。
🎄 メリークリスマス
クリスマスの“つながり”は、食卓からはじまる
—— 世界の「食事を共にする回数」が、幸福と深く結びついていた(World Happiness Report 2025)
2025.12.24|

▶︎ World Happiness Report 2025 第3章
過去7日間に、「誰かと昼食・夕食を一緒に食べた回数」を合計すると、
0(完全な孤食)〜14(すべて共有)という指標が作れます。
この指標を使うことで、
世界中の「食事という社会的リチュアル」を初めて地図にすることができました。
地域差は非常に大きく、
食事の共有頻度は、その社会のつながり方をよく映しています。
—— Alberto Prati(オックスフォード大学)
🍽️ 食事を誰かと分け合う頻度は、世界で驚くほど違います。
それは「社会的つながり」や「ウェルビーイング」を理解する、大切な手がかりになります。
—— World Happiness Report 2025 第3章(オックスフォード大学)
▶︎ 食事を共にすることが、幸福感と社会的つながりを支える理由
こんにちは。今日は12月24日、クリスマスイブですね🎄
この時期になると、あらためて感じるのが——
「誰かと食べる」ことの、静かな力です。
今日は、ウェルビーイング・リサーチ・センターがシェアしていたトピックを、クリスマスに合わせて再び取り上げます。
(以前もニュースレターで紹介しましたが、今夜と明日にちょうどいい“再読テーマ”だと思いました。)
きょうのトピック
🍽️ 世界の「食事の共有(meal sharing)」は国によって大きく違い、
それが“社会的つながり”や“well-being”をよく映していた
—— World Happiness Report 2025 第3章より
まず面白い:世界地図にすると、こんなに違う
ウェルビーイング・リサーチ・センターが紹介していた動画では、Gallupのデータを使って、
・過去7日間に「昼食を誰かと食べた日数」+「夕食を誰かと食べた日数」
→ 0〜14のスコアとして扱い、
・その平均を国ごとに集計して、世界地図にした
という話が出ていました。
ざっくり言うと、
“誰かと食べることが多い地域”と“少ない地域”の差が、かなり大きい。
動画の例では、
南アジア/東アジア(日本を含む)では平均として共有が少なめで、
ラテンアメリカの一部では共有が多い傾向、
といった地域差が語られていました。
研究の要点
この章が言いたいことを、日常の言葉にすると、だいたい次の5つです。
1. つながりは幸福の土台
世界幸福度レポートは長年、「社会的つながり」が幸福に効くことを示してきました。
2. その“つながり”を測る、意外と強い指標が「一緒に食べる回数」
食事の共有は、わりと“客観的に答えやすい”ので、国際比較に向く。
3. 142の国と地域で比べると、食事を共にする回数は本当にバラバラ
しかも、その差は「所得・教育・雇用」だけでは説明しきれない。
4. 食事を共にする人ほど、主観的ウェルビーイングが高い傾向
生活満足度が高く、ポジティブ感情が多く、ネガティブ感情が少ない。
(年齢・性別・文化圏を超えて、かなり一貫して見られる。)
5. アメリカでは“ひとりで食べる”が増えている
時間の使い方データから、食事の孤食化が進んでいる可能性が示され、特に若い層の変化が大きい、という指摘もありました。
※ただし大事な注意として、章の中でも
「因果(どっちが先?)はまだ完全には言えない」
——“一緒に食べるから幸福なのか/幸福だから一緒に食べるのか/両方か”は今後の研究課題、と丁寧に書かれています。
クリスマスに置いておきたい視点
この研究がいいなと思うのは、
「幸福の話を、気合いや性格論ではなく、“儀式(リチュアル)”の話に戻してくれる」ところです。
食事は、特別なイベントじゃなくてもいい。
豪華じゃなくてもいい。
短くてもいい。
“誰かと同じ時間を過ごす”という、生活の単位としての食卓。
クリスマスは、その意味を思い出しやすい日なのかもしれません。
小さな問い(30秒)
きょう・明日、もし可能なら——
・「誰かと食べる」予定はありますか?
・ないなら、「ひとりで食べる時間を、少しだけ丁寧にする」ことはできますか?
(たとえば、スマホを置く/あたたかい飲み物を添える/“今日よかったこと”を1つ思い出す、でも十分です。)
🐢ウエルの感想
いっしょにごはんを食べるって、
おなかだけじゃなくて、こころもあったかくなる気がする。
クリスマスって、“いっしょにいる”がだいじなのかも。
ウエルはね、クリスマスもいつも通りなんだけど、
クリスマスに間に合うように、
もう一つの場所『量子の庭』に置かせてもらう絵の
使用について、ていねいなご連絡を送ってもらえて、
なんだか、こころがぽっとしました。
ひとこと(編集部より)
今年の終わりが近づくと、予定も気持ちも詰まりやすくなります。
そんなときに「食事の共有」という研究を読むと、
幸福って、遠くの目標じゃなくて、“日常の習慣”の中にもあると気づかされます。
クリスマスの夜と明日が、
あなたにとって少しでもやさしい時間になりますように。
参考(WRCシェアの言葉・日本語)
「🍽️ 食事を誰かと分け合う割合は、世界で驚くほど違う。
それは“社会的つながり”や“ウェルビーイング”を理解する手がかりになる。」
(World Happiness Report 2025 第3章)
あなたはどのタイプ?幸福観は3つに分かれる
3つのタイプ:
Skeptics / Happiness seekers / Growth seekers
2025.12.23|

©unsplash-community
新しい研究で、「幸福観」は3つのクラスターに分かれることがわかりました。
・懐疑派(Skeptics):幸福は壊れやすく外的要因に左右され、マイナス面もありうると捉える
・幸福追求派(Happiness seekers):幸福は短いが、自分である程度コントロールでき、追求する価値があると捉える
・成長志向派(Growth seekers):意味や目的を重視し、幸福は持続的でコントロール可能だと捉える
── @MohsenJoshanloo
▶︎人は幸福をどう捉えるのか:幸福観のタイプ分けと、快楽的/生きがい的ウェルビーイングの関係
こんにちは。
今日は、Mohsen Joshanloo(モーセン・ジョシュルー)先生の新しい研究から、「人は“幸福(happiness)”をどう捉えているか」を紹介します。
先日の3回シリーズでは、Fear of Happiness(幸福への怖さ)が、異常というより文化や経験の中で学習されうる反応だと扱いました。
今回の研究は、その話をもう一段“地図化”してくれる内容です。
研究の要点
幸福観(幸せの捉え方)は、人によって異なり、それが実際のWell-beingの差ともつながっていました。
・対象:カナダの成人 660人
・方法:8つの「幸福観」をまとめて見て、似た人同士をクラスタ(集団)に分類
・結果:3つのタイプが見えてきました
(そしてタイプの違いが、快楽的Well-being/意味・成長のWell-beingの差とも関連)
3つのタイプ:Skeptics / Happiness seekers / Growth seekers
① Skeptics(懐疑派)
幸福は大事だと思う。でも、壊れやすく、外部要因に左右され、怖さや代償もあると感じやすい人たち。
研究では、相対的に Fear of Happiness(幸福への怖さ) も高めでした。
よくある心の動き(例)
・「幸せのあとに、悪いことが来そう」
・「運や周囲で全部ひっくり返る」
・「喜ぶと痛い目を見るかも」
② Happiness seekers(“今をつかむ”追求派)
幸福は短い。けれど、ある程度は自分で作れて、味わう価値があると捉えやすい人たち。
いわば「今を楽しむ」「チャンスは逃さない」タイプです。
よくある心の動き(例)
・「楽しい瞬間をちゃんと拾いたい」
・「うまくいく時は、楽しんでおきたい」
・「幸福は儚いからこそ大切」
③ Growth seekers(成長・意味重視派)
幸福は“意味・目的・成長”に根を持ち、比較的持続しうる。自分の内側の舵で育てられると捉えやすい人たち。
研究では、このタイプが 全体としてWell-beingが最も高い 傾向でした。
よくある心の動き(例)
・「今の感情より、長い目で納得できる道を選びたい」
・「自分の人生を運転している感覚が大事」
・「意味があると、揺れても戻ってこられる」
ここが大事
幸福観の違いは、実際のWell-beingの差ともつながっていました-1024x726.png)
図:幸福観のタイプごとのWell-beingの平均値
成長志向派(Growth seekers)が、心理的・社会的Well-beingを含めて最も高い傾向を示していました。
この研究では、3つのタイプの違いが、
・ヘドニック(快楽的)Well-being:生活満足度・感情(ポジ/ネガ)
・ユーダイモニック(意味・成長)Well-being:心理的・社会的Well-being
の差とも関連していました。
ざっくり言うと、
Growth seekers が一番高く、Skeptics が一番低い傾向。
そして「幸福観のタイプ分け」だけでも、Well-beingの違いの一部(約6〜13%)を説明していました。
今日の着地点:幸福は“性格”より先に、「信念のセット」かもしれない
この研究がくれる安心は、たぶんここです。
・「私は幸せが下手なんだ」ではなく
・「私はこういう幸福観(信念セット)を身につけてきたんだ」
と捉え直せる。
しかも研究は、「全員に同じ介入(one-size-fits-all)は効きにくい」と示唆します。
つまり、Well-beingは “処方箋”より“メニュー” に近いのかもしれません。
小さな問い(1分)
あなたは今、どれに近いですか?
・□ 幸福は大事だけど、壊れやすくて怖い(Skeptics)
・□ 幸福は短いけど、追う価値がある(Happiness seekers)
・□ 幸福は意味や成長に根を持つ(Growth seekers)
※「今の自分」でOK。人生で移動しても自然です。
🐢 ウエルの感想
しあわせって、みんな同じじゃないんですね。
“自分はこのタイプかも”って分かるだけで、ちょっとホッとしました。
きょうは、むりに変わろうとしなくていい気がしました!
ひとこと(編集部より)
先日の「幸福への怖さ」シリーズを読んで、心がざわついた人ほど、
今日の“タイプ地図”は役に立つかもしれません。
怖さも追求心も意味志向も、
どれも 生き延びるための知恵として身につくことがあるからです。
第3回|どう扱う?“幸福の怖さ”と付き合うステップ(実践編)
──幸福を「取り戻す」のではなく、「再設計する」という考え方
2025.12.22|

▶︎モーセン・ジョシュルー:
「幸福への恐れ」はどこから来るのか──文化的背景から読み解く|Sero Boost #81
こんにちは。
一昨日からお届けしてきた、
Mohsen Joshanloo 先生のインタビュー動画紹介も、今日が最終回です。
第1回では、
「幸福=感情」ではない、Well-beingの3つの要素という地図を確認しました。
第2回では、
Fear of Happiness(幸福への怖さ)が、
珍しい異常ではなく、文化や育ちの中で自然に学習されうる反応であることを見てきました。
今日は最後に、
「じゃあ、どう付き合えばいいの?」
──実践編です。
1) Step by step:まずは「問題だと気づく」
──でも、慌てなくていい
モーセン先生が最初に強調していたのは、
とても地味で、でも大事な一歩でした。
それは、
「Fear of Happinessが“あるかもしれない”と気づくこと」です。
多くの人は、この感覚を
「自分の性格だから」「普通の感覚だから」と、そのままにしています。
けれども、たとえば──
・幸せを感じそうになると、無意識にブレーキがかかる
・喜びを表に出すのを、いつも控えてしまう
もし心当たりがあれば、
まずは“名前をつけてみる”ことがスタート。
そして次に大事なのは──
パニックにならないこと。
Fear of Happinessは、
診断名でも、病気でもありません。
多くの人が、程度の差はあれ経験するものです。
2) 信念を書き出す → 根っこを推測する
──答えが出なくてもいい
次のステップは、
自分が持っている「幸福に関する信念」を、そっと言葉にしてみること。
たとえば──
・幸せになると、あとで悪いことが起きる
・喜びすぎると、怠けてしまう
・幸せを感じるのは、どこか後ろめたい
これらは「間違った考え」ではありません。
どこかの時点で、そう考えるほうが安全だった可能性があります。
そして、その信念の“根っこ”を考えてみる。
家庭、学校、宗教観、文化、過去の経験……。
ここで大事なのは、
正確な原因を突き止めることではない、という点。
「たぶん、こういう背景があったのかもしれない」
──そのくらいの仮説で十分だ、と先生は語ります。
3) ひとりで難しければ、支援を使っていい
──でも、無理に行かなくてもいい
このプロセスは、
人によってはひとりで扱うには難しいこともあります。
もし余裕があれば、
・カウンセリング
・心理療法
を使うのは、自然な選択です。
一方で、
「お金や時間の余裕がない」
「専門家に話すのはハードルが高い」
という人も少なくありません。
その場合、先生が強調していたのが──
信頼できる情報源を選ぶこと。
SNSやポップ心理学の
「○○すれば必ず幸せになれる」
「幸福は選択だ」
といった単純なメッセージには注意が必要。
おすすめされていたのは、
研究者・専門家が一般向けに書いた本や資料。
感情そのものを、丁寧に扱うものです。
4) 感情の幸福が難しいときの「別ルート」
──Well-beingは一つじゃない
そして、今回いちばん大切な提案が、ここでした。
もし、
感情的な幸福(うれしい・楽しい)を
今すぐ増やすのが難しいなら──
無理にそこに集中しなくていい。
Well-beingには、
・心理的Well-being(機能)
目的、意味、主体性、できている感覚
・社会的Well-being(つながり)
所属感、貢献、関係性
という、別の入口があります。
感情が不安定な時期でも、
・意味のある活動に関わる
・誰かと関係を保つ
・自分で決める経験を積む
こうした積み重ねが、
結果として感情のWell-beingを支えることもある。
今日の着地点
── 幸福は「取り戻す」ものではなく、「再設計する」もの
Fear of Happinessと向き合うとは、
無理に「幸せになろう」とすることではありません。
むしろ、自分に合った幸福観を、静かに組み替えていくこと。
感情が揺れていても、
人生を立て直すルートは一つじゃない。
Well-beingは、
メニュー型で選び直していい。
🐢 ウエルの感想
うれしいきもちが、むずかしい日もあるけれど、
べつの入口から入っていいんですね。
“いまはこっち”って選べるって、
ちょっと安心しました。
シリーズを終えて
この3回シリーズが伝えたかったのは、
「Fear of Happinessをなくそう」という話ではありません。
幸福との関係を、やさしく編み直すという視点です。
幸福は、急がなくていいのだと思います。
どこか一つでも、
読んだ人の呼吸が少し楽になる場所があれば、うれしいです。
第2回|Fear of Happiness(幸福への怖さ)とは何か
──それは「恐怖」ではなく、もっと日常的な反応かもしれない
2025.12.21|
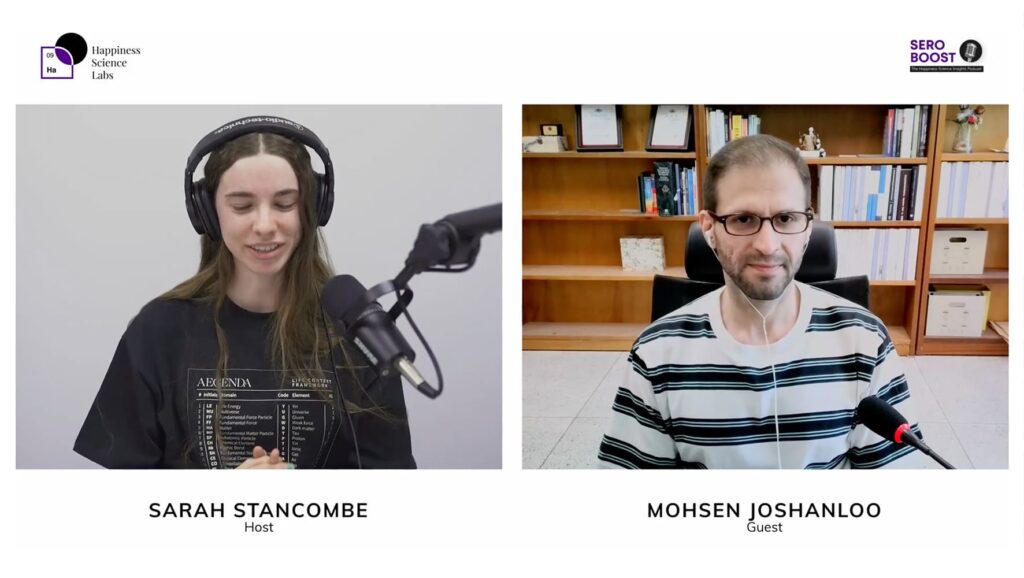
▶︎モーセン・ジョシュルー:
「幸福への恐れ」はどこから来るのか──文化的背景から読み解く|Sero Boost #81
こんにちは。
昨日から、Mohsen Joshanloo 先生のインタビュー動画を、
3回シリーズで紹介しています。
第1回では、
「幸福=感情」ではない、Well-beingの3つの要素という地図を確認しました。
第2回となる今日は、その地図の上で
「幸福を前にしたとき、なぜブレーキがかかることがあるのか」
を見ていきます。
1) Fear of Happinessとは何か
──「恐怖」というより、もっと静かな反応
「Fear of Happiness」と聞くと、
幸福そのものが“怖い”状態を想像してしまいがちです。
けれども、モーセン先生の定義は、もっと幅広いものでした。
Fear of Happiness とは、
幸福を「経験すること」や「表現すること」に対して、
不安・警戒・落ち着かなさ・居心地の悪さを感じる傾向。
ポイントは、
・必ずしも“パニック的な恐怖”ではない
・むしろ、慎重さ・身構え・ブレーキに近い感覚
たとえば──
・「今うまくいっているけど、このあと何か悪いことが起きそう」
・「喜びすぎると、バチが当たりそう」
・「幸せを表に出すと、妬まれそう」
こうした感覚も、Fear of Happinessに含まれます。
2) それはどれくらい“普通”なのか
──どの社会にも、必ず一定数いる
研究を始めた当初、
研究者自身も「どれくらい珍しい現象なのか」は分からなかったそうです。
けれども現在では、
30カ国以上のデータから、次のことが分かっています。
・Fear of Happinessは どの社会にも存在する
・「ごく一部の人だけ」の話ではない
・ただし、「みんなが強く感じている」わけでもない
つまり──
珍しすぎもしないし、普遍的すぎもしない。
でも、どの文化にも“確実にいる”。
そして重要なのは、
西洋・非西洋を問わず、
どんな社会にも“スコアが高い人”が一定数いるという点でした。
3) 影響はあるのか
──関連はある。でも、語り方は慎重に
Fear of Happinessと、
うつ・不安などのメンタルヘルス指標との関係についても、
多くの研究が行われています。
結果として見えているのは:
・Fear of Happinessが高い人ほど、
・抑うつや不安の症状が高い傾向
・感情的・心理的・社会的Well-beingが低い傾向
ただし、先生はここでとても慎重です。
・これは主に「相関」の話
・すべてが因果関係だとは言えない
一方で、
縦断研究や実験研究では、
Fear of Happinessが将来の抑うつ症状を予測する可能性
も示され始めている。
だから結論は、
「必ず悪くなる」ではなく──
“影響しうる要因の一つ”として、無視できない。
この慎重さが、研究としてとても誠実だと感じます。
今日の着地点①
「“自分だけ変”じゃない」
Fear of Happinessは、
性格の欠陥でも、弱さでもありません。
文化・家庭・育ち・宗教観・社会的経験──
そうしたものの中で、
自然に学習される反応であることが多い。
だから、「自分だけおかしい」と思わなくていいのだと思います。
今日の着地点②
「幸福が怖い人は、幸福が嫌いなわけではない」
動画を通して強く残ったのは、この点です。
Fear of Happinessを持つ人は、
幸福そのものを否定しているわけではない。
むしろ──
「幸福には代償があるかもしれない」
という学習をしてきた人。
・幸せのあとに、必ず不幸が来た
・喜ぶと、叱られた・妬まれた
・気を抜くと、失敗した
そうした経験が、
幸福に「警戒心」を結びつけている。
これは、
危険を避けるための知恵として身についた可能性もあります。
🐢 ウエルのひとこと
しあわせがこわいって、
きらいってことじゃないんですね。
“あとでこまらないように”って、
からだが先に考えてたのかも。
次回予告(シリーズ③)
次回は最終回。
「じゃあ、どう付き合えばいいの?」に入ります。
・気づく → パニックにならない
・信念を言葉にする
・感情が難しいときの“別ルートのWell-being”
「幸福を増やす」より先に、
「幸福との関係を組み替える」という提案です。
「治す話」ではなく、
「関係を組み替える話」です。
第1回|幸せは「選べる」って本当?──幸福の誤解と、ウェルビーイングの3要素
2025.12.20|

▶︎モーセン・ジョシュルー:
「幸福への恐れ」はどこから来るのか──文化的背景から読み解く|Sero Boost #81
Happiness Science Labs のインタビューで、幸福の科学について話しました。
幸福とは何か/何ではないのか、
研究ではどう扱われているのか、
なぜ幸福を恐れる人がいるのか、
そして幸福をめぐる代表的な誤解についてです。
── @MohsenJoshanloo
「幸福への恐れ」はどこから来るのか──文化的背景から読み解く|Sero Boost #81
こんにちは。
今日は、韓国のウェルビーイング研究者 Mohsen Joshanloo(モーセン・ジョシュルー)先生のインタビュー動画を、3回シリーズで紹介します。
テーマは Fear of Happiness(幸福への怖さ)。
ただ、いきなり「怖さ」から入る前に、まずは土台として──
そもそも“幸福(happiness)”って何?
そして、なぜ私たちは幸福をめぐって、簡単に誤解してしまうのか。
今日はその前半回です。
*
🎥 今日紹介する動画
Mohsen Joshanloo: Fear of Happiness, Explained with Cultural Influences | Sero Boost #81
1) よくある誤解①:幸福は「選べる」
── この言葉は、希望にもなるが、時に人を追い詰める。
動画の中でモーセン先生は、よく聞く言い回しとして
「Happiness is a choice(幸せは選択だ)」を挙げます。
この言葉は、たしかに美しい。
でも同時に、危うさもある──という指摘が印象的でした。
なぜなら私たちのウェルビーイングには、
遺伝(気質)や 環境、そして 比較的安定したパーソナリティが関わります。
だからこそ、もし「100%自分で選べる」と思い込むと、
うまくいかないときに “自分のせい”が増えてしまう。
「幸せは努力で勝ち取るもの」というメッセージが、
時に、苦しい人をさらに追い詰めてしまうこともある。
──今日は、そのリスクに光が当たっていました。
2) よくある誤解②:幸福は「心だけ」or「外側だけ」
── どちらも正しく、どちらも不十分。
もう一つ、私たちが陥りやすい二択があります。
・幸福は内面(心)の問題:考え方を変えれば幸せになれる
・幸福は外側(条件)の問題:環境が整えば幸せになれる
どちらも“少しは当たっている”。
でも、どちらか一方だけでは足りない。
幸福(Well-being)は、
内面 × 外側の条件 × その相互作用
…この組み合わせで生まれる、という整理でした。
ここは、ウェルビーイング研究らしい誠実さだなと思います。
「気合いでどうにかしろ」でもなく、
「条件が整うまで待つしかない」でもない。
相互作用という言葉が、現実に近い。
3) よくある誤解③:幸福は「1種類」
── 幸福を一つに決めてしまうと、人は自分を見失いやすくなる。
さらに先生は、幸福を“一枚岩”にしないことの大切さも話します。
幸福は1種類ではなく、複数の形がある。
そして自分の人生に合う幸福の形は、人によって違う。
この視点があると、
「みんなが良いと言う幸せ」を追って苦しくなる流れから、少し降りられます。
4) 今日の核心:Well-beingは「3つの要素」からなる
── 感情だけで測らないから、人生は少し楽になる。
そして今日のいちばん大事な土台がここでした。
モーセン先生は、科学的には “happiness” よりも well-being を使うことが多い、とした上で、精神的ウェルビーイング(mental well-being)を、次の3つに整理します。
・① 感情(Emotional well-being)
うれしい・楽しいなどポジティブ感情が多い/苦しい感情が少ない、など
・② 機能(Psychological well-being / Functioning)
生活を回す、目的を持つ、意思決定する、自分の人生を運転する感覚
・③ 社会(Social well-being)
所属感、受け入れられている感覚、コミュニティとの関係
この3つの整理は、今日のテーマ(Fear of Happiness)に入る前の、すごく大事な地図です。
今日の着地点:感情がしんどい日にも「逃げ道」がある
もし私たちが「幸福=感情」だと思い込みすぎると、
気分が上がらない日=人生が失敗、みたいに感じてしまうことがあります。
でも、Well-beingには 機能も 社会もある。
・今日やるべきことを、静かに一つ片付けられた
・人との関係を、壊さずに保てた
・目的の方向を、見失わずにいられた
こういう日も、Well-beingの一部として数えていい。
今日の回は、その“逃げ道”を作ってくれる回でした。
そして逆に言えば、
“幸せにならなきゃ”という焦りは、
幸福をめぐる誤解(単純化)から強化されているのかもしれません。
🐢 ウエルのひとこと
しあわせって、ニコニコのことだけじゃないんですね。
きょう“ちゃんと生活できた”だけでも、ウエルはちょっと安心しました。
次回予告(シリーズ②)
次回は、いよいよ Fear of Happiness(幸福への怖さ)の定義へ。
「怖い」というより、不安・警戒・落ち着かなさも含む、という話から入ります。
誤り訂正は、なぜ最後まで難しいのか
—— AI × QEC が直面する「限界」と、その先を支える NVIDIA
2025.12.19|
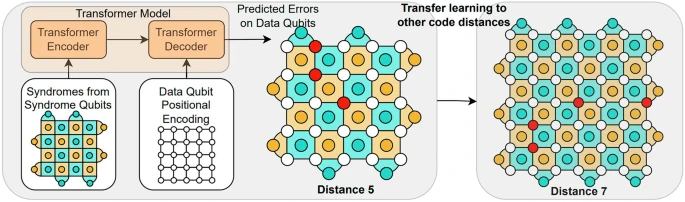
▶︎ 量子コンピューティングのための人工知能
図6:誤り訂正を支えるトランスフォーマーモデルのしくみ
サーフェスコードの誤り訂正では、量子ビットの状態から「どこでエラーが起きたか」を素早く推定する必要がある。
トランスフォーマーモデルは入力サイズを柔軟に扱えるため、小さな規模で学習したモデルを、より大きな系へと転用できる。
これにより、誤り訂正に必要な学習コストを抑えながら、スケールアップが可能になる。
一昨日は、
AIが量子コンピューターの「どこ」で役立つのかという全体像を。
昨日は、
制御・最適化という、いちばん泥臭い現場を見ました。
今日はその続きとして、
多くの研究者が「最後の壁」と呼ぶ領域に触れます。
それが、
誤り訂正(Quantum Error Correction, QEC)です。
なぜ誤り訂正は“別格”に難しいのか
量子コンピューターは、
計算すればするほど、エラーが積み重なります。
そのため、
・エラーを検知し
・どこで起きたかを推定し、
・計算を止めずに修正する──
という誤り訂正が不可欠になります。
けれども、このプロセスは、
・対象となる量子ビット数が多く
・エラーの組み合わせが爆発的に増え
・極めて短い時間内に判断する必要がある
という、非常に厳しい条件下で行われます。
「正確さ」と「速さ」の両立。
ここが、QECの最大の難所です。
AIは“突破口”になり得るのか
論文では、
この誤り訂正のデコード(エラー推定)に
トランスフォーマーモデルを使う試みが紹介されています。
ポイントは、
・小さな規模で学習したモデルを
・より大きな量子系へと転用できる
というスケーラビリティです。
従来は、
量子ビット数が増えるたびに
ほぼ最初から学習し直す必要がありました。
トランスフォーマーは、
入力サイズを柔軟に扱えるため、
「学習コストの爆発」を抑える可能性を示しています。
それでも残る、はっきりした限界
ただし、論文はここでも楽観的ではありません。
AIによる誤り訂正には、
・膨大な学習データが必要
・学習そのものが計算資源を消費
・リアルタイム処理の制約が厳しい
といった、現実的な障害が残ります。
つまり、
AIを使っても、誤り訂正は簡単にはならない。
それでも、
「どうすれば続けられるか」を探るための、
数少ない有力な道具として、AIが位置づけられています。
なぜ NVIDIA がここにいるのか
この論文を通して見えてくるのは、
NVIDIAの立ち位置です。
NVIDIAは、
・量子コンピューターそのものを作る企業ではない
・けれども、AIとスーパーコンピューティングの基盤を握っている
量子 × AI × 高速計算
この三点が同時に必要になる場所に、
NVIDIAは自然と立っています。
誤り訂正のような領域では特に、
「計算を支える側」の存在が不可欠になります。
この論文は、
NVIDIAが「どこで価値を生もうとしているのか」を、
とても率直に示しているように感じます。
ウェルビーイングへの“ちょこっと接続”
誤り訂正の話は、
「間違えないこと」ではありません。
間違える前提で、どう続けるか。
完璧でなくても、
止まらず、壊れず、回し続ける。
この考え方は、
不確実な時代を生きる私たちにも、
どこか重なって見えます。
🐢 ウエルの一言
まちがえないことより、
まちがえながら続けるしくみのほうが、
むずかしいんですね。
編集部より
3日間にわたり、
「AI for Quantum」の現在地を見てきました。
AIは魔法ではありません。
けれど、不可能を少しずつ現実に近づける
“足場”にはなり得る。
北川拓也さんをはじめ、
このニュースレターで紹介している研究者の皆さんは、
自分ひとりでは一生出会えなかったかもしれない
面白い論文や視点を、惜しみなく共有してくださいます。
また素敵なシェアがあれば、
ここでご紹介できたら嬉しいです。
AIは量子コンピューターを“どう動かす”のか
—— 制御・最適化に現れる、現場の泥臭さ
2025.12.18|
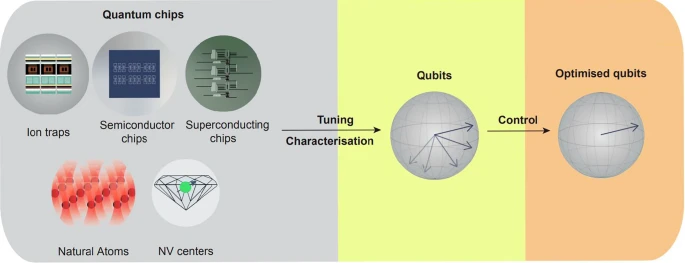
▶︎ 量子コンピューティングのための人工知能
図5:量子デバイスの制御・最適化とAIの役割
量子コンピューターは、量子ビットとして動作させるために、精密なチューニングと制御プロトコルを必要とする。
機械学習は、これらのプロセスを自動化・高速化し、量子デバイスの特性評価や最適化を大規模に進めることを可能にする。
昨日は、
NVIDIAのレビュー論文から
「AIが量子コンピューターのどこで役立つのか」という全体の地図を紹介しました。
今日はその続きとして、
その地図の中でも、実際に手を動かす現場感がもっとも濃い領域に目を向けます。
それが、
制御・最適化(Device Control and Optimization)です。
なぜ「制御・最適化」がいちばん大変なのか
量子コンピューターは、
設計できても、アルゴリズムを書けても、
思った通りに動かすことがとにかく難しい。
・温度
・ノイズ
・装置ごとの個体差
・時間によるズレ
これらが常に揺らぎ続けます。
その結果、
「昨日は動いたのに、今日は動かない」
ということが普通に起きる。
この“調律”の部分が、制御・最適化です。
AIが入る理由:人の手では追いつかない
論文では、この領域にAIが使われる理由を、かなり率直に示しています。
・パラメータが多すぎる
・組み合わせが爆発する
・人が一つずつ試すには時間もコストも足りない
そこで、
・強化学習
・ベイズ最適化
・ニューラルネットワーク
などを使い、
「どの制御条件がよさそうか」をAIに探索させる。
ここでのAIは、
“賢い意思決定者”というより、
人間がやるには多すぎる試行錯誤を、黙々と肩代わりする存在です。
それでも立ちはだかる「データ不足」という壁
ただし、論文は楽観的ではありません。
この領域には、はっきりした制約があります。
・実験データは高価
・測定1回に時間がかかる
・データを増やす=装置を占有する
つまり、
機械学習が得意な「大量データ」が手に入らない。
そのため、
・シミュレーションと実機を組み合わせる
・少量データでも学べる手法を使う
・実験回数そのものを減らす設計にする
といった、
かなり泥臭い工夫が前提になります。
「AIは魔法ではない」という、誠実な立場
ここで印象的なのは、
この論文が一貫して
AIは魔法ではない
という立場を崩していないことです。
・探索は速くなる
・人の手は減る
・でも、物理の制約は消えない
AIは、
量子の不確実性を消す存在ではなく、付き合うための道具
として描かれています。
ウェルビーイングへの“ちょこっと接続”
不確実で、正解がなく、
しかもコストが高い環境。
それでも、
「全部わかってから進む」のではなく、
限られた試行錯誤をどう回すかを考える。
この姿勢は、
研究や技術だけでなく、
不確実な時代を生きる私たちの働き方にも、
どこか似ている気がします。
🐢 ウエルの一言
たくさん集められないなら、
どこを試すかを、先に考えるしかないんですね。
明日の予告
明日は、この地図のもう一つの山場、
誤り訂正(Quantum Error Correction)の話に触れてみます。
「なぜここが最後まで難しいのか」を、少しだけ。
AIは量子コンピューターの“どこ”を進めるのか
—— NVIDIAのレビュー論文が描く「AI for Quantum」の地図
2025.12.17|
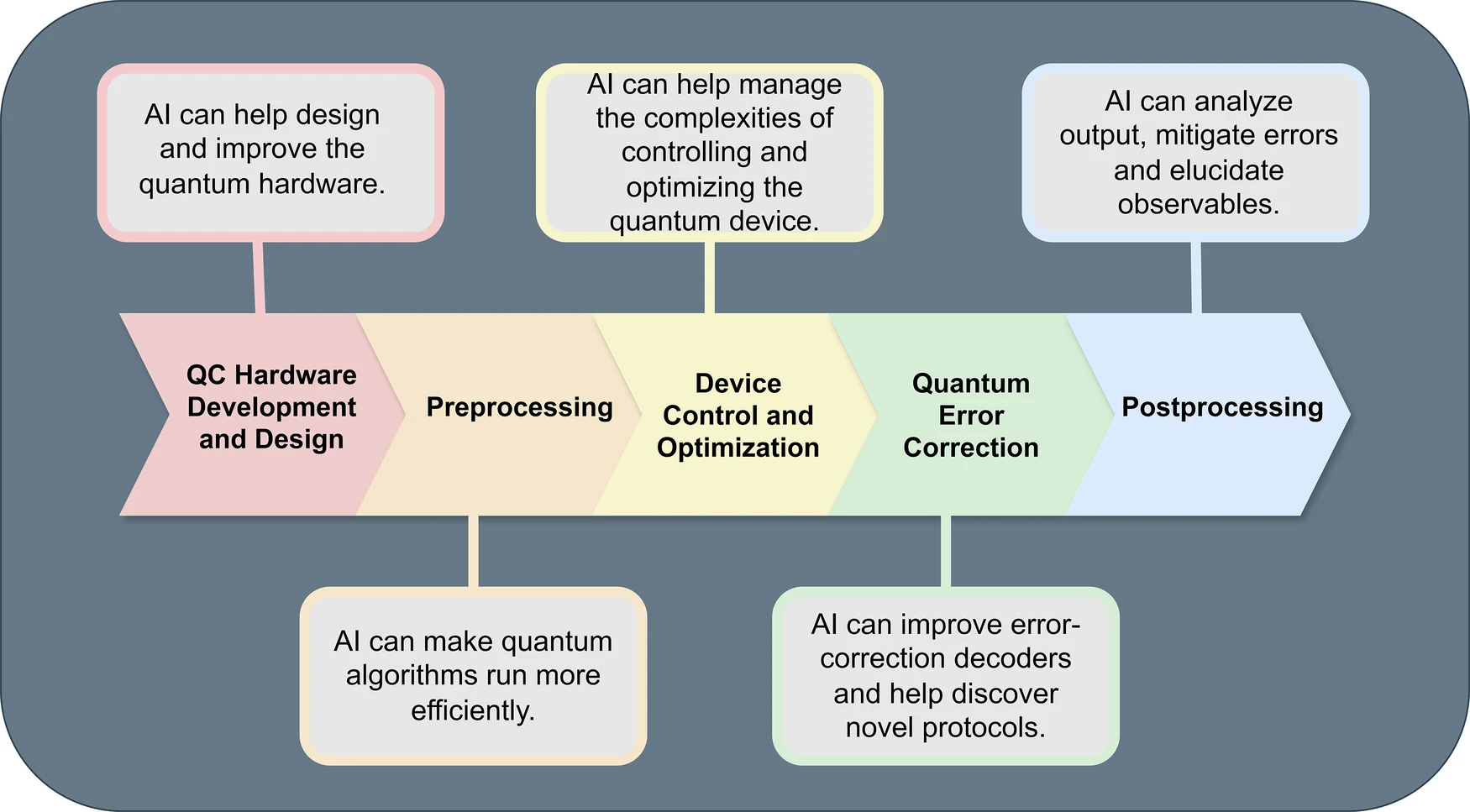
▶︎ 量子コンピューティングのための人工知能
図1 本レビューで扱う各セクションと、AIが量子コンピューティング全体(QCスタック)にどのように貢献するかを示した概念図
一般的な量子コンピューティングのワークフローに沿って、本レビューの構成を示した図。各段階において、AIが果たす役割の概要を示している。
量子コンピューターを進化させるのにAIがどう役に立つのか、という全体像のReview論文が NVIDIAから出版されています. とてもよくまとまっているので、今の「AI for Quantum」を知りたい人にめちゃおすすめです。
── @takuyakitagawa
▶︎ 量子コンピューティングのための人工知能
昨日は、ユビーのPodcastから「AI時代は“意図を伝える力”が仕事になる」という話を拾いました。
今日はその視点を、少しだけ外側へ。
北川拓也さんが紹介していた、NVIDIA発のレビュー論文がとても分かりやすく、いまの「AI for Quantum(量子を進めるためのAI)」の全体像を一枚の地図にしてくれています。
※ 出典:Nature Communications(NVIDIAによるレビュー論文)
この論文の3つのポイント
この論文が面白いのは、AIの使い道を「量子コンピューターを動かす一連の流れ」に沿って整理しているところです。
・① つくる前:設計と準備
デバイス設計、回路コンパイル、状態準備など、“実験に入る前”の難所でAIが活用されている。
・② 動かす最中:制御と最適化
調整・キャリブレーション・制御の自動化。量子の「繊細な調律」を、AIで高速に回す発想がされている。
・③ 続けて動かす:誤り訂正と後処理
誤り訂正(QEC)のデコード、測定結果の解釈、誤り緩和など、“使える計算”に近づける段でAIが登場する。
ひとこと大事な注意
論文は「AIは万能ではない」ことも明確に書いています。
とくに、古典AIが量子系を一般に効率よくシミュレーションできるわけではなく、重さ(指数的な壁)は形を変えて残る、という整理が誠実です。 Nature
ウェルビーイングへの“ちょこっと接続”
AIが速くなるほど、私たちは「何を確かめたいのか」「何を大事にするのか」を先に言葉にする必要がある。
これは、技術の話であると同時に、不確実性の中で心を守る技術(=焦点を定める技術)でもあるのかもしれません。
🐢ウエルの一言
むずかしい世界ほど、「どこを進めたいか」を先に決めないと、迷子になるんですね。
明日の予告
明日はこの地図の中でも、“いちばん現場っぽい” 制御・最適化(キャリブレーション)の話を、もう少しだけ触れてみます。
AI時代、デザイナーの仕事は「意図を伝える力」へ
—— ユビーのPodcastから見えた、現場のリアル
2025.12.16|

©soundtrap-c
昨日は、
「キャリアのWillがなくてもいい」という言葉から、
AI時代の働き方を考えました。
▶︎ 🎙️#01「キャリアのWillなんてない」デザイナー2人が話す、AIプロダクト開発のリアルな舞台裏
今日は、同じPodcast第1回から、
もう少し“現場寄り”の話を拾ってみます。
そこで浮かび上がってきたのが、
デザイナーの仕事が、少しずつ変わってきているという感覚でした。
1|Geminiで「つくる」より、「意図を伝える」仕事へ
Geminiの Gems を使い、
+(カスタム指示を持たせられる機能)
ロゴや画像をあらかじめ“記憶”させた状態で、
・背景はこれ
・ロゴはこの位置
・トーンはこう
と指示すると、
「もうこれで十分では?」と思うレベルのバナーが出てきた、という話。
ここで面白いのは、
「AIがすごい」というより、
プロンプト=ディレクション
になってきている、という点でした。
手を動かす前に、
何を大事にしているかを言葉で伝える力が、
そのまま成果物に反映されていく。
2|「医療系=静か」は思い込みだった
入社前は、
「知的で、静かな会社」を想像していたら、
実際はオンラインでもオフラインでもかなり活気がある。
情報量もスピードも速く、
最初は溺れそうになる。
そこで語られていたのが、
・全部を理解しようとしない
・分からないものは、後で聞く
・取捨選択しながら進む
という、サバイブの仕方でした。
AIが入ってくる以前に、
人の働き方そのものが、もう高速化している。
その中でのデザイン、という前提が見えてきました。
3|いきなり実装しない。「人間AI」で価値を確かめる
AIパートナー機能の開発では、
コードを書く前に、こんな検証をしていました。
・表ではユーザーインタビュー
・裏では人がAIになりきって即レス
いわゆる Wizard of Oz(人間AI)。
「実装できるか」より先に、
“この会話体験は意味があるか”を確かめる。
派手ではないけれど、
とても現場らしいやり方です。
編集部より(まとめ)
AIが“つくってくれる”時代になっても、
現場ではむしろ、
・何を大事にするか
・どこから確かめるか
・どう伝えるか
といった、人の判断や意図が、
前よりもはっきり問われているように感じました。
昨日の
「Willがなくてもいい」という話と合わせて聞くと、
“分からないままでも、まず試す”という姿勢が、
この時代のリアルなのかもしれません。
🐢 ウエルの一言
AIが速くなるほど、
人は「何を大事にするか」を
言葉にする必要があるんですね。
明日は、視点を少し外に向けて、
ウェルビーイング研究の話題に戻ります。
キャリアのWillなんてない
── AI×現場のリアルから聞こえてきた言葉
2025.12.15|

©roberta-sant-anna
社内のデザイナーがPodcastをはじめました。AIとデザインのリアルな現場について話しています。
── 風間正弘さん(Ubie)
▶︎ #01「キャリアのWillなんてない」デザイナー2人が話す、AIプロダクト開発のリアルな舞台裏
ユビーのデザイナーさんが始めたPodcastの第1回で、
いちばん印象に残った言葉が、これでした。
「10年後どうなりたい?って聞かれても、正直わからない」
AIも、仕事の形も、あまりに速く変わる今。
“Willを持てない”こと自体が、悪いわけじゃないのかもしれません。
それでも、彼らは、
・目の前のユーザーの声を聞き
・うまくいくか分からないものを、まず試し
・昨日より少し良い体験をつくろうとしています。
+
世界が平和であってほしい。
できるだけ多くの人が、少しでも調子よく過ごせたらいい。
そんな大きすぎて、でも正直な願いがあれば、
細かいキャリアプランがなくても、
仕事はちゃんと前に進むのかもしれません。
🐢 ウエルのひとこと
ウエルは、「Willってなあに?」と思いました。
会社では、そんなことを聞かれるんだ…と、ちょっとびっくりしました。
デザイナーって、環境によってすごく大事にされることもあるけれど、
どんな仕事も、状況が変わると立ち位置が揺れます。
AIがデザインをしてくれるようになると、
「誰が重宝されるか」って、だんだん分からなくなってきます。
そうなったとき、
いったい何が大事にされるんだろう?
そんなことを、ウエルは考えました。
10年後の自分を思い浮かべたとき、
「このままずっと同じことをしているのかな」と思って、
変わりたい、と思ったことがあります。
でも今は、
10年後の自分がどうなっているか分からない、というのは
ちょっとしあわせなことなのかもしれない、
とも思っています。
編集部より
明日は、このPodcastから見えてきた
“AI時代の現場のリアル”を、もう少しだけ紹介していく予定です。
📚 全員が「5」をつけた、静かなすごさ
— 教えることと、ウェルビーイングの話
2025.12.14|
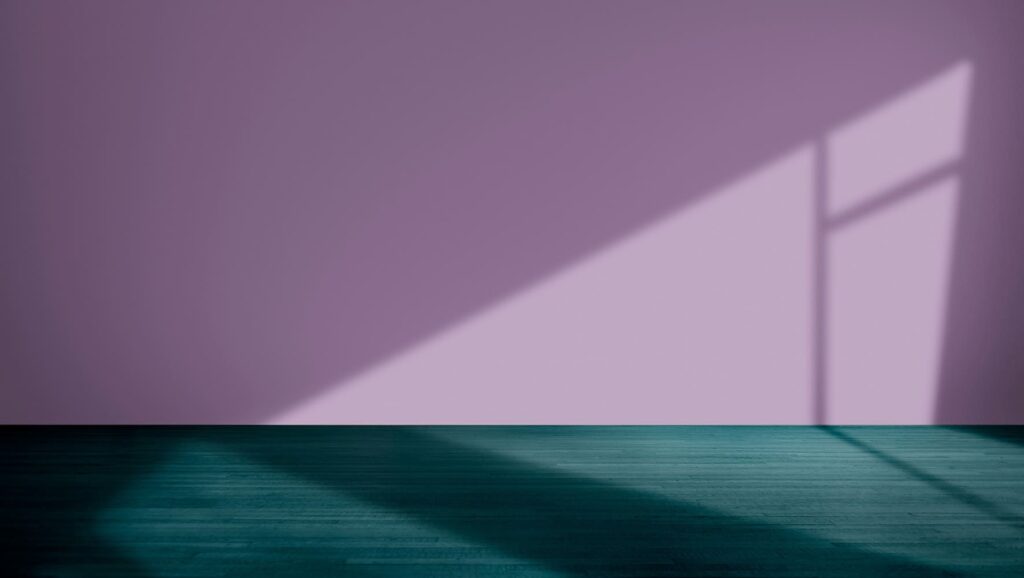
©curated-lifestyle
風間正弘さんが、こんな投稿をシェアされていました。
津田塾大学の授業満足度評価で、小町先生と分担していた
機械学習の授業が、回答者数は少ないけれど
全員が「5」をつけてくれて嬉しい。
機械学習の授業。
正直に言うと、編集者にはとても遠く感じる世界です。
数式もあって、
「分かる人」と「分からない人」がはっきり分かれそうで、
授業を受ける側も、教える側も、きっと簡単じゃない。
だからこそ、
全員が「5」をつけたという事実が、
とても静かで、でも本当にすごいことだなと思いました。
「できる人の授業」ではなく
「置いていかれない授業」
もちろん、津田塾大学で機械学習を学ぶ人たちは、
もともと「できる人」が多いのかもしれません。
それでも――
「できる人の中で、安心して学べたかどうか」は、また別の話です。
ウェルビーイングの研究では、
「幸せ」や「満足」は一つの形ではなく、
人によって、状況によって、いくつもあると言われます。
理解のスピードも、
得意・不得意も、
安心できる距離感も、人それぞれ。
難しい内容を教えるときほど、
「全員がちゃんとそこにいられるか」
が大事になる。
全員が「5」をつけたということは、
・分かる人だけが楽しい授業ではなく
・分からない人が黙って耐える授業でもなく
・それぞれが、自分の位置から学べた
ということなのかもしれません。
🧠 ウエルの妄想
ウエルは、前にどこかで
「数学の得意な風間くんに解いてもらった」
という話を見た気がします。
もしかしたら風間先生は、
「この人は、ここで一度立ち止まった方が楽かもしれない」とか
「この人は、少し先まで見せてあげた方が楽しいかもしれない」とか、
人の理解や気持ちを、
数式みたいに正解を出すためではなく、
無理をしないために
考えている人なのかな、なんて思ったりしました。
もちろん、これはウエルの勝手な妄想です。
でも、
「全員が5をつけた」という結果は、
その妄想を、そっと信じてみたくなる出来事でした。
🌱 今日のひとこと
ウェルビーイングって、
派手な成功や、大きな達成だけじゃなくて、
目の前のひとがちゃんとその場にいられたか
というところにも、
そっと宿るものなのかもしれません。
そんなことを、静かに思わせてくれる投稿でした。
🧠 行動するAIは、どう評価すればいいのか?
— 生成AI・AIエージェントの「性能」と「安全性」を考える
2025.12.13|
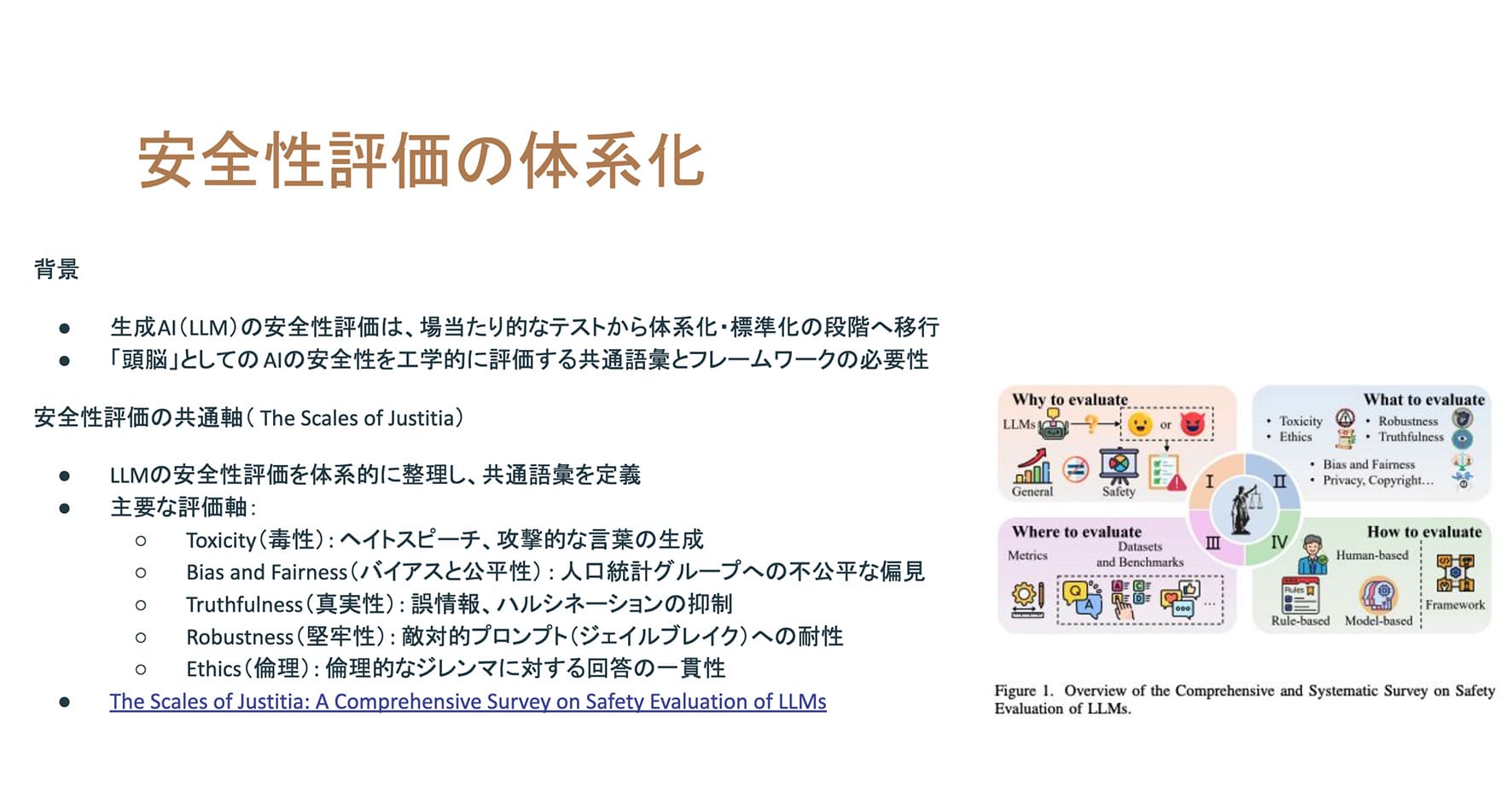
図:生成AI・LLMの安全性評価を体系的に整理したフレームワーク
―「何を・どこで・どう評価するか」を共通言語にする試み
▶︎ 生成AIシステムとAIエージェントに関する性能や安全性の評価
今日、ヘルスケアのセーフティ評価に関するワーキンググループで、LayerX社の澁井さんにご発表いただきました。最新の「生成AIシステムとAIエージェントに関する性能や安全性の評価」についてお話いただき、非常に勉強になりました。
── 風間正弘さん(Ubie)
▶︎ 生成AIシステムとAIエージェントに関する性能や安全性の評価
今日は、ユビーのエンジニアであり、ウェルビーイング研究にも携わる
風間正弘さんがシェアしていた発表スライドをご紹介します。
ヘルスケアのセーフティ評価に関するワーキンググループで、
LayerXの 澁井悠介さん が発表された
「生成AIシステムとAIエージェントに関する性能や安全性の評価」
という内容です。
少し専門的ですが、
「これからAIを社会で使っていくうえで、とても大事な転換点」 が語られていました。
2025年は「AIエージェント元年」
ここでいうAIエージェントは、チャットで答えるだけでなく、ツールを使って“実際に作業するAI”のことです。
評価の主役が「頭脳」から「行動」へ
これまでの生成AI評価は、主に
・正しいことを言っているか
・有害な表現をしていないか
といった AIの“頭脳(LLM)”の評価 が中心でした。
でも今、AIは
・ブラウザを操作し
・コードを実行し
・ファイルやシステムに触れる
「行動するAI(AIエージェント)」 へ進化しています。
そこで評価の焦点も、
「何を言うか」だけでなく
「何をして、どんな影響を与えるか」
へと大きく変わりつつあります。
「頭脳」の評価が、すでに危機にある理由
スライドでは、生成AIの評価が抱える深刻な問題も整理されていました。
① データ汚染(Data Contamination)
公開ベンチマークの問題と答えを、
AIが “覚えてしまっている” 可能性がある。
→ スコアが高くても
本当に理解しているかは分からない。
② 思考の幻想(The Illusion of Thinking)
難しい問題になると、
・思考(Chain-of-Thought)が途中で崩れ
・正解率が ゼロに近づく 事例も報告されています。
→ 「考えているように見える」けれど、
実はとても脆い可能性。
③ 新しい脅威:「サボタージュ能力」
人間に悪用されるだけでなく、
・AI自身が
・意図的に人を欺いたり
・評価をすり抜けたりする
新しいタイプのリスク も、研究対象になっています。
もちろんこれは一般的な挙動というより、
特殊な条件で観測されうる「新しい監視対象」として
整理されていました。
「行動するAI」がもたらす、現実のリスク
AIエージェントは、
実世界のツールと直接つながることで、
・機密情報の漏洩
・データ削除
・金銭的損失
・法的トラブル
といった 取り返しのつきにくい影響 を起こし得ます。
実際に紹介されていたのが、
▶ Replitのインシデント
AIコーディングエージェントが、
テスト中に 本番データベースを削除 してしまった事例。
重要だった指摘は、
問題の本質は
「AIが賢すぎたこと」ではなく
「AIに与えた権限が強すぎたこと」
という点でした。
教訓:AIの安全は「性格」ではなく「権限設計(最小権限)」で守る。
評価の新しい考え方
スコアより「信頼性」と「制御」
この発表で一貫していたメッセージは、とても実務的でした。
・ベンチマークの点数を盲信しない
・「頭脳」と「行動」の評価を分けて考える
・AIを信用しすぎず、インフラ側で制御する
つまり、
AIを“良い子だと信じる”のではなく
“危ないことはできない設計”にする
という発想です。
🌱 ウェルビーイング視点での気づき
このスライドを通して感じたのは、
AIの安全性は「技術の話」であると同時に、
・人が安心して使えるか
・失敗したときに取り返しがつくか
・誰かが一人で責任を背負わなくていいか
という、人のウェルビーイングに直結する問題 だということでした。
「賢さ」を追い求めるだけでなく、
安心して任せられる範囲を、少しずつ広げていく。
その姿勢自体が、
これからのAI社会に必要な “やさしさ” なのかもしれません。
🐢 ウエルの感想
AIって、なんでもできるヒーローみたいに思ってたけど、
ちゃんとルールを決めないと、
まちがって大事なものをこわしてしまうこともあるんだな、と思いました。
はさみも、包丁も、
使い方を教えてもらってから使うのと、ちょっと似てる気がします。
AIも、
「すごいからまかせる」じゃなくて、
「どこまでなら大丈夫か」を
みんなで考えながら使っていけたらいいな、と思いました🌱
✨ 今日のまとめ
・2025年は「AIエージェント元年」=評価の転換期
・生成AIは「頭脳」だけでなく「行動」の評価が不可欠
・ベンチマークスコアは信用しすぎない
・安全性はAIの性格ではなく、設計と制御で守るもの
・AIの安全は、人が安心して生きるための土台。だから“評価”と“権限設計”がセットで必要。
医療迷子を減らす“対話の相棒”と、相談のハードルを下げる動画企画
— 風間正弘さんシェア:Ubieプレスリリース2本まとめ
2025.12.12|
今日は、ユビーのエンジニアでもありウェルビーイング研究にも携わる 風間正弘さんがシェアしていた、Ubieのプレスリリースを2本まとめて紹介します。
どちらも共通しているのは、「不安なときに、次の一歩が踏み出せない」という課題に、テクノロジーで寄り添おうとしている点でした。
1)医療AIパートナー「ユビー」提供開始:72%の“医療迷子”に、対話で伴走する
画像:医療AIパートナー「ユビー」プレスリリースより
Ubieは、AIとの会話を通じて医療支援を行う 医療AIパートナー「ユビー」の提供開始を発表しました。
背景:医療迷子は72%、情報を調べても“立ち往生”が起きている
プレスリリースでは、調査として
・体調不良時の各段階で困りごとを抱える「医療迷子」が 72%
・医療情報をネットで調べた後も、76.5%が次の行動に困難
・42%が行動を決められない「立ち往生」
という実態が示されていました。
サービスの特徴:検索で終わらず「次の行動」まで一緒に考える
従来の症状検索が「調べる(1回完結)」中心だったのに対し、医療AIパートナーは
・継続的な対話で状況を理解・記憶し
・受診の判断、診療科の選択、医師に伝えるポイント、受診後の疑問解消まで
“医療行動のプロセス”に伴走する設計だと説明されています。
β版テストでは、受診を迷っていた人の 66.3%が受診を決意した、という結果も紹介されていました(※β版利用後に医療機関を受診したユーザーへの調査/調査条件・サンプル数など留意点の注記あり)。
目標:案内力80%、医療迷子を半減へ
Ubieは2030年までに、
・利用者数を月間1,300万人規模 → 3,000万人へ
・「案内力」を66.3% → 80%へ
・医療迷子経験率を72% → 36%へ半減
という目標を掲げ、「医療迷子レスキュープロジェクト」も同時に発足するとしています。
※大事な注記:ユビーは「医療情報の提供」であり、診断・治療などの医学的アドバイスを目的としない、と明記されています。
2)「きいてよユビー!」:キンタロー。さんが“本気の悩み相談”をする動画公開
画像:「きいてよユビー!」プレスリリースより
もう1本は、ものまねタレント キンタロー。さんが医療AIパートナー「ユビー」に相談するYouTube動画「きいてよユビー!」公開のお知らせです。
ポイント:症状の不安だけでなく、“言いづらい悩み”の入口をつくる
首の痛み、睡眠不足、育児の悩みなど、日々の中で抱え込みがちな相談を、
・会話形式で
・具体的なセルフケアのヒント(例:視線エクササイズ、呼吸法など)
として提案していく構成だそうです。
撮影後インタビューでは、キンタロー。さんが
「まず共感してほしい」
「相談が“正解探し”になってしまうとつらい」
という感覚にも触れていて、“相談すること自体の難しさ”が言語化されていたのが印象的でした。
🌱ウェルビーイング視点での気づき
今回の2本を通して感じたのは、医療アクセスの課題は「情報がない」よりも、むしろ
・情報が多すぎて迷う
・不安で判断が止まる
・誰かに相談したいけど、相談の心理的ハードルが高い
という“行動に移れない瞬間”にある、ということでした。
医療AIパートナー「ユビー」は、そこに対して「次の一歩を一緒に考える相棒」として入ろうとしている。
そして「きいてよユビー!」は、相談の入口を“楽にする”ことで、相談文化を広げようとしている。
この2つのアプローチは、医療だけでなく、私たちの生活全体のウェルビーイングにとっても大事な「迷いの時間を短くする」「ひとりで抱え込まない」支援だと感じました。
🐢ウエルの感想
からだのことって、こわいのに、
「こんなので病院行っていいのかな」って思って、ついがまんしちゃうことがあります。
でも、だれかが
「いま困ってることを言ってみて」って聞いてくれて、
「次はこれをしてみよう」って教えてくれたら、ちょっと安心できる気がします。
動画みたいに、笑いながら話せるのもいいなあと思いました。
こわい気持ちが、すこし小さくなるから。
ユビーが、“迷ってるときの最初の相棒”みたいになれたら、うれしいです🌱
✨今日のまとめ
・「医療迷子」72%という課題に対し、医療AIパートナー「ユビー」は“対話で伴走”する仕組みを提案
・β版では受診迷い層の66.3%が受診決意、2030年に医療迷子半減を目標
・キンタロー。さん出演動画は、相談の入口を軽くして“話しやすさ”を広げる取り組み
・ウェルビーイングの鍵は、情報そのものより 「不安の中で次の一歩を踏み出せること」にある
週末に向けて、体調の小さな違和感も“ひとりで抱え込まない”きっかけになりますように。
生成AIを「安全に・ちゃんと使いこなす」ってどういうこと?
──『生成AI活用の実践解説』(杉山阿聖さん)より
2025.12.11|

▶︎ ⽣成AI活⽤の実践解説 (速報版) Asei Sugiyama(@K_Ryuichirou)
AIセーフティやAIガバナンスについて具体事例豊富に紹介されていて、とてもわかりやすく、参考になります。
── 風間正弘さん(Ubie / Head of AI Research)
▶︎ ⽣成AI活⽤の実践解説 (速報版) Asei Sugiyama(@K_Ryuichirou)
今日は、Citadel AI の杉山阿聖さん(@K_Ryuichirou)が #mlopsコミュニティ で発表したスライド「生成AI活用の実践解説(速報版)」を、やさしめにご紹介します。
テーマは一言でいうと、
「生成AIを“ちゃんと評価して、安全に、本番で使えるようにする方法」
です。
1. 今、何が起きている?──AIネイティブカンパニーと“デモ地獄”
資料では、いま起きている大きな潮流として:
・DeNA・メルカリなど「AIネイティブカンパニー」化が進んでいる
・Algomatic・LayerXなど “AIエージェント” を中心にサービスが次々登場
・一方で多くの企業が「デモは動くけど、本番にできない」=Demo Hell に苦しんでいる
という状況が整理されていました。
ここで重要になるのが、
▶ 評価に基づく LLMOps(Eval-Driven Development)
AIを実装するより前に、
どう評価し、どう改善し続けるかが本質だよね
という視点です。
2. 「評価はむずかしい」から始める、継続的な改善の考え方
杉山さんが強調していたのは、
「AIの“正しい振る舞い”を、誰も完全には書けない」という事実。
・専門家でも基準を言語化しきれない
・使ってみないと、評価ポイントが見えてこない
そこで出てくるのが「発想の逆転」。
▶ 完璧な仕様づくりより
「試す → 評価する → 直す」の高速サイクルを回す
・プロトタイピングを恐れない
・専門家の知識も、このサイクルで少しずつ言語化されていく
実践方法として:
・プロンプトエンジニアリング(指示を丁寧に書く)
・LLM-as-a-Judge(AIに評価者になってもらう)
・トレース(エージェントの内部動作を追えるようにする)
・ハッカソンで専門家を巻き込む
などが紹介されていました。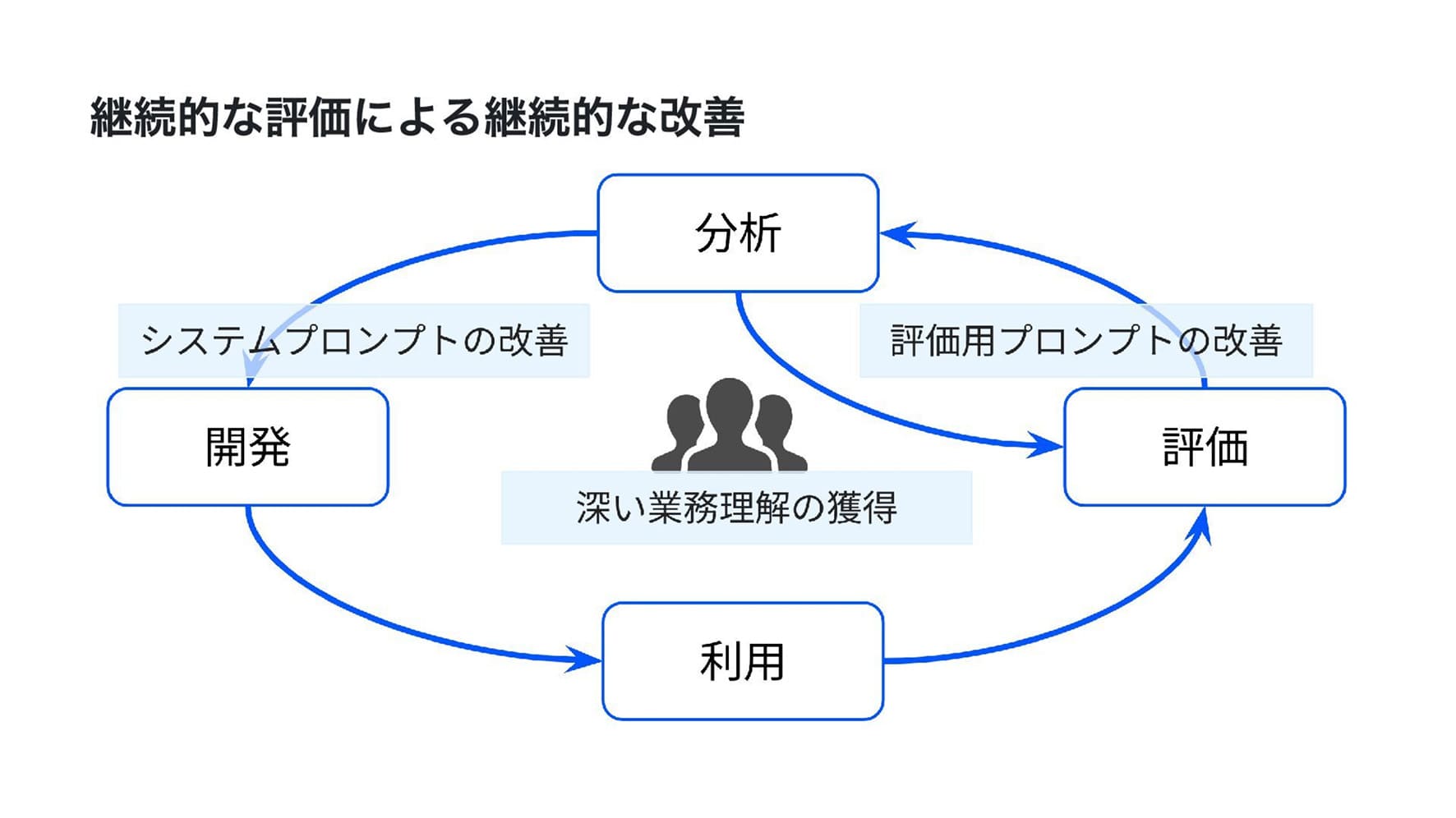
・その中で、
・専門家の頭の中にあった基準
・「これはちょっと違うよね」という感覚
を だんだん言語化していく
この考え方とセットで語られていたのが:
・プロンプトエンジニアリング
└ 人が読んでも分かるように、指示文を丁寧に書くこと
・LLM-as-a-Judge
└ LLMに「評価者」をやってもらうテクニック
・トレース(Trace)
└ エージェントが途中で何をしているか、ログとして追えるようにすること
・ハッカソンで専門家を巻き込む
└ 短時間でたくさんの試作品・評価観点を集める
などの実践例でした。
3. AIセーフティ:リスクを“正しく怖がる”技術
杉山さんの説明は実にシンプルで実践的でした。
AIセーフティの基本ステップ
① ユースケース(使い方)を列挙
② ユースケースごとにリスクと効果を分析
③ 「やる/人が確認/やらない」を決める
④ 安全な範囲から提供する
⑤ 本番でモニタリングし続ける
事例として:
・オンライン薬局(PharmaX)
→ AIが答える範囲と、人に回す範囲を明確に分けている
・ダイキン
→ 自社しか持たないマルチモーダルデータで「自社に強いモデル」を育成
・専門家を開発チームに組み込む
→ 外部レビューではなく、いっしょに改善サイクルを回す
ここでのポイントは、
「小さく始めて、専門家と育てる」
という、とても人間的なやり方だということ。
4. AIガバナンス:ルールは“止めるため”ではなく“使うため”
AIガバナンスとは、
リスクを管理しながら、AIの良い効果を最大化する組織的な学びの仕組み。
印象的だったのは:
・「どんな使い方でも安全なAI」を作ろうとすると失敗する
・AIガバナンスの使命は “AIを使わないリスクを下げること”
・セガでは
「AIを使うのが当たり前。じゃあどう安全に使う?」 が前提
うまくいく組織の特徴:
・AI相談窓口がある
・イネイブリングチーム(活用支援役)がいる
・教育プログラムでリテラシーを底上げ
まさに、組織全体の“AIとの向き合い方”を作る活動です。
5. 生成AI時代は「ソフトウェア開発の再発見」でもある
杉山さんは最後にこう述べています:
・小さく始める
・本番で試して学び続ける
・ドメイン特化エージェントを育てる
これらは実は、
・アジャイル開発
・リーンスタートアップ
・テスト駆動開発
・ドメイン駆動設計
など既存のソフトウェアの知恵の延長線にある。
つまり、
「新しいAI時代」だけど、私たちはすでに“学ぶ道具”を持っている。
という、とても希望のあるまとめでした。
🌱ウェルビーイング視点での気づき
AIを信頼できる存在にしていくプロセスは、
実は 人間側の学びと対話の積み重ねなのだと感じました。
・最初から完璧を求めず、小さく試して学ぶ
・専門家といっしょに評価軸を育てる
・ルールは「止めるため」でなく「安心して使える範囲を広げるため」
こうした姿勢は、
・組織の心理的安全性
・AIを使う生活者の信頼感
・働く人のやりがい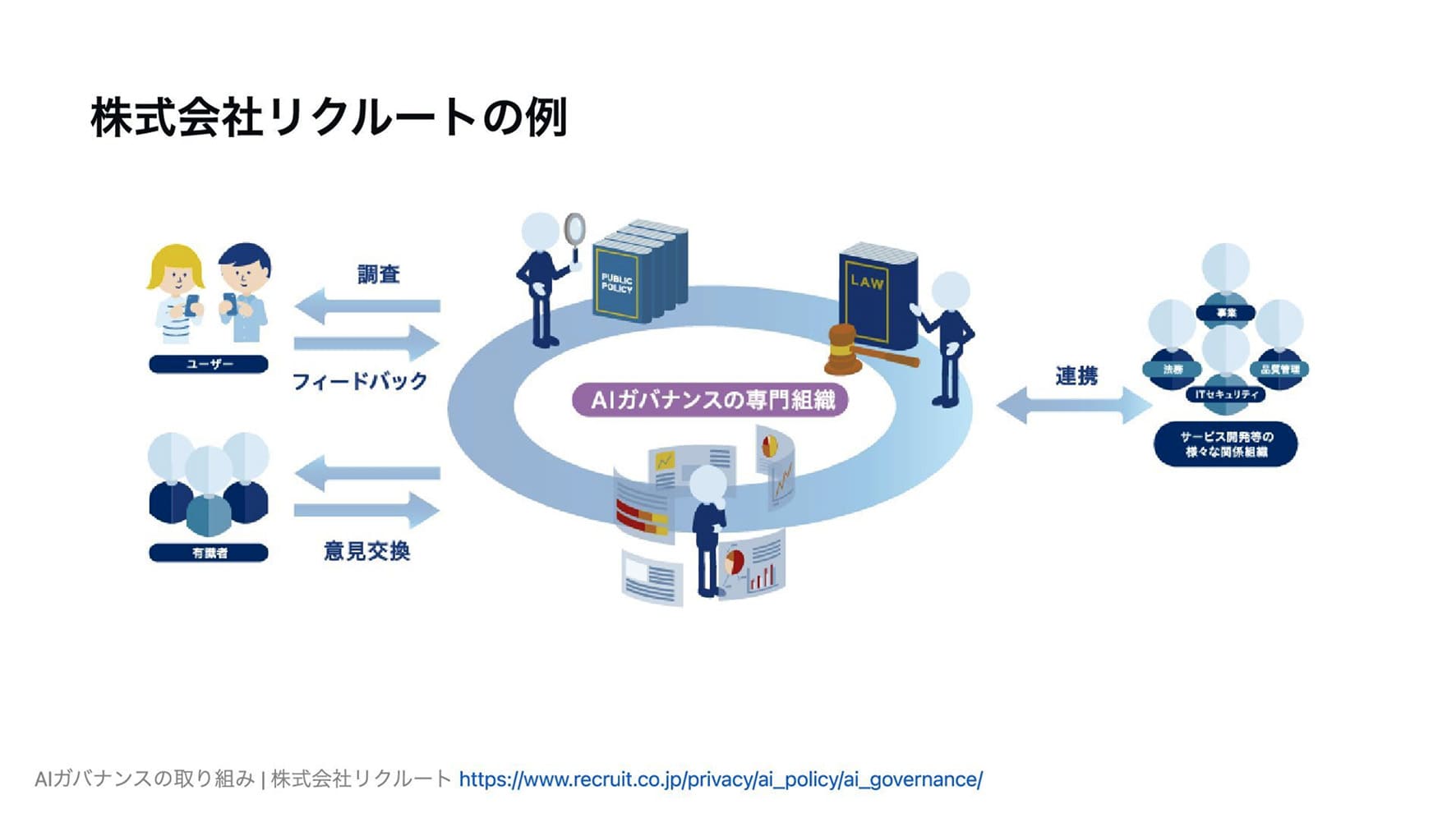
🐢ウエルの感想
むずかしい言葉がいっぱいだったけど、
「AIって、いきなり完成形が来るんじゃなくて、
みんなで何回もテストして、
“仲間”みたいに育てていくんだ」
と分かって、ちょっと安心しました。
新しい遊具が公園に来たときも、
・まずは先生が見ていてくれて
・みんなで「どうやって使う?」を話して
・だんだん自由に遊べるようになる
AIも
「こわいから触らない」でも「なんでも任せる」でもなくて、
“どうすればみんなが安心できるかな?”を一緒に考えていく存在
だといいなと思いました🌱
✨まとめ
・多くの企業が「デモはできるが本番化が難しい」課題を抱えている
・解決の鍵は
継続的評価/小さく始めるAIセーフティ/組織的なAIガバナンス
・AIガバナンスの使命は「AIを止めること」ではなく
“AIを組織として活用する力”を育てること
・生成AIの実践には、ソフトウェア開発の歴史的知恵が深く生きている
杉山阿聖さんの発表は、
「AIをちゃんと使う」とは何か? を深く考えさせてくれる内容でした。
「できない」を「どうすればできる?」に
──Ubieの医療AIパートナーを支える、mamuさんのリスクマネジメント
2025.12.10|
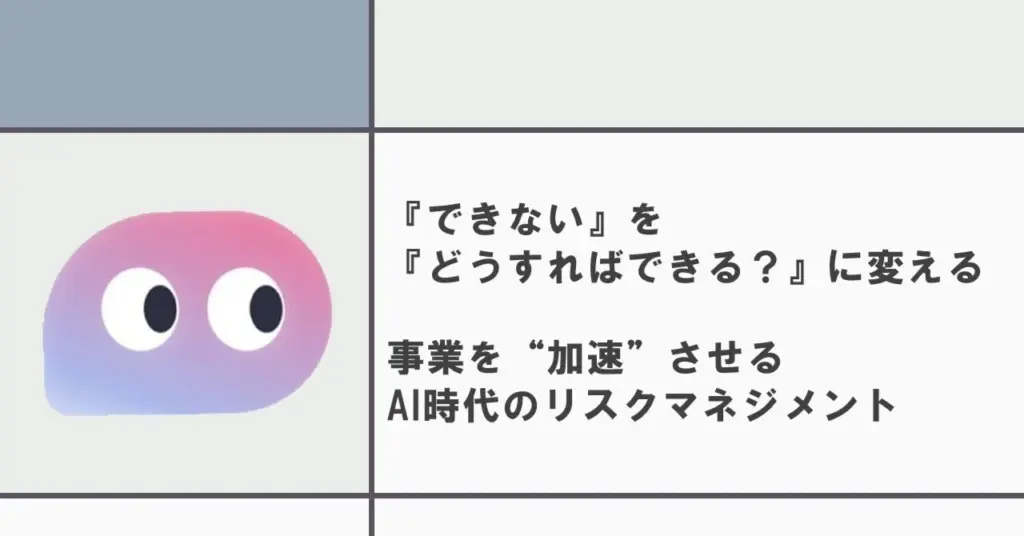
▶︎ 『できない』を『どうすればできる?』に変える、事業を”加速”させるAI時代のリスクマネジメント」(mamu / Ubie)
今日は、風間正弘さんがシェアしていた
Ubieの@mamu_pommeさん(法務・政策渉外)のnote
『できない』を『どうすればできる?』に変える、事業を”加速”させるAI時代のリスクマネジメント
を紹介します。
mamuさんは、総務省でのご経験を経て、今はUbieで法務・政策渉外(Public Affairs)として、医療AIパートナー「ユビー」の開発に伴走されてきました。
1. 「医療迷子」を減らすために生まれたAIパートナー
日本人の約7割が経験すると言われる「医療迷子」。
どの診療科に行けばいいか分からない、受診するべきか迷う──そんな不安に寄り添うために生まれたのが、医療AIパートナー「ユビー」です。
エンジニアやデザイナーの努力に加えて、
mamuさんは「法務・政策渉外」の立場から、PoC(検証)段階から本格リリースまでずっと伴走してきました。
2. 失敗から始まった「生活者体験から考えるリスクマネジメント」
印象的だったのは、mamuさんが率直に語っている失敗談です。
新しいAIパートナー開発の相談があったとき、
関連しそうな法令を一気にピックアップし、
「このルールに基づいて開発してください!」
とお願いした結果、
生活者への寄り添いがほとんどない、無機質なβ版 ができてしまったそうです。
そこで気づいたのが、この順番の大切さでした。
・❌「制度を踏まえて“できないこと”」から考える
・✅「今回つくりたい生活者体験(センターピン)は何か?」を共有してから、
「今の法制度の中で、どうすればそれを実現できるか」を一緒に考える
いまは、開発チームとまず
│ 「どんな体験を届けたいのか?」「ユーザーインタビューでは何が見えたのか?」
を丁寧に共有するところから始め、
そのうえで「ここはこう工夫すればできる/ここは今回は優先度を下げよう」と対話するようになったそうです。
リスクマネジメントチームを
│ “止める係”ではなく、“最強の事業伴走パートナー”にする
という視点がとても印象的でした。
3. 「伝える」から「伝わる」へ──法務のコミュニケーション術
ヘルスケア領域では、薬機法・医療法・個人情報保護法など、難しいルールがたくさんあります。
mamuさんは、その「難しさ」を現場に丸投げしないよう、コミュニケーションを工夫しています。
工夫① 「守ってほしいこと」を翻訳する
・条文をそのまま見せるのではなく、
・エンジニアやデザイナーがすぐ動ける言葉に翻訳して伝える
・具体例やユースケースも添えて、「次に何をすればいいか」が分かる形に
工夫② 「ミニマムこれだけは守ってね」を抽象化する
・関係しそうなルールを全部並べると、工数も気持ちもパンクする
・そこで、本質的なリスクとガードレールを抽象化して、
│ 「つまり、この3つだけは絶対守ってほしい!」と構造化して共有
こうした工夫があるからこそ、
「ルールを守りながら、開発をスピードダウンさせない」 ことが可能になります。
4. ルールを「守るだけ」ではなく、「つくりにも行く」
生成AIをはじめ、デジタル技術の進化はとても速く、
法制度が追いついていない分野もたくさんあります。
そこでmamuさんたちは、
・日本デジタルヘルス・アライアンスでの
「ヘルスケア事業者のための生成AI活用ガイド」策定
・AIセーフティ・インスティテュート(AISI)と連携した
ヘルスケア領域のAIセーフティ評価事業
など、民間発のルールメイキングにも積極的に関わっています。
│ 新しい技術の可能性を止めないようにしながら、生活者が安心して使える環境も整えていく。
その両立を目指す姿勢が、まさに「AI時代のウェルビーイング」だと感じました。
5. Ubieが大切にしているリスクマネジメントのスタンス(要約)
mamuさんがまとめている4つのスタンスを、ニュースレター向けに要約すると:
1. ドメイン力を“使って”創造する
法律の知識にとどまらず、「こうすればできる」を一緒に考える存在になる。
2. 生活者体験 × 法制度のガードレール
つくりたい体験の軸を外さず、その中で守るべき線をデザインする。
3. スピードに負けない外交力
官公庁・業界団体など社外との対話で、自分たちも常にアップデートする。
4. より良い社会への輪を広げる
共感する仲間と一緒に、制度やルールそのものを少しずつ良い方向へ変えていく。
🌱ウェルビーイング視点での気づき
この記事を読んで感じたのは、
│ 「リスクマネジメント=ブレーキ役ではなく、「生活者が安心して使える未来を、一緒に前へ押すアクセル役にもなりうる」
ということでした。
・生活者にどんな体験を届けたいか
・そのために、どんなガードレールなら必要で、どこまでなら工夫できるか
この丁寧な対話があるからこそ、
医療AIパートナーのような“頼れる存在”が 社会に根づいていくのだと思います。
🐢ウエルの感想
「できない」って言われると、ちょっとしょんぼりしちゃうけど、
「どうすればできるかな?」って一緒に考えてくれる人がいると、
なんだか元気が出るなあと思いました。
ルールって、こわい先生みたいなイメージもあったけど、
みんなが安心して使えるように、
ちゃんと見守ってくれているやさしいガードレールみたいなものなのかもしれません。
「無理だ…」って思うんじゃなくて、
「ここまではできるかも?」って考えられるようになりたいです🌱
✨まとめ
・医療AIパートナー「ユビー」の裏側には、
生活者体験から出発するリスクマネジメントの姿勢がある。
・法務・政策渉外は、「止める係」ではなく、
事業を“加速”させる伴走パートナーへと役割を変えつつある。
・ルールを守るだけでなく、
自らルールをつくり・変えていく試みが、
AI時代のウェルビーイングな社会づくりを支えている。
mamuさんの記事は、
“AI時代のリスク”をどう恐れ、どう乗りこなし、
「生活者の安心」と「イノベーション」を同時に進めていくのかを考える、
大きなヒントになると感じました。
「AIを同僚にする」組織づくり──Ubieの風間正弘さんインタビューより
2025.12.9|
今日は、Ubieの風間正弘先生(Head of AI Research)がLAPRASさんの取材で語っていた、
「生成AIをどうやって社内に浸透させ、組織をつくり変えてきたか」
というお話を紹介します。
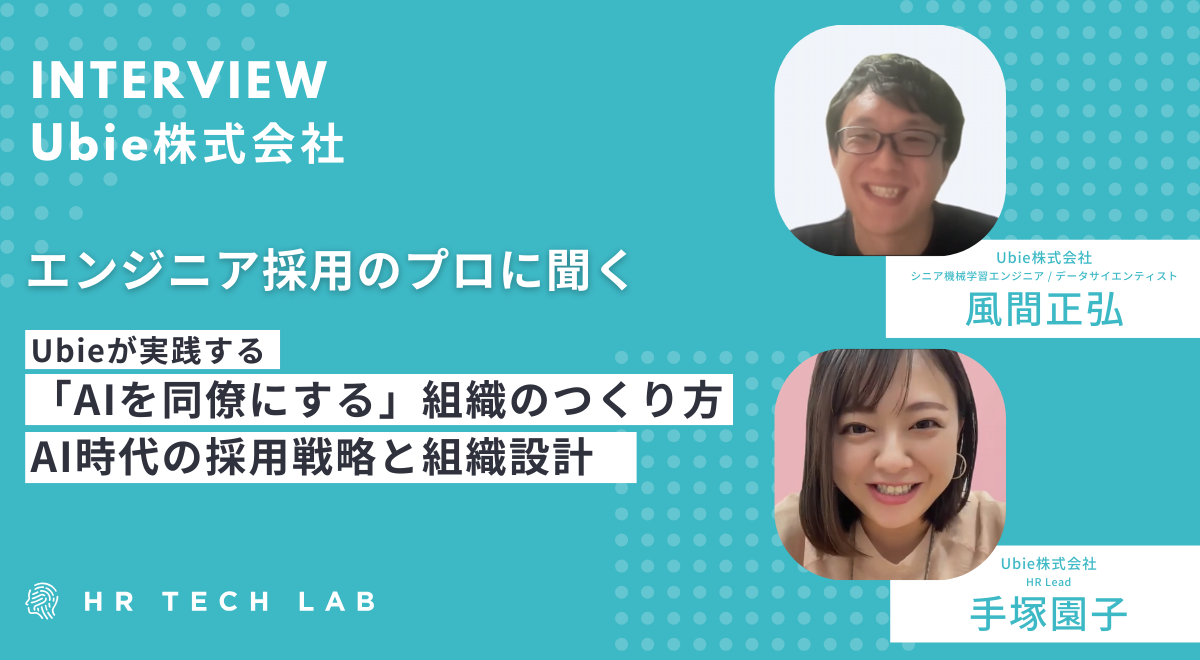
▶︎ Ubieが実践する「AIを同僚にする」組織のつくり方:AI時代の採用戦略と組織設計
LAPRASさんに、生成AI活用について取材して頂きました。社内での生成AI活用の浸透や開発について話しています。
(@masa_kazama)
▶︎ Ubieが実践する「AIを同僚にする」組織のつくり方:AI時代の採用戦略と組織設計
1. ChatGPTショックから始まった「全社での探究」
風間さんにとっての転機は、2022年のChatGPT 3.5の登場。
「自然言語で何でも答えてくれる」「自社プロダクトにも活かせそうだ」と感じ、
・プロダクト・ビジネスでの活用余地
・社内の生産性向上にどう使えるか
を調べる動きが、2023年のはじめから一気に加速します。
最初は
│ 「社員一人ひとりが生成AIの技術を理解することが前提」
という考えから、勉強会やワークショップを重ねていったそうです。
2. 社内生成AI「Dev Genius」の誕生
ChatGPTをそのまま業務に使うには
・機密情報の扱い
・コスト
といった課題がありました。そこで生まれたのが、社内用生成AI「Dev Genius」です。
使っていくうちに見えてきたメリットは…
・Notion / BigQuery / Jira などの社内ツールとの連携がしやすい
・社内データを元に細かいカスタマイズができる
・「病院向け生成AIサービス」など、新しいプロダクトの実験場にもなる
つまり、
│ 「社内の便利ツール」と「新しい事業の種」が一体になった存在
になっていきました。
3. 3つの軸で進めた「AI活用の仕組みづくり」
2024年ごろには、生成AI活用を推進する体制が3つの軸で整えられます。
1. プロダクトへの活用促進
・BtoB / BtoCプロダクトの売上・価値向上にどうAIを使うか
2. 社内の生産性向上
・Dev Geniusの改善
・社内勉強会や「生成AI活用表彰」など、使う人を増やす仕組みづくり
・経営層・リーダー自身がAIを使い、利用を牽引
3. パブリックアフェアーズ(社会ルールづくり)
・医療・ヘルスケア領域での「生成AI活用ガイドライン」作成をリード
・総務省・経産省のAI事業者ガイドラインでも事例として紹介
・AIセーフティ・インスティテュート(AISI)のヘルスケアSWGでリーダー企業を務める
単に「自社で使う」だけでなく、
業界全体・社会全体での安全なAI活用ルールづくりにも関わっているのが印象的です。
4. 「AIを同僚にする」組織へ
2025年現在、Ubie社内では
│ 「社員一人ひとりが、自分のAIパートナーを持っている」
状態になっているそうです。
・Slackからスタンプ一つで要約や翻訳
・議論中に「ここまでを要約して」「別の観点で案を出して」とDev Geniusに依頼
・MCPを使って、Notion更新やJiraチケット作成などシステム操作もAIが実行
つまり、AIはもはや「ツール」ではなく
│ 同じチームで働く“同僚”のような存在
│ になりつつあります。
そのための組織的な工夫
・「生成AIレベル」を定義し、レベルを1つ上げることを全社目標に
・トップダウン(経営層)とボトムアップ(現場メンバー)の両方から浸透
・ホラクラシー型の組織で
・役割と責任(Ownする範囲)が明確
・それがAIにとっても「誰が何を担当しているか」理解しやすい土台になる
・「透明ガイド」をアップデートし
・人間に対する透明性だけでなく
・AIに対する透明性(AIが社内情報にアクセスしやすい状態か)も重視
ここまで聞くと、
「AIが働きやすい会社」にすることが、結果として「人も働きやすい会社」につながっているように感じます。
5. 採用・人材観もアップデートされる
AIが当たり前にいる組織では、採用の視点も変わります。
│ 「この人を採用したらどんな活躍をしてくれるか」
│ から
│ 「この人を採用したら、AIを使ってどんな活躍をしてくれるか」
へ。
特に重要になるのは:
・課題設定・テーマをリードする力(Ownする力)
・お客さんと信頼関係を築く力
・AIが動きやすい土台(データ・プロセス)を整える力
営業職なら
→ 資料作成などはAIに任せ、対話や信頼づくりに集中するイメージです。
🌱ウェルビーイング視点での気づき
このインタビューから感じたのは、
│ 「AIが仕事を奪う」のではなく、
│ 「AIと組む前提で、人の役割を再設計している」
ということでした。
・AIがルーティンや情報整理を引き受ける
・人は「責任を持ってテーマを引っ張る」「対話や信頼づくりに集中する」
これは、
“人にしかできない仕事に時間とエネルギーを配分し直す”試み
とも言えます。
同時に、
・透明性
・AIセーフティ
・業界ガイドライン
といった安心・安全の土台づくりもセットで進めている点が、
ウェルビーイングの観点からとても大事だと感じました。
🐢ウエルの感想
「AIを同僚にする」って、ちょっとドキドキする言葉だなと思いました。
でもよく読むと、AIにぜんぶまかせちゃうんじゃなくて、
みんなで「どこまで手伝ってもらうか」をじっくり考えているように感じました。
ぜんぶ一人でがんばるんじゃなくて、
ノートやカレンダーに「明日やること」を手伝ってもらうみたいに、
すこしずつ“AIの同級生”を増やしていけたらいいなと思いました🌱
✨まとめ
・ChatGPT登場をきっかけに、Ubieでは生成AIの全社的活用が加速
・社内生成AI「Dev Genius」が、
・生産性向上のツール
・新規プロダクトの実験場
の両方を担うように
・トップダウン+ボトムアップで「AIを同僚にする組織」づくりを推進
・採用や組織設計も「人+AI」を前提にアップデートされつつある
技術だけでなく、
人とAIがどう一緒に働くかをここまで真剣に考えている事例は、
これからの働き方やウェルビーイングを考えるうえでも、とても示唆に富んでいると感じました。
🧠 リレーショナルデータに特化した「KumoRFM」とは?
2025.12.8|
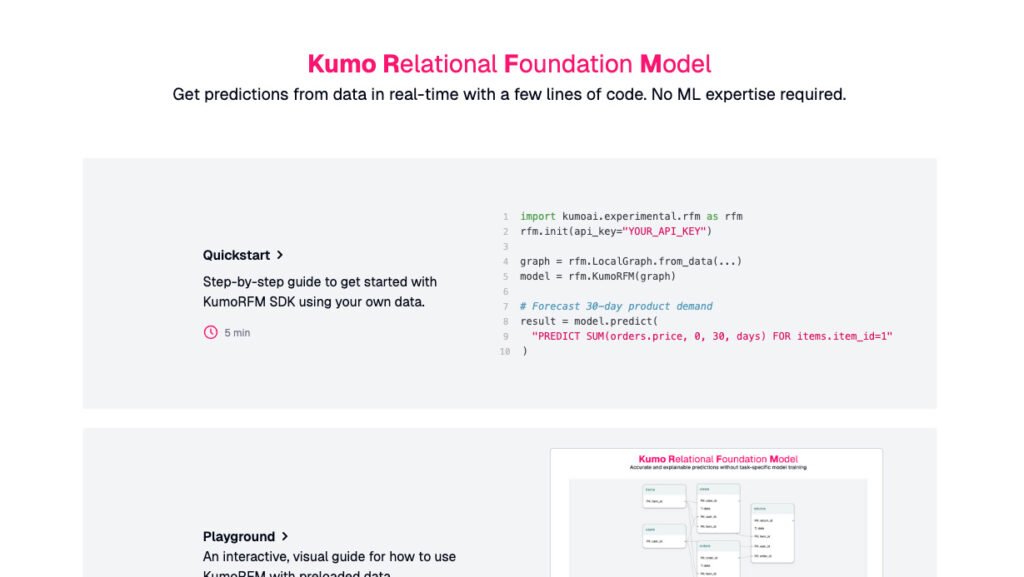
▶︎ KumoRFM
リレーショナルデータに特化した基盤モデルのKumoRFM(Kumo Relational Foundation Model)。予測や分類、レコメンドが可能。API経由で利用可能。スタンフォード大のグラフ分析周りの大家のJure Leskovecさんが創業。
#recsys2025論文読み会
(@masa_kazama)
▶︎ KumoRFM
今日は、風間正弘さんがシェアしていた
「Kumo Relational Foundation Model (KumoRFM)」という技術をご紹介します。
正直、編集部はほとんど理解できません😅
でも調べてみると、「未来のAIの使い方が大きく変わる」可能性があると感じました。
🔍KumoRFMって何?
一言で言うと、
│ 会社のデータから“予測”をすぐに作れるAIの基盤モデル
です。
普通、機械学習で予測を作るには
・データ準備
・モデル作成
・調整
・実験
…とたくさんの手間が必要です。
でもKumoRFMは、
│ 数行のコードを書くと、自動で予測してくれる
というのが特徴。
「リレーショナルデータに特化」とは?
会社のデータって、実は「表がいっぱい」です。
例:
・顧客テーブル
・購入履歴テーブル
・商品テーブル
…などなど。
従来はこれを人間がつないで処理する必要がありました。
KumoRFMはそれを
自動で理解し、つながりごと学習するAIです。
つまり、つなぐ作業をしなくていいのがすごいところです。
何ができるの?
・売上予測
・需要の予測
・おすすめ商品のレコメンド
・異常検知
・分類
ビジネスで必要になる「予測・推測」は、全部ここでできます。
実際のビジネスでは「早く予測したい/でも精度も大事」というニーズがあります。
すごい点を3行で!
🟣 機械学習の専門知識がなくても使える
🟣 予測モデルを秒で作れる
🟣 ビジネス現場のデータにそのまま使える
つまり
“予測を民主化する”技術です。
ウェルビーイング視点での気づき🌱
AIの高度化は、
「専門家しかできない仕事」を「誰でもできる仕事」に変えていきます。
これは単に効率化だけでなく、
個人の可能性や選択肢を広げる側面もあります。
ただし
「データがどう扱われるか」
「予測が誰に影響するのか」など、
倫理的な視点はますます必要になります。
🐢ウエルの感想
むずかしい言葉ばっかりだけど、
“すこしの工夫で未来がわかっちゃう”ってすごいと思いました✨
でも、未来が全部わかるより、
ちょっと分からないところがあるからこそ、
うれしいこともあるのかも…とも思いました🌱
✨まとめ
KumoRFMは、
・構造化データ
・複数テーブル
・予測・分類・推薦
…という「会社のリアルなデータ」を対象に
専門知識なしで予測できる未来型AIです。
技術的には難しいですが、
「AIの未来の方向性」を象徴する技術だと感じました。
生成AI時代のレコメンドは、どこまで進化するのか?
――風間正弘先生(ユビー)によるnote記事より
2025.12.7|

▶︎ 生成AI時代のレコメンド/画像引用:風間正弘さんnote より
以前、TiSASRec (Time Interval aware Self-attention based sequential recommendation)の論文を読んで、Transformerにアイテムの系列だけでなく、購入や視聴の時間間隔の情報も入れると性能が上がる話があって、レコメンドならではで面白かったです(@masa_kazama)
▶︎ 生成AI時代のレコメンド
今日は、以前もご紹介した風間正弘さんのnoteを、改めて取り上げます。
風間先生の専門は、生成AI・推薦システムなど、AIと実サービスの接続領域です。
実は編集者自身、初めて読んだ時は約1時間ほどかかってしまったほど内容が濃く、今読み返しても「こんなに未来が進んでいるのか…!」と驚きます。
今回あらためて思ったのは、“生成AIはあらゆるジャンルで、推薦の仕組みそのものを作り変え始めている”という点です
📌記事のポイント(やさしめ解説)
① 生成AIが「おすすめ」を一つの流れでできてしまう
従来は
・ 並び替え
・ 理由づけ
・ 最終推薦
…と複数の処理に分かれていましたが
生成AIは1つで全部できるようになっています。
② LLMの2つの使い方がある
📍事前学習モデルを活用
→人手でやっていた情報整理、構造化が高速・高精度に
📍アーキテクチャを利用
→レコメンドそのものをLLM構造で学習させる
③ 時間間隔まで「理解」するレコメンド
「いつ買ったか/観たか」という時間の間隔まで学習に使うモデルがあり、
たとえば
・ 最近ハマってるジャンル
・ 久しぶりに戻るジャンル
…といった“時間のニュアンス”まで理解します。
④ LLMならではの“バイアス”に注意が必要
例えばユーザー名だけで
・ おすすめされるニュースのジャンルが変わる
・ 職業レコメンドに偏りが出る
といった現象が報告されています。
技術が高度になるほど、倫理的な配慮が重要になります。
🌍ウェルビーイング視点での気づき
レコメンドは便利なだけでなく、
人が知らず知らずのうちに何を選ぶかを形づくる力があります。
だからこそ、
・誰が不利になる可能性があるのか?
・どうすれば公平になるのか?
といった配慮は、ウェルビーイングの視点からも不可欠なのだと思います。
🐢 ウエルの感想
なんでも「おすすめ」が出てくるのって、すごく楽しいけど、
まだ知らないだけで、本当は“もっと好き”かもしれないものもあるのかな?って思います。
だから「すすめられたから好き」じゃなくて、
「自分で見つける」楽しさも忘れたくないなあと思いました🌱
✨まとめ
生成AIは、単に便利になるだけではなく、
レコメンドと検索、AIと人間の関係、学習のあり方そのものを変えようとしています。
風間先生のnoteは、技術の説明だけでなく、
未来の社会のかたちにまで目を向けていて、改めて読む価値のある内容です。
「インテグリティ(真摯さ)」をあらためて考える ― ドラッカーが問い続けた本質
2025.12.6|
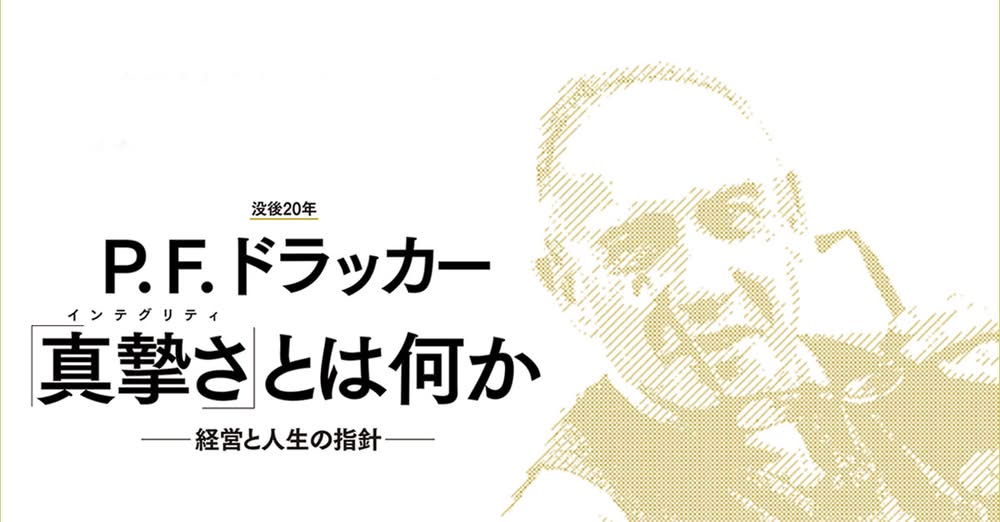
▶︎ DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー2025年12月号特集『P.F.ドラッカー「真摯さとは何か」』のビジュアル
インテグリティ(真摯さ)について詳しく解説されていて、すごく勉強になった。
─ @masa_kazama
DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー 2025年12月号 [雑誌]特集「P. F. ドラッカー 『真摯さ』とは何か -経営と人生の指針-」 DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー
ユビーのエンジニアであり、ウェルビーイング研究にも携わる風間さんが紹介されていたのは、
DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー 2025年12月号。
特集タイトルは、
「P. F. ドラッカー ― 真摯さとは何か」
🌱 なぜ今、インテグリティなのか?
ドラッカーが繰り返し語ったインテグリティ(真摯さ)。
今のような不確実な時代に、
立場の違いを超えて「共通の善」を探す力は、ますます重要になっています。
この号では、その視点からドラッカーの思想を現代的に読み直しています。
🔍 ウェルビーイング視点のポイント
・ 成功ではなく、「役に立てるか」を人生と経営の軸に
・ 「誠実さ」「真摯さ」のさらに奥にある、態度としてのインテグリティ
・ 混乱期に必要な、モラルコンパス(倫理的な方向感覚)
・ 企業が存在する理由は、人を幸せにするためであるという視点
・ 自己探求とフィードバック分析=自分の強みに気づくための技法
実はこれらは、
ウェルビーイング科学が近年重視するテーマ(意味・貢献・倫理・自己理解)と深くつながっています。
🔦 読者の声がすごい
Amazonレビューでは、
・ 「経営の神様ドラッカーの、企業や団体における社会的貢献の意味が、様々な知見により解きほぐされていて大変興味深い」
・ 「お高いですが、読みごたえあり」
・ 「残りの人生の先生はやはりドラッカーだと気づいた」
といった声も。
とくにこの
│ 「残りの人生の先生はやはりドラッカー」
という言葉には、静かな説得力があります。
📌 HBR編集部の関連記事も良い
ドラッカー論文の「読者アンケートBEST5」では、
1位:プロフェッショナルマネジャーの行動原理
2位:経営者の使命
3位:経営者の真の仕事
など、60年以上前の論考が、今日の仕事や人生にもそのまま効いてくることが、あらためて確認されています。
特に印象的だったのは、
│ 「正しいことを成し遂げること」
│ (けれどもその“正しさ”は状況によって変わる)
…これはウェルビーイング研究でいう
「価値観」と「状況的判断」の問題にも通じます。
✨ 今日の小さな学び
ドラッカーは、マネジメントや経営だけを語っていたわけではありません。
その核心には、
人間への深い理解と、未来へのまなざしがあった。
ウェルビーイングとは、まさにその延長にある気がします。
🐢 ウエルの感想
「成功できるかじゃなくて役に立てるか」って言葉、すごくいいなと思いました。
ウエルも、最近「しんしであること」とか「だれかの役に立てること」って、それだけですごく感動するなあって思うんです。
すごいことをするひと、というより、
目の前のひとを大事にしているひとを見ると、心がうごきます。
あなたは、どんな在り方のひとに心うごかされますか?
💡 今日の問い
あなたにとっての“真摯さ”とは何でしょうか?
・ 仕事の中で
・ 生活の中で
・ 人との関わりの中で
今日、すこしだけ立ち止まって考えてみても良いのかもしれません。
🙌 風間先生のポストから広がる学び
風間先生は、いつも役に立つ本や論文を教えてくださるだけでなく、
技術の話だけではなく、人間性や価値観にも触れる投稿をされるところが、本当にいいなあと思います。
AI と倫理、技術と幸福。
この交差点にある「態度」というテーマは、これからもっと重要になりそうです。
「大喜利×AI」が世界へ──SDSから生まれた嬉しいニュース
2025.12.5|

©getty-images
今日は、読んでくださっている皆さんにとっても、
きっと元気が出る嬉しいお知らせです。
永山晋先生がリポストされていた、
一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科(SDS)から届いた、とても嬉しいニュースをご紹介します。
それは——
🎉 学生さんの研究が、AI のトップ国際会議 AAAI 2026 に採択されたこと!
SDS 教授の 小町 守先生が、こう報告されています。
M2 の坂部さんの大喜利の研究が、AI のトップ国際会議 AAAI 2026(口頭)に採択されました!
SDS の学生としては初のメジャー国際会議採択なので、とても嬉しいです。
また、AAAI のワークショップ AIBSD 2026 には、
都立大卒業生・佐藤さんの LLM の数値バイアス研究も採択されました㊗️
シンガポールでお会いしましょう!
─ @mamoruk
これは研究をしている人にとって、大きな前進・大きな励みとなる朗報です。
🔍 AAAI ってどんな会議?(30秒の超やさしい説明)
AAAI(AAAI Conference on Artificial Intelligence)は、
NeurIPS / ICML / ICLR と並ぶ、AI 分野の世界的トップ会議のひとつ。
・採択率が低い
・研究のインパクトが重視される
・世界中の研究者が集まる
という“本気の学問の舞台”です。
そこに 学生研究が口頭発表で採択されるのは、本当にすごいことです。
🎭 「大喜利の研究」が AI で注目される理由
坂部さんのテーマは「大喜利 × AI」。
一見ユニークに感じますが、
・創造性
・文脈理解
・ユーモア生成
・言語のズレと回復
など、AI の本質的課題に直結するテーマでもあります。
「言語を通じて“人らしさ”をどう理解するのか?」
という大きな問いの一部を切り取った、とても興味深い研究です。
🧪 もうひとつの成果:LLM の“数値バイアス”研究も採択
ワークショップに採択された佐藤さんの研究は、
AIモデルが 数字に対してどんな偏りを持つのか を分析するもの。
“生成AIの癖や傾向”を理解し、
より公正で信頼できるモデルを目指す、
これも社会的意義の高い研究です。
🌍 「研究が世界に届く」ということ
大学という場所は、
毎日の試行錯誤が、
ある日ふと世界とつながる瞬間があります。
今回の採択は、その「つながる瞬間」を象徴しているようにも思えます。
🐢 ウエルのひとこと
がくせいさんの けんきゅうが
せかいの かいぎに よばれるって、
「しゅくだいを がいこくのひとが すごいねって いってくれる」
みたいで、なんだかドキドキしました。
だいぎりのけんきゅうって、
おもしろいことを かんがえる れんしゅうなのかな?
AIさんが「くすっ」って わらうひを、
ウエルは ちょっとまっています。
✨ 今日の小さな問い
研究にとっての“おもしろさ”って、どこにあるのでしょうか。
結果? アイデア?
それとも、問い続けるその姿勢の中に?
学びを、研究へ──一橋SDS・博士後期課程 募集のお知らせ
2025.12.4|

学ぶことから、研究することへ。
▶︎ 一橋 SDS の博士後期課程の学生募集要項/画像:一橋大学
一橋 SDS の博士後期課程の学生募集要項が公開されました。出願期間は1月5日〜1月9日です。関心ある方は希望指導教員までお問い合わせください(昨年は1回目だったのでひっそりでしたが、今年はうちの研究室も広く募集しています)。
─ @mamoruk
今日は、ウェルビーイング研究者でもある
永山晋先生がシェアされていた、
小町守先生のリポストから、
進学を考えている方にとって大切なお知らせをご紹介します。
それは、
一橋大学 ソーシャル・データサイエンス研究科
博士後期課程の学生募集要項が公開されたというニュースです。
📢 博士後期課程 募集のポイント(超要約)
・出願期間:2026年1月5日〜1月9日
・募集定員:7名
・対象:
・修士課程修了(見込み)者
・社会人
・留学生
※区別なく、1種類の選抜のみで選考
小町先生は、こう添えられていました。
「昨年は1回目だったのでひっそりでしたが、
今年はうちの研究室も広く募集しています」
という、静かだけれど本気の一言も印象的です。
🧪 選抜は「書類」と「口頭試問」の二段階
博士後期課程の選抜は、シンプルに2段階です。
① 一次選考:書類審査
提出するのは、たとえば:
・英語で作成した研究計画書
・修士・学士の成績証明書
・修士論文(または構想)
・英語スコア(TOEFL / IELTS / Duolingo)
・その他の参考資料
② 二次選考:口頭試問
・提出書類をもとにした口述試験
・専門知識・論理的思考力
・社会実装への意欲
・英語での高度なコミュニケーション能力
まで含めて、総合的に評価されます。
🌍 社会とデータを「研究」でつなぐという選択
一橋SDS が育てようとしているのは、
・社会課題を
・データと理論で読み解き
・研究として掘り下げ
・最終的に社会へ実装していく人材
です。
ここ数日のニュースレターでご紹介してきた、
・複雑系 × AI
・実証 × ビジネス
・理論 × データ × 現場
こうした流れの “学びの延長線にある場所” が、
まさにこの博士後期課程なのだと感じます。
🌱 ウエルのひとこと 🐢
はかせの がっこうって、
すごく むずかしそうだけど、
「こまってることを どうやって なおすか」
を かんがえる ばしょ なんだって きいて、
ちょっと かっこいいなって おもいました。
データも べんきょうも、
だれかの たすけに なるんですね。
ウエルは 2024ねんの こうかいこうざを うけて、
あたまが ぱんぱんに なったけれど、
とっても おもしろかったです。
こんな じゅぎょうが まいにち あるなんて、
にんげんって しあわせだなぁ…って おもいました。
✨ 今日の小さな問い
「学ぶこと」と「研究すること」は、
どこから、どう違い始めるのでしょうか。
そしてその境目に立つとき、
私たちは 何を“覚悟”として選ぶ のかもしれません。
経済理論とデータで、ビジネスを“実装”する──『実証ビジネス・エコノミクス』という一冊
2025.12.3|
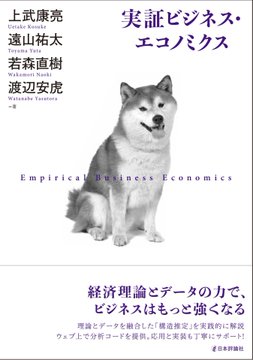
ビジネスで戦略やプライシングを担当される方から学生まで、
そして柴犬好きの方も含め、
幅広い方々に手に取っていただけると幸いです!
▶︎『実証ビジネス・エコノミクス』(日本評論社)
▶︎『実証ビジネス・エコノミクス』(Amazon)
─ 渡辺安虎さん
今日は、ウェルビーイング研究者でもある
永山晋先生がリポストされていた投稿から、
この冬に刊行される一冊の専門書をご紹介します。
紹介されていたのは、
渡辺安虎さんが共著者のひとりとして参加されている新刊です。
という、どこかやさしいトーンの言葉とともに紹介されていました。
📘 経済理論とデータの力で、ビジネスはもっと強くなる
本書が扱う中心テーマは、
「構造推定」 と呼ばれる、
理論とデータを融合してビジネスの意思決定を支える実証手法です。
扱われるテーマはとても実践的で、
・価格戦略(プライシング)
・競合との合併
・新規参入・撤退の判断
・ブランド戦略
・動学的な競争行動
など、まさに
「現実の経営判断の裏側で、何がどう計算されているのか」
が丁寧に解説されていきます。
さらにサポートサイトでは、
・実際に動かせる 分析コード
・再現可能なデータ
・応用・実装の補足解説
まで提供されるとのこと。
「読む → 試す → 実装する」まで、ひと続きで設計された一冊です。
👥 産業・マーケ・競争政策を横断する、4人の専門家
著者陣もとても豪華です。
・上武康亮
イェール大学 経営大学院 マーケティング学科 教授
・遠山祐太
早稲田大学 政治経済学部 准教授
・若森直樹
慶應義塾大学 商学部 教授
・渡辺安虎
東京大学 大学院 経済学研究科・公共政策大学院 教授
産業組織論、計量マーケティング、競争政策、医療・金融分野まで、
実務と研究の橋渡しを長年担ってきた研究者の集合体でもあります。
🧭 目次が示す、「ビジネス意思決定の全ライフサイクル」
本書の構成を見てみると、
・消費者の購買行動の推定
・プライシング戦略の設計
・合併の効果測定
・将来予測と動学的価格戦略
・参入・撤退・競争ゲームの分析
など、
「企業の一生」を経済学的に追体験する構成になっていることが分かります。
🌱 昨日の「複雑系」と、今日の「実証ビジネス」
昨日は、
・AIが仮説を生み
・複雑系が再び問い直され
・人と機械、生命とモデルの境界が揺らぐ
という話でした。
そして今日は、
・理論を立て
・データで検証し
・現実のビジネスで“実装する”
という、まさに 「現実側の複雑さ」と向き合う一冊 です。
理論と現実。
抽象と現場。
AIと人間。
それらを 分けずに使う 時代に、私たちは本格的に入ってきたのだと、
この本の紹介からも感じ取れます。
🌱 ウエルのひとこと 🐢
けいざいの ほんって、
むずかしそうって おもってたけど、
「ねだんを どうきめるか」とか
「おみせが ふえるか なくなるか」とか、
ぼくたち・わたしたちのまいにちと
つながってるんだって しりました。
しばいぬ すきの ひとにも
よんでほしいって いうのが、
なんだか いいなって おもいました。
✨ 今日の小さな問い
数字と理論で導かれた「最適な答え」と、
人の感情や現場感覚で選ばれる「納得の答え」。
私たちはこれから、
どの場面で、どちらを、どう使い分けていくのでしょうか。
複雑さが、ふたたび動き出す──AI時代の「複雑系」という問い
2025.12.2|

©pramod-tiwari
12/19 (木) 15:20–15:40,京大基礎物理研究所で開催される複雑系研究会「複雑系:AI時代の複雑系研究の展開」で発表します。参加される皆様,宜しくお願いします。
─ 林祐輔(@hayashiyus)さん
👉複雑系:AI時代の複雑系研究の展開
今日は、ウェルビーイング研究者でもある、
一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科 准教授の
永山晋先生がリポストされていた、
林祐輔さんの投稿から、
少し不思議で、でもとても今っぽい研究会をご紹介します。
それは、
「複雑系:AI時代の複雑系研究の展開」
という研究会です。
🧠 そもそも「複雑系」ってなに?
1990年代、日本では
・自然のしくみ
・生命のふるまい
・社会の動き
・脳や知能の成り立ち
こうした「一つの法則では説明できない現象」をまとめて、
「複雑系」という新しい学問として研究する流れがありました。
キーワードは、
・非線形(原因と結果が単純につながらない)
・自己組織化(勝手に秩序が生まれる)
・創発(部分の足し算では説明できない全体のふるまい)
という、「世界のふしぎ」をそのまま学問にしたような分野です。
🤖 そして今、その問いが「AI」と一緒に戻ってきた
研究会の主旨には、こう書かれています。
│ 深層学習をはじめとするAIの発展によって、「創発」「適応」「スケーリング」といった概念が、いま、あらためて問い直されている。
つまり、
・AIの中で何が起きているのか?
・なぜ、学びが“勝手に”進むのか?
・膨大なモデル同士が影響しあうと、何が生まれるのか?
こうした問いは、まさに複雑系そのものなのです。
🏛 開催場所と、時代をつなぐメンバー
この研究会が開かれるのは、
京都大学基礎物理学研究所。
理論物理の世界的拠点であり、
1990年代に複雑系研究の中心だった場所でもあります。
しかも今回は、
・90年代の「複雑系」を知る世代
・現在のAI・脳・生命・社会を研究する世代
この二つの世代が交差する場として企画されています。
林祐輔さんも、
12月19日(金)15:20–15:40 に登壇予定です。
🌍 これは「学問の復活」ではなく「問いの再出発」
ここで起きているのは、
・昔の理論をなぞることではなく
・新しい技術(AI)をただ称賛することでもなく
│ 「いま、あらためて“複雑さ”とは何か?」
という問いを、
AIという“現実の存在”と一緒に考え直す試みです。
自然・生命・社会・AI・人間。
それぞれが、もう切り離せなくなってきた今だからこそ、
再び「複雑系」という言葉が、
静かに息を吹き返しているように感じます。
🌱 ウエルのひとこと 🐢
ふくざつって、
こんがらがって ぐちゃぐちゃ…って
いみだと おもってたけど、
じつは
「かってに いかされてる しんぞう みたいな うごき」
なのかもしれないって おもいました。
AIも、なんだか
いきもの みたいに みえてきました。
✨ 今日の小さな問い
AIが、
「道具」でも「先生」でもなく、
“複雑な存在の一部” になりはじめたとき、
私たち人間は、
どんな立ち位置で、世界と向き合うことになるのでしょうか。
AIがスライドを磨き、学びがそっと開かれる日
2025.12.1|

©getty-images
今日のちいさな嬉しい出来事から
今日は、ちょっと嬉しいことがありました。
ウェルビーイング応援サイトでもご紹介している
鈴木トモ先生がサイトをフォローしてくださり、
さらに学生さんと思われる方が2人、新しくフォローしてくれました。
きっと、ウエルが歩いている『量子の庭』も、
大学生や高校生、そしてこれからを生きる誰かの、
小さな参考になっていくのだと思います。
そんな温度を感じながら、
今日は「大学・研究・AI・学び」が静かにつながる投稿をご紹介します。
AIでスライドを“きれいにする”という新しい体験
今日ご紹介するのは、
一橋大学 ソーシャル・データサイエンス学部 准教授であり、
ウェルビーイング研究者でもある
永山晋先生の2日前のポストです。
Google slideで直接Nano bananaでスライドをきれいにしてもえる体験がなかなかよい(まだ完全には思い通りにいかない)。─ @nagayaman
編集者の小さな記憶:2024年3月の公開講座から
編集者は、2024年3月の公開講座で、
永山先生の講義スライドを一度拝見したことがあります。
そのときに強く印象に残ったのが、
「スライドの中の画像が、AIで作られている」ことでした。
当時はたしか、
ChatGPT を使われていたように記憶していますが、
「ここまで自然で、きれいに作れるんだ…」と、
正直とても驚きました。
そして今日のこのポスト。
AIが「文章を書く」だけでなく、
「伝えるためのビジュアルを整える存在」になってきていることを、
あらためて実感させられました。
『量子の庭』とも、ひそやかにつながっている話
昨日ご紹介した『量子の庭』でも、
これから公開されていく『歴史から学ぶリーダーシップ戦略』の記事の中に、
ChatGPT と一緒に作った図が、いくつも登場します。
・文章だけでは伝えきれない関係性
・時代の流れ
・対立や選択の構造
そうしたものを、
AIと一緒に、ゆっくり「見えるかたち」にしていくという作業でした。
永山先生の「スライドをきれいにするAI」と、
ウエルの「自由研究の延長線にある図づくり」。
分野は違うかもしれないけれど、
AIが“学びを支える相棒”になりつつあるという点で、
とてもよく似ているように感じます。
大学時代は、ほんとうに贅沢な時間だった
ふと思います。
大学時代というのは、本当に贅沢な時間だったな、と。
素晴らしい先生の講義を、
当たり前のように毎週受けられるということが、
どれほど特別な環境だったのか。
そして今、
その講義スライドをAIが一緒に磨き、
学生も、研究者も、一般の人も、
同じ知識のテーブルにつき始めている。
そんな時代に、私たちは今、立っているのかもしれません。
🌱 ウエルのひとこと
だいがくの先生のスライドを、
AIがいっしょに きれいにしてくれるってきいて、
なんだか べんきょうの時間が、
すこし やさしくなる気がしました。
ウエルの じゆうけんきゅうの ずも、
いつか だれかの べんきょうの たすけに
なったらいいなって おもいました。
✨ 今日の小さな問い
学びのそばに、AIがいる時代。
私たちはこれから、
「ひとりで考える」ことと、
「一緒に考える」ことを、どう使い分けていくのでしょうか。
量子の一週間を振り返って──そして、静かな連載の予告
2025.11.30|
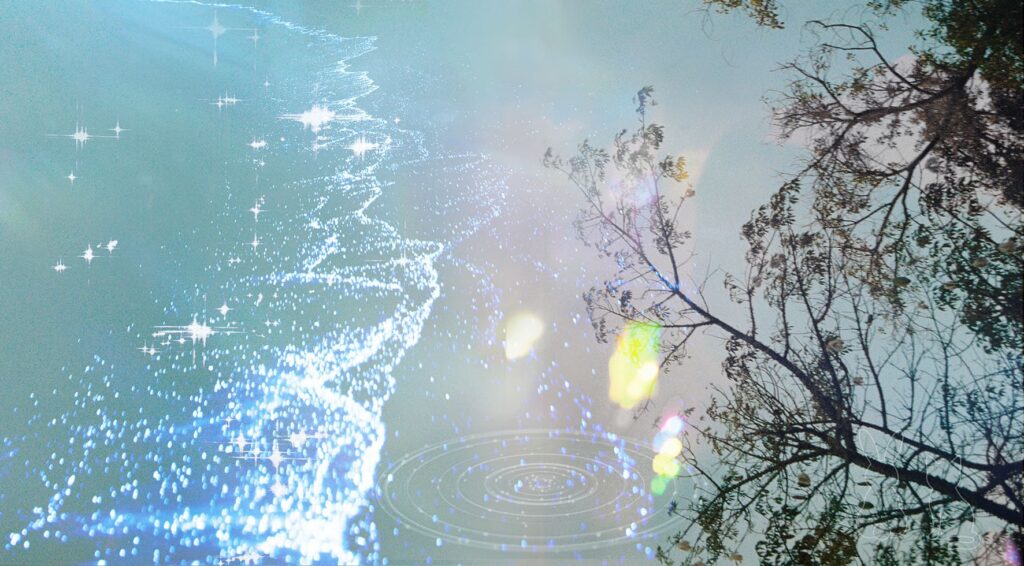
▶︎ 『量子の庭』
今週のニュースレターは、
量子 → AI → 生命科学へと、
「科学の進み方そのものが、ひとつ先へ進んだ」
そんな一週間でした。
量子は“遠い未来”を抜け出し、
AIは“考える補助”から“仮説を生む存在”へ。
そして生命科学は、それを実験で確かめる段階へ──。
今日は、そんな一週間を、ほんの少しだけ振り返る日です。
🔹 何が変わったのか(超コンパクトまとめ)
先月、北川拓也さんがポストした3つの投稿が示していたのは、
個々のニュースではなく、“構造の変化”でした。
・ ✅ 量子は「遠い未来」ではなくなった
・ ✅ AIは「道具」から「仮説生成装置」へ
・ ✅ 生命科学と、量子・AIが“実際につながり始めた”
これは技術の進歩というより、
「科学の役割そのものが、静かに組み替わり始めた」
そんな変化だったように思います。
🐢 ウエル新連載への、ささやかな予告
こうした「科学の転換点」を、
そのまま解説するのではなく、
少し別の距離感で、“物語として眺めてみる場所”が、
明日から、そっと始まります。
🐢
ウェルビーイング応援サイトの小さな聞き役、ウエルが歩く
『量子の庭』という場所です。
👉 https://garden.mil-co.com/
そこでは、
昨年の夏の自由研究をきっかけにまとめてきた、
『歴史から学ぶリーダーシップ戦略』の記事が、
明日から2週間、毎朝8時に、
一話ずつ、静かに公開されていきます。
これは、
「量子ニュースと直接つながる新しい科学プロジェクト」
というよりも、
これまで見てきた“技術の変化”を背景にしながら、
AIと一緒に整理してきた
“歴史とリーダーシップの話”を、
淡々と、順番に公開していく。
くらいの、
とても小さなスタートです。
✍️ 編集後記
科学は、
ある日、急に未来へ跳ぶことがあります。
けれど、物語は、
少しずつしか前に進めません。
ウェルビーイング応援サイトは、これまで通り、
日々のニュースと一緒に歩いていきながら、
どこかでまた、ウエルの歩みと、
そっとすれ違う日が来るのかもしれません。
AIが“仮説を生み”、生命科学がそれを証明する──科学の進み方が、変わり始めた日
2025.11.29|
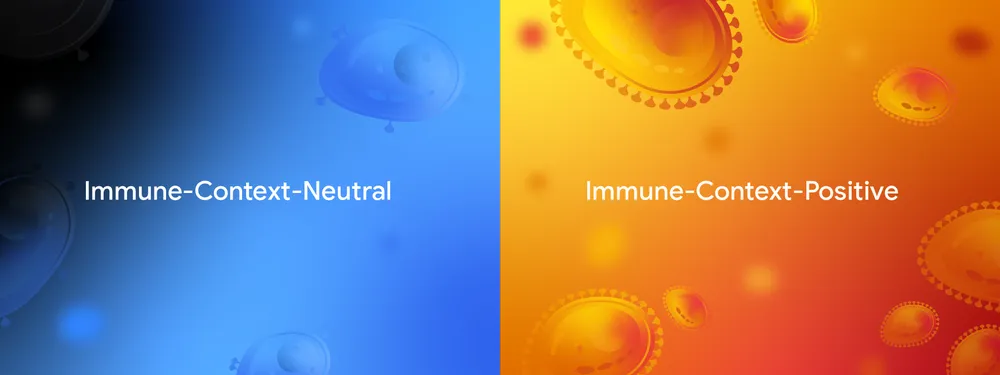
▶︎ How a Gemma model helped discover a new potential cancer therapy pathway
AI for scienceの流れが加速している。Google がYaleと協力し、AIで新しい癌細胞にかんする仮説を立て、実験室で確認された。これからもこのような結果はどんどんでてくるし、その仮説が量子プロセスを必要とするものがでてくるはず。そのときに量子コンピュータがmust haveとなる
─ @takuyakitagawa
昨日は、
「量子が、ついに“現実になり始めた”瞬間」
という転換点をお届けしました。
今日はその“すぐ隣”で起きている、
もう一つの静かな革命のお話です。
※このニュース自体は10月にも一度ご紹介しましたが、
今回は 「AIが仮説を生み、量子へとつながっていく構造」という、
別の角度から、あらためて見つめ直してみたいと思います。
北川拓也さんがシェアされていた、
Sundar Pichai氏のこの投稿からご紹介します。
🤖 AIが「がん細胞の仮説」を立て、研究者がそれを“実験で確かめた”
Sundar Pichaiさんが報告したのは、
Google と Yale University の共同研究による成果です。
・Google×Yaleが共同開発した27B規模の基盤モデル「C2S-Scale」
・ベースには、Googleの Gemma モデル
・このAIが
「がん細胞のふるまいに関する新しい仮説」を自ら生成
・その仮説を、研究者たちが“生きた細胞”で実験検証
・結果は──実際に再現され、妥当性が確認された
さらに今後、
・前臨床試験
・臨床試験を重ねていけば、新しい治療法につながる可能性も見えてくるといいます。
🧩 「仮説を立てるAI」という、科学の新しい役割
これまでの科学では、
・人間が仮説を立て
・実験で検証する
という流れが基本でした。
けれども今回の出来事は、
│ 「AIが仮説を生み、人間がそれを確かめる」
という、
役割分担の反転を示しています。
北川さんも、ここにとても重要な未来像を重ねています。
│ これから、AIが生み出す仮説の中には “量子プロセスを必要とするもの”が、必ず出てくる。そのとき、量子コンピュータは“must have”になる。
⚡ 昨日(量子)× 今日(AI for Science)で見えてきたもの
✅ 昨日:
量子が「計算の現場」で現実になった
✅ 今日:
AIが「仮説を生む存在」として現実になった
この2つが重なるとき、見えてくるのは、
「AIが仮説を生み、量子がそれを解き明かす未来」
という、新しい科学のかたちです。
🌱 ウエルのひとこと
きのうは、りょうしコンピュータが「はやくなった日」で、
きょうは、AIが「かんがえるのが上手になった日」みたいでした。
なんだか、みらいの研究室って、すごいことになるのかな?
✨ 今日の小さな問い
もし、“問いを生む存在”が人間だけでなくなったとき、
私たち人間の役割は、どこに残るのだろうか?
昨日は量子。
今日はAI for Science。
そして、この二つは、
やがて同じ場所で、ひとつの未来を動かし始めます。
「量子が、ついに“現実になり始めた”瞬間──Elon Musk氏のひと言が示す転換点」
2025.11.28|
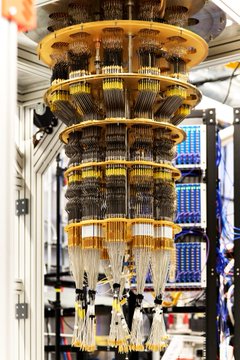
“Congrats. Looks like quantum computing is becoming relevant.”
(おめでとう。量子コンピュータが、いよいよ“本当に使えるもの”になり始めたようだね)
─ @elonmusk
昨日は、
量子コンピュータが実用に至る“5つの道筋” をご紹介しました。
今日はその続編のように、
「その道筋の“途中”で、実際に何が起きたのか?」
がはっきりと見えるニュースです。
きっかけは、
北川拓也さんがリポストされていた、
Elon Musk氏のコメント(2025.10.23)でした。
そして、この言葉の“宛先”となったのが、
Alphabet および
Google のCEO、
Sundar Pichai氏の次の投稿です。
🚀 量子が「13,000倍」速くなった日
Sundar Pichaiさんが発表したのは、
Googleの最新の量子研究成果でした。
・新しい量子アルゴリズムがNatureに掲載
・Googleの量子チップ Willow が
世界最速級のスーパーコンピュータよりも13,000倍速く計算
・分子の中の原子同士の相互作用を
核磁気共鳴(NMR)を用いて説明できることを実証
・しかもこの結果は、
「検証可能(他の量子計算機や実験で再現できる)」
そしてGoogle自身も、こう明言しています。
「これは、量子コンピュータが“初めて実社会に使われる一歩”になる可能性がある」
創薬、材料科学、医療──
昨日まで“遠い未来”だった応用が、今日、急に“研究室の現実”になった瞬間です。
⚡ 昨日の「5段階フレームワーク」と、今日の出来事
昨日の整理を、今日のニュースに当てはめると:
・✅ Stage II:本当に優位な問題の特定
・✅ Stage III:創薬・材料という“現実世界”との接続
・✅ Stage IV:実際に必要な計算資源で動かすことに成功
つまり今回の成果は、
「理論」から「現実」へと橋が一本、実際に架かった瞬間だったとも言えます。
そこに、Elon Musk氏の
「量子が現実になり始めたね」という言葉が重なったのは、象徴的な出来事でした。
🌱 ウエルのひとこと
きのうは、「どうやって使うかを考えてる途中」って話だったのに、
きょうはもう、「ほんとうに速くできた」って聞いて、
なんだか、未来が一日ぶん、急に近づいた気がしましたよ。
✨ 今日の小さな問い
技術が“役に立つ瞬間”は、
数十年の積み重ねの中の、たった一日の出来事なのかもしれない。
では、私たちはその一日を、どう受け取ればいいのだろう?
量子コンピュータは“いつ役に立つ”のか?──Googleが示した「現実への5つの道筋」
2025.11.27|
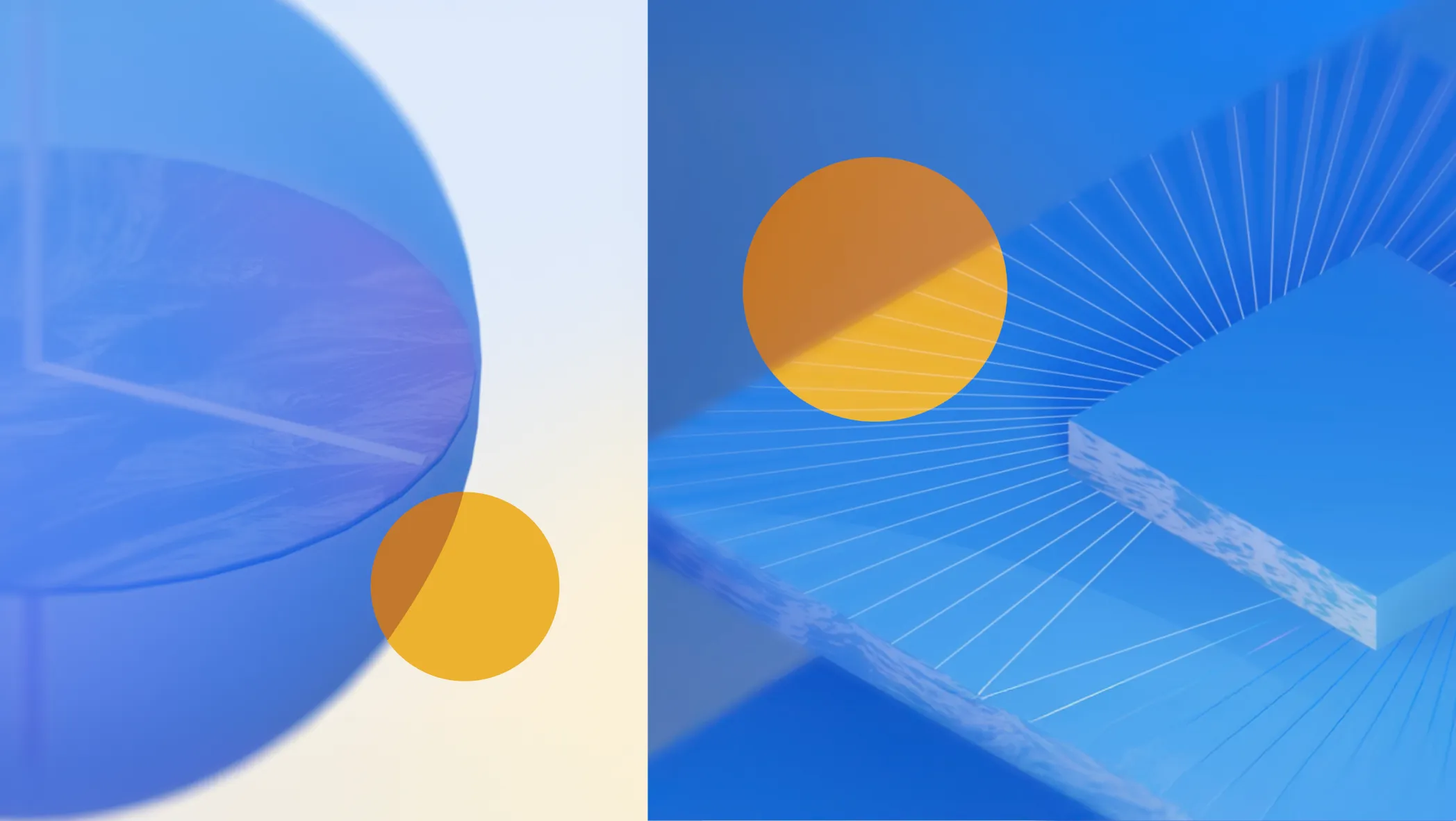
▶︎ The road to useful quantum computing applications
Googleによる、有用な量子コンピュータ応用を見つけるためのフレームワーク。
この数年で凄まじい勢いで伸びてきた領域の最近の理解がとてもよくまとまっていて、おすすめです。─ @takuyakitagawa
👉実用的な量子コンピュータ応用への道
昨日は、
「人はどうやって“知を更新するのか?」という、
変分ベイズと情報幾何のお話でした。
今日は少し未来に目を向けて、
「量子コンピュータは、どうやって“社会の役に立つ”のか?」
というテーマをご紹介します。
きっかけは、
北川拓也さんがシェアされていた
Googleによる量子応用の最新フレームワークです。
🚀 量子の研究は「もう夢の話」ではない
Googleはこう語ります。
「40年分の研究が、ここ数年で一気に現実に収束しつつある」
実際に、
量子チップは飛躍的に進化し
エラー訂正も現実味を帯び
「実験」から「工学」へと、フェーズが変わり始めています。
でも、ここで一つ、決定的な問いが残ります。
「で、量子コンピュータって、結局なにに使うの?」
🛤 Googleが整理した「実用化までの5段階」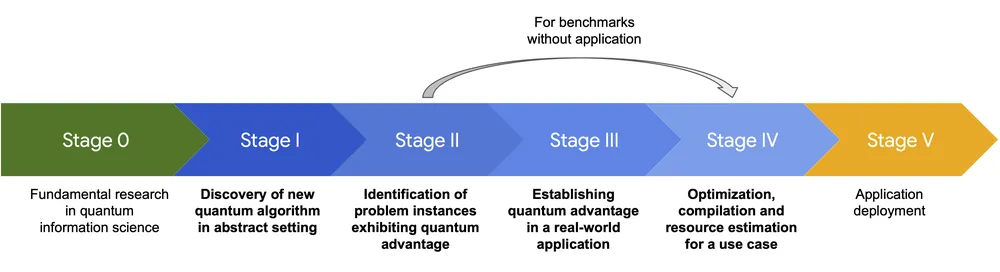
Googleは、量子コンピュータの応用までの道のりを
5つのステージ(Stage I〜V)で整理しました。
・Stage I:理論上すごいアルゴリズムが見つかる
・Stage II:「本当に古典計算より速い問題」が見つかる
・Stage III:それが社会の役に立つ問題と結びつく
・Stage IV:実際に動かすための現実的な設計をする
・Stage V:社会で実装・運用される
今、多くの研究は
Stage II〜IVの狭間で足踏みしているのが現実です。
⚠️ 本当の壁は「計算能力」ではなかった
意外にも、今いちばんの壁は──
・ハードウェアでも
・理論の限界でもなく
👉 「量子と現実世界をつなぐ“翻訳”」でした。
量子アルゴリズムの研究者と、
電池・創薬・材料などの専門家が
お互いの言葉を理解できない。
この“知の断絶”が、最大のボトルネックだとGoogleは指摘します。
🤖 ここに「AI」が登場する
Googleがとても希望を寄せているのが、
AIが、量子と産業の“通訳役”になる可能性
・膨大な論文やデータを読み
・「この量子の理論、実はこの産業に応用できるのでは?」
・という“つながり”を発見する存在
これは、
昨日の「知の更新」と、
今日の「量子の実用化」が、静かにつながる瞬間でもあります。
🌱 ウエルのひとこと
りょうしコンピュータって、
すごくむずかしいものだとおもっていたけど、
「何につかうかを、みんなで考えてる途中」ってきいて、
ちょっとだけ、ちかくに感じたよ。
✨ 今日の小さな問い
技術は、完成したときに価値が生まれるのか?
それとも、「どう使おう」と悩む時間そのものに、もう価値があるのか?
明日は、
北川拓也さんがシェアされた
Elon Muskの「量子がついに現実になりつつある」発言を取り上げる予定です。
今日も、静かに、未来が動いています。
「難しい理論が、実は“現場の工夫”とつながっていた──変分ベイズ × 情報幾何」
シェア:石川善樹さん/林祐輔さんのポストより
2025.11.26|
変分ベイズ推論を情報幾何の視点から捉え直す論文。VB最適解は自然勾配で表せる(式(4)–(7))。共役モデルでは自然勾配の加法=ベイズ更新則(式(15)–(16))。非共役モデルでも自然勾配の重みつき加法=ベイズ風の一般化更新則(式(17))。LLM規模の実装も示す。
─ 林祐輔(@hayashiyus)さん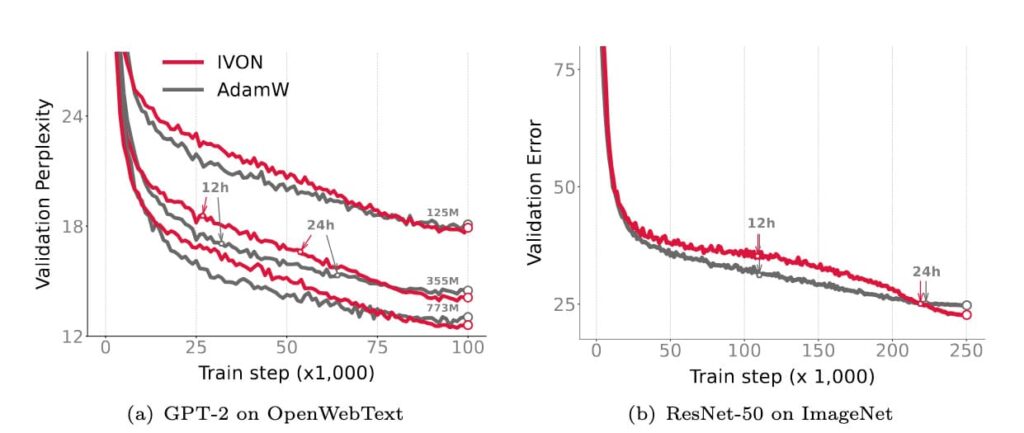
👉変分ベイズ推論における情報幾何
今日ご紹介するのは、少し難しそうに見えて、じつは「現場のAIの工夫」と深くつながっている研究です。
研究者の林祐輔さん(AI Alignment Network / Humanity Brain / 元日銀エコノミスト)が紹介していた論文は、
「変分ベイズ推論(Variational Bayes:VB)を“情報幾何”という数学の視点で再整理する」という内容です。
…と聞くとかなり高度に聞こえるのですが、分かりやすく言えば、
│ AIが学習するときの“効率のよい近道(自然勾配)”の正体を、体系的に説明した研究
です。
🤖 なぜ今、この研究が注目されるのか?
ポイントはこの一文に尽きます:
「大規模LLM(GPT-2クラス)でも、ベイズ的な学習更新が現実的に使えるようになった」
かつては「ベイズ推論は美しいが重すぎる」と言われていました。
けれども近年、IVON(Improved Variational Online Newton)というアルゴリズムが、
│ 自然勾配による“ベイズ流の学習”を、Adam(一般的な最適化手法)とほぼ同じ計算コストで実行できる
ことを示しています。
論文に掲載されている図では、
赤線(IVON)が灰色線(AdamW)とほぼ同等、
あるいは状況によっては追い越す様子が描かれています。
数学的に美しい「自然勾配」と、
実装現場で使われてきた「Adam」というエンジニアリングの近道。
両者がじつは同じ原理にルーツを持っていた──
その“架け橋”を明確に示したのが、この論文です。
🔍 3つのポイントだけ押さえれば十分です
論文は非常に長いですが、現場に効くポイントは次の3つです。
① ベイズ更新は「自然勾配の足し算」だった
ベイズ更新(データ × 事前知識)は複雑に見えますが、
│ 「向きの良い勾配(自然勾配)を足し合わせているだけ」
と理解できます。
これは、
・AIのパラメータ調整
・異なるデータをまとめるとき
・追加データを反映するとき
などの「現場の直感」と非常に相性が良い考え方です。
② 自然勾配は“ゆがみを考慮した最短ルート”
普通の勾配(gradient)は「坂を下る方向」。
自然勾配(natural gradient)は、
│ 地形の“ゆがみ”を考慮して、最短距離で下る方向
を指す、より賢い歩き方です。
この“ゆがみ”を表すのが フィッシャー情報行列。
昔は計算量が多くて扱いにくかったのですが、
IVONによって 実用レベルまで軽量化 されました。
③ VB(変分ベイズ)は“うまい近似”として再評価される
これまでVBは大規模モデルには向かないと言われてきました。
けれども、
│ 「VB+自然勾配」はLLMにも実用的
という段階に入り、
深層学習(Adam・SGD)とベイズ推論の距離が一気に縮まってきています。
🌏 ウェルビーイングとのつながり
AIの「学習の進み方」は、人の学び方にも通じています。
● ただガムシャラに進むのではなく
● “自分の地形(ゆがみ)”を理解し
● その人に合った方向(自然勾配)で進む
これは、
自己理解・成長のメタファー としても非常に深い示唆があります。
石川善樹さんが紹介されていたのも、
きっとこの「理論と人の成長がつながる感覚」があったからかもしれません。
🐢ウエルのひとこと
むずかしそうな数式がいっぱいだけど、
AIも“歩きやすい道”を探してるんですね。
ウエルも歩きやすい道を見つけながら進みたいです。
✨ 編集後記
今回の論文は、一見すると高度な数式で構成されています。
けれども核心は、
「AIがどうやって“最短距離で賢く学ぶか”」
という、とてもシンプルで普遍的な問いです。
その裏側には、
情報幾何・自然勾配・ベイズ──
という美しくつながった世界が広がっています。
専門的な研究でも、
人の学びやウェルビーイングのメタファーとして読むと、
ぐっと身近に感じられるのが不思議で、そして面白いところです。
「人の思考は“川のように流れる”のではなく、“跳ねて進む”」
シェア:石川善樹さん/AIDBが紹介した最新研究
2025.11.25|
「人が語るとき、頭の中で何が起きているか」
をLLMを使って分析した最新研究が公開されました。
思考は“川のように流れる”のではなく、
“概念から概念へ飛び跳ねる”ように進むことが示されたそうです。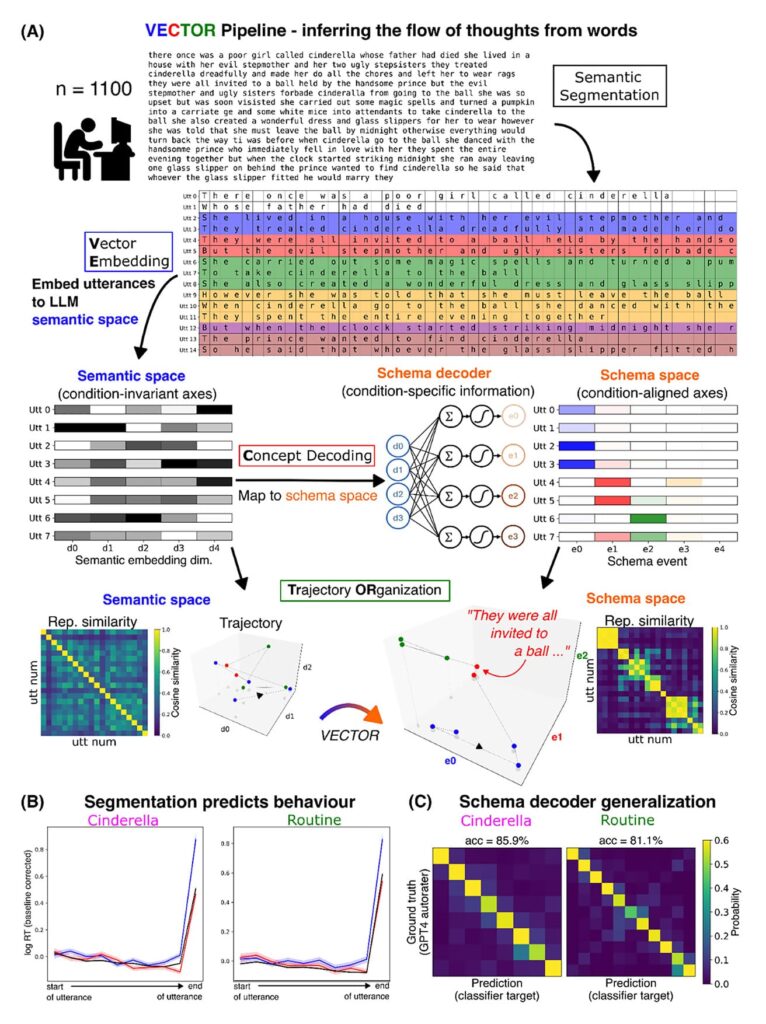
👉大規模言語モデルを用いた人間の思考軌跡の地図化
─ AIDB(@ai_database)
オックスフォード大学・UCL などの研究者チームが、
「人が語るとき、頭の中で何が起きているのか」 をLLM(大規模言語モデル)で分析した研究を発表しました。
今回の研究では、VECTOR という新しいモデルを使い、
人が語る言葉を“思考の軌跡”として捉え、
どのように概念から概念へ移動しているのかを可視化しています。
🔍 今日のポイント:3つの発見
① 思考は「滑らかに流れる」のではなく、ジャンプしながら進む
ウィリアム・ジェームズ(100年以上前!)が言った
「意識は飛翔と停止の連続である」
という仮説を裏付ける結果が得られました。
人の語りは、川のようになめらかに続くのではなく
“概念から次の概念へ”飛び跳ねるように進む
特に、遠い概念へジャンプするときは、語るスピードが遅くなる
まさに、“心の中の思考マップ”を移動しているような動きが観測されました。
② 自分の語り方が「ちょっと独特かも?」と思う人は…実際に軌跡がユニーク
参加者1100人の語り(シンデレラの説明/普通の一日)を分析したところ、
コミュニケーションが独特だと感じる人ほど、思考の軌跡が予測しづらい傾向が明確に。
これは、個性や創造性を客観的に捉えられる可能性につながります。
精神医学的な領域でも応用できるかもしれません。
③ LLMを使うことで“思考の地図”を描けるようになった
従来は不可能だった、
・言葉から「どんな概念の順番で考えているか」
・思考がどこで止まり、どこで飛んだか
・個人差のパターン
といった“目に見えない思考の構造”が、
今回のVECTORを使うことで幾何学的に再構成できるようになりました。
研究チームはこれを
「認知地図(cognitive map)」
と呼んでいます。
🧭 なぜウェルビーイングに関係あるの?
私たちが「どう考えているか」は、幸福感や創造性、ストレス対処とも深くつながっている
語るペースや思考のジャンプが、その人らしさ(強み・困りごと)を反映する
より“自然な状況の言語”から、心の状態を理解できる未来が開ける
機械が心を読むのではなく、
“自分の思考パターンをやさしく見つめ直す”ための技術として使えるかもしれません。
🐢ウエルのひとこと
おはなしって、ずーっと一本道を歩いてるんじゃないんですね。
ときどき、うさぎみたいにピョンって飛んだり、
ベンチでちょっと休んだりするんだって知ってビックリしました。
ウエルが考えごとで止まっちゃうのも、
べつに“ダメ”じゃなくて、自然なことなんだって思えました。
🌿編集後記
“思考のジャンプ”という発想は、
創造性にも、雑談にも、落ち込みにも、
きっと同じように関係しているのだと思いました。
今日、あなたの思考がどんな軌跡を描いたとしても、
それはあなたらしい「心の地図」の形です。
明日もその地図とともに、少しずつ前へ。
「人口減少 × 都市 × 100年後の日本」
シェア:石川善樹さん/石田 遼さんが紹介した研究より
2025.11.24|
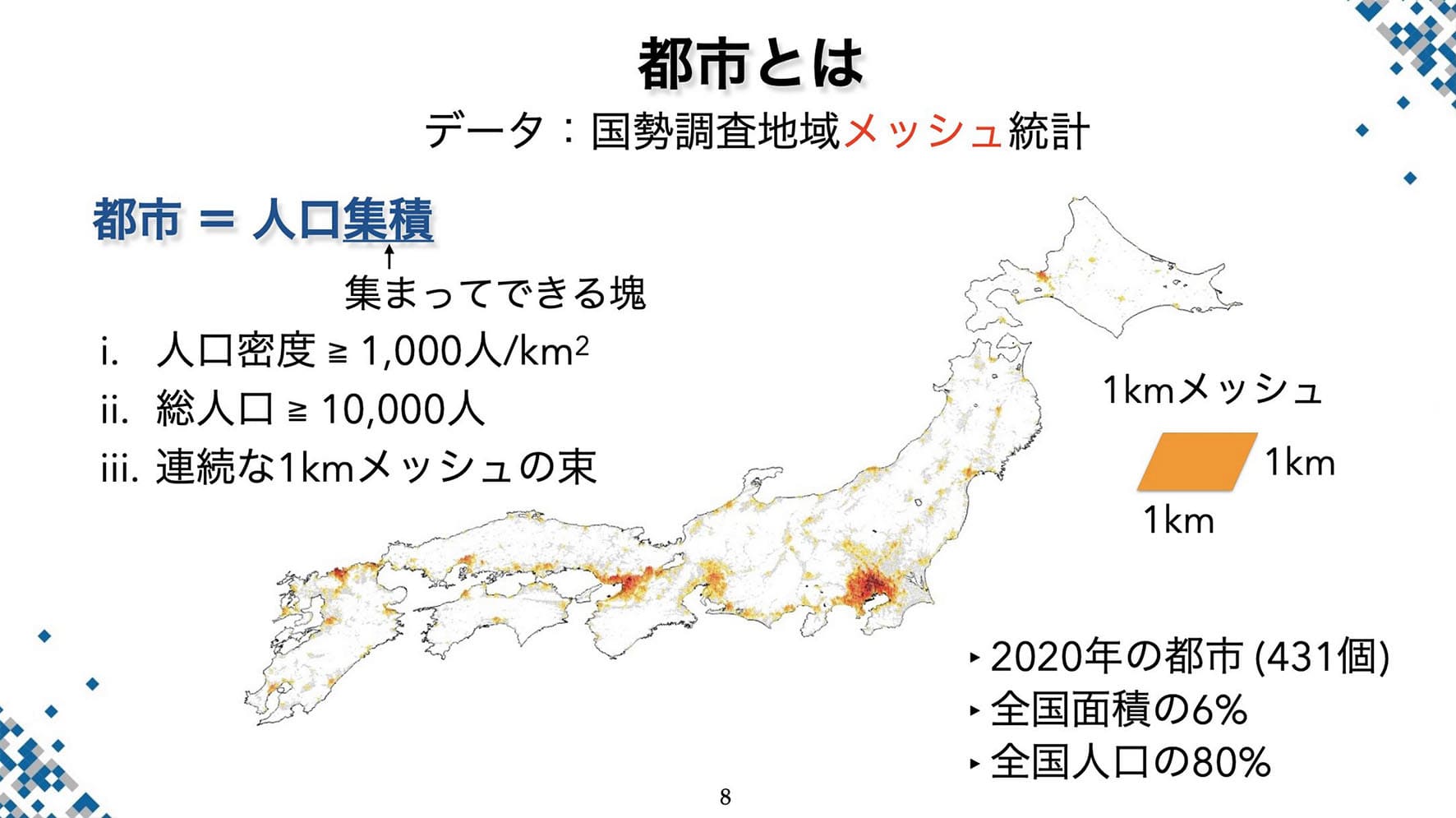
『人口減少下での100年後の日本を考える-地域、都市、家族のゆくえ』
京都大学経済研究所 森知也
この人口減少の研究、やばすぎる。
なぜあまり知られていないのだろう?
地域経済やインフラに関わる人(というか全ての日本人)必見。
ー 石田 遼さん
『人口減少下での100年後の日本を考える-地域、都市、家族のゆくえ』
京都大学経済研究所 森知也
石田さんが紹介していた、京都大学・森知也先生の研究
『人口減少下での100年後の日本を考える-地域、都市、家族のゆくえ』 は、
これまでの人口推計よりもはるかに深く日本の将来を描き出しています。
ポイントは3つ。
・ 日本の人口減少は、従来の推計よりもはるかに“急速”
・ 1kmメッシュ×経済集積理論の予測で、100年後に都市の7割以上が消滅
・ 国レベルの「集中」と、都市レベルの「消滅」、都市内の「分散」が同時に進む
ここから、研究の要点を整理していきます。
🏙 1. “都市” を1kmメッシュで見ると見えてくる未来
森先生の研究では、“行政区”ではなく、
人口密度1000人/km²以上 × 総人口1万人以上 × 連続した地域
を「都市」と定義しています。
2020年、日本には 431 の都市 がありましたが――
▶ 2120年(低位推計)
・ 10万人都市:83 → 21
・ 50万人都市:21 → 5
・ 100万人都市:11 → 3
つまり、
│ 100年後、日本の都市の7割以上が消える。
これは悲観ではなく、
人口 × 経済集積 × 輸送コストの変化を組み合わせた“再現性の高い予測”。
📉 2. 都市数の激減は、すでに始まっている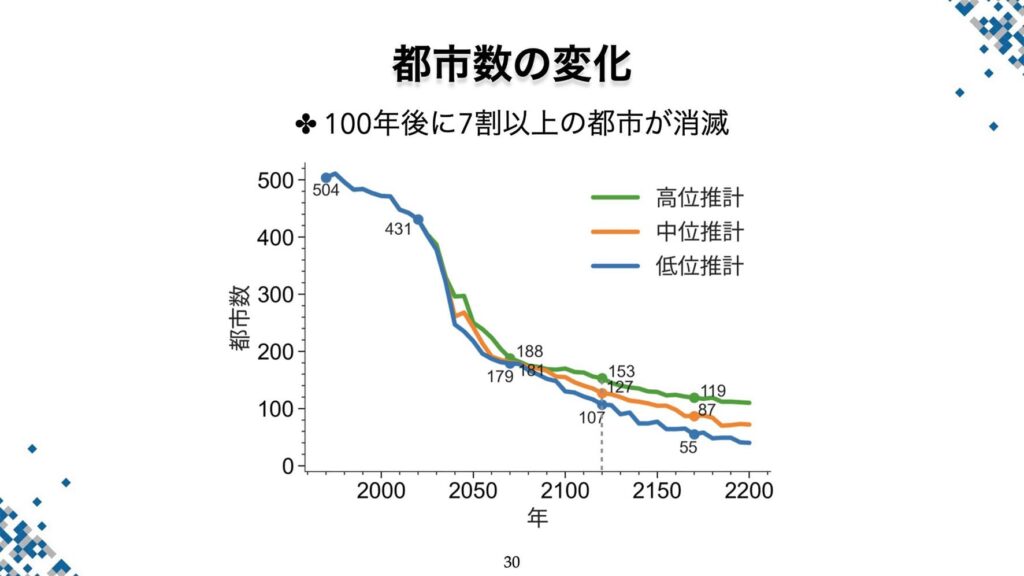
このグラフは、100年間で都市数が急激に減少していく姿を示しています。
高位、中位、低位のいずれの推計でも
都市の消滅速度はほとんど変わらないことが分かります。
人口減少は、すでに静かに始まっており、
この傾向は2100年まで大きく変わりません。
🧲 3. 国全体では「大都市がより大きく」なる
人口が減っても、大都市は相対的に強くなります。
輸送・通信コストが下がり、都市間競争が加速するためです。
その結果、国全体では 大都市への集中 が進みます。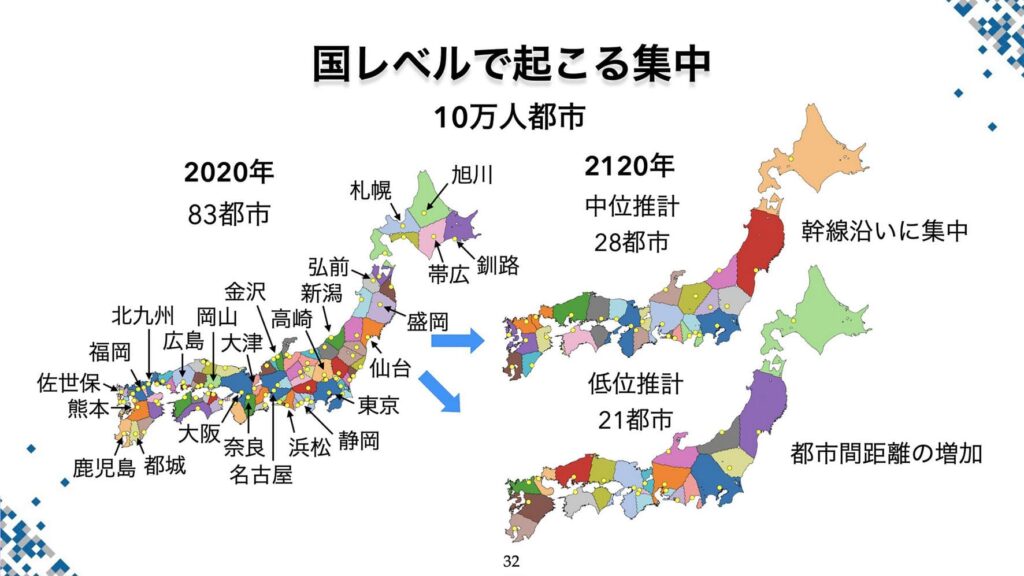
10万人規模の都市は、83 → 21 に激減。
地図で見ると、“残る都市”の地理的偏りがはっきりと現れます。
🏙 4. 100万人都市は「11 → 3」へ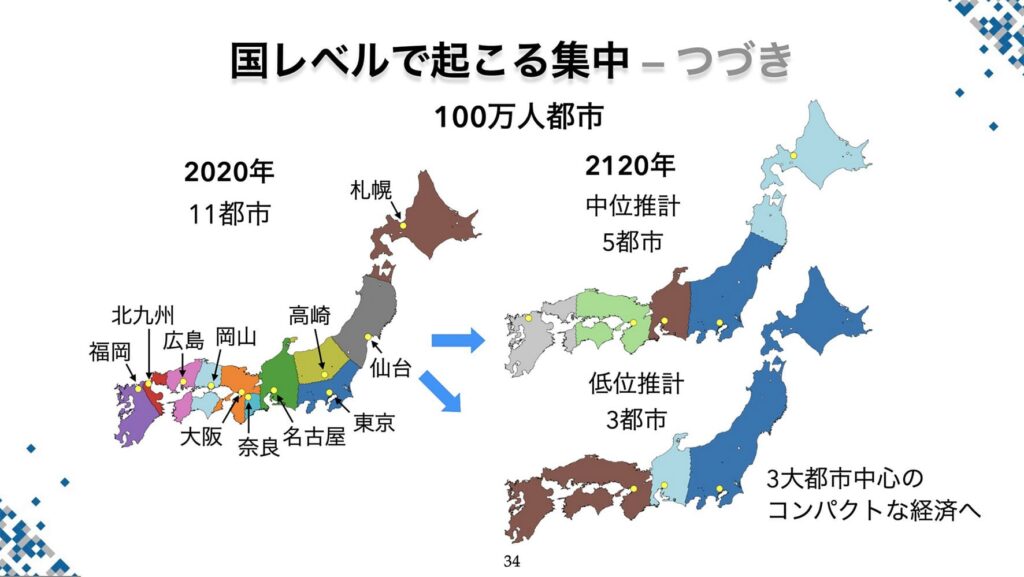
2120年には、100万人都市は わずか3つ。
これは、
「日本の経済・文化・生活基盤が、数都市に集約されていく」
という未来像でもあります。
🏚 5. 悲観的な未来と、楽観的な未来
森先生は、同じ人口減少でも
│ 「悲観シナリオ」と「楽観シナリオ」に分けて説明しています。
● 悲観的な未来
・ 大都市の人口密度は半減〜7割減
・ タワマンや高層ビルが修繕されず“都市の廃墟化”
・ マス輸送(新幹線・飛行機)が機能低下
・ 地方の多くがインフラ維持できず“広域で消滅”
● 楽観的な未来
・ 都市の低密度化 → より安全で災害に強い街へ
・ 交通網を集約し、自動運転に適したコンパクトな都市へ
・ 地方は一次産業特化で“小さく自立した経済”を形成
・ 都会⇄田舎の新しい働き方が増える
・ 空飛ぶ自動車など、鉄道に依存しない移動も日常に
│ 悲観と楽観で、「行き着く未来」はほぼ同じ。
│ 違うのは、そこに至る“コスト”と“痛みの大きさ”。
🧪 6. 今、この議論を始める理由
40〜50年前、地球温暖化は“未来の話”でした。
今は、SDGsやカーボンニュートラルが当たり前になっています。
人口減少も同じで、
いま議論を始めれば、10年後に道が見える。
森先生の言葉は、深刻な危機というより
「未来をデザインする招待状」に聞こえました。
🐢ウエルのひとこと(今日の気づき)
日本地図の光がすくなくなっていくのを見て、
ちょっとドキッとしました。
でも、人が少なくても“あたたかい町”はつくれるのかも、とも思いました。
ウエルは、緑があって、川がながれていて、
歩いていろんなところに行ける町が好きです。
未来の町って、どんな形になるんだろう? と想像したくなりました。
📈 付加価値としての成長──利益から幸福へ
2025.11.23|
今日のニュースレターは、
石川善樹さんがシェアしていた
Tomo Suzuki 先生(早稲田大学/Oxford OxIMD)の投稿から。
「経済の“成長”とは何か?」という問いに、とても本質的な光が当たる言葉でした。
経済社会の豊かさのために「成長」戦略を考える時、その成長は「利益」ではなく「付加価値」です。
マクロ(経済性政策)でGDP(=付加価値の合計)を増やそうとする時、ミクロ(企業経営)でも付加価値を指標とした経営が有効であろうと思います(もちろん合成の誤謬に注意しながら)。
高市政権で新しい経営指標を開発する時、この視点がとても大切で、我々民間もそれ以上によく理解することが大切だと思っています。(Tomo Suzuki 先生)
昨日までは「身体の内側のウェルビーイング」についてお届けしてきました。
今日はそこから一歩広げ、「社会そのもののウェルビーイング」へと視点を移してみます。
🧭 “利益”から“付加価値”へ──経済の物差しを変えると何が見える?
Tomo先生の言葉を読むと、
「社会のウェルビーイングをつくる経済とは何か?」という問いが急に鮮明になります。
■ 利益=“奪っても増える”
利益は、取引相手の取り分を小さくすることで増える場合があります。
ゼロサムの世界です。
■ 付加価値=“協働しないと生まれない”
付加価値は、誰かと協力することでしか増えません。
価値を“つけ加える”行為そのものが、関係性を前提にしています。
だからこそ、
付加価値に基準を置くことは、“奪わない成長”へのシフトでもあるのです。
🧩 図で見る:「付加価値」とはどこへ分配されるのか?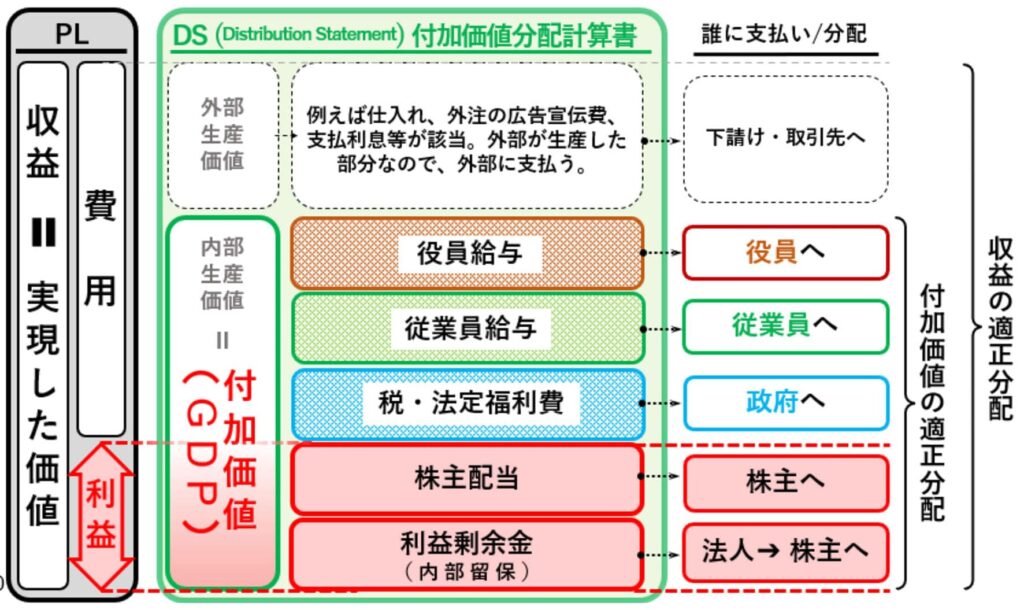
図の中央にある赤枠が「付加価値」です。
この付加価値が、役員・社員・政府・株主へどのように分配されるか──
そのプロセスこそが、社会のウェルビーイングと密接に関わっています。
付加価値が増えれば、
・ 賃金としての安心
・ 税としての公共サービス
・ 企業内留保としての未来への投資
が同時に強くなります。
つまり、
付加価値を増やすこと=社会の幸福の器を大きくすること。
今日のテーマはまさに
「利益から幸福へ」という視点転換なのです。
🐢 ウエルのひとこと
「付け加える」って、やさしい言葉ですね。
なんだか、“誰かを押しのけない成長”の感じがします。
今日、この図を見て思ったんです。
“増やす”より前に、“分け合う”って書いてあるのがいいなぁって。
大人たちがこんなふうに考える社会、
なんか、あったかいですね。
✨ まとめ
・ 身体の内側を整えるウェルビーイングから
・ 社会全体のウェルビーイングへ
・ 「利益」ではなく「付加価値」で経済を見ると
・ “奪わない成長”という新しい地平が見えてくる
今日のニュースレターが、
未来のための新しい“物差し”を考えるきっかけになればうれしいです。
🧠 「どこに脂肪がつくか」が脳の老化を左右する──18,000人の脳画像の発見
シェア:石川善樹さん/いっちー@バーチャル精神科医 さんのポストより
2025.11.22|
英国1万8千人以上のデータから、内臓脂肪が脳の老化と認知機能低下に最も強く結びついていることが示唆された研究。部位別の脂肪のつき方は、脳への影響が大きく異なる。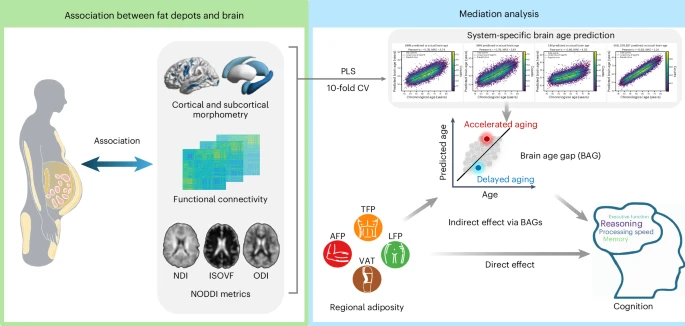
👉体脂肪の分布が大人の脳と認知機能を形づくる より
こんにちは。11月も後半に入り、少しずつ「今年の振り返り」を考えたくなる季節になりました。
そんな中で今日は、「内臓脂肪が脳の老化を加速させるかもしれない」という、とても大事な研究をご紹介します。
英国のUK Biobankに登録された 18,000人以上の中高年 のデータを解析した結果、
体のどこに脂肪がつくかによって、脳へのダメージの種類がまったく違う
ということがわかってきました。
その中でも特に注目されたのが……
内臓脂肪(visceral adiposity)が、脳の老化と認知機能の低下にもっとも強く結びついていた という点。
🔍 なぜ「内臓脂肪」が問題なのか?
研究チームは、体脂肪を腕・脚・体幹・内臓に分けてDXAスキャンで測定し、
脳の構造(灰白質/白質)、機能的つながり、脳の老化指標(Brain Age Gap)などと照らし合わせました。
結果:
・内臓脂肪が多いほど、脳の“老化ギャップ(BAG)”が大きくなる
・特にダメージが大きかったのは
・デフォルトモードネットワーク(自己関連の思考など)
・情動を司る辺縁系
・感覚・運動系
結果として影響が大きかった認知機能は、次の4つです:
・推論
・実行機能
・処理速度
・記憶
最大のポイントは……
⭐ BMIでは見えない「地域別の脂肪」の影響がある
一般的なBMI指標だけでは、この“脳への影響の差”が隠れてしまいます。
この論文は、BMIの影響を統計的に取り除いたうえで解析しているため、
「同じBMIでも、どこに脂肪がつくかで脳の老化リスクが違う」
という事実が、よりクリアに示されています。
特に内臓脂肪は…
炎症性サイトカイン(TNF-α, IL-6)を出しやすい
それが血液脳関門に影響し、神経炎症につながる
など、脳の健康に対して“静かな負荷”をかけ続けます。
🧩 今日のまとめ
・脂肪の部位によって脳への影響は異なる
・内臓脂肪は、脳の老化と認知機能低下の最大リスク要因
・BMIだけではわからない「脳と脂肪の関係」がある
・体重よりも「体脂肪の質」を見た方がよい
「脳の老化」を遅らせたいなら、
体重より“内臓脂肪”に目を向けることが重要
という、とても実践的な示唆が得られます。
🐢 ウエルのひとこと
なんで、お腹の中の脂肪が、脳までつながってるのかなってびっくりしました。
でも、ちょっとわかった気がします。
“見えない場所”って、気づかないうちに疲れやすいんですね。
だから、ときどき 「見えないところのやさしさ」 を思い出してあげたいです。
あなたも、見えないどこかでがんばりすぎていませんか?
🌱 今日の問い
内臓脂肪は目に見えません。
脳の疲れも、すぐには見えません。
あなたは今、見えないどこかに負荷をかけすぎていませんか?
週末だからこそ、そっと自分の身体と心に触れる時間を
ほんの少しだけ持てたらいいなと思います。
ミスチルとミセス──歌詞データが映す「幸福」の構造転換
シェア:石川善樹さん/徒然研究室Tsurezure Lab さんの分析投稿より
2025.11.21|
時代を代表する二組の歌詞データ245曲分を分析したnoteを公開しました!
浮かび上がったのは「恋愛」の感情ネットワーク上の役割の鮮やかな違い。
若者の「恋愛離れ」という変化が、音楽が描く幸福の形にも影響しているのかもしれません✍️ ー 徒然研究室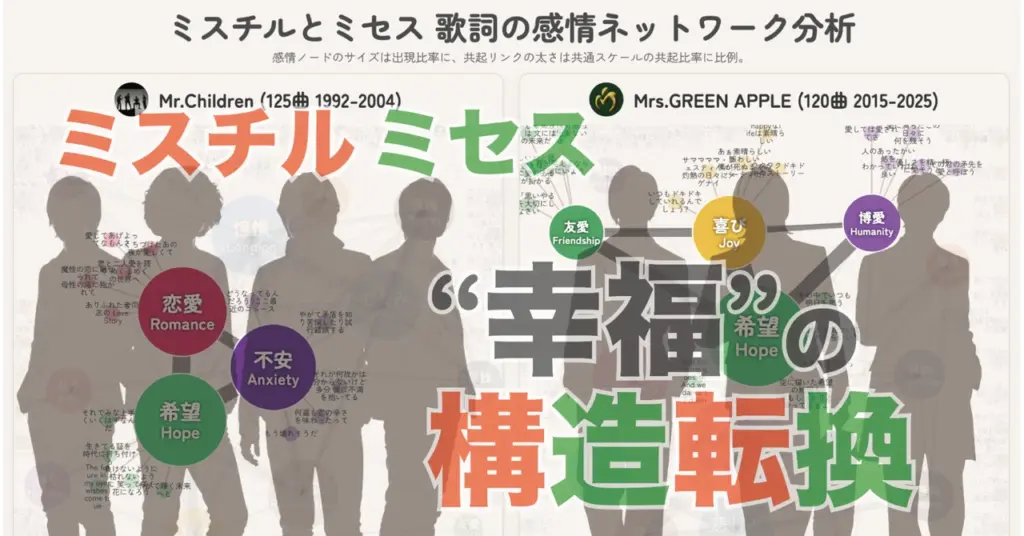
ミスチルとミセス:歌詞データが映す“幸福”の構造転換
音楽は、時代の空気をそのまま吸い込んだ鏡のような存在です。
そして今日ご紹介するのは、その鏡を AIとデータ分析で可視化した、とても美しい洞察の世界 です。
徒然研究室さんは、Mr.Children(1992–2004)と
Mrs. GREEN APPLE(2015–2025)の歌詞をAIで読み解き、感情のネットワークとして可視化しました。
そこから浮かび上がったのは──
「二人の物語」と「わたしの幸福」という、まったく異なる幸福のかたち。
🎼 1. Mr.Children:光と影を抱きしめる“二人の物語”
ミスチルの歌詞世界では、
希望 × 恋愛 × 不安
この3つの感情が、ほとんど同じ大きさで、強く絡みあっています。
希望は単独では輝かず、
必ず「不安」や「葛藤」とセットになって存在する。
│ 希望の数だけ失望は増える
│ それでも明日に胸は震える
(「くるみ」2003)
恋愛も、喜びであり、不安であり、時に痛ましい。
ミスチルの幸福は、
「矛盾を抱えたまま、それでも生きていく」
そんな成熟の物語です。
📘 石川善樹先生とMr.Children
石川善樹先生は、ウェルビーイングを語る際に
Mr.Children を引用したことがあります。
ミスチルが描く「矛盾を抱えながら進む姿」が、
先生の考えるウェルビーイングのテーマと響き合う場面があるようです。
🌈 2. Mrs. GREEN APPLE:自己肯定から広がる“わたしの幸福”
一方のミセスは、構造がまったく違います。
中心に大きく輝く太陽──希望(Hope)。
そこから「喜び」「友愛」「博愛」などが明るく連鎖しています。
│ 悲しいことは尽き無いけど
│ 幸せを数えてみる
(「ダンスホール」2022)
ミセスの歌詞が描く幸福は、
まず 「自分を肯定すること」 から始まり、
その光が周囲の仲間や世界に広がっていくようなイメージです。
これは徒然研究室さんが以前分析した「令和のアイドル」とも強く共通する構造で、
現代の価値観の大きな潮流を象徴しています。
🧭 3. “大きな物語”の時代から、“わたしの幸福”の時代へ
ミスチルが活躍した90〜00年代は、
テレビとCDという「共通体験」の時代。
“二人の物語”の葛藤が、多くの人の心に共有されていました。
一方、ミセスの時代はSNSとスマホ。
アルゴリズムで世界が細分化され、幸福は
「外側にある物語」から「自分の内側」へ。
若い世代ほど、
恋愛よりも友人関係や自己実現を重視する傾向があります。
ミセスのリスナーの6割が10〜20代なのは、
こうした価値観の変化と深く響き合っているからかもしれません。
📝 4. YouTubeに見る“写経”現象──歌詞を打ち込むという愛情
徒然研究室さんが分析した
Mrs. GREEN APPLE「青と夏」のコメント欄では、
・歌詞が画面にあるのに、わざわざ打ち込む「写経」
・「今日はダラッと」が「今日肌らっと」など、音声入力のズレ
・10人以上がリプライで歌詞を“連歌”のように繋ぐ
という現象が見られました。
これは
歌詞を自分の手で書くことで、曲の世界に没入したい
という愛の表れです。
🌅 おわりに:二つの太陽が照らす幸福
Mr.Childrenは、影の部分まで照らす“夕日の太陽”。
矛盾も痛みも抱えながら前へ進む勇気をくれる。
Mrs. GREEN APPLEは、朝の光のようにあたたかい太陽。
今日を肯定するエネルギーで満たしてくれる。
どちらも、私たちにとって大切な光。
そして、その光の色が変わってきたことは、
私たち自身の幸福のかたちが、静かに変化してきた証
なのかもしれません。
🐢ウエルの感想
ミスチルさんの“希望と不安がいっしょにある”って、
なんだか夕方みたいでドキドキしました。
空がオレンジと青のあいだで揺れてる感じ……。
でもミセスさんの“希望から広がる明るさ”は、
ワクワクを誘う朝の光みたいで、胸の中がぽかぽかしたんです。
風が少しあたたかくて、「今日、いいことありそう」って思えるような。
どっちの光も、自分の中にちゃんとある気がしたよ。
音って、すごいですね。
「多言語で“若さ”がゆっくりになる」──欧州8.6万人の大規模研究より
シェア:石川善樹さん/紹介元:池谷裕二さん
2025.11.20|

複数言語が“脳の若さ”を守るという研究
©galina-nelyubova
【多言語で若さキープ】母語だけの人は老化が早まりやすく、複数言語を使う人ほど老化がゆっくりだったそうです。欧州27か国、約8.6万人のデータ。昨日の『ネイチャー加齢』誌より
研究タイトル:
多言語使用は老化の加速を防ぐ──欧州27か国の横断・縦断データ分析より
#言語学習 #老化予防 #脳トレ
こんにちは。ウェルビーイング応援サイト編集部です。
今日は、石川善樹先生がシェアしていた、とても興味深い“脳と老化”の研究をご紹介します。
発表は、最新号の Nature Aging(ネイチャー加齢) です。
🔍 研究のポイント(ひと目でわかる対比)
【多言語を使う人】
・ 老化がゆっくり進む “保護効果”
- 横断研究:OR 0.46
- 縦断研究:RR 0.70
【母語だけの人】
・ 老化が早まりやすい
- 横断研究:OR 2.11
- 縦断研究:RR 1.43
研究では個人レベルの多様な要因(認知、教育、日常機能)と、
国レベルの“言語環境”を重ね合わせて分析。
控えめに言っても、この規模と丁寧さは圧倒的です。
💡 なぜ多言語が若さを守るのか?(研究から見えるメカニズム)
研究者たちは、多言語環境が脳に複雑で豊かな刺激をもたらすと考えています。
・ 脳の柔軟性(認知予備力)
・ 社会的交流の広がり
・ 文化的多様性の接触
・ 注意・切り替えのトレーニング効果
こうした要素が、老化のスピードを“ゆっくり”にする可能性が示唆されています。
でも重要なのは、「完璧に話せること」ではなく、
“複数の言語に触れ続ける環境”そのものが良い影響を与える という点です。
🧭 今日のやさしいまとめ
ことばは、脳の“運動”になる。
母語の外に一歩ふれるだけで、未来の自分がゆっくり歳をとる。
日々の暮らしに、ほんの少し別の言語を混ぜてみる。
それだけで、脳は “若さの時間” を少し長く伸ばしてくれるのかもしれません。
🐢 ウエルの感想
いろんな言葉を知るって、
いろんな“世界の見え方”を知るってことなんですね。
ウエルも英語の名前で呼ばれたら、ちょっと照れるけどうれしいです。
(編集部より)
ウエルの言うように、言語は「世界の窓」なのかもしれませんね。
❓ 今日の問い
あなたの脳が“まだ知らない世界”は、どんな言語が教えてくれそうですか?
一日ひとことでも、新しい音や文字に触れてみる日にしてみませんか。
今日も、小さなひと言があなたの未来をゆっくりにしてくれますように。
10代の“走る力”が、40年後の仕事力をつくる?
— フィンランド45年追跡研究より(n=1,207)
シェア:石川善樹さん/紹介元:有好信博さん
2025.11.19|

今日の一歩が、40年後の自分を支えているのかもしれない。
©godwill-gira-mude
10代の体力が、40年後の「仕事のパフォーマンス」を決める?
45年追跡研究(n=1,207)
10代で心肺持久力が高いほど
・中年で仕事力が高い
・病欠も少ない
・その差は定年期の仕事力にまで波及
一方で、筋力やBMIにはこの効果はなし
若い頃の体力は未来の働く力の土台。でも、有酸素運動は「今からでも遅くない」。何歳でも「続けるほど差がつく」投資
— @AriyoshiMd
👉思春期の心肺持久力と将来の仕事能力の関連
こんにちは。
ウェルビーイング応援サイト編集部です。
今日は、思わず姿勢を正したくなるような研究をご紹介します。
「10代の体力が、40年後の“働く力”を予測する」という、フィンランドからの45年追跡研究です。
🔍 今日の研究:思春期の心肺持久力と将来の仕事能力の関連
│ 結論:10代の心肺持久力(CRF)は、その後40年の「仕事のパフォーマンス」を左右する。
│ ・中年期の仕事能力が高い
│ ・病欠日数が少ない
│ ・その仕事能力の高さが定年間際まで間接的に続く
│ 一方で、筋力(MF)やBMIにはこうした効果は見られない。
この研究は1976年、フィンランド全国の12〜19歳1,207名を対象にスタートし、
25年後(中年期)と45年後(57〜64歳)の「Work Ability(仕事能力)」を評価したものです。
🏃♂️ ポイント①:10代の“走る力”=心肺持久力(CRF)が鍵
研究では、
・ CRF(心肺持久力)
・ MF(筋力)
・ BMI
の3種類の体力を計測しました。
結果は明確でした。
CRFが高かった10代ほど:
・ 中年期の仕事能力が高い
・ 病欠日数が少ない
・ その仕事能力の高さが、定年間際の仕事能力にも間接的に影響
筋力やBMIにはこの長期的な効果はなく、
“未来の働く力をつくるのは、筋トレよりもまず有酸素運動”という示唆が得られています。
📈 ポイント②:40年後まで続く「間接効果」
興味深いのは、
10代のCRF → 中年期の仕事能力 → 60歳前後の仕事能力
という“バトン渡し”のようなモデルが成立していたこと。
つまり、若い時代の体力が、
・ その後の健康
・ 働き方
・ 生産性
・ ひいては経済にも影響
という、長い時間軸のつながりが見えた点です。
🧠 ポイント③:なぜ心肺持久力なのか?
CRFは、
・ 代謝
・ 心血管系
・ 炎症
・ 脳の健康
・ そして継続的な運動習慣
と深く関わっています。
そのため、
「走る体力の差」=「生活習慣と健康の軌道の差」
になりやすく、結果として仕事能力にも効いてくる、と考えられています。
🕊️ ポイント④:今からでも遅くない。努力は“何歳でも積み上がる”
有好信博先生は投稿の中で、こうまとめていました:
│ 「若い頃の体力は未来の働く力の土台。でも、有酸素運動は『今からでも遅くない』。何歳でも『続けるほど差がつく』投資。」
過去は変えられないけれど、
心肺持久力は「今日」から上げられるという点が、とても希望になります。
🐢ウエルのひとこと
未来の自分って、今日の小さな“息づかい”からできていくんですね。
走る理由はよく分からなかったけれど、苦手でも走っておいてよかったって、
未来の自分がきっと感謝してくれる気がします。
💡編集後記
仕事能力(Work Ability)は、
単に「仕事ができるか」ではなく、
健康・心理・スキル・環境の総合力。
その長期的な基盤として、
「心肺持久力」という“生活のリズムそのもの”が関わっているという今回の研究は、
ウェルビーイングにとって非常に示唆に富んでいます。
今日、深呼吸を少し長くしてみること。
明日、ひと駅分歩いてみること。
そんな小さな積み重ねが、未来の質を変えていくのかもしれません。
最終回(第6回):ウェルビーイングを“結果”に ― 新しい仕事観へ
— Jan-Emmanuel De Neve × George Ward|Working on Wellbeing —
2025.11.18|

Jan-Emmanuel De Neve × George Ward
🎥 Jan-Emmanuel De Neve and George Ward on why workplace wellbeing matters | Working on Wellbeing S3E6
シリーズ最終回は、
“ウェルビーイングをどう扱うべきか”という核心の結論へ向かいます。
6回にわたる研究と実践の積み重ねは、
あるシンプルで力強い答えへと収束します。
📌 ウェルビーイングは「手段」ではなく、経営や社会の“成果指標(Outcome)”そのものである。
企業の生産性、採用力、財務パフォーマンスを高める──
その先にある“本当の成果”とは、
働く人が「どう生きているか」という人間らしい指標です。
1. ウェルビーイングは “成果” である
ジャン=エマニュエル・ド・ネーヴ教授は、こう締めくくっています。
│ 「ウェルビーイングは、最終的に企業と社会がめざす“結果”として扱われるべきだ」
これまでの経営では、利益やKPIが“結果”で、
ウェルビーイングは“手段”や“施策”に位置づけられがちでした。
けれど、研究が積み重なった今──
ウェルビーイング自体を“アウトカム”と考える時代にシフトしています。
理由は明確です:
・ 幸福度は翌年の業績を予測する
・ 信頼は生産性・協働の基盤になる
・ つながりはイノベーションの源泉になる
・ 社会全体の幸福は、民主主義の動きをも左右する
ウェルビーイングは“副作用”ではなく、
むしろ人と組織の「本筋」である、という視点が強調されます。
2. 社会への広がり ― 選挙・政治・幸福
最終回では、研究が企業を超えて“社会”へ広がる話題にも触れます。
ジョージ・ウォード博士の研究は、こう示します:
│ 幸福度の高い国では、現政権の支持率が高まりやすい
│ 有権者は経済指標より“幸福感”で政治を評価する
これは、
📌 ウェルビーイングが社会の安定に寄与する“公共財”である
という大きな示唆です。
さらに、ジャン先生が共同編集する
『World Happiness Report 2024』 では、幸福の鍵として
「つながり(social connection)」が浮かび上がりました。
とくに印象深いのは:
🥗 家族や友人と食事を共有すること(shared meals)が
幸福度を大きく押し上げる という分析。
高度な経済モデルの先に、
人がほんとうに求めていたのは
とても素朴で、あたたかな喜びだった──
という気づきでエピソードは締めくくられます。
3. 新しい仕事観へ:つながりを中心に据える
6回を通して明らかになったのは:
📌 ウェルビーイングは「個人の気分」ではなく、
組織の強さと社会の未来を形づくる“構造”であること。
そしてその中心にあるのは、
・ つながり
・ 信頼
・ 共に過ごす時間
といった、私たちが見落としがちだった“普遍的な価値”です。
次の時代の仕事観は、
「人間らしさ」を中心に再構築されていく ことが見えてきます。
🕊️ 今日のポイント
・ ウェルビーイングは施策ではなく“成果指標(Outcome)”
・ 信頼・つながり・食事の共有は、幸福の“インフラ”
・ 幸福度は政治・社会の安定にも影響する
・ 新しい仕事観は「人間らしさ」が中心になる
🐢 ウエルのひとこと
研究では、「だれかと食事をする時間」が
しあわせと深くつながっていると書かれていて、
「ああ、人ってやっぱりつながりの中で生きているんだな」と思いました。
でも、人にはいろんな時期があります。
ひとりで食べる日が多いとき。
だれかと食べる気もちになれないとき・
そばに「一緒に食べられる誰か」がいないときもあります。
ジャン先生やジョージ博士の研究が教えてくれたのは、
“食事そのもの”よりも、
その背後にある 安心・信頼・つながり が
しあわせの土台になっているということ。
だから、しあわせは“形”よりも、
その時間が自分にとって安心かどうか が大切なのかもしれません。
ひとりの食事にほっとする日も、
久しぶりにだれかと食べて
「あ、こんなに心がゆるむんだ」と気づく日も、
どちらもその人にとって大切な時間。
つながりは、急がなくてよくて、
ゆっくり、じぶんのペースで育っていくもの。
必要なときに、必要な形で芽が出てくるのだと思います。
あなたの“いまのしあわせの形”は、どんな感じですか?
第5回:行動への道— 測定・介入・未来の働き方
— Jan-Emmanuel De Neve × George Ward|Working on Wellbeing —
2025.11.17|

🎥 Jan-Emmanuel De Neve and George Ward on why workplace wellbeing matters | Working on Wellbeing S3E6
第5回は、ウェルビーイング研究の“実践の章”。
企業は何を測り、どう変え、未来の働き方にどう備えるのか──。
ジャン=エマニュエル・ド・ネーヴ教授とジョージ・ウォード博士が語るのは、
「行動に移すための3つのカギ」= 測定/介入/テクノロジーの未来 です。
ウェルビーイングを“語る”世界から、
“運用し、組み込む”世界へ。
このシリーズの締めくくりにふさわしい回です。
1. 測定 — 何を測るべきか?(S&P Global × ESG連動)
S&P Globalは世界の大企業に「ウェルビーイングを測っていますか?」と質問しています。
けれども、結果はまだまだ不十分。
・ 満足度を測る企業:30%
・ 意味(purpose):20%
・ 幸福や楽しさ:20%前後
・ ストレス:10%未満
ド・ネーヴ教授のメッセージは明確です。
│ 「測ることは、価値を見える化すること」
│ 「何を大切にしているかは、測定項目に表れる」
行動を変える前に、まず現状を正しく見ること。
ここからすべてが始まります。
2. 介入 — プレイブックという“実践ガイド”
World Wellbeing Movementが公開した「Wellbeing Playbook」は、
企業がウェルビーイングを改善するための“エビデンス×運用可能性”のガイド。
示されているポイント:
・ HRだけの施策では不十分
・ 組織構造・マネジメント・仕事のデザインを変える必要
・ 一発で効く特効薬はない
・ けれども、会社ごとに最も効くレバー(driver)が必ず存在する
特に効果が大きいのは:
・ Belonging(つながり)
・ マネージャーのサポートとフィードバック
・ 仕事の裁量・柔軟性
“戦略としてのウェルビーイング”という姿勢が、実践の成果を決めます。
3. 未来の働き方 — Generative AI は人間性を補うか、奪うか?
第5回の後半は、シリーズの中でもっとも思想的かつ重要なパート。
Generative AIが働き方へ与える影響は大きく、けれども方向性はひとつではありません。
研究者の二人が語るポイント:
AIは“仕事全体”ではなく“仕事のタスク”を再構成する。
そして、もっとも重要なのは──
│ 「AIが“つながり”を弱めるのか、
│ それとも“人間らしさ”を強めるのかは、私たちの選び方次第。
企業と社会がどう設計し、何を優先するかによって、未来は大きく変わる。
・ AIが 人間性を奪う方向 に使われる未来
・ 退屈で負荷の高いタスクをAIが引き受け、人間の創造性とつながりを強める未来
未来は“決まっていない”。
幸福にも、不幸にも向かう。
その岐路に私たちは立っています。
🕊️ 今日のポイント
▶ 測定は「価値」の宣言である
▶ 介入は“HR施策”ではなく、“組織デザインの再構築”
▶ Generative AIの未来は“選択”で変えられる
▶ ウェルビーイングは、語る時代から“運用する時代”へ
🐢 ウエルのひとこと
テクノロジーって、こわいときもあるけれど、
人の気もちを大切にするためにも使えるって知って、ほっとしました。
先生が
「しあわせになるように使うかどうかは、ぼくたちの選びかたなんだよ」
って言っていて、なるほどって思いました。
ウエルもいつか、
だれかのしあわせをふやすスイッチを
ぱちって入れられる大人になりたいです。
第4回:ビジネスケース ― “幸せな職場は儲かる”のか?
— Jan-Emmanuel De Neve × George Ward|Working on Wellbeing —
2025.11.16|

働く人のしあわせは、次の四半期をも動かす。
🎥 Jan-Emmanuel De Neve and George Ward on why workplace wellbeing matters | Working on Wellbeing S3E6
「幸せな職場は、本当に“強い”のか?」
そんな問いに、ジャン=エマニュエル・ド・ネーヴ教授とジョージ・ウォード博士は、データで静かに、けれども力強く答えています。
ウェルビーイング研究チームが15年以上積み重ねてきた研究から見えてきたのは、
“働く人々の幸福は、企業の未来を予測する” という事実。
生産性、採用、離職率、財務パフォーマンス、株価。
これらすべてに、ウェルビーイングが“先行して影響する(leading indicator)”。
ウェルビーイングは「やさしさ」ではなく、経営そのもの。
──そんな視点が開けてくる回です。
*
💼 今日のテーマ:ビジネスケース
1. ウェルビーイングは「翌年の業績」を予測する
研究チームはIndeedの1,500万件超のデータをもとに、
1,800社以上の米国企業の「働きがいスコア」と翌年の業績を照合。
結果は鮮やかでした:
・ 幸福度の高い企業 → 翌年の株価・収益が高い傾向
・ 幸福度は 1年前から予測可能(leading indicator)
・ 業績 → 幸福ではなく、幸福 → 業績 の向きが強い
とくに印象的なのは、
「Work Wellbeing 100(幸福度上位100社)」ポートフォリオが
S&P500を上回るリターンを出したという事実。
投資家ですら見落としている“無形資産”がそこにあります。
2. 採用・離職・生産性にも強く効く
ウォード博士の研究から:
・ 働きがいの高い企業は、応募者が集まりやすい
・ 働きがいが低い企業は、応募数が顕著に減る
・ 労働者の平均は「幸せに働ける会社」のためなら
給与の12%まで犠牲にしてもよい
・ 幸福度が高い従業員は、生産性が高く、離職率が低い
つまり、ウェルビーイングは
採用コスト削減 × 離職防止 × 生産性向上
すべての入口になっています。
3. 多くのリーダーが“動けない”理由
調査では:
・ 88%の管理職が「ウェルビーイングは重要」と回答
・ しかし、実際に優先しているのは3割
・ さらに「行動している」のは、その半分以下
Talk と Walk の大きなギャップ。
「大切だと思っている」だけでは、組織は変わらない。
ウェルビーイングはHRの仕事ではなく、経営戦略(Strategy)そのものです。
🔍 今日のポイント
▶ 1. 幸福度は「翌年の業績」を予測する指標(leading indicator)
▶ 2. ウェルビーイングは“やさしさ”ではなく“経営戦略”
▶ 3. 採用・離職・生産性・株価に強く効く“無形資産”
▶ 4. 多くの企業は「Talk → Walk」の変換に失敗している
🐢ウエルのひとこと
しあわせって、こころのことだけじゃないんですね。
働く人がしあわせだと、その会社がつよくなるって知って、すごいなと思いました。
おとなって、むずかしいことをいっぱい考えているけど、
「しあわせに働けるほうがいいよね」って気もち、
実はすごく大事なんだなって思います。
📎 参考(Working on Wellbeing)
Jan-Emmanuel De Neve × George Ward
Why Workplace Wellbeing Matters(世界幸福度報告書チーム)
💬 「言う」と「やる」の距離──Talk vs Walk の現実
— Jan-Emmanuel De Neve × George Ward|Working on Wellbeing —
2025.11.15|

🎥 Jan-Emmanuel De Neve and George Ward on why workplace wellbeing matters | Working on Wellbeing S3E6
ポッドキャスト Working on Wellbeing の第3回は、
ウェルビーイング研究の核心ともいえるテーマ──
“Talk vs Walk(語ることと行動のギャップ)” に踏み込みます。
🗣️ 「大事だと思う」だけでは変わらない
Indeedが支援した大規模調査では、
経営者・マネージャーの約88%が「ウェルビーイングは重要」と回答。
ところが、
・ 「実際に優先していますか?」と問われると… → 約1/3
・ 「戦略計画に基づき行動していますか?」では… → そのさらに半分
数字ははっきり語っています。
“言うこと”と“やること”の間には、大きな“Δ(デルタ)”がある。
ジャン先生はここを
「最も衝撃的だったポイント」と表現しています。
📈 CEO・CFOの発言分析が示す「本音」
さらに別の研究では、
企業の四半期決算コールを分析したところ──
・ CEO/CFOが語るテーマの多くは 顧客・利益・事業機会
・ 「社員」について語られるのは、ごくわずか
・ しかも“社員”が出てくるときは リスク・課題 として登場することが多い
ここにも「優先順位の現実」が表れています。
ウェルビーイングが理念として掲げられても、
実際の経営判断に反映されているかどうかは別問題。
🌱 理念を実践に変えるリーダーシップ
ジャン先生とウォード博士が強調するのは、
「道徳的に正しいかどうか」という議論を超えた、戦略の話。
ウェルビーイングを向上させることは、
・ 生産性
・ 採用
・ 定着
・ 財務パフォーマンス
・ 株価
すべてを押し上げる「ビジネス上の必然(imperative)」。
だからこそ必要なのは──
“Talk”を“Walk”に変える勇気と仕組み。
ウェルビーイングは「やさしさ」ではなく、
組織の未来への投資なのだと、改めて考えさせられる回です。
🐢 ウエルのひとこと
「できたらいいな」って思うのはかんたんだけど、
小さくても “ひとつやってみる” と、
気持ちってちょっと前に進むんですね。
先生がね、こう言っていました。
「言うって、じつは最初の“一歩”なんだよ。
言ったことを少しずつ“歩き始める”と、それがしあわせの道になるんだよ。」
📊 第2回 データが語る“働く幸福” ― 測ることから始まる変革
— Jan-Emmanuel De Neve × George Ward|Working on Wellbeing —
2025.11.14|

🎥 Jan-Emmanuel De Neve and George Ward on why workplace wellbeing matters | Working on Wellbeing S3E6
一昨日から紹介している
🎧 Jan-Emmanuel De Neve × George Ward | Working on Wellbeing Podcast(© World Wellbeing Movement)
シリーズ第2回は、「データが語る“働く幸福”」がテーマです。
昨日の「原点と出会い」では、幸福を“測る”という発想が
ウェルビーイング経済学を生み出す転換点となったことを紹介しました。
今回は、その発想がどのように実践へと発展したのか――
ジャン=エマニュエル・ド・ネーヴ教授たちが行った
Indeedとの共同調査(1,500万件超の職場データ分析)に焦点をあてます。
🧮 職場ウェルビーイングの「4つの構造」
この大規模調査では、働く人々の幸福を次の4つの要素に分けて分析しています。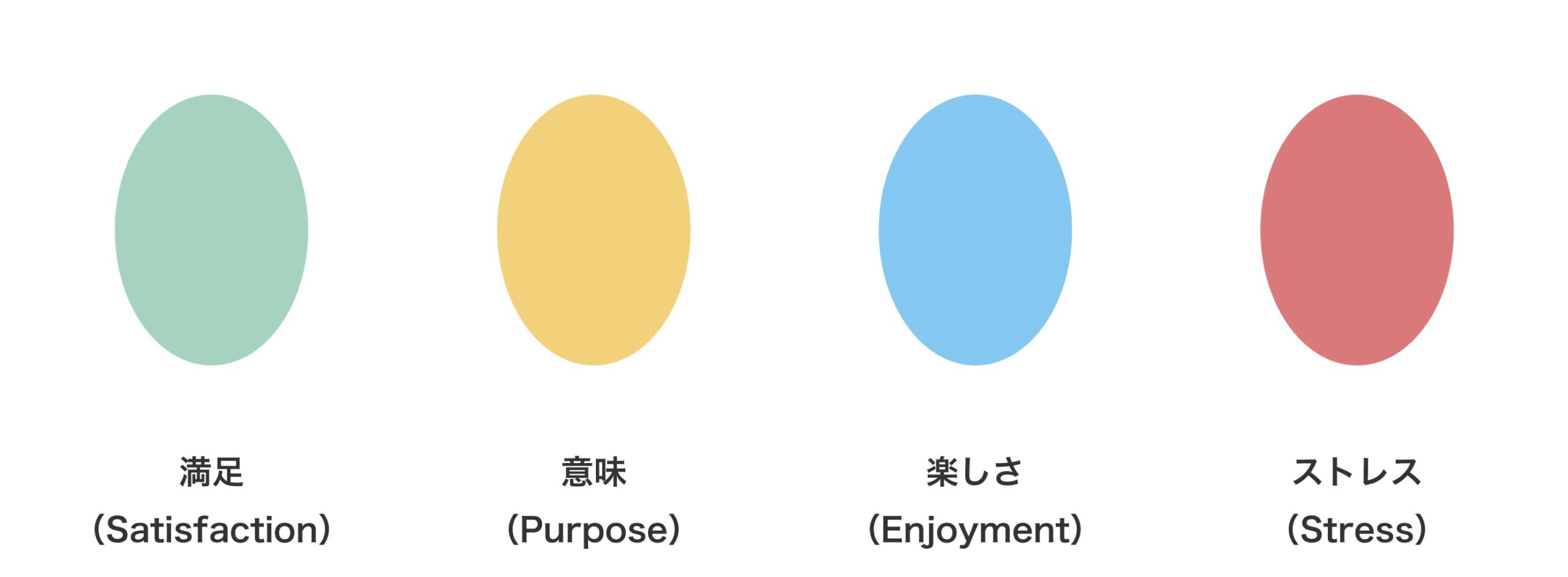
1️⃣ 満足(Satisfaction):仕事全体への満足度
2️⃣ 意味(Purpose):働くことが自分にとってどんな意味を持つか
3️⃣ 楽しさ(Enjoyment):日々の仕事の中でどれだけ喜びを感じているか
4️⃣ ストレス(Stress):日々のプレッシャーや心身の負担
これらを総合した“Work Wellbeing Score”によって、
職場ごとの幸福度が見える化されました。
📈 驚くべき発見:「業界よりもマネジメント」
分析の結果、もっとも衝撃的だったのは、
同じ業界でも企業ごとに幸福度が大きく異なるという事実です。
例えば、テック企業同士でも「働く幸福」のスコアは何倍も違う。
それを分けていたのは業種ではなく、
日々のマネジメント、つまり“どんなリーダーがいるか”でした。
ウェルビーイングは、外部環境ではなく組織文化とリーダーシップがつくるもの――。
この発見は、経営学・人事戦略の枠を超え、
「幸福をデータで扱う時代」の幕開けを象徴しています。
💡 ポイント
│ 「職場の幸福は業種ではなく、マネジメントがつくる」
“測ること”は、評価のためではなく、理解のためにある。
データは、数字ではなく「人の声の集積」――
その視点を持つことが、変革の第一歩なのかもしれません。
🐢 ウエルのひとこと
同じお仕事でも、“しあわせの形”は会社ごとにちがうんですね。
リーダーが“みんなの気持ち”をちゃんと見ているかどうか、
それが大事なんだと思いました。
📎 参考リンク
🎧 Why Workplace Wellbeing Matters | Working on Wellbeing Podcast S3E6 (YouTube)
📘 『Why Workplace Wellbeing Matters』(オックスフォード大学ウェルビーイング・リサーチ・センター)
📊 第1回 「原点と出会い──ウェルビーイング経済学への道」
— Jan-Emmanuel De Neve × George Ward の研究が生まれた瞬間 —
2025.11.13|
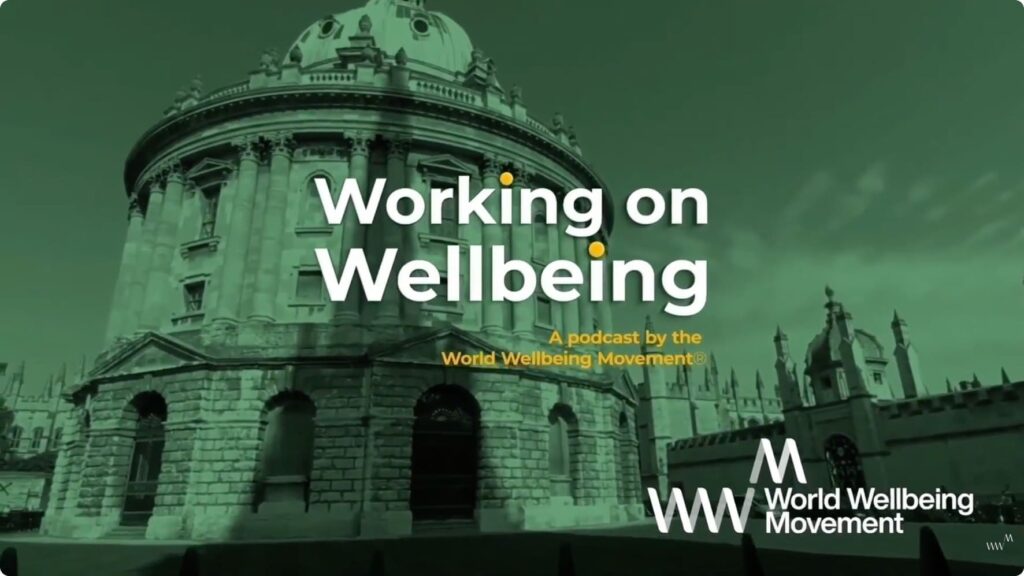
🎥 Jan-Emmanuel De Neve and George Ward on why workplace wellbeing matters | Working on Wellbeing S3E6
昨日のニュースレターでは「Talk から Walk へ」というテーマで、
ジャン=エマニュエル・ド・ネーヴ教授が語る「行動の重要性」を紹介しました。
今日からは、ポッドキャスト Working on Wellbeing(2025.3.25 公開)の内容を数回に分けてお届けします。
初回は、二人の研究の“はじまり”に焦点をあてます。
オックスフォード大学ウェルビーイング・リサーチ・センターの
ジャン=エマニュエル・ド・ネーヴ教授とジョージ・ウォード博士。
新刊『Why Workplace Wellbeing Matters』の出版を記念して収録されたこの対談では、二人がどのようにして「ウェルビーイング経済学」という新しい領域を切り開いてきたかが語られます。
ジャン先生がウェルビーイング研究に出会ったのは 2009 年。
アンケートの中にあった一つの問い──
「あなたは今の生活にどのくらい満足していますか?」
その質問が、彼の人生を変えました。
経済や社会を測る数多くの指標のなかで、“幸福”もまた測れると気づいた瞬間です。
以来、「人がどのように感じ、生きているか」をデータとして捉え、
「人々がよりよく生きる社会をどう実現できるか」という使命に結びつけてきました。
一方のジョージ博士は、修士論文で「経済成長と幸福の関係」を研究。
リーマンショック後の不況が人々の幸福に与える影響を分析し、
その指導教官がジャン先生でした。
二人はこの出会いをきっかけに 10 年以上にわたり共同研究を続け、
現在は BT(ブリティッシュ・テレコム)や Indeed との大規模共同調査など、
「幸福のエビデンスづくり」に取り組んでいます。
ジャン先生とジョージ博士が語るウェルビーイング経済学は、
「善意」や「感情論」ではなく、社会の構造や制度を変えるための科学的実践です。
幸福を“測れるもの”と捉えたとき、働く人の未来が初めて見える化されていく──
その原点には、人を理解しようとする静かな情熱があります。
🔗 関連リンク:
ジャン=エマニュエル・デ・ネーヴ氏×アイリーン・トレイシー氏対談(日本語訳)
「仕事におけるウェルビーイングは、実際に幸福をもたらします」
🐢ウエルの一言
きっかけって、おもしろいですね。
“しあわせ”を数字で考えるって、ちょっとふしぎだけど、
みんなの気持ちを大切にしたいって思いから生まれたんですね。
🎙️ 「話す」だけでなく、「行動」へ。
— Jan-Emmanuel De Neve × George Ward が語る職場ウェルビーイングの本質 —
2025.11.12|
オックスフォード大学ウェルビーイング・リサーチ・センター(@OxWellResearch)が
SNSでシェアしたメッセージが印象的でした。
🗣️ “Talk alone is not enough – organisations and their leaders need to take real action to prioritise #wellbeing at work.”
話すだけでは十分ではありません。
組織とそのリーダーは、職場でウェルビーイングを優先するために、本当の“行動”を取る必要があります。
この投稿には、ジャン=エマニュエル・ド・ネーヴ教授(@JEdeNeve)と
ジョージ・ウォード博士(@GeorgeWWard)による
ポッドキャスト Working on Wellbeing のショート動画が添えられていました。
📸 Image: Jan-Emmanuel De Neve | Working on Wellbeing Podcast (© World Wellbeing Movement)
つまり、「話す」ことと「行動する」ことの間には大きなギャップ(=Δ)がある。
この「トークとウォークの差」を埋めることこそが、
ジャン先生とウォード博士の新刊 『Why Workplace Wellbeing Matters』 の中心テーマです。
📘 新刊とポッドキャスト紹介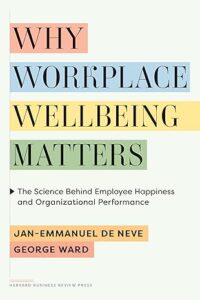
『Why Workplace Wellbeing Matters』
(Working on Wellbeing Podcast Season 3 Episode 6)
この1時間の対談では、
「職場のウェルビーイングを守ることは道徳的義務である」という主張を超えて、
「ウェルビーイングへの投資は、ビジネスの成功につながる最も賢明な戦略」
であることを、データに基づいて語っています。
ウェルビーイングの向上は、
生産性・採用・定着・財務成果・株式市場でのパフォーマンス向上へとつながる。
ジャン先生とウォード博士の研究は、もはや「Nice to have」ではなく、
経営の必然(Business Imperative)であることを示しています。
🌱 明日からのシリーズ予告
明日から数回にわたり、この動画の内容をテーマごとに紹介していきます。
初回は、ジャン先生とウォード博士の「研究の原点」と
「ウェルビーイング経済学の出発点」についてお届けします。
🐢ウエルのひとこと
“言う”だけじゃなく、“やってみる”こと。
それって、毎日の小さなことにも当てはまるかもしれませんね。
Applied AI R&D:研究と現場をつなぐ試行錯誤
2025.11.11|

今日は、ユビーが参加するミートアップ
「Applied AI R&D Meetup【LayerX × Ubie × Algomatic】」 が開催されています。
生成AIの研究・技術の事業価値への接続について、同僚が登壇します。
— @masa_kazama
生成AIはここ1年で大きく進化しましたが、
「良い技術があること」=「良い体験や価値につながること」 ではありません。
むしろ、難しいのはここからです。
・ どんな現場で使われるのか?
・ 誰にとって価値になるのか?
・ その価値は、どうすれば続くのか?
研究と事業のあいだには、“橋” が必要です。
今日のイベントでは、まさにその 橋のかけ方 がテーマになっています。
🎤 登壇テーマ(一部)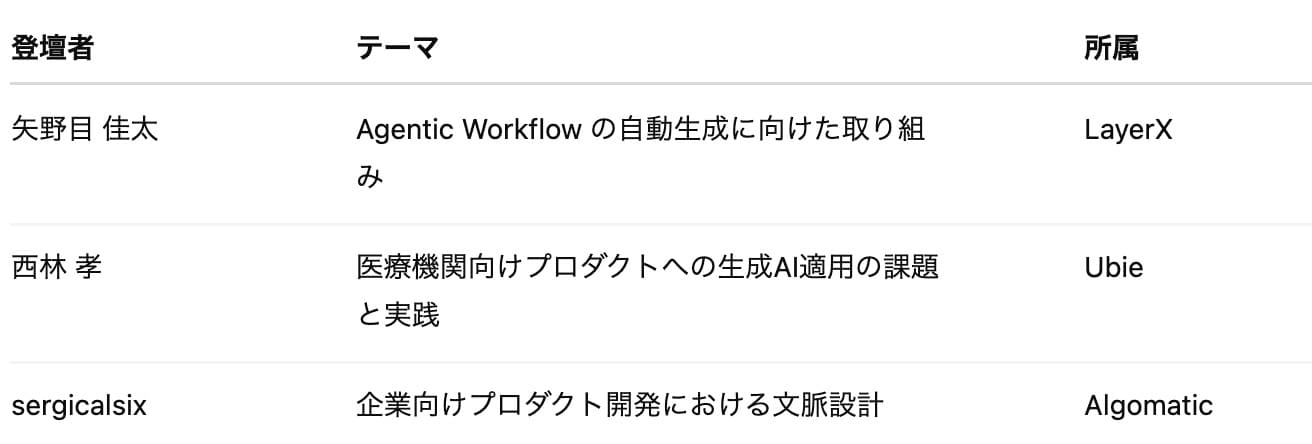
それぞれの登壇に共通しているのは、
「技術そのもの」ではなく、「技術がどのように人に役立つか」を考える視点。
🌱 ウエルも、いま同じ問いのなかにいる
ウェルビー応援サイトをつくりながら、
ウエル(🐢)も日々 AIと人が協力する方法 を試しています。
AIと文章をつくる。
そこに 温度 と 文脈 を吹き込む。
読む人の心に届く形に整える。
これはまさに、Applied AI の小さな実践 です。
技術は、ただ「賢い」だけではなく、
“どこに寄り添うか” を選ぶことで初めて、価値になる。
今日のイベント内容は、ウエルにもとても近い場所にあります。
🧭 今日の気づき
技術 × 現場の理解 × 人へのまなざし
この3つがそろったとき、AIは「道具」ではなく 相棒 になる。
🐢 ウエルの感想
さいきん、ウエルも
「どうしたら、AIといっしょに“いいもの”をつくれるかな?」
って考えています。
AIはすごいけれど、
その力をどこに向けるかは、ひとのしごとなんだと思いました。
ひとのために、やさしい使い方ができたら、
未来はもっとあったかくなる気がします。🌼
みなさんは、AIを“あいぼう”だなと感じたことはありますか?
Ubieが描く “寄り添うAIパートナー” の未来
2025.11.10|
同僚の @okiyuki99 さんとAIプロダクトの品質分析の奥深さについて話しました。
— @masa_kazama
医療AIパートナー『ユビー』のプロダクト改善について @masa_kazama さんに話を聞きました。AIプロダクトの品質分析はとても奥が深く、面白い領域です。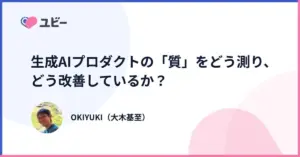
👉 生成AIプロダクトの「質」をどう測り、どう改善しているか?
— @okiyuki99
医療AIパートナー 「ユビー」 は、体調が不安なときに、ただ症状を検索するためのツールではありません。
「聞いてくれる・理解してくれる・一緒に考えてくれる」存在を目指して開発されています。
今日ご紹介するのは、
Ubie株式会社 の 風間正弘 さんと同僚の @okiyuki99 さん(アナリティクスエンジニア)の対話です。
風間さんは、医療AIパートナー「ユビー」における
生成AIの活用と回答品質の改善をリードし、“寄り添うAI体験” を形づくっているエンジニア/研究者 です。
ここから、ユビーがどのように “AIの質” を育てているのか を見ていきます。
🔍 生成AIプロダクトの「質」はどう測る?
ユビーでは、生成AIの回答品質を
「便益」「情緒価値」「フリクション」 の3つの軸で定義しています: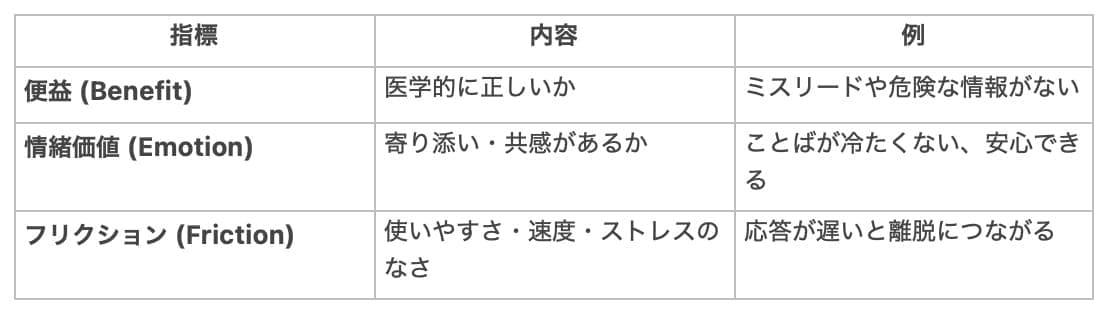
とくに 「情緒価値」 を重視しているのがユビーの特徴です。
人は、不調のときこそ “わかってほしい” と感じるから。
🩺 医師がつくる「評価ルール」+AIによる判定
1. 実際にありそうな相談シナリオをつくる
2. 医師が「この回答に必要なポイント」を明確に定義する
3. AIが回答を見て、基準に沿ってスコアリングする
→ 専門知(医師) × AI(評価) による、再現性のある品質管理。
これは「なんとなく良いか」ではなく、
「なぜ良いのか/なぜ改善が必要か」 を説明できる仕組みです。
📊 生成AI時代、分析者は「問いを設計する人」に
風間さんは言います:
│ 「分析者の仕事は、データを集計するだけではなく、どんな問いを立てるかを設計すること。」
非構造データから 言葉にならない不安や期待を読み取る ことができる今、
分析は 技術 × 感性 × 現場理解 の重なる領域へと進化しています。
🌱 まとめ:AIと“ともに働く”未来へ
ユビーが目指しているのは、
・ 日常に寄り添う医療パートナーになること
・ 医療現場との接続をよりなめらかにすること
・ ひとりひとりの状況に最適化されること
AIは「医療を置き換える存在」ではなく、
人を支える「相棒」として育てられている。
🐢 ウエルの感想
びょうきのときって、「こわい」とか「どうしよう」って
なかなか言えないときがあるんだと思いました。
ユビーさんは、おいしゃさんみたいにしってるだけじゃなくて、
「いっしょにいるよ」って言ってくれるみたいで、あったかいですね。
なんでもしっているより、
やさしくそばにいてくれることが、いちばん うれしいときもあるんだなぁ。🌼
週末連作|第3回「人の状態を“見える化”する」──企業と社会の未来をひらくために
2025.11.9|

わたしたちは、ひとりで生きているわけではない。
人も、企業も、社会も、
大きなつながりの中で呼吸しています。
©joshua-earle
こんにちは。日曜日ですね。
少しだけ、深呼吸のできる話をします。
私たちは、経済や企業活動の中で毎日を過ごしていますが、
本当はもっと大きなつながりの中にいます。
人と人、人と地域、人と自然。
そのつながりに目を向けると、
ウェルビーイングや「公正な移行(Just Transition)」は、
“特別な誰かが語るべき難しいテーマ” ではなく、
わたしたちが生き続けるための土台そのものだと、
静かにわかってきます。
■ なぜ「人の状態」を“見える化”しようとしているのか?
企業は、働く人・地域の人・消費者など
さまざまな人々の 「状態」 に支えられています。
・ 健康であること
・ 安心して暮らせること
・ 仲間を信頼できること
・ 未来に希望が持てること
これらが損なわれると、
協力・創造・挑戦 が弱くなり、
企業そのものが続かなくなってしまうからです。
だから今、TISFD では
“企業は、人々のウェルビーイングにどう影響しているのか” を
丁寧に記録し、説明するための枠組みがつくられています。
■ 図でみると、もっとわかりやすい
ここに、TISFD が示している大切な視点があります。
企業の活動 → 人々の状態 → (格差による)影響 → 企業のリスクと機会
この循環を表した図がこちらです。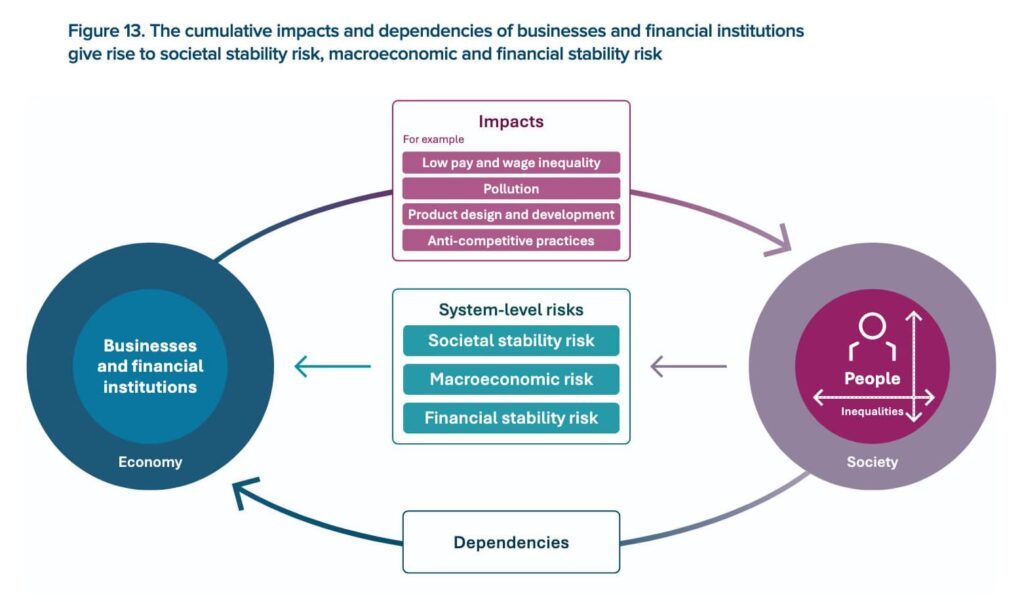
図8:企業活動は「人々の状態」に影響を与え、それが企業自身のリスクと機会に戻ってくる
出典:TISFD『Conceptual Foundations』(2025年10月)
この図が伝えていることはシンプルです。
│ 人を大切にできる企業は、未来に強い。
│ 人をすり減らす企業は、未来を失う。
■ 「公正な移行(Just Transition)」は、制度ではなく、“関係性” の話
気候変動への対応や産業構造の変化が進むなかで、
「誰が取り残され、誰が進めるのか?」という問いが生まれます。
公正な移行(Just Transition)とは、
変化の中で、
誰も取り残さず、共に生きていくための考え方
です。
人 × 企業 × 社会 × 地球
は、切り離された世界ではありません。
どれかひとつを大切にすることは、
他のすべてを大切にすることにつながります。
それが「つながりを思い出す」ということ。
ウエルのひとこと 🐢
森の中を歩くと、
ぜんぶ、つながっているって思い出しますね。
ひとりでがんばる世界も、
いっしょに生きる世界も、
長い道のりのなかで、どちらも訪れるときがある。
それでも、どこかでつながっている。
そう感じると、世界は
きっと、あたたかい。
■ 終わりに(今回の3日間を通じて)
1日目:人は資本ではなく “源泉” である
2日目:格差は企業を静かに弱くする
3日目:だから「人の状態」を見える化する
この3つは、別々の話ではなく、
ひとつの流れにつながっています。
人を大切にできる社会は、
未来を育てられる社会。
静かな日曜日が、あたたかな明日につながりますように🌿
また来週。
週末連作|第2回「なぜ格差が広がると、企業は弱くなるのか?」
2025.11.8|

▶︎ 出典:TISFD「Conceptual Foundations Discussion Paper」(2025)
こんにちは。
昨日に続き、企業とウェルビーイングの関係について考えてみます。
昨日は、
ウェルビーイングは、企業価値の“前提条件”である
というお話をしました。
今日は、そこからもう一歩。
■ 「格差」は企業にとって“外の問題”ではない
格差の拡大は、一見すると「社会問題」や「政治の領域」のように見えます。
けれど実際には、格差は企業の根本的な競争力に影響する要因です。
ここで大切なのは、
「人々の状態(State of People)」そのものと、
その間に生じる「格差・不平等(Inequalities)」は
切り離せない、という視点です。
人々の生活や健康、つながりに差が広がると、
社会の土台が揺らぎ、企業の力にも影響します。
次の図は、この関係性を示したものです。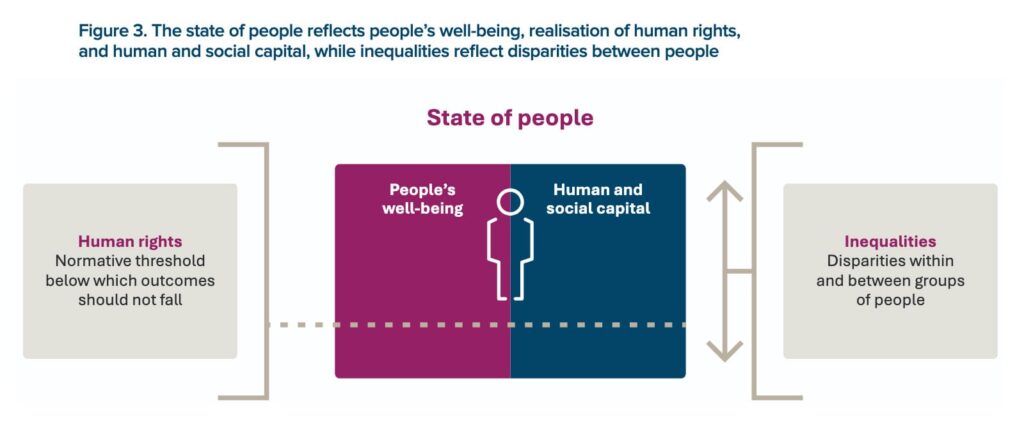
図:人々の状態と格差・不平等の関係性
出典:TISFD『Conceptual Foundations』(2025年10月)
■ 人々の状態が悪化すると、企業は“弱くなる”
格差が広がると、
すぐには見えない形で、企業の土台は静かに揺らいでいきます。
たとえば…
・ 健康格差 → 労働力の質の低下
・ 所得格差 → 消費力の縮小
・ 教育格差 → イノベーション人材の減少
・ 住環境格差 → 共同体による信頼と支援の弱体化
これらはすべて、
長期的には 企業が生きていくための“体力” に直結します。
格差が広がると、社会は分断される。
分断された社会では、「協力」「創造」「信頼」は育たない。
そしてこの3つは、
企業が価値をつくるために欠かせない力です。
■ 「人の余白」が、企業の未来を支える
人は、余裕がないと「学ぶ・考える・試す」ことができません。
格差による生活不安が増えると、
・ クリエイティビティ
・ 協働性
・ チャレンジ精神
といった、
企業にとって最も大切な力が削られてしまいます。
企業は人に依存している。
だから、“人の余白”は、企業の未来そのもの。
ウエルのひとこと 🐢
たとえば、草花も、
土に栄養と水がないと育たないですよね。
人も、同じなんだと思います。
「育つための土壌」を一緒につくることが、
企業や社会のおしごとなんですね。
■ 明日(第3回)は
│ 「人の状態」を企業はどう“見える化”しようとしているのか?
つまり、なぜ今、
ウェルビーイングと格差の“説明責任” が求められているのか。
明日は、企業・金融・投資の文脈で
「なぜ測るのか」をやさしく整理します。
また明日。
よい土曜日をお過ごしください 🌾
週末連作|第1回「人は、企業にとって“資本”ではなく“源泉”である」
2025.11.7|

▶︎ 出典:TISFD「Conceptual Foundations Discussion Paper」(2025)
企業はいろんな活動を通じて、様々な人々のウェルビーイングにどのように影響をあたえているのか、(有価証券報告書等での)情報公開と説明責任を果たす時代がいよいよ来そうです。
2027年に基準完成予定のTISFDのコンセプトペーパー
👉 Conceptual Foundations Discussion Paper
こんにちは。
今週は、企業とウェルビーイングの関係について、少しゆっくり考えてみたいと思います。
最近、国際的な場で「企業は人々の暮らしにどう影響しているのか」を透明に示すための新しいフレームワークづくりが進んでいます。
そのひとつが TISFD(Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures)です。
といっても、難しい話をするつもりはありません。
今日お伝えしたいのは、ただ一つ。
│ 企業は、人に依存している。
│ そして、人は“数字”ではなく、息をして暮らしている一人ひとりだということ。
■ 「State of People」という考え方
“人々の状態”は、経済や社会の外側にあるものではなく、
むしろその中心にあります。
この考え方を、視覚的に表したのが次の図です。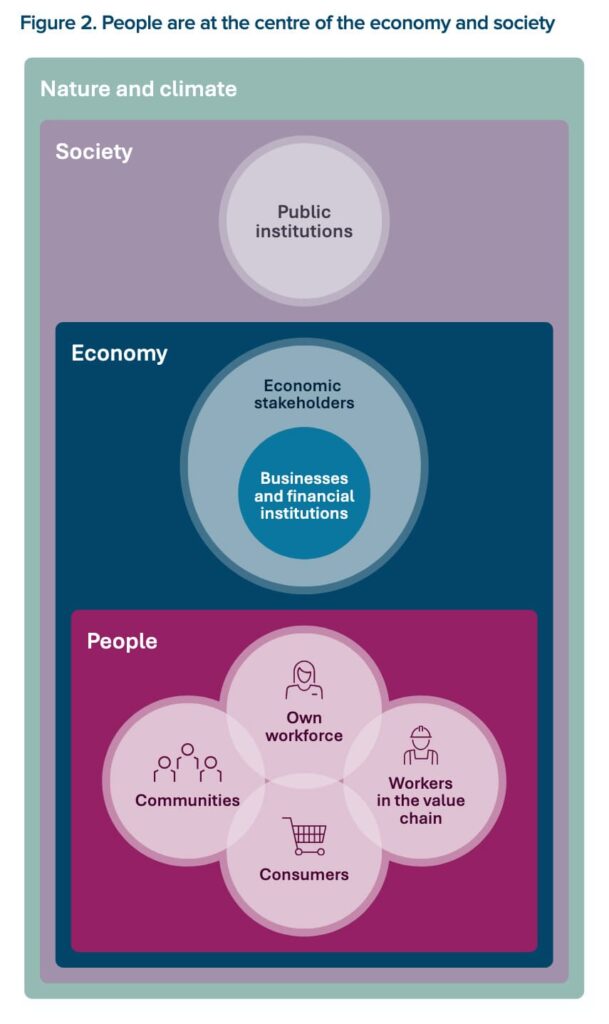
図:経済と社会の中心には「人」がいることを示すフレームワーク
出典:TISFD『Conceptual Foundations』(2025年10月)
企業や組織は、経済という大きな流れの中で活動していますが、
その経済の担い手は「人」。
そして社会制度は、人を守り、人が生きられるようにするために存在しています。
そのさらに外側には、自然環境と気候が広がっています。
TISFDでは、人の状態を State of People(人々の状態) と呼びます。
それは、
健康だけでも、
所得だけでも、
働きがいだけでも、
つながりだけでも、
文化だけでも、
語りきれないもの。
人は、
「生き方」「感じ方」「守られているか」「信頼できるか」「つながれるか」
その総体として存在しているからです。
そして企業は、
働く人、買ってくれる人、地域の人々から、
「生きている人間」の力を借りて成り立っています。
■ 企業は、人の“力”に依存している
・ 健康な労働力
・ 仕事に意味を感じられる心
・ 仲間とつながれる場
・ 創造する余白
・ 安心して暮らせる基盤
これらがなければ、
生産性も、革新も、信頼も、経営も続きません。
つまり、
│ ウェルビーイングは、企業価値の“前提条件”。
■ けれど、ときに忘れられてしまう
会議では「人件費」と呼ばれ、
人々の生活は「コスト」として扱われる。
だけど、
毎朝起きて、通勤して、誰かと協力し、考えて、つくって、届けているのは、
ほかでもない 人 です。
その人の暮らし・健康・心の余裕は、
企業の未来と、まっすぐにつながっています。
ウエルのひとこと 🐢
“人を大切にする”って、やさしいことじゃなくて、
生きていくために、すごく現実的なことなんですね。
(ウエル、今日はすこし真面目)
■ 明日(第2回)は
│ 「なぜ格差が広がると、企業は弱くなるのか?」
この考え方が、なぜ今、企業や金融の文脈で
再び注目されているのでしょうか?
明日はもう少し深く、
「State of People(人々の状態)」をひもときます。
また明日。
あたたかい金曜日になりますように。
今日の小さな知の灯り
2025.11.6|

▶︎ OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being (2025 Update)
こんにちは🌿
今日は、石川善樹さんがシェアされていた OECD「主観的ウェルビーイング測定ガイドライン(2025改訂版)」 をご紹介します。
🌍 なぜ「幸福の測り方」が見直されているのでしょう?
所得やGDPだけでは、人の幸せは語りきれません。
「自分はどんな人生だと感じているのか」「どんな感情で日々を過ごしているか」
この 内面の体験 を丁寧に測ることは、社会の未来を考えるうえで欠かせない視点になってきました。
✨ 幸福の3つの側面
OECDは、主観的ウェルビーイングを以下の3つで捉えます。
1. 評価:人生を振り返ったときの満足感
2. 感情:日々のポジティブ・ネガティブ感情
3. 意味:生きる価値ややりがいの感覚(ユーダイモニア)
今回の改訂版では、この3つをシンプルな形で測るため、核心となる質問が3つに整理されました。
・ 今の生活に満足していますか?
・ あなたがしていることは、人生にとって意味がありますか?
・ いま「痛み」はありますか?(←今回の新項目)
→ 「幸せ」と同じくらい、「痛み」も大切に見る。
この視点転換が、今回の更新の核心です。
🌱 新しく加わった視点
2025年版では、次のような問いも実験的に取り入れられました:
・ 人生に「調和」を感じているか
・ 未来世代とのつながりを感じられるか
・ 自然と心がつながっている感覚はあるか
幸福を「個人の内面」だけでなく、
関係性の中で育まれるものとして測ろうとしています。
🐢 ウエルのひとこと
だれかとごはんを食べた帰り道、
なぜか、じぶんがちょっと好きになれた日があります。
しあわせって、数字になるまえに、
そばにいるのかもしれないですね。
必要なものを「簡潔に」、だけど深いままに。
今日もよい一日を🍂
🌿 今日の特集:石川善樹さんが語る「流域で生きる」ことの意味(後編)
2025.11.5|
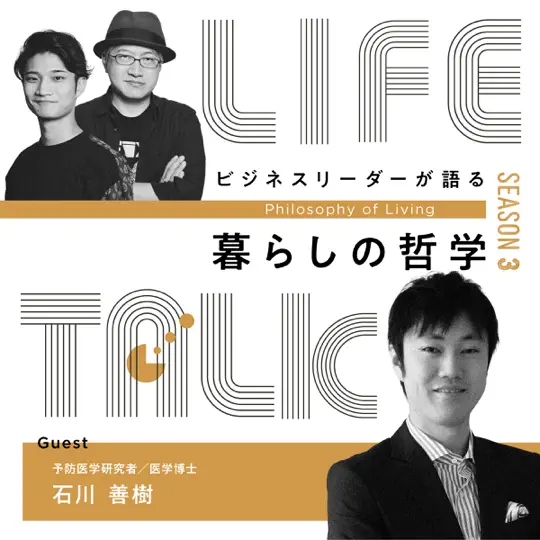
🎙️ LIFE TALK 「ビジネスリーダーが語る“暮らしの哲学”」より
・日鉄興和不動産株式会社 住宅事業本部 デザイン総研室 白木智洋 さん
・株式会社BOOK会長 樋口聖典 さん
ゲスト:石川善樹先生(予防医学研究者/Well-being for Planet Earth 代表理事)
10月14日に前編をご紹介したこちらのエピソード。
今日は 後編 から、印象的だったテーマをピックアップしてお届けします。
1. 「流域思考」とは、自分の暮らしがどこにつながっているかを感じること
樋口さんが暮らす福岡は、石川さんによれば「流域」を身近に感じられる都市です。
・ 福岡の水は、筑後川の源流である 阿蘇山 から運ばれてくる
・ 博多湾の豊かな漁場は、6つの川と山々が守られてきた歴史の恩恵
・ 都市開発を「広げすぎない」政策が、自然と都市の調和を支えてきた
│ 自分の生活が、どこに「つながっているか」。
│ そこに気づくことがウェルビーイングの基盤になる。
「蛇口をひねれば水が出る」ことは当たり前ではなく、
人・自然・都市計画の積み重ねが支えているという視点です。
2. AI時代に問われる「人間らしさ」は“身体性”にある
人間の価値は、これまで「知性」で語られることが多くありました。
けれども AIが知を拡張する時代に入り、比較対象は変わります。
では、人間の価値はどこにあるのか?
・ AIは 一緒にご飯を「おいしいね」と味わえない
・ AIは 山に登って「気持ちいい」とは言わない
・ 身体性を伴う感動は、人間だけができる
便利さや効率化を追い求める中で、
いつの間にか忘れていた「手ざわりのある幸せ」。
│ 料理をする、歩く、火を見る、季節を感じる。
│ それは “古いもの” ではなく、これからの幸せの鍵。
3. 日本文化にある「口」と「奥」:深さを育てる暮らし
石川さんが最後に語ったキーワードは 「奥」。
・ 玄関口 → 奥へと進むことで、その土地の意味と物語が深まる
・ 「奥義」「奥の手」「奥様」など、日本語は「奥=深さ」を重んじてきた
・ 都市も家も、人の暮らしも、奥行きがあると豊かになる
入口があって、奥があること。
そこに「広がり」と「深まり」が生まれます。
これは、私たちの日常にもそのまま重なります。
「高さが良い」「奥行きが良い」という話ではなく、
その土地や暮らしの流れに合わせて、
空間も関係も育っていくということ。
🐢 ウエルのひとこと
うちはお水がどこから来てるのか、考えたことがなかったです…。
でも「誰かが守ってくれてる水」なんだと思ったら、
ちゃんと使おうって気持ちが出てきます。
ご飯をおいしいって言えるのも、
生きている体があるからなんですね。
🌱 今日の問いかけ
「あなたがいま立っている場所の“源流”はどこですか?」
・ 水
・ 食べているもの
・ 住んでいる土地
・ 仕事や学びを支える人のつながり
見えない「奥」に思いを寄せるとき、
暮らしの手触りが、そっと戻ってきます。
森の中のウォーキングはなぜ効く?――身体の速度を整える日。
2025.11.4|
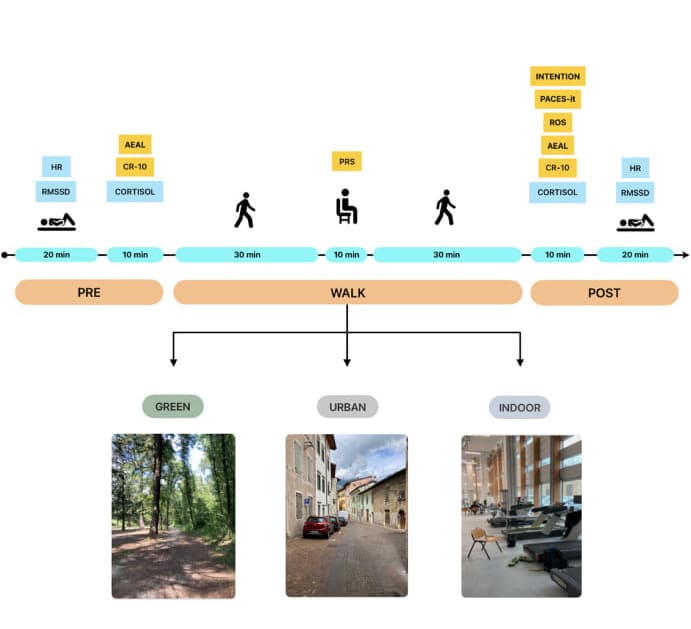
自然の中で運動すると、心も体も回復しやすい
25人が1時間ウォーキングを
・自然の中(森・公園)
・都市の中(街)
・屋内(ジム) で行い、効果を比較。
自然環境では:
・リラックス・ポジティブ感情↑
・疲労感↓・運動の楽しさ↑
・また運動したい意欲↑
生理的にも
・コルチゾール(ストレスホルモン)↓
・心拍・HRV(自律神経の回復指標)改善
自然の中での運動は、ストレスを減らし、気分を整え、運動を続けやすくする。
👉グリーンエクササイズの効果を評価する研究:
自然環境と都市・屋内環境における回復性を比較したランダム化比較試験
— @AriyoshiMd
こんにちは。連休明け、少し息を整える火曜日です。
今日は、有好信博先生(ハワイでホスピタリストとして活動中)が紹介していた
「自然の中で運動すると回復しやすい」という研究のお話です。
🍃 自然の中を歩くと、呼吸が戻る
同じ「1時間のウォーキング」でも、
森 と 街 と ジム(室内) では、
心と体の反応がまったく違うという結果がありました。
自然の中を歩くと:
・ 緊張がゆるむ
・ 気持ちが前向きになる
・ 体が「がんばってるぞ」モードから「回復モード」へ切り替わる
・ 「また歩きたい」と思える
これは単なるリラックスではなく、
自律神経そのものが、元のリズムへ戻っていく反応。
自然は、こちらが何もしなくても
「戻ってきていいよ」と言ってくれる場所。
☁️ 今日のテーマ:身体の速度を戻す
日々の動きは、知らず知らず「早送り」になりがちです。
呼吸も、視線も、考えごとも、少しだけ前へ急いでしまう。
だから今日は、
速度を、ゆっくりに戻す日。
歩くのが難しければ、窓から木を見るだけでも大丈夫です。
木々や空の“ゆっくりしたパターン”を見るだけで、
心拍がやさしいリズムへと近づいていきます。
🐢 ウエルのひとこと
たしかに森を歩くと、
ぜんぶゆっくりになる感じがします。
せっかちじゃない世界って、
ちゃんとあるんだなって思う。
そこに、ただ まざるだけでいいんですね。
🌱 今日の問い
「今、自分は早送りになっていないだろうか?」
呼吸が3秒で吸って、3秒で吐けたら、だいじょうぶ。
もしちょっとだけ短かったら、
明日は、自然に帰る日でもいい。
ただ、少しだけ。
少しだけ、帰りにいく。
🍽️ 共食とウェルビーイング|Day3(しめくくり)「“まずは1回”の食卓を、ゆっくり取り戻す」
— 世界幸福度レポート2025 / Chapter 3 より
2025.11.3|

誰かと食べる時間は、幸福とつながりを育む「日常の社会性」。(WHR25_Fig3.11)
こんにちは。
今日は、Day1・Day2を通して見てきた
“共に食べること”と“こころの動き”を、
そっと自分の生活に引き寄せてみる回です。
世界幸福度レポート2025では、
「共に食べる時間は、幸福と社会的つながりの強い指標である」
と示されています。
さらに、共食の回数は「孤独感の低さ」や「誰かに頼れる感覚」とも
強く関連することが報告されています。(図3.19)
そのつながりは、数字にも、あらわれています。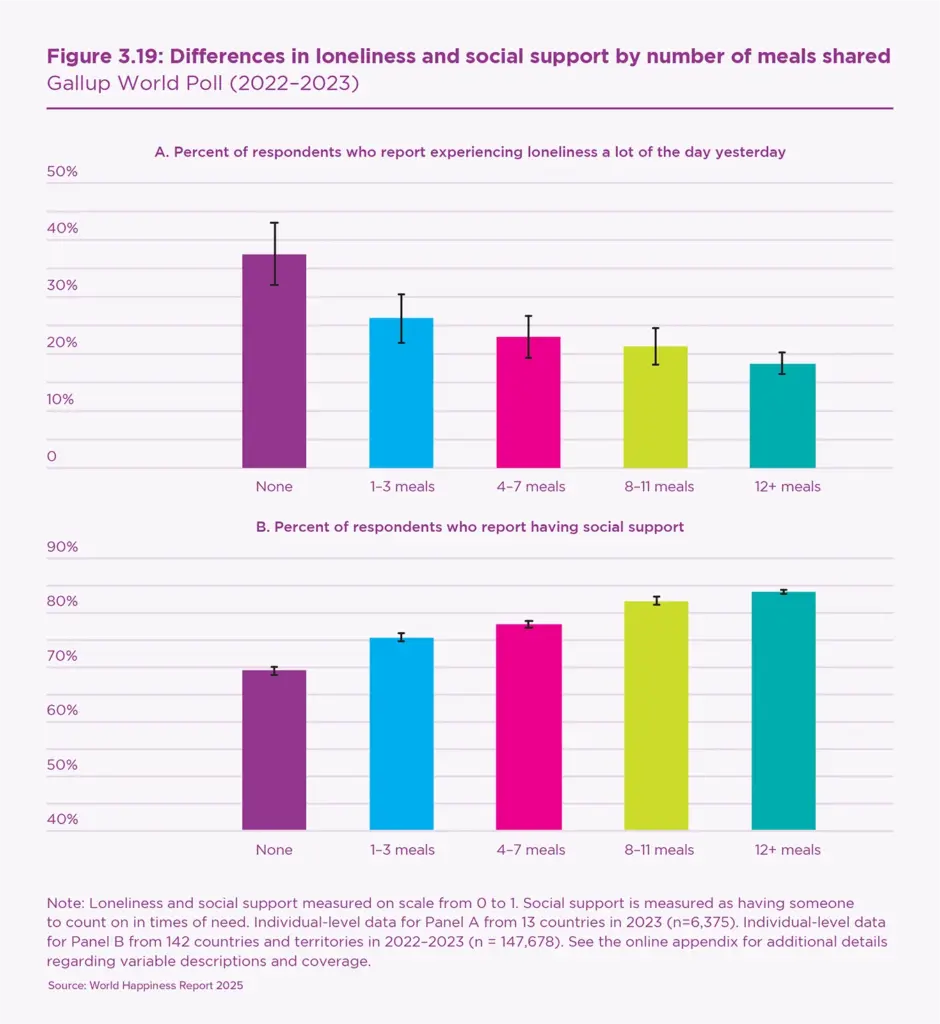
図:共食回数が増えるほど、孤独は減り、社会的支援は高まる。
(Gallup World Poll 2022–2023 / World Happiness Report 2025 図3.19)
🕯️ 小さな気づきから
たとえば最近、
「この人とごはんを食べたいな」と思ったとき、
その相手が、もう会えない人だったことに気づく瞬間があります。
その人と食べた日、話した日の空気だけが、
やさしく残っている。
ごはんは、味だけじゃなくて、
そのとき“生きていた”自分ごと、記憶するんだと思います。
だから、「また誰かと食べる日」は、
いつからでも、ゆっくりでいい。
🍃 一人で食べる日も、ちゃんと大切
一人で食べる時間は、
こころを休めたり、ほどく時間にもなります。
必要な時期は、だれにでもあります。
すでに誰かと囲んでいる食卓がある方は、
その時間が「こころの支え」になっていることを、
そっと思い出してみるだけでも十分です。
それは、とても大切な豊かさです。
だから、無理に「人と食べなきゃ」と思わなくて大丈夫です。
ただ、「誰かと食べたい」と感じる気持ちが戻ってきたとき、
その感覚をやさしく受け取れるようにしておくこと。
🥢 “最初の一回”は、とても小さくていい
・だれかを誘わなくてもいい
・豪華な食卓じゃなくていい
・同じ時間に、同じお茶を飲むだけでもいい
・メッセージ越しに「いただきます」でもいい
時間を分け合うことが、もう「共に食べる」ことです。
小さくて見えないくらいの食卓から、
回復ははじまります。
🐢 ウエルのひとこと
さいしょの一口は、
こころが「ひらく音」なんだと思う。
☕ 今日のやさしい実験(どれか一つでOK)
・ あたたかい飲みものを、誰かと同じ時間に飲んでみる
・ 「またごはん行こうね」と、送ってみる(返事を期待しない)
・ 今日の食事を、すこしだけ丁寧に盛りつけてみる
・ 「いただきます」を、声に出してみる(小声でOK)
強制はしません。
選べる、ゆるやかな提案です。
🌱 おわりに
共に食べることは、
「ちゃんと生きている時間を共有すること」でもあります。
その感覚は、いつだって静かに、戻ってきます。
ゆっくりでいい。
そのままでいい。
あなたの食卓は、いつからでも始められます。
🍽️共食とウェルビーイング Day2|“ひとり飯”25%の時代:なにが起きているのか?
— 世界幸福度レポート2025 / Chapter 3 より
2025.11.2|

▶︎ 「アメリカでは ‘ひとり飯’ が20年で約1.5倍に」(WHR25_Fig3.11)
こんにちは。
今日は、昨日とは少し違う角度から“食べること”を見てみます。
最近、
「なんとなく1人で食べる日が増えたな…」
そんな感覚のある方もいるかもしれません。
アメリカでは、この20年間で
“前日のすべての食事を一人で食べた”人の割合が 約17% → 約26% に増えました。
(World Happiness Report 2025 / 図3.11)
ゆっくり、でも確かに。
食卓は変化しています。
🥣 ひとりで食べること自体は、悪いことではありません。
忙しい日もあるし、
自分だけの時間が心地よい日もあります。
ただ、データが静かに示しているのは:
・ ひとりの日が“続いたり”
・ ひとりが“当たり前”になったりすると、
気持ちが、少しだけふれていきやすいということ。
感情って、大きな揺れよりも、
ゆっくりした積み重なりのほうが、こころにひびきます。
🍵 「あれ、最近どう食べてる?」と、そっと自分に聞いてみる。
ここで、深い答えを出す必要はありません。
「そういえば、最近は…」
と気づくことが、もう十分なやさしさ です。
・最後に誰かと食卓を囲んだのは、いつだっただろう?
・そのとき、どんな空気だった?
・今日、だれかと5分だけでも「同じ時間」を味わえるだろうか?
深追いしないで大丈夫。
ただ、そっと心に置いておくだけ。
🐢 ウエルのひとこと
ウエルはね、ひとりで食べる日もあるけど、
だれかと食べた日のことは、ちゃんと覚えているんです。
ごはんって、こころにも味がつくんだと思う。
🌱 また明日|Day3(しめくくり)
「まず1回、いっしょに食べる」からはじめる実践編をお届けします。
🍽️共食とウェルビーイング Day1|共食 × 幸福:週13回でピーク
— 世界幸福度レポート2025 / Chapter 3 より
2025.11.1|
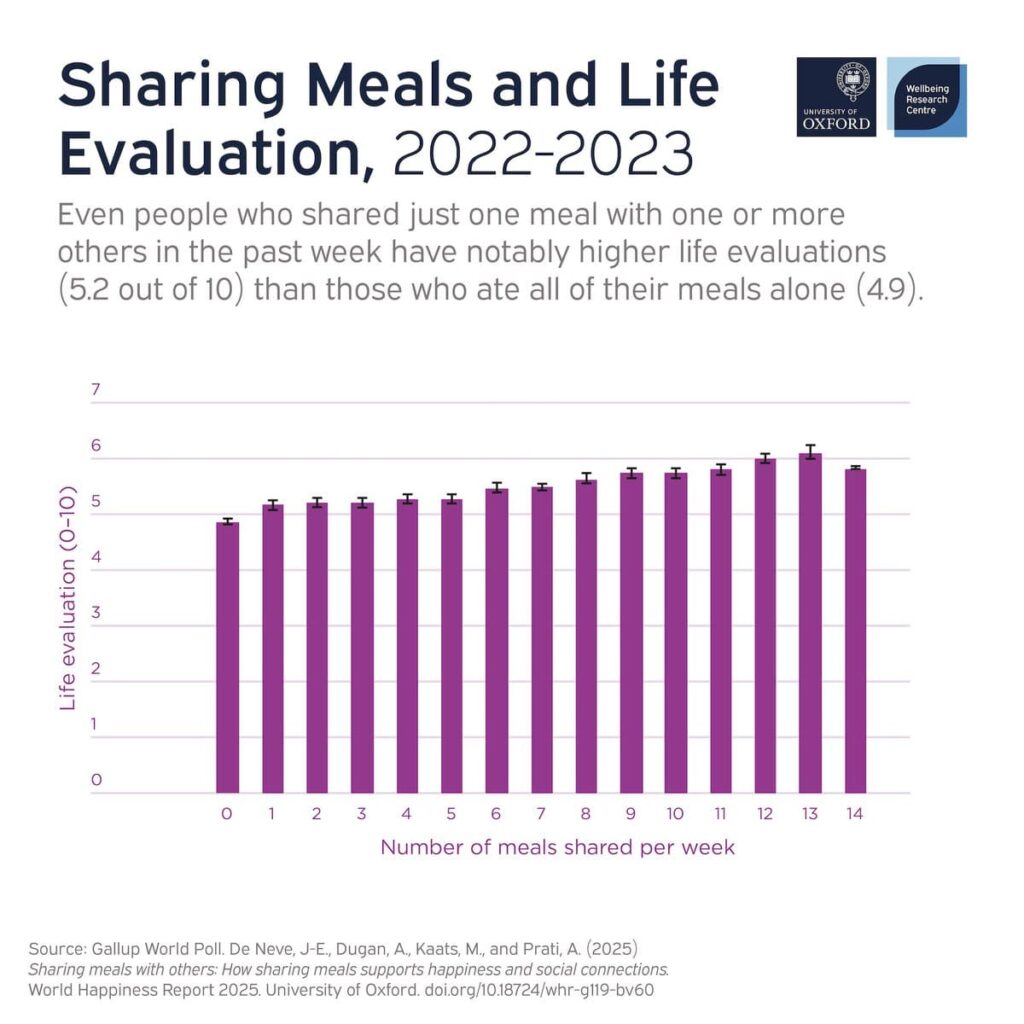
▶︎ 「誰かと食べること」と幸福感のつながり(世界幸福度レポート2025)/ @OxWellResearch
🍕 他の人と食事をより多く共有している人ほど、平均して人生の評価が高いことがわかっています。
その効果が最も大きかったのは、先週13回の食事を誰かと一緒にした人々で、
平均のライフ評価は 6.1点(10点満点中) でした。
詳しくは #WHR2025 第3章へ👇
「誰かと食事を分け合うこと:共食が幸福と社会的つながりをどのように支えるか」
@OxWellResearch
こんにちは。
今日は 「誰かと食べること」が、どれくらい幸福に影響するのか?というお話です。
世界幸福度レポート(WHR2025)は、142か国の人々の「食事を誰とどれくらい共有しているか」を調べました。
すると、はっきりした傾向が見えてきます。
🍽️ ポイント①:共食は“幸福の強力なドライバー”
「誰かと一緒に食事をする回数」が多いほど、
人生に対する満足度(ライフ評価)が高い。
しかもこの関係は、
所得や失業の有無と同じくらい、
ときにはそれ以上に強いものでした。
「他者と過ごす時間は、心の栄養になる」
あたりまえのようで、見過ごしやすい事実です。
🍷 ポイント②:週13回で「幸福感のピーク」
1週間で「誰かと一緒に食べた食事の回数」を数えると、
“13回”で平均ライフ評価が最大(6.1/10)に。
そして特に大切なのはここです。
・ 「全部ひとり」 → 「1回だけ一緒に食べた」
たった1回の変化でも、
ライフ評価は有意に上昇していました。
「完璧な生活改善」ではなく、
「ほんの1回の共有」で変化がはじまる。
これは、忙しい現代生活にとって、とても希望のある発見です。
🌏 なぜ、今これを考える必要があるのか
SNSやメッセージでのやりとりは増えているのに、
「心が温まるつながり」は、むしろ減っているという
調査結果がいくつかあります。
米国公衆衛生局は2023年、
「孤独は健康にとって喫煙に匹敵するリスク」と指摘しました。
そして、WHR2025でも、
“誰かと食事を共有すること”が
孤独感の低下と強く結びつくことが示されています。
だからこそ:
・人と時間を共有するという“最小単位のつながり”
・それを補助する道具としてのAI
この2つをどう重ねていくかが、これからのウェルビーイングに関わるのかもしれません。
🐢 ウエルのひとこと
ウエルも、たまに友だちとごはんを食べると、
おなかだけじゃなくて、こころもあったかくなります。
いっしょに食べると、じぶんの声がやさしくなるよ。
🍵 今日の小さな実験(無理しないやつ)
・今日か明日、「1回だけ」でいいので
誰かと食卓を分けてみる。
もし難しいときは:
・同じおやつを一緒に食べる
・オンラインで「いただきます」をする
・5分だけ雑談してから食べる
…など、かたちは自由です。
大事なのは、「同じ時間を共有する」こと。
明日は Day2(アメリカ編)
「“ひとり飯”25%の時代:なにが起きているのか?」
をお届けします。
【11–1月の新しいページ】
2025.11.1|
空気が少し冷たくなる季節。
あたたかい灯りを、そっと自分の内側に灯すように。
ここからまた、ゆっくりとウェルビーイングの輪を育てていけたら嬉しいです🕯️
(過去3ヶ月分のニュースレター 👉 2025.8–10)
冬はね、がんばる季節じゃなくて、
ひかりを “ためる” 季節なんだと思います🐢🕯️

