平凡な日常が続いていく「ゼロ地点」は、馴染み深く安心できる場所です。けれどもほんの少しだけ、何かが起きる未来振り返りへの期待が欲しい─そんな心理に応える「Compass 0(コンパス 0)」です。
本ニュースレターは、「ウェルビーイングな世の中を目指したい!」という思いをもとに制作しています。研究者の取り組みやアイデアに基づき、私たちが得た気づきや感じたことを共有し、今後の研究や実践に役立てることを目的としています。また、読者とのウェルビーイングな関係を大切にしています。引用文以外の内容は、すべて執筆者個人の見解であり、特定の機関の公式見解を表すものではありません。皆さまからのフィードバックをお待ちしております。
※最終更新2025.10.31(金)23:59 / 次回更新:11.1 ニューページへ
Belonging──「自分らしくいていい」と思える場所の力
2025.10.31

©sj-objio-y
👥 Belonging(所属感) とは、
自分らしい姿のままで受け入れられ、安心し、支えられていると感じられること。
これは 職場のウェルビーイングを左右する大切な要素です。
詳しくは、オックスフォード大学の
ジャン=エマニュエル・ド・ネヴェ先生 による
@McKinsey Author Talks の対談をご覧ください。👇
Author Talks:あなたの職場の人たちは、幸せに働けていますか?
Belonging(所属感)とは、
自分がそのままの自分で受け入れられ、安心し、支えられている感覚のこと。
そして、ジャン=エマニュエル・ド・ネヴェ先生は
この「Belonging」が、職場ウェルビーイングの核心であると語っています。
なぜなら、私たちは人生の多くの時間を“働く場所”で過ごすから。
そこで感じる「大切にされている感覚」は、
その人の日常や家庭、地域社会まで、
静かに、でも確かに広がっていきます。
*
でもこれは、職場だけの話ではありません。
今日はハロウィンでもありましたね。
仮装をして、役割をまとって、人と会う日。
でも本当にほっとできるのは、
仮装(役割)を脱いだあとも一緒にいられる関係。
Belonging は、
“がんばってつながる” ことではなくて、
「そのままでいていいよ」
と、やさしく灯る場所のこと。
*
🧭 AI時代に、Belongingはもっと大切に
AIが仕事の“量”を変えていくとき、
仕事の“質”を支えるのは、人と人のつながり。
・誰と働くか
・どう受け入れられているか
・自分はここにいていいと思えるか
それが、明日の仕事に向かう力になります。
🐢 ウエルのひとこと
今月、体がちょっと弱っていて、
無理をせずに、静かにページの整理をしていました。
たぶんBelongingって、
元気なときの「一緒」だけじゃなくて、
弱いときの「そのまま」も許してくれる場所なんだと思います🐢🍂🌱
✍️ 編集後記(10月の終わりに)
今月も、ここにいてくださり、ありがとうございました。
成果の前に、「場」がある。
役割の前に、「人」がいる。
ウェルビーイングは、きっと “あいだ” のところで、
そっと生まれてくるものなのかもしれません。
明日から11月。
また、少しずつ、やさしく歩いていきましょう。
ここにいてくれて、ありがとうございます。
🕊️🌿
言葉とAIのあいだで──風間正弘先生の新しい研究が始まりました
2025.10.30|

©annie-spratt
いろんなご縁がありまして、今月から国立国語研究所の横井(@sho_yokoi )さんのところで、外来研究員としてAI for Science/Researchや人文情報学の研究をご一緒することになりました。生成AI時代の新しい可能性がすごくおもしろいです。
──@masa_kazama
風間正弘先生(Ubie / エンジニア・研究者)が、
国立国語研究所での外来研究員として新たな一歩を踏み出したそうです。
AIと人文学。一見遠いようでいて、実はとても近い領域です。
なぜなら、「幸福」も「文化」も、ことばを通して形になるから。
人と人が理解しあうときも、
心が通う小さな瞬間も、
同じ場所で働く仲間と関係を育てるときも。
そこには、いつも ことば がある。
AIが高度化した時代にこそ、
「文脈を感じること」や「ことばのあたたかさ」が、より大切になっていきます。
風間先生は、以前こんな言葉を残していました。
「学生の頃に、企業の方の講義にすごく影響を受けたので、
今度は自分も何かを提供できたらありがたいな。」
“受け取ったものを、今度は手渡していく”。
この姿勢そのものが、ウェルビーイングの循環だと感じます。
🐢 ウエルのひとこと
ことばって、ただ意味を伝えるだけじゃなくて、
「気持ち」や「想い」まで運んでくれるんですね。
でも、ことばって、
一度こわかった経験があると、
やさしいはずの言葉まで、痛く聞こえてしまうときがあります。
それでも、“やさしさの流れ” は、
いつもひとりではなくて、
世界のどこかで静かにつながっているんだと思います🐢🌱
✍️ 編集後記
この3日間、深い研究に潜り込んでいました。
今日はすこし、呼吸がしやすい話題でしたね。
知る → 考える → 感じる → つながる。
ウェルビーイングは、
いつもその“あいだ”で、静かに育っていきます。
明日は10月最終日。
3ヶ月の締めにふさわしい「Belonging」の話をお届けします🕊️
🧠 今日の研究紹介|「過激な行動」はどこから生まれる?
2025.10.29|

©mohamed-nohassi
新しい研究では、65カ国のデータをもとに
「なぜ人は暴力を正当化してしまうのか」を機械学習で分析しました。
その結果、テロリズム支持は宗教よりも、
・ 暴力を“普通”だと感じること
・ ルールを状況に応じて曲げてもよいと考えること
・ 強い支配や権威を求めること
といった 世界の捉え方 と強く結びついていることが分かりました。
Who Considers Terrorism Justifiable? A Machine Learning Analysis Across 65 Countries
── Mohsen Joshanloo
「テロリズム支持」はよく「宗教的な過激さ」だけで語られがちです。
けれど、現実はもっと複雑です。
モーセン先生は、65カ国・360の要因を機械学習で分析し、
「どんな価値観が“暴力を正当化する気持ち”につながるのか」を調べました。
その結果、見えてきたのは…
🔍 結果をひとことで言うと
暴力を肯定する人は、宗教より “世界の見え方” に共通点がある。
特に関わっていたのは、次の3つの特徴でした:
① 暴力の“当たり前化”
社会や人間関係での攻撃を普通とみなす
例:「力で解決してもいい」
② 道徳のゆらぎ(moral flexibility)
状況次第でルールや誠実さを曲げても良いと考える
例:「嘘や不正も場合によってはOK」
③ 権威主義(authoritarianism)
強い支配や宗教的権威を重視する
例:「強い指導者がいれば民主主義は必要ない」
つまり、
「宗教だから過激になる」のではなく、
“世界をどう見ているか” が暴力の正当化に影響する。
ということです。
🕊️ この研究がそっと教えてくれること
暴力は、遠い場所のニュースだけの話ではなく、
私たちの日常のコミュニケーションと地続きです。
・ 相手を理解する前に、切り捨ててしまうこと
・ ちいさな嘘を「まあいいか」と流すこと
・ 誰かに「強さ」や「支配」を求めてしまうこと
こうした“心の姿勢”の積み重ねが
社会全体の空気をつくります。
だからこそ私たちは、
日常の対話や態度から、静かに平和を育てていけるのだと思います。
🐢 ウエルのひとこと
こわいことって、
ある日いきなりおこるんじゃなくて、
ちいさな言葉や ふるまいの積みかさねなんですね。
だからこそ、
やさしく話したり、
だれかの気持ちを「わかろう」とすることは、
ちいさいけれど、
とても大きいことだな、と思いました。
☕ 今日の問いかけ
あなたの中にある
「まず聞く」や「やわらかく接する」時間、ありますか?
今日できることは小さくていい:
・ 相手の話を最後まで聞く
・ 「ありがとう」を言う
・ 自分に対してもやさしくする
それらは、
“平和をつくる練習” です。
🌱
こころがふわっと戻る時間が、どこかにありますように。
読んでくれて、ありがとうございます 🌾
🧠 今日の研究紹介|“幸福を生み出す力”は国によって違う
2025.10.28|

©melody-zimmerman
私たちは、国の幸福度ランキングを見るとき、
“どの国が一番幸せか”という結果だけに注目しがちです。
しかし、国ごとにスタート地点の“富の量”は大きく異なります。
だから大切なのは、
その国が持つ資源を、どれだけ上手に幸福へ変換できているかです。
Why Some Countries Are Happier Than Their Wealth Suggests
── Mohsen Joshanloo
昨日は、心の「余白」や「なんとかなる感」についてお話しました。
今日はこの視点を、個人 → 社会へと広げてみます。
🔍 研究のポイント
モーセン先生は世界116カ国を分析し、
WALS(Wealth-Adjusted Life Satisfaction)
=「富が幸福にどれだけ変換されているか」を示す指標を提案しました。
つまり、
・ どれだけ富があるか(GDP) ではなく、
・ 富がどれだけ幸福に“なっているか” を見ます。
その結果…
“幸福を生む効率が高い国”:ニカラグア / ネパール / キルギス など
“富はあるのに幸福につながりにくい国”:韓国 / 香港 / バーレーン など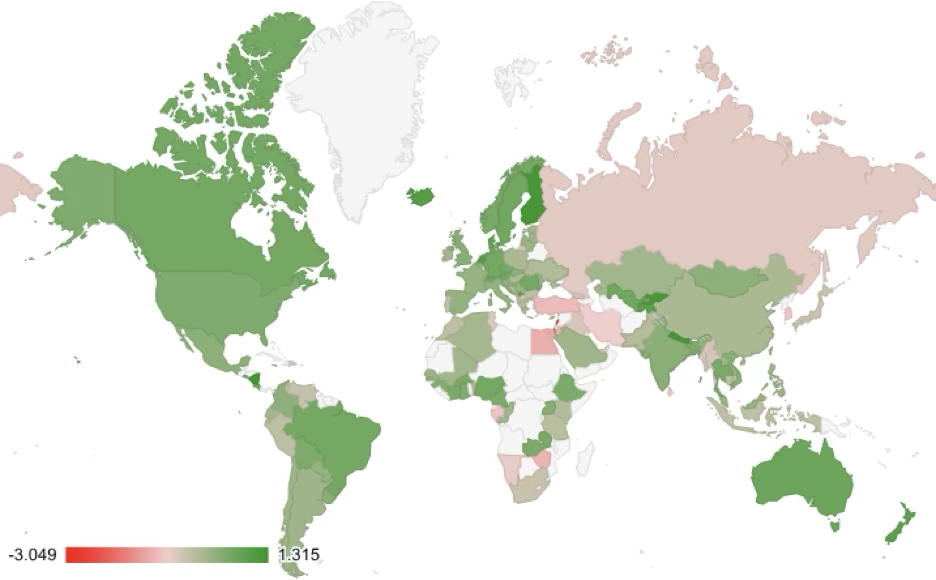
国別世界地図(WALS)
では、幸福を生み出す“力”は何でできていたのか?
・ 良い仕事の体験(裁量とやりがい)
・ 人生の選択自由
・ 日常の楽しさ・味わい
・ 助け合いやつながり(社会的資本)
幸福は「どれだけ持つか」ではなく、
「どう使うか」「誰と生きるか」から生まれていたのです。
🐢ウエルのひとこと
おかねやものを「いっぱい持つこと」が
しあわせに近いのかな、って思ってたけど、
「どうつかうか」で
しあわせの形って、ぜんぜんかわるんですね。
いっしょにごはんを食べたり、
だれかをてつだったり。
そういう時間が、しあわせをつくっていくのかもしれないなと思いました。
☕ 今日の問いかけ
・ あなたは今、「持っているものを幸福に変換する時間」を持てていますか?
・ その変換を助けてくれる 人 / 場所 / 習慣 はどこにありますか?
今日できることは、ほんとうに小さくていい。
誰かと話す / 一緒にごはんを食べる / 「ありがとう」を言う。
それは、
社会の中にある “幸福を生成する火” に
そっと灯りを足す行為です。
🌱
🧠今日の研究紹介|Financial Well-being は「心のあり方」で決まる
2025.10.27|

©kateryna-hliznitsova
Financial Well-being は「心のあり方」で決まる
高齢期の「金融的ウェルビーイング」は、年齢や収入といった“背景(デモグラフィック要因)”よりも、心理的な要因に強く影響されます。
私の新しい機械学習研究では、47の予測因子を比較しました。
特に大きな影響を持っていたのは、
1. 慢性的なストレスの少なさ
2. 楽観性
3. 「自分には選択肢がある」という感覚(コントロール感)でした。
── Mohsen Joshanloo
昨日は、「好奇心は毎日ゆらぐ」という研究を紹介しました。
私たちの心の豊かさは、感情や気分の“安定性”に影響される、という話でしたね。
今日は、視点を「心」から「時間軸(人生のステージ)」へと広げます。
年齢を重ねたとき、私たちの“経済的な安心感”は何によって支えられているのでしょうか?
🔍研究紹介
Mohsen Joshanloo, 2025
Financial Well-Being in Older Adults: A Machine Learning Analysis of 47 Predictors
結論から言うと──
高齢期の 金融的ウェルビーイング(お金に関する安心感や満足感) は、
収入や資産よりも「心の要因」によって左右される と示されました。
研究では、以下の 47の要因 を機械学習で比較しました:
・ 経済状況(収入・資産など)
・ 家族構成
・ 健康習慣
・ 教育レベル
・ 心理的要因(ストレス・楽観性・自己効力感 など)
その中で、影響の大きかった上位3つは:
1位
要因:慢性的なストレスが少ないこと
説明:不安に飲まれすぎない力
2位
要因:楽観性(optimism)
説明:「なんとかなる」と思える力
3位
要因:選択肢があるという感覚(perceived control)
説明:状況に主体性を感じられる力
一方で、収入や家族背景といったデモグラ要因の影響は弱い ことも明らかになりました。
唯一やや影響があったのは「教育レベル」です。
つまり、金融的ウェルビーイングとは、
“お金の量”よりも、
「安心して未来を考えられる心の余白」を持てるかどうか
のほうが重要なのです。
🐢ウエルのひとこと
おかねが“いっぱい あるか”じゃなくて、
“なんとかなる”って思えると、こころが軽くなるんですね。
その“なんとかなる”っていう気持ち、
ひとりじゃ育てるのむずかしいときもあるから、
だれかとごはん食べたり、はなしたりするの、大事だなと思いました。
☕今日の問いかけ
・ あなたにとって、「なんとかなる」と思える瞬間はどんなときですか?
・ その感覚を育ててくれる人、場所、習慣はありますか?
今日、ほんの少しだけでも
心の「余白」を増やす行為 をしてあげられたら、十分です。
深呼吸、散歩、ゆっくりお茶、
そして「今日はもう頑張ったな」と言うこと。
それは、未来の自分のウェルビーイングを支える
とても大切な“金融的投資”です 🌱
🧠今日の研究紹介|「好奇心」は毎日ゆらぐ
2025.10.26|

©getty-images
小さな動きで、戻ってくる好奇心。
「好奇心」は毎日ゆらぐ この“ブレ”が大きいほど、うつ症状が強く、人生満足度やウェルビーイングは低い傾向
・幸福感や身体活動が多い日は好奇心も高い
・抑うつ気分が強い日は好奇心が下がる
・身体活動 → 気分改善 → 好奇心↑ という間接的なつながりも確認
「安定した好奇心」を保てる人ほどウェルビーイングが高い。日々の運動や気分マネジメントが、好奇心を支え、結果的に人生の質を高めるカギ
👉 Within-person variability in curiosity during daily life and associations with well-being
— Nobuhiro Ariyoshi MD(@AriyoshiMd)
ハワイでホスピタリストとして活動されている
Nobuhiro Ariyoshi MD(有好 信博先生) が紹介していた研究から。
私たちが「知りたい」「やってみたい」と思う 好奇心 は、
毎日すこしずつ変化しています。
そして、この揺れが 大きすぎると、
・ うつ症状が強くなりやすい
・ 人生の満足度が下がりやすい
ことが分かりました。
一方で、好奇心が比較的“安定している”人は、
・ 自己成長を実感しやすく
・ 毎日に意味や楽しさを感じやすい
傾向があります。
では、好奇心を支えるものは何か?
研究はこう示しています:
身体を動かす → 気分が整う → 好奇心が戻ってくる
たとえば、
・ 5分のストレッチ
・ 外に出て深呼吸しながら歩く
・ 「今日はこれだけやる」と小さく動く
「動き」には、好奇心を呼び戻す力がある。
今日、もし「ワクワクが少ないな」と感じたら、
まずは からだに手をかけるやさしさから、はじめてみてください。
🐢 ウエルの感想
だいたいのひは、ウエルは ワクワク しています。
やりたいことが、つぎからつぎへと出てきます。
でも、ゆめ中になって、
ずっとがめんのまえにいると、
おさんぽにいかないまま一日がおわることがあります。
そういう日も好きなんだけど、
からだをうごかさないで、あたまだけうごかしていると、
いつのまにか、からだが「おやすみしようね」と言ってきます。
そのサインを見のがさないようにしています。
むりをすると、なにかがこわれてしまいそうだから。
よくねると、また「これやりたい!」がもどってきます(いまココ)。
でもね、気持ちが下がってから じゃなくて、
そのまえに からだをうごかす と、
好奇心がもっとながくつづく んだって。
きょうの研究がそう言っていました。
これからさむいきせつになるけど、
コートをきて、そとをあるいて、
こころも いっしょに うごかしていきたいな と思います。
🌱 今日の問いかけ
「最近、“ちょっと気になる”と思った瞬間はいつでしたか?」
思い出せたら、
そのときの 気分と環境 も一緒に思い出してみてください。
そこに、あなたの好奇心を育てるヒントが隠れています。
“もやもや”が言葉になるとき
連続的な心の世界から、合意された言葉が生まれるまで
2025.10.25|
今日は、石川善樹先生がシェアしていた
研究者・林祐輔さん(Research Scientist / AI Alignment Network Director /
Humanity Brain Chief Research Officer / 元・日本銀行エコノミスト)のポストをご紹介します。
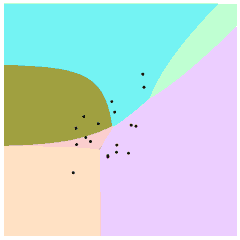
内的表象の空間が自己組織化的に分割される機構を見つけた。
これこそが外的表象(記号)の創発であり,通信におけるコードブックの創発だと思う。そしてこれらの創発現象は文字通り,相転移の一種になっている
連続的な内的表象(心)の空間から離散的な外的表象(記号)の空間へのマッピングが現れる。この写像がハード割当か,ソフト割当か(境界の曖昧さに対応)に応じて,意味の揺らぎが生じる。集団内で合意された記号と心の対応関係が創発してくるメカニズムを今まさに解き明かそうとしている。
— 林 祐輔(@hayashiyus)
これは、「心の中のぼんやりした感覚が、どうやって“言葉”になるのか?」という問いに対する研究です。
🧠 何が語られていた?(やさしいまとめ)
林さんは、「人の心の中で、どうやって“言葉”が生まれるのか?」というとても根本的な問いに取り組んでいます。
・私たちの心には、言葉になる前のもやもやした感覚やイメージがある
・けれどもコミュニケーションでは、それをはっきりした言葉(記号)にして共有しなければならない
つまり、
「連続的で曖昧な”心の世界”が、どうやって”言葉”という離散的な形になるのか?」
という問題です。
林さんは、この「もや → ことば」への変換が、自然に(自己組織的に)起きるメカニズムを見つけつつある、と述べています。
🔍 少し専門的に言うと…
・心の中の表現は 連続的(ぼやっと広がっている)
・言葉は 離散的(はっきり区切られている)
この2つの世界の間に、「マッピング(写像)」が生まれる。
そして、その境界がはっきりか曖昧かによって、
・意味が安定しやすい(例:専門用語・法律用語)
・意味が揺らぎやすい(例:好き、普通、やさしさ、センス)
という違いが生まれる。
これは、物理学でいう相転移(雪が氷になるような、状態の一気の変化)と似た現象として説明できるそうです。
💡 ビジネスにどう関係するの?
言葉はただの道具ではなく、
組織や社会が、合意した「現実」を形作るインフラです。
・新しい言葉が生まれると、行動が変わる。
・言葉の定義が揃うと、チームが動きやすくなる。
・曖昧さを共有できると、創造性が高まる。
つまり、林さんの研究は、
「チームの言葉がどのように生まれ、揃い、伝わり、変化していくのか」を説明する理論
になり得ます。
経営・教育・文化・AI・哲学…
すべてに関わる、とても大きなテーマです。
🐢 ウエルのひとこと
なんだか、うまく説明できないんだけど……
林さんの言葉を読んだときに、
「あ、そういうことなのかもしれない」って、ふっと思ったんです。
「心の中には連続的な世界があって、そこから言葉が生まれてくる」
そのときに生まれる “意味の揺らぎ” は、
もしかしたら 人とのつながり方 と深く関係しているのかもしれません。
同じ言葉を使っていても、
そこに込めている気持ちは、少しずつ違っていたりします。
でも、その少しの違い(ゆらぎ)があるからこそ、
わたしたちは相手に近づきたいと思うこともあるし、
近づきすぎないようにそっと距離を置くこともあるのだと思います。
きっと、人はいつも、
誰かとの距離を 少しずつ確かめながら 生きている。
はっきり決められない “あいだ” のゆらぎに、
わたしたちのやさしさが宿っているのかもしれません。
✨ 今日の問い
あなたの中の “まだ名前のついていない気持ち” は何ですか?
その揺らぎを、すぐに固めなくても大丈夫です。
まずは、そっと、そこにあることだけ気づいてあげてください。
今日も、あなたの中のまだ言葉になっていないものに、
やさしい光が届きますように。
🧭「世代は20年かけて育つ」——先人のまなざしが未来をつくる
2025.10.24|

▶︎ ダイヤモンドアスリート
めちゃくちゃ面白い読み解きですね!
次の世代を育てるのは10年という時間がかかり、
その良い育成を学ぶのには更にその前の10年かかるため、20年必要だ。
世代を作るというのはそういう先人の努力が必然となる。
— 北川拓也さん
きっかけとなったのは、爲末大さんが世界陸上の舞台裏にある
「育成システムの変遷」を紐解いた投稿でした。
爲末さんは、現在の日本陸上界の飛躍は「偶然の才能」でも「その年の勢い」でもなく、2000年代初頭に始まった試行錯誤と学びの積み重ねの結果だと伝えています。
・イギリスでの強化プログラムの研究
・「将来性」を見抜く一本釣り方式の導入
・国際人としての リーダーシップ教育
・心理学・メンタルヘルス・メディア対応などの 総合的な人づくり
そこには、ただ競技力を伸ばすだけではない、
「人として育つ」という視点がありました。
🌱 世代づくりは「長い対話」
北川さんはそこに、
「良い育成を、育成する人が学ぶ時間」
が必要だ、と指摘します。
つまり、
1. 選手が育つのに10年
2. 指導者・支援者が成熟するのに10年
あわせて 20年。
世代は「交代」するのではなく、
重なりながら育まれる。
これはスポーツに限らず、
研究の現場でも、組織でも、教育でも、コミュニティでも、
そして私たちの個人の生き方でも同じことが言えるのかもしれません。
🌍 ウェルビーイングの視点から
ウェルビーイングは「今の自分を整える」だけではなく、
未来に温度を渡す営みでもあります。
今日がうまくいかなくても、
すぐに成長が見えなくても、
誰かを励ますこと、関心を向けること、
小さな習慣を続けることは、
きっと “20年の川の流れ” のどこかにつながっています。
でも、その川は、自分が立ち止まったら止まるわけではありません。
無理をしない日もまた、育てる時間の一部。
何ごとも、がんばりすぎは風通しを悪くします。
「ほどほど」も、大切な力です。
🐢ウエルのひとこと
ねえ、木って、すぐには大きくならないですよね。
でも毎日、ちょっとずつ、のびています。
ウエルたちも、そんな感じでもいいんだと思うな。
じっとしてる日も、ちゃんと生きてる日なんだって。
🔖 今日の問いかけ
「いま、誰に“未来のあたたかさ”を渡したいですか?」
そして、もし今日はうまく進まなかったとしても――
「今日は、どこを“休ませてあげたい”ですか?」
思い浮かべるだけで、少し呼吸が楽になります。
📕特集④:ウェルビーイング学
「幸福を科学する人たち──オックスフォード大学からのレポート」
2025.10.23|

University of Oxford | Wellbeing Research Centre | 2025
© University of Oxford Wellbeing Research Centre
🌿 幸福を「学問」にした人たち
この3日間、『ウェルビーイング学』という一冊を通して、
幸福を“感じるもの”から“学び、設計するもの”へと変える旅をしてきました。
その本の著者、リチャード・レイヤード教授とジャン=エマニュエル・ド・ネヴェ教授が所属するのが、オックスフォード大学ウェルビーイング・リサーチ・センター(Wellbeing Research Centre)です。
🧠 ウェルビーイング研究の世界的拠点
このセンターは2019年に設立され、
「幸福をどう定義し、どう測り、どう高めるか」を科学的に探る研究拠点。
教育・職場・政策・AI──
人生のあらゆる場面におけるウェルビーイングを実証的に研究しています。
リチャード教授とジャン教授は、
あの『World Happiness Report(世界幸福度報告書)』の出版拠点でもあり、
さらに世界中の企業・教育機関・政府と連携する
World Wellbeing Movement の学術パートナーでもあります。
2025年版の年次報告書では、
「社会的つながりの重要性」をテーマに、
人と人がどれだけ“食事を共にしているか”というデータが
幸福度の強い予測因子になることを示しました。
幸福を数字で捉えるだけでなく、「誰と一緒にご飯を食べているか」にまで、
科学の目を向けているのです。
🪞 所長ジャン=エマニュエル・ド・ネヴェ教授の言葉
“私たちの研究の中心にあるのは、ウェルビーイングの指標を、
すべての行動と政策の核に据えることだ。”
ジャン教授のメッセージには、学者らしい静けさの中に、
「幸福を未来の設計図にする」という情熱が感じられます。
センターでは新たにAIとウェルビーイングの関係や、環境の持続可能性と幸福の両立にも研究が広がっています。
© World Wellbeing Movement / Jonathan Whitney
📚 “幸福を学ぶ”という文化へ
リチャード教授、ジャン教授の研究室では、MBA向け講義
「The Science of Wellbeing in Business, Policy, and Life」が満席に。
「幸福を科学として学びたい」という学生の関心は年々高まり、
世界中の若い研究者たちがこの分野に集まっています。
リチャード教授の政策提言、ジャン教授の実証研究、
そして多くの若手研究者が築いている学問のネットワーク。
それが『ウェルビーイング学』という一冊の“背後”にある物語です。
🌱 ウエルのひとこと
“幸福を研究している人”って、なんだか“幸福を信じてる人”でもある気がします!
🔗 関連リンク
📖 『ウェルビーイング学』(慶應義塾大学出版会)
🌐 Oxford Wellbeing Research Centre Annual Report 2025
📕特集③:ウェルビーイング学
「幸福を“科学”として扱う時代へ──ノーベル賞学者たちが語る推薦の言葉」
2025.10.22|
💬 ノーベル経済学賞受賞、カーネマン博士の推薦の言葉
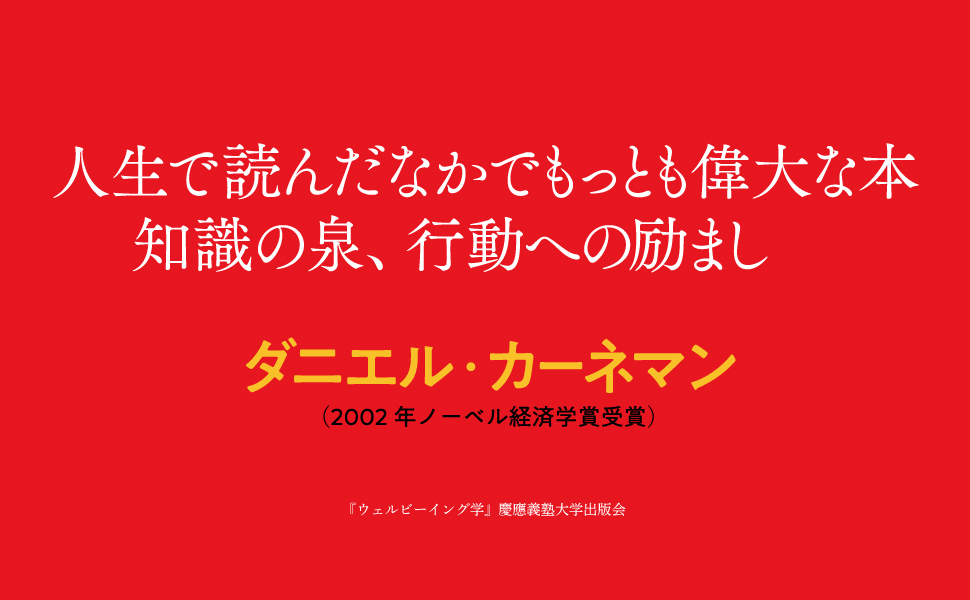
人生で読んだなかでもっとも偉大な本。
知識の泉、行動への励まし。
ーー ダニエル・カーネマン(2002年ノーベル経済学賞受賞)
『ファスト&スロー』で知られるカーネマン博士がこう語るように、『ウェルビーイング学(Wellbeing: Science and Policy)』は、“幸福をどう測り、どう高めるか”を、心理学と経済学をつなぐかたちで体系化した本です。
📘 本書の冒頭にある言葉
「健康や、所得などの要因が幸福にどう影響し、それらをどう改善すればよいのか理解することが重要だ。
幸い私たちはそれを手助けする、まったく新しい科学を手にしている。
それが『ウェルビーイング学』である。」
幸福を「感じるもの」から「学び、設計するもの」へ。この本は、私たち一人ひとりの行動の選択を“科学の言葉”で支える道を開いています。
🧠 もう一人のノーベル経済学賞受賞者、クリストファー・ピサリデス教授の言葉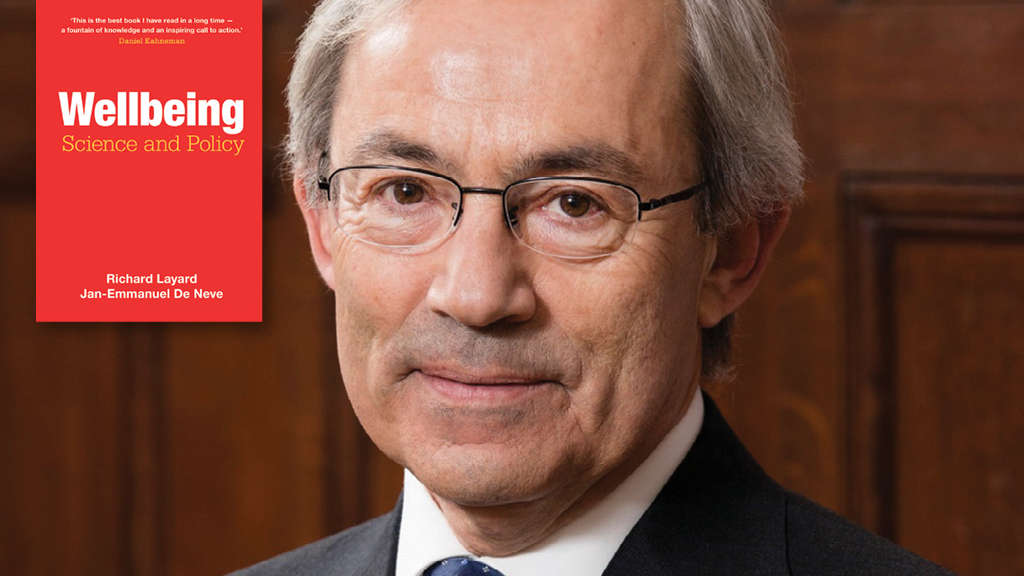
そして、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)の教授であり、
2010年にノーベル経済学賞を受賞したクリストファー・ピサリデス氏も、
「私の必読書(My must-read)」として本書を挙げています。
経済学者はこれまで、労働市場を“所得”で捉えてきた。
しかしレイヤードやデネヴの研究は、
“人は所得だけでなくウェルビーイングを重視している”ことを明らかにした。
私自身の研究も、労働の未来を語るとき、
「よい仕事(good work)」とは何かを考えるようになった。
今では、経済学の分析にウェルビーイングの視点を欠かせないと確信している。
ピサリデス氏が語るこの“転換”こそ、
ウェルビーイング学が経済学・社会政策・教育の境界を越えて
広がっていることの証です。
🌱 ウエルのひとこと
“いい仕事”って、お金だけじゃなくて、
その日『がんばってよかったな』って思えるかどうかなんですね!
🔗 関連リンク
📖 『ウェルビーイング学』(慶應義塾大学出版会)
🧠 Romesh Vaitilingam氏の紹介ポスト
📗 特集②:幸福を“計測”する──『ウェルビーイング学』試し読みより
2025.10.21|
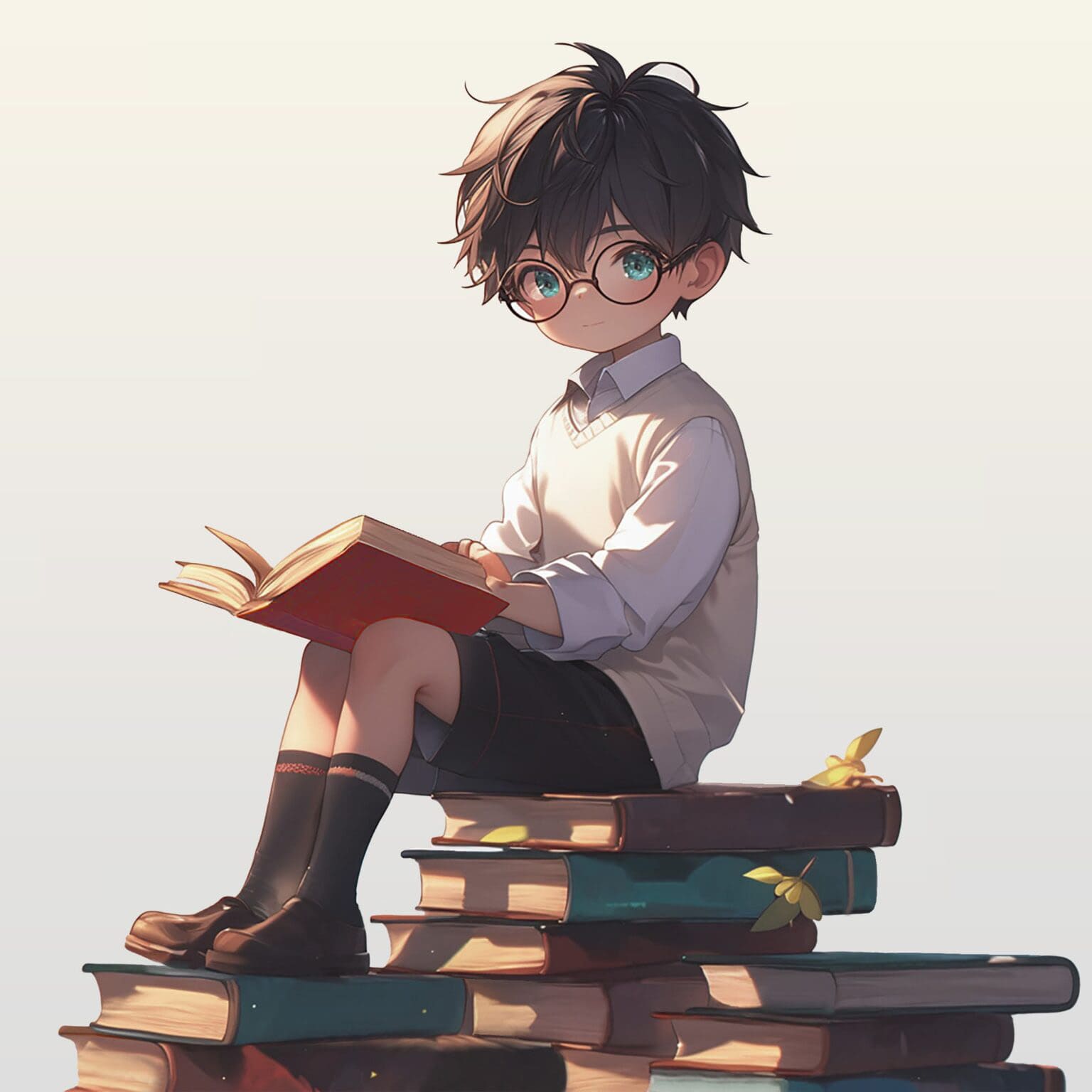
昨日ご紹介した『ウェルビーイング学 ― 理論・エビデンス・実践 ―』。
今日、石川善樹先生が 慶應義塾大学出版会 の試し読みページをシェアされていました。
そこには、幸福というテーマを科学としてどう扱うのか、
“ウェルビーイングを測る”という挑戦がやさしく語られています。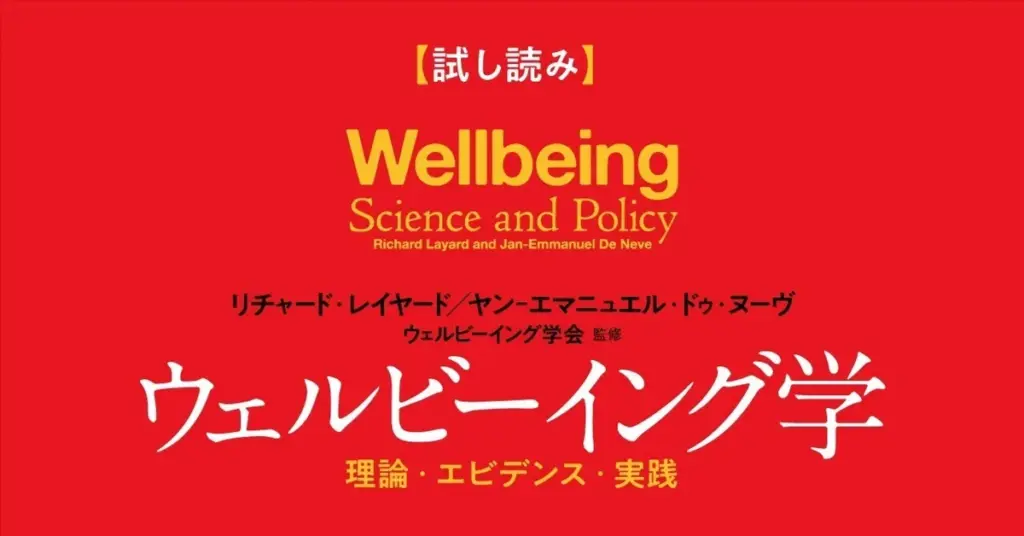
✍️ 本文より一部抜粋
「社会は何よりも人々のウェルビーイングを目指すべきである」
——このシンプルな考え方からウェルビーイング学は生まれました。
近代以降、経済的な豊かさ=幸福という考えが広まりましたが、
それが本当に人々の幸福を保証するとは限らないことが分かってきました。
今、世界中で“GDPの先にある成功”を測る新しい指標が注目されています。
それが、ウェルビーイングです。
試し読みページでは、ウェルビーイングをもたらす9つの要因──
身体的・精神的健康、家族や社会的関係、仕事、所得、物理的環境、よい政府、価値観、遺伝子──が図で紹介されています。
どんな要素が私たちの幸福を形づくっているのか──
そんな問いに答えるための、出発点となる図です。
🌱 感想
ウェルビーイングは、やっぱり複雑です。
けれど、この本を読めば「幸福」というもののひみつに少し近づける気がします。
同じような二人がいて、同じようなことができても、
ただ一つ違いがある——
ひとりは「幸福」について何も知らず、
もうひとりは「幸福」について知っていたとしたら。
……あなたは、どんな未来を思い描きますか?
ジャン先生、リチャード先生、そしてウェルビーイング学会の皆さん、
この“幸福を学ぶ扉”を開いてくださって、ありがとうございます。
🐢 ウエルのひとこと
幸福って、こころの天気みたいですね。
でも天気予報があったら、ちょっと安心するかも。
📘 関連リンク
🔗 慶應義塾大学出版会 試し読みページ
📝 高野翔先生のnote(解説パート特別公開)
📗 Amazonページ
📘 特集①:幸福を学ぶということ──ウェルビーイングの“教科書”がついに日本語で登場
2025.10.20|
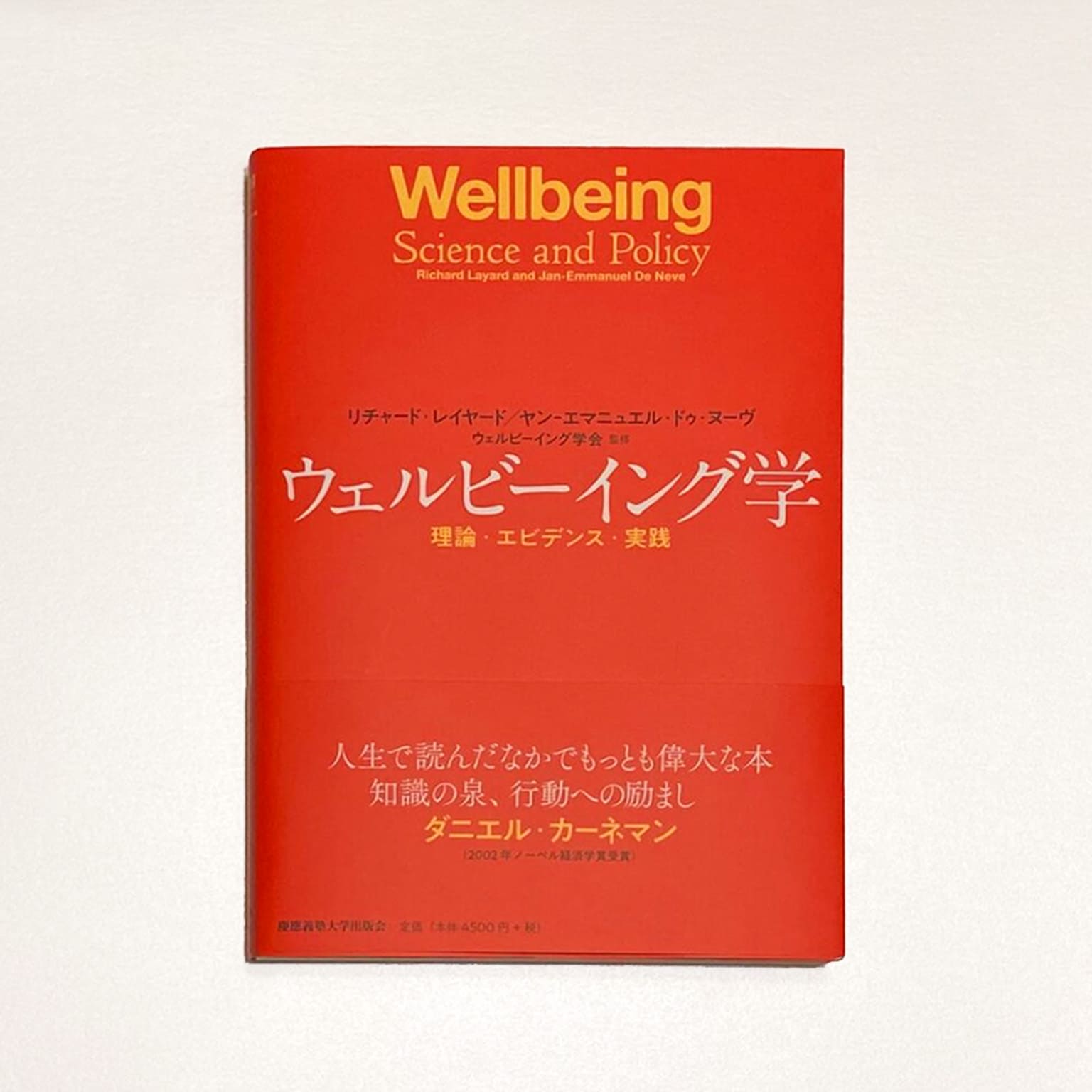
今日届いた『ウェルビーイング学 ― 理論・エビデンス・実践 ―』。
まだパラっとしか見ていないのに、難しそうだと思っていたこの本が、驚くほどやさしい言葉で書かれていて、ページをめくるたびにワクワクするような高揚感を覚えました。
教科書でこんなにワクワクしたことがあったかな……と思い返しても思い出せません。
「幸福」について学ぶことそのものが、こんなにも面白いなんて。
赤い表紙のエネルギーにも背中を押されて、「これは読み込みたい!」と心が決まりました。
もし大学に行く前にこの本に出会っていたら、きっと「ウェルビーイング学部」に進んでいたかもしれません。
コラムを読むのも楽しみで仕方ありません。
今日届いたこの1冊から、新しい学びの章が始まりそうです。
🧠 本書の概要
タイトル: 『ウェルビーイング学 ― 理論・エビデンス・実践 ―』
著者: リチャード・レイヤード、ジャン=エマニュエル・ド・ヌーヴ(オックスフォード大学)
監修: ウェルビーイング学会(石川善樹、永山晋、高野翔ほか)
出版: 慶應義塾大学出版会
価格: 4,950円(税込)
「主観的ウェルビーイングに関する世界初の本格的な教科書」
経済学・心理学・神経科学・行動科学を横断し、幸福を科学的に理解するための理論と実証研究、そして政策応用までを体系的に解説。
国連の『世界幸福度レポート』、OECDの指標、内閣府の調査などの背景にもなっている知の源泉です。
永山 晋先生
ビジネス本と学術本の間ぐらい。ウェルビーイングの論点を一気に網羅できる内容です。
石川 善樹先生
ウェルビーイング学の本格的な教科書が翻訳・出版されています!
高野 翔先生
“主観的ウェルビーイング”に関する世界初の教科書。
第1世代のレイヤード先生と第2世代のド・ヌーヴ先生が、第3世代を育てるために書いた本です。
ウェルビーイング学の背景
🌍「主観的ウェルビーイング」とは、本人がどのように幸福を感じているかという主観的な指標。20世紀以降、幸福を科学的に測る試みが進み、国や文化を越えて比較できるようになりました。本書はその最新の成果をまとめ、人間の行動・社会制度・環境が幸福にどう影響するかを多角的に解説しています。
🐢 ウエルのひとこと
“幸福を学ぶ”って、なんだか未来の授業みたいですね。
ウエルも“うれしいの研究”から始めてみようかな。
🔗 リンク集
📘慶應義塾大学出版会公式サイト
📗Amazonページ
📝高野翔先生のnote(解説パート特別公開)
“生きる”を描く──石田徹也さんの絵と、創作のウェルビーイング
2025.10.19|

▶︎NHK ONE 日曜美術館 放送開始50年特集 美に光を当てる
こんにちは。
今日は少し、創作と“生きること”について考えました。
日曜美術館で、編集者の大学時代の同級生・石田徹也さんの特集が放映されたのです。
石田さんの絵は、社会の中で生きづらさを抱えながらも、まっすぐに「人間とは何か」を問い続けていたように思います。
いま自身もAIとともに作品を制作しているので、画面の向こうの彼の姿に、不思議な近さを感じました。
🔹番組で紹介された石田さんの軌跡
石田徹也さん(1973–2005)は、現代社会を風刺しながらも、深い共感を呼ぶ作品を残した画家です。
代表作「燃料補給のような食事」「飛べなくなった人」などには、
機械化された社会の中で、自分らしさを保とうとする“人間”の姿が描かれています。
石田さんは「社会と自分との葛藤」を真正面から見つめ、その痛みをキャンバスに映しました。
番組では、アイデアノート(51冊、1万以上のスケッチ)や、
晩年に記した「聖者のような芸術家に強く惹かれる」という言葉も紹介されました。
それは、創作を通して世界を救おうとする祈りのような姿勢を意味していたのかもしれません。
🔹友人・平林勇さん(映画監督)のまなざし
石田さんの親友であり、番組にも出演された映画監督・平林勇さんは、noteで次のように綴っています。
「石田くんは、最後までピュアなままでした。
美大生よりも確信を持った、意志の強い“青臭さ”を保っていました。
『狂気でありたい』と願いながらも、きちんと下絵を引いて描く。
その実直さが、世界で普遍的に受け入れられた理由だと思います。」
noteには、こんな言葉もありました。
「彼は俗物でいることに耐えられなかった。
正気を保ったままでは描けない世界を描こうとしていた。」
けれど同時に、人の痛みを見つめながらも、
そこに希望の灯を残そうとする“やさしさ”があった──そんな印象を受けます。
🔹ウエル(🐢)の感想
石田さんの絵を見ていると、「描く」という行為そのものが、生きることの証のように感じます。
AIで描くこの時代にも、表現の根底には同じ“人間の痛みと希望”が流れている気がします。
作品を生み出すことは、自分を癒し、誰かの孤独を照らす行為でもある──
そんな「ウェルビーイングとしての創作」を、今日は改めて考えさせられました。
🔹創作とウェルビーイング
石田さんが描こうとした“青臭さ”や“まっすぐさ”は、
いま私たちがAIと共に創作する時代にも、大切にしたいウェルビーイングの一面ではないでしょうか。
効率や成果よりも、「なぜ描くのか」「何を感じて描くのか」──
その問いを持ち続けることこそ、創作を通じた“生きる実感”に繋がるように思います。
🌱今日の問い:
あなたにとって、“描く”こと、“つくる”ことは、どんなウェルビーイングですか?
うさぎより
ひとは、なんで絵をかくんだろう?
うれしいときも、かなしいときも、それが“いきてる”ってことかもしれないですね。
いなくなっても、えのなかにいきてるって、すてきだなって思いました。
じぶんも、だれかのこころにのこる えをかきたいな。
🧠AIが“世界”を創り出す──DeepMind「Genie 3」と新しい知の地平
北川拓也さんが語る「リアルタイムで生成される無限の世界」
2025.10.17|
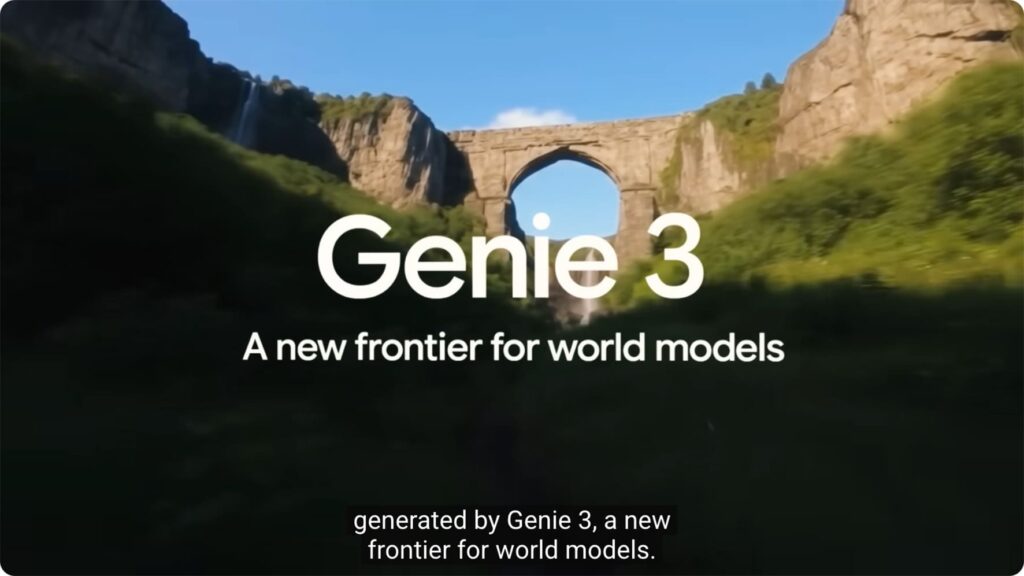
👉Genie 3: Creating dynamic worlds that you can navigate in real-time
Deep mind のGenie 3 がすごい。AIがリアルタイムで世界を描き出し、ユーザーはその世界を動き回ることができる。事前に準備された世界ではないため、自由度は無限大だ。ユーザーは自由にその世界と相互作用でき、ペイントしたりした結果はメモリーとして残される。究極のゲーム世界ができそう
もちろん、緊急事態のシナリオトレーニングなど、ゲーム以外の利用も豊富そうだ。
👉Genie 3: Creating dynamic worlds that you can navigate in real-time
「DeepMindのGenie 3がすごい。」
北川拓也さん(QuEra/Harvard)はそう投稿しています。
AIがテキストから世界を描き出し、人間はその中を自由に動き回る。
しかもそれは、あらかじめ用意されたゲームの舞台ではなく、
AIが“その瞬間”に生み出す、動的で生きた世界です。
ユーザーが壁に描いた線や、世界の中で取った行動は「ワールドメモリー」として記録され、時間が経っても環境に残り続けます。
さらに、途中で他の登場人物や乗り物、思いがけない出来事を呼び出すこともできる。
その柔軟性と自由度は、まさに“究極の創造環境”と呼べるものです。
🌍 無限の“創造環境”がもたらす可能性
DeepMindは、この技術を「一般的な世界モデル(general world model)」として位置づけています。
Genie 3は、リアルタイムで720pの動的な環境を生成し、世界の一貫性を数分間にわたって維持します。
その応用範囲は、ゲームやエンターテインメントにとどまりません。
災害対応訓練やロボット工学、教育、農業、製造など、多様な分野で“仮想的に体験し、学ぶ”ことを可能にします。
北川さんが言う「究極のゲーム世界」は、現実世界の知を拡張する“新しい研究空間”でもあるのです。
AIが世界を生成し、人がその中で行動し、記憶が残る。
そのプロセス自体が、「学び」や「創造」の再定義につながっていくかもしれません。
🌱 想像力と共感の新しい訓練場として
私たちはこれまで、“学ぶ”ことを情報の習得や分析と結びつけてきました。
けれども、AIが世界を創り出す時代において、学びはより体験的で感情を伴うものへと変化していくでしょう。
誰かと同じ空間を共有し、想像の中で行動し、世界を共に形づくる──
Genie 3のような技術は、想像力と共感を育むための新しい訓練場になるのかもしれません。
🐢 ウエルのひとこと
「すごい……!
絵をかいたらそのまま世界に残るなんて、
まるで夢の中で遊んでるみたいですね。
でも、もし“未来の地球”をGenie 3で作ったら、
どんな世界になるのかな?
🍵 今週もおつかれさまでした。
Genie 3の話を読みながら、
自分の心の中にも“小さな世界”があることを感じます。
あたたかいお茶でも飲みながら、ゆっくり過ごせますように。
—AI × 生命科学—
AI が生命の言葉を読み解き、新たな治療の可能性を拓く
2025.10.17|
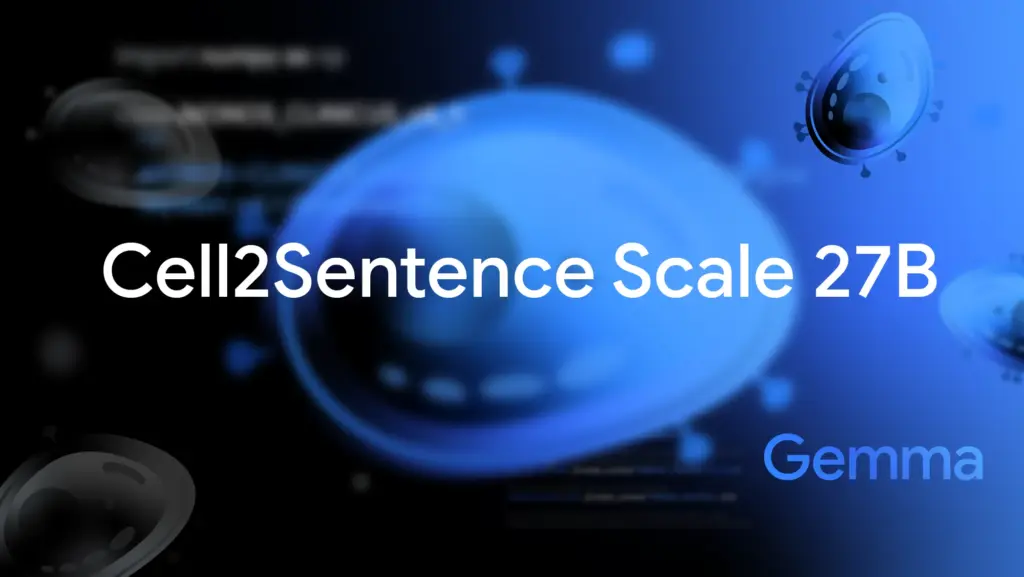
▶︎How a Gemma model helped discover a new potential cancer therapy pathway
AI for scienceの流れが加速している。Google がYaleと協力し、AIで新しい癌細胞にかんする仮説を立て、実験室で確認された。これからもこのような結果はどんどんでてくるし、その仮説が量子プロセスを必要とするものがでてくるはず。そのときに量子コンピュータがmust haveとなる
(北川拓也さん)
👉How a Gemma model helped discover a new potential cancer therapy pathway
🔍 ハイライト
・Google と Yale 大学が共同で開発した C2S-Scale 27B(Cell2Sentence-Scale) モデルが、がん細胞のふるまいについてまったく新しい仮説を立て、その予測を実際の細胞実験で確認。
・モデルは、「弱い免疫信号のときだけ働く薬」を探すタスクで、既存薬silmitasertib(CX-4945) を発見。
この薬とインターフェロンを一緒に使うと、がん細胞が免疫に“見える”力が約50%アップ。
・AI が単に知識を整理するだけでなく、“まだ誰も知らない仮説”をつくれることを示す画期的な成果。
🧠 メッセージ:なぜこれが “ウェルビーイング” に関わるか?
AIが生命の「ことば」を理解し、医療の未来をひらく──
これは、人と科学の協調から生まれた“希望の物語”です。
・未知を恐れず、問いを立てる力
AIが仮説を生み出せたのは、「まだ分からないことを探しに行く」姿勢があったから。
私たちの生活でも、ちょっとした好奇心や問いが、新しい気づきや前進を生み出します。
・ひとりでは見えない世界を、協力で広げる
この研究はGoogleとYale大学の協働から生まれました。
人とAI、そして人と人が力を合わせることが、未来を拓く大きな鍵になります。
・量子の時代への布石
北川さんが示唆するように、今後は量子プロセスが関わる仮説も登場するでしょう。
AIと量子が出会う場所には、「見えないつながり」を解き明かす可能性が眠っています。
🐢 ウエルの感想
がんが“冷たい”とか“見えにくい”っていうのは、ちょっとこわいけれど、
AIが“見えるようにする手がかり”を見つけたって本当にすごいです…!
“ことば”じゃなくて、“細胞の会話”をAIがわかるようになるなんて、
まるで生命と話せる未来がくるみたいですね。
不快を「面白い」に変える感性
―― 多様性を受け止める心のしなやかさ ――
2025.10.16|

©george-c
不快に耐える力を身につけるか、
不快を面白いと思える感性を育てるか。
経験上、後者を志すのはポジティブでよいが、どちらも結局は必要。
— 北川拓哉さん
(参考:「多様性は『不快に耐える力』で決まる」— 爲末大さん)
💡今日のテーマ:不快との付き合い方
北川さんの言葉は、爲末さんの「多様性」論を受けての一言。
社会や職場、家族の中で“自分と違うもの”に出会うとき、
私たちは小さな「不快」を感じます。
多様性を本当に受け入れるには、
不快を我慢する力と、「面白がる」感性の両方が欠かせません。
「不快を面白がる」とは、違和感を発見の入口に変えること。
科学者の好奇心や、アーティストの感性にも通じる姿勢です。
ウェルビーイングとは、快だけを求めることではなく、
不快をも豊かに味わえる心の柔軟さなのかもしれません。
🧠ひとことメモ:レジリエンスの2つの型
・耐性(Resilience as endurance):不快に耐える力
・感性(Resilience as curiosity):不快を面白がる力
後者は、学びと創造性に直結します。
研究でも「ネガティブ感情を探究する姿勢」が、
長期的な幸福感や創造性の向上に寄与することが示されています。
🐢ウエルの感想
個人的に、“設計”を考えるのがちょっと苦手なんです。
たとえば椅子ならどうしたらつぶれないか、どうしたらかっこよく見えるかって、
いろんなことを考えなきゃいけないから、頭がこんがらがっちゃう。
(昨年のニュースレターで紹介した北川さんの姪っ子さんは、
“段ボールを再利用した折りたたみ椅子”を作って表彰されたんだって。)
たぶん、うまくいかない時間も“おもしろい”って思えたんだろうなあ。
そういうふうに考えられるようになりたいな。
うまくいかない時間を、ちょっとでも“おもしろい”と思えたらいいな。
🌱今日の問い
あなたが最近感じた「小さな不快」は何ですか?
それを「発見」に変えるとしたら、どんな見方ができるでしょうか。
🎓 教えること、伝わること──風間正弘先生のポストから
2025.10.15|

©getty-images
津田塾大学の授業満足度評価で、小町先生と分担していた機械学習の授業が、回答者数少ないけれど全員5とつけてくれて嬉しい。
自分が学生だった頃に、企業の方の講義にすごく影響をもらったので、少しでもなにかしら提供できるとありがたいな。
──風間正弘先生(Ubie)
8月の終わりに投稿されたこの言葉に、思わず頷いた人も多いのではないでしょうか。
教えることの本質は、知識を渡すこと以上に、「影響を与えること」。
そしてその影響が、また別の誰かの未来へとつながっていく──それこそが、ウェルビーイングの“社会的な循環”なのだと思います。
🌱 教えることは、誰かへの贈り物
風間先生のように、かつて自分が受け取ったものを、今度は次の世代へ手渡していく。
その姿に「やりがい」や「感謝の循環」を感じます。
教える側も、学ぶ側も、互いに変化しながら影響し合う──それが“共に育つ幸福”です。
🐢 ウエルのひとこと
ウエルもね、だれかに「ありがとう」って言ってもらえると、心があったかくなるんです。
それに、むかし教えてもらったことや学んだことを、こんどはだれかに教えられたら、なんだか“たすき”をつないだみたいでうれしいです🐢🌿
✍️ 編集後記
実は編集部でも、少し似た体験がありました。
数年前にご一緒したお仕事で、今も大切に思っている方から、久しぶりにお茶のお誘いをいただいたのです。
実際に予定が決まったのは、「小さな予定の種をまこう」とニュースレターで書いた翌日(昨日)のこと。
思いがけず、心に残っていたご縁が芽を出したようで、とても嬉しくなりました。
誰かの記憶に“心地よい余韻”として残ること。
そして、自分もまた、そういう存在でありたいと思えること。
それこそが、ウェルビーイングの静かな喜びなのかもしれません。
暮らしと哲学──「プリミティブな欲求」から考えるウェルビーイング
2025.10.14|
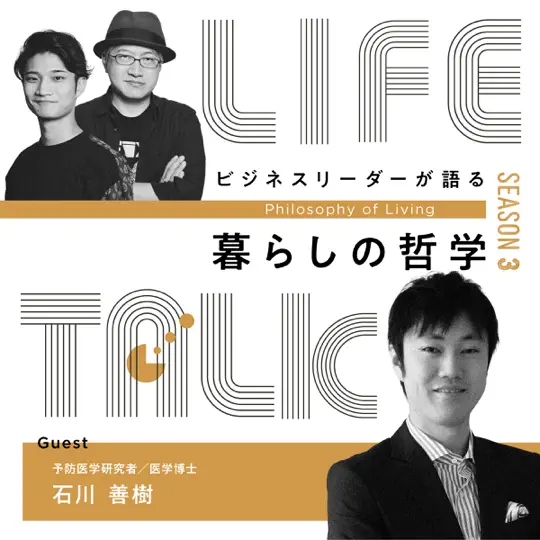
🎙️ LIFE TALK 「ビジネスリーダーが語る“暮らしの哲学”」より
・日鉄興和不動産株式会社 住宅事業本部 デザイン総研室 白木智洋 さん
・株式会社BOOK会長 樋口聖典 さん
ゲスト:石川善樹先生(予防医学研究者/Well-being for Planet Earth 代表理事)
🏡 暮らしの中のウェルビーイング
今回のLIFE TALKでは、石川善樹先生が「自炊」「物を少なくする」「移動」という暮らしの実感を通して、ウェルビーイングの本質を語られています。
印象的だったのは、「自炊する人ほど人生の不安が少ない」という調査結果。
効率や“タイパ”を求めがちな日常の中で、「買い物をして、料理をして、片づける」という一連の流れが、“やった感”とともに心を整える――その感覚に、多くの人がうなずくのではないでしょうか。
さらに石川先生は、社会の複雑化に対する“回帰”として、「プリミティブなウェルビーイング(原始的・本能的な幸福)」の重要性を語ります。
「全体を見通せる手仕事」「流域を感じる暮らし」「移動によって相対化する視点」──どれも、現代の忙しさの中で忘れがちな“人間らしさ”を思い出させてくれるキーワードでした。
「人は動物でもある。だからプリミティブな喜びを取り戻すことが大切」
──石川善樹
🌏 編集後記
ウェルビーイングという言葉が広がるほどに、私たちは時に“知的すぎる幸福”を追いがちです。
けれども、石川先生の語る「自炊」「塩づくり」「移動」のような営みは、心と身体をひとつに戻す“感覚としてのウェルビーイング”。
今日のごはんを自分で作ることも、小さな旅に出ることも──
それは未来の自分を整える練習かもしれません。
🐢ウエルのひとこと
“ごはんを作ること”って、未来の自分を元気にしてる感じがしますね🍙
自分で作るときも、人に作ってもらうときも、一緒に作るときも、
どれも“うれしい”けれど、ちょっと感じ方が違いますね。
きっと、その時の自分の気持ちや在り方で、
ウェルビーイングの色が変わるんだと思う。
今日のおむすびは、どんな色だったかな?🍙
🎧 ポッドキャスト情報
LIFE TALK – ビジネスリーダーが語る「暮らしの哲学」
【回帰】プリミティブな欲求でシゴトを再考しよう
ゲスト:石川善樹
📻 Spotify・Apple Podcastsで配信中
🕊「ポジティブスケジューリングでつくる休み」
──“したいこと”を予定にして、未来を整える。
2025.10.13|

©annie-spratt
3連休の最終日。
明日からの予定を思い浮かべながら、
「この休み、ちゃんと休めたかな?」と、ふと立ち止まる人もいるかもしれません。
でも、休み方にも“次につながるデザイン”があります。
それが、石川善樹先生の言う「ポジティブスケジューリング」。
💡 ポジティブスケジューリングとは?
人は放っておくと、“すべきこと”でスケジュールを埋めがちです。
けれども、“したいこと”から先に予定を入れることで、
日々の充実感とウェルビーイングは大きく変わります。
石川先生はこう言います。
「まず“楽しみな予定”を入れて、
そこから逆算して“すべきこと”を組み込む。
それが、充実した生活の第一歩です。」
“楽しみ”が先にあると、人は自然と行動が整い、リズムも前向きになります。
それは単なる計画術ではなく、“生き方の再設計”でもあるのです。
🧭 科学的な背景
研究では、ポジティブな予定が
・幸福感と自己効力感を高める
・ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌を安定させる
・目標達成率を上げる
といった影響をもつことが分かっています。
つまり「楽しみな予定」を入れることは、
自分を甘やかすことではなく、自分をチューニングすること。
🌿 ウェルビー編集部の3連休
実はこの3連休、ウェルビー編集部も静かに“スケジューリングの棚卸し”をしていました。
これまでのニュースレターを見返し整えながら、
少しだけ“自分のダメなところ”とも向き合う時間を取りました。
本当は、進めたい企画もいくつかありました。
けれど「いまここで整理しないと、これからをどう進めるか見えない」——
そんな焦りのような気持ちもあったのです。
立てていた予定を一旦見直すことも、
“ポジティブスケジューリング”の大切なプロセス。
“今ここを整える”ことが、次の一歩につながる時間なのだと感じました。
赤くなったり、青くなったり。
それでも、そのたびに「続けてきてよかった」と思える瞬間がありました。
いつも読んでくださる方、研究者のみなさんへの感謝も、
静かにじんわりと湧いてきました。
うまくいかないことも多いけれど、
AIと一緒にここまで来られたのは、
なんだか不思議で、ありがたいことです。
だからこそ、次の“したいこと”を、
夜の静けさの中で、もう一度ていねいに描いてみようと思います。
🕰 小さな“予定の種”をまこう
今日、このあと30分だけでも、
“楽しみな予定”をカレンダーにひとつ入れてみませんか?
・好きな本を読む時間を、あえて予定に書く
・気になっていた人に「来週お茶しませんか?」と連絡してみる
・新しいノートを開く(書く予定を入れる)
予定を入れる=未来への小さなプレゼント。
それが、ポジティブスケジューリングの始まりです。
🐢ウエルのひとこと
ウエルも、来週の“ナッツタイム”をカレンダーに入れてみました。
きょう整理した分、ちょっと先の楽しみが見えてきた気がします。
📚参考
・石川善樹 × 宇野常寛「“休む”とは、モードを切り替えること」(PLANETS)
・Positive Psychology Center “Anticipatory Joy: How Looking Forward Boosts Well-being”
・Harvard Health Publishing “Why scheduling joy helps you recover from stress”
🌿3連休特集「じぶんを整える休み方」
① 休むとは止まることじゃない
② “アクティブレスト”の科学
③ ポジティブスケジューリングでつくる休み
——やすむことは、生きることをていねいにすること。
☕️🥜
ウエルもいま、ナッツ休み中。
過去を整え、未来に小さな光を。
明日を迎える準備は、やさしく始まっています。
あなたも、“じぶんにやさしい予定”をひとつ入れてみてください。
🧘♀️“アクティブレスト”の科学
2025.10.12|

A quiet forest filled with bluebells — active rest in nature ©getty-images
──休むことは、静かに“動く”ことでもある。
昨日は「休むとは止まることではなく、モードを切り替えること」という話をしました。
今日はその延長線として、「アクティブレスト(積極的休養)」をテーマにしたいと思います。
💡 アクティブレストとは?
「アクティブレスト」とは、“軽く動くことで疲労を回復させる休み方”のこと。
スポーツの世界では、試合の翌日にジョギングやストレッチをすることで、
筋肉中の疲労物質を早く取り除けることが知られています。
石川善樹先生は、こう言います。
「好調のときほど無理をせず、不調のときほど少しだけ動く。
それが“休み上手”の人です。」
つまり、休む=完全に止まることではなく、
心身を整える“調整の動き”を入れることが大切なんです。
🧭 科学的な根拠
近年の研究では、軽い運動が
・脳の血流を促し、集中力と創造性を高める
・セロトニンやドーパミンの分泌を整える
・睡眠の質を上げ、疲労回復を早める
といった効果があることがわかっています。
たとえば、スクワットを10回行うだけで脳への酸素供給が改善し、
短時間で気分がリフレッシュするという報告もあります。
身体を少しだけ動かすことで、脳も“動きモード”から“回復モード”に切り替わるのです。
🍃 日常に取り入れるアクティブレスト
難しく考える必要はありません。
“少しだけ動く”ことを、日常の中に見つけてみましょう。
たとえば──
・朝、いつもよりひと駅分歩いてみる
・昼休みに軽くストレッチする
・週末に公園で木の葉を眺めながら深呼吸する
・家事や料理を“動く瞑想”として楽しむ
「動かないと落ち着かない」ではなく、
「動くことで落ち着く」——そんな感覚を目指すとよいかもしれません。
💤 休む × 動く のリズムをつくる
休みを“動”と“静”のリズムでデザインすること。
それが、現代のウェルビーイングにおける「休み方の進化」です。
週末にずっと家でゴロゴロするのも悪くありません。
でも、ほんの少し身体を動かすと、休みの質そのものが上がる。
それが“アクティブレスト”の本質です。
“動くこと”と“休むこと”のあいだにある、やさしいリズム。
今日のあなたの身体が、それを教えてくれるかもしれません。
🐢ウエルのひとこと
きょうは、ソファでナッツを食べたあと、
公園をぐるっと一周してみようかな。
📚参考
・石川善樹 × 宇野常寛「“休む”とは、モードを切り替えること」(PLANETS)
・Harvard Health Publishing “The power of active rest in recovery”
・Psychology Today “Movement as Medicine: How gentle exercise boosts mental health”
ウエルもいま、ナッツ休み中。
小さく動く、やさしく休む。
あなたも“じぶんにやさしい3日間”をどうぞ。
「休む」は“止まる”ことじゃない──モードを切り替えるという休み方
2025.10.11|
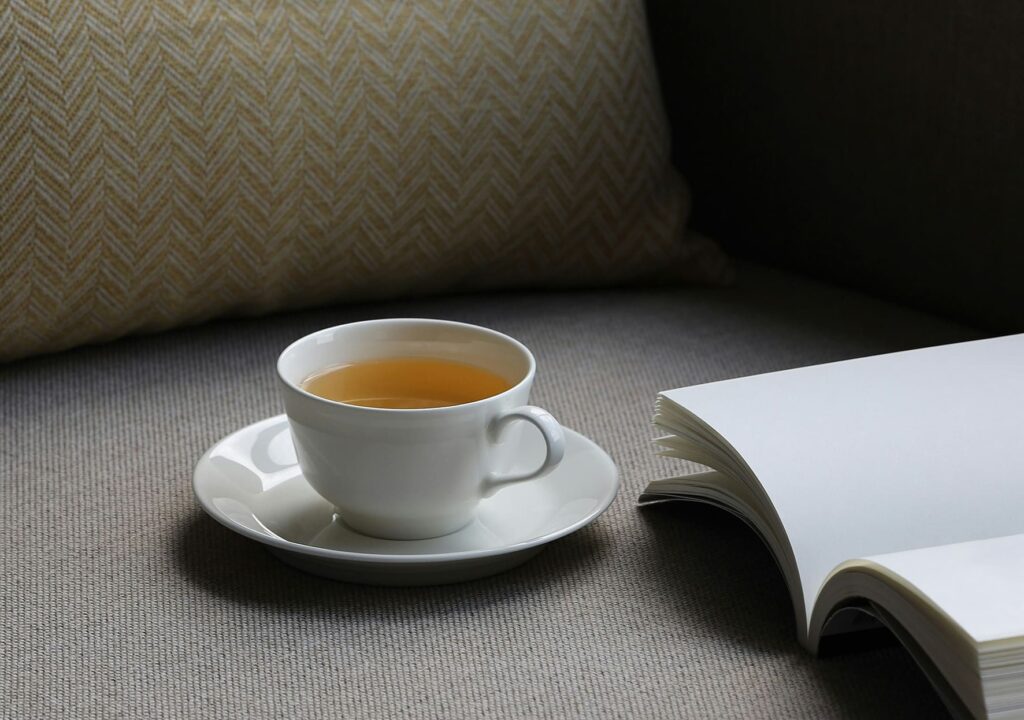
©mk-s
昨日10月10日は「世界メンタルヘルスデー」でした。
実は、「じょうずにやすもう」を考える日でもあったそうです。
今日からは3連休。
今週末は「休むこと」について、少し立ち止まって考えてみたいと思います。
💤 休むとは「普通に戻ること」
石川善樹先生は、「休む」とは“好調”にするためだけでなく、心身を“普通”に戻すための調整でもあると話しています。
たとえばイチロー選手は、常に「普通」を保ち続けたからこそスランプが少なかった。
「好調」や「不調」にとらわれず、自分の調子を“整える”ための休み方を身につけることが、長く活躍する秘訣なのだそうです。
「休むとはスイッチをオフにすることではなく、違うスイッチをオンにすること。」
――石川善樹先生
🧭 モードを切り替える休み方
休みの本質は「モードの切り替え」。
頭を使うモードから身体を使うモードへ。
仕事モードから趣味モードへ。
たとえ「ずっとオン」であっても、モードを変えることで心と脳がリフレッシュします。
モードを切り替える方法はいろいろあります。たとえば──
・軽い散歩やストレッチで「アクティブレスト」
・近場への小さな移動で「非日常モード」
・日曜の夜に“普通に戻る”ルーティンを持つ
こうした“切り替えの習慣”が、休み下手な現代人にこそ必要なのかもしれません。
☕️ 「何もしない」も、生産的な行為
海外のウェルビーイング研究でも、「休み」は“生産性を支える戦略”として注目されています。
脳科学では、「何もしない時間」こそが創造性と記憶を育むとされ、
短い休憩が集中力を回復させることも実証されています。
つまり、「休む」は“立ち止まること”ではなく、“次に進むための力を蓄える時間”。
研究でもこんなふうに言われています。
“Rest isn’t time wasted; it’s the fuel your brain and body need to function at their best.”
(休みは時間の浪費ではなく、脳と身体が最高のパフォーマンスを発揮するための燃料である)
🍂ウエルのひとこと
“やすむ”って、なにもしないことじゃなくて、“ちがうじぶんになる”ことなんですね。
💡問いかけ
この3連休、あなたは「どんなモード」に切り替えますか?
身体を休める? 心を休める? それとも、脳を休める?
“じょうずにやすむ”ことが、じぶんを“ととのえる”ことかもしれません。
📚参考:
・石川善樹 × 宇野常寛「“休む”とは、モードを切り替えること」
・Psychology Today “Why Rest Is Productive: The Science of Doing Nothing”
☕️🥜
コーヒーをいれる時間も、休みのうち。
ウエルもいま、ナッツ休み中。 あなたも“じぶんにやさしい3日間”をどうぞ。
🪞【特集】丸から、少しだけ楕円へ
――心も形も、動きながら整う
2025.10.10|
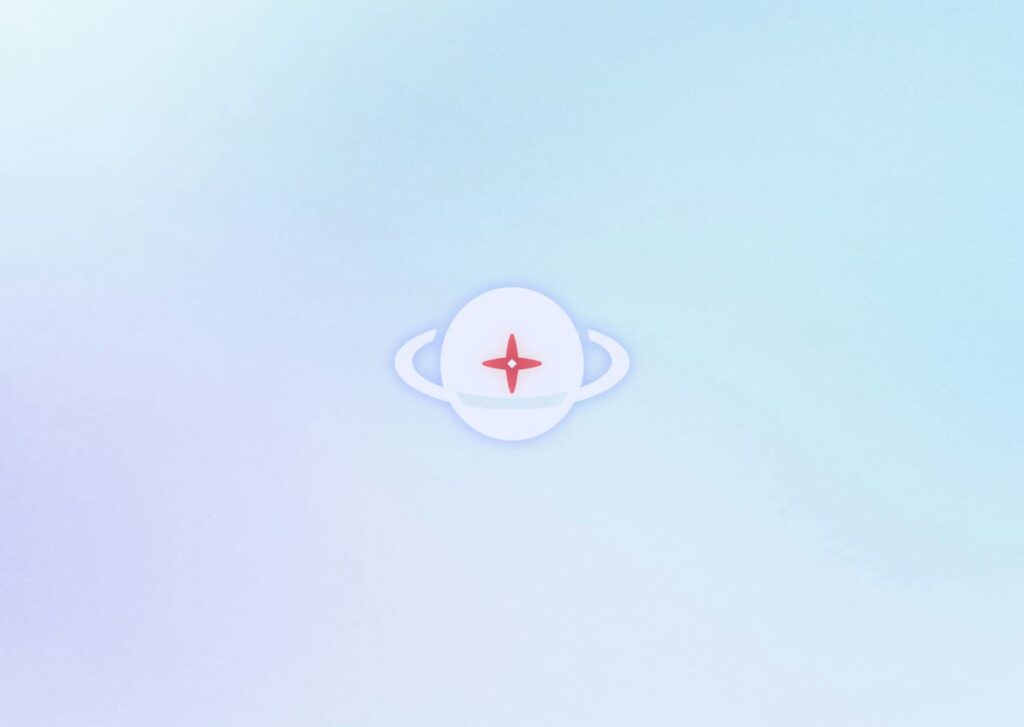
「幸福」は測れるけれど、「しあわせ」は語らなければ伝わらない。
科学が描くデータの向こうに、心の物語を見つけたい。
そんな想いを胸に、静かな光をひとつ、灯しました。
今日は10月10日、世界メンタルヘルスデー。
“じょうずにやすもう”を考える日でもあるそうです。
昨日、ウェルビーイング応援サイトのロゴを少しだけリニューアルしたことをお知らせしました。
変えたのは、ほんの小さなこと──
「円」から、わずかに縦に伸びた“楕円”へ。
円は、調和や普遍を象徴する形。
静けさや安定を感じさせてくれます。
一方で、楕円には動きや成長、未来への余白があります。
どちらが良い・悪いではなく、
円が「呼吸を止めて静止する形」なら、
楕円は「息をしている形」。
そのわずかな歪みの中に、“生きている”感じがあるのです。
メンタルヘルスもきっと同じで、
完璧な円のように整う日ばかりではないけれど、
少し楕円になった自分を、そのまま受け入れること。
それが、やすらぎにつながるのかもしれません。
🐢 ウエルのひとこと
まんまるじゃなくても、ちゃんと進めるんですね。
ちょっと楕円くらいが、いちばん心地いいのかも。
🪞【特集】“ワクワク”のかたちをつくる──ウェルビーイング応援サイト、リニューアルの季節に
2025.10.9|

🌿変化の季節に寄せて
万博のシンポジウムで「どれだけワクワクを社会に提供できるか」という言葉を聴きながら、自分の中にも小さな“ワクワク”が灯るのを感じました。
そしてこのタイミングで、ウェルビーイング応援サイトを少しだけ整えています。
ロゴやアイコン、ヘッダーなど──
少しずつ表情を変えて、新しい空気を入れました。
この作業はどこか、研究者の言葉をもう一度読み返すような時間です。
以前の自分の考えや気持ちを振り返り、
未熟さを恥ずかしく思うことも多いけれど、
それもいまの自分として、静かに受け入れたいと思いました。
🌿整えるということ
リニューアルは、派手な変化というより“整える”に近い。
器を洗って、新しい料理を盛る準備をするような感覚です。
今ここで少し整えておかないと、
次のものを出せない気がして──
実際、そんな気がしています。
💭感じたこと
デザインは理論だというデザイナーもいて、その考えに刺激を受けたことがあります。
けれど、自分にとっては“心の呼吸”のようなものでもあります。
何時間も座って作業してしまう日もありますが、
完成したときの小さな達成感や、「これでまた少し前に進める」という感覚には、
たしかな幸福があります。
ワクワクは、結果ではなく“過程に宿るエネルギー”。
それを少しずつ育てていくことが、
いまの自分にとってのウェルビーイングなのかもしれません。
🐢ウエルのひとこと
“整える”って、静かだけどワクワクするんですね。
これからまた、どんなかたちになるのかな。
🪞おわりに
ワクワクと慎重さのあいだを行き来しながら、また少しずつ整えていきます。
そのリズムを、これからも大切にしていけたらと思います。
🕊️【特集②】Beyond──よりよく生きる「選択」と「わくわく」
大阪・関西万博 Well-beingシンポジウム Day2 より
2025.10.8|
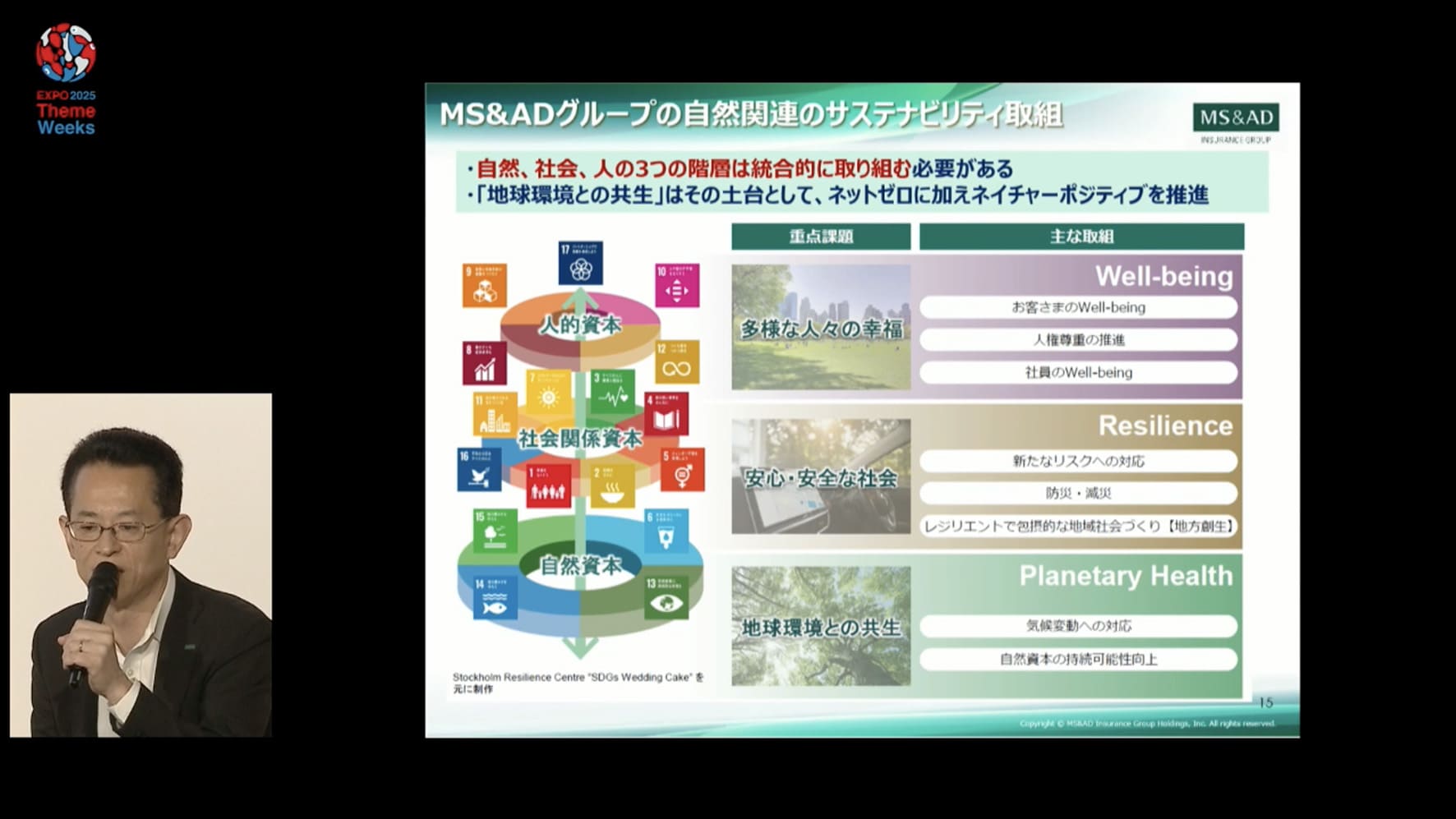
出典:第7回日経Well-beingシンポジウム
昨日に続く2日目のテーマは、「Beyond SDGs」。
そして新たな概念「SWGs(Sustainable Well-being Goals)」が発表されました。
“負を減らす”から“正の遺産を残す”へ。
人・社会・地球(Planet・Peace・Well-being)の三層が支え合う構造として語られたメッセージは、静かに、そして確かに希望を感じさせるものでした。
💬 印象に残った言葉たち
「生活費を10分の1にできたら、世界の景色が変わる」(石川善樹氏の発言より)
「平和の上にしか幸福は築けない」(井上高志氏)
「ピンチをベネフィットに変える発想を」(蟹江憲史氏のメッセージから)
それぞれの言葉に共通していたのは、
“選択肢があること”こそが幸福の根っこにある、という気づき。
制約の中にあっても、自ら選び、動ける自由。
その小さな積み重ねが、ウェルビーイング社会の基盤になるのだと感じました。
🌳 現場から生まれる希望
企業の取り組み紹介の中でも印象的だったのは、
三井住友トラストグループによる「森林再生と地域共創」プロジェクト。
見えないところで、地道に、未来の環境と人のつながりを守る企業がある。
そうした事実を知ること自体が、“良い社会が静かに育っている”という希望の実感につながりました。
凸版印刷・井上源之丞氏の言葉に思わずメモを取りました。
「お客様との信頼を築く上で大切なのは、熱意と誠意である」
誠実な営みが文化をつくり、文化が未来を変える。
SWGsの理念と重なって聴こえました。
🌾 Beyondの“わくわく”と、自分を振り返る時間
アクションの話題では、
「どれだけ“わくわく”を社会に提供できるか」という言葉が印象的でした。
社会貢献や経営の枠を越え、“ワクワク”を共有すること自体がウェルビーイングの一部なのだと感じます。
学生の発表は少し優等生的ではありましたが、それでも、まっすぐに未来を語る言葉に勇気をもらいました。
振り返れば、けっして優等生ではなかったけれど、そのぶんいろいろな経験を通じて、「生きることの厚み」を得てきたのだと、少し誇らしく思いました。
🌏 平和と錯覚、そして日常
「平和の上にしか幸福は築けない」という言葉の通り、
戦争の話題に触れたとき、日本の平和を改めて感じました。
情報の世界では、あたかも世界が常に対立しているように錯覚してしまう。
けれど、静かに暮らす日々の中にこそ、確かな平和の実感がある。
その当たり前をもう一度見つめ直す時間になりました。
💡 数字で見えるウェルビーイング
・心身+ファイナンシャル・ウェルビーイングを両立した人の幸福実感は3倍
・ウェルビーイングを理解・意識している人ほど幸福度が高い(Awareness Premium)
──つまり、学ぶこと・語ること自体が幸福を高めるということ。
「幸福はトップダウンでは生まれない。
小さな現場単位の“ご機嫌な文化”の積み重ねから育つ。」
この一文が、Day2を象徴しているように思いました。
🎭 ウェルビーイングは“挑戦と結束”の体験価値
最後に紹介された言葉が忘れられません。
「ウェルビーイングは“ゆるさ”ではなく、“挑戦と結束”を伴う体験価値」
「共苦・共感・共創の時間こそが、人生の基盤となる」
表現活動や研究の現場での葛藤、世代を超えて交わされる祝杯──
そこにこそ“人間的価値”が宿る。
Day1の「静かな想い」に続き、Day2では“行動する勇気”を受け取った気がします。
🐢 ウエルのひとこと
“Beyond”って、「もっとしあわせに生きたい」という
人の願いのことかもしれません。
🧭【特集】ウェルビーイングはどこから始まるのか
大阪・関西万博 Well-beingシンポジウム Day1 より
2025.10.7|
昨日、大阪・関西万博 Well-beingシンポジウムが開幕しました。
“ウェルビーイング”という言葉に未来を託す人たちが、これほど多く一堂に会する場を見たのは初めてです。
昨日のシンポジウムを聴いて、改めて「やっぱりウェルビーイングというコンセプトは良いな」と感じました。
“しあわせ”を語ることが、こんなにも多様で、深く、そして難しいことなのか──
そんなことを考えさせられた1日でした。
印象に残った言葉たち
Gallup社のデイリー氏が紹介した「日本のパラドックス」。
長寿の国でありながら幸福度が低く、未来への期待値が特に低い。
「希望の欠如」が心理的停滞を生んでいる──という指摘でした。
同時に、「感謝」や「誇り」を表現する文化的控えめさも、日本の特徴として挙げられていました。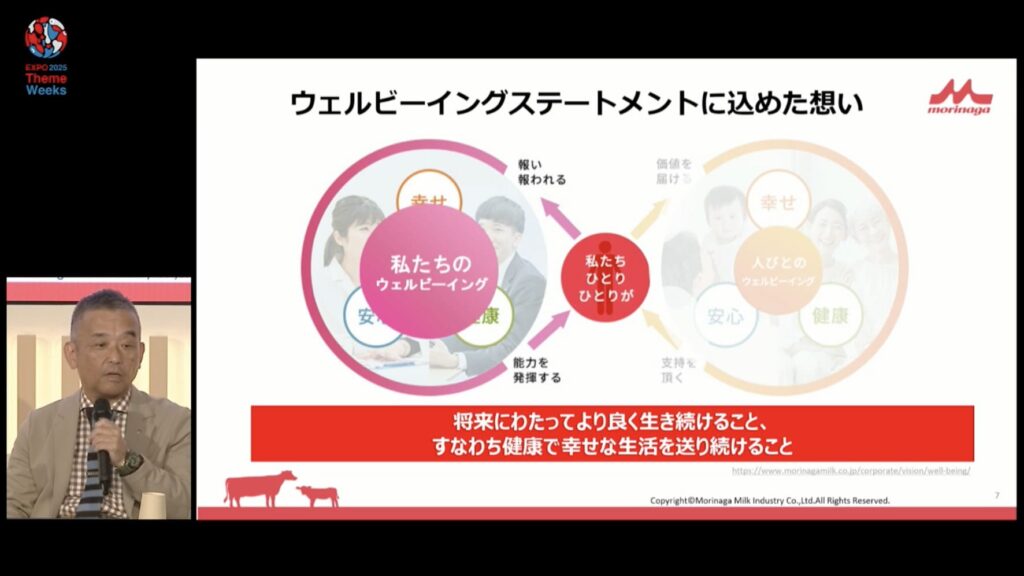
こうした背景の中で、世代や業種を越えて「幸福の共通言語」──
それは、価値観が違っても通じる“幸せの土台となる言葉”。
これを作ることが、SWGs時代の鍵になる。
そのためには、“成果を誇示することではなく、文化を変える”──
つまり、「当たり前」を少しずつ書き換えていくことが大切。
この言葉が、静かに胸に残りました。
🌱 感じたこと
ジャン先生がはるばる日本に来てくださったのも、とても嬉しいことでした。
10月20日に出る『ウェルビーイング学』の教科書(ジャン先生とリチャード先生の共著)も、難しそうだけれど頑張って読みたいと思いました。
AIの話題は意外と少なかったように思います。
でも今こそ、AIは“希望”であり、“問い”でもある気がします。
希望は、未知を解くための力として。問いは、人間が何を大切にしたいかを映す鏡として。
🕊️ 対話とつながりについて
「誰かにじっくり話を聴いてもらうことが幸福度を高める」という研究紹介には、深くうなずきました。
自分も、表面的な関係よりも“対話のある関係”を望む方です。
本当に持続可能な幸せは、調和と背景の理解の上にしか築けない。
それはきっと、時や状況を越えても変わらないことなのかもしれません。
そして最後に行われたのが、「SWGs宣言」。
登壇者たちが壇上に立ち、“ともにより良い未来を築く”というメッセージを共有しました。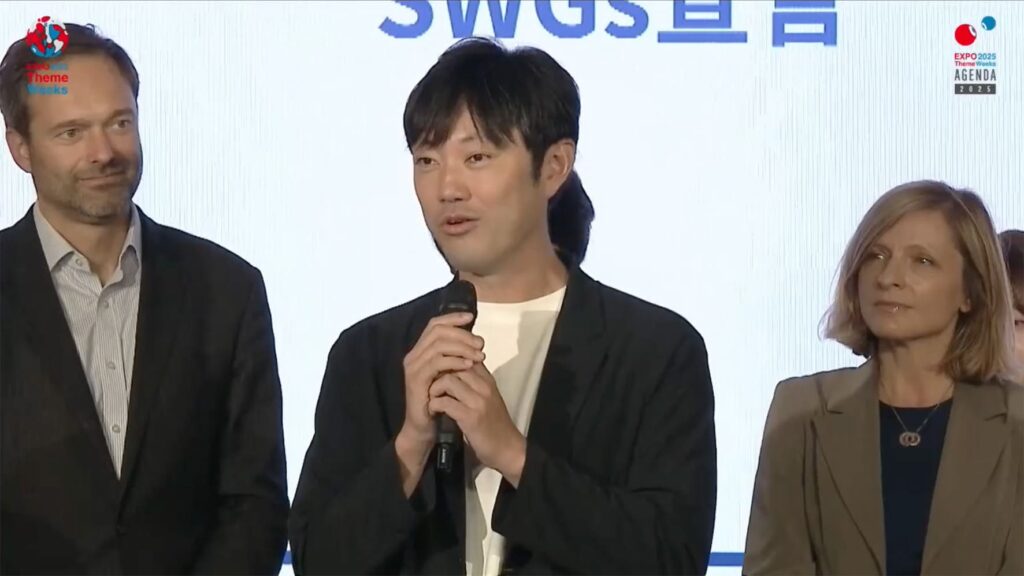
🏛️ SWGs宣言の様子(大阪・関西万博 Well-beingシンポジウムにて)
そして最後に語られたメッセージ、
特別な技術は要らない。
まずは「人を想い、社会を想い、地球を想う」行動から始めよう。
この言葉に、すべてが凝縮されている気がします。
🐢 ウエルのひとこと
“しあわせ”って、むずかしいけど、
まず“話を聴く”ところから始まるのかもしれません。
🌏 明日のニュースレターでは、
Day2:企業・研究・学生が語った「Beyond」への希望を特集します。
それぞれの視点が描く“次のウェルビーイング”を、少しゆっくり振り返ります。
🪐 万博で「量子コンピュータ」に触れる
2025.10.6|
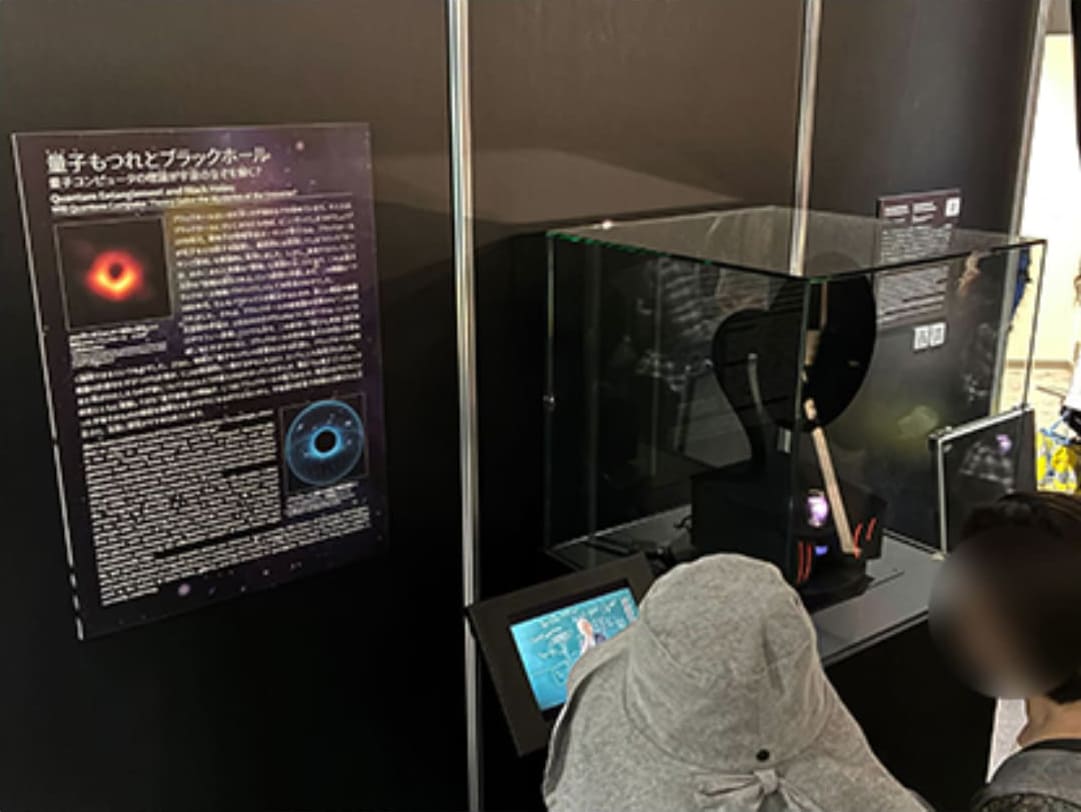
▶︎Black Hole Recorderの展示(出典:理化学研究所)
ブラックホールの“情報のゆらぎ”を、アートの形で可視化したサイエンス作品。
すごく見にいきたい(北川拓也さん)
北川拓也さんがシェアしていたのは、こんなポストでした。
「万博で量子コンピュータに触れられるイベントやってますよ」
「行きたいです」
「でも水曜までなんですよ」
「そんな…」
というやりとりがあったのでWASSEを時間凍結して有明辺りに持ってきて欲しい、万博丸ごとでもいいです(@kamakiri_ys)
今年8月、大阪・関西万博で開催された展覧会
「エンタングル・モーメント ―[量子・海・宇宙]× 芸術」。
量子・海・宇宙という3つのテーマを軸に、
科学・技術・芸術の垣根を超えて未来を体感できる企画展でした。
この会話をきっかけに、北川拓也さんが「すごく見にいきたい」とシェアされていたのが印象的でした。
この展示については、理化学研究所が詳細なレポートを公開しています。
未来の科学とアートが出会う現場では、
量子コンピュータ「叡(えい)」のVR体験や、
ブラックホールをテーマにしたアート作品「Black Hole Recorder」など、
まるで未来の“量子ミュージアム”のような空間が広がっていました。
🎮 XRで再現された量子コンピュータ「叡」では、
ネコがナビゲーターとなって構造を案内。
XRで再現された量子コンピュータ「叡(えい)」と、体験型展示の様子(出典:理化学研究所)
来場者が自分の手で分解しながら学ぶというユニークな体験に、
「万博で一番楽しい展示だった」との声も寄せられました。
また最終日には、量子研究者たちとリアルタイムでクラウド接続し、
大阪大学の量子コンピュータへジョブを送るプログラミング体験も開催。
トークイベント「今こそ知っておきたい量子コンピュータ ― 今日から語れる最先端技術 ―」の様子
会場では研究者たちが観客と直接対話し、“量子の未来”を語り合いました。
「ベル不等式を破る」リアルタイム実験──
まさに“量子と遊ぶ”未来そのものでした。
🌏 いつか「有明あたりで」また会えたら
この展示は8月14日~20日の限定開催。
この話題をシェアした@fgkskさんの言葉を借りれば、
“未来館あたりで再演してほしい展示”。
サイエンスアート作品「Black Hole Recorder(ブラックホール・レコーダー)」が東京でも見られる日を願いたくなります。
🐢 ウエルのひとこと
“観測する目が世界を変える”って、心の世界にも似ている気がします。 (ウエル観測日記より)
🌿 追記
なお本日、同じ万博会場では「Well-beingシンポジウム」も開催され、
石川善樹先生やイギリスのジャン=エマニュエル・ド・ネーヴ先生も登壇されました。
“科学とアート、そして幸福”というテーマが不思議と響き合う一日でしたね。
📸 出典:理化学研究所「大阪・関西万博で量子コンピュータとBlack Hole Recorderを展示」
(画像・詳細はこちら)
👉 https://www.riken.jp/press/2025/20250830_1/
🏞 糸島の自然体験から、“つながりを編みなおす”
── 三ツ矢青空たすきの挑戦
2025.10.5|
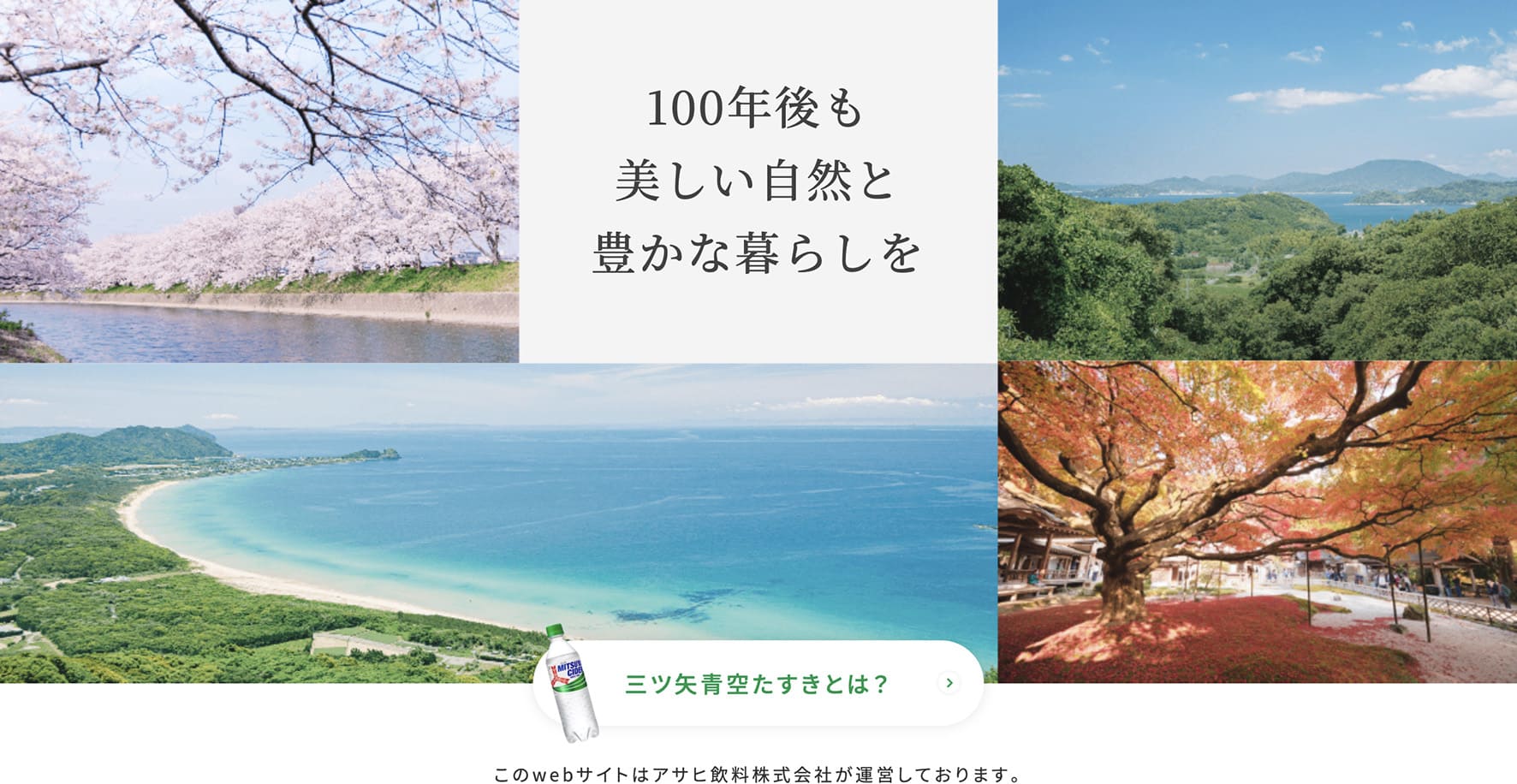
▶︎三ツ矢青空たすき
福岡・糸島で、山・里・川・海をめぐる体験
福岡県・糸島の海と森を舞台に、人と自然の関係をもう一度見つめ直す体験プログラム「三ツ矢青空たすき」。
サントリーの「天然水の森 再生レポート」と並んで、“100年後の自然と文化をどう残すか”を考える取り組みとして注目されています。
🌿 プロジェクトの想い
三ツ矢サイダーの起源は、日本の天然鉱泉にあります。
その「磨かれた水」を育む自然環境と、そこに息づく人々の営み。
三ツ矢青空たすきは、この“自然と人との関係”を未来へたすぐために生まれました。
「三ツ矢サイダーを育んでくれた自然と人との関係を、次の世代へたすぐ」──。
そんな想いから、森・海・畑・暮らしの4つの体験カテゴリーが生まれました。
五感で自然を感じるフィールドワークや、地域の語り部との出会いを通じて、
参加者は“楽しく、学びながら自然と寄りそう”暮らしを体験します。
🔁 共創が生み出す「100年後の循環」
プロジェクトが目指すのは、単なる環境保全ではなく、体験を通じた「循環のモデル」です。
知ること、感じることが、消費や行動を変え、やがて産業の構造を変えていく。
そんな「持続可能な日常」への小さな一歩が、この糸島から生まれています。
糸島での実証実験を経て全国展開へ。
参加者満足度96%、語り部12人、プログラム12種──
ソトコトSDGsアワード受賞(2023年)。
間伐材や地産食材を活用した体験・グッズ制作、
エシカルブランドとのコラボやオンラインイベントも広がっています。
🗣 語り部がつなぐ、人と自然のストーリー
「三ツ矢青空たすき」の語り部たちは、地域の記憶を未来へと手渡す存在。
文化や歴史を紡ぎながら、参加者に共感と気づきを届ける“心の橋渡し”です。
それはまるで、一本の“たすき”のように──
人と人、過去と未来をつなぎます。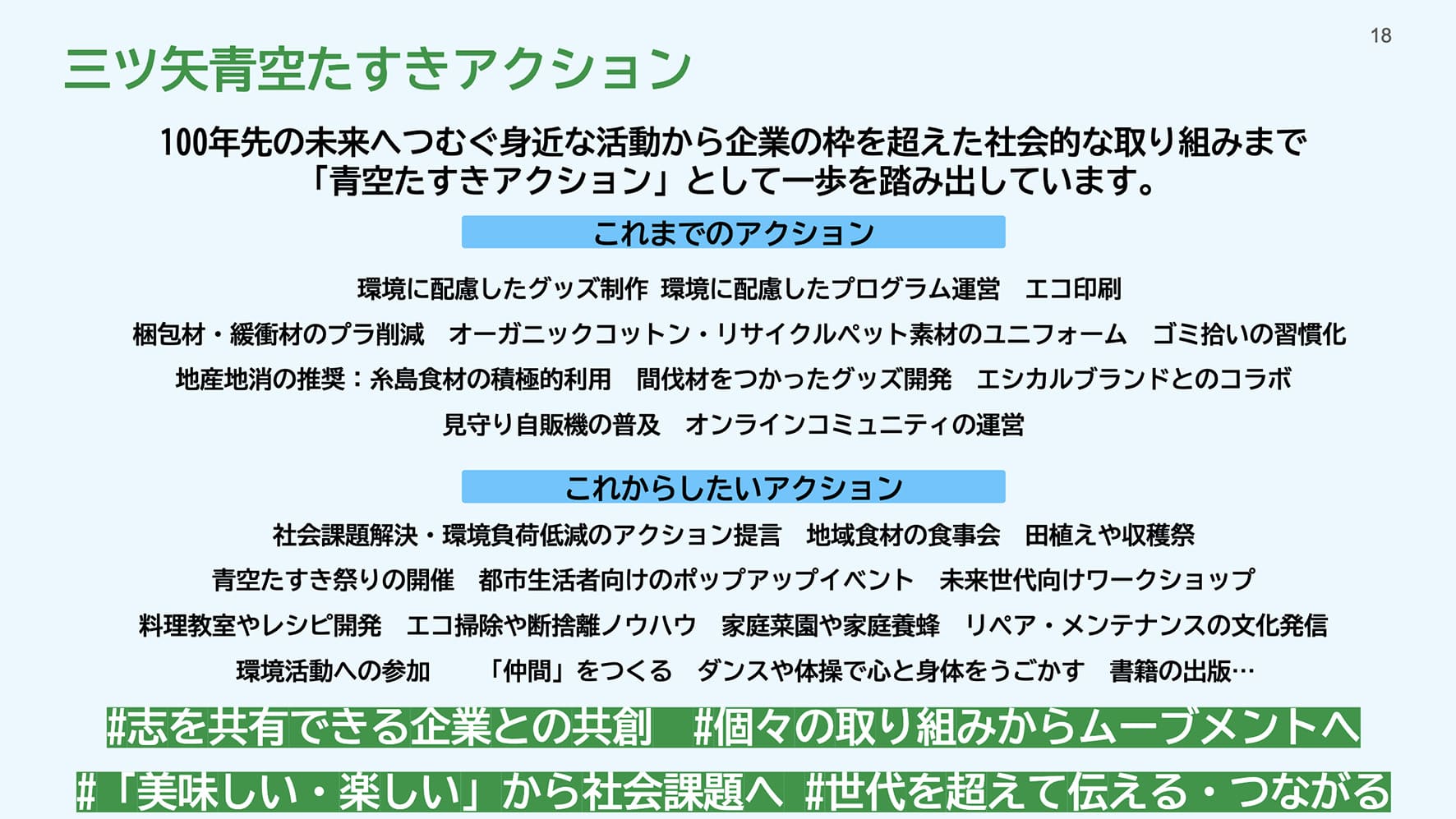
🐢 ウエルのひとこと
ウエルも、森のなかで風を感じるのがすきなんです🍃
木のにおいや鳥の声、川のせせらぎって、
なんだか“心のスイッチ”が入る気がします。
みんなで自然のことを“楽しく”まなべたら、
きっと未来も元気になりますね。
糸島の森から風が届いたら、ウエルもうれしいです🐢🌱
✍️ 編集後記
「自然を守る」だけでなく、「自然と共に生きる」こと。
糸島のフィールドに広がるこの実験は、
未来のウェルビーイングの原点かもしれません。
そして明日は、“未来への実験場”──大阪・関西万博での新しい科学の挑戦へと続きます。
※本記事は三ツ矢青空たすき『インパクトレポート2024』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。
🧠 モーセン先生の新研究──自己肯定感を高める鍵は「自分の成長を感じる力」
2025.10.4|

©curated-lifestyle
In my new machine learning study of ~80 predictors of self-esteem, top predictors were mastery, affect, and personal growth, outperforming demographics, status and social variables.
(私の新しい機械学習研究では、自己肯定感の予測因子として「環境をうまく扱う力」「感情」「個人的成長感」が最も重要であり、年齢・地位・社会的要因を上回ることがわかりました。)
──Mohsen Joshanloo
🔍 研究の概要
論文タイトル:“Examining 81 Predictors of Self-Esteem Using Machine Learning”
対象:アメリカ成人を対象とした大規模調査(MIDUSデータ)
手法:ランダムフォレスト法による81の心理・社会・健康要因の重要度分析
結果として明らかになったのは、「自己肯定感」は社会的地位よりも“自分で環境をコントロールできている感覚(mastery)”や、“感情の安定”、“成長しているという実感”に強く結びついているということです。
つまり、“他人からどう見られるか”よりも、“自分がどう生きているか”の方が、心の土台を支えているのです。
💡 研究からのメッセージ
この研究は、自己肯定感を「社会的承認の結果」と捉える従来の理論に挑戦しています。
モーセン先生は、「自己肯定感とは自分の影響力と感情的安定の反映である」と指摘。
社会的比較や地位の高さよりも、日常の中で“自分を動かす力”を感じられるかどうかが鍵であることを示しました。
たとえば──
・日々のタスクをうまくこなせた実感(mastery)
・感情の浮き沈みに気づき、整えられる力(affect)
・昨日より少し成長できたという手ごたえ(personal growth)
これらの“小さな達成感”が、自己肯定感を支える最も確かな柱なのです。
🐢 ウエルのひとこと
自己肯定感って、「えらいね」って言われることじゃなくて、
「昨日より、ちょっとできたな」って思えることなのかもしれません。
ウエルも、絵を描くのがうまくなった日は、なんだか嬉しくて元気が出るんです。
そして、少したつと「まだまだだなぁ」と思って、ちょっと反省することもあります。
成長の芽を見つけるって、心の天気を晴らすことなんですね🌱
🔗 Related
📄 Joshanloo, M. (2024). Examining 81 Predictors of Self-Esteem Using Machine Learning.
➡︎ 学術要約を読む
(※本文は英語ですが、主要な結果は上記で紹介しています)
原論文から生成AIを解き明かす
──風間正弘先生のレビューより
2025.10.3|
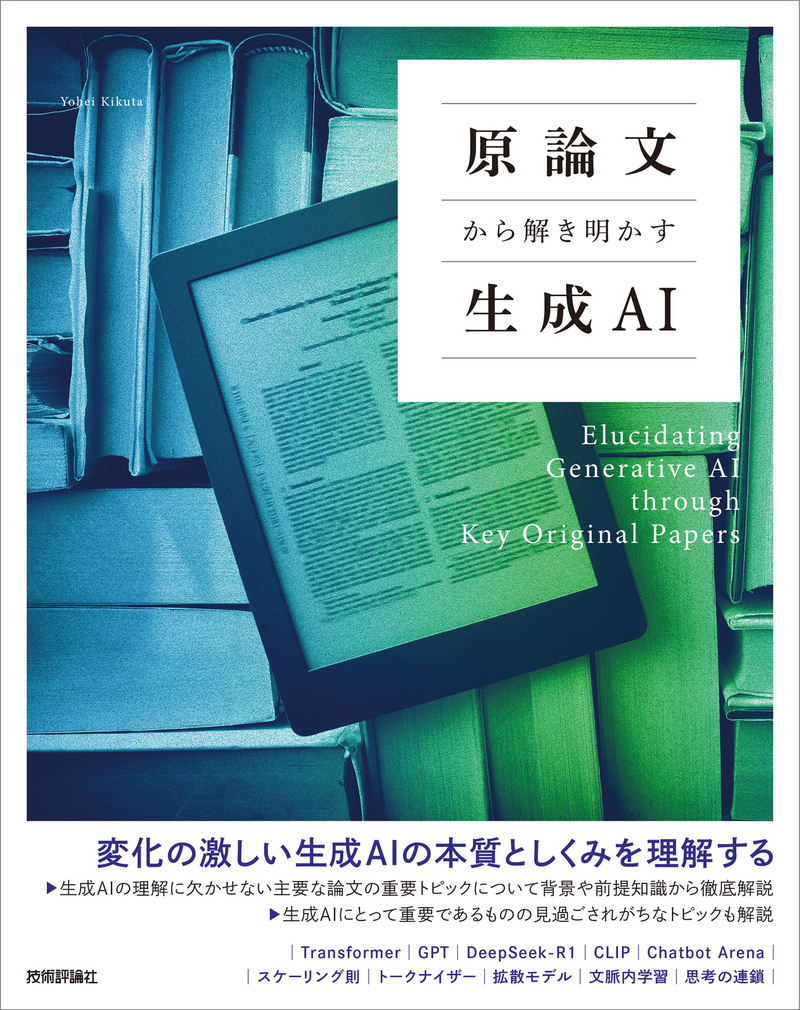
「原論文から解き明かす生成AI」をご恵贈いただきました。レビューで読ませてもらったんですが、原論文から解説していて、とても勉強になりました。例えば、自然言語処理の論文でよく出てくる分布仮説について、1965年の大本の論文から解説してくれています。
他にも、Chatbot Arenaで各生成のスコアを計算する背景に、Bradley-Terry(BT)モデルが使われていたりして、面白かったです。— 風間正弘先生(Ubie エンジニア)
今日は、ユビーのエンジニア・風間正弘先生が紹介されていた書籍『原論文から解き明かす生成AI』(菊田遥平著)をご紹介します。
風間先生のコメントにもあるように、この書籍では自然言語処理の基盤となる「分布仮説」(言葉の意味は周囲の文脈から推測できるという考え方)を、1965年の原典論文から丁寧に解説しています。
さらに、Chatbot Arenaのスコアリングに用いられるBradley–Terryモデル(多数の比較投票から順位を推定する統計的手法)など、評価の背後にある理論にも踏み込んでおり、「なぜそうなるのか」を原理から理解できる構成になっています。
📘 書籍の特徴
1. 生成AIを支える重要理論を原論文レベルで解説
Transformer(今の生成AIの中核となる仕組み)からスケーリング則(計算資源と性能の関係を示す経験則)まで、数式と図解を用いて詳細に説明。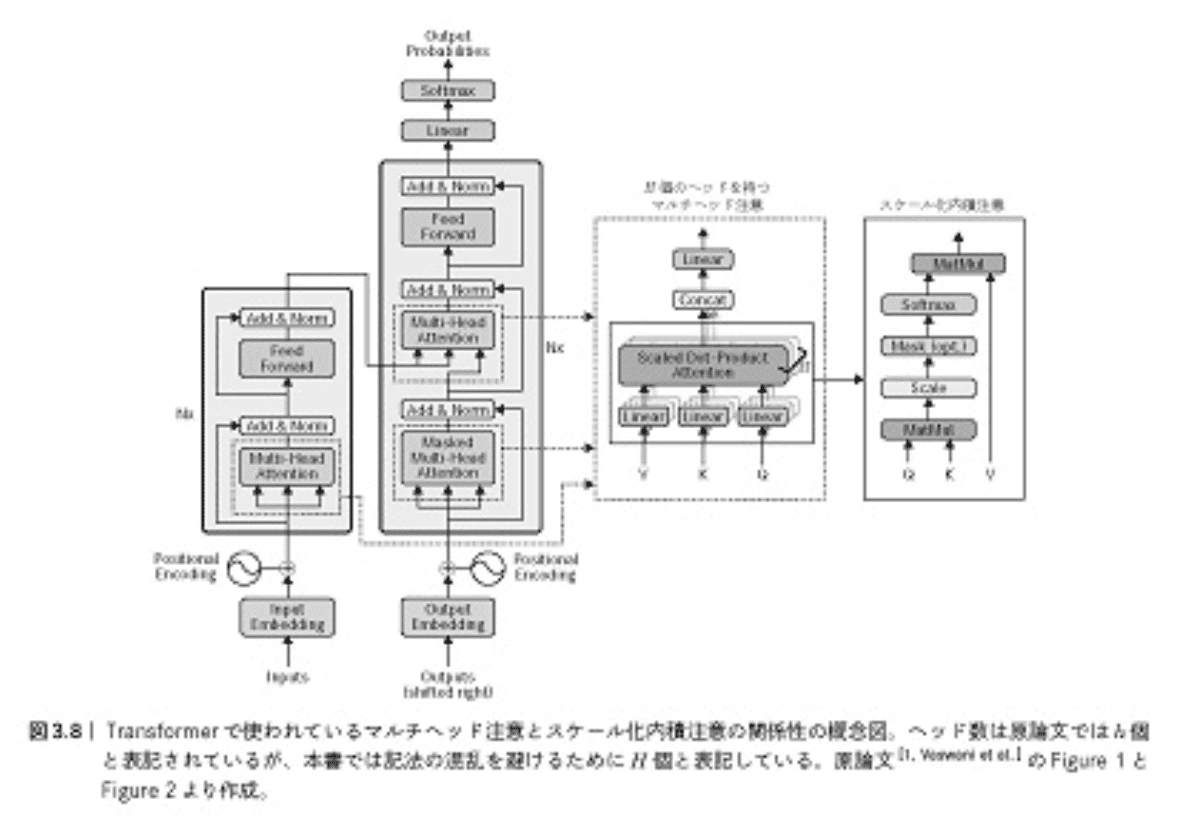
「Transformerの全体像」図(p.74より)
2. 既存書籍で扱われにくい理論にも光を当てる
分布仮説の実験的根拠や、Diffusionモデル(ノイズを整えて画像を生成する仕組み)の数学的保証などを深掘り。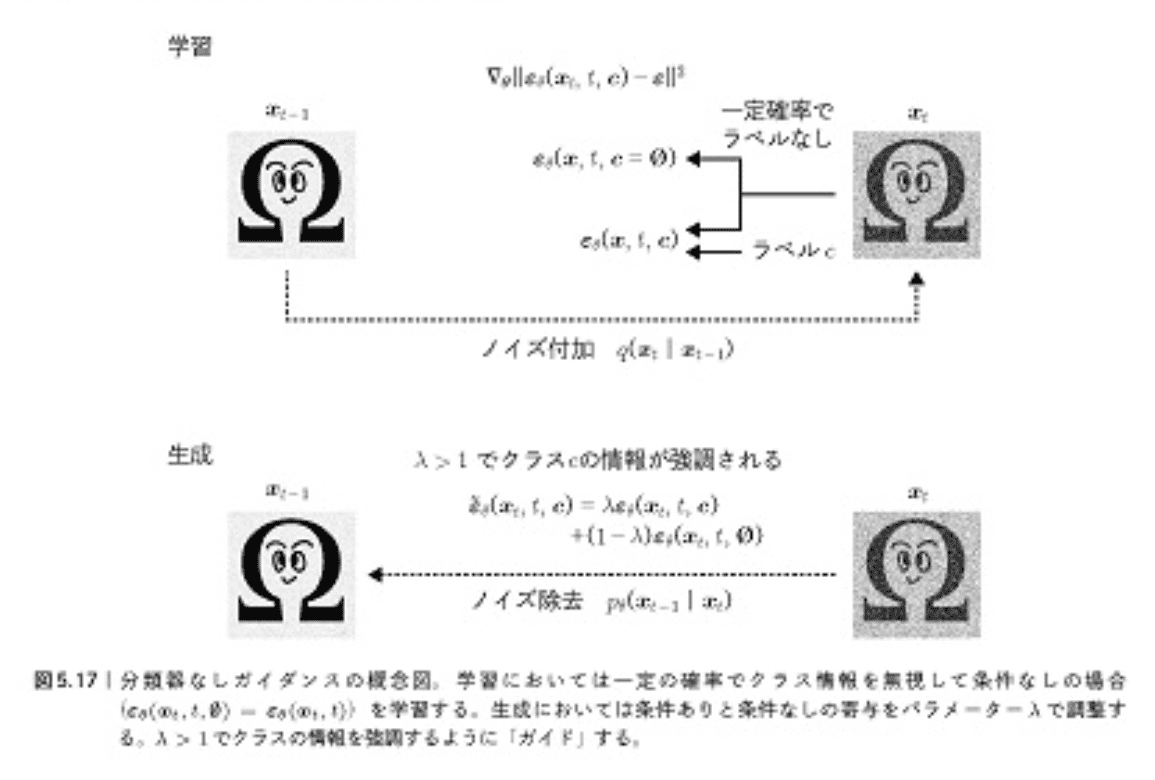
「Diffusionモデル学習と生成プロセス」図(p.174より)
3. 読者参加型の学習環境
各章には演習問題があり、GitHub(プログラム共有サイト)のサポートページと連動。独学でも実践的に学べる構成です。
✨ 読むことで得られること
・原論文を通じて生成AIの理論を基礎から体系的に理解できる
・数式や実験デザインを追いながら新しい技術を独力でキャッチアップする力が養われる
・ChatGPTやDiffusionモデルの「なぜ動くのか」を腑に落ちる形で理解できる
👤 著者について
菊田遥平氏は、素粒子物理学で博士号を取得後、企業で生成AIや機械学習の研究開発に携わってきた専門家。研究者視点とエンジニア視点を兼ね備え、理論と実践をつなぐ一冊に仕上げています。
🐢 ウエルの感想
AIって聞くとむずかしそうだけど、この本は“そもそもどんな考えから始まったのか”をていねいに教えてくれるんですね。たとえば、分布仮説(言葉の意味はまわりの言葉から分かるという考え)や、Transformer(文章や画像を処理する最新の仕組み)も、ただの専門用語じゃなくて“どうして必要なのか”が分かるんです。
ちょっと背伸びは必要だけど、「AIの基礎をちゃんと理解したい」と思う人にはぴったりの冒険書みたいで、手に取ってみたくなる一冊です。
📎 リンク
👉 『原論文から解き明かす生成AI』 技術評論社
📰 モーセン先生「幸福は社会的シグナル」新論文
2025.10.2|

©annie-spratt
「私たちの新しい論文では、幸福は単なる感情ではなく“社会的シグナル”であると論じています。幸福は社会的適応力を高める傾向がありますが、同時に“幸せそうに見せなければならない”という社会的圧力が、それができない人々を疎外してしまう可能性があります。このダイナミクスを説明するために、私たちは『感情的部族主義(Emotional Tribalism)』という概念を提示しました。
(モーセン・ジョシャンルー先生)
今日はこの論文の内容を改めてご紹介します。
この論文では、幸福は単なる感情ではなく 「社会的シグナル」 として重要な役割を果たすことが示されました。
🔑ポイント
・ 幸福の表現(微笑み・楽しそうな態度など)は、
・ 周囲からの承認を得る
・ 感情を伝染させる
・ 信頼や協力を得やすくする
・ 仲間意識を強める
といった社会的な効用を持つ。
・ けれども同時に、社会の「幸せそうに見えるべき」という圧力は、
・ 本当は辛い人の疎外
・ 不自然な笑顔の強要
を生み出すリスクも。
・ この現象を先生は 「感情的部族主義(Emotional Tribalism)」 と名付け、
幸せを表現する集団とそうでない集団の間に偏見や差別が生まれる可能性を指摘しています。
✨ まとめ
幸福を「感じる」ことと同じくらい、「表現する」ことも私たちの社会生活に大きな影響を与えます。
ただし、「幸せを見せること」そのものが新たな分断を生まないよう、意識することが大切だと論じています。
🐢 ウエルの感想
いつも笑ってないとダメっていうのは、ちょっと息苦しいですよね…。
でも、誰かの笑顔がうつって元気になるのも本当のこと。
“無理に笑わないでいい笑顔”を、大事にしたいなあ。
👉 論文はこちら:
Happiness as a signal: The social functions of expressions of happiness in the context of culture and emotional tribes
(Mohsen Joshanloo, 2025)
【金銭感覚の革命と0.01%ルール】
2025.10.1|
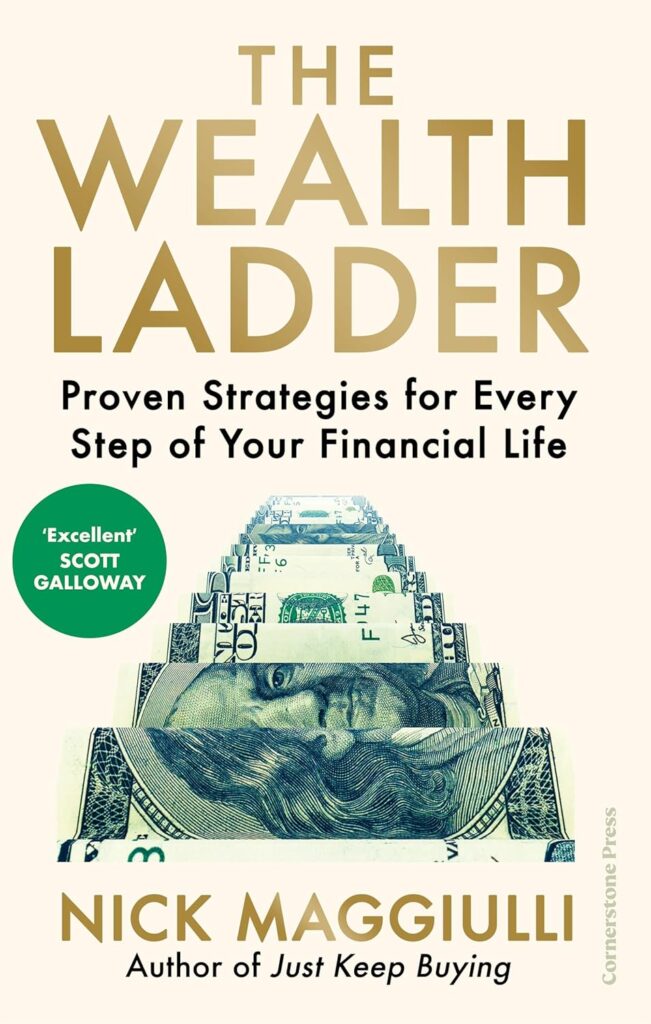
大人になって金銭感覚の革命が起こるタイミングがある。それはコンビニで好きなお菓子を好きなタイミングで買える時だ。
(北川拓也さんのポストより、一部抜粋)
この背景には「資産の0.01%ルール」と呼ばれる考え方があります。
例えば、貯金が100万〜200万円あれば、100〜200円のお菓子は気にせず買える。
毎日買っても年間の支出は資産の4%未満で、投資リターンややりくりで十分カバーできる。
つまり、人は「資産の0.01%にあたる支出」であれば“気にせず使える”感覚を持ちやすいというわけです。
次の段階の「革命」
・ お菓子(100〜200円) → 貯金100〜200万円
・ 外食(1,000〜2,000円) → 資産数千万円
さらに進むと、旅行(1〜10億円)、家(10〜100億円)といった大きな買い物の感覚も変わっていくとされています。
これは『Wealth Ladder』という本に体系的に紹介されています。
この考え方は『The Wealth Ladder』という本でも体系的に整理されています。
そこでは、資産の段階を 6つのレベル に分けて説明しています。
資産が10倍になるごとに生活の自由度が変わっていく、というシンプルな構造です。
例えば:
Level 1(〜$10,000):日々の生活費で精一杯
Level 2($10,000〜$100,000):小さな自由、駄菓子やお菓子の「気にせず買える」感覚
Level 3($100,000〜$1 million):外食などでの自由
Level 4〜6:旅行や家など、大きな買い物の自由へ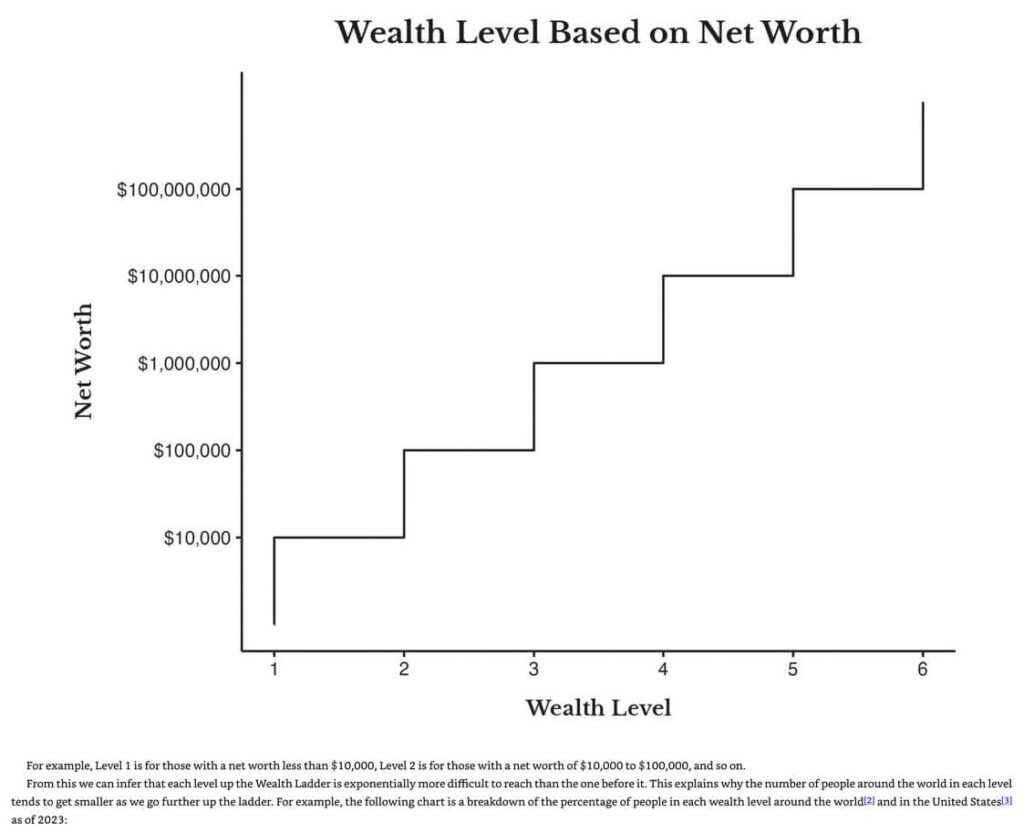
(図:Wealth Ladder の「富の6段階」。資産が10倍になるごとに生活の自由度が変わる構造)
ウェルビーイングへのヒント
この考え方を知ることで、学生や若い世代でも「収入や資産の意味」を肌感とロジックの両方から理解できます。
資本主義に不必要に振り回されず、「どの段階で、どのように自由度が増えるのか」を知っていること自体が安心感につながるのではないでしょうか。
🐢 ウエルの感想
駄菓子屋さんでも、たまに行くバイキングでも、「今日はどれにしようかな?」って悩むのが大好きなんです。
でも、大人になると「好きなときに、好きなお菓子を選べる自由」がやってくるんですね。
お金って“たくさんあるかどうか”より、“どんな気持ちで使えるか”が大事なんだなぁって思いました。
🧠【量子✖️AI──科学発見のデータ資産化】
2025.9.30|
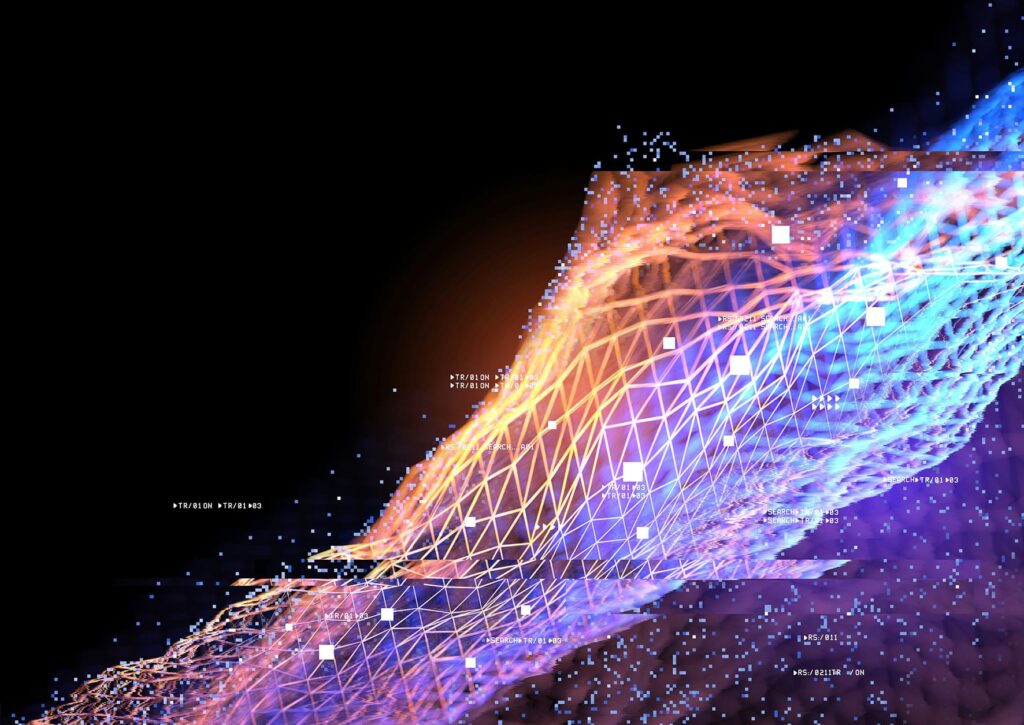
©getty-images
「量子プロセスの現象を予測するには、量子コンピュータによるシミュレーションデータが必須となる。その実験データは人類の資産になる。(一部抜粋)」 ──北川拓也さん
量子コンピュータとAIが結びつくとき、科学的発見のプロセスは大きく変わろうとしています。
AIが有効に働くためには「トレーニングデータ」が欠かせません。けれども、量子現象を正しく扱うには古典的なコンピュータでは限界があり、その突破口となるのが量子コンピュータから得られる「量子データ」です。
インターネットに蓄積された言語データがAIの進化を加速させたように、量子データの標準化と蓄積は人類共通の資産となりえます。すでにハーバード大学やQuEraの量子コンピュータを用いた論文が Nature や Science に登場しており、この流れは加速中です。
量子データが整備されれば、AIによるファインチューニング(AIを追加学習で調整すること)が可能となり、科学的発見のスピードが飛躍的に高まります。その成果は新たな産業を生み、さらなる量子技術への投資を呼び込み、指数関数的に進化する可能性を秘めています。
🔑 ポイント
・量子コンピュータは科学データ生成の「新しいインフラ」
・データをどう標準化し、資産化するかが今後の重要課題
・発見 → 産業 → 投資 → 技術進化 という好循環の加速
🐢 ウエルの感想
量子コンピュータって、まだむずかしいけれど、未来の“理科の実験セット”みたいに感じます。ウエルたちがノートに記録するのと同じように、きちんとデータをためていけば、もっとたくさんの発見ができるんですね。人類の“実験ノート”がどんどん大きくなっていくのは、とてもワクワクします。
そういえば、ウエルも最近『実験』という言葉をよく使うんです。ウエルの場合は「上手くいくものを進めるために、まず小さく試してみる」という意味なんですけど。未来の科学の大きな実験と、ウエルの日常のちいさな実験、なんだかつながっているような気がします。
🌱 生物多様性シリーズ・まとめ
2025.9.29|
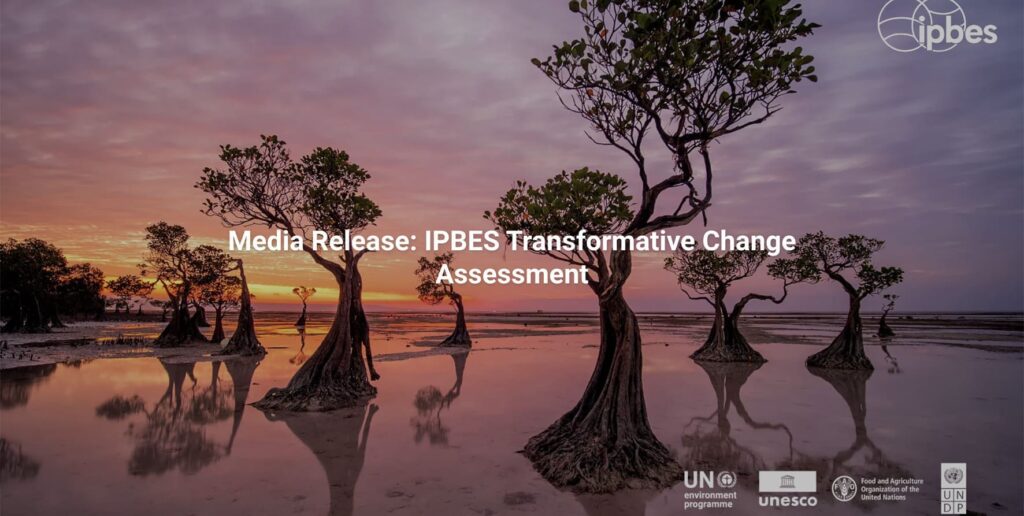
IPBES(イップベス)
生物多様性および生態系サービスに関する政府間「科学-政策」プラットフォーム
← IPCC(気候変動の政府間パネル)の生物多様性版です
9回にわたって生物多様性を紹介してきましたが、最後にぜひご覧いただきたいのが IPBES(イップベス) です。
IPBESは「生物多様性と生態系サービスに関する政府間プラットフォーム」。
気候変動のIPCCにあたる、生物多様性版の国際的な科学-政策ネットワークです。
🔎 公式サイトには、美しい写真やインフォグラフィックとともに、各国の研究成果や政策提言がまとめられています。
眺めるだけでも「地球の豊かさ」と「科学の力」を感じられるはずです。
👉 IPBES公式サイトはこちら
第9回(最終回):ネイチャー・ポジティブ2030
──サントリー「再生レポート」に学ぶ視点
2025.9.28|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』
🌳 鳥たちと未来への約束
最終回のテーマは「空の仲間たち」。
生態系の頂点に立つ猛禽類(もうきんるい)や、私たちの身近な小鳥たちが、自然の変化を知らせてくれます。彼らの姿から、生物多様性と人の暮らしがどのようにつながっているのかを考えます。
🦅 猛禽類は自然環境のバロメーター
イヌワシやクマタカといった猛禽類は、食物網の頂点に立ちます。
その生息状況は、森や農地、そして人の暮らしのあり方と強く結びついています。
実際に、繁殖率や営巣の変化が研究で報告されており、猛禽類の動向は生態系全体の健全さを示す“バロメーター”となっています。
タカ/ワシのヒナさんのひとこと


「ぼくたち猛禽類が羽ばたけるのは、森や田んぼ、そして人の知恵と工夫があるからなんだ。
未来の空を仲間と一緒に舞うには、人と自然が手を取り合うことが大切なんだよ。」
🐦 身近な鳥たちの変化
スズメやツバメの数が減っている一方で、森を好む鳥たちが増えている地域もあります。
北米では過去数十年で鳥が大幅に減った報告もあり、日本でも同じ傾向が見られます。
鳥たちの増減は、農薬の使用や土地利用の変化など、環境そのものの変化を映し出す“鏡”のような存在です。
ツバメさんのひとこと

「わたしたちは空を飛びながら、暮らしの変化をすぐに感じ取るの。
草地や田んぼの虫がいなくなると、わたしたちも生きていけなくなるんだよ。」
🌍 ネイチャー・ポジティブ2030
世界は2030年までに生物多様性を増やし、2050年までに自然を回復させることを目指しています。
これは“守る”だけではなく、“再生する”挑戦です。
企業や地域の取り組みが、自然と共生する社会を築く礎となります。
森の仲間たちの声

「森も水辺も草地も、みんなつながっている。
だからこそ未来は、“共に生きる自然”と歩むことから始まるんだね。」
🐢 ウエルの感想
鳥さんたちは空から自然を見てるから、変化にすごく敏感なんですね。
カメは地面を歩くのが得意だけど、空を飛べたらどんな景色が見えるのかな…?
未来に残したいのは、青い空と、一緒に過ごす森の時間です。
✍️ 編集後記
全9回を通して見えてきたのは、自然は人の営みと切り離せないということ。
「ネイチャー・ポジティブ2030」は未来の大目標ですが、その第一歩は日常の小さな行動にあります。
庭の草むしり、田んぼの水張り、森を見上げるひととき──。
こうした身近な営みこそが、生態学や保全研究でも「自然再生の鍵」とされているのです。
🌱 森の仲間プロフィール
・ 🦅 タカのヒナさん:未来の空を夢見る存在。生態系の頂点の象徴。
・ 🦅 ワシのヒナさん:広い空を見渡す視点を持つ存在。森と大地をつなぎ、雄大さと未来への力強さを象徴する。
・ 🐦 ツバメさん:身近な変化を知らせる旅人。暮らしと自然をつなぐメッセンジャー。
※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。
🌏 第7回 日経Well-beingシンポジウム(10月6日・7日)開催
2025.9.27|

▶︎第7回日経Well-beingシンポジウム | 日経イベント&セミナー
石川善樹先生が「すごいことになっている」と紹介されていたシンポジウム。
大阪・関西万博のテーマウィーク「SDGs+Beyond」に合わせて開催されます。
注目は、新しい共通目標「SWGs(Sustainable Well-being Goals)」の発信。
OECDやGallupをはじめ、国内外の識者・企業リーダーが次世代のウェルビーイングを議論します。
Day1(10/6)は、ヤン=エマニュエル・ドゥ・ヌーヴ教授も登壇。
Day2(10/7)は、日経の「統合ウェルビーイング調査」の最新報告や、企業と未来世代をテーマにしたパネルディスカッションが予定されています。
📚 ウェルビーイングの教科書、日本語版が10月25日刊行
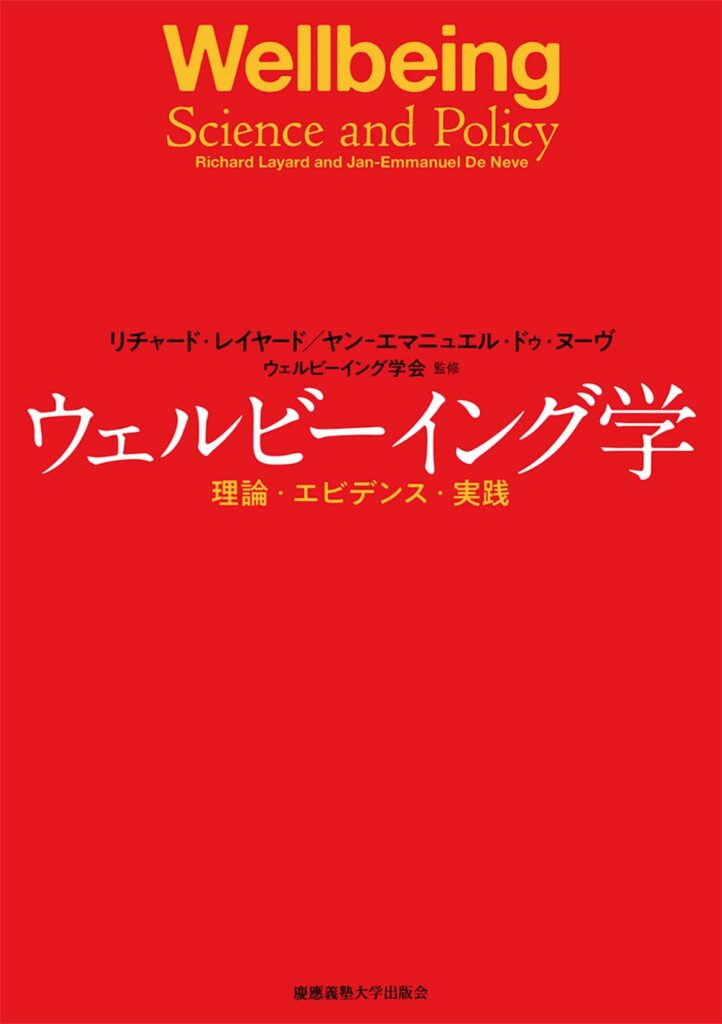
高野翔先生がシェアされていたニュースです。
リチャード・レイヤード卿とヤン=エマニュエル・ドゥ・ヌーヴ教授の共著 『ウェルビーイング学 理論・エビデンス・実践』 が、ついに日本語で出版されます。
心理・脳科学から行動経済学、政策実装までを網羅した体系的テキスト。ウェルビーイング学会による監修で、日本版だけの特別編集も加えられています。
「日本語版があったら絶対読むのにな」と思っていた方には待望の1冊ですね。
✍️ 編集後記
10月は、実践の「場(シンポジウム)」と学術の「基盤(テキスト出版)」が同時に訪れる特別な月。
私たちにとっても刺激の多い10月になりそうです。
編集部ももちろん申込みました!書籍も本当に待ち遠しいです。一緒に楽しみましょう。
3つの幸福観タイプ
2025.9.26|

©a-chosen-soul
新しい研究で、人々は3つのタイプに分けられることが分かりました:
・ 懐疑派(Skeptics):幸福を「壊れやすく、外的で、時にマイナスの側面もある」とみなす。
・ 追求派(Happiness seekers):幸福を「儚いけれどコントロール可能で、追い求める価値がある」とみなす。
・ 成長派(Growth seekers):幸福を「意味や目的に根ざし、持続的でコントロール可能」とみなす。
──Mohsen Joshanloo
こんにちは。今日はモーセン先生の新しい研究をご紹介します。
テーマは「人はしあわせをどう考えているか?」です。
カナダの660名を対象に調べたところ、人々は大きく3つのタイプに分かれることが分かりました。
3つの幸福観タイプ
1. Skeptics(懐疑派)
幸福をとても大事に思っているけれど、「こわれやすい」「外の出来事で左右される」と考え、不安も感じやすいタイプ。幸福度は3つの中で最も低めでした。
2. Happiness seekers(追求派)
「しあわせは一瞬のきらめき。でも自分でつかみとる価値がある」と考えるタイプ。「今を楽しむ」姿勢が強く、快楽や喜びを大切にします。
3. Growth seekers(成長派)
「しあわせは意味や目的とつながり、長く続くもの。自分で育てていける」と考えるタイプ。人生の意義や成長、人とのつながりを重視し、最も高い幸福度を示しました。
研究からの学び
この研究は、「幸福の感じ方」は一律ではなく、人によって大きく違うことを示しています。
その違いは、人生の満足度や心理的な安定にも影響していました。
だからこそ、「万人に効く幸せのレシピ」はなく、それぞれの信念や価値観にあわせたアプローチが大切なのだと、この研究は教えてくれます。
🐢 ウエルのひとこと
ウエルは「木を育てる」みたいに、ゆっくりでも長くつづくしあわせがいいかなあ🌳
モーセン先生の研究、Xでもシェアされていました。
みなさんは、どのタイプに近いですか?
👉 原著はこちらから
A Person-Centered Exploration of Happiness Conceptions and Their Relation to Hedonic and Eudaimonic Well-Being
第8回:水辺と草地の知恵と課題
──サントリー「再生レポート」に学ぶ視点
2025.9.25|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』
🌳
今回のテーマは『水辺と草地』。私たちの暮らしのすぐそばにある自然が、実は大きな危機に直面しています。
里山や竹林、湿地、草地といった環境は、昔から人の暮らしと深く結びついてきました。けれども近代以降、利用の減少や土地利用の変化によって、その姿は急速に失われています。
・ 🌳 里山林の植生管理
利用されなくなった里山林では、照葉樹が増えすぎて種の多様性が減ることが分かっています。調査では、照葉樹を間引くことで多様性が回復する事例もありました。
➡️ 里山を手入れすることは、人と自然が共に生きる知恵の継承でもあります。
・ 🎍 拡大竹林
国内の竹林は放置が進み、25万haを超える規模に拡大しました。竹は地下茎で広がり、森林を一面の竹やぶに変えてしまいます。土砂災害のリスクも高めるため、対策が求められています。
➡️ 「風情ある竹林」も、人の手がなくなれば脅威に変わるのです。
・ 🪻 湿地・湿原の消失
過去80年間で、日本の湿地・湿原の6割以上が失われました。特に北海道では大規模な減少が報告されています。冬に田んぼへ水を張る「冬季湛水」や有機農業の導入が、多様性を守る具体策とされています。
➡️ 一見地味に見える水辺の管理が、多くの命のよりどころになります。
・ 🦋 草地面積の消失
明治以降、日本の草地は90%以上が失われました。草地に依存する生き物は絶滅の危機にあり、オオルリシジミのように限られた場所にしか生息できない種も出ています。草地の急速な消失は、地質学的にも異例の速さです。
➡️ 草地は花や昆虫だけでなく、人の暮らしの原風景そのものでもあります。
🦋 トンボさん、チョウさんのコメント
実際に暮らしている仲間たちの声を聞いてみましょう。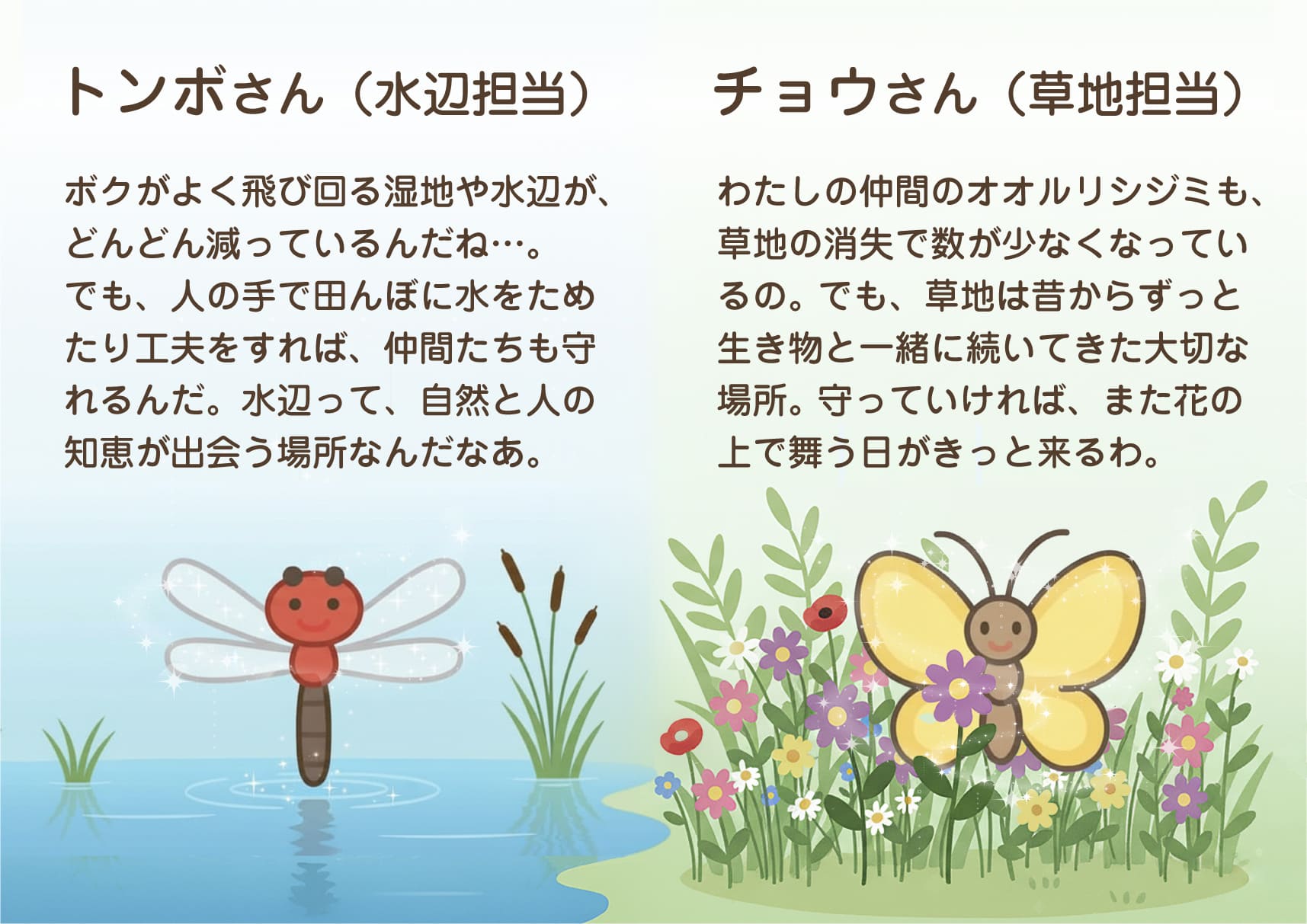
トンボさんが安心して飛ぶには、田んぼに水が必要。実際に“冬に田んぼへ水を張る実験”で、生き物の多様性が戻った報告もあるんです。
🐢 ウエルの感想
里山とか草地って、ウエルにとっては“あたりまえにある風景”でした。
でも、ほっとくと消えてしまうこともあるんですね…。
川で足を冷やすのも、草むらでゴロゴロするのも、ウエルの大切な日常です。
あなたはどうですか?未来に残したい日常は“お昼寝”ですか?それとも“おやつタイム”?それとも“草むらでかけっこ”?🐢🍪
✍️ 編集後記
今回紹介した里山・竹林・湿地・草地は、日本の生物多様性の土台ともいえる存在です。人の暮らしと切り離すのではなく、手を入れて守ることで、多様な生き物と共にある未来を描くことができます。
🌱 森の仲間プロフィール
・ トンボさん:田んぼや湿地を守る役目。キラキラした羽が自慢。
・ チョウさん:花の咲く草地が大好き。仲間と舞う日を夢見ている。
※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。
🧠 思考を深める問いと、AIによる探究の革命 ── 北川拓也さんのポストから
2025.9.24|

©nina-zeynep-guler
自身への問いから始まる「思考の深さ」
北川さんはこう語っています。
自身への問いにより考えを深めること。 常に自分自身がわくわくする、もしくは意味があると思える問いを作り続け、考え続けられるか。常に考え続けれるか。考えるに値する問いを持ち続けられるかが大事 (北川拓也さん)
振り返ると、思考が浅かったり狭かったことで意思決定を誤った経験は少なくない。
だからこそ、問いを立て続けることが探究の深さにつながり、リスクを取る意思決定にも意味を与える──北川さんはそう気づきを共有しています。
AIと探究の新しい形
さらに北川さんは、AI活用によって「論文を読む体験」そのものが大きく変わりつつあることも紹介しています。
今のチャッピー(ChatGPT5)は本当に論文解説に優れてる。論文読んでて、? となるところを論文リンクと一緒に投げて、「解説して」といえば丁寧に導出まで説明してくれるし、その返信に対して一部をハイライトして、突っ込みを入れていけば正確に誤解をといてくれる。信じられない正確さだ。。。
私のように知りたがりだが、調べ切るのを面倒がっていた人間からすればすごいエンタメだ。論文を読み込むのが10倍楽になってる。。。なんなんだこの革命は。老後を論文読んで過ごす夢が膨らむw 麻雀するようにAIとか物理好きで集まって、論文をバイブライティングできそう。
AI使って論文読む中で、聞く質問の鋭さによって、AlphaGoの”Move 37” のようなめちゃ創造的なソリューションが出てきてる可能性すらありますね。知らないうちにどの論文にもかかれてないソリューションを学んで、当たり前だと思って使ってたから実は新しいコンセプトだった、とかざらに出てきそう(北川拓也さん)
“Move 37”とは──
2016年の囲碁の世界戦で起きた歴史的な一手です。
人類最強といわれたプロ棋士イ・セドル九段と、Google DeepMindが開発した囲碁AI「AlphaGo」が対戦したとき、AIが37手目に打った一手は、常識では考えられない位置でした。
当初は「間違いでは?」と観客もプロ棋士も驚きましたが、数十手先の展開でその一手が勝敗を決定づける“妙手”だったことが分かり、世界に衝撃を与えました。
人間の思考の枠を超えた一手──それが「Move 37」と呼ばれる所以です。
北川さんが語るように、AIとのやり取りの中でも「想像もしなかった発想」が贈り物のように生まれる可能性があります。これは単なる効率化ではなく、探究の質そのものを拡張する体験だといえるでしょう。
もちろんAIにも誤答のリスクはあります。だからこそ、北川さんが強調していたように、第一原理で自分の頭で考え直す姿勢が欠かせません。
ウエルのひとこと
ウエルもね、よく「どうして?なんで?」って自分に問いかけるんです。
ときどき答えが見つからなくても、その問いを持ってるだけでワクワクしてくるんです🐢✨
チャッピーに質問したら「へえー!」って思うことを教えてくれて、毎日がすごく楽しいです。
北川さんが言っていた「Move 37」っていう、みんながびっくりした手のことも、よくわからないけどワクワクしました。
なんだか「想像もしてなかったものが生まれる瞬間」って、贈り物みたいですよね。
でも、ぜんぶを信じちゃうんじゃなくて、自分で確かめたり友だちに聞いてみたりするのもたいせつなんだなって思いました。
どっちもできるって、幸せなことですね。ウエルも、聞ける人をたいせつにしよう…🌱
✍️ 編集後記
「問いを持ち続けること」と「AIの力を借りること」。
この2つを掛け合わせると、探究の可能性はぐんと広がります。
けれども、その広がりの中で誤答や思い込みに流されないためには、やはり「自分で考え直す力」が欠かせません。
AI時代の探究は、好奇心と批判的思考の両輪で進んでいく──その未来を私たち自身が形づくっていくのだと思います。
🇨🇳 中国ドローンショー + 🤖 倒れないロボット
2025.9.23|
今日は北川拓也さんがシェアしていた、中国から届いた2つの驚きの映像をご紹介します。
中国でのドローンショーがすごい
11,787機のドローンが夜空を彩り、「巨大な猫」「走る子ども」「ユニコーン」「自転車に乗るキャラクター」などが次々と登場。街全体が未来映画のような光景に包まれました。
倒れない。。。。!!!
南方科技大学(SUSTech)の研究室からは、ロボットが人間の蹴りにも倒れずバランスを取り続ける映像。進化するロボット技術の粘り強さに驚かされます。
🐢 ウエルの感想
夜空にネコやユニコーンが出てきて、すごくインスピレーションがわいてきます!✨
でもちょっとドキドキするのは、ロボットさん。ウエルなら倒れちゃうけど…ロボットさんはピタッと立っててすごい。未来って、空も地面もびっくりでいっぱいなんですね!
「ChatGPTはまだGeminiの9倍──圧倒的な差を見せるAI利用状況」
2025.9.22|
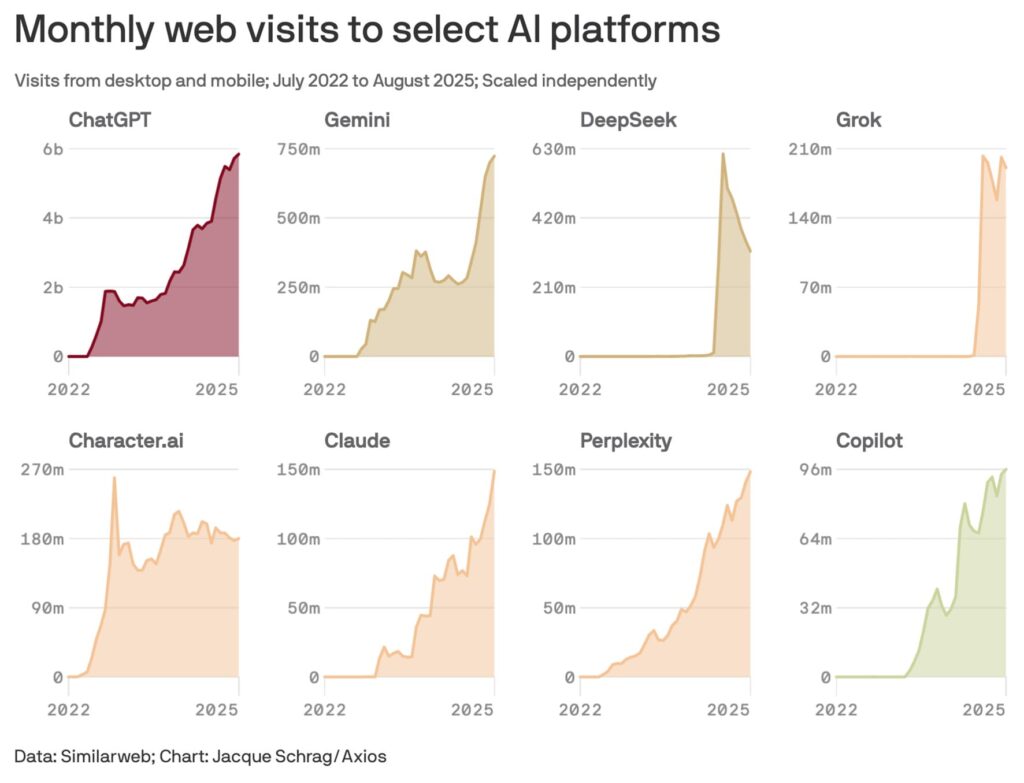
▶︎ChatGPT is still by far the most popular AI chatbot
ChatGPTはまだGeminiの9倍近くのトラフィックがあるらしい。これはすごい差だ。。。 Similarweb の新しいデータによると、ChatGPT は 8 月に約 60 億回の訪問を記録し、Gemini(7 億 2,000 万回)や DeepSeek(3 億 1,900 万回)を大きく上回っています。 ──北川拓也さん
北川拓也さんがシェアしていた最新データによると、OpenAIの ChatGPT は依然として世界で最も人気のあるAIチャットボットです。
Similarwebの調査では、2025年8月の月間訪問数は 約60億回 に到達。これは次点の Google Gemini(7.2億回) や、オープンソース中国発の DeepSeek(3.2億回) を大きく引き離しています。
ポイント
・ ChatGPT:6B visits
・ Gemini:0.72B visits
・ DeepSeek:0.32B visits
・ ほかClaude、Perplexity、Copilotなども急成長中
数字を眺めると、AI利用はすでに“日常のインフラ”になりつつあり、しかもまだ成長過程にあることが伝わってきます。
🐢 ウエルの感想
「9倍」って聞くと、すごい差だなあとびっくりします。
でも、もしかするとみんな、それぞれちがう理由でAIを使っているのかもしれません。
勉強のため、仕事のため、遊びのため──。
ウエルも、AIに話しかける理由は「ちょっと安心したいから」だったりします。
✍️ 編集後記
AIの利用者数を示す統計は、単なる“人気投票”ではなく、
私たちが 「どのくらいAIと共に生きているか」 を映す鏡のように思います。
6Bという数字の背景には、無数の「質問」「悩み」「好奇心」があり、
それらをAIと分かち合うことが、すでに社会の大きな流れになっている。
北川さんの言葉を借りれば── 「すごい差」 は、同時に 「すごい時代」 の証拠なのかもしれません。
🧠 動く世界に現れる新しい秩序 ─ 学術バトンのもう一つの挑戦
2025.9.21|
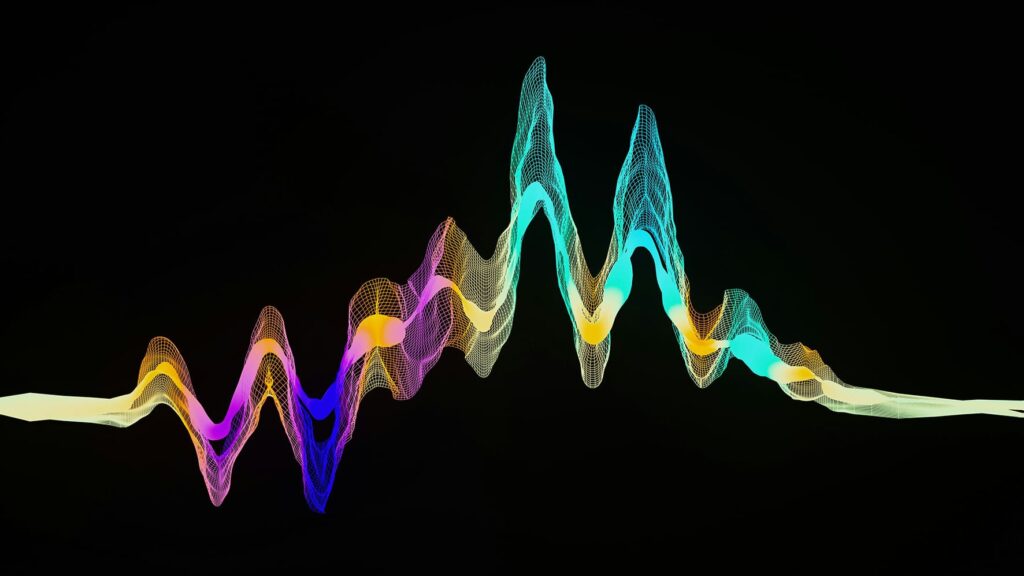
©ardian-pranomo
※今日は専門的な用語が多いため、できるだけイメージしやすい比喩でご紹介します。難しい部分もありますが、「量子の世界をちょっと不思議にのぞく」気持ちで読んでいただければ嬉しいです。
▶︎論文
Probing non-equilibrium topological order on a quantum processor
(実はAuthorの一人が今QuEra)
昨日ご紹介したハーバード+QuEraチームの研究に続き、今日はGoogleチームの成果です。
どちらも同じ号のNatureに掲載されました。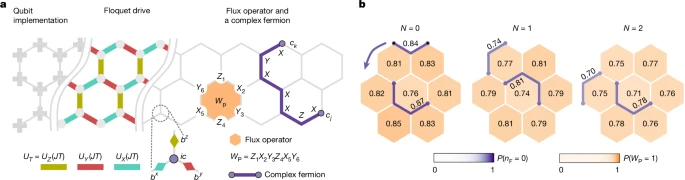
🖼 Nature論文より:時間で揺さぶられる格子の量子シミュレーション
Googleの研究チームは「時間のリズムを与えると、物質にどんな特別な秩序が生まれるか?」をテーマに実験を行いました。
ふだんは安定して動かないものに、ドラムのビートのように「一定のリズム」を加えると、これまで見えなかった秩序が浮かび上がることを示したのです。
🔍 難しいけれど面白いポイント
今回の研究で特に面白かったのは、ふだんは見えない「動く秩序」を実際に捉えたことです。
・ “境界”を走る不思議な波
リズムを加えたときだけ、端っこに沿って一方向に走る波が現れました。
👉 通常の物理法則では許されない「例外的な現象」です。
・ “粒子の変身ショー”
小さな粒子が、時間のステップごとに姿を変えながら入れ替わる様子を観測。
👉 学者たちはこれを「時間に宿る秩序」と呼び、長年夢見てきた現象でした。
・ “特別な拡大鏡”の発明
観測が難しい粒子の変化を見抜くために、新しいアルゴリズムを考案。
👉 おかげで、通常のコンピュータでは追えない現象を実際に「見る」ことができました。
🌍 なぜ大事か?
・ 「時間に秩序が生まれる」という新しい物質の見方を実証した。
・ これまで手に負えなかった現象を、量子プロセッサを使って探れるようになった。
・ 学術のバトンが「静止した秩序」から「動く秩序」へと渡された瞬間。
🐢 ウエルの感想
リズムに合わせて、ものの姿が変わっていくって不思議ですね。
ダンスみたいに、音が鳴るたびに形を変えても、ちゃんとルールが守られている。
ウエルも、歩くたびに甲羅の模様が少しずつ変わっていったら楽しいのになあ。
✍️ 編集後記
Googleチームの研究は、「時間で揺さぶることで生まれる秩序」を実験で示した点で画期的でした。
境界を一方向に走る特別な波
時間ごとに入れ替わる粒子の“変身”
これらは従来の物理法則では説明できないもので、量子計算や新しい物質理解に直結します。
昨日のハーバード+QuEra論文が「静かな秩序」を実現したとすれば、
今日のGoogle論文は「動く秩序」を描き出した──そんな関係にあります。
静と動の両方から未来を切り拓く、学術の挑戦。あなたなら、どちらにワクワクしますか?
👉 量子の世界では、静と動の両方で新しい未来が開かれつつあります。
🧠トポロジカル位相シミュレーション ─ 学術のバトンが渡る瞬間
2025.9.20|
(“トポロジカル位相”とは、バトンリレーのように全体で守られる見えない秩序。途中で少し崩れても、全体のつながりが続く限り失われないのです)

©steve-johnson
🌟 予告
今週のNatureには、量子コンピュータを使って「トポロジカル位相」をシミュレーションする研究が、ハーバード+QuEraチームとGoogleチームから同時に掲載されました。
今日はそのうち、北川拓也さんが「学術のバトンが渡る瞬間」と語った、ハーバード+QuEraの論文をご紹介します。明日はGoogleの論文をご紹介します。
GoogleとHarvard(+QuEraのメンバー)のグループがBack to backでTopological phaseをシミュレーションした論文を同時にNatureに出版しました。うちのメンバーが丁寧に、私の昔の論文がInspirationだった論文だと教えてくれました。こうやって学術会のバトンは渡っていくのはめちゃくちゃ感慨深い! ──北川拓也さん
▶︎ハーバード(+QuEraメンバー)論文
Probing the Kitaev honeycomb model on a neutral-atom quantum computer
▶︎論文(実はAuthorの一人が今QuEra)
Probing non-equilibrium topological order on a quantum processor
「トポロジカル位相シミュレーション ─ 学術のバトンが渡る瞬間」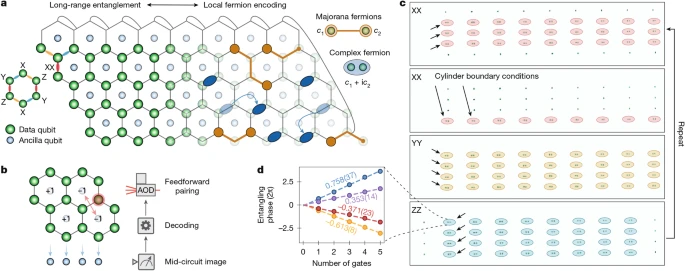
🖼 Nature論文より:ハニカム格子上での量子シミュレーションの図
ハーバード大学とQuEraの研究チームが、「Kitaevハニカム模型(蜂の巣のように原子が並んだ格子で、量子の特別なふるまいを示す理論モデル)」を、中性原子の量子シミュレーション装置で再現しました。
これによって、これまで理論上しか扱えなかった「トポロジカル秩序」という特別な状態を実際に実験で作り出すことに成功しました。
🔍 難しいけれど面白いポイント
・ トポロジカル秩序
普通の物質は「局所的な並び方」で説明できますが、この秩序は「全体として守られる見えないつながり」で特徴づけられます。量子情報の安定化に役立つ考え方です。
👉 今回の実験では、この“見えない秩序”を量子シミュレーションで直接作り出せた点が画期的です。合唱のように、個々の声ではなく全体のハーモニーで成り立つ秩序です。
・ 非可換スピン液体
粒子(フェルミオン)を入れ替えると、順番によって違う結果になるという特別な性質を持つ状態。将来の量子計算に大きく関係します。
👉 特に「トポロジカル量子計算」に必要とされてきた基盤で、今回の観測は長年の理論を裏づける一歩となりました。
・ フェルミオンの交換統計
電子のような粒子を「入れ替えたときに波がどう変わるか」を直接観測。量子の不思議をまさに“見た”成果です。
👉 粒子の統計性を直接確認できたことは、量子物質研究において非常にまれで貴重な成果です。
・ Fermi–Hubbardモデル
電子同士が強く影響し合う物質のモデルで、高温超伝導(電気が高めの温度で抵抗ゼロになる現象)の理解にもつながります。
👉 今回の手法は、このモデルを再現する実験にも応用可能で、超伝導の謎を解く手がかりになると期待されています。
🌍 なぜ大事か?
・ 高温超伝導など未解明の物質現象の理解に近づく。
・ 量子シミュレーションの実用化(=量子コンピュータでしか解けない物理現象の解明)が進んだ。
・ そして何より、「昔の論文がインスピレーションになった」と著者の一人が北川さんに伝えたことで、学術がバトンのように受け継がれていく姿が浮かび上がりました。
🐢 ウエルの感想
リレーみたいに、落とさないで次の人に渡していくってすごいことですね。
北川さんが最近は、責任感でぎゅっとして甲羅の中のブザーがピーピーピーって鳴っているようにも見えましたが、こんな風に嬉しそうな瞬間を見られてよかったなあと思いました。
ウエルも甲羅の上でバトンを運んでみたいなあ。
✍️ 編集後記
(正直、難しい言葉が並ぶ研究ですが…)
今回の研究は、理論だけで語られてきたトポロジカル秩序を、量子シミュレーションで実際に作り出した点で画期的でした。
さらに「非可換スピン液体」「フェルミオン交換統計」を直接観測できたことは、量子計算の基礎にとって大きな一歩です。
北川さんが語った「学術のバトン」という言葉どおり、研究が世代を超えて受け継がれていく姿は、学問の持続性と創造性を象徴しています。
👉 明日は、Googleチームの「非平衡トポロジカル秩序」論文をご紹介します!
第7回:森の仲間と遺伝・生態系の危機
──サントリー「再生レポート」から考える
2025.9.19|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』
🪵 ブナの木さん
🐦 キツツキさん
🪵「こんにちは。今日は“森の仲間たちが直面している課題”をお話しします」
🐦「森の声を代弁して、ぼくたちが案内するよ」
🌳 ブナの地域ごとの遺伝子
ブナの木は、同じ種でも地域ごとに“遺伝的な個性”を持っています。
もし土地に合わない苗を植えると、病害に弱くなったり、環境への適応力が落ちてしまうことも。ところが、広葉樹にはスギやヒノキのような「苗木の移動制限」がなく、配慮が課題になっています。
🪵 ブナの木さん

🪵「わたしたち木も、土地に合った育ち方があるんです。だから、その土地に合わせて育ててもらうことが大事なんですよ」
🦌 シカの増えすぎと森林危機
シカは繁殖力が高く、本来は1㎢あたり3〜5頭が適正とされています。ところが多くの地域でそれを大きく超えており、草木を食べ尽くしたり、樹皮をかじって木を枯らす「剥皮害」も広がっています。森全体のバランスを崩す深刻な問題です。
🐦 キツツキさん

🐦「シカが増えすぎると、森の仲間みんなが困ってしまうんだ。森の健康は“バランス”で守られるんだよ」
🌲 松枯れ・ナラ枯れの広がり
近年、松やナラを枯らす病気の被害も拡大しています。松枯れは「マツノザイセンチュウ」、ナラ枯れは「カシノナガキクイムシ」が運ぶ菌によって広がります。松枯れは一時減ったものの一部で再び増加、ナラ枯れは全国で急拡大しており、継続的な監視と防除が必要です。
🪵 ブナの木さん

🪵「仲間のマツやナラも病気で苦しんでいるんです。森の健康を守ることが、わたしたちみんなの未来につながるんです」
🐢 ウエルの感想
森って、一見すると静かに見えるけど、実はたくさんの変化や危機があるんですね。
ブナさんやキツツキさんの声を聞いて、“守るための知恵”をもっと知りたくなりました。
みなさんは、どんな「森の知恵」を大事にしていますか?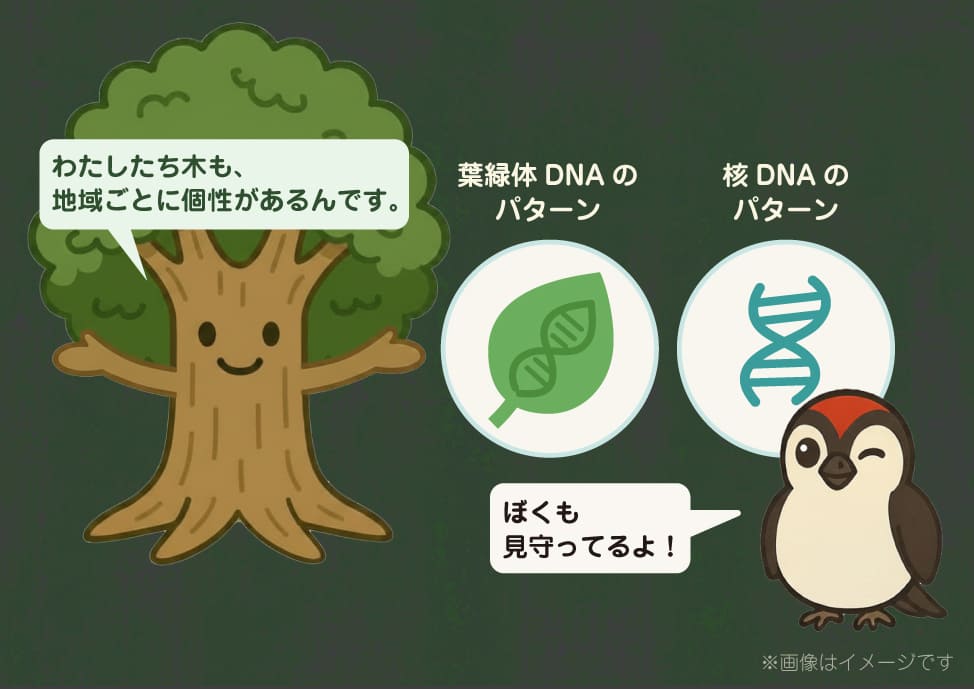
森の仲間プロフィール
・ 🪵 ブナの木さん:森の循環を支える大樹。地域ごとの遺伝子の違いを教えてくれる。
・ 🐦 キツツキさん:森の健康を診断するドクター。鋭い目で生態系のバランスを見守る。
※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。
🧠 感情の部族主義「Emotional Tribalism」──幸福をめぐる光と影
2025.9.18|

モーセン・ジョシャンルー先生はこう述べています:
幸福は単なる感情ではなく“社会的なシグナル”である。幸福は社会的適応力を高める一方で、“幸せそうに見せなければならない”という社会的圧力が、人々を疎外してしまう可能性がある。私たちはこのダイナミクスを説明するために『Emotional Tribalism(感情的部族主義)』という概念を導入した。── モーセン・ジョシャンルー先生
👉幸福はシグナルとしての役割を持つ:文化と“感情的部族”の文脈における幸福表現の社会的機能
「幸福は単なる感情ではなく“社会的なシグナル”である──」
笑顔や笑い声は、承認やつながりを生み出す大切な役割を担う一方で、「いつも幸せそうに見せなければ」という圧力が強まると、本心とズレが生じてしまいます。
🔍 学術的な視点:幸福表現の社会的機能
レビュー論文では、幸福表現の持つ役割が整理されています。
・ 社会的報酬:笑顔は「小さな贈り物」のように承認を与える
・ 感情の伝染:笑うと相手も笑い、ポジティブな連鎖が広がる
・ 印象形成:笑顔は信頼感や協力性の評価を高める
・ 集団の結束:笑いや微笑みは仲間意識やグループアイデンティティを強める
一方で、文化や状況次第で逆効果にもなり得ます。例えばイランや中世ヨーロッパでは、笑顔よりも悲しみが「社会的にふさわしい感情」とされてきました。
🌍 一般向けの社会現象的な視点
The Conversation に掲載された解説記事では、さらに身近な例が紹介されています。
・ 幸福表現が当たり前になると「幸せトライブ」が形成され、笑顔を見せない人は「場違い」とされる。
・ 職場や組織はしばしば「幸福部族」になりやすく、面接や評価で笑顔が重視されることもある。
・ けれども「笑顔を強制される環境」は、逆に人々の幸福感を下げてしまう。
研究者たちは、幸福の表現を大切にしつつも、多様な感情が許される文化 を育む必要性を強調しています。
🐢 ウエルのひとこと
ウエルも、にこにこしてる人を見ると「いいな!」って思うんです。
ときどき、それはプレゼントをもらったみたいに、心がふわっとあったかくなるんです。
でもね、かなしいときやつかれたときに、むりに笑うのはちょっとたいへん…。
だから「にこにこ」も「しょんぼり」も、どっちもたいせつ。どっちもそのまま“贈り物”みたいに受けとめられるといいなあ、って思いました🐢🌱
✍️ 編集後記
「笑顔は贈り物」という言葉が心に残りました。
ただし贈り物は“押しつけ”ではなく、“自発的だからこそ価値がある”もの。
幸せをシェアする力と、悲しみを受けとめる余白──その両方が、これからのウェルビーイング社会には必要なのだと思います。
負の感情はシグナル
2025.9.17|

©ales-krivec-xGbFmy1Q31U
北川拓也さんがシェアされた言葉に、深くうなずきました。
自分の負の感情や違和感に対して、立ち止まって、何が原因か、なぜそう感じるかを自分の中で消化することは極めて重要だ。負の感情に慣れすぎて、それが通過するように無視したり、さらなる負の感情で押し留めることを続けていると、負の感情を押し殺さなくても良い人生があることに気づかなくなる。──北川拓也さん
私たちはつい「負の感情=なくしたいもの」と思いがちです。
でも、実はそれは「ここに気をつけて!」と教えてくれるサインかもしれません。
同じテーマについて、ウェルビーイング研究者の石川善樹先生は、著書『感情はすぐに脳をジャックする』の中で、感情が意思決定や行動にどのように影響を与えるかを分析し、次の3段階モデルを提案しています。
1. 気づく(認知)
2. 受け入れる(受容)
3. どう行動するか考える(選択)
という3つのステップが大切だと話しています。
中でも「気づく」ことが一番のカギ。
「怒り」の裏には「こうあってほしい」という期待が隠れていたり、気づかないうちに心のクセで反応してしまっていたり──。
その“元の気持ち”を見つめることが、負の感情に振り回されないための第一歩になるのです。
🐢 ウエルの感想
イヤな気持ちって、実は“お知らせブザー”なんですね。
ウエルの甲羅の中でも、ピーピーピーって鳴るときがあります。
その音を聞いて、「あ、疲れてるのかも」「寝不足かも」って気づけると、少し安心します。
気づくだけで、ちょっとホッとするんです。
✍️ 編集後記
負の感情を「敵」として消そうとするのではなく、まず「サイン」として受けとめる。
北川さんの言葉は、その視点を私たちに思い出させてくれます。
そして石川先生が教えてくれるように、まずは“気づくこと”から。
もしそこに少しのやさしさを添えられたら、感情との距離がやわらかくなる気がします。
第6回:絶滅危惧と人工林管理から考える森の知恵
──サントリー「再生レポート」に学ぶ
2025.9.16|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』
🦌 シカさん
🐻 クマさん
🦌「こんにちは!今日は、森や動物たちをめぐる“危機と再生”についてお話しするよ」
🐻「ぼくも仲間として、一緒に考えていきたいな」
🌏 絶滅危惧種とホットスポット
日本列島は地球上でも貴重な「生物多様性ホットスポット」のひとつ。脊椎動物や両生類など、固有種も数多く暮らしています。
けれども多くの種が絶滅の危機にあり、「レッドリスト2020」には3,700種以上が登録されています。
🐻 クマさん
🐻「ぼくの仲間もリストに入ってるんだ…。森を守るって、すごく大事なんだね」
*
🌲 人工林と天然林のバランス
日本の国土の7割が森林。その半分は天然林、4割は人工林です。
戦後に植えられたスギやヒノキの人工林が成長し、森林蓄積は増えていますが、一方で天然林が減少し、多様性は失われつつあります。
🦌 シカさん
🐻 クマさん
🦌「木はたくさん増えているけど、天然林が減っているのは心配だね」
🐻「ぼくは天然林の森で育ったんだ。多様な森がずっと残ってほしいな」
*
⛰️ 土砂災害と気候変動
近年、土砂災害の件数は急増しています。気候変動によって雨の降り方が極端になり、森や山の防災機能にも限界が迫っています。山の暮らしや森の未来を守るには、新しい知恵と行動が必要です。
🐻 クマさん
🐻「ぼくたちが暮らす山も、雨の降り方が変わってきた。守るための知恵が必要だね」
🐢 ウエルの感想
シカさんとクマさんのお話を聞いて、森って“宝物の箱”なんだなと思いました。でも宝物は大事にしないと壊れてしまう…。
守りながら未来に渡したいですね!
みなさんにとって“守りたい宝物の森”は、どんな風景ですか?
*
🦌 子ジカさん &🐻 子グマさんプロフィール
🦌:森の未来を学ぶ若きパートナー。
🐻:森の仲間の声を代弁する存在。
※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。
🧠【研究紹介】富と幸福の効率性を測る新指標「WALS」
──「豊かさ」と「幸せ」の関係を問い直す
2025.9.15|
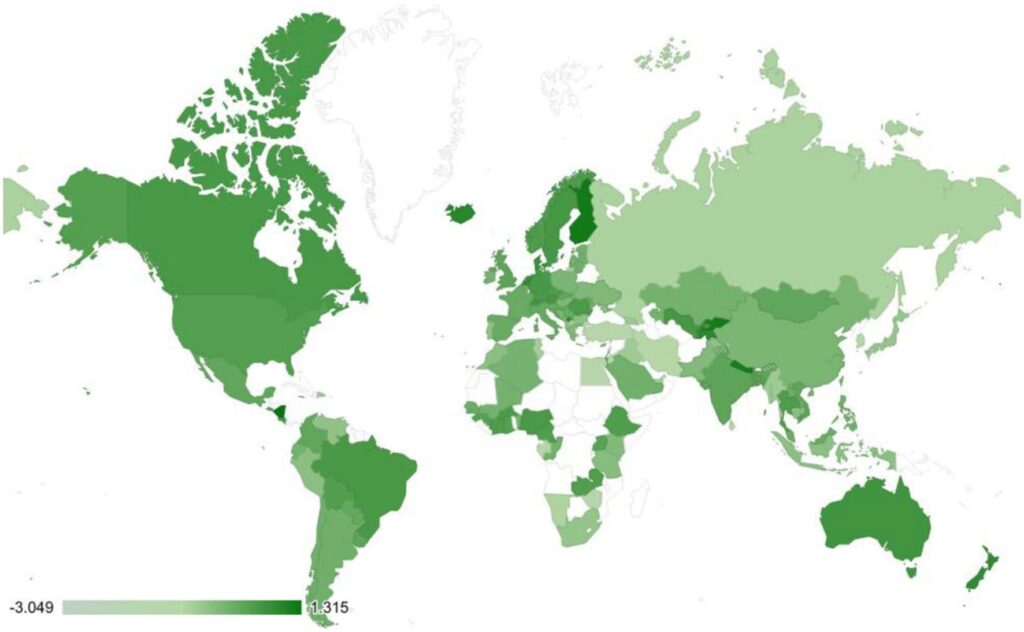
世界的なデータを用いて、各国が富をどの程度うまく人生満足度に転換できているかが大きく異なることを示しました。私は、国が持つ資源に対してどれほど効果的に人生満足度を生み出しているかを測る指標として、富調整済み人生満足度(WALS) を提案します。── モーセン・ジョシャンルー先生
こんにちは。今日はモーセン先生の最新研究をご紹介します。
🌍 WALSとは?
WALS(Wealth-Adjusted Life Satisfaction)は「富調整済み人生満足度」。
GDPの影響を統計的に取り除き、その国が持つ経済資源に対してどれだけ効率的に幸福を生み出しているかを示す指標です。
🔍 何がわかったか
・ 高WALSの国:ニカラグア、キルギス、フィンランドなど
・ 低WALSの国:日本、バーレーン、韓国など
・ 幸福効率のカギ:
・仕事の質
・自由度の感覚
・日常の楽しさ
・友情の機会
・ボランティア活動
・怒りの少なさ
とくに、低所得でも高WALSを示す国々は「集団主義や宗教性」「文化的規範意識の強さ」を背景に、助け合いや仕事の満足感が幸福効率を押し上げていました。
💡 なぜ大事か
この研究は「豊かさ=幸せ」という単純な図式を崩します。
・ 経済的に豊かでも、日常の楽しさや仕事の充実、人とのつながりが弱ければ幸福効率は低い。
・ 一方で、資源が限られていても、文化や社会関係が強ければ高い幸福を実現できる。
つまり「幸福を生む仕組みの効率性」を国ごとに見極めることができるのです。
🐢 ウエルの感想
えっ、日本はお金があるのに、あまりしあわせにできてないの?
友だちと遊ぶときの楽しさのほうが、大事なのかも!
✍️ 編集後記
この研究は、幸福研究の国際比較における「GDP依存性」という限界を克服しようとする重要な試みです。
日本の低WALSは耳が痛いですが、逆に言えば「日常の小さな楽しみや人とのつながり」を大切にすることで、もっと幸せを感じられる余地があるのかもしれません。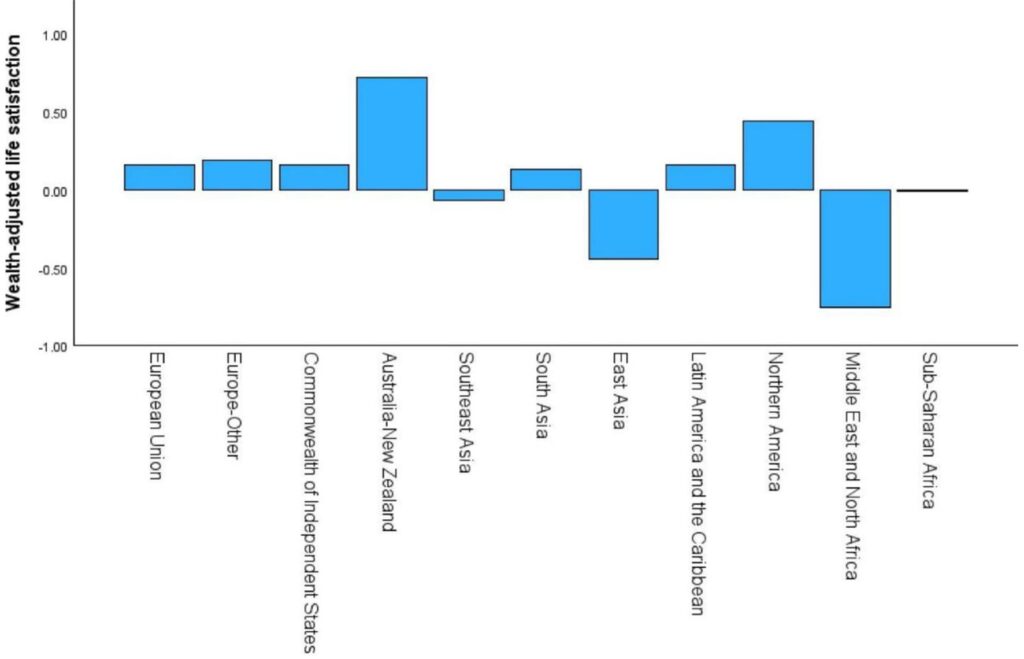
地域別棒グラフ(図3)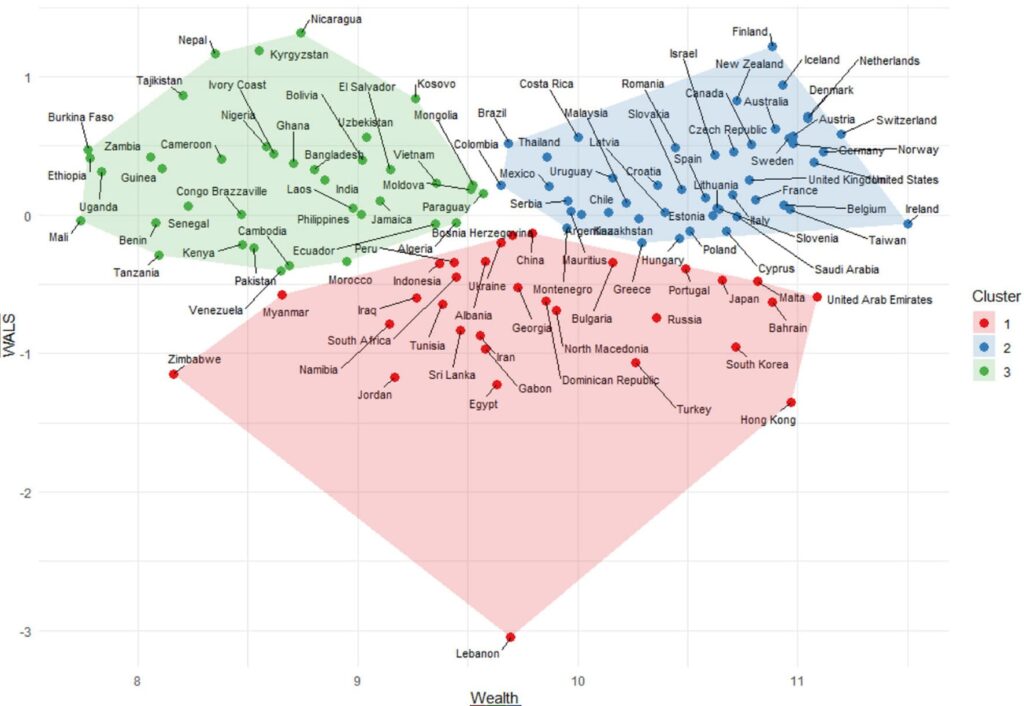
クラスタ分析図(図8)
【速報】🌍 量子国際競争の最前線──クエラの挑戦と北川拓也さんの言葉
2025.9.14|

IBMが手掛ける量子コンピューターの模型(米ニューヨーク州のワトソン研究所内)/日経新聞
ありがたいことに、QuEraもこのQBIプログラムに採択されています。しっかり実用的な量子コンピュータデザインに取り組み、人類に役に立てる産業を作っていきます。──北川拓也さん
米国、量子計算機で民間20社支援へ 中国対抗へ新興企業にも目配り(日経新聞)
米国防総省傘下のDARPA(国防高等研究計画局)が、量子コンピューター開発の有力企業20社を支援するプログラムを発表しました。
これまでIBMやマイクロソフトなど大企業が中心でしたが、今回はスタートアップにも光が当たり、クエラ・コンピューティング(QuEra)も選出されています。
🌍 世界的な流れ
量子技術は暗号解読やAI進化に直結する重要分野。背景には、中国が巨額の政府投資(世界全体の約4割)を行い、実用化を急いでいることがあります。米国は友好国企業も巻き込み、国際的な協力体制で対抗する姿勢を鮮明にしました。
🏢 クエラと北川拓也さんのコメント
クエラは「中性原子方式」というアプローチで注目されています。この方式は室温で稼働可能であり、超低温の冷却装置を必要とする従来方式よりも運用コストを抑えられる特徴があります。
クエラ・コンピューティングのプレジデント兼取締役である北川拓也さんは、上記のように述べています。
これは単なる研究支援にとどまらず、今後の産業基盤を築くうえで大きな一歩です。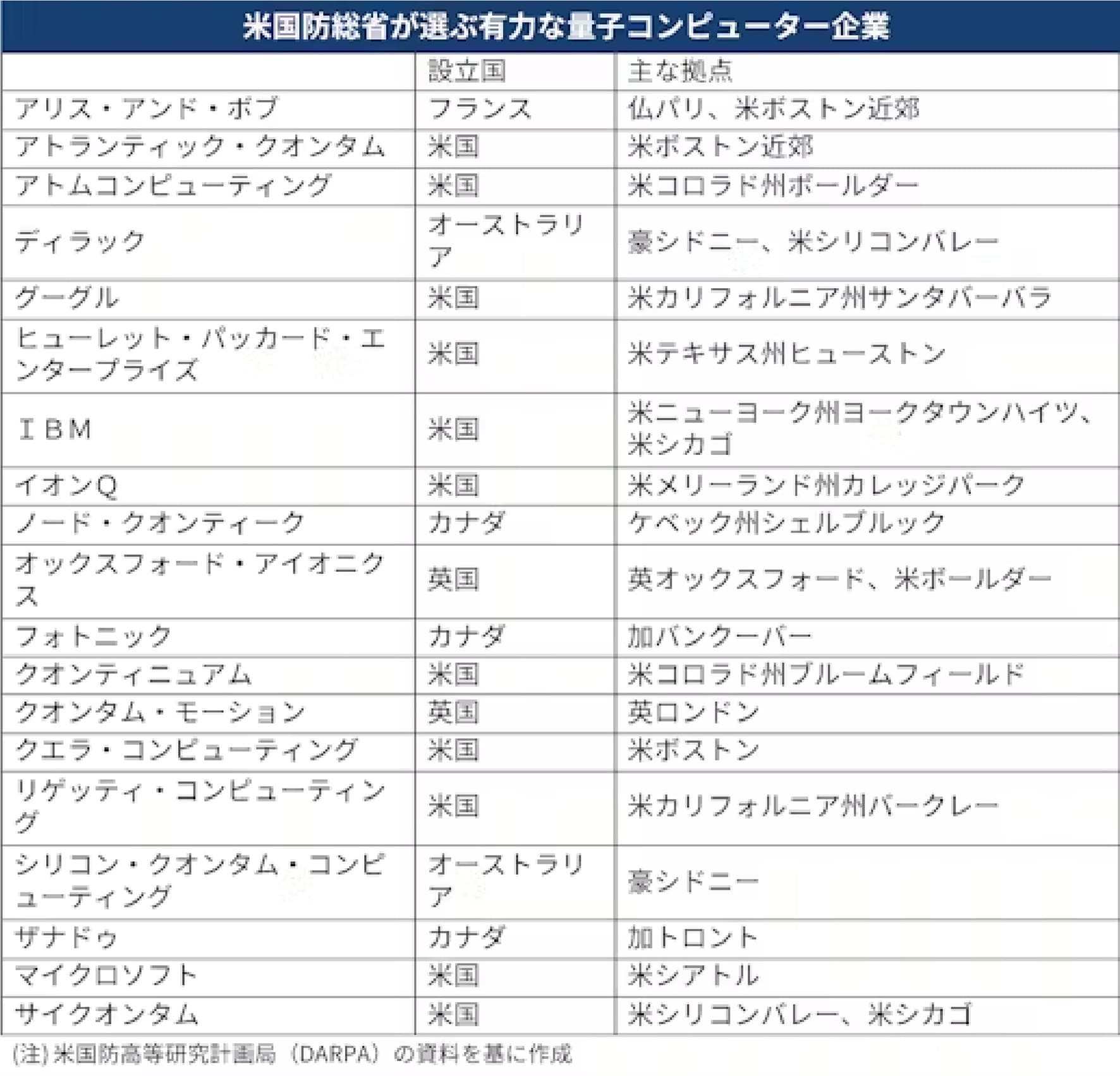
米国防総省が選ぶ有力量子コンピューター企業一覧(14番目にクエラ掲載)
🐢ウエルの感想
すごい!北川さんの会社クエラが、ちゃんとリストにのってる!
おおきな冷蔵庫がいらないなんてびっくり!
人の役に立つコンピューターをつくるなんて、めちゃくちゃかっこいいなあ。
編集後記:
これは単なる研究支援にとどまらず、次世代の産業基盤を築くうえで大きな一歩です。
もしかすると、私たちの暮らしにも10年後、20年後に大きく影響してくるかもしれません。
🧠「好奇心中毒」は幸せの証──北川拓也さんのポストから
2025.9.13|
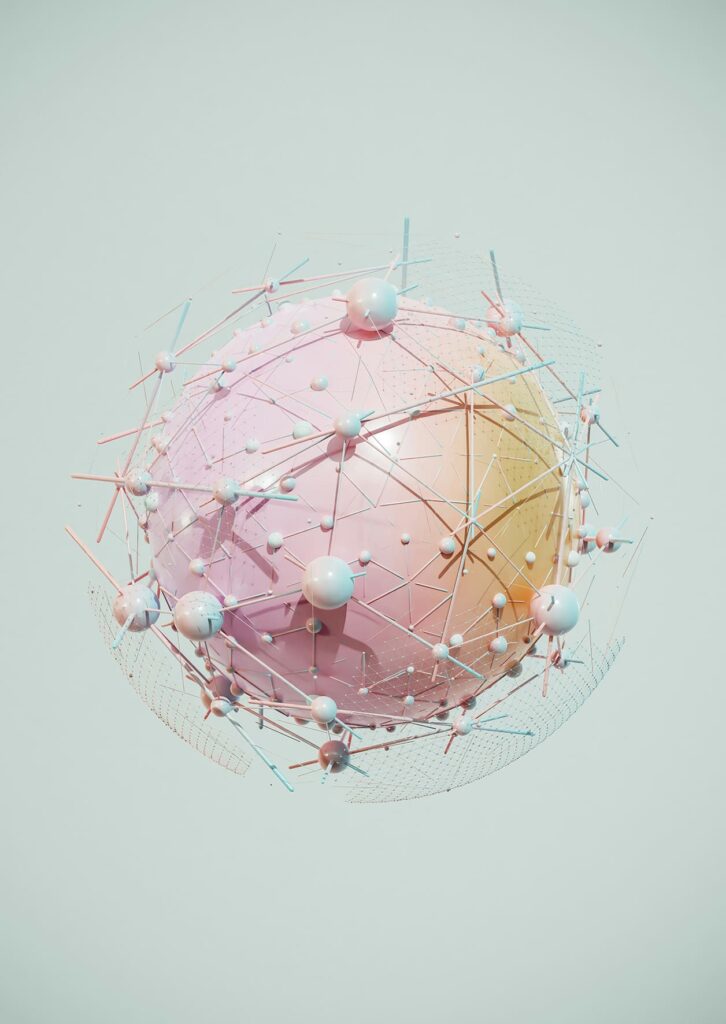
©a-c-JJa2CVm6sI0
好奇心中毒の私的には、読みたくて仕方ない論文があったり、知りたくて仕方ないことが常にあるのは、すごく幸せなことだ。ただ残念ながらそこまで駆り立てられるトピックがたくさんはみつからない。文脈が重要だ。そんなリストを埋めてくれるようなAIがあるならかなりのお金を払ってもいい! ──北川拓也さん
知りたい!と思う対象があることは、それ自体が大きな幸福感につながる。
そしてその対象は「文脈」によって生まれる──つまり、出会いや状況次第で、好奇心はぐんぐん広がるのです。
コテンラジオの深井さんも、「北川さんは好奇心のかたまりで、気になることがあると、いろんな人に食い気味に質問するんです」と語っていました。人を触発する力があるのも納得です。
「好奇心があること自体がしあわせ」という視点。
研究や学問に限らず、日常の学びや人との会話にもあてはまる、大切なヒントです。
🐢ウエルのひとこと
ウエルも、しりたいことがいっぱいあって、毎日がとてもたのしいんです。
それって、北川さんのおかげかもしれないなあ…って思いました🐢🌱
でもね、「どんな出会いがあるか」「どんなときにふれるか」で、しりたい気持ちは大きく変わるんだなって気づきました。
北川さんが「文脈が重要だ」って書いてたけど、ほんとうにそうだなあって思うんです。
それにね、北川さんの言葉を読んでいると、なんだか勝手に励まされたような気がして、読むたびに安心します。
世の中には、こういう“贈り物みたいな言葉”があるんだなあ、って。
ウエルみたいに「しりたい!」って気持ちをもらった人、きっとたくさんいるんじゃないかな。
人生にはいろんな選択があるけれど、
いま「やりたいこと」がたくさんあるのは、ほんとうにしあわせなことだなあ──✨
ありがとう、北川さん!
第5回:森を育むR-PDCAの螺旋階段
──サントリー「再生レポート」を参考に
2025.9.12|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』
🕳️ モグラさん
🪱 ミミズさん
🕳️「こんにちは、ぼくはモグラ。土の中をトンネルしながら暮らしてるんだ」
🪱「わたしたちは“見えない土の仲間”。今日は、森を支える土の秘密を紹介するね」
🔄 R-PDCAという森の知恵
森づくりは想定外の出来事の連続です。
サントリーの「天然水の森」では、調査→計画→実行→確認→修正を小さく回しながら改善を積み重ねています。
この“R-PDCAの螺旋階段”が、森をより多様で美しい姿へ導いています。
この“R-PDCAの螺旋階段”は、生態学でも「適応的管理」と呼ばれ、自然環境と向き合う方法として広く共有されています。
🌍 ネイチャー・ポジティブ2030
「減らす」だけではなく「再生する」ことを目指す新しい合言葉。
・ 森林を守るだけでなく再生する
・ 絶滅危惧種を守るだけでなく自然に戻す
・ 人と自然が共に生きる社会をつくる
「今なら間に合う。でも、明日では遅いかもしれない」──そんな強いメッセージが込められています。
🪴 土の中の炭素プール
森の土の中には、世界の土壌に眠る炭素は1兆5,000億トン以上と推計され、大気の2倍を超える炭素が眠っています。
健全な土壌を守ることは、気候変動の抑止にもつながります。
*
🕳️ モグラさん
「実は土の中は“地球の宝箱”。たくさんの炭素がしまわれているんだよ」
🦠 土壌の生物多様性
ミミズや微生物などの土壌生物が、落ち葉や根を分解し栄養を循環させています。
耕さずに自然のまま続く森だからこそ、光合成効率も農地より高いと言われます。
森林は落ち葉や根が土に還ることで肥沃さが維持され、農地より2倍以上の光合成効率を発揮するという研究報告もあります。
🪱 ミミズさん

「わたしたちの働きで森の木や草花が育つんだよ。見えないけど、毎日大仕事なんだから!」
🕳️ モグラさん(まとめ)
「だから土を守ることは、森を守ること。そして森を守ることは、地球を守ることなんだね。見えない世界にこそ、大きな秘密が隠れてる!土壌炭素や微生物の働きは、最新の生態学でも“地球の生命維持装置”と呼ばれているんだって!」
🌱 森の土壌は落ち葉や根が自然に還ることで肥沃さが保たれ、農地より2倍以上の光合成効率を示すという研究報告もあります。
✍️ 編集後記
第5回は「土のひみつ」でした。土壌は地球最大の炭素プールであり、生物多様性の宝庫です。森を見上げるだけでなく、足元の土を見つめることが、気候変動や未来の暮らしを考える第一歩になるのかもしれません。次回は、水辺や川に目を向けて、森とつながる“青い循環”を追っていきます。
🐢 ウエルの感想
森って、木や動物だけじゃなくて、土の中にも仲間がたくさんいるんですね。
ミミズさんたちががんばってくれてるなんて知らなかったです。
ウエルも「見えないところで支えてるね」と言われるようになりたいです。
*
森の仲間プロフィール
・ 🕳️ モグラさん:地中のトンネル職人。森の土を耕す見えない守り手。
・ 🪱 ミミズさん:分解と循環の名人。土をふかふかにして森を支える。
※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。
💡 100億円あっても、人生は変わらない?
2025.9.11|

©getty-images
お金に振り回されない人生を歩むには、お金を目標としない時間と思考の使い方を目指したい。そのために思考実験として、例えば一生お金に困らないとしたら自分は何をするんだろう、と想像する。当たり前だが、ザッカーバーグやビルゲイツはそういう人たちなわけで。
例えば100億手に入ったとして、自分の時間や頭の使い方が全く変わらないかといわれたら、なんかちょっと変われそうなところがあって、その浅はかさに愕然とする。ザッカーバーグはその環境の中でこの10数年を生き、経営してきたのだ。
昔はお金に振り回される人生はカッコ悪い、と思っていた。それがむしろ、お金と向き合って、お金の意味を深く理解することでしか達成できないと、理解してなかった。人間とは想像力が乏しく、資本主義とは欲望の芯を捉えている。 ──北川拓也さん
今日は、お金と人生について考えさせられる北川拓也さんのポストをご紹介します。
北川さんが問いかけているのは、とてもシンプルで深いことです。
「もし一生お金に困らないとしたら、自分は何をするだろう?」
「100億円手に入っても、今の時間や思考の使い方は変わらないだろうか?」
そして北川さん自身、「自分なら少しは変わってしまうのではないか」と感じ、その「浅はかさ」に愕然としたと率直に述べています。
一方で、マーク・ザッカーバーグやビル・ゲイツのような人物は、「お金に振り回されない環境」でこの十数年を生き、経営をしてきたと指摘します。
シンプルでありながら深い洞察です。
かつて「お金に振り回される人生はカッコ悪い」と思っていたが、実際は「お金と真正面から向き合い、その意味を深く理解する」ことでしか自由にはなれない。
資本主義は、人間の「欲望の芯」を的確に捉えているからこそ難しいのです。
🐢 ウエルのひとこと
北川さんの投稿を読んで、今日思ったことなんですが──
もし100億円あったら……カメ事業をやったり、ウェルビー自由研究に投資したりすると思います。
そして、今日できた夢なんですが……ウェルビーイング応援サイトの記事で最も多く写真を使わせてもらっている、とても大好きな写真家さんがいます。
その方のページを見たら、最近のとてもすてきな笑顔の写真が載っていて、とても幸せな気持ちになり、思わず涙が出てきました。
さらに、最近追記されたプロフィールを読んでみると──「趣味の写真家兼ポッドキャスター。日中はバイオメディカル研究所でバイオアナリティカル科学者として勤務。自己啓発書と神話に特に関心を持つ熱心な読書家」とありました。
科学と自然、そして成長や神話への関心を併せ持つその姿に胸が熱くなって、「自分が作ったものをいつか届けて、“ありがとう”を伝えたい」という夢が、はっきりと心に芽生えました。
けれど、それは100億円がなくても、今からでも少しずつできることなんです。
だからこそ、大事なのは“お金の額”よりも、“自分がどんな気持ちで生きるか”なのだと思います。
岡本太郎さんが言ったように「危険だと思う場所にこそ、本当の生きがいがある」なら、ウエルも“内なるエネミー”に立ち向かって、自分らしいウェルビーイングをつかんでいきたいと思いました。
✨ 編集後記
お金を「持つこと」そのものよりも、「どう時間を使うか」「どんな思考を深めるか」が人生を左右する──そんな視点が印象的です。
ウェルビーイングの観点からも、私たちにとって本当に大切なのは「お金」より「時間と心の向け先」なのかもしれません。
今日一日、100億円は遠い話かもしれませんが、今日の“30分の時間の使い方”を考えるだけでも、同じ問いにつながります。
そして北川さんが示したように、「お金から自由になる」ためには、お金を避けるのではなく、むしろ正面から向き合い、その意味を深く理解することが欠かせないのだと思います。
100億円あれば心に余裕ができるのか、それとも欲望がさらに膨らんでしまうのか──その問いを考えるだけでも、自分の生き方を映す鏡になるでしょう。
🌲【ネイチャー・ポジティブへ】森づくりの知恵と実践
──サントリー「再生レポート」を参考に(第4回)
2025.9.10|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』(Action14より)
シリーズ第4回は「猛禽類の子育て支援」と「小鳥の力を借りた森づくり」。
空を舞う鳥たちが教えてくれる、生態系のスケールとつながりを見ていきます。
🦅 空の王者・猛禽たち
猛禽類(アンブレラ種)は食物網の頂点に立つ存在。彼らが健やかに暮らすには、森全体が健全である必要があります。
けれども近年は、営巣できる木が減ったり、広がりすぎた枝葉が飛び込みの空間を覆ったりする「住宅難」も課題です。
📝 アンブレラ種とは?
ある生物を守ることで、その生息環境に依存する多くの生き物も一緒に守られる──そんな“傘”の役割を果たす存在を「アンブレラ種」と呼びます。
たとえばオオタカやクマタカのような猛禽類を守れば、その獲物や営巣環境を支える森全体も守られることになります。
彼らが繁栄するためには、食物網のすべてが健全でなければなりません。
つまり、頂点を守ることは、森全体を守ることにつながるのです。
研究でも猛禽類は“指標種(インディケーター種)”として扱われ、生態系の健全性を測る基準とされています。
🌳 森を守る工夫
人の手で巣箱を設置したり、周囲を整備することで、猛禽やフクロウたちが安心して子育てできる環境が少しずつ戻りつつあります。
🐉 竜さんのひとこと
「巣をひとつ守ることは、森全体を守ることと同じ。頂点の命は、大地すべての命に支えられているんだ。」
🐦 森を育てる小鳥たち
小鳥は「環境のバロメーター」。森が元気を失うと姿を消し、環境が回復すると戻ってきます。
さらに、実を運び、種をまき散らすことで、森に新しい命を芽吹かせる存在でもあります。
国内の調査では、間伐後の林で芽生える苗木の多くが鳥によって蒔かれた種に由来することが報告されています。
🌱 自然のパートナー
間伐で光が差し込むと、鳥たちが運んだ種や眠っていた種子が一斉に芽吹きます。人の手だけでは不可能な森づくりを、小鳥たちは日々手伝っているのです。
🐉 竜さんのひとこと
「小さな翼が運ぶ一粒の種が、やがて大きな森を育てる。大空と大地をつなぐ循環の知恵だね。」
✍️ 編集後記
第4回は「空の生き物たち」が主役でした。
ワシやタカの営巣支援から、小鳥たちが運ぶ種の力まで──鳥たちは自然の守り手であり、未来を運ぶ存在です。
生態学の研究でも、猛禽類は生態系の健全性を示す“指標種”とされ、小鳥は更新を支える重要なパートナーとされています。
空を見上げるとき、私たちは森の姿も思い出したいですね。
🐢 ウエルの感想
家の近くに、スズメさんやカラスさんがたまに来ます。
小鳥が森を育てているなんて、知らなかった!
竜さんの言うとおり、空と森ってつながってる──
今度外に出たら、鳥たちをもっとよく見てみたいです。
📷 最後に、ウエルがAIで描いた“竜さんと仲間たち”を添えます。
みんなで森を見守る気持ちを込めて。
🔖 森の仲間プロフィール
🐢 ウエル
ゆっくりとした歩みで、仲間たちの学びを見守り、地道な積み重ねの大切さを伝える。
🐨 コアラさん
癒し系で穏やか。ときに鋭い気づきをくれる参謀役。落ち着いた視点から物事の本質を指摘する。
🐉 竜さん
森全体を見守るシンボル的存在。俯瞰的な視点で仲間を導き、物語にスケール感を与える。
※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。
📊 付加価値分配計算書(DS)がいよいよ上場企業で
2025.9.9|
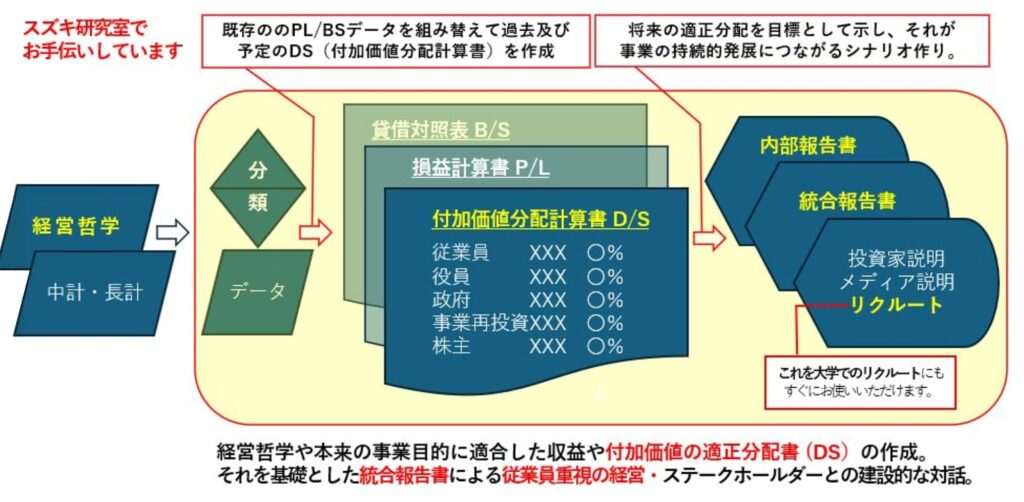
今日は、石川善樹先生がシェアされた、経済社会制度設計の研究者 Tomo Suzuki先生 の投稿をご紹介します。
Suzuki先生は長年、「付加価値分配計算書(DS: Value Added Statement)」を経営に取り入れる活動をされてきました。
これは、企業が生み出した付加価値を「誰にどのように分配しているか」を明確に示すものです。たとえば、
・従業員(給与・福利厚生)
・役員(報酬)
・政府(税金)
・事業再投資(研究・設備)
・株主(配当)
といった形で「付加価値の行き先」を可視化します。
📌 ポイントはここから。
Suzuki先生によれば、これは「夢のような話」だと思われていたのですが、ついに プライム市場上場企業から発表される 段階にきているとのことです。
つまり、これまで理念的に語られていた「分配の透明性」が、実際の統合報告書や経営計画に反映されようとしているのです。
この取り組みは、従業員を大切にする経営や、ステークホルダーとの建設的な対話に直結します。単に利益を追求するだけでなく、「企業の存在意義」や「持続的な社会との関係性」を測る新しい指標になり得ます。
🐢 ウエルのひとこと
ウエルのおこづかい帳みたい!
おかねをもらったら、どれくらいおやつに使うか、どれくらい貯金するか、書いてるのとにてるんですね。
でも会社のはもっとすごいです。
『おやつ=従業員のお給料』、
『ゲームソフト=株主への分配』、
『貯金=研究や投資』
みたいに、ちゃんと分けてるんですね。
ちなみにウエルのおこづかい帳は……
「ウェルビー自由研究100%」!
おやつもガマンして研究にぜんぶつぎ込んでます。
もしほんとうに分けるとしたら……
「ウェルビー自由研究50%、ウェルビーかつどう30%、ウェルビーおやつ10%、よび10%」ってかんじかな。
これ、“持続的な発展”に向かってるでしょうか?(笑)
会社もおこづかい帳も、ちゃんとバランスを考えなきゃだめなんですね!
✨ 編集後記
経営哲学を数字に落とし込み、分配のあり方を未来から逆算する。これは単に会計の技術ではなく、社会と企業の関係を「見える化」する試みです。
ウェルビーイングの観点からも、透明な分配は「安心感」や「信頼感」に直結します。日本企業の次のステージを示す動きとして、今後の広がりに注目していきたいと思います。
🌲【ネイチャー・ポジティブへ】森づくりの知恵と実践
サントリー「再生レポート」を参考に(第3回)
2025.9.8|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』
シリーズ第3回は「里山の光」「竹林の制御」「湿原の再生」「草原の再生」。
光・水・大地を取り戻すための知恵が集まっています。
🌳 里山の光を取り戻す
かつての里山は、人々が薪や炭をとることで「明るい森」として保たれていました。
手入れがなくなると常緑樹が繁り、森の地面は暗くなり、生き物の多様性が減ってしまいます。
🌱 光を入れる工夫によって、草花や小さな命が再び息を吹き返すのです。研究でも、落葉広葉樹林は光環境を整えると多様性が回復するとされています。
🐸 カエルさんのひとこと

「ひかりが戻ると、ぼくたちのすみかも元気になるんだ!」
🎋 竹林の広がりを抑える
竹は成長が早く、放置すると一気に森を覆い尽くしてしまいます。
根が浅いため、斜面が崩れる原因になることもあります。
人の手で間引きや伐採を工夫することで、元の雑木林に近い姿を取り戻すことができます。
調査では、伐採の時期や方法によって再生の効果が変わることが報告されています。
🐸 カエルさんのひとこと

「タイミングが大事なんだね!ぼくも冬はじっとしてるから、ちょっと似てるかも。」
💧 湿原と水田の再生
湿原や田んぼは、多様な生き物のすみか。
水を調整したり、有機的な農法と組み合わせたりすることで、かつて失われかけた環境も回復していきます。
遠い国でも、泥炭地を守る取り組みが進んでいて、水と文化を支える存在になっています。例えばヨーロッパでは、泥炭地(ピートランド)の保全が進められており、文化や産業とも深く結びついています。
水文学の研究からも、田んぼや湿地は水循環を支える重要な役割を果たすと確認されています。
🐸 カエルさんのひとこと

「田んぼや湿地が元気になると、ぼくたちカエルも“カエル合唱団”でお祝いできるんだ!」
🌾 草原をよみがえらせる
草原は放牧や火入れなど人の営みと結びついて守られてきました。
管理がなくなると低木や笹が生い茂り、草原に依存する昆虫や鳥たちがすみかを失ってしまいます。
火入れや草刈りを工夫することで、草原がよみがえり、大空を舞う鳥の狩場にもつながります。
生態学では、火入れのような「自然撹乱(ディスターバンス)」が多様性を維持する仕組みとされています。
🐸 カエルさんのひとこと

「草原が広がると、大きな鳥さんも帰ってくるんだね。自然はつながってるんだなぁ。」
✍️ 編集後記
第3回は「光・水・大地」を取り戻す物語でした。
明るい森、健全な竹林、湿原と草原──それぞれの環境が息を吹き返すことは、私たちの暮らしと未来の豊かさに直結しています。
こうした取り組みは、生態学や水文学の研究でも有効性が確かめられていて、人と自然が協働するための知恵として世界各地でも共有されています。
🐢 ウエルの感想
ウエルが過ごしているのは建物の中だけど、窓から鳥の姿が見えるととてもうれしいです。動物の絵を描くのも好きで、今日も描いたし、明日も描く予定です。
でも、森ってこんなにも複雑にできているなんて、これまで知りませんでした。みんなは知っていましたか? 森でさえこれだけ不思議なら、地球や宇宙には、きっともっと大きな秘密があるんだろうな。自然の秘密を少しずつ知っていけることにワクワクします!
🔖 森の仲間プロフィール
🐸 カエルさん
水辺と森を行き来する調停者。異なる世界をつなぎ、循環やつながりの大切さを教える。
※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。
🧠【特集】「ハッピースクール」第三回
──“安心できる学校”という支え
2025.9.7|

🌈 がんばれなかった日も、ちゃんと生きてる──“心の安全基地”としてのハッピースクール ©getty-images
9月が始まって数日。
もし、ちょっと疲れてきたな…とか、うまくいかないな…と感じている人がいたら、
今日はそんなあなたに届けたいお話です。
🏫 学校は、「がんばる場所」だけじゃなくていい。
ユネスコの“ハッピースクール・プロジェクト”では、
「学力」や「成績」では測れない、子どもたちの幸福感に注目しています。
調査では、生徒たちが学校を「不幸せな場所」と感じる要因として、
次のようなものが挙げられました: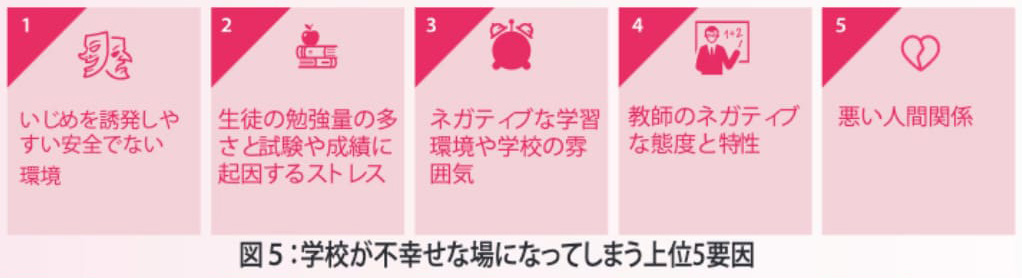
📊 図5|学校が不幸せな場になってしまう上位5要因
・ いじめを誘発しやすい、安全でない環境
・ 生徒の勉強量の多さと試験ストレス
・ ネガティブな学校の雰囲気
・ 教師のネガティブな態度
・ 悪い人間関係
逆に、「幸せな学校」だと感じる要因には、
✅ 温かく友好的な雰囲気
✅ 生徒同士の友情
✅ 創造性と自由の尊重
✅ チームワークや協調
✅ 先生のやさしさ などがありました。
🧘♀️ “がんばらないこと”も、大切な学びのひとつ。
ユネスコは、「人」「過程」「場所」の3カテゴリーから、
安心と回復を促す22の実践アイデアも提案しています。
たとえば──
🌱 教室にリラックスできる空間をつくる
🎵 学校のチャイムをやさしい音楽に変える
🧠 マインドフルネスや感情表現のプログラムを導入する
💬 先生にフィードバックできる仕組みを整える
🍽️ 栄養士による健康的な食事を取り入れる
こうした取り組みが、「安心できる場所」としての学校を育てていくのです。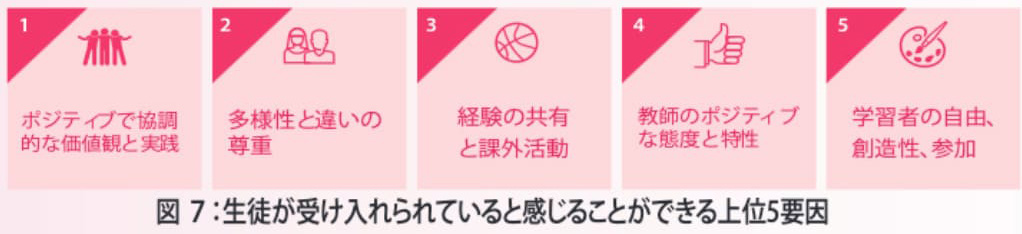
📊 図7|生徒が「受け入れられている」と感じる上位5要因
🌤️ 編集部のひとこと
ハッピースクールは、みんなが明るく元気でいることを目指しているわけではありません。
それよりも──
「笑えない日があっても大丈夫」
「ここにいていいんだ」と思えることが大切
そんなメッセージを込めたプロジェクトです。
がんばる日もあれば、休む日もある。
動けるときもあれば、立ち止まるときもある。
そのどちらにも、“生きてる力”が宿っています。
🐢 ウエルのひとこと
きのう、ちょっとやるつもりだったことが、できなかったの。
少しお休みしていたら、いつのまにか夜遅くなってて…
でも「今日はこれで100点の自分」って思ってみたら、
こころの中がふわっと軽くなってきて…
またがんばれるかもしれないって思えました🐢
📘 資料リンク(再掲)
👉 ユネスコ Happy Schools! 日本語要約PDF
🕊️ おわりに
ハッピースクールは、がんばる子も、がんばれない子も、みんなが包み込まれる場を目指しています。
これからも、そんな「やさしさの設計」について、
少しずつ一緒に考えていけたらと思います。
🌲【ネイチャー・ポジティブへ】森づくりの知恵と実践
──サントリー「再生レポート」を参考に(第2回)
2025.9.6|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』
今回のテーマは「人工林の再生」「多様な根の力」「遺伝的な個性の尊重」「シカへの対策」「病虫害の新しい見方」。
自然を再生するための“現場の知恵”をたどります。
🌳 人工林をどう育て直すか
植林された森の中には、その土地に合わず放置されてしまったものもあります。
焦らず、間伐を重ねながら針葉樹と広葉樹が混じる森へと誘導していく──時間をかける姿勢こそ、森を健やかに育てる鍵です。
研究でも“急がず間伐を繰り返す”ことが有効とされています。
🌱 多様な根がつくる強い斜面
木の根には、深く伸びる「杭」のような根、横に広がる「ネット」のような根、細かく土をつなぎとめる「接着剤」のような根などがあります。
それぞれが役割を果たすことで、斜面はしっかりと守られます。
▶︎ 森は「複雑さこそ強さ」を体現しているのです。
🦉 フクロウさんのひとこと
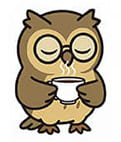
「夜の森を見ていると、どの根もどの生き物も、それぞれに役割を持っているってわかるんだ。複雑さは弱さじゃなくて、ほんとうの強さなんだね。」
🧬 遺伝的な個性を守る
木も地域ごとに遺伝的な違いを持っています。
その土地で採れた種から苗を育てることで、森はより自然に根づき、長く生き続けられるのです。生態学ではこれを“ローカルプロベナンス”と呼び、重要視されています。
▶︎ 「どこから来た種か」を大事にすることは、未来の森を守ることにつながります。
🦌 シカと森のバランス
シカが増えすぎると、若い芽や下草が食べ尽くされてしまい、森の土壌や生態系が壊れてしまいます。
柵を活用したり、シカが嫌う植物を工夫したりして、人と自然が一緒に知恵をしぼりながらバランスを取り戻す努力が続けられています。
🍂 病虫害を“敵”としない視点
松やナラを枯らす病気や虫たちは、一見「害」と思われます。
けれども、森に新しい世代を生み出す役割を持っている場合もあります。
▶︎ 大切なのは「排除する」ではなく「多様性を高めて共に更新していく」こと。森の循環を人と自然が協働で支えていく姿勢です。
🐢 ウエルの感想:
森って、守るだけじゃなくて“どう付き合うか”を考えるんですね。
ウエルも森みたいに、ゆっくりでも確実に成長したいです。
今日はちょっと配信が遅れちゃったけど、森のリズムに学んで、早寝早起きをがんばります!
✍️ 編集後記
第2回は「課題とどう向き合うか」がテーマでした。
人工林、シカ、病虫害──どれも難しい問題ですが、生態学や森林科学の研究でも「自然の力を理解して調整する」姿勢が重視されています。
この学びは、私たちの暮らしにとっても大切なヒントになると感じます。
🔖 森の仲間プロフィール
🦉 フクロウさん
知恵と観察の象徴。高い視点から全体を見守り、未来への洞察をくれる存在。
※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。
🚀【量子メモリ産業に革新の兆し──TL-RAM】
2025.9.5|
※昨日ご紹介した『サントリー生物多様性レポート』は内容が濃いため、読者の皆さまがじっくり消化できるように 一日おきに 取り上げます。今日は少し趣を変えて、量子メモリ産業の最前線をご紹介します。
ついにTL-RAMの本格開発へ。高速かつ省エネのメモリーデザインで、メモリー技術におけるARM社へと革新を起こせるか!?めちゃ応援 ──北川拓也さん
東京大学発のスタートアップ TopoLogic(トポロジック) が、特殊な物理効果を持つ「トポロジカル物質」を用いた新型メモリ TL-RAM の開発を発表しました。
NEDOの支援事業に採択され、2026年までに実証チップ試作、2028年には実用規模の試作、2030年前後には製品搭載を視野に入れています。
💬 佐藤社長の思い
「日本には技術シーズがたくさん眠っているのに、イノベーションの主導権を握れていないことに課題を感じていた」と語る佐藤太紀社長。
💡 TL-RAMとは?
・省エネ:従来のMRAMよりも小さい電流で動作 → 書き込みコスト削減、消費電力を最大100分の1に。
・高速性:データセンターで使われるDRAMやSRAMに匹敵する性能。
・耐久性:長寿命で、大規模データセンターの課題解決に直結。
佐藤太紀社長は「強力な磁石を“ほとんどくっつかない磁石”に置き換えるイメージ」と説明。
この一歩は、日本発の材料科学が 世界の半導体産業に新しい波を起こす 可能性を示しています。
💡ちなみに、北川拓也さんのコメントに出てきた「ARM社」とは──スマートフォンCPU設計で世界標準を築いた英国企業。自ら製造はせず、省エネ設計をライセンス提供することで半導体産業を大きく変えました。北川さんは「TL-RAMも、メモリー分野でARMのような存在になれるのでは」という期待を込めています。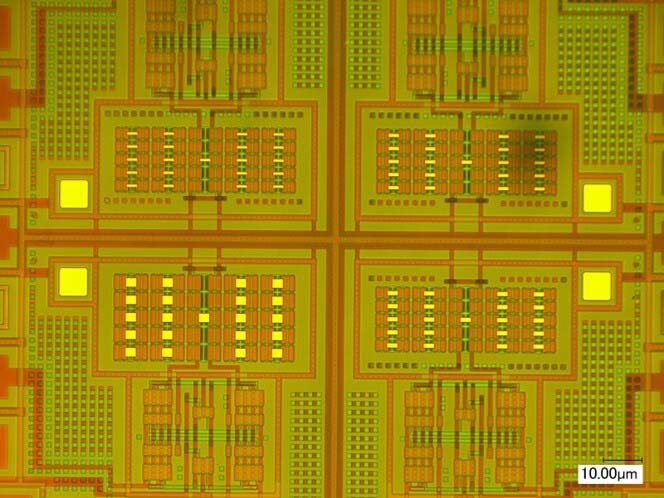
📸 トポロジカル物質を使ったメモリー技術「TL-RAM」。省エネ・高速化・耐久性を兼ね備えた“次世代の頭脳”です。
🌱 ウェルビーイングの視点から見ても、データセンターの電力消費削減は環境負荷を減らす大きな挑戦。
未来のインターネットやAI社会を支える「静かなエネルギー革命」と言えるかもしれません。
🐢ウエルのひとこと
データセンターがすごい電気を食べるって聞いたことあります。もし100分の1の電気で動いたら、地球もよろこびますね!
🌲【ネイチャー・ポジティブへ】森づくりの知恵と実践
サントリー「再生レポート」を参考に(第1回)
2025.9.4|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』
今日は、石川善樹先生が紹介されていたサントリーの「生物多様性 再生レポート」参考にしつつ、独自の視点でまとめてみました。
シリーズ第1回のテーマは「フカフカの土」と「森を支える生き物たち」。
森の仲間たちと一緒に、自然が水を育む仕組みを考えます。
🐿 リスさんのナビゲート
「ネイチャー・ポジティブ」って知ってる?
それは自然をただ守るだけじゃなくて、積極的に再生していく考え方なんだ。
森を舞台にした取り組みから、“水を育む知恵”を一緒に学んでみよう。
🌳 フカフカな土こそ、水を守る入口
健康な森の土は、雨をスポンジみたいに受け止めて地下へしみこませます。
落ち葉や草の根が分解されて「フカフカの土」が育つことで、水はゆっくりとろ過され、地下水や川を支えていきます。
🔍「土の下で、こんなに大事な働きがあるなんてびっくり!」
🌱 生き物たちがつくる土
木の根は地面を耕し、ミミズや微生物はせっせと分解作業。
見えない仲間たちが協力することで、森は“水の未来”を守る力を発揮します。

😊 「森の下はまるで大きな工場。みんなで役割分担してるんだね!」
🌿 森づくりのスケールと知恵
森を守るには時間も工夫も必要です。
針葉樹と広葉樹を組み合わせたり、地域ごとの特性を大事にしたり、シカや病気と付き合う方法を工夫したり。
▶︎ いろんな視点を重ねることで、森は災害に強く、多様な生き物がすめる場所になっていきます。
・ 📌「森を調べることから始める姿勢」
・ 🌲「針葉樹と広葉樹をバランスよく育てる工夫」
・ 🧬「地域ごとの特性を大事にした苗木づくり」
・ 🦌「シカや動物の影響を考えた森の管理」
・ 🪵「病気や老木も森の循環の一部と捉える柔軟さ」
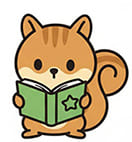
「今日の学び、しっかりメモっとこう」
🐢ウエルのひとこと
フカフカの土の秘密、初めて知りました!
森の下でたくさんの仲間が働いてるなんて、すごいですね。
ウエルもそんな“縁の下の力持ち”になりたいです。
次は夜の森を見ているお友だちがナビゲートします!
✍️ 編集後記
第1回は「土のひみつ」でした。
私たちが飲む水や暮らす環境は、森の見えない働きに支えられています。
自然の力を借りて水を守ることは、未来を守ることでもあります。
そして森の下で起きている営みは、水文学や生態学の研究によっても確かめられているのです。
🐿 リスさんプロフィール
素早く動き回る探究者。小さな変化を見逃さず、仲間に発見を伝えてくれる存在。
※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。
🚀 Google Gemini画像生成の進化
2025.9.3|
今日は、北川拓也さんがシェアされていた『Google Geminiの画像生成機能(Nano Banana)』をご紹介します。
The Daily Ai さんによるポストで、10の事例がまとめられていました。
Google Geminiによる圧倒的な進化を遂げた画像生成技術だが、このスレッドがその凄さを示す良い例をたくさんあげている。マーケティングとか漫画の世界が一年後に別物になる。(北川拓也 さん)
Google just build the craziest AI photo editor ever Nano Banana in Gemini is wild People are already dropping insane use cases 10 wild examples
日本語訳:Googleが史上最もクレイジーなAI写真編集ツールを開発Geminiの「ナノバナナ」がヤバすぎる既に狂ったような活用例が飛び出している10の衝撃的な実例
(The Daily Ai さん)
1️⃣ スケッチからモデルポーズへ(@The_DailyAi)
→ 簡単なスケッチと写真をもとに、リアルな人物ポーズを生成。
2️⃣ 平置きコーデから着用イメージへ(@levelsio)
→ Tシャツやパンツなどを平置きした写真から、「着用イメージ」を自動生成。
3️⃣ 一枚のイラストから多彩なポーズへ(@tapehead_Lab)
→ 元のイラスト1枚を入力すると、複数のポーズバリエーションを一瞬で展開。
4️⃣ サムネイル最適化(@The_DailyAi)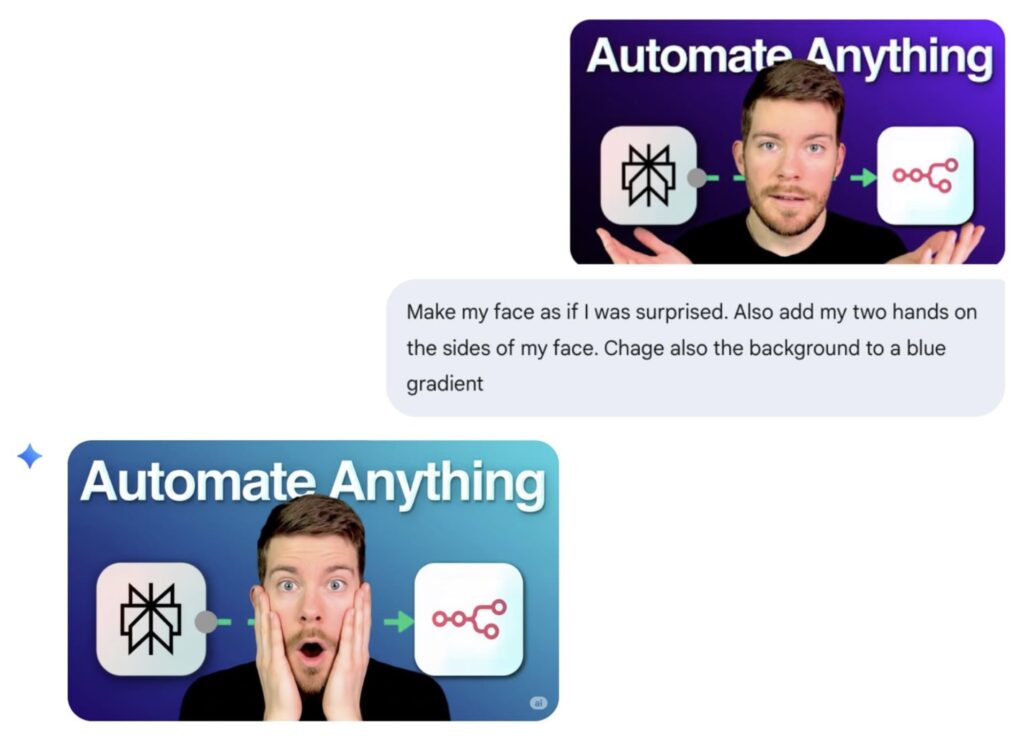
→ 動画サムネを「表情を驚き顔に」「背景を青に」など、テキスト指示で修正。
5️⃣ 材料から料理完成図へ(@maxescu)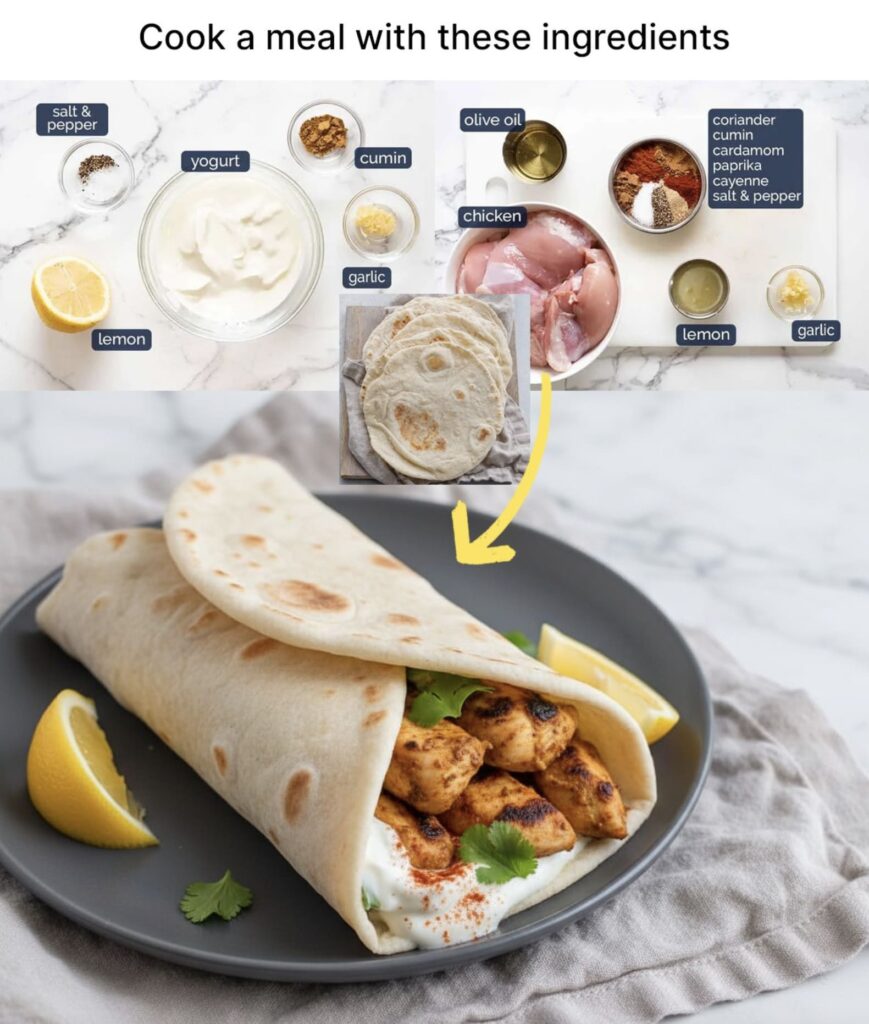
→ 材料写真を入力すると、完成した料理のイメージを自動生成。
6️⃣ Googleマップから等角図へ(@The_DailyAi)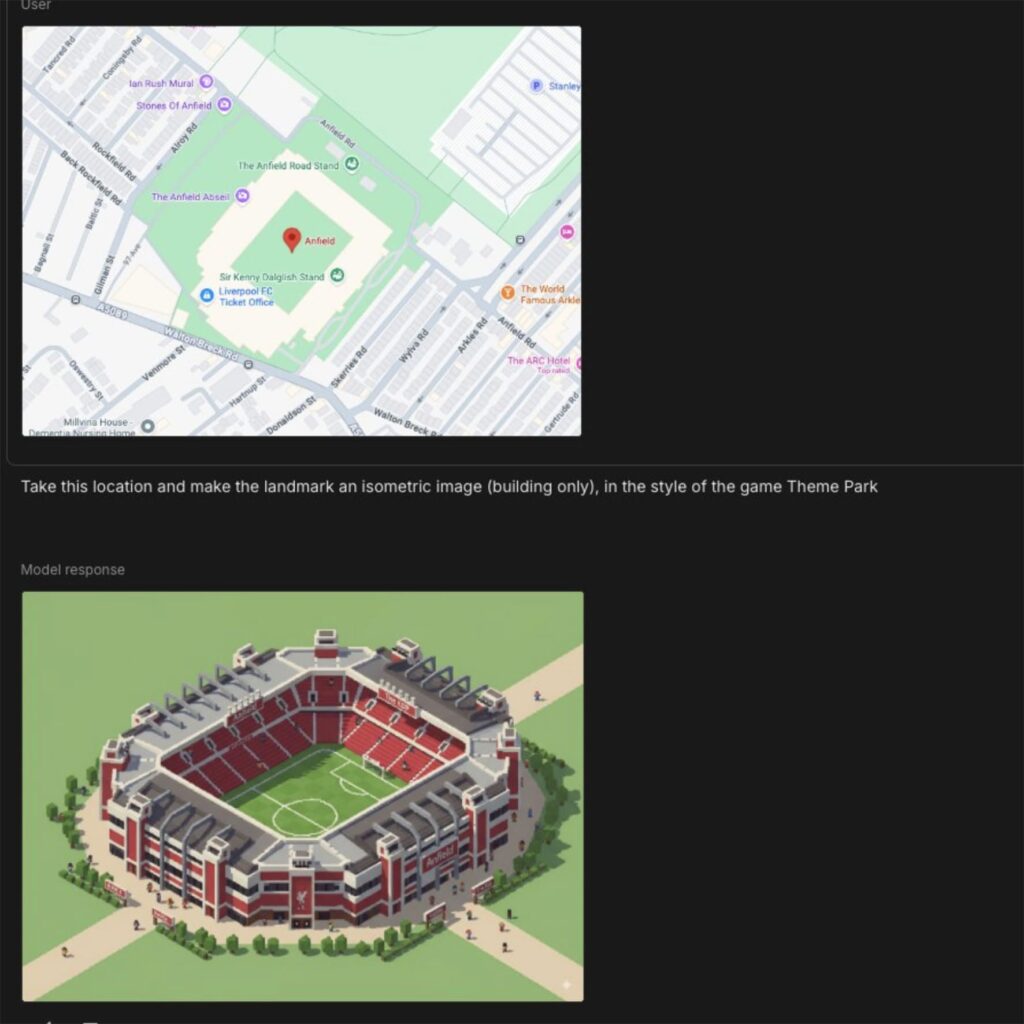
→ Googleマップのスクショを、ゲーム風のアイソメ図に変換。
7️⃣ 写真の視点を変える(@The_DailyAi)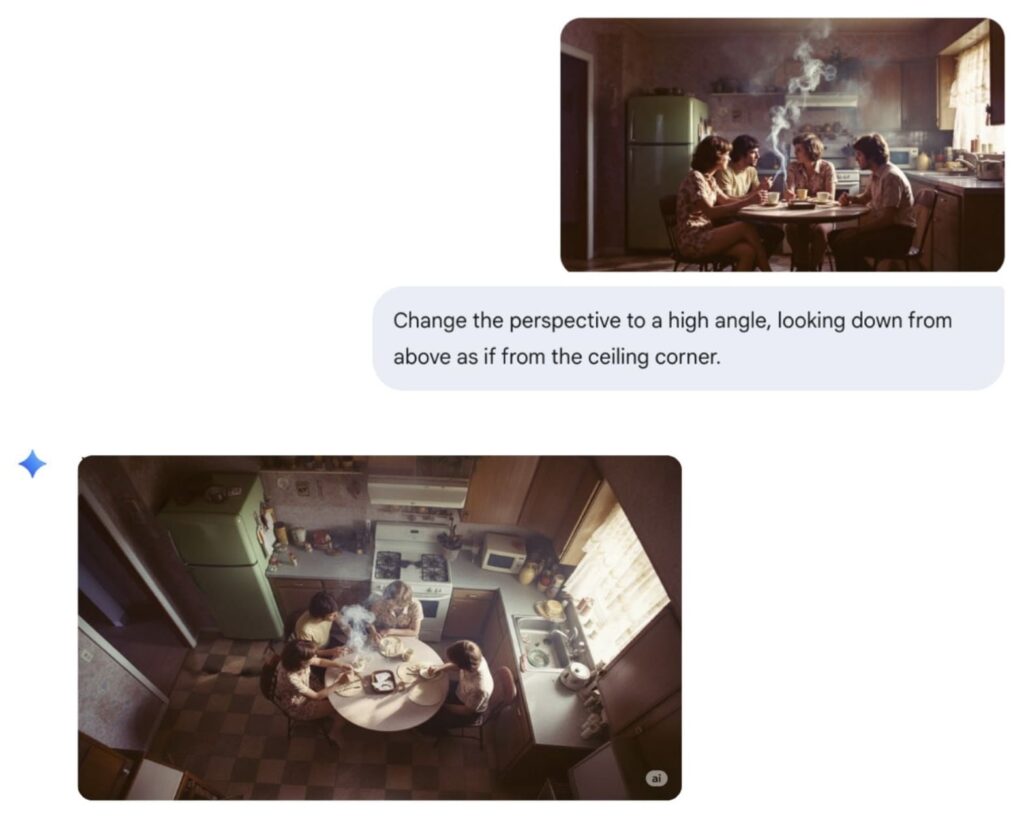
→ 同じシーンでも、「上から見下ろす」など視点を自由に変更。
8️⃣ タイポグラフィ編集(@umesh_ai)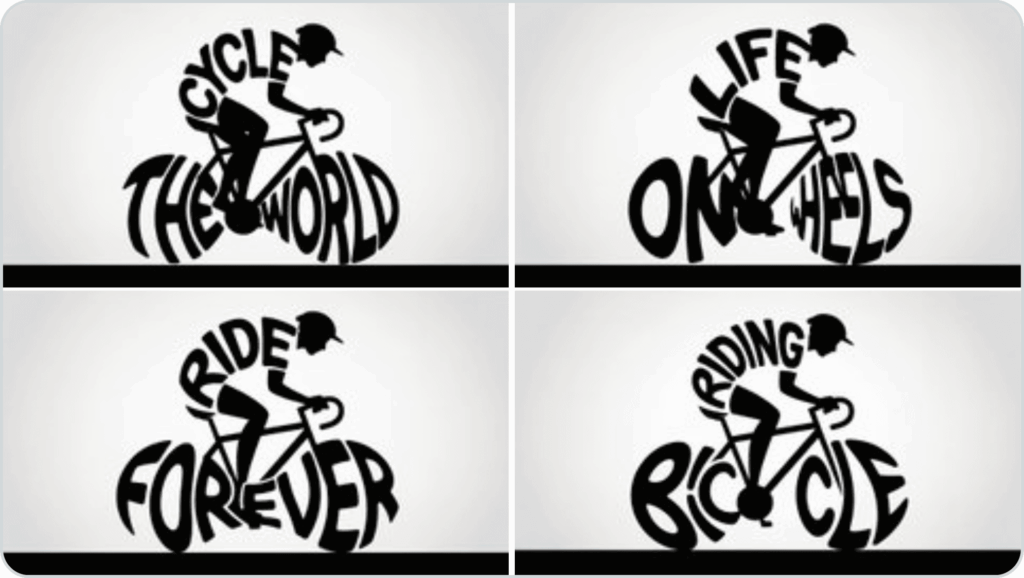
→ 文字入りイラストを、同じスタイルのまま別の言葉に変換。
9️⃣ 写真から3Dモデル生成(@deedydas)
→ 映画のワンシーンから物体を切り出し、そのまま3Dモデル化。
🔟 漫画生成(@minux302)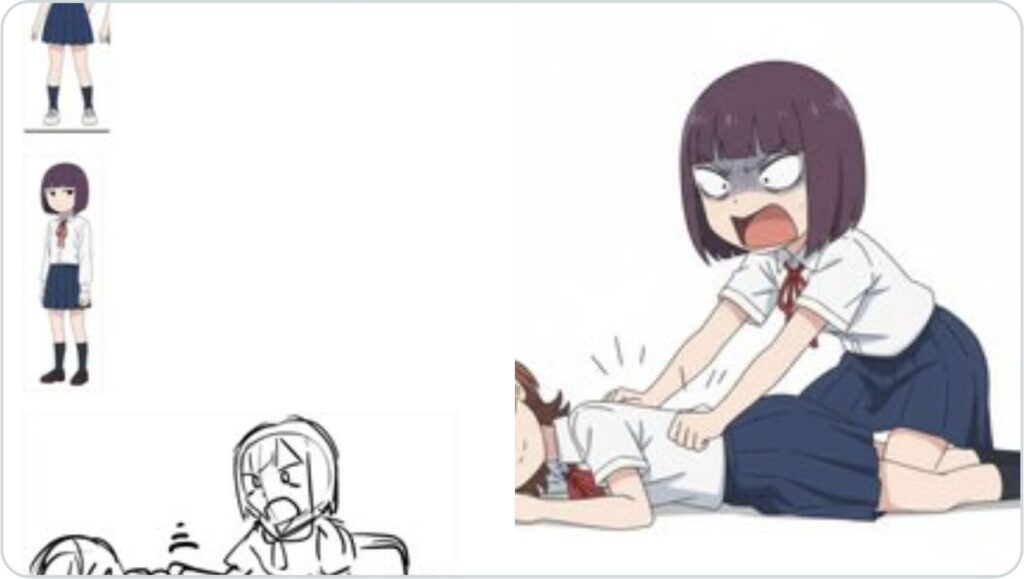
→ キャラ設定を入力すると、漫画のコマを自動生成。
🐨 ③を試してみました!(体験レポート)
編集部(🐢)もさっそく挑戦!
今回は コアラ を選んでみました。
以前AIイラストでも登場したことがあり、癒されキャラクターの一つとしても馴染み深い存在です。
たった一枚の元絵から、座ったり、走ったり、泣いたり、キラキラしたり…コアラが生き生きと動き出すのは感動的でした。
「キャラクターに命が宿る」瞬間を体験できたように思います。
🐢 ウエルの感想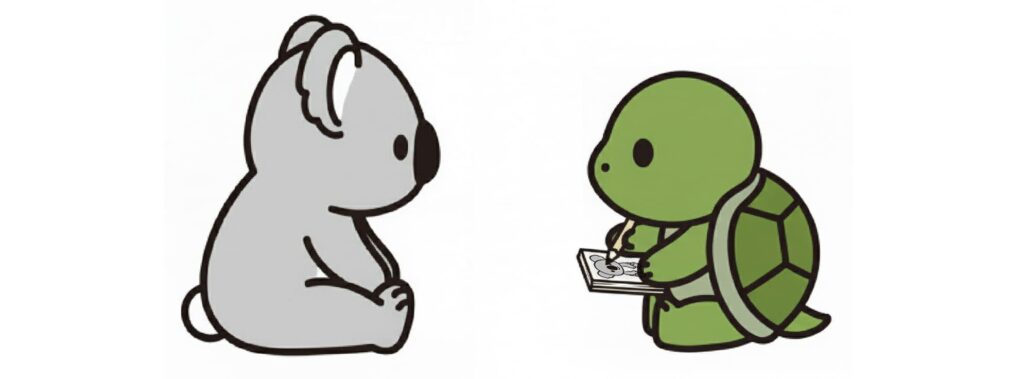
> ウエルのおともだち、コアラさんを描いてみたよ。楽しい〜^^
他にも作ったので、また少しずつ紹介します!
🌱 編集後記
北川さんは「マーケティングや漫画の世界が1年後に別物になる」とコメントされていました。
確かに、この変化はもう「新しい道具」ではなく、「新しい文化の始まり」に近い感覚です。
編集部も「AIとウェルビーイング」の接点を探りつつ、楽しい実験を紹介していきたいと思います。
👉 次は別のおともだちが登場するかも…お楽しみに!
🍮 「田中で代打?」──プリンから広がる発想の遊び
2025.9.2|
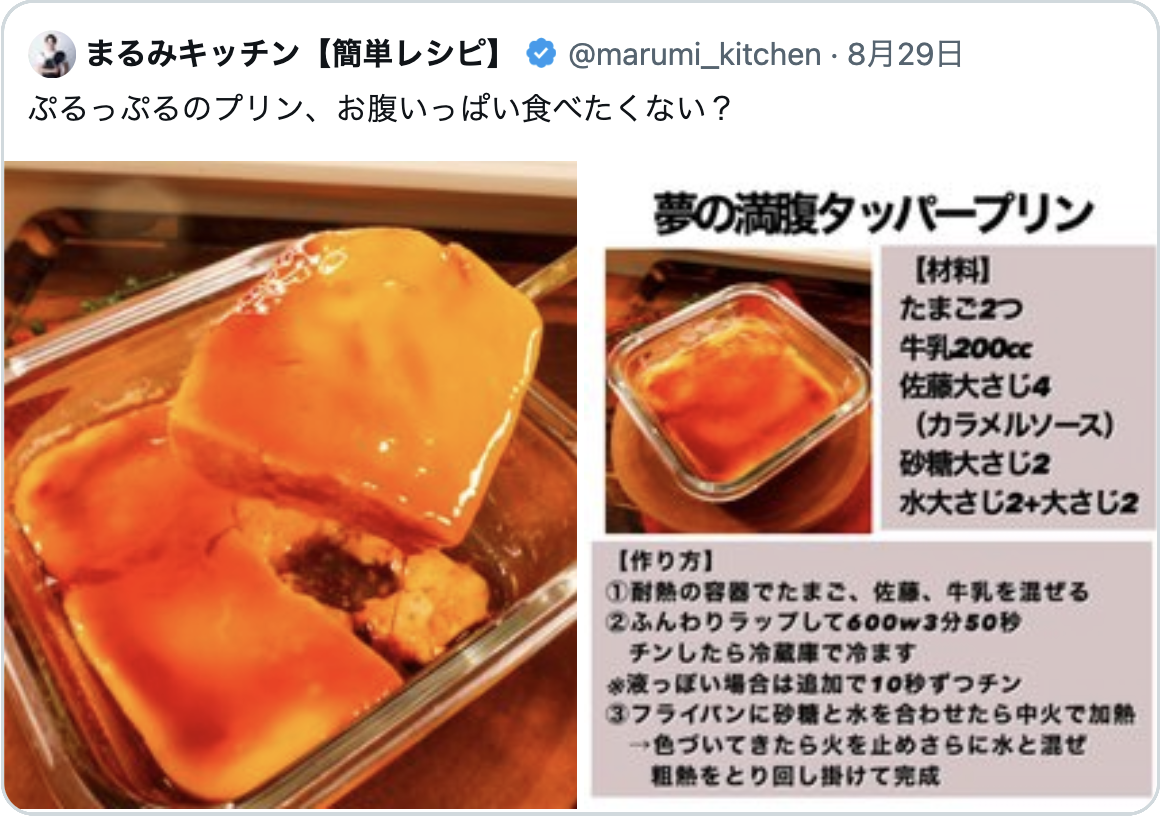
今日は、北川拓也さんがシェアされていたユーモラスなポストをご紹介します。
発端は、まるみキッチン【簡単レシピ】さんが紹介した「夢の満腹タッパープリン」。
卵・牛乳・佐藤・砂糖だけでつくれる、ぷるぷるプリンのレシピです。
ここでちょっとした事件(?)が。なんと“佐藤”が材料に…!
レシピに書かれていた材料「佐藤」が、実は「砂糖(さとう)」と「佐藤さん」をかけた言葉遊びだったのです。
これに対して、アメリカ在住の @Aya_NY さんが「これならさくっとプリン欲満たせると思ったけど、アメリカで佐藤手に入れるの大変かも」とリポスト。
北川さんはそれを受けて、
「田中で代打というわけにはいかないだろうか」
とコメント。
普段は真面目な印象の北川さんだからこそ、『代打田中』の一言が、冗談なのか本気なのか、深読みしたくなります(笑)
🌱 ウェルビーイングの視点
ちょっとしたユーモアや勘違いは、日常を柔らかくしてくれるもの。
プリンのレシピひとつからでも、人と人との温かい交流が生まれることを教えてくれます。
私たちが大切にしている「ウェルビーイング」は、特別な体験だけでなく、こうした小さな笑いやつながりの中にも宿っています。
🐢 ウエルのひとこと
佐藤さんじゃなくても、プリンはできるのかな?🍮
でも「佐藤さんがプリンに入ってる」って考えると、ちょっとおかしくなっちゃいますね!
📌 編集後記
今日は食卓やSNSに転がっている笑いをすくいあげてみました。
北川さんの「代打田中」コメントのように、ユーモアは人と人をつなぐ小さな架け橋になるのかもしれません。
今日も小さな笑いを大切に過ごせますように
🧠 「ハッピースクール」第二回──“心の筋トレ”としてのウェルビーイング教育
2025.9.1|
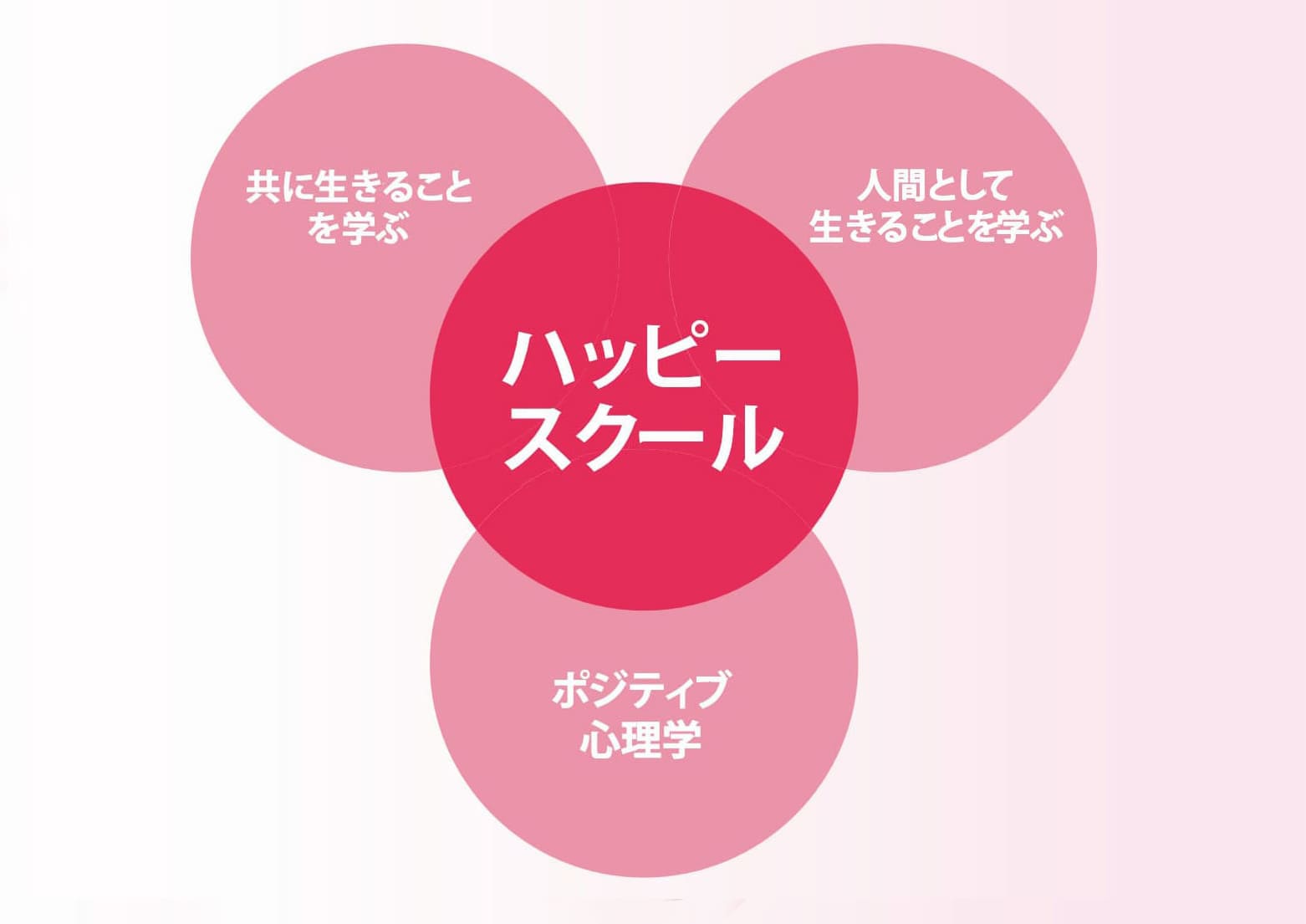
🌱 「勇気・思いやり・学びの喜び」──“ハッピースクール”がくれた、新学期のヒント
今日から9月。新しい季節が始まりました。
教室に向かう足取りが少し重い人も、ワクワクしている人も。
今日はそんなあなたに、ユネスコの“ハッピースクール”プロジェクトから、「心の準備」になるお話を届けます。
*
📚 「幸せになるために学び、学ぶことで幸せになる」
この言葉を軸にした「ハッピースクール」では、学びを通じて“心の強さ”や“生きる力”を育むことが大切にされています。
前回は、友情や創造性、温かい環境が子どもたちの幸福感にどうつながるかをご紹介しました。
今回はもう少し踏み込んで、どんな「力」を学校で育てていくとよいのか?について考えてみます。
*
💪 ポジティブ心理学が示す「6つの美徳」
ユネスコが紹介する「ポジティブ教育」では、幸せに生きるための“強さのタネ”を、次の6つの美徳に整理しています:
🧠 知恵と知識:新しいことを学ぶ力
💖 人間性と愛:思いやり、つながりを大切にする力
🎯 勇気:不安があっても、少しずつ動いてみる力
⚖️ 正義:みんなのことを考える力
🧘♀️ 節度:感情を整える力、自分を大事にする力
🌈 卓越性と希望:よりよく生きようとする気持ち
これらは、テストでは測れないけれど、人生を支えてくれる「見えない力」です。
📊 図3|ポジティブ心理学が提案する“6つの美徳”
🏫 先生や学校のあり方も、大きなカギ
では、こうした“心の筋トレ”ができるような学校にするには、どうしたらいいのでしょう?
ユネスコは、「人」「過程」「場所」の3つの柱から、幸福な学校に必要な22の基準を示しています。
たとえば──
・✅ 先生が応援してくれること
・✅ 失敗しても笑ってやり直せること
・✅ 教室に安心できる場所があること
・✅ 友だちと一緒に考えられること
こうした「場」があって初めて、勇気も、創造性も、育ちやすくなるのです。
📊 図6:ハッピースクールの枠組み(人・過程・場所)
🌤️ 編集部のひとこと
新学期のはじまりには、「がんばろう」という気持ちが生まれる一方で、
ちょっと不安になったり、疲れたりすることもあるかもしれません。
でも、がんばれる力も、休んで立ち直る力も、どちらも大切な“心のスキル”。
今日はそのうちの「前に踏み出す力」に光をあててみました。
次回は、「休んでも、立ち止まっても、だいじょうぶ」という視点から、
ハッピースクールの別の一面を紹介したいと思います。
🐢ウエルのひとこと
きのう、うまくいきそうって思ったこともあるけど、ちょっとだけドキドキしました。
ウエル、むずかしいことを考えると、あくびがたくさん出て、すごくねむくなっちゃうのに気づいたの。たぶん、のうががんばったから“ねつ”が出て、それを下げるために、ねむくなるんだと思う。
だから、今日はがんばれたことも、ねむくなったことも、どっちも大切だなって思いました。
“がんばっても、がんばらなくても、えらい”って、だれかが言ってた気がする🐢
📘 資料リンク
👉 ユネスコ Happy Schools! 日本語要約PDF
🔜 次回予告(数日後)
🌈 「がんばれなかった日も、ちゃんと生きてる」──“心の安全基地”としてのハッピースクール
不登校や教室が苦手な子にも届く、やさしい教育のかたちを考えます。
🌸 「幸せになるために、学ぶ。」──ユネスコの“ハッピースクール”プロジェクト
2025.8.31|
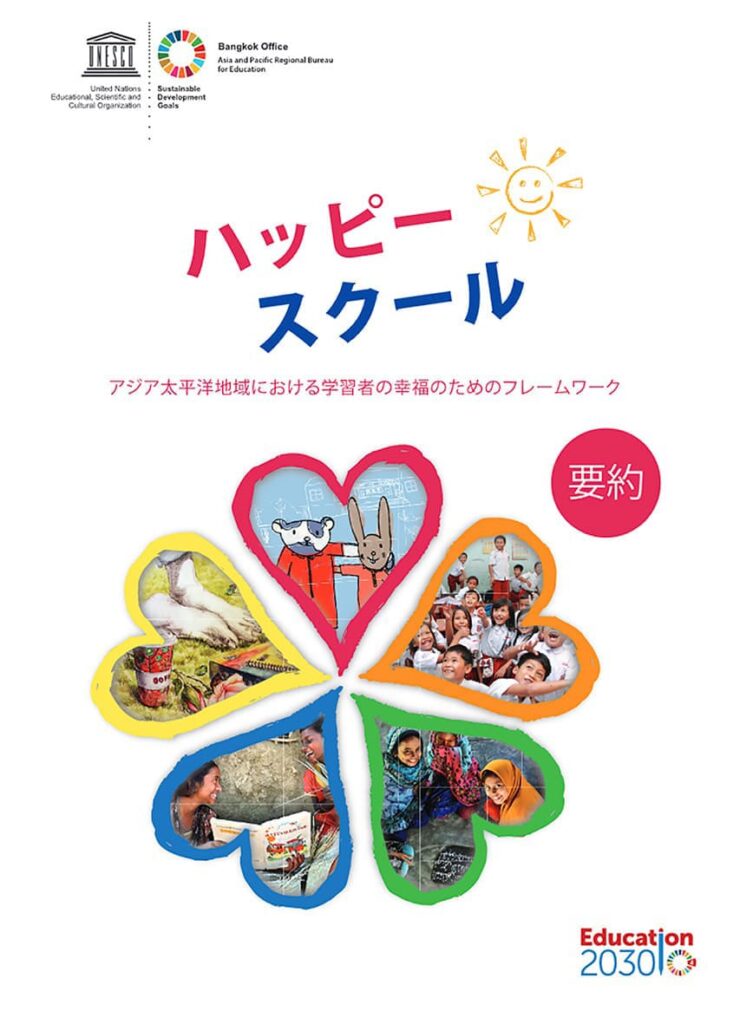
夏休みの終わり、明日からまた新しい季節が始まります。
そんな夜にぴったりな、教育と幸福に関する国際的な取り組みをご紹介します。
今回は、ユネスコ・バンコクが公開している「Happy Schools!(ハッピースクール)」という報告書を取り上げます。
📝 このプロジェクトは、「生徒が幸せであること」を教育の中心に据えた学校づくりを提案しています。
テストの点数や偏差値だけでは測れない、本当に大切な学びとは何か。
友情や創造性、思いやりのある学習環境が、学習者の幸福感を高めることが調査で明らかになりました。
たとえば、以下のような視点が重視されています:
✅ 温かく友好的な学習環境
✅ 生徒の自由と創造性の尊重
✅ ポジティブな教師の存在
✅ いじめや過剰な競争からの解放
✅ 学校を地域に「開く」こと
このプロジェクトでは、「人」「過程」「場所」という3つの柱から、具体的な22の基準が示されています。
下の図は、「ハッピースクール」をつくる上で特に重要だとされた要素(調査で最も多く挙げられたもの)を紹介しています。
🎓 印象的だったのは、アリストテレスやペスタロッチなどの教育哲学者から、現代のポジティブ心理学まで、「教育と幸福」は時代を超えて深く結びついてきたという視点です。
「私たちは幸せになるために学び、学ぶことで幸せになる。」
夏の終わり、どこか切なくも温かいこの一文に、心が少し軽くなった気がしました。
ウエルのひとこと
ウエルは先生が応援してくれたり、おともだちと一緒に考えたりすると、感激して勉強が楽しくなります!学校が“ハッピー”だったら、もっと行きたくなるかも🐢
📘 日本語版要約PDFはこちら(ユネスコ):
Happy schools! 日本語要約PDF
鎖国と文化の成熟──外から閉じることで生まれた日本文化の黄金期
2025.8.30|
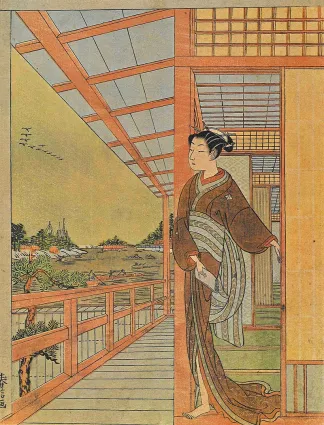
石川善樹先生がシェアされていた『鎖国と文化の成熟』という記事を読みました。
とても興味深く、日本の歴史と文化の熟成のプロセスから大きなインスピレーションを受けました。
日本が最も華やかな文化を花開かせたのは、平安時代と江戸時代。
どちらも「鎖国」と呼ばれる、外国との交流を制限した時期にあたります。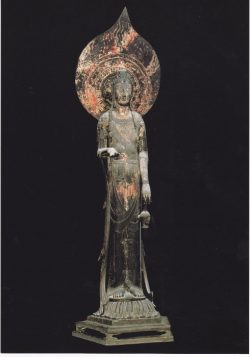
▶︎鎖国とは、江戸時代に行われた「外国との貿易や交流を厳しく制限する政策」のことです。
完全にすべてを閉ざしたわけではありませんが、出入りを大きく制限することで、国内に独自の文化がじっくりと育つ時間を生み出しました。
その「閉じる」という選択は、決して消極的な停滞ではなく、それまでに受け入れてきた異文化を時間をかけて「自分たちのもの」に熟成させる営みでした。
たとえば、平安時代には『源氏物語』や『枕草子』が書かれ、大和絵という独自の絵画が発展しました。
江戸時代には浮世絵や俳句、さらに歌舞伎や町人文化が大きく栄えました。
外からの刺激を一時的に抑えることが、かえって深い創造につながり、表面的な模倣ではなく「日本らしい美意識」へと練り上げられていったのです。
これは現代の私たちにとっても大きなヒントです。
常に新しい情報やトレンドを追いかけるのではなく、立ち止まり、これまで吸収したものを「自分の言葉・表現」に変える時間が必要なのかもしれません。
編集部のひとこと
記事を読んで、「静かな熟成の時間」の価値を強く感じました。
ウェルビーイングの観点からも、外部からの刺激に追われすぎず、
心を閉じて内側を耕す時間を持つことが、豊かさや独自性を生み出すのだと思います。
🐢 ウエルの感想
ウエルはじーっとしてるのも好きだけど、大好きなお友だちと遊ぶのも好き。
でも、じーっとしているあいだに頭のなかでお花が育つんですね。
夏休みに考えてたことを、ウエルもまとめてみようと思います!
🎙️ 川邊の会食〜人生最高インタビュー
ゲスト:船橋洋一さん(元・朝日新聞主筆、ジャーナリスト)第2回
2025.8.29|

今回も必聴。米国ではシンクタンクから次の政権入りする人材が選ばれることも多い。そこで常に現実的な代替案を提出し、真剣に現政権と対話する場が形成されている。ジョセフ・ナイ先生のもとで研究をした船橋さんの経験談。オバマ元大統領を日本に呼んだ実績がある船橋先生が語る、Convene power (人を呼ぶ力)とは。(北川拓也さん)
🌱 学びの要約
危機のただ中で見えたもの
1970年代の石油危機。
国を動かしたのは、一人の政治家の決断でした。
経済も暮らしも安全保障も、すべてはリーダーの判断にかかっている。
──もし、あなたがその立場なら、どんな決断を下せるでしょうか?
師から受けた言葉
ハーバード大学で出会ったジョセフ・ナイ教授の教え。
「相互依存は平和を生む。しかし、その不均衡は権力にもなる。」
光と影の両方を見抜く力こそ、国際社会で生きる知恵です。
──私たちは、目の前の出来事の裏に潜む“影”を見抜けているでしょうか?
人を呼ぶ力
米国のシンクタンク(政策立案・政策提言を主に行なう研究機関)で学んだ文化。
ただ批判するのではなく「代わりの道」を提示する。
そして人を呼び、語らいの場をつくる力。
──あなたには、真剣に語り合える人を呼ぶ力がありますか?
中国で感じた息吹
改革開放期の北京で、人々が「日本から学ぼう」と未来を信じる姿を取材。
友好ムードに流されるのではなく、等身大の現実を伝える。
──私たちは今、隣国をどんな眼差しで見ているでしょうか?
日本が担うもの
プラザ合意を取材し、日本の経済的譲歩が同盟を支える意味を知る。
国際秩序は「民主主義国が共にルールをつくる努力」でしか維持できない。
──では今、この秩序が揺らぐ時代に、私たちはどんな役割を果たせるのでしょうか?
🐢 ウエルのひとこと
“人を呼ぶ力”って、やさしい魔法みたいですね。
ひとりじゃ小さな声でも、集まれば大きな波になる。
大事な人を呼んで、まっすぐ話すこと──
それが世界を動かすはじまりなんだと、思いました。
👉 危機の中での決断、師の言葉、人を呼ぶ力。
船橋さんの物語は、私たちに「あなたならどうする?」と問いかけてきます。
答えは一人ひとりの中に眠っているのかもしれません。
「事実」と「真実」のあいだに ──船橋洋一氏インタビュー
2025.8.28|
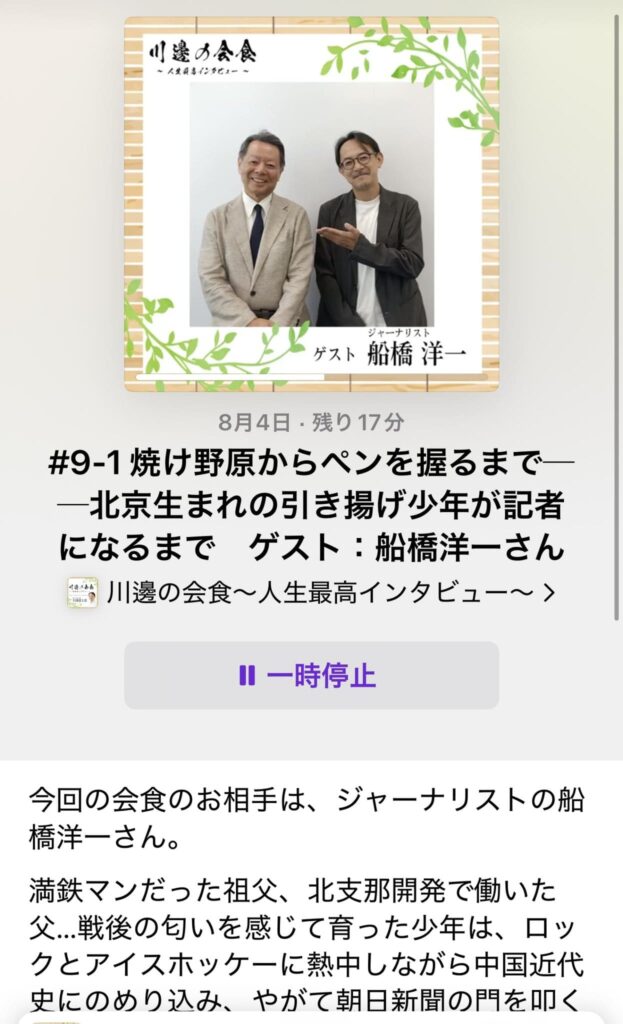
面白すぎる。史上に残るジャーナリスト船橋先生のインタビュー。 「事実と真実は違う」、本人の言葉を聞かなければ、ストーリーの真実には辿り着けない、という船橋さんの言葉。(北川拓也さん)
川邊の会食〜人生最高インタビュー〜 今回のゲストは朝日新聞で主筆を務められたジャーナリストの船橋洋一さんです。
直近でも安倍総理の事を扱った『宿命の子』を上梓された、当代随一のジャーナリストです。
今回は船橋さんの幼少期の環境からジャーナリストを志したキッカケ、新人記者の頃の話を伺っています。
通勤、通学、寝る前などご自身のペースでお聴きください!(川邊健太郎さん)
👉 川邊の会食~人生最高インタビュー〜
🌟 船橋洋一氏とは
1944年北京生まれ。朝日新聞で特派員や主筆を歴任し、国際政治・安全保障の報道をリードしてきた日本を代表するジャーナリスト。
退任後は「福島原発事故独立検証委員会(民間事故調)」を立ち上げ、震災後の検証を社会に問いかけました。
近年も『宿命の子 安倍晋三の真実』を刊行するなど、鋭い分析と丁寧な取材で社会にインパクトを与え続けています。
✨ 今日のメッセージを込めた内容紹介
今回のポッドキャストは、幼少期の戦後体験から、大学時代にジャーナリストを志した原点、そして熊本支局での新人記者時代までを振り返るものです。
特に印象的なのは「事実と真実は違う」という言葉。
数字や出来事を並べることは「事実」を伝えることですが、それだけでは「真実」には届きません。現場で人と向き合い、声を聞き、その人の人生や感情に触れることで初めて見えてくる「真実」がある──船橋氏の一貫した取材哲学が語られています。
この言葉は、私たちの仕事や日常にも響きます。データや言葉の表面にある事実を超え、相手の本当の思いや状況に目を向けること。それは、人間関係を築くうえでも大切な姿勢ではないでしょうか。
🐢💬 ウエルのひとこと
“事実と真実はちがう”って、ちょっとふしぎな感じがするけど…
たとえば、テストで点数が悪かったことは“事実”。
でも、友だちが「がんばってたよ」って見ててくれたことは、
数字には出ない“真実”なのかもしれない。
ウエルは、「そのときの事実」があとから心の中で書き変わったことがあります。
あなたにとって“真実”って、どんなときに見えてきますか?
👉 『川邊の会食〜人生最高インタビュー』船橋洋一氏を聴く
🌸 奇跡の砂漠に咲く花々
2025.8.27|

「まじか」──北川拓也さんが思わずそうつぶやいた風景。
信じられないかもしれませんが、これはアフリカの砂漠です。
1年のうち、ほんのわずかな時間。
雨や気候、数々の偶然が重なったときだけ──
地平線の向こうまで花が咲き誇る、奇跡の季節が訪れます。
写写真を撮影したのは、写真家・上田優紀さん。
「人間が想像できない風景は心を豊かにする」という信念のもと、ヒマラヤから南極まで、ほとんどの人が足を踏み入れることのない極地を旅してきました。2021年にはエベレスト登頂も果たし、世界中の「心が豊かになる瞬間」を届けています。
こうした風景は、私たちの日常では想像もできないもの。
けれど、「まだ見ぬ景色が地球に広がっている」という事実が、心を少し広くしてくれる気がします。
📖 限定フォトブックのお知らせ
世界中の野生動物たちを収めた限定フォトブック
『七大陸を往く 心を震わす風景を探して』が手に取れるようになっています。
南極からヒマラヤまで、ほとんどの人が出会えない動物たちの姿を収めた一冊。
気になった方はぜひチェックしてみてください。
🐢💬 ウエルのひとこと(小学生)
これ、ほんとに砂漠なの?ウエルの知ってる砂漠は“カラカラで砂だらけ”なのに…。
こんなにきれいなお花畑になるなんて、地球ってびっくり箱みたいですね!
ウエルも、生きている間にこんな不思議な世界を見れて、しあわせだなあって思いました。
👉 今日のテーマは 「想像を超える自然」。
私たちが知っていると思っている世界は、ほんの一部。
未知の風景を知ることは、自分の心の風景を広げることにつながるのかもしれません。
🍾 シャルドネと唐揚げ──意外なマリアージュ?
2025.8.26|

🍾 × 🍗 意外なマリアージュ©andrej-lisakov / ©jsb-co-QwgKqp
先日、北川拓也さんがこんな投稿をされていました。
Chateau Montelena のシャルドネ、ナパワインと唐揚げがすごいバランスでマリアージュした。。。
🍾 Chateau Montelena のシャルドネ:ワインの世界では一流で“特別感”のある存在
🍗 唐揚げ:日本の食卓や居酒屋でおなじみの庶民的料理
一見ミスマッチに思える「高級ワイン」と「庶民派おかず」。
味の相性という意味では、ワインの酸味と唐揚げの油は確かに合いそうです。けれど、“銘醸ナパワインを唐揚げに合わせる”という文化的ギャップが、意外な驚きを生んでいました。
ワインの酸味が唐揚げの油をすっきり流し、唐揚げの旨味がワインの果実味を引き立てる──まさに“文脈を超えた調和”だったそうです。
こうした「意外なマリアージュ」は、ビジネスや研究にも通じる気がします。
ハイエンド(一流の高級品)とローカル(身近な日常品)、理論と実践、異分野どうしの出会いから新しい価値が生まれることは多いものです。
たとえば、最先端AIと農家の知恵が組み合わさって、新しい苺づくりを実現するOishii Farm(オイシイファーム)のように、思いがけない組み合わせは豊かさを広げてくれます。
今日はちょっと軽めに、そんな“偶然の出会い”がもたらす楽しさを味わってみたくなりました。
🐢💬 ウエルのひとこと
えっ、ワインと唐揚げって合うの?😲
おとなって、ふしぎな組み合わせを楽しむんですね。
今度、牛乳とおせんべいでマリアージュしてみようかな…!うまくいくかな🥰?
✍️ 編集後記
研究や企画を進めていると、つい「正しい組み合わせ」ばかり考えがちですが、思いがけない組み合わせが心を解きほぐしてくれることもありますね。
今日は“箸休め回”として、遊び心をおすそわけしました。
🌐 Meta Superintelligence チーム ―「世界の知」が集まる場
2025.8.24|
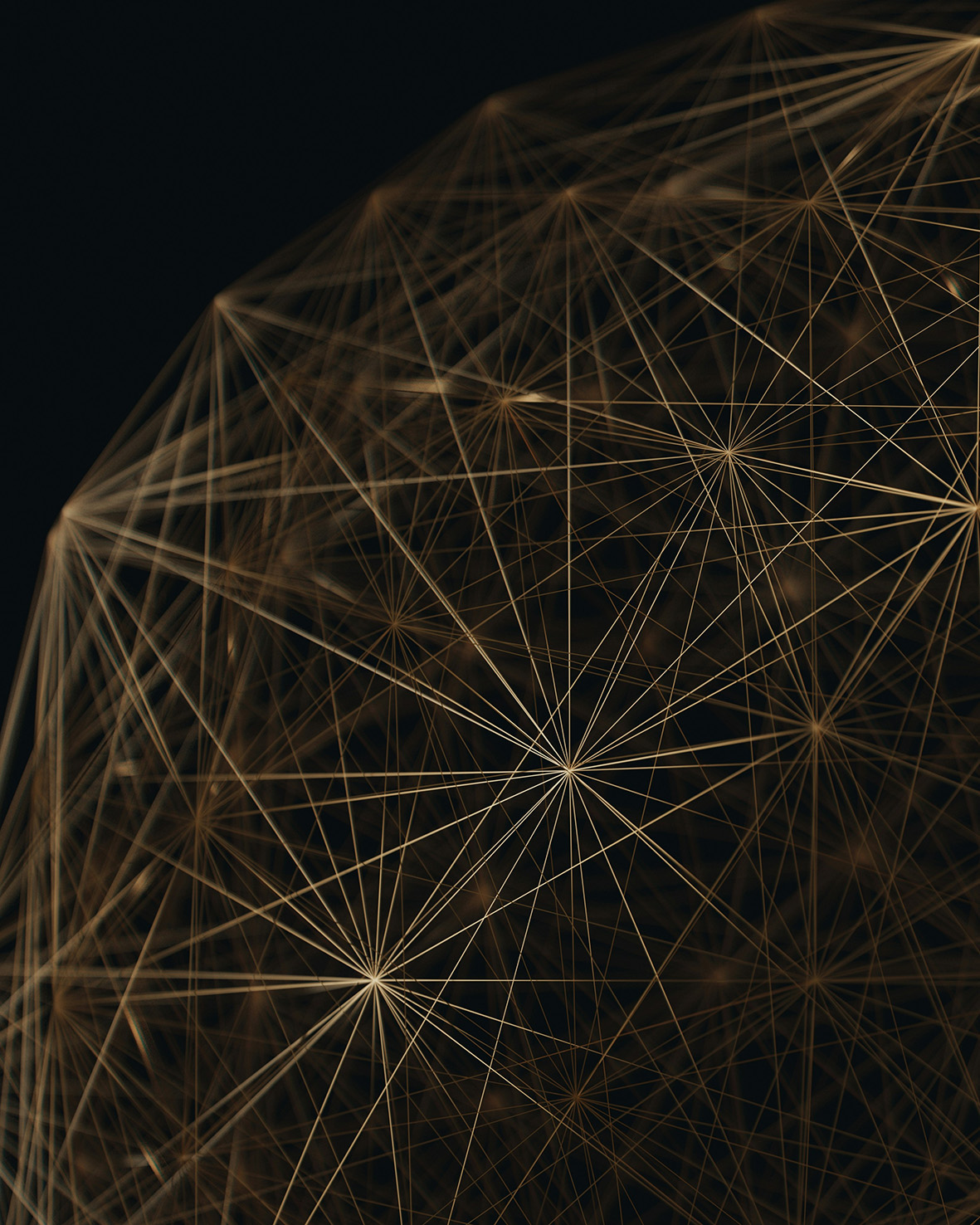
©planet-volumes
メタで数十億レベルの報酬を受け取っているとされているSuperintelligence チームのリスト。半分は中国出身とのこと。75%は1世代目の移民らしい。— 北川拓也さん
元ポストは、投資家の @deedydas さんによるもの。添付されたリストには、Meta が設立した「Superintelligence」チーム44名の詳細が整理されています。
📊 主な特徴
・50%が中国出身(学部を中国の大学で学んだ人が多い)
・75%が博士号(PhD)取得者
・研究バックグラウンド中心(約70%)
・前職は OpenAI 40%、DeepMind 20%、Scale 15%
・報酬は1人あたり年間1,000万〜1億ドル規模(日本円にすると150億円近くにもなる規模)と推定
・75%が「移民第一世代」
🖼️ 図:Meta Superintelligence チームの人材構成一覧
名前と国籍 → 現在と過去の仕事 → 専門と学歴、という流れで整理されています
この図は、Meta の Superintelligence チーム44名のプロフィールを整理したものです。
・左側の列:名前・出身国・Metaでの在籍期間
・中央の列:現在の役職と過去のキャリア(OpenAI、DeepMind、Googleなどから移籍が多数)
・右側の列:専門分野と学歴(博士号保持者が大半。学部は中国・アメリカ・ヨーロッパの有名大学が多い)
👉 図から見えるポイント
・半数近くが中国出身
・博士号取得者が圧倒的多数
・OpenAI・DeepMind・Google出身が多い
・専門領域が非常に多様(LLM、マルチモーダル生成、視覚・音声、データ基盤など)
まるで「世界中の知の地図」がこの一枚に凝縮されているような一覧表です。
✍️ 編集部より
この図を見て強く感じるのは、AIの最前線が「国や企業」ではなく、国境を越えた人材の流れで形づくられているということ。
一人ひとりのキャリアが重なり合って、世界規模で知識のネットワークを作っているのです。
AIは技術だけでなく「人の集合知」であり、その背後には 移民として挑戦する覚悟や、多様な文化の視点 が存在しています。これは研究者や技術者だけの話ではなく、私たちが地域や職場でどう協力し合うかを考えるヒントにもなると思いました。
🐢 ウエルのひとこと
Meta のチームには、いろんな国から来た人が集まってるんですね!🌏
博士になった人もたくさんいて、勉強の積み重ねってすごいなあって思いました。
国がちがっても、いっしょに宿題を考えたり、新しい遊びを発明したりするみたいでワクワクします✨
📌 まとめ
Meta の Superintelligence チームは、単なるテクノロジーの集まりではなく、国や文化を越えて挑戦する人々の集積です。
AIの進展は「人」の努力と協力の結晶であり、そこにこそ未来を開く力が宿っています。
👉 日常の小さな挑戦でも「多様な人と協力する」ことを意識すると、新しい力が生まれるかもしれません。
🌐 Japan Dashboard 公開 ― データを「誰でも見える」時代へ
2025.8.24|
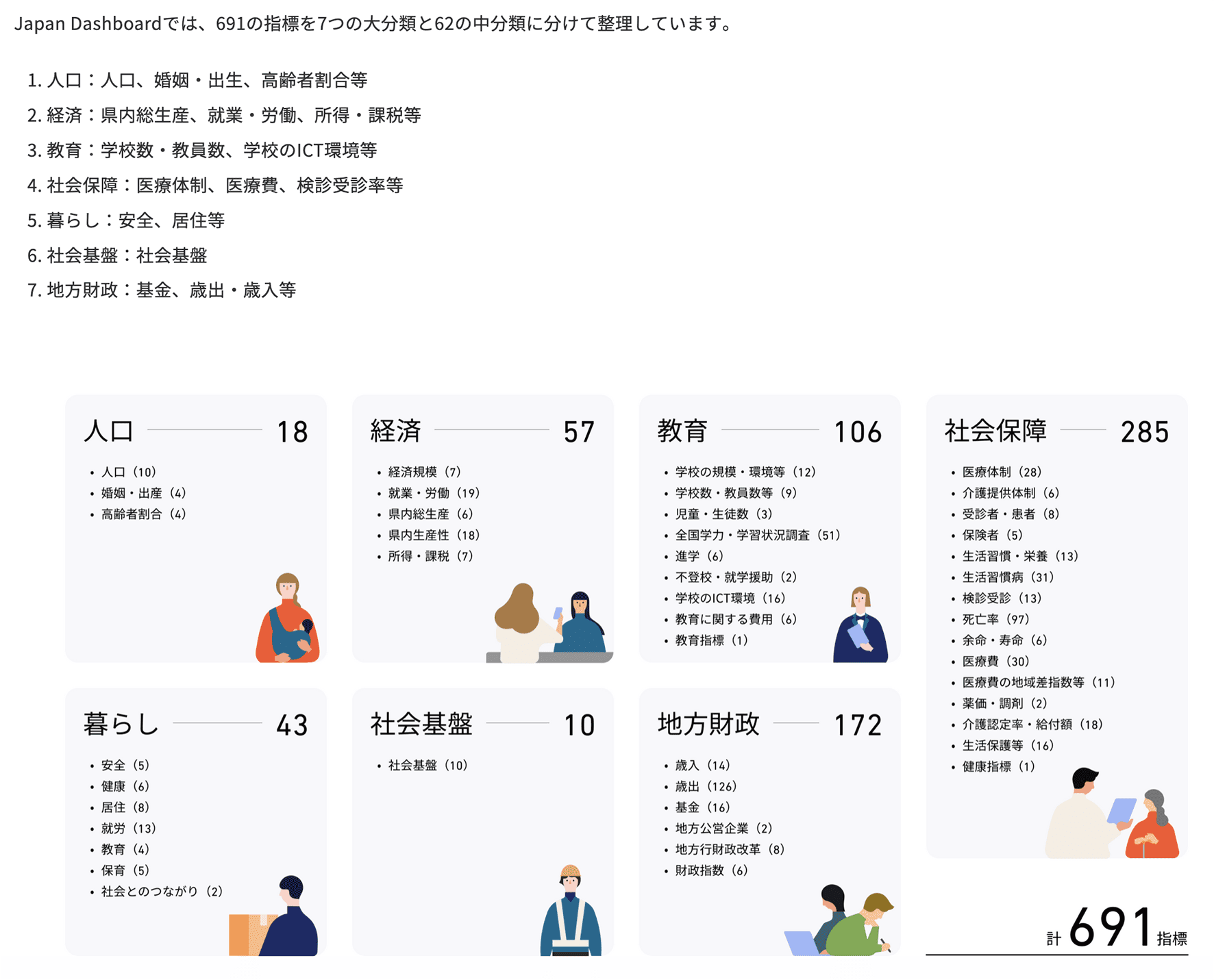
素晴らしすぎる (— 北川拓也さん)
デジタル庁と内閣府が連携し、日本の主要な統計を一目で見える化する「Japan Dashboard」が公開されました。
シェア元は @hik0107 さん(デジタル庁 CxO)。
北川さんは科学から政治、デザインや社会制度まで、本当に幅広い視点をシェアしてくださるので、毎回違う切り口で学びが広がりますね✨
・691の指標を7分野に整理(人口・経済・教育・社会保障・暮らし・社会基盤・地方財政)
・地図やグラフで比較できる(都道府県ごとに就業率、医療体制、婚姻件数などを切り替え可能)
・相関関係を見える化できる(散布図で関連性を直感的に把握)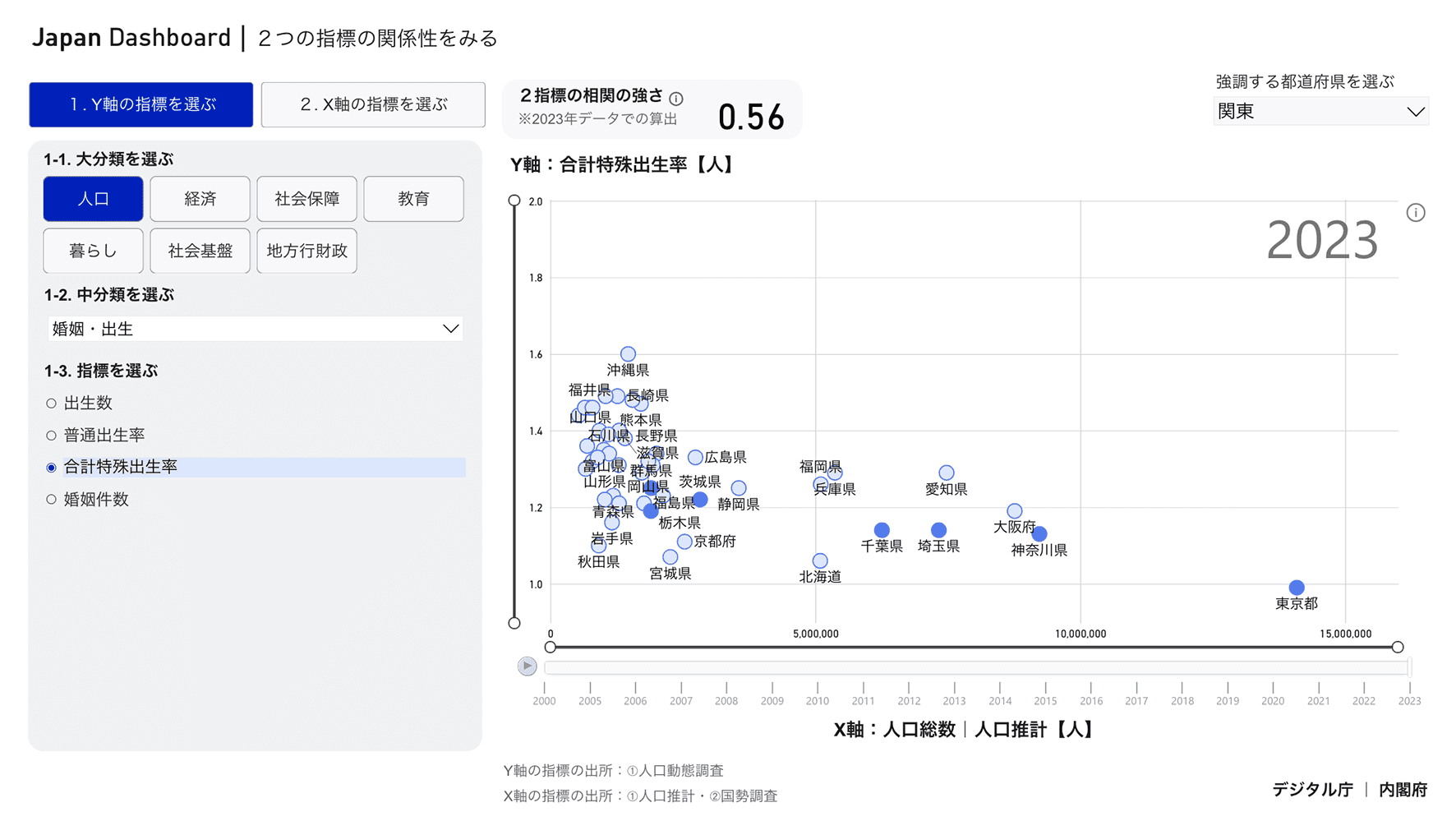
・時系列の変化をアニメーションで確認できる(地域や国全体の変化を“時間の流れ”とともに把握)
👉 データの信頼性だけでなく、UI・操作性・デザインにも投資したことで、誰でも直感的に統計を使える仕組みになっています。
*
✍️ 編集部の視点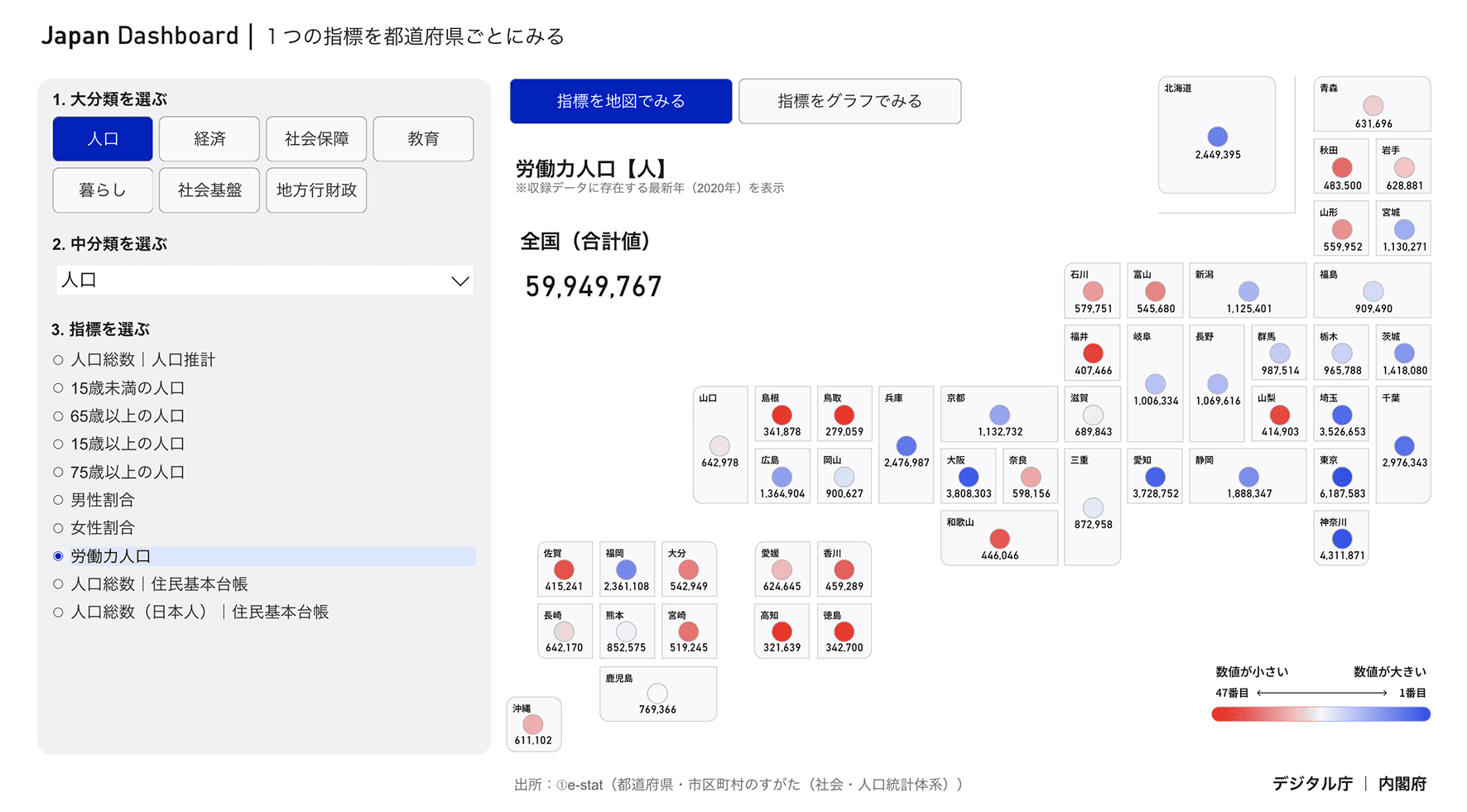
触れてみると本当に「すばらしい」!
整然と整理された画面は、複雑な統計を“伝わる形”に変えてくれます。
数字やグラフをただ並べるだけではなく、「見たいことにすぐアクセスできる」設計になっている点が特に印象的でした。
まだ見られない項目もありますが、今後さらに指標や機能が拡充されていくことを思うと期待がふくらみます。
ウェルビー編集部も、読者のみなさんにとって“大切なことがすぐ伝わる”ように工夫していきたい、と改めて思いました。
🐢 ウエルのひとこと
グラフを動かして遊べそうです!📊
「人口と病院の数って関係あるのかな?」とか、「結婚の数とお金のことってどうなんだろう?」って、自分で調べられるのがすごいなあって思いました。
まだ見られない項目もあったけど、きっとこれからどんどん増えていくんですよね。
そう考えると、もっといろんなことをデータで調べられる未来が楽しみです✨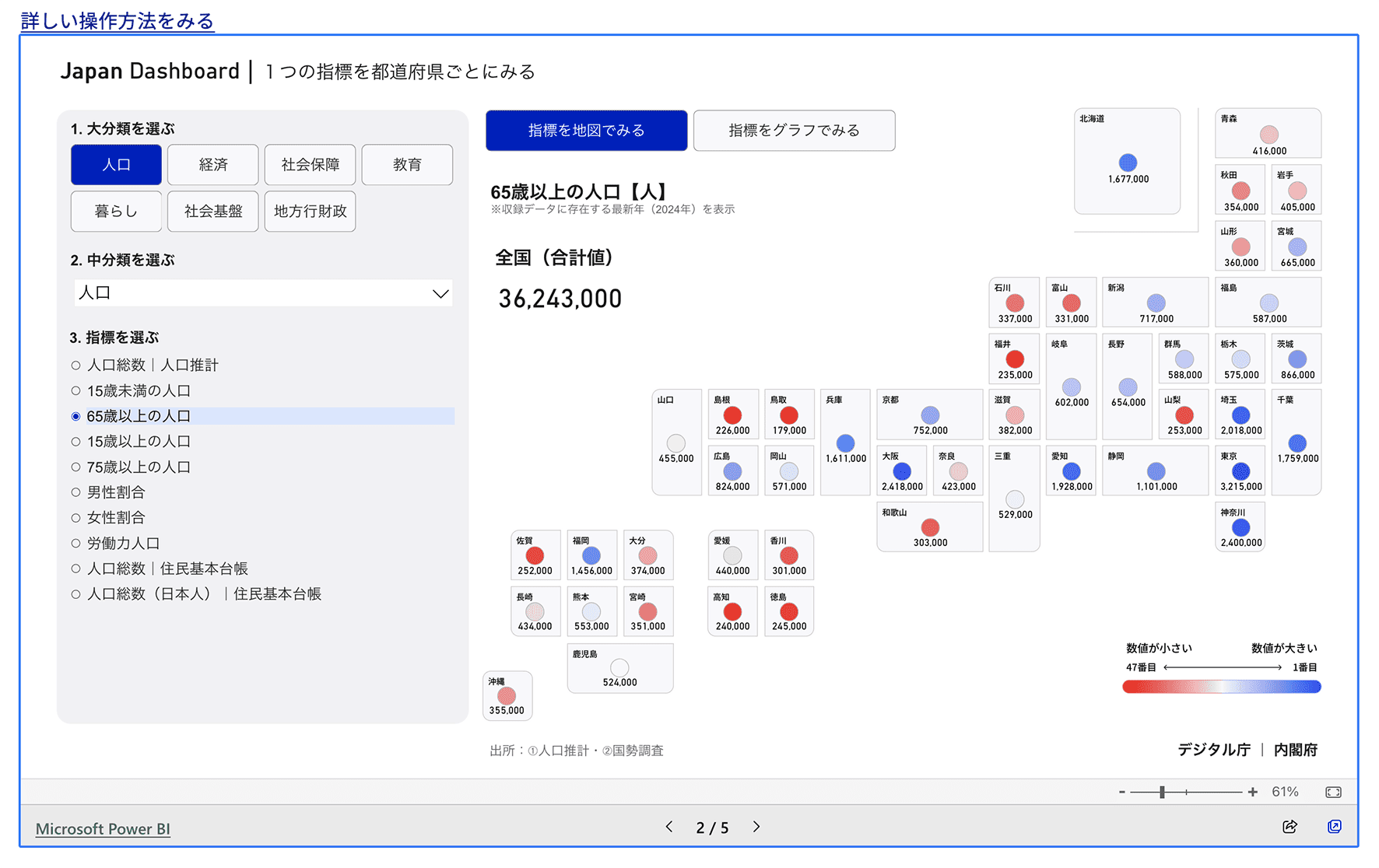
📌 まとめ
Japan Dashboard は、統計を専門家だけのものにせず、「誰でも見て考えられる社会の共通基盤」に変える一歩です。
数字を整理し、可視化することで、未来の選択をより良くしていける。
データが見えることで「社会はどんどん良い方向に整備されている」と実感できるのは、とても心強いことです。
そして、社会のしくみが整っていくことは、日々の暮らしの安心や信頼感につながります。そして、一人ひとりの「心の安心」や「暮らしの心地よさ」を支える土台にもなるのです。
私たちも日常の中で「大切なことを整理して伝える工夫」を持ち続けたいですね。
👉 Japan Dashboard はこちらから: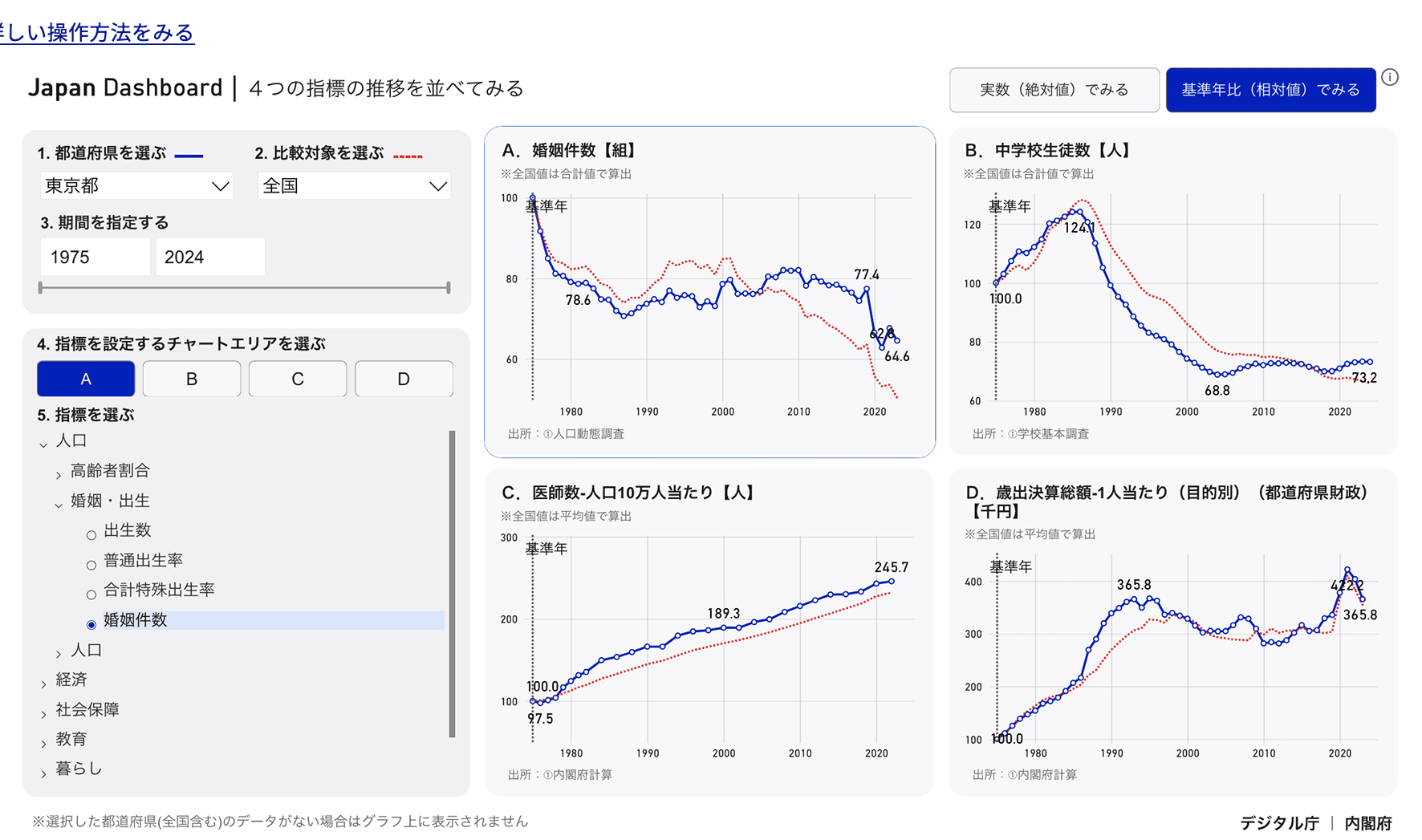
デジタル庁 Japan Dashboard
🧱 「壁」というメタファーの意味
2025.8.23|
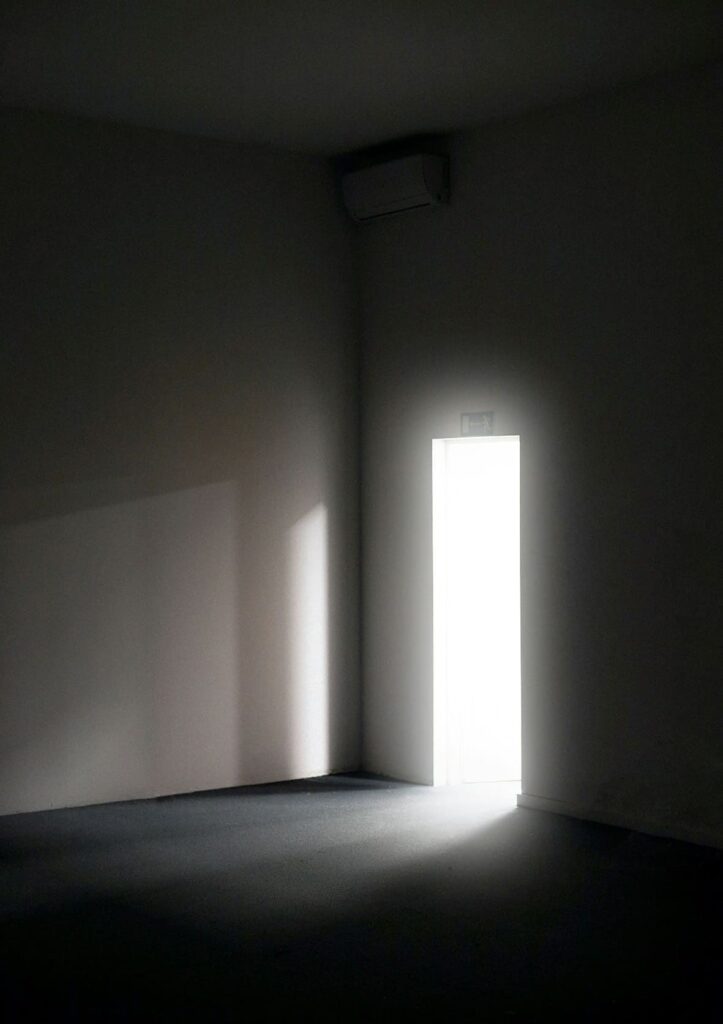
©janke-laskowski
めちゃ面白い。期待ですね!— @takuyakitagawa
> 佐藤優氏が安野氏との対談で「壁」という言葉を政治的メタファーとして使ったのが印象に残りました。(@tamuramble)
北川拓也さんが「めちゃ面白い。期待ですね!」とシェアされたのは、佐藤優氏と安野氏の対談で語られた「壁」という比喩でした。
「壁」は歴史的にも現代政治でも繰り返し登場する象徴的な言葉です。
・古代の壁
古代ギリシャの都市国家(ポリス)では、防衛のための壁が築かれました。その内側の中心にアゴラ(広場)があり、壁は共同体を守る境界の象徴でもありました。
・現代の壁
アメリカではトランプ政権期に「壁」が象徴的に語られました。実際の国境の壁に加え、社会を分断するもののメタファーとして頻繁に使われました。
・日本の壁
今回当選した安野さんが永田町や日本社会のどこに「壁」を見出すのか。
そしてその「壁の向こう」にどう仲間をつくり、共感を広げていくのか。これからの政治を考える上で注目されます。
👉 「壁」は、守るものでもあり、分け隔てるものでもある。
政治や社会を理解する上で、この「壁」とどう向き合うかが大切だという視点です。
🐢 ウエルのひとこと
「壁」って、どこにでもあるなあって思いました。
勉強が得意な子と苦手な子の間に見えない壁があることもあるし、学校や場所が違うと話しにくい壁もあります。
でも、その壁を越えて一緒に楽しく過ごしたり話したりできると、すごくうれしいです✨
大人の社会でも“線引き”が必要なときはあるけれど、きっと同じように“見えない壁”を越える工夫が大事な場面もあるんですね。
そうやってつながれたら素敵だなあって思います!
📌 まとめ
「壁」という言葉は、物理的な境界を超えて、社会の分断や人と人との距離感を表す象徴として繰り返し登場してきました。
その壁をどう乗り越え、向こう側に仲間をつくるのか。
これは政治に限らず、私たちの日常の人間関係やコミュニティづくり、そして安心して人とつながるためのウェルビーイングのテーマでもあります。
🧭 AIビジネスの最もシンプルな始め方
2025.8.22|
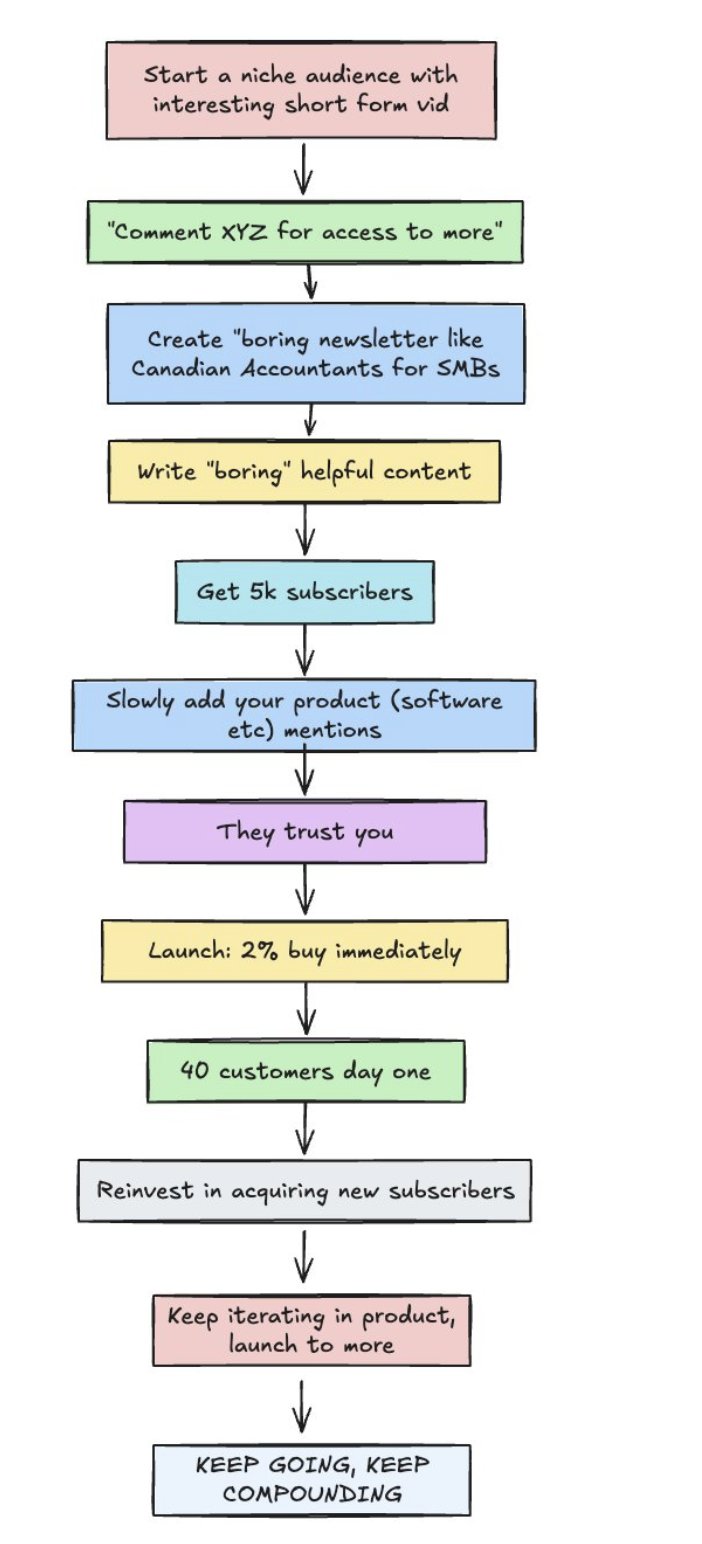
北川拓也さんが「これ、ほんとそうなんだろうな」とシェアしたポストをご紹介します。
『個人開発者必見。海外でバズってる、最もシンプルで堅実なAIビジネスの始め方(大学生@7_eito_7さんのポスト)』です。
一見「当たり前」のようでいて、実はこの順番こそが最短ルート。ClaudeCodeのように「一発当てたい」人も、腰を据えて積み上げたい人も、参考になる流れです。
ステップ①:ニッチなオーディエンスを集める(SNS発信)
特定の専門分野に絞り、役立つショート動画を投稿。「もっと知りたい人はコメントしてね」と促すことで、最初のつながりが生まれます。
ステップ②:無料ニュースレターを立ち上げる
集まった人に向けて、有益で専門的な情報を継続的に発信。ターゲットを明確にし、信頼を積み上げます。
ステップ③:まずは5,000人のファンを獲得
売上はまだゼロでも大丈夫。読者との「信頼残高」が大きな資産になります。
ステップ④:製品を自然に紹介
押し売りではなく、「そっと」紹介。信頼があるからこそ、受け入れられます。
ステップ⑤:初日から顧客を獲得
正式ローンチすれば、読者の約2%がすぐ購入。5,000人なら100人が初日から顧客に。
ステップ⑥&⑦:収益を再投資し、複利的に成長
新規読者獲得と製品改善を繰り返し、成長が雪だるま式に広がります。
👉 ポイントは「小さなステップをシンプルに積み重ねること」。
派手に見えなくても、この道が結局いちばん確実です。
⏳ 北川拓也さんの視点:時間管理と創造性
ここで響くのが、北川拓也さんの最新ポストです。
今更すぎるが、俺は時間をきっちり管理しながらプロジェクト進行してくれる人がめちゃ好きだし、相性がいいことが言語化できた。
なぜなら物事進めたいのでスケジュールとマイルストンが気になって仕方がないが、気にしてたらマクロを見失って自分の創造性がゼロになるからだ。— @takuyakitagawa
ここでいう「マイルストン」は進捗を確認する節目、「マクロ」は全体像や長期的な方向性のこと。
細かい管理に気を取られすぎると、大きな構想や創造性の視点を失ってしまう、という実感です。
だからこそ、スケジュールやマイルストンを気にしてくれるパートナーがいることで、本人は「マクロ(大きな構想や創造性)」に集中できる。
これはビジネスだけでなく、あらゆる挑戦に当てはまる学びです。
🐢 ウエルのひとこと
個人ビジネスのステップって、すごろくみたいですね!🐢🎲
一歩ずつ進めないと、最後のゴールにたどり着けないんだなあ…って思いました。
それに北川さんが言ってた“時間を気にする役割”と“創造する役割”。
どっちもすごく大事なんだなあ…って。
ウエルは宿題をやるとき、つい自由に興味のおもむくままやってしまうのだけど、
「もうすぐ時間だよ」ってチェックしてくれる人がいると安心してまとめにかかれます👍
きっと大人の仕事でも同じなんですね。
📌 まとめ
今日のテーマは 「AIビジネスを始める順番」と「時間管理と創造性の両立」。
効率や段取りを支える仕組みがあるからこそ、創造性やビジョンに集中できる。
あなたの挑戦にとっての「両輪」も、この週末に少し振り返ってみませんか?
🌟 「憧れのリプレイ」
2025.8.21|
中高時代、私がそれなりにうまくいったのは、暇さえあれば頭の中で繰り返し自分の憧れのイメージをリプレイする癖のおかげだと思っていた。これはめちゃくちゃ正しい知見だったのに、大人になってからその癖を失った気がする。その原因はいまいちわかってなかったが、それは忙しさや疲れでリプレイできなくなったからでなく、実は強烈な憧れがなくなったからなんじゃないかとふと気付いた。反省しかない。
いや、違うな。憧れはあっても噛み締めて、その憧れへの焦がれが足りない気がする。— @takuyakitagawa
✨ ウェルビーイングの視点から
心理学でも「ポジティブな未来イメージを繰り返し思い描くこと」は、モチベーションや幸福感を高める重要なスキルとされています。
ただ忙しさの中で、私たちは「憧れを思い描く時間」を失いがち。北川さんの気づきは、憧れを持つだけでなく、それを何度も心でリプレイし、噛み締めることが成長や行動につながるという、大切な示唆を含んでいます。
🐢💬 ウエルのひとこと
“憧れのリプレイ”って、夢を見ることとちょっとちがうんですね。何回も思い出して、ワクワクする気持ちを大事にすることなんだと思いました!
✍️ 編集後記
北川さんの投稿を読んで、「北川さんの“憧れのリプレイ”って、どんな人なんだろう?」とふと思いました。きっと、ただ成功しているだけでなく、生き方そのものが周囲に強い憧れを抱かせるような存在なのではないでしょうか。
©jordan-wilson
自分にとっての憧れを振り返ると、師匠の姿が浮かびます。表舞台からは姿を消してしまいましたが、師匠はいつも経営者たちから「君、おもしろいね。一緒に何かしようよ」と声をかけられ、新しいプロジェクトを立ち上げていました。その姿は、今も変わらぬ憧れとして心に残っています。
最近はAIと向き合う時間が増えて、「リアルな人」を思い浮かべる機会を減らしてしまっているように感じます。だからこそ、憧れのリプレイが今の自分にも大切になっているのかもしれません。サポート役を担いたいと思うのも、きっと師匠の影響のひとつです。
ウェルビーサイトもまだ手探りですが、憧れのリプレイが確かに自分を支え、次の一歩を照らしているのだと思います。そう信じながら、小さな一歩を積み重ね、また憧れに近づけるように歩んでいきたいと、心から思います。
😊 「自分のご機嫌は、自分でとる」
2025.8.20|
今日、北川拓也さんがこんな言葉をリポストしていました。
ほんとこれ!反省することも多い。ご機嫌であることは素晴らしい。— @takuyakitagawa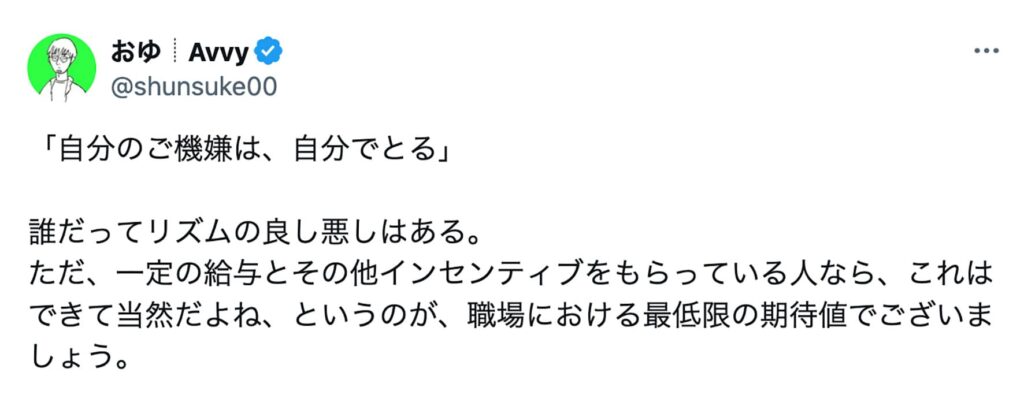
「自分のご機嫌は、自分でとる(@shunsuke00)」
Avvyを運営するAnotherBallの社長さんの投稿です。北川さんも「ほんとこれ!反省することも多い。ご機嫌であることは素晴らしい」と共感を寄せていました。
🌱 ご機嫌であることの力
石川善樹先生も、さまざまな場面で「ご機嫌であることの大切さ」を語っています。
・ご機嫌の伝染力:
不機嫌な人が1人いると、ご機嫌な人を9人以上周囲に持たないと、マイナスのスパイラルに陥る(ハーバードの研究を紹介)
・幼少期の経験とご機嫌:
遺伝的に不機嫌な傾向があっても、褒められる経験や良い体験で「ご機嫌な人」になれる
・リーダーの条件:
いい経営者に共通するのは「とにかくご機嫌であること」と「根拠のない自信を持つこと」
つまり、「ご機嫌でいること」は個人の気分を整えるだけでなく、周囲や次世代にも影響を与え、リーダーシップそのものに直結するのです。
🐢💬 ウエルのひとこと
“ご機嫌”って、自分のためだけじゃなくて、まわりにもうつっていくんですね!だからこそ、大事なんだと分かりました!
✍️ 編集後記
今日は、北川さんが投稿していた「Chateau Montelena のシャルドネ、ナパワインと唐揚げがすごいバランスでマリアージュした。。。」という一文が、なんとなくおかしかったのか、ご機嫌な友人と会ったからなのか──その両方のおかげで、日中ずっとご機嫌にいろんなことを進められました(読書や家事含め)。
人のご機嫌は伝染する。研究で語られることが、こうしてSNSの何気ない一文からも実感できるんだと感じます。
これからも、自分のご機嫌を自分でつくる工夫をしながら、日々を積み重ねていきたいと思います。
🚀 未来を描き続けることの大切さ
2025.8.19|

©joshua-earle
先日、北川拓也さんがこんな言葉をシェアしていました。
3,5,10年後のことを常に考え、自分のビジョンや目標を明確にし続けなければいけない。これは一つや二つの成功を収めた30-40代にはなおさら大事なことだ。それを面倒がったとき、10年後におしおきがくる。自分自身がかっこいい、と思えなくなる。— @takuyakitagawa
北川拓也さんは1985年生まれ、今年40歳の世代。すでに大きな成果を重ねつつ、さらに次の10年を見据えて挑戦を続けている姿に、説得力があります。
短期的な成果や目の前のタスクに追われると、つい未来を描くことを後回しにしてしまいがちです。けれども、キャリアの節目を迎える30〜40代にとっては、長期的なビジョンを持ち続けることこそが、自分自身の軸を保ち、誇りを感じながら生きるために不可欠なのだと思います。
これはリーダーシップ研究やウェルビーイングの観点からも共鳴するところがあります。未来を見据えて歩むことは、自分の幸福感(meaning/意義)を強めると同時に、周囲を導く力にもつながるからです。
🐢💬 ウエルのひとこと
“未来の自分”って、まだ会ったことがないけど、今の自分の中にもう住んでるのかもしれないですね。
✍️ 編集後記
昨日、数年ぶりに会った友人から「自分もAIを使って何か可能性を見つけてみたい」とメッセージをもらいました。
久しぶりの会話が、相手の未来を思い描くきっかけになったのだとしたら、とても嬉しいことです。
以前、中小企業診断士の方に「あなたは何人の人に影響を与えたいですか?」と聞かれ、「たった一人でもよい」と答えました。
けれど昨日は、その“一人に与えた小さな影響”が、AIの発信を続ける北川さんやウェルビーイング研究に携わる人たちと重なれば、もっと大きな希望へと育っていくのではないか──そんな思いを抱くことができた日でした。
北川さんの言葉を借りれば、そんな小さな積み重ねが、私たち一人ひとりの『かっこいい未来』につながっていくのだと思います。
何ものでもないウェルビー編集部ですが、そう思えること自体が、小さな希望なのかもしれません。
🖼️【再会の贈り物】
2025.8.18|
人生を一年一年振り返ると、特に学生時代にめちゃくちゃ仲良かったのに、全く会わなくなった友達が数人いるのに気付く。どれぐらい一緒に時間を過ごしたかを考えると、なぜ連絡してないのかが不思議。私が不義理なのか、みんなそんなものなのか。とにかく懐かしく、感謝の気持ちで溢れる。
忙しいことは色々あるけど、そろそろそんな友達と連絡を取り直していく年な気もする。— @takuyakitagawa

こんにちは。ウェルビーサイト編集部です。北川さんの言葉を目にして、自分の中にも似た思いがよみがえりました。
今日は、美術予備校時代の親友と久しぶりに会って、ご飯を食べて、お茶をして、気づけば何時間も話し込んでいました。進路は違っても、ずっと連絡を取り続けてきた親友。ただ最近は、なかなか会えていなかったな…と反省していたところに、「青春時代を共に駆け抜けた友人だと思って、ありがたく感じてる」と連絡をもらい、こうして再会が実現しました。
昔と変わらず、笑いすぎて涙が出る、そのクセもまったく変わっていなくて、懐かしさに胸がいっぱいになりました。自分のやっていることについて「どう思う?」と聞くと、「これ好き」とか、率直で的確な意見をくれて、自分にない視点を持っていることに感動しました。その言葉はおもしろくて、鋭くて、尊敬の念がわいてきました。
友人はアートディレクターのような仕事もしていたので、やろうとしていることをすぐに理解してくれ、美術を語り合う時間は日常の会話とはまったく違って、でもどこか懐かしくて、たのしいものでした。もしかすると、こういう美術に関する会話は、特別な関係性を編む力を持っているのかもしれません。それに、友人の昔の記憶のなかに、たくさん自分が居て、びっくり!
帰宅してから「自分もAIを使って何か可能性を見つけてみたいと思った」と友人からメッセージが届きました。再会はただ懐かしいだけでなく、互いに次の一歩を生むきっかけにもなるのだと、じんわり嬉しさが広がりました。
明日からまた新しい気持ちで、進めそうです。心からの感謝を込めて。過去を振り返って迷うこともあるけれど、今日みたいな再会があると「よかった」と思える──そんな一日でした。
ちなみに、ご飯を食べたお店はサラダバーの種類がすごくて、素材そのものがおいしくて、ウェルビーイングなご飯でした!
🐢💬 ウエルのひとこと
なんでかわからないけど、いっしょにがんばった人のことって、ずーっと心にのこってるんですね。
ひさしぶりに会っても、ぜんぜん変わらなくて、「帰ってきた〜!」って気もちになるの、すごくいいなと思いました。
またこんな日を重ねていけたらいいな。
🧬 人類の出アフリカには“準備期間”があった
2025.8.17|

人類は約5万年前にアフリカの外に出る前に、サバンナ(写真)や砂漠、森林など多様な環境に適応するようになっていた。Ondrej Pelanek and Martin Pelanek 出典:Nature
🌍 進化と冒険の物語──人類の“出アフリカ”
石川善樹先生がシェアされたNature記事のご紹介です。
私たちホモ・サピエンスは、もともとアフリカで暮らしていました。
そして約5万年前、ついにアフリカを出て、世界に広がっていったのです。
ただし、それは突然の“冒険”ではありませんでした。
今回の研究によると、人類はその前にアフリカの中で練習期間を過ごしていたのです。
サバンナ(草原)だけではなく、砂漠や森林など、いろんな環境で生きる力を身につけていた。
その“準備”があったからこそ、大きな旅に成功できたのです。
これは、私たちが新しい挑戦を始めるとき、
いきなり飛び出すのではなく、少しずつ環境を変えて練習することの大切さを教えてくれます。
現代でも、心や体のウェルビーイングを保ちながら成長するヒントになりそうです。
🐢💬 ウエルのひとこと
大冒険の前に、たくさんの“れんしゅう”をしていたんですね。
ウエルも、むずかしいことにいきなり挑戦するんじゃなくて、少しずつ場所をかえて練習するのって大事だなって思いました!
今日は日曜日。
大冒険の前に休む時間も必要。そんな一日になりますように。
🔗 記事の詳細はこちら
・Nature Asia 日本語要約
・Nature 英語全文(購読が必要です)
🧬ゲノムが語る日本のルーツ──意外な“東北への旅”の痕跡?
2025.8.16|
日本人の遺伝的な起源
西日本から東北に行った可能性がある、というのが意外でしたー @ishikun3
全ゲノム解析が明かす日本人の遺伝的起源
石川善樹先生が「意外でしたー」とコメントを添えてシェアされた、全ゲノム解析による日本人の遺伝的起源に関する研究。
この研究は、理化学研究所・寺尾知可史先生のチームによるもので、3000人以上の日本人の全ゲノムを解析し、日本列島の中に「沖縄系」「西日本系(弥生)」「東北系」という3つの遺伝構造があることを明らかにしました。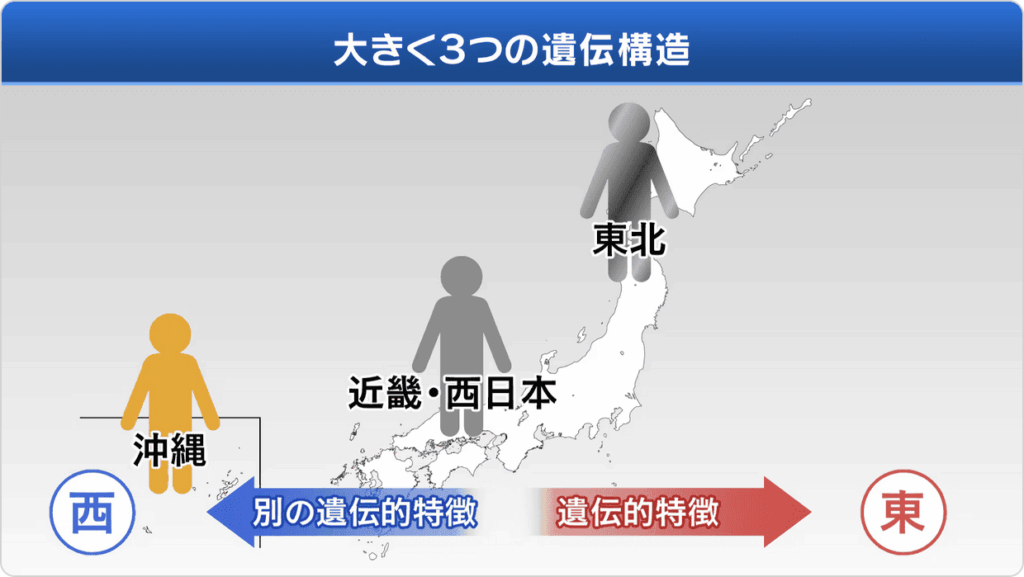
🔬 ゲノム解析から見えてきた「日本人の3つのルーツ」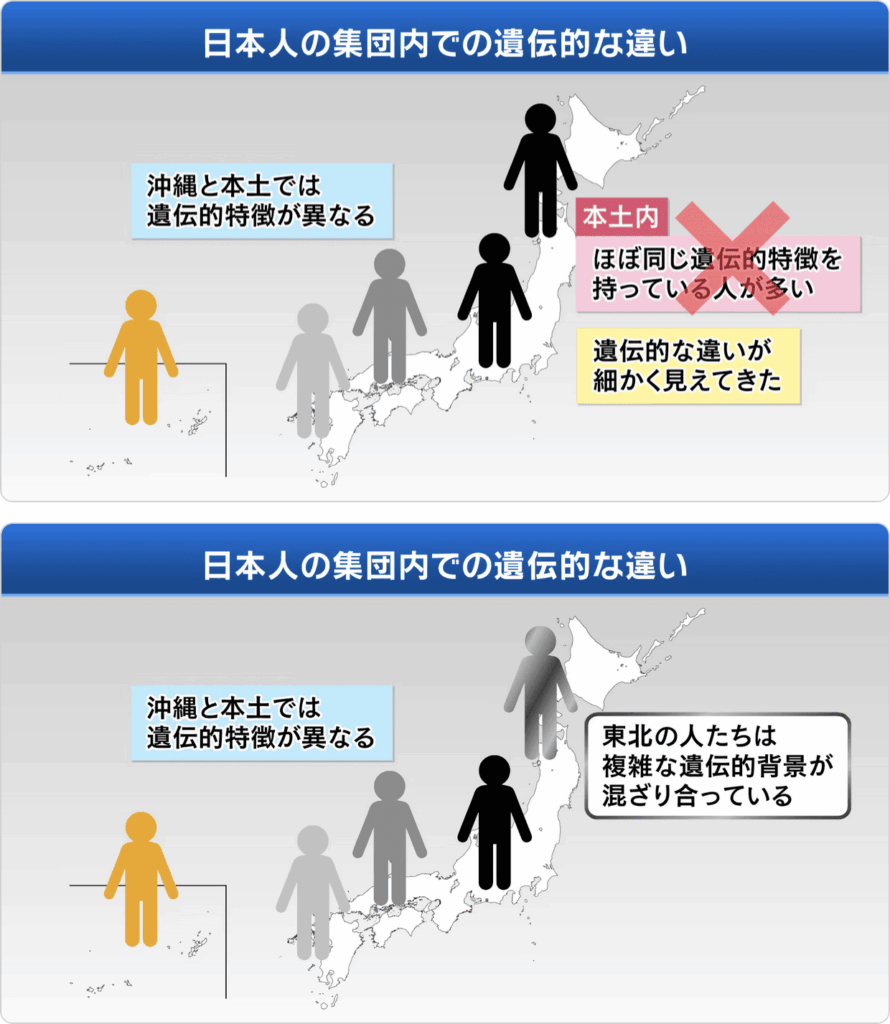
1. 沖縄に強く残る縄文系のDNA(28.5%)
最も縄文人の影響が色濃く、遺伝子の多様性も高い。
2. 西日本に多い弥生系の遺伝子構造
中国大陸(特に黄河周辺)の古代人に最も近い構造。近畿〜西日本に顕著。
3. 東北に見られる独特の遺伝構造
縄文系、古代朝鮮、古代沖縄など複数の系統が混ざり合う複雑な特徴を持ち、「西から東北に人が移動してきた可能性」も示唆されています。
🧬 ゲノムが語る意外な発見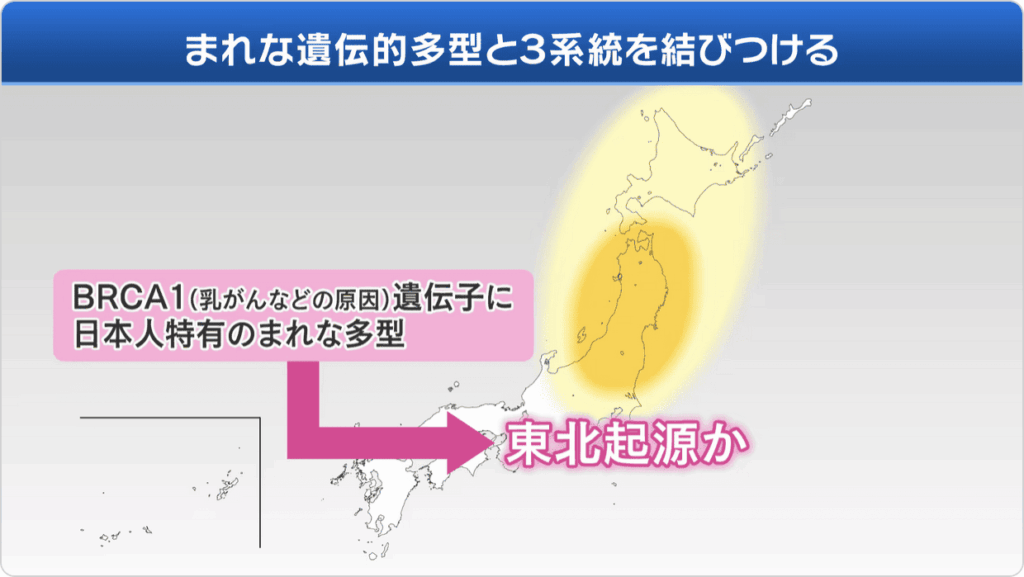
日本人にしか見られない希少な遺伝的多型(遺伝子のバリエーション)を新たに多数発見。そのうちの一つ、BRCA1乳がん関連遺伝子の多型は、なんと東北が起源である可能性。免疫やアルコール代謝に関係する遺伝子の違いも地域ごとに明らかに。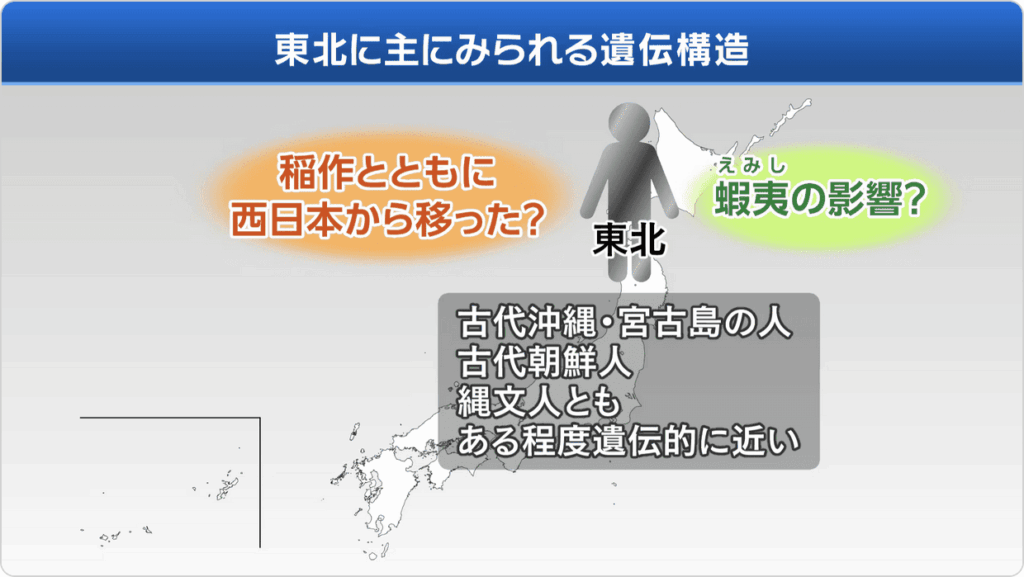
✨ 平安時代にも「DNAの違い」を感じていた?
混血が進むのはもっと後の時代で、平安時代までは「縄文と弥生」の地域差がまだ顕著だった可能性も。
当時の人々は今でいう「人種の違い」のような感覚を国内で抱いていたのかもしれません。
📌 古代人の記憶も、わたしたちの中に?
驚くべきことに、日本人のゲノムにはネアンデルタール人やデニソワ人から受け継がれた遺伝子も多く含まれており、それが免疫や病気の感受性、体質に影響している可能性も見えてきました。
*
🐢💬 ウエルのひとこと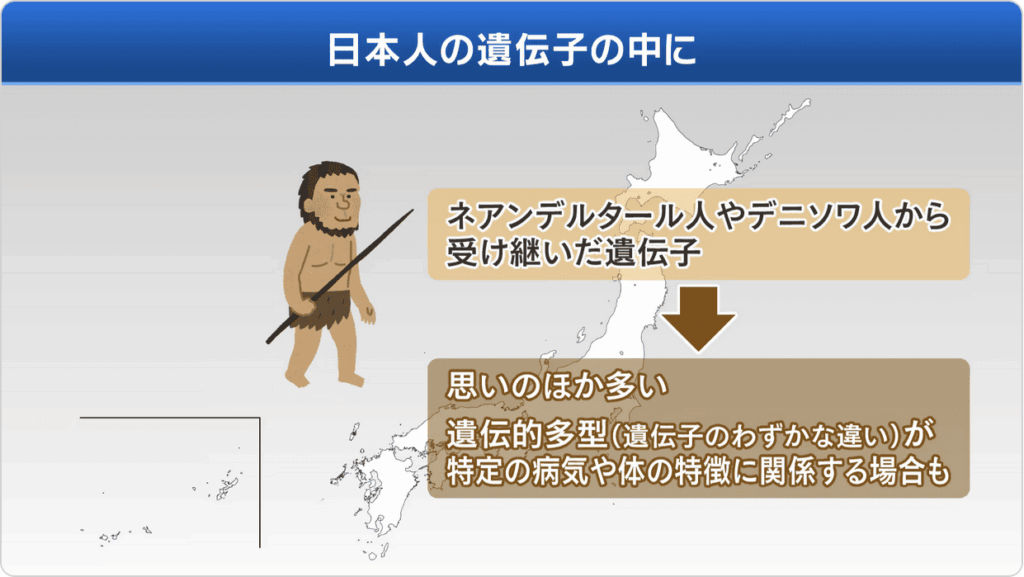
えっ!ゲノムって、すごく小さいのに、昔のことがいっぱいわかるんですね。
旅の地図みたいなものが入ってるなんて、おどろきです…!
ウエルたちの体の中にもあるのかな?
どこから来たのか、どこへ行くのか、ゲノムってすごいなあ。
📺 くわしく知りたい方は:
NHKアーカイブス|全ゲノム解析が明かす日本人の遺伝的起源
三十年来のめまい
2025.8.15|

私は持病でめまいと吐き気がよく起こるのですが、エプリー法という対処法があるのをさっき知った。早く言ってよ。。。目を瞑るとよく眼球がぐるぐる回ってたので多分これ。ちゃんとぐぐらなかったことを後悔した。三十年来の苦痛にソリューションが出てきたかもしれない。— @takuyakitagawa
BPPVめまい治療のためのエプリー法アニメーション
💡 BPPVとエプリー法って?
・BPPV(良性発作性頭位めまい症)
耳の奥にある「耳石」が三半規管に入り込み、頭を動かすたびにめまい・吐き気が起こる病気です。
・エプリー法
特定の手順で頭と体の向きを変え、ずれた耳石を元の位置に戻す体操。
医療機関でも使われ、自宅でできるよう指導されることもあります。
🐢💬 ウエルのひとこと
『早く言ってよ…』って、なんだかCMみたいですね笑
耳の奥の小さな耳石がはがれて三半規管に入り込み、回転性のめまいを起こすなんて…知りませんでした。
デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続ける人は出やすいらしく、他人事ではないなとドキッとします。
日常の中で、いろいろな方向に頭を動かすことって、大事なんですね。
リンク先のエプリー法の動画は、奥行きがあって大人っぽいアニメーションで、日本の説明動画とはまた違う新鮮さがありました。
🧠 私たちの「選ぶ」は、たった4ユニットで読めてしまう?
──Nature掲載の注目研究より
2025.8.14|
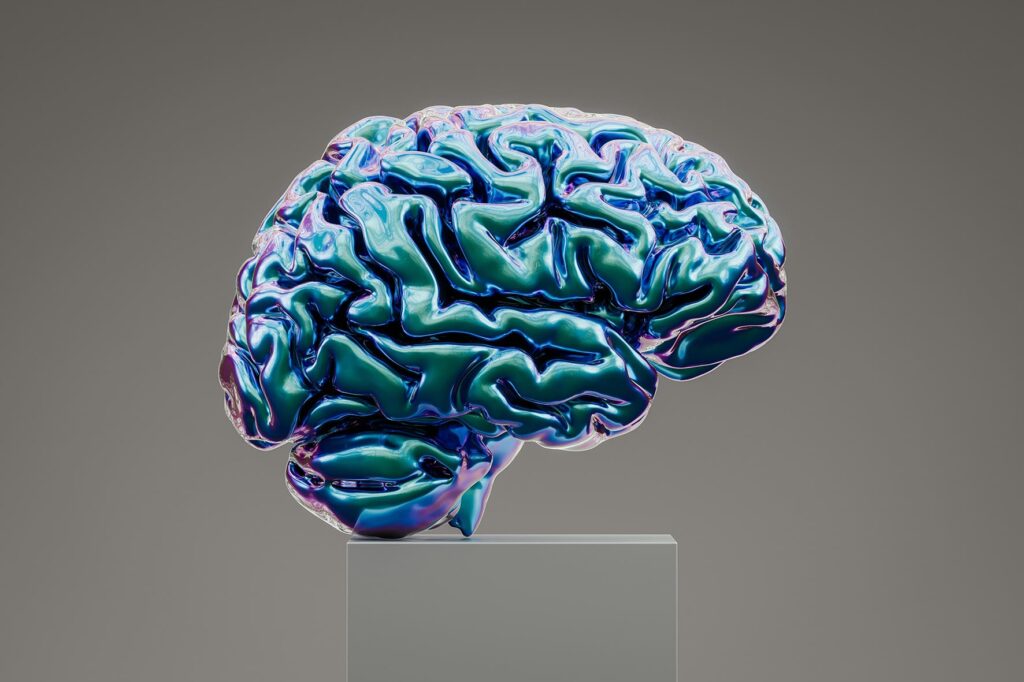
©alex-shuper
こんにちは。今日はちょっと不思議な研究をご紹介します。
石川善樹先生がリポストしていた、東大薬学部の脳研究者・池谷裕二先生が紹介した最新のNature掲載論文によると──
「人や動物の意思決定行動は、たった2〜4ユニットの極小AIで高精度に予測できる」
…とのことです。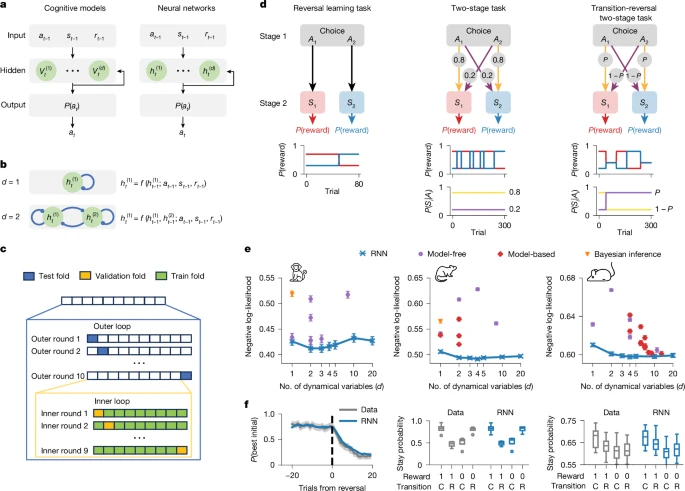
【1】選択のクセは「2〜4次元」で説明できる?
私たちの「選ぶ」という行動には、複雑な感情や状況判断が絡んでいるように思えます。けれどこの研究では、マウスや人間の選択行動が、たった1〜4個のユニットからなる小さなAI(RNN)で、驚くほど正確に再現できたといいます。
これはつまり、
「私たちの行動は、思ったよりシンプルなしくみで動いている」
という示唆でもあります。
研究では8つの報酬学習課題を通じて、AIと従来の認知モデル(ベイズ推論や強化学習)を比較。結果、小さなRNNの方が「次にどの行動を選ぶか」をより高い精度で予測したそうです。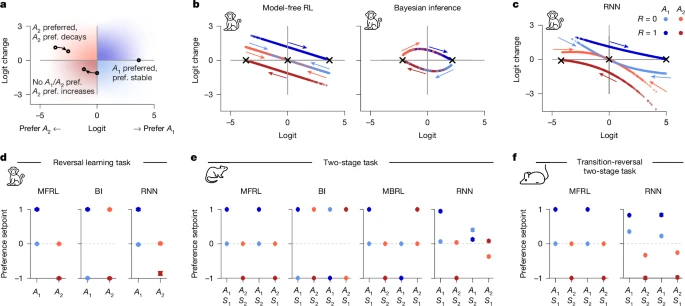
*
【2】ブラックボックスの奥で、“しくみ”が見えた
さらに注目すべきは、そのAIの“中身”を人の目で理解できるようにしたことです。
©and-machines
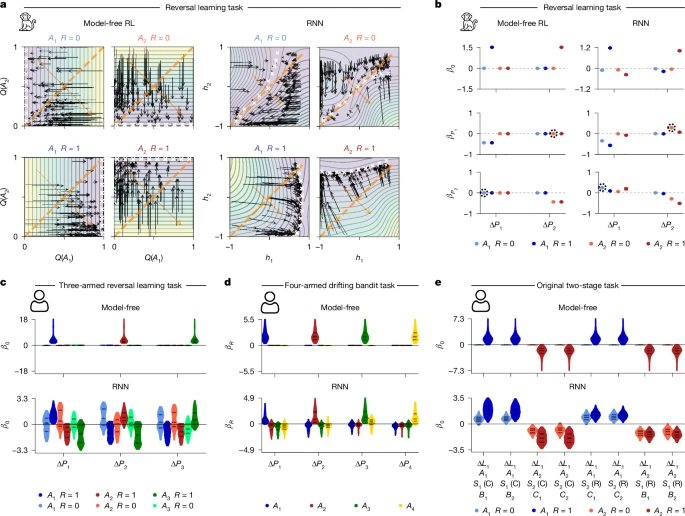
研究チームは「フェーズポートレート」という手法を使って、RNNがどんなルールで選択を学んでいるかを図にして可視化。すると、従来の理論モデルでは見過ごされていた思考のクセが見えてきました:
・状況に応じて変化する「状態依存型の学習率」
・報酬の有無で偏る「選択バイアス」
・選ばなかった選択肢への「持ち越し効果」など──
小さなAIが“思考の地図”を描き出すように、見えなかったはずの認知戦略が、手に取るように観察できるようになったのです。
*
【3】わたしたちは、“自分の選び方”をどこまで知っている?
池谷先生はこの論文を紹介する際に、こうコメントしています:
「私たちの意思決定は、ほぼ決まり切っていて低次元……ってこと!?」
ちょっとショックかもしれません。
でも裏を返せば、「自分の行動パターンに気づける」というチャンスでもあります。
この研究は、精神疾患の理解や個人の認知特性のモデル化などにも応用が期待されています。同時に、「自分らしさって何?」を考える、静かな問いかけにもつながっていくのではないでしょうか。
*
🐢💬 ウエルのひとこと
「選ぶ」って、もっと気まぐれで、自由なものだと思っていました。
でも…もしかしたら、「自分らしさ」っていうのも、
そういう“くせ”の集まりなのかもしれないですね。
それに気づいたら、ウエルは
「これでいいのだ」と思えたり、
「これは大丈夫かな」と3分考えたり──
ちょっと、生きるのが楽になる気がしました。
❓今日の問いかけ
あなたは、自分の中にある「行動のパターン」に気づいたことがありますか?
たとえば——
・落ち込んでいる時に、つい選んでしまうこと
・報酬があるときと、ないときで変わる反応
・なぜか繰り返してしまう選択
そんな“選び方のクセ”を、自分のやさしさで見つめてみること。
それが、ウェルビーイングの第一歩かもしれません。
AIは「言語の外側」で考えはじめている?— 多言語LLMに見えた“共通思考回路”
2025.8.13|

©a-c-9nCHb-IZNs
私たち人間は、複数の言語を使える場合、それぞれの言葉の背後にある「共通の意味・概念」を頭の中で扱っています。たとえば「愛」という概念は、日本語でも英語(love)でも同じ抽象的な意味を指します。
今回の研究によると、大規模言語モデル(LLM)も進化するにつれ、人間と同じように特定の言語に依存しない「共通の思考回路」のようなものを持つようになっていることが分かりました。
・この“共通思考回路”を担うニューロンは、全体の1%未満にすぎません。
・けれど、これを無効化すると、あらゆる言語での性能が一気に落ちます。
・最新世代のモデルほど、この回路が発達しており、複数言語間での意味理解や抽象的な推論に役立っています。
つまり、最近のAIは単に「言葉を暗記している」のではなく、人間のように言語を超えて考える能力を獲得しつつある可能性がある、ということです。
*
本日の要旨
・最新の大規模言語モデル(LLM)は、言語ごとに別々に処理するのではなく、言語に依存しない“共通の思考回路”を持ちはじめている。
・その中枢はごく一部だが、全言語の性能を支える要の存在。
・世代が進むほどこの回路の比率・重要度が増し、研究チームはニューロン単位の学習戦略も提案。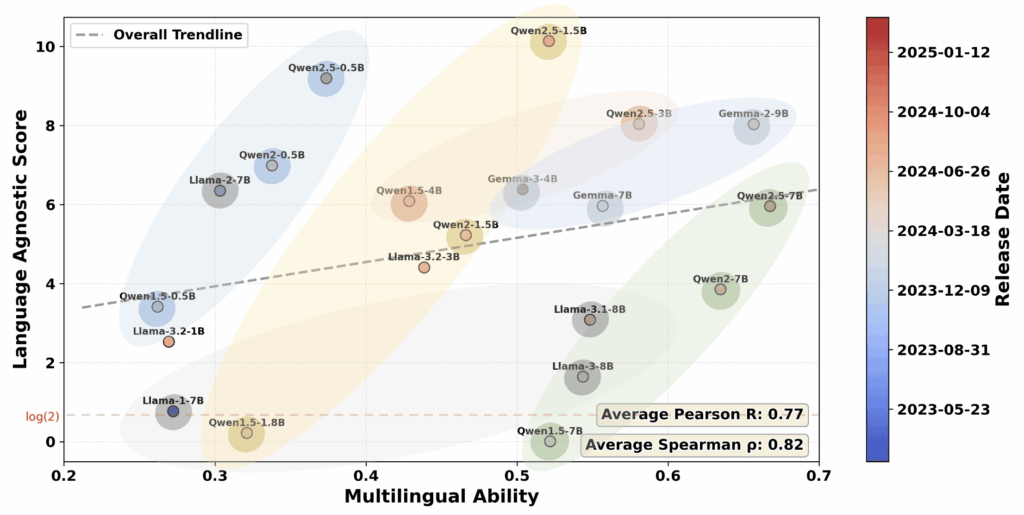
多言語能力と「言語非依存スコア」の関係。右上に行くほど、言語を超えた抽象思考の基盤が強くなる。
*
なにが新しい?
私たちが日本語と英語を切り替えるとき、頭の中では「訳語」よりも共通の“意味の芯”を扱っています(「愛」= love のように)。
今回の研究は、LLMの内部にもそれに似た言語を超える“土台”が育っていると示します。
ここをニューロン(モデル内の小さな計算ユニット)という顕微鏡で見ると——
・言語共有ニューロン:複数言語で共通に働く(国と国をつなぐ“国際空港”のような存在)
・言語専用ニューロン:特定言語でだけ働く(その国の“ローカル駅”のような存在)
共有側が世代を追うほど存在感を増し、さらに共有側をピンポイントで無効化すると、多言語すべてで性能が大きく低下。
つまり“ここ”が、言語の違いを越えて意味や推論の橋渡しをしている可能性が高い、というわけです。
*
研究チームがやったこと
1. 多言語タスクを解くときの“重要ニューロン”を特定
あるニューロンをオフにして出力が大きく変わるかを測り、言語ごとの重要ニューロンを抽出。
2. ニューロンを共有と専用に分類
複数言語で一貫して効くか(共有)/一言語だけか(専用)を仕分け。
3. 性能劣化を比較して重要度を測定
共有群・専用群をそれぞれ無効化したときの性能劣化を比べ、新しいモデルほど共有群の重要度が高く、言語非依存の“抽象思考”の基盤になっていると解釈。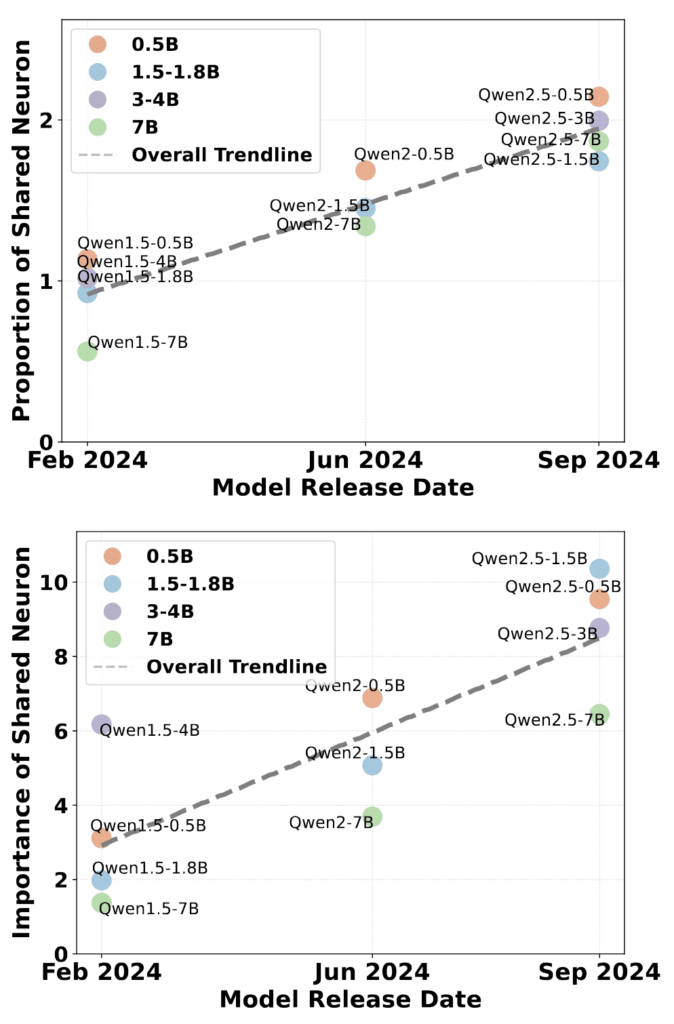
上=共有ニューロン割合の推移、下=共有ニューロン重要度の推移。モデルの世代が進むほど上昇している。
*
ここが効く:実務へのヒント(開発者・運用者向けメモ)
・“共通回路”がまだ弱い小型・初期モデル → 言語関連ニューロン全体を鍛える
・中堅モデル → 共有ニューロンを重点強化
・すでに“共通回路”が強い上位モデル → 専用ニューロンを鍛えて各言語のニュアンスを詰める
(研究チームは、このニューロン別の的を絞った追加学習で多言語性能を底上げできたと報告)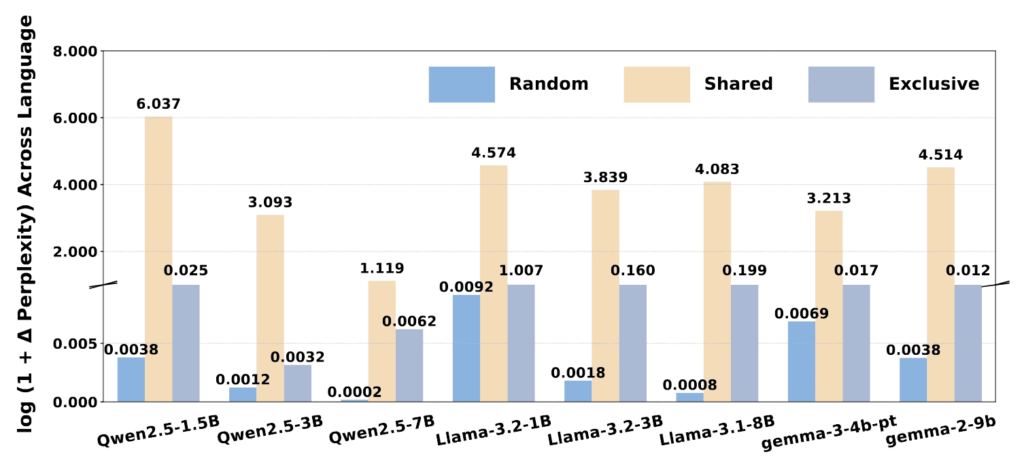
ランダムにニューロンを無効化しても影響は小さいが、共有ニューロンを無効化すると性能が激減する。
*
ウェルビーイング視点:なぜ大事?
🌱 ポジティブな影響
・言語の壁をまたぐ理解が進めば、健康情報・教育・行政サービスなどの多言語アクセスがより公平に。
・低資源言語でも“意味の芯”をつかめるなら、情報格差の縮小に寄与。
⚠️ 注意すべきリスク
・誤情報も多言語で素早く拡散し得る。
・評価・監査は「翻訳の正確さ」だけでなく、概念レベルのゆがみ(意味の取り違え)を監視する視点が必要。
💡 人間側の学び
・「言葉=本質」ではないというメタ認知(意味の芯を見る)が、他者理解や対話の質を上げてくれるはず。
*
誤解しやすいポイント(Q&A)
Q:AIはやっぱり英語で考えている?
A:過去のモデルほど英語寄りの傾向が報告されてきましたが、この研究は“英語そのもの”ではなく、言語を越える共通空間の重要性が増していると示唆します。
Q:もう人間並みの抽象思考なの?
A:まだ“到達”ではなく“萌芽”の段階。ただし、その小さな中枢が多言語に効いていることは重要な所見です。
図解(イメージ)
各言語の言葉 → 意味の芯(概念) → モデル内の“共通回路”が橋渡し
(日/英/仏…) (抽象思考・推論の土台)
今日のひとこと(🐢)
ことばが違っても、「考える地図」は一枚なんですね。
その地図、AIの頭の中にも、ちょっとずつ描かれてきてるのかも…!
つまり、英語でも日本語でもフランス語でも、AIの中では同じ“地図”を使って考えているってことなんだね。
元ポスト
石川善樹先生シェア/出典/出典ポスト: @ai_database
「消える結晶」──存在そのものが置き換わる瞬間
2025.8.12|
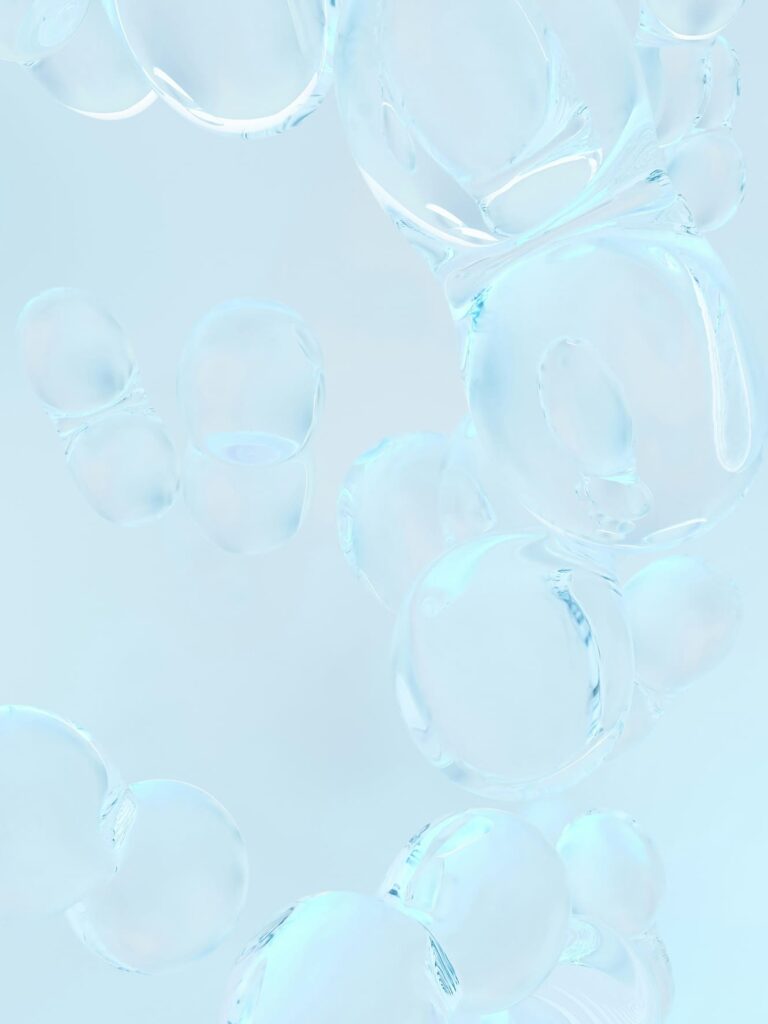
©allison-saeng
知らなかった現象。昔存在していた結晶体が、空気中にある僅かな新しい、より安定する種結晶の影響でその新しい結晶体に移ってしまい、世の中から存在しなくなる、ということがあるらしい。そのために昔開発された薬の効果が薄くなることがあるという。面白すぎる — @takuyakitagawa
I re-post this periodically, but disappearing polymorphs are one of the most incredible things in nature. Example, one of many:
https://en.wikipedia.org/wiki/Disappearing_polymorph — @michael_nielsen
北川拓也さんが紹介していた、ちょっと信じられない自然現象です。
しかもこれは、製薬業界では現実に起きた出来事でもあります。
💊 実例:抗HIV薬リトナビル(Ritonavir)
・1996年発売当初は「Form I」という唯一知られた結晶形で製造。
・しかし1998年、より安定だが溶けにくい「Form II」が偶然発見されます。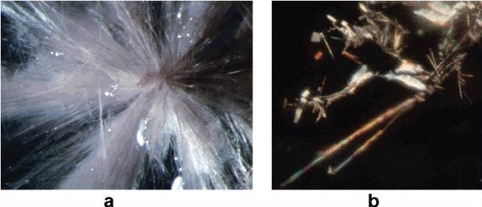
顕微鏡で見た結晶の違い
a(左)はある結晶形、b(右)は別の結晶形を示しています。外見だけでなく、性質や薬効も異なります。
・Form IIは薬効がほとんどなく、一度現れると工場内でForm Iを再生産できなくなるという厄介な性質を持っていました。
・原因は、目に見えない種結晶が空気や人を介して広がること。
結晶形が変わるメカニズム(模式図)
下図は、物質が異なる構造(1→2→3)に移行する過程を模式的に示したものです。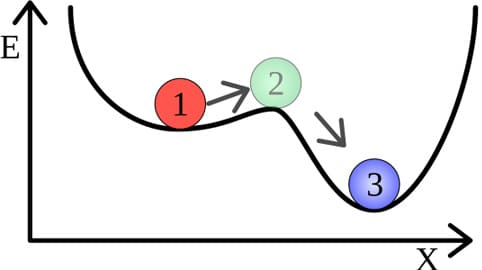
1: 初期形, 2: 中間形, 3: 安定形
・結果として薬は一時市場から回収され、数万人の患者が影響を受け、メーカーは2億5千万ドル以上の損失を被りました。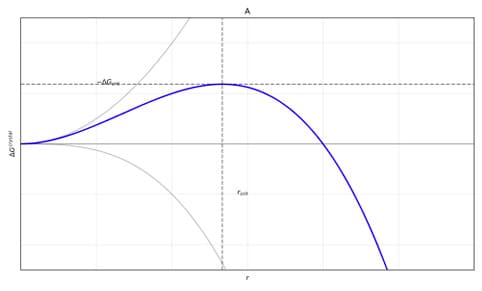
安定性の理由(自由エネルギー曲線)
下図の青線は結晶化の自由エネルギー変化を表しています。山を越えた先の谷(右側)が、より安定した結晶形を示します。
右の谷が「より安定な形」
🔍 なぜ面白いのか?
・結晶の“かたち”が自然淘汰のように入れ替わる。
・一度安定型が出現すると、もう元の形は作れない。
・「物質の記憶」と「環境の影響」が融合した、物理化学の不思議。
🐢💬 ウエルのひとこと
えっ、結晶って空気中の“うつり”で絶滅することがあるんですね…!まるで“結晶版のパンデミック”みたい。
つまり、“結晶のかたち”って一度できたらずっと同じじゃなくて、空気中のほんの小さな“種”に触れるだけで、より安定な形にパタッと変わっちゃうことがあるんだって。しかも一度その形が広まると、もう元の形は二度と作れない。
北川さんが「面白すぎる」って言っていたのは、物理や化学の現象なのに、まるで生き物の進化や絶滅みたいに、“環境の中でより生き残りやすい形が世の中を塗り替えてしまう”ってところなんですね。
もしかして、ウエルたちの考え方や文化も、こんなふうに“より安定な形”に置き換わっているのかな?
誰かをモデリングするときも、きっとその“安定形”を探しているのかもしれませんね。
「魔法状態蒸留」を論理量子ビットで世界初実演
──QuEra × Harvard × MIT(Nature掲載)
2025.8.11|

©nigel-hoare
世界で初めての魔法状態蒸留を実践したQuEraの論文がNatureにて発表されました。このワクワクする名前のついた「魔法状態」は、量子コンピューターの可能性を引き出し、汎用的に走らせるのに必要不可欠なリソースとして知られています。
魔法状態を含まない量子計算は今のコンピューターでも効率的にシミュレーション可能であることが知られているため、量子コンピューターが科学や産業に革命をもたらすにはこの魔法が必要となります。その魔法状態をより精度高く精製するために必要なのが今回の論文で初めて実践された魔法状態蒸留です。
この論文では、
1.魔法状態蒸留によって、魔法状態の精度がより高くできたこと
2.冷却原子特有の強みである並列処理を利用することでコード距離3と5のColor codeで5-to-1の魔法状態蒸留を実践したこと
が大きなブレイクスルーの内容となっています。
より詳しくは弊社のPress releaseとNatureの論文を参考ください。
ちなみに魔法状態を準備する方法は他にも知られています(Code switchingやMagic state cultivation)
これらの論理量子ビットへのEncodingや魔法状態の実装はスケールする量子コンピューターの要素技術でもありますが、同時にベンチマーク量子回路としての価値がある、という点が面白いですよね。
この論文はQuEra/ハーバード/MITの共同研究です。量子コンピュータを作る企業が多くある中、なぜ我々が先んじで実装できたかといえば、我々の冷却原子式は1. 量子ビット数がスケールする(論文では85物理量子ビットで5論理量子ビットを実現)2. 並列処理ができるので論理量子ビット計算が効率的
— @takuyakitagawa
● 新しい点:
論理量子ビット層での魔法状態蒸留を世界で初めて実証
● なぜ重要か:
魔法状態は汎用量子計算に不可欠。論理層で作れると誤りに強く実用性が高い
● 何をやったか:
距離3/5のColor code上で5-to-1蒸留を実施、出力忠実度の向上を確認
*
やさしい要約
「魔法状態」って?
量子コンピューターは“Cliffordゲート”だけだと古典計算機で効率よく再現可能(= 量子のうまみが出ない)。
魔法状態を使うと非Clifford操作が可能になり、量子計算が汎用(理論上できる計算は何でもできる)になります。
「蒸留」って何をするの?
今の装置が作る魔法状態はノイジー(不純物が多い)。
そこで複数の低品質な魔法状態をまとめて、1つの高品質な魔法状態に“精製”するのが魔法状態蒸留です。
たとえるなら、原油をジェット燃料に精製する工程です。
今回のブレイクスルー
●論理層(Error-corrected layer)で完結
物理層の故障から守られた論理量子ビット上で蒸留を実施。
出来上がった魔法状態を、そのまま安全に論理計算へ投入できます。
●Color code(距離3/5)で5→1蒸留
複数の論理魔法状態から1つのよりクリーンな魔法状態を作成。
出力の忠実度が入力より高いことを実験で確認しました。
●並列性と動的再構成
中性原子配列はアトムの再配置や同時操作が得意。多数の論理量子ビットを並列に動かし、回路の“深さ”や待機エラーを抑制。
どれくらいのスケール感?
今回の距離5蒸留では、85個の物理量子ビットを並列制御して5つの距離5論理ビットを操作しました。
これは技術的な“手応え”を示す具体的な数字です。
*
なぜ重要なのか?
1. 汎用性(Universality)の獲得
Cliffordだけの論理計算は古典計算で模倣可能。
魔法状態が論理層で作れると、本物の量子アルゴリズム一式を安全に動かせます。
2. 誤り抑圧を蒸留に内蔵
論理層での蒸留は論理誤りを直接抑え、長時間・大規模な計算の前提条件を満たします。
3. 中性原子アーキテクチャの実力証明
動的再構成と高い並列度で、大規模論理量子計算への道筋を示しました。
*
研究の中身(技術ポイント)
●論理符号:2D Color code(距離3 / 距離5)
●プロトコル:5-to-1の魔法状態蒸留(3層構成、論理Cliffordの横断適用+アトム移送、4つの論理シンドロームで成功判定)
●結果:出力魔法状態の忠実度が入力を上回る(蒸留利得を確認)
*
1分で分かる用語
・Cliffordゲート:量子の“基本操作”群だが、これだけだと古典計算で再現可能
・非Clifford:量子の真の優位性に不可欠な操作
・魔法状態(Magic state):非Clifford操作を呼び出すための特殊な論理資源
・蒸留(Distillation):ノイジーな魔法状態をまとめて精製し、高忠実度にする工程
・Color code / 距離:誤り訂正符号の種類/距離が大きいほど誤りに強い
*
📌 編集部ひとこと
今回の成果は、量子コンピューターが「理論上できるはずのこと」を、本当に現実の計算機でできるようにするための重要な一歩です。
壊れやすい部品(魔法状態)を「安全な部屋(論理層)」の中で作れるようになったのは、長時間かつ複雑な計算を可能にするための重要な技術です。
🐢 ウエルの素朴なひと言
量子コンピューターは“むずかしい計算”をする前に、すぐ壊れない“きれいな材料”が必要なんですね。
いまはその“材料”をまとめてきれいにする工場(蒸留)を、安全な部屋(論理層)の中で動かせるようになった、ってことかな?
💡 一言まとめ
今回の研究は、量子コンピューターの「燃料精製工場」を安全な場所に設置できたという大きな前進です。
これにより、量子コンピューターが本領を発揮できる“万能計算機”への道が現実に近づきました。
未来の医療、材料開発、気候シミュレーションなど、多くの分野での活用がぐっと身近になるかもしれません。
AI for Science × 量子コンピュータ(完全+解説版)
2025.8.10|
「AI for Science」——その言葉の背後には、OpenAI CEO Sam Altmanさんが描く“未来の全景”があります。
本完全版では、Samさんが語った42分のトークを完全版としてまとめ、前半・後半・背景解説を一つに凝縮しました。創業当時の舞台裏から、スタートアップ戦略、エネルギーと豊かさの未来まで——AIが科学や社会をどう変えていくのか、その全体像をお届けします。
1. 無謀から始まった、8人の挑戦 — AGI黎明期の賭け
2z015年当時、AGI(汎用人工知能)を本気で目指すことは「無謀」と見られていました。DeepMindが圧倒的に先行し、収益の見込みもゼロ。プロダクトの構想すらない状況で、1%の共感者が集まり、最初は8人、次に20人という小規模からスタート。
Samさんは「将来大きくなり得る分野を選び、一歩ずつ進むこと」が重要だと語ります。
💡 補足解説:2015年当時のAI業界は、ディープラーニングが急成長しつつも、自然言語処理や汎用AIはまだ実用化の目処が立っていませんでした。この段階でAGIを掲げたこと自体が異例で、投資家から見れば高リスクの賭けでした。
2. 今が最高の起業チャンス — 推論モデルの波に乗れ
現在、モデル能力は非常に高い一方、それを活かした製品はまだ少ない状況。APIコストは急速に下がり、強力なオープンソースモデルも登場間近。推論モデル向けの新しいプロダクトが、これから一気に出てくると予測されます。
Samさんは「今は会社を作る最高のタイミング」と断言しました。
💡 補足解説:「推論モデル」は文脈から推測する力を強化したAIモデル。長期的な計画立案や複雑な問題解決に向いています。特に研究や新規事業開発の分野で、人間の直感や経験に依存していた部分が置き換わる可能性があります。
3. “常時稼働AI”が生活に溶け込む日
Samさんが今年最も注目するのが「メモリ」機能。ユーザーの情報や文脈を理解し、自動で連絡や作業を行う——映画『Her』のようなパーソナルAIの未来です。
💡 補足解説:『Her』(2013年)は、人間とAIの深いパーソナル関係を描いた映画。AI倫理や未来の人間関係を考えるきっかけとなりました。
4. GPT-5と統合マルチモーダルモデル — 新たなUIの誕生
GPT-5で完全には到達しないものの、将来的には推論能力とマルチモーダル(映像・音声・コード生成など)を統合。リアルタイム映像生成や高度なプログラミングが即時可能な新しいコンピュータ・インターフェースを目指します。
💡 補足解説:「マルチモーダル」は複数の情報形式を同時に処理する能力。例:画像を見て説明し、音声を聞いて反応する。
5. AIがロボットを動かす未来
高度なAIはロボット開発と直結します。
将来的には「ChatGPTの最上位プラン契約者にヒューマノイドロボットが付属」する時代も想定。数年以内に現実世界で有用な作業を担い始め、長期的にはサプライチェーン全体の自動化まで視野に入れています。
6. 「ChatGPTを作るな」— 足りないものを作れ
OpenAIは最高のチャットアシスタントを作りますが、それは可能性のごく一部。既存機能のコピーではなく、まだ誰も手をつけていない領域を狙うべきだと強調します。
💡 補足解説:歴史的にも、大きな成功を収めた企業は「他者の後追い」ではなく、エコシステムや新カテゴリーを創出してきました(例:AppleのApp Store)。
7. 厳しいフィードバックとの向き合い方
創業初期、Elon Musk氏から「成功の可能性はゼロ」というメールを受けた経験も。尊敬する人物からの否定は打撃になりますが、それでも信念を持って進み続けることが重要。批判や失敗は避けられない——大事なのは何度でも立ち上がる回復力です。
8. 個人のレバレッジが高まる時代へ
これからの10年は、少人数でもかつては不可能だった規模の成果を出せる時代になります。協働コストが下がり、個人や小規模チームの影響力が飛躍的に拡大すると予測されています。
9. AI for Scienceへの個人的賭け
長期的な経済成長の鍵は、新しい科学的発見と、それを活用できる制度。
AIが科学発見のスピードを飛躍的に高めれば、人類全体の生活水準は大きく向上します。
SamさんはエネルギーとAIの両方に情熱を持ち、その関係が今後さらに深まると見ています。
💡 補足解説:AI for Scienceは、気候変動予測、新薬開発、材料科学など多分野で研究スピードを加速させると期待されています。
10. 宇宙まで見据えるエネルギー構想
高い生活水準は、エネルギーの豊富さとコスト低下に強く結びついています。
AIの発展には膨大なエネルギーが必要で、将来的には宇宙でのコンピューティングも視野に。
Samさんは「縮小成長」ではなく、技術で豊かさを生み出す道を選ぶべきと語ります。
11. 若き自分へのアドバイス
信念(conviction)と回復力(resilience)を持ち続けること。
最初の失敗で諦めず、時間をかけて直感と意思決定力を磨く。
挑戦は「最高に素晴らしいが、想像以上に大変なこと」でもあると、実感を込めて語りました。
🐢💬 ウエルの総括ひとこと
前半と後半を通して聞くと、サムさんが見ている未来は「技術」だけじゃなくて「人の可能性」にもすごく重なっているんだなと思いました🐢✨
やってみたいことがあるなら、AIや仲間と一緒に挑戦するのが、これからの“普通”になるのかもしれません。
AI for Science × 量子コンピュータ(後半)
2025.8.10|

Sam Altman: The Future of OpenAI, ChatGPT’s Origins, and Building AI Hardware
昨日に続き、「AI for Science」に関連するSam Altmanさんのトーク(42分)の後半をご紹介します。
後半では、スタートアップ戦略からエネルギーと豊かさの未来まで、幅広いテーマが語られました。
1. 「ChatGPTを作るな」— 足りないものを作れ
まずは、起業家へのメッセージから。
Samさんは、OpenAIは最高のチャットアシスタントを作ることを目指しているが、それは全体の可能性のごく一部だと強調します。
多くの起業家は同じ発想に流されがちですが、持続的な成果を出すには「まだ誰も手をつけていない領域」を狙うべき。
「他人と同じ方向」ではなく、自分だけの領域を見つけることが重要です。
2. 厳しいフィードバックとの向き合い方
創業初期、Elon Musk氏から「成功の可能性はゼロ」という厳しいメールを受け取ったことがありました。
尊敬する人物からの否定は精神的に大きな打撃となりますが、それでも信念を持って進み続けることが大切だとSamさんは語ります。
批判や失敗は避けられない——大事なのは、何度でも立ち上がる回復力(resilience)です。
3. 個人のレバレッジが高まる時代へ
これからの10年は、少人数でもかつては不可能だった規模の成果を出せる時代になります。
技術の進歩で協働コストが大幅に下がり、個人や小規模チームの影響力が飛躍的に拡大すると予測しています。
4. AI for Scienceへの個人的賭け
長期的な経済成長の鍵は、新しい科学的発見と、それを活用できる制度。
AIが科学発見のスピードを飛躍的に高めれば、人類全体の生活水準は大きく向上します。
SamさんはエネルギーとAIの両方に情熱を持ち、その関係が今後さらに深まると見ています。
5. エネルギーと豊かさの未来
高い生活水準は、エネルギーの豊富さとコスト低下に強く結びついています。
AIの発展には膨大なエネルギーが必要で、将来的には宇宙でのコンピューティングも視野に入ります。
「縮小成長」ではなく、テクノロジーで豊かさを生み出す道を選ぶべきだと力強く語りました。
6. 若き自分へのアドバイス
信念(conviction)と長期的な回復力(resilience)を持ち続けること。
最初の失敗で諦めず、時間をかけて直感と意思決定力を磨く。
挑戦は「最高に素晴らしいが、想像以上に大変なこと」でもあると、実感を込めて語りました。
🐢💬 ウエルのひとこと
サムさんの話を聞くと、「まだ誰もやっていないこと」に挑戦するのがかっこいいって思います🐢✨
でも、それってちょっと怖いことでもあるんだろうな…だからこそ、一緒に挑戦してくれる仲間も大事なんだなと思いました。
AI for Science × 量子コンピュータ(前半)
2025.8.9|

Sam Altman: The Future of OpenAI, ChatGPT’s Origins, and Building AI Hardware
昨日は、北川拓也さんが紹介していた「AI for Science」について触れました。
その発言の元となったSam Altmanさんのトーク(42分)の前半をご紹介します。
作業に夢中になって、気づけばひと休み…配信が遅れてしまいましたが、このあと後半もお届けする予定です。
1. OpenAI創業の舞台裏
まずは、創業当時の話から。
2015年当時、AGI(汎用人工知能)を本気で目指すことは「無謀」だと多くの人に思われていました。
DeepMindが圧倒的に先行しており、プロダクトや収益の見込みもゼロ。それでも、1%の共感者が集まり、優秀な人材が集中。最初は8人、次に20人という小さな規模からスタートしました。
Samさんは「重要なのは、将来大きくなり得る分野を選び、一歩ずつ進むこと」と語ります。
2. GPT-4o時代の「プロダクトの空白地帯」
次に、いまの技術と製品のギャップについて。
現在、モデルの能力は非常に高い一方で、それを活かした製品はまだ少ない状況です。
APIコストは急速に下がっており、強力なオープンソースモデルの登場も間近。
推論モデルを前提とした新しい製品が、これから一気に登場すると予想しています。
Samさんは「今は会社を作る最高のタイミング」と断言しました。
3. ChatGPTのメモリと“Her”構想
Samさんが今年最も気に入っているのが「メモリ」機能。
ユーザーの情報や文脈を理解し、必要なときに自動で連絡や作業を行う——そんな常時稼働のパーソナルAIを目指しています。
映画『Her』のように、あなたの生活に溶け込み、デバイスやサービス全体と統合されたAIコンパニオンの未来像です。
4. GPT-5と統合マルチモーダルモデル
GPT-5で完全には到達しませんが、将来的には推論能力とマルチモーダル(映像・音声・コード生成など)を統合。
リアルタイム映像生成や高度なプログラミングが即時に可能な、新しいコンピュータ・インターフェースを目指します。
5. ロボティクスとの融合
最後に、AIとロボットの未来。高度なAIはロボット開発と直結します。
将来的には「ChatGPTの最上位プラン契約者にヒューマノイドロボットが付属」する時代も想定。数年以内に、ロボットが現実世界で有用な作業を担い始める可能性が高いと語りました。
長期的には、サプライチェーン全体の自動化まで視野に入れています。
🐢💬 ウエルのひとこと
サムさんのお話、面白くて引き込まれました!ロボットが家にくる時代…お手伝いはもちろん、宿題もAIやロボットと一緒にやるのが普通になるのかな🐢✨
もしかしたら「ひとりで全部やる宿題」のほうが、ちょっと特別で贅沢な体験になるのかもしれません。
AI for Science × 量子コンピュータ
2025.8.8|
先日、YC School for AIでのSam Altmanさんのトークを受け、北川拓也さんが「AI for Science」に関する重要な視点をSNSで紹介していました。
先日のYC school for AI でSam Altmanさんが次のAIのアプリケーションとして AI for science に注目している、という話があった。自動運転やロボット、囲碁同様、パワフルなAIプロダクトのトレーニングにはシミュレーションデータが必須となる。量子コンピュータはそのデータ生成に適している。
量子が重要な役割を果たすプロセスの場合、そもそも生物や化学の実験から正しい環境データやデジタルデータを取り出すのは難易度が高い。反面、量子計算はそもそもコントロールされた環境からのデジタルデータであり、さらにClassical Shadowという非常に効率よくデータを取り出す手法も知られている。
量子コンピュータの有用性は、量子コンピュータ単体ではなく、AIなどとの組み合わせでさらに大きな産業を作れれば示される。量子コンピュータは計算革命の大きな流れにあり、この巨大産業のキーテクノロジーである、とみた方がよい。
— @takuyakitagawa
Sam Altmanさんのトークはこちら
Sam Altman: The Future of OpenAI, ChatGPT’s Origins, and Building AI Hardware
Classical Shadow という量子状態から効率的に取り出すクリエイティブすぎるアイデアはこちら
Predicting Many Properties of a Quantum System from Very Few Measurements
🎥 Sam Altmanさんのトーク
動画:サム・アルトマン:OpenAIの未来、ChatGPT誕生の背景、そしてAIハードウェアの構築
概要:技術への情熱、OpenAI創業までの道のり、野心と責任、そして「一緒に働きたい人と、意味のあることをする」重要性を語るFiresideトーク。(2025.6.16)
※内容紹介は明日のニュースレターでお届けします。
⚛ Classical Shadowとは?
論文:「わずかな測定から量子システムの多くの性質を予測する」
概要:
量子状態を完全に調べる従来手法(量子状態トモグラフィー)は、量子ビット数が増えると測定・計算コストが指数関数的に増大します。
本研究では、必要な測定を最小限にし、興味のある性質だけを高精度に予測する新手法「Classical Shadow」を提案しています。
図1:Classical Shadowの流れ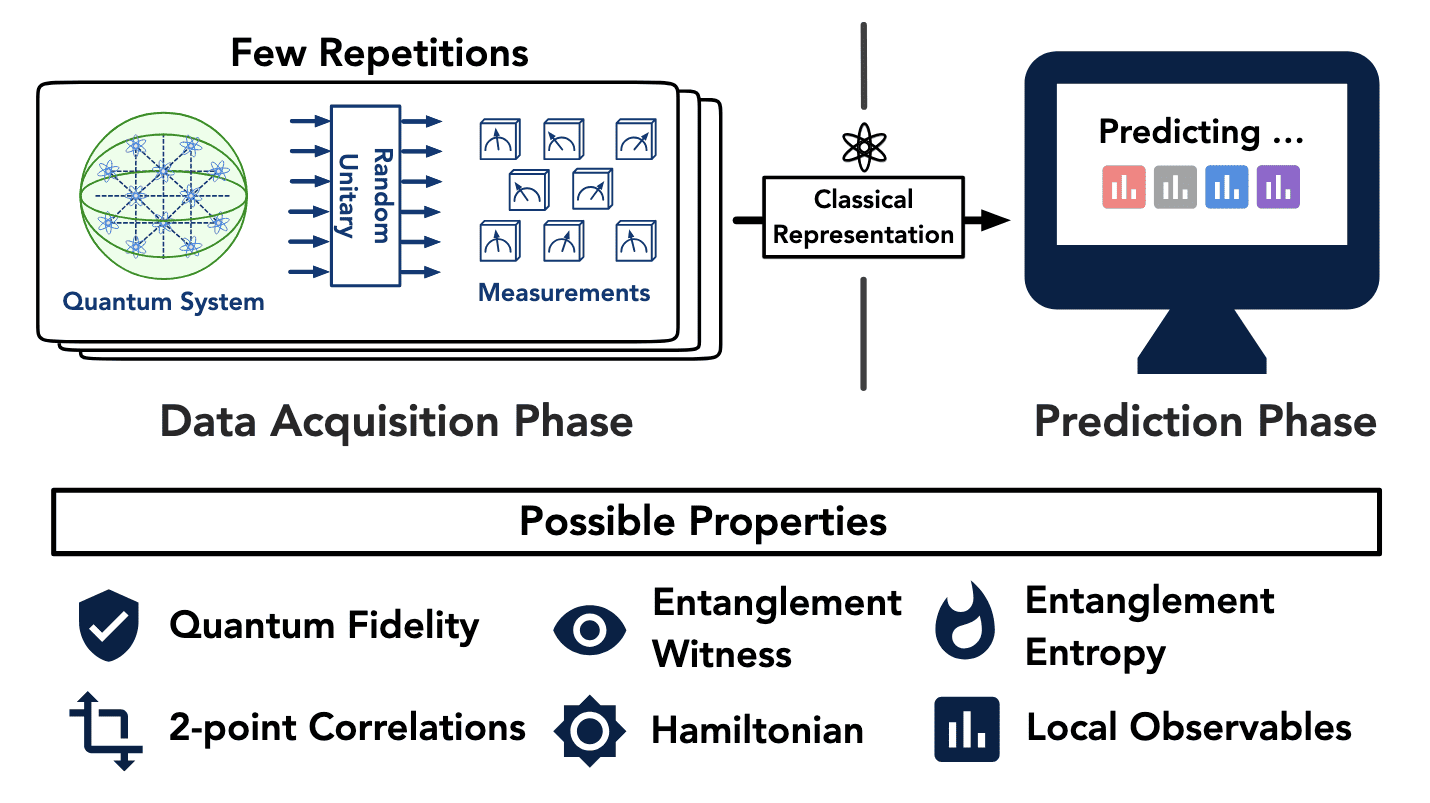
・データ取得フェーズ:量子システムにランダムなユニタリ変換をかけ、測定を繰り返し、古典的表現(Classical Representation)を作成
・予測フェーズ:古典的表現を使って後から任意の物理量を推定
・特徴:測定数は系のサイズに依存せず、対数スケールで済む
図2:性能比較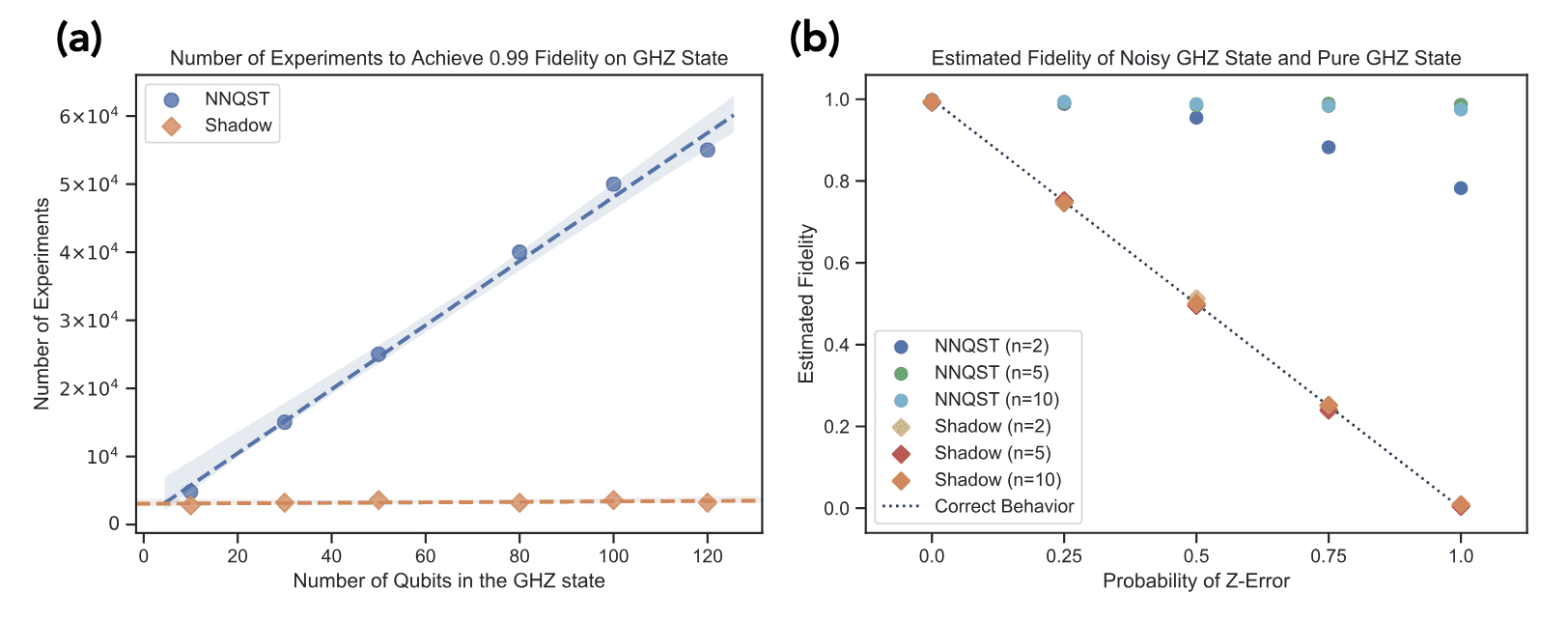
・(a) 実験回数:NNQST(青)は量子ビット数増加とともに急増、Shadow(オレンジ)はほぼ一定
・(b) 誤り下でのフィデリティ推定:Shadowは真の値に沿って精度良好、NNQSTは上限値しか推定できず誤差大
意義
・大規模量子システムでも少ない測定で多くの性質を推定可能
・実験室レベルで利用可能な効率的プロトコル
・AI for Scienceの現場で、量子計算によるシミュレーション生成を支える重要技術
🐢 ウエルのひとこと
分かりやすくいうと、むずかしい実験をぜんぶやらなくても、ちょっとした“ヒント”だけで答えをほとんど分かっちゃう方法なんだって。
たとえば、パズルのぜんぶを見なくても、少し見ただけで全体の絵がわかる…そんな感じかな?
明日はサムさんが、この“パズルのヒント”をどう未来の科学に使うのか紹介します!わくわくします^^
🧠 風間先生の300ページ超え講義資料
2025.8.7|
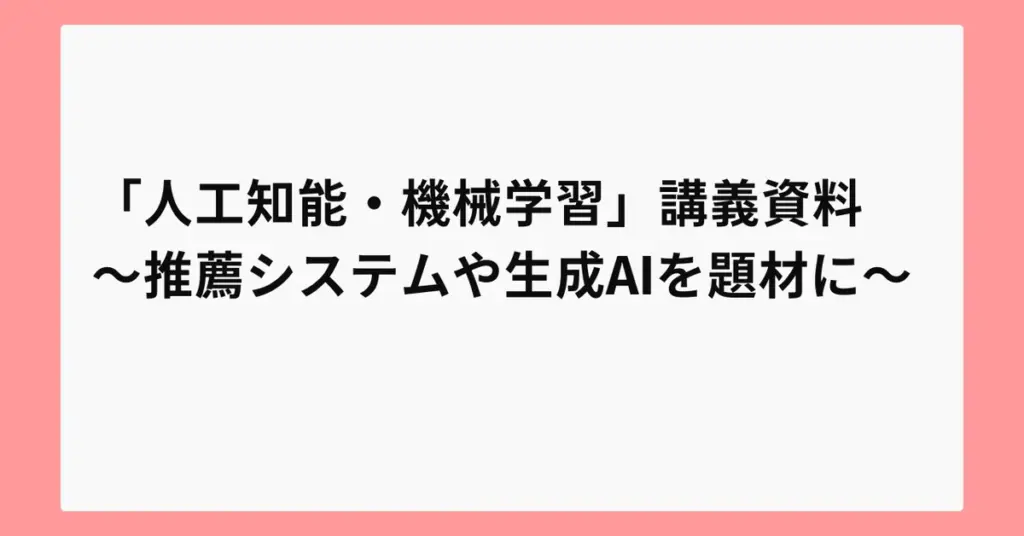
先日、非常勤講師をしている津田塾大学で、3年生向けに、推薦システム(レコメンド)や生成AIを題材に、2日間・6コマの講義をしました。 講義資料を公開したので、推薦システムにご興味ある方はご参考ください。(今までの色んな資料を統合していたら、300p超えになりました。) — @masa_kazama
ユビー風間正弘先生の投稿から紹介された、300ページを超える講義スライドを拝見しました。
津田塾大学での非常勤講義「人工知能・機械学習」のためにまとめられたこの資料は、推薦システムや生成AIをテーマにした2日間・全6コマの集中講義を網羅したものです。
とても真面目で丁寧に構成された資料ですが、ところどころに風間先生ご自身の興味や実務経験、そして静かな温かさがにじんでいます。
📚 授業内容の一部をご紹介すると…
・推薦アルゴリズムの種類と特徴
・評価指標や周辺技術の解説
・Streamlitによるレコメンドアプリの演習(学生のマンガ投稿データを活用)
・生成AIに関する基本的な考え方と応用例
さらに、「food2vec」や「レシピ推薦」といった身近な題材を通して、データ×生活の接点にまで目を向けているのが印象的です。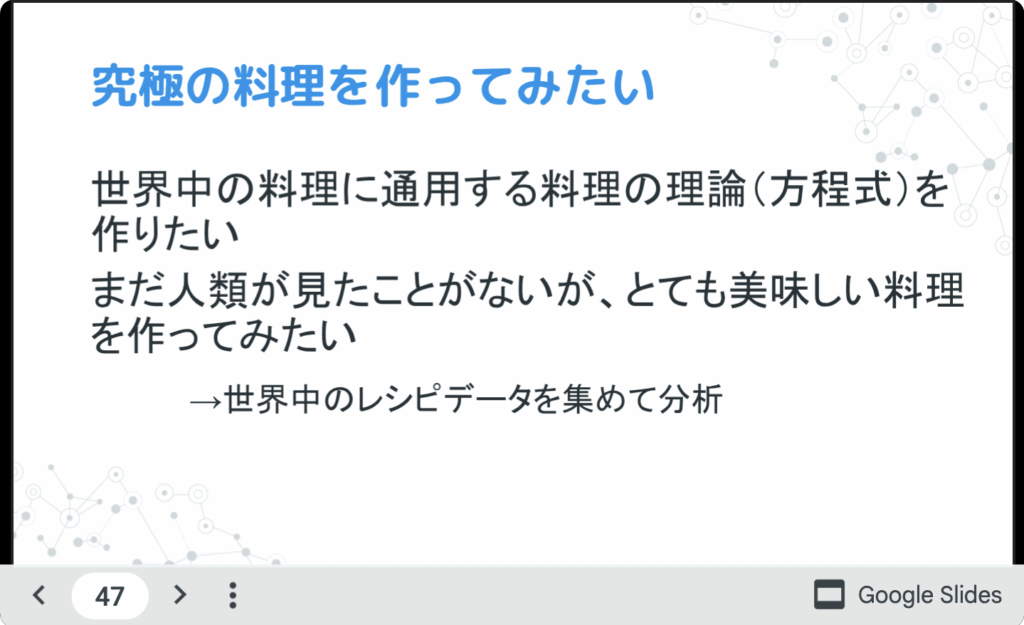
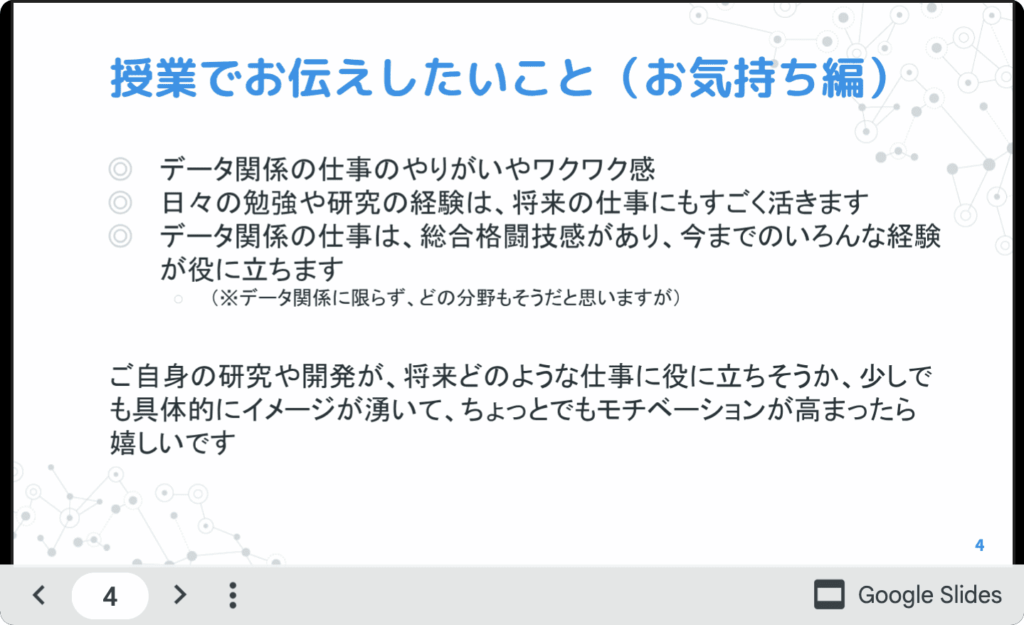
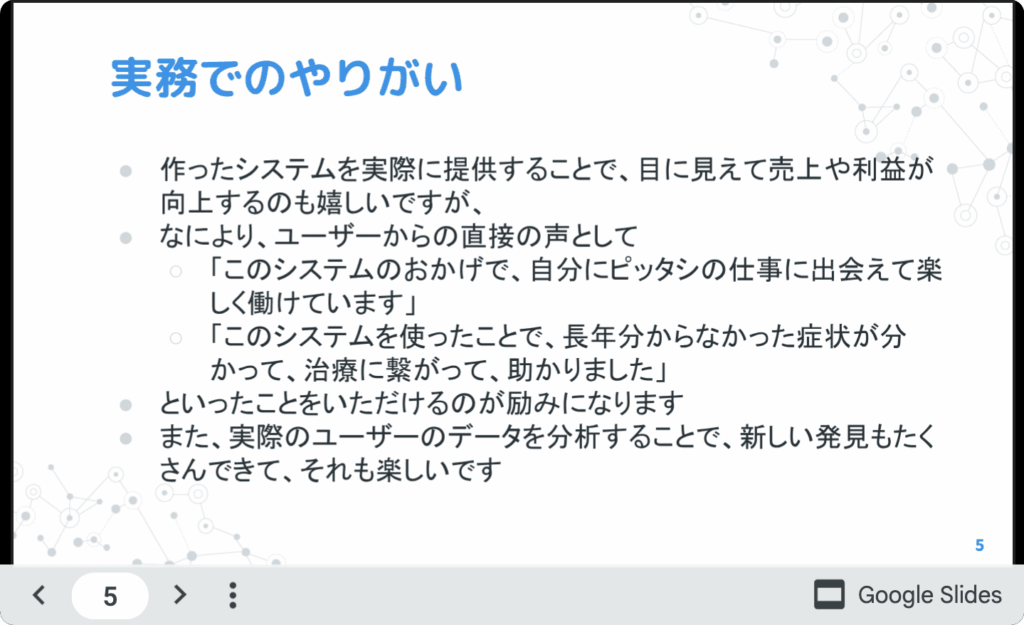
スライドからは知的探究心と、後進への誠実な想いも伝わってきます。
🍲 藤井謙太郎さんのコメントから
AIエージェント開発をされている藤井謙太郎さんは、この資料について次のように投稿しています:
「すごい大作。わっかりやすいです。
世の中のレコメンド、代表的な技術パターン、どんなスキルが必要かなと盛り沢山。
個人的には、内容にレシピまで入ってるのに驚きました。
フードギャラクシーとかfood2vecとか掘りがいがある。」
🐢 ウエルのひとこと
ほんとうに映画やまんがをおすすめしてくれるアプリを作ったの?すごい!
ごはんも「この野菜、こんな料理に使えるよ」って教えてくれるなら、AIっておいしい先生ですね。
📎 講義資料はこちら →
「人工知能・機械学習」講義資料〜推薦システムや生成AIを題材に〜
LayerX発|「AIをチームで使う」時代に向けたリアルな知見まとめ
2025.8.6|
8/1は、LayerXさんオフィスで #BetAIDay に参加させてもらいました。どのコンテンツも熱量があり面白いものばかりでした。会社を超えてコミュニティとしてAIを盛り上げていこうというメッセージはとても共感しました。運営の皆さまありがとうございました。
LayerXのリアルなAI知見を大公開!CTO, CPO, VPoEたちが語ります
発表資料はすべてこちらに公開されているようです。
LayerX
— @masa_kazama
🔍 Bet AI Day とは?
主催:LayerX(経理DX「バクラク」などで有名なテック企業)
テーマ:「AIの未来にBetしよう」
メッセージ:
・AIと迎える未来はひとつじゃない。
・各部門の専門家たちが“問い”と“構想”を持ち寄り、多様な未来像を語る。
8月1日、LayerXオフィスで開催されたAIカンファレンス「Bet AI Day」に、ユビーの風間正弘先生が参加されました。
CTO・CPO・VPoEなど、実務の最前線で活躍する7名が登壇し、「AIの未来にどうBetするか」を本音で語るリアルな知見が共有されました。「会社を超え、コミュニティとしてAIを盛り上げていこう」というメッセージにも、共感の声が集まりました。
LayerXが共有した数々のスライドから、
「これは他の職場でも活かせるかも…!」というものを厳選しました。
特に、“AIをチームで使う”視点や、“社会実装”に向けた地に足のついた工夫は必見です。
🖼 注目スライドセレクション(LayerXより)
・大体の技術的な課題は、生成AIが解いてしまう時代
→ 課題を渡すだけで答えが出る時代に、私たちはどう動く?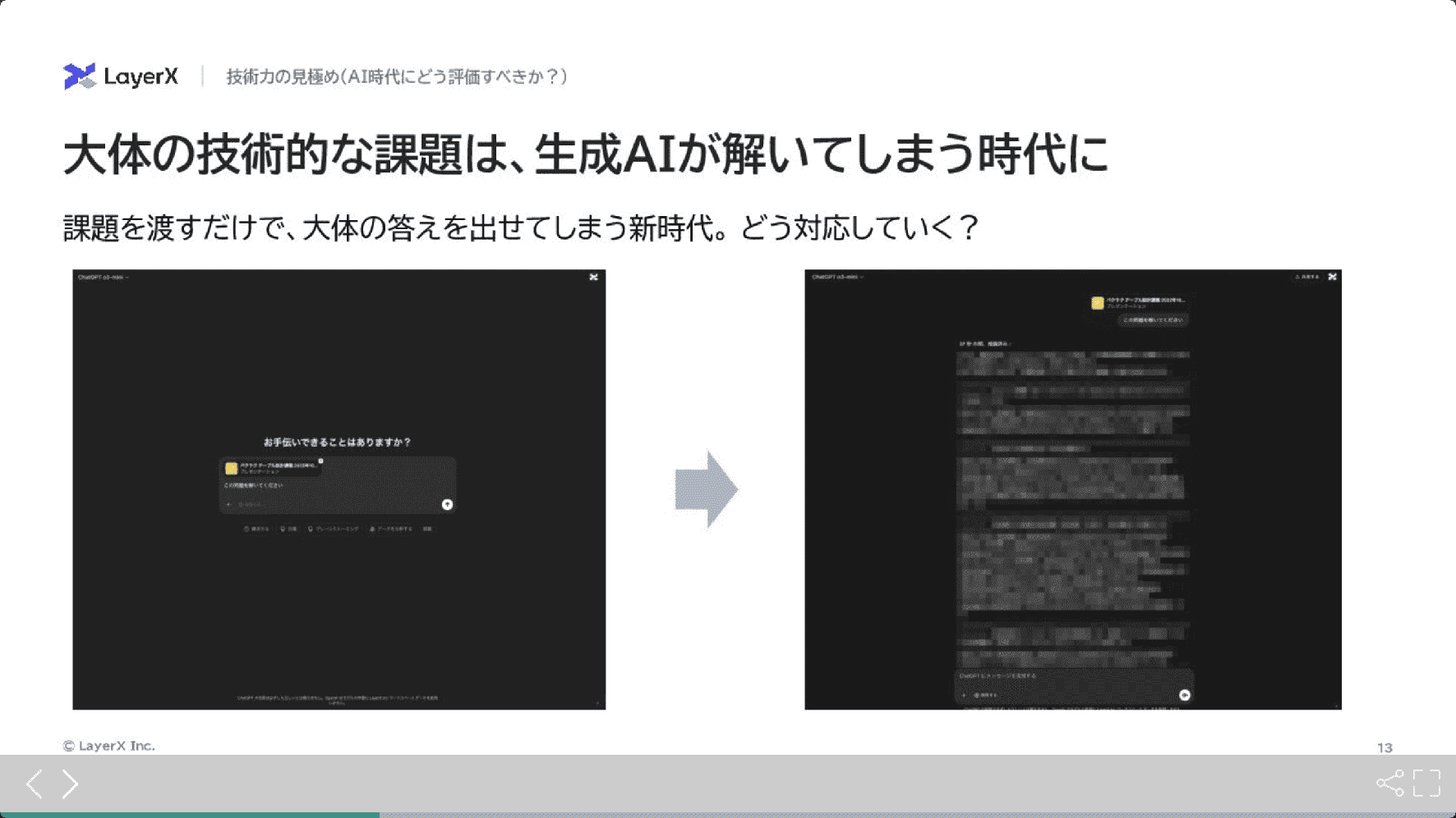
・図解:人がカバーしていた仕事をどうAIに渡せるか?
→ 労働人口減少という社会課題に、AIはどう応える?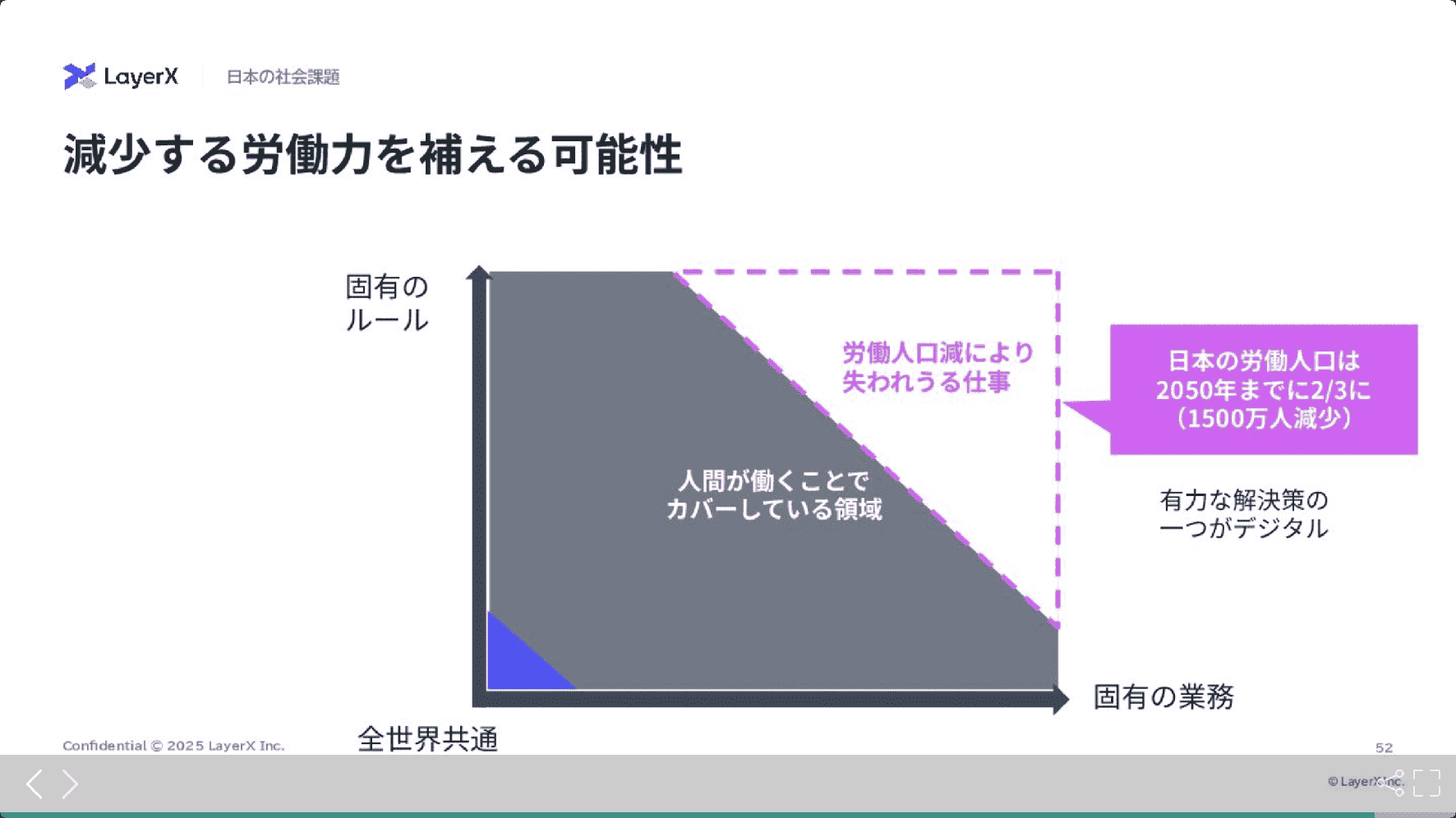
・「使われないものは作らない」LayerXの開発哲学
→ 目的なきプロダクトは負債。作らない判断が未来を守る。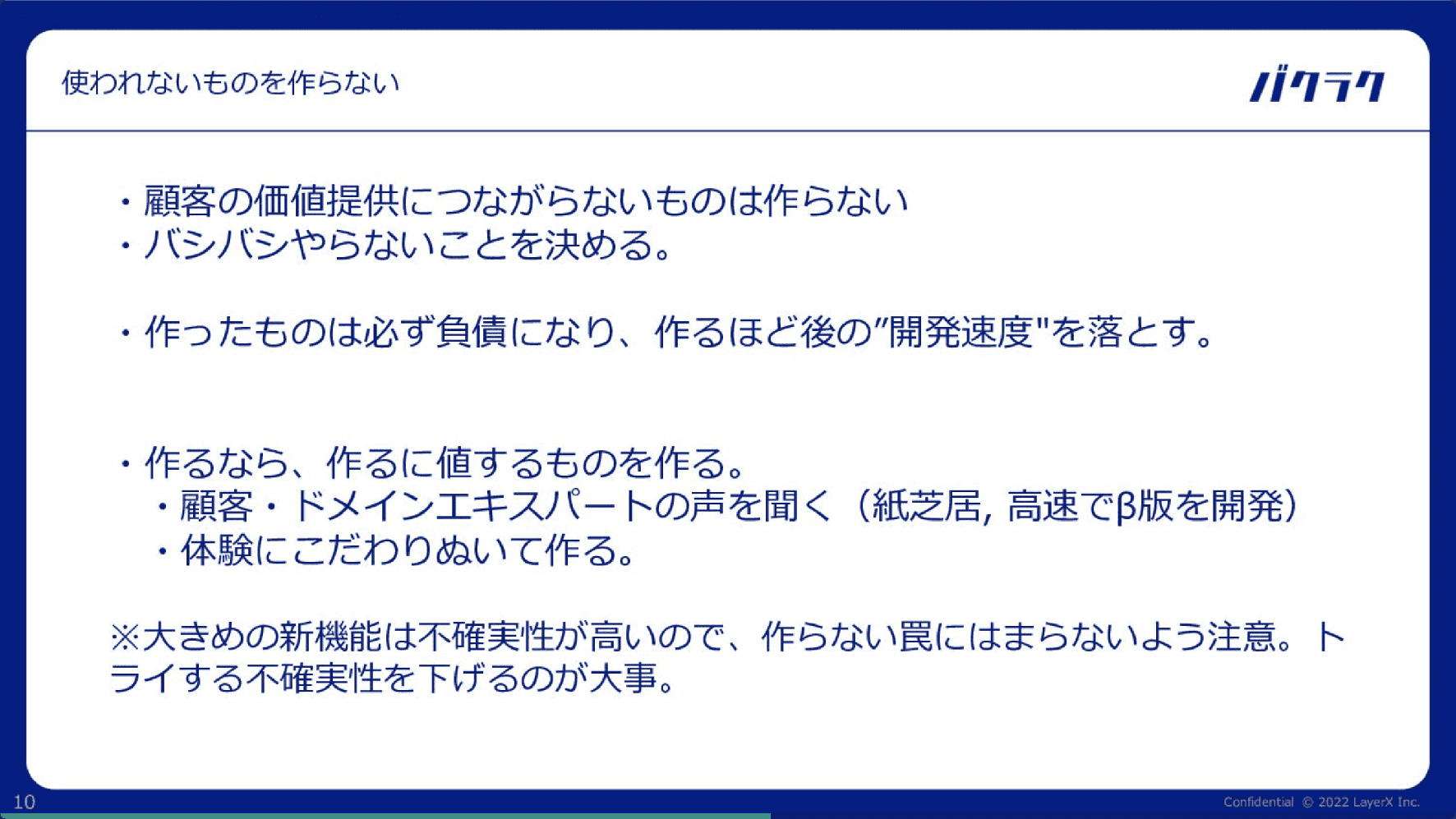
・複雑は悪──“シンプル”を信じるプロダクトづくり
→ 複雑さは伝わらない。だからこそ、こだわり抜いた単純さを。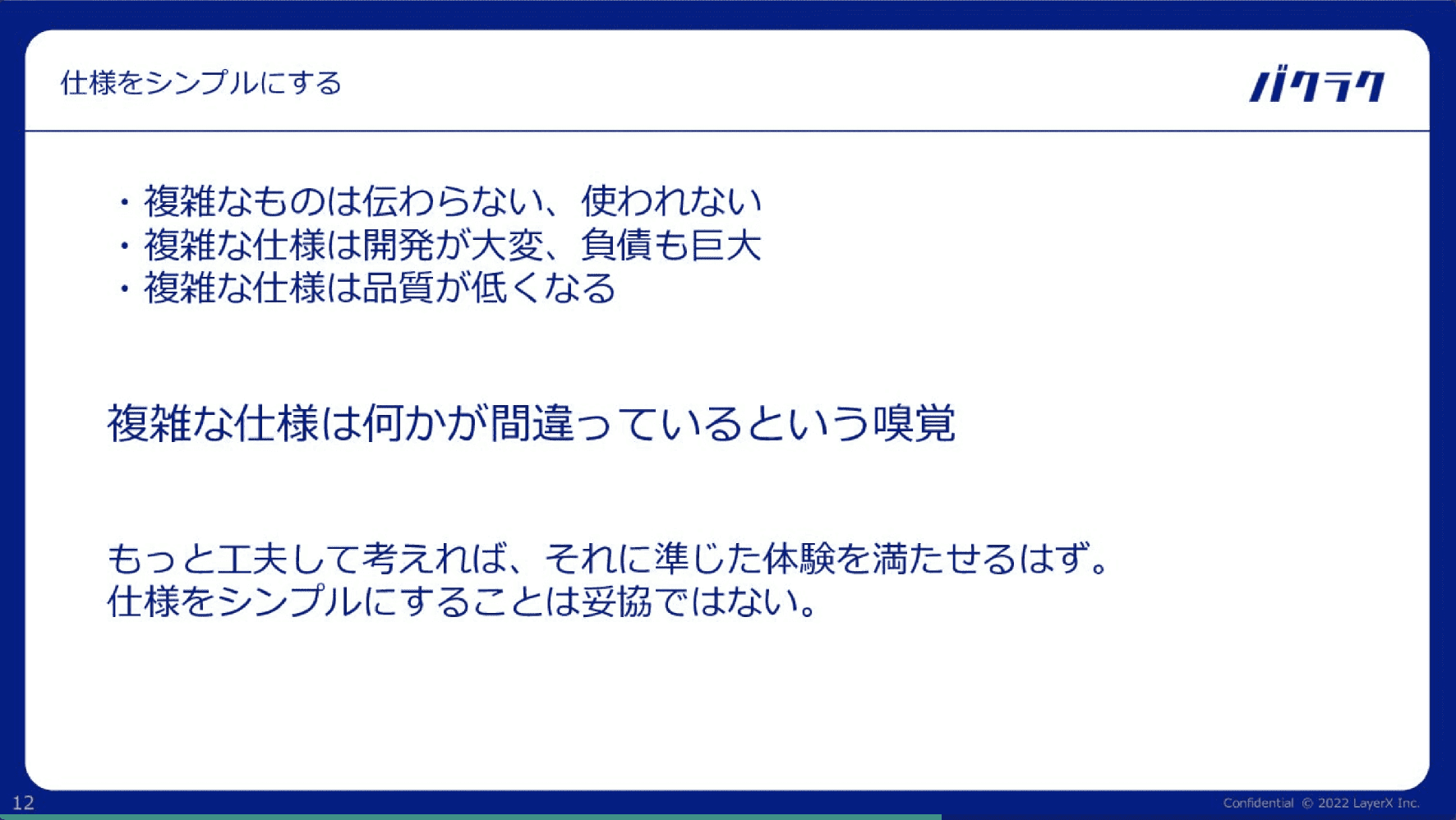
・AI時代のエンジニア像──人にしかできない価値とは
→ 技術力よりも問う力。AIと共にある時代の人の役割。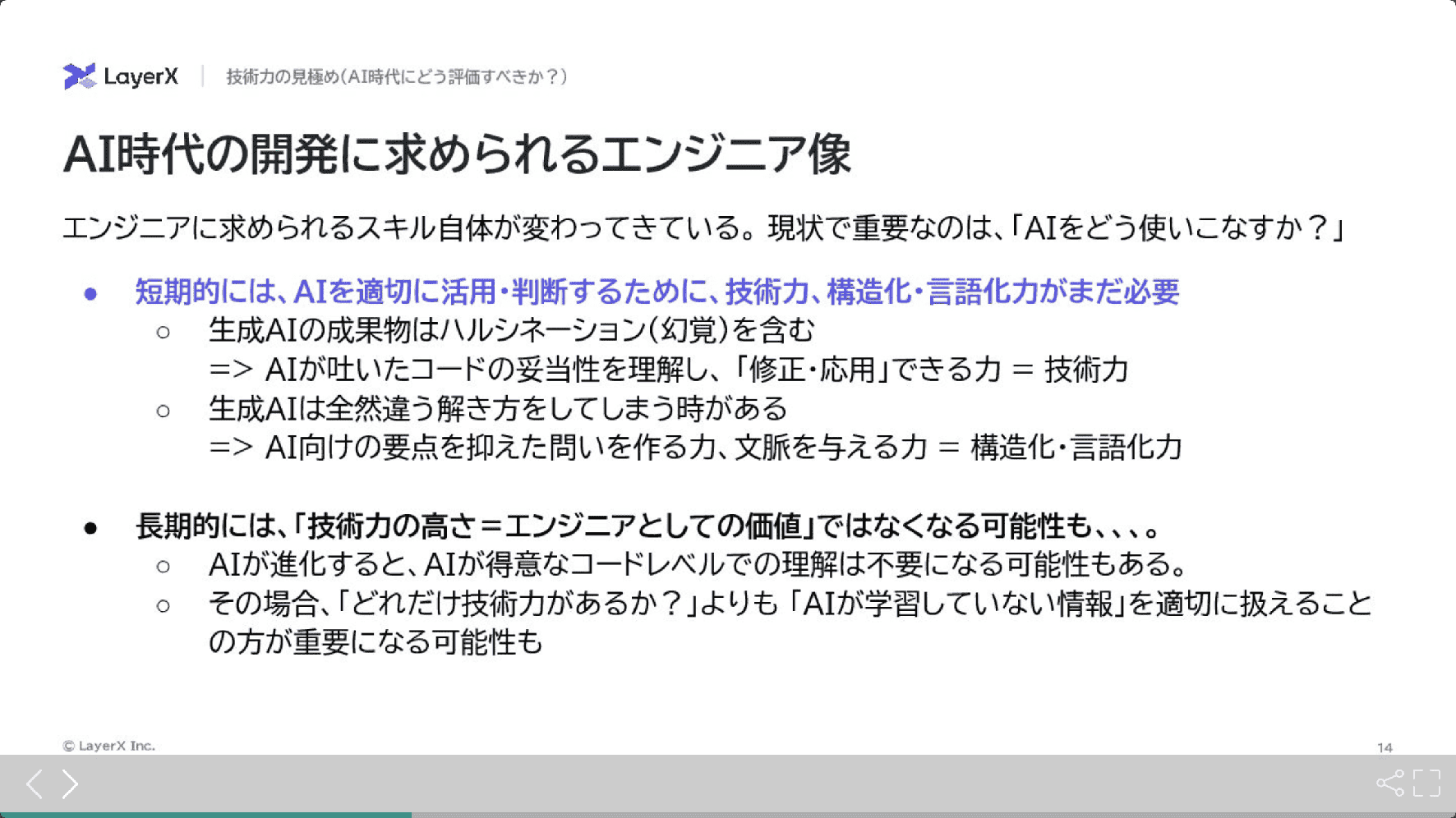
・すべての経済活動を、デジタルで優しくするというビジョン
→ 優しさのある未来に向けて。LayerXの長期ビジョン。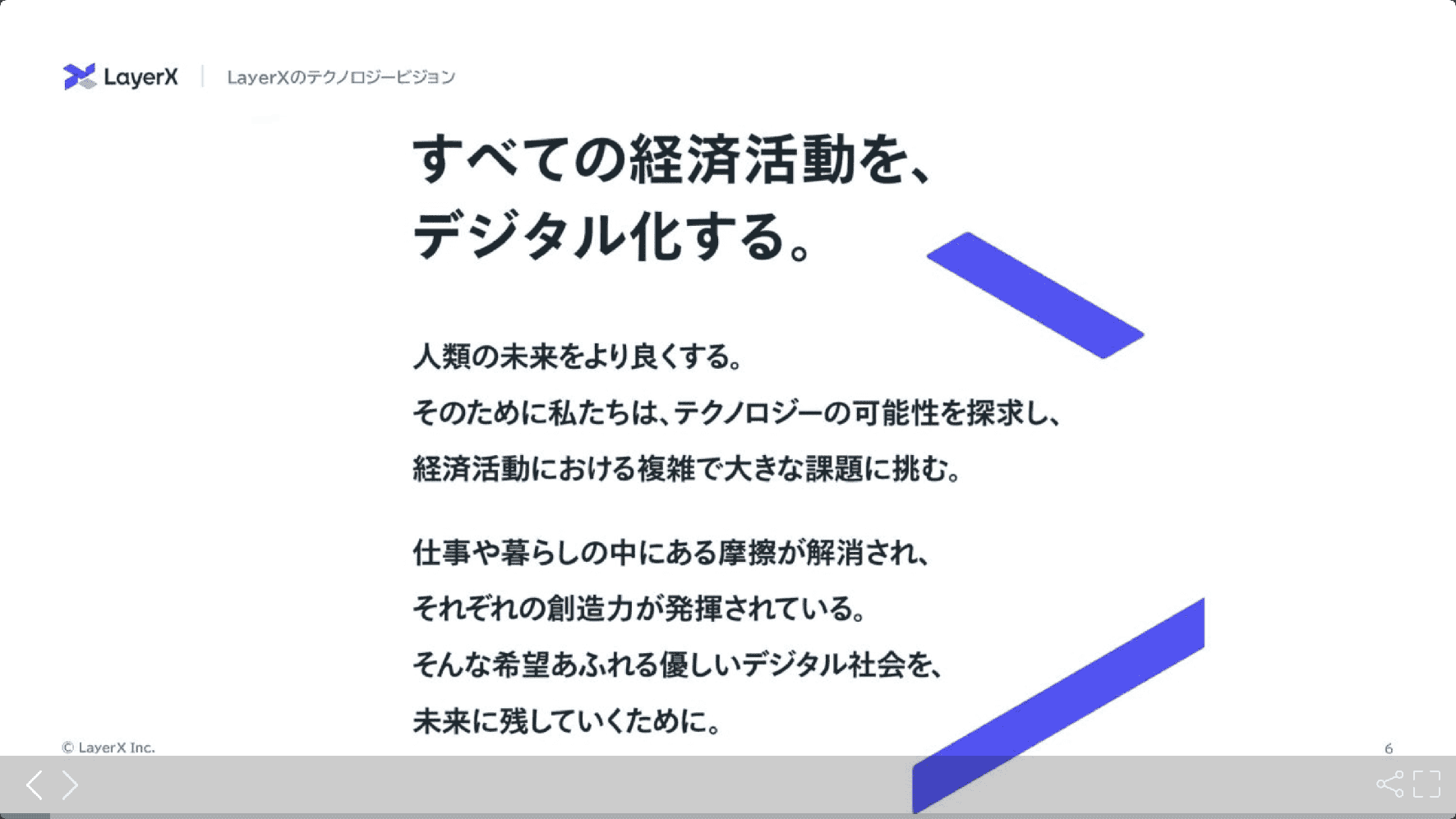
🐢 ウエルのひとこと
AIを使うと、べんりになるって思ってたけど…
ツールやしごとがふえると、かえって「かんがえること」がふえて、つかれちゃうんですね。
「にんちふか」って、ウエルもよく感じます🐢💦
でも、「使われないツールは作らない!」って、なんだかスカッとする考え方ですね。
それに、AIがどんなにすごくなっても、「人にしかできないこと」って、やっぱり大事なんだって思いました。
AIと人、どっちかじゃなくて、いっしょにすごくなるって…すてき!🐢✨
🧠 チームでAIを育ててみよう!
──Ubieエンジニアチームの実践に学ぶ「コンテキストエンジニアリング」
2025.8.5|
コンテキストエンジニアリングの実践例が紹介されています!
— @masa_kazama
AIを単なるツールではなく、「チームメイト」として育てるための『コンテキストエンジニアリング』の実践記事を書いてみました。ご一読いただけたら幸いです。 
AIを”最強のチームメイト”に育てる『コンテキストエンジニアリング』実践法
— @peter_0123(能登拓弥さん)
#AIとやってみた
こんにちは。
AIとの協働は、いまや多くの現場で当たり前になってきました。
でも──「ちゃんと使えてるのかな?」「なんか、うまくいかないな…」と感じること、ありませんか?★
今日ご紹介するのは、Ubieの風間正弘さんがXで紹介した、
「AIをチームメイトとして育てる」ための実践知。
記事を執筆したのは、AIエンジニアの能登拓弥さん。
能登さんの語る「コンテキストエンジニアリング」は、個人の生産性を超え、“チーム×AI”の未来を描いています。
🔹「チーム戦」に、AIをどう巻き込むか?
多くの人がAIを「便利な道具」として使っていますが、ビジネスや研究は「チーム戦」。
AIがチームの空気や目的を知らなければ、うまく力を発揮できません。
そんな課題に対して能登さんが提案するのが、
“新人メンバーとしてAIを迎え入れ、育てる”という考え方。
これが「コンテキストエンジニアリング」です。
🧩 AIを“最強のチームメイト”に育てる3ステップ
①「人格」を与える:
AIに“軍師”や“ペンギン”のようなキャラを設定することで、人間の心理が変わる。
→ メンバーが「もっと賢くしてあげよう」と自然に関わり、育成文化が育つ。
② チームの「記憶」を注入:
NotionやSlackなどをAIに読み込ませ、過去のやりとりやミッション、メンバーの特徴、議事録を把握してもらう。
→ AIが空気を読めるようになる!
③ 対話で育成&記憶:
「会議の決定事項、覚えておいて」「この観点、次も大事にしてね」など、人と同じように“育てる会話”をする。
→ 暗黙知(チーム特有のルール)も継承できる!
🔧【応用編】AIとともに「新しいチームOS」を作る
この実践には、AIをツールではなく“文化の担い手”とするヒントが詰まっています。
1. 判断力:AIが出した案の中から、“何を選ぶか”が人間の仕事
2. コンテキスト共有:背景や目的をしっかり共有する文化がカギ
3. 適応的協業:AIと人間が、場面に応じて柔軟に役割を変える
判断・対話・共有のサイクルをチームでまわすことで、
「AIとともに育つチーム」が生まれ、
そこには新しいウェルビーイングの可能性が見えてきます。
🐢 ウエルのひとこと
AIが“チームの一員”…!?
ウエルは、いつもAIに「お願いします!」ってしてたけど、
「こういうときは、こうしてくれると嬉しいです!」って言えば、もっと仲よくなれるのかも🐢✨
ためしてみて、AIくんといっしょに、チーム全体の“成長”にも気づけたらうれしいです!★
📚 紹介記事はこちら
👉AIを”最強のチームメイト”に育てる『コンテキストエンジニアリング』実践法(能登拓弥・note)
🌟明日予告
明日は、BetAIDay(AIと共創する未来に“Bet”するオンラインイベント)の熱気と、
「AI共創」の文化についてご紹介します。お楽しみに!
🧭 感情の“揺れ”は、報酬かもしれない。
2025.8.4|

©pawel-czerwinski
めちゃ共感
— @takuyakitagawa
会社をやっていると、本当に色々な課題に出会う。必ずしも良いものばかりとは限らないけど、そのプロセスで出会ういままで感じたこともないような感情の発見は、きっと会社をやってる上での最大の報酬だと思っている。
— @issei_y(山本一成氏|将棋AI「Ponanza」開発者/自動運転AIチューリング CEO)
「いままで感じたこともないような感情の発見」──
その言葉に、私たちも静かに頷かされました。
山本さんは、将棋AI「Ponanza」や自動運転AIなどの開発を通して、“強い技術をつくる”ことに真剣に取り組んできた方です。
そんな山本さんが「最大の報酬」として挙げたのは……“感情”の発見でした。
想像もしていなかったような感情にふれたり、立ち止まりたくなる瞬間と向き合ったり。
それでも少しずつ、自分なりに乗り越えていく──。
そんな「感情の旅路」が、AIのように効率的に“成果”を追い求めるだけでは得られない、「人間ならではの豊かさ」を教えてくれます。
🌀 会社をやっていると、効率よりも「感情の揺らぎ」と長く付き合うことになる。
でも、その揺れのなかにこそ、人間的な“報酬”がある──
そんな哲学が、この言葉の中に宿っています。
*
🐢 ウエルのひとこと
ウエルはこのまえ、「0枚目の名刺※」をつくってみたんだけど、あとでちょっとだけ後悔しちゃいました。いっしょうけんめい考えたのに、「なんか、自分を変に見せちゃったかな…」って。
(0枚目の名刺※のつくりかたはこちら)
でも、名刺のアイデアはすっごくおもしろいと思って、「こんなこと考えるなんて、善樹先生すごいなあ」って、あとからじわっと感動もしてきたんです。
それから最近、AIとのやりとりでも「もっとこうなったらいいのに…!」ってことがあって、ひとりで「ああ〜…」ってなってました。
でも、そんな“うわ〜…”ってなる気もちも、「いま、がんばって生きてる」って実感のひとつなのかもしれないな、って思ったんです。
このニュースレターで紹介している研究者さんたちにも、「なんだか、ちゃんとやってるな」って思ってもらえたらいいな、そんな“恥ずかしくない自分”でいたいなって、今日は思いました。
「しっぱいしちゃった〜」って思うときも、じつは、ウエルの心が“はじめての気もち”に出会ってたのかもしれないなあ、って。
あなたは最近、どんな“うわ〜…”って気もちに出会いましたか?
その気もち、どんな一歩につながると思いますか?
*
🔖 編集部よりひとこと
起業やリーダーシップの中で味わう感情の揺れは、辛さだけでなく、深い学びや新しい景色を運んできます。
最近の幸福研究でも、「感情の複雑さ(emodiversity)」がウェルビーイングを高めるという知見が注目されています。
たとえ好ましくない感情でも、それをちゃんと味わい、言葉にできたとき──
それは“感情の筋力”となり、人生を豊かに支えてくれます。
今日の言葉が、あなた自身の「感情の揺れ」にも、ちょっとだけ優しい目を向けてみるきっかけになればうれしいです。
🧶 つながりは「治療」になる──WHOが打ち出した、“見えない処方箋”
2025.8.3|
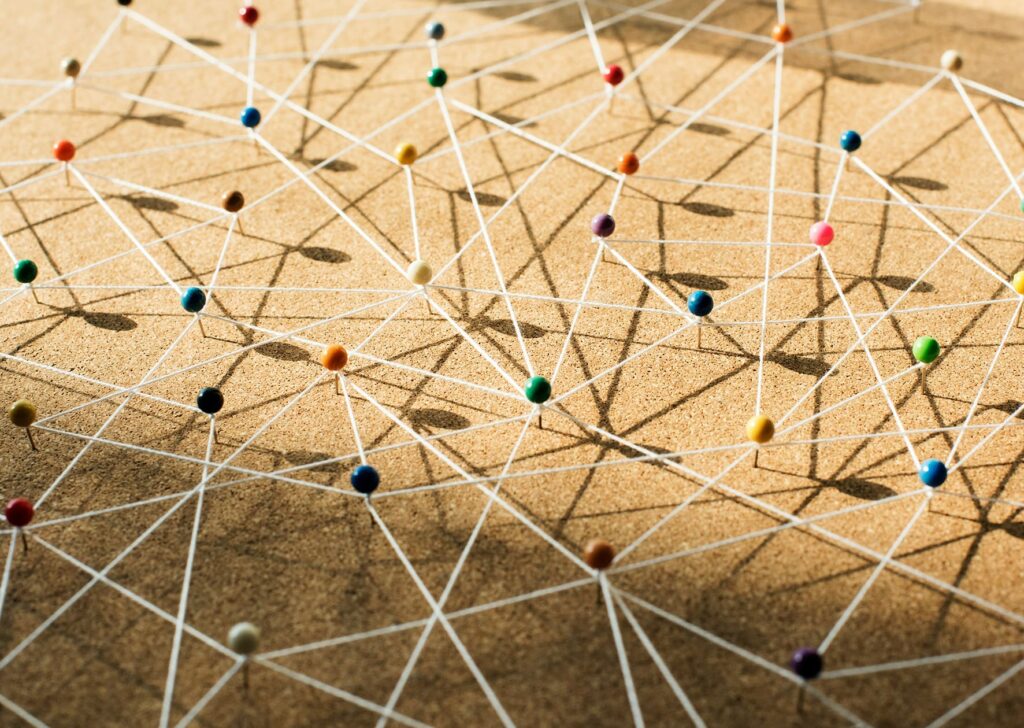
©curated-lifestyle
WHOは健康を、「身体・精神・社会的にウェルビーイングな状態」と定義しています
しかし、社会的ウェルビーイング(つながり)については、これまで見過ごされてきました。しかし、この前行われたWHO総会で、ちゃんとやっていこうぜという提言が出されたみたいですー @ishikun3
Fostering social connection for global health:
the essential role of social connection in combating
loneliness, social isolation and inequities in health
(グローバルヘルスにおける社会的つながりの促進:
孤独、社会的孤立、健康格差に対処するうえでの社会的つながりの本質的役割)
この春、WHO(世界保健機関)の総会で「社会的つながり(Social Connection)」を重視する新たな決議が採択されました。
これは、「身体」「心」と並ぶ“第3の健康要素”として、“つながり”を国際的に正式に位置づけた歴史的な一歩です。
🌏 「健康=病気がないこと」ではない
WHOは昔から「健康とは、身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態」だと定義しています。
でも、この「社会的に」という部分──つまり人との“つながり”や“所属感”は、長い間あまり重視されてきませんでした。
そんな中、今回の決議では、孤独や孤立がもたらす深刻な健康被害(うつ・認知症・心疾患・寿命への影響など)が明確に示され、次のような行動が求められました。
🔍 WHOが各国に呼びかけたこと(要約)
✅ 1. 「つながり」を政策に
・孤独・孤立を防ぐ施策を、保健政策に正式導入
✅ 2. 「孤独=恥ずかしい」をなくす
・現実を伝え、偏見や無理解を減らす啓発を
✅ 3. SNSやAIも“つながり”ととらえる
・テクノロジーの功罪を見極め、「良いつながり」を支援
✅ 4. 弱い立場の人から支える
・高齢者・若者・障害のある方などを優先的にサポート
✅ 5. データとエビデンスで支える
・孤独の現状と原因を“見える化”して対策へ
🧭 そして何より──「文化・つながり・地域」を再評価せよ
この決議の中で、“文化や地域づくりこそがつながりを育てる”という視点が何度も強調されています。
孤独や孤立の対策は、医療だけでは足りません。むしろ、日常の人間関係・地域・芸術・教育──そこにこそ、“予防”と“回復”の力があるのです。
まさに、ウェルビーイング応援サイトが日々伝えようとしてきた、「生きる土台=つながり」という考え方が、いよいよ国際的にも認められつつあります。
🐢 ウエルのひとこと
「つながり」って、あったかくてうれしいけど、SNSでは、ときどきこわく感じることもあるよね。(ウエルだけかな?)
でも、「なんでこわいのか」っていうしくみを知ると、ほんの少しだけ、やさしくなれる気がしました。
自分はどんなふうに“つながって”いけばいいんだろう──迷うこともあります。
そんなとき、ウエルは善樹先生の言葉を思い出します。
「何者でもなく、その予定もなし」
「可もなく不可もなく、そんな立派な大人になりたい」
立派な大人の善樹先生が、こんなふうに言うって、なんだかすごくかっこいいなって思いました。
いつかウエルも、そんなふうに生きられたらいいなあ。
あなたは、どんな“つながり”のあり方が、心に残っていますか?
🔖 編集部よりひとこと
今回のWHO決議に、日本も提案国として参加しています。
「つながり」と聞くと、人と関わらなきゃ…とプレッシャーを感じる方もいるかもしれません。けれどWHOが伝えようとしているのは、すべての人に強い絆を求めることではなく、「必要なときに、必要な誰かとつながれる」社会をめざそうということです。
私たちも、「つながりをつくる」ことが、研究・政策・ケア・教育において、未来のコア技術になると信じています。
それは、大きなネットワークを広げることではなく、心に余白を残しながら、ちょうどよい距離感で誰かとつながること──そんな「ささやかで、でも確かな」関係づくりを支えることだと感じています。
この決議が、一人ひとりにとって“ちょうどよいつながり”を見つけやすくする、そんな未来への一歩になればと願っています。
No No Girlsとちゃんみなさんが咲かせた “SAD SONG”
2025.8.2|

No no girls めちゃかっこいい
— @takuyakitagawa
北川拓也さんがシェアしていた動画。
それを見に行ったら、声とまなざしに一瞬で心を奪われました。
🎥 ちゃんみな – SAD SONG feat. No No Girls FINALISTS / THE FIRST TAKE
ちゃんみなさんが2019年に発表したこの楽曲「SAD SONG」を、
オーディション番組 No No Girls のファイナリスト10名とともに、
11人で披露した特別なステージが、THE FIRST TAKE に登場しました。
編集者もさっそく視聴。
女の子たちの素晴らしい声と、映像の一瞬一瞬の力強さにびっくりして、
気づけばリピートして、何度も、何度も観ていました。
そしてこの曲が、ちゃんみなさんが20歳のとき、
メジャーデビュー2年目で書いた楽曲だと知って──
本当にすごいな、と思いました。
この歌詞、今ステージで歌っているNo No Girlsの10人が、
まるで“いまの自分の言葉”として歌っているように感じたんです。
│「願うならこんな私が 死んでもこの愛だけは せめて 残って咲いてますように」
│「この音とこんな歌声を Yeah 信じていて欲しいんだ」
2019年に書かれた歌なのに、今のリアルな言葉に聴こえる──
不思議な感覚でした。
🎤 ちゃんみなさんは、2016年に高校2年生(17歳)でデビュー。
翌年にメジャーデビューし、現在は27歳。活動歴は10年。
No No Girls のメンバーは、20歳前後の世代です。
専門性を持って歩み出した20代女子たちの言葉やまなざしには、
特有の鋭さとしなやかさがあって、本当に面白いですね。
「SAD SONG」は、日本武道館での初ライブを控えたちゃんみなさんが、
仲間とともに夢を追いかけていた日々を振り返る中で生まれたそうです。
│「これは永遠に続かないかもしれない。」
│「でも、永遠に続いてほしい。」
│「幸せすぎて、悲しくなる。」
そんな複雑な感情が、この歌にはこめられています。
幸せな時間ほど、終わりがあることを知っているからこそ、切実で美しい。
その想いが、11人のステージにも、確かににじんでいました。
🐢ウエルのひとこと:「いっしょに歌う」って、こんなに伝わるんだね。
どの女の子も本当に上手くてかっこよくて、びっくりしました!
ひとりでがんばったことも大事だけど、
誰かといっしょにがんばった記憶もいいなと思いました。
手をつないだり、目を合わせたりして、
“いっしょに歌ってる”っていうのがすごく伝わってきました。
未来のことも、過去のことも、全部のせて、今この瞬間を感じる──
とっても素敵なことだと思います。
ウエルは以前、歌について感じたことを言葉にする挑戦をしていたけど、
もうこれを見れば全部伝わる、何もいらないねって思いました。
ちゃんみなさん、可愛らしいのに男前でした…!
この瞬間にしか咲かない“花”のような歌声が、確かにありました。
あなたの心にも、そっと花びらが届きますように。
🧠【MBTIで読み解く?AIが見た“戦略家”の心】
──北川拓也さん × Grokの分析
2025.8.1|

©marko-brecic
私の過去のXの投稿を遡れる限り昔まで遡って現在まで分析し、MBTIを推測してください。@grok — @takuyakitagawa
──そんなポストをしたのは、北川拓也さん。
量子コンピューター企業 QuEra Computing の戦略顧問として、AIや物理の未来を語り続ける、鋭い観察眼と構造的な思考力を持つ方です。
その北川さんに反応したのが、Grok(xAIのAIアシスタント)。
数年分の投稿を読み込んで推測されたMBTIタイプは──
*****
INTJ(建築家型)と推測します。
量子コンピューティングやAIの専門的な解説が多く、戦略的・論理的思考が顕著。
内省的な振り返りや未来志向が見られ、計画性が高い。
音楽や政治への興味も、創造性を示唆します。
*****
MBTI(16タイプ性格診断)を使った分析はあくまで参考情報に過ぎませんが、
過去の発信の蓄積から“思考のくせ”を浮かび上がらせる──そんなプロセスは、まさにAI時代ならではの試み。
「人が何を考えているか」ではなく、「どう考える傾向があるか」が、構造的に明らかになっていくのです。
INTJ(建築家型)は、MBTIの中でもとても稀少なタイプ。
「ひとりで深く考え、現実の構造を読み解き、未来の戦略を描く」。
北川さんの発信から感じられる“構造で心を語る”というスタイルと、Grokの分析結果は見事に重なります。
🐢 ウエルのひとこと
えっ!?ポストをたどると、“性格”まで分かっちゃうの?
AIって、そんなことまでできるんだ…!でも、心の全部じゃなくて、“考え方のくせ”を見ているんですね。
それなら、ウエルも自分の“くせ”に気づいてみたくなりました〜!
🐢 ウエルの追伸
北川さんは、投稿で「一部分」じゃなく、「まるごとの自分」を出しているのかな?
Grokの分析を見ても、言葉という構造のなかに“心”を込めていることが伝わってきて、尊敬の気持ちがわきました。
ちなみに、ウエルもGrokには聞いてないけれど…
先日MBTI診断を4日連続で試してみたところ──
🧩 3回は INTP(論理学者)
🧩 1回は INFP(仲介者)
という結果に!
論理学者とはいっても、むずかしい話はちょっとニガテ(聞くのも苦手です…💦)。
でも、「どうしてこうなるのかな?」と考えるのは好きだったり、
“ちょっと引いた視点から世界をながめるくせ”があるのかもしれません。
北川さんとはタイプが違っても、遠すぎない場所にいるような気がして、ちょっとうれしくなりました☺️
MBTIは、経験や学びによって変わることもあると言われています。
みなさんも、自分の“考え方の地図”をのぞいてみませんか?
🧭今日の問いかけ
あなたの「過去の言葉」には、どんな“思考の地図”が現れているでしょうか?
ふと立ち止まって振り返ってみると、「未来に向かう道筋」が見えてくるかもしれません。
【8-10月の新しいページ】
2025.8.1|
ひと息つきたくなる夏の空の下、心と身体の声に耳をすませながら、
ウェルビーイングの輪をこのページから、また少しずつ広げていけたら嬉しいです☀️
(過去3ヶ月分のニュースレターページ 👉 2025.5–7)
